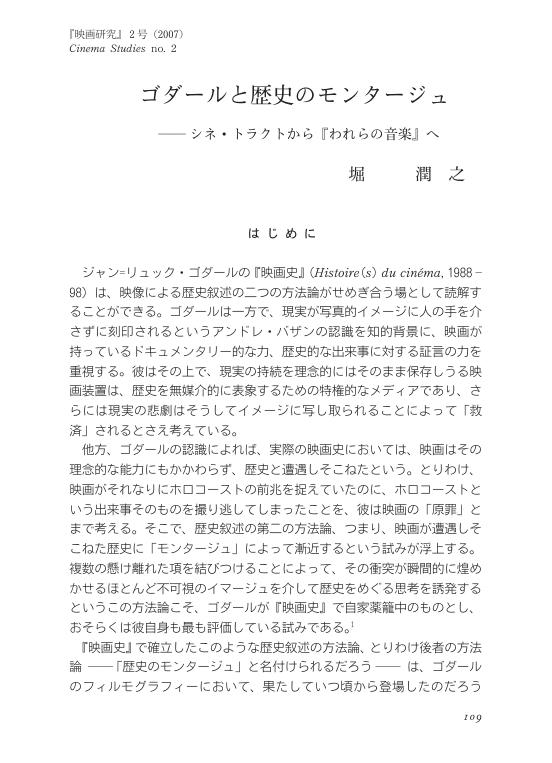1 0 0 0 OA 「美しい四姉妹」の生成と変容 『細雪』におけるリメイク/翻案の過程
- 著者
- 森 年恵
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.28-50, 2020-12-05 (Released:2022-07-04)
- 参考文献数
- 48
本論は、阿部豊監督作品(1950年、新東宝)、島耕二監督作品(1959年、大映)、市川崑監督作品(1983年、東宝)の三作の『細雪』を、『アダプテーションの理論』(ハッチオン)、『映画リメイク』(Verevis)による「リメイク/翻案」の概念拡大を参照しつつ検討することを目的とする。阿部作品は原作への忠実を旨としながら妙子に焦点を当て、島作品は阿部作品の基本構造を採用してメロドラマ化しつつ雪子と妙子にトラウマの主題を導入し、市川作品は原作からの新たな翻案を試みて貞之助の雪子への欲望の描写と四姉妹の描き分けを行った。三作の製作の中に、「リメイク/翻案」の両者を含む『細雪』=「美しい四姉妹の物語」の図式の生成過程を見ることができる。「リメイク」および「翻案」の概念は、近年の概念拡大によって、それぞれを「メディア内」「メディア間」の現象として理解することが困難になっているが、産業、受容の側面も含めた三作の検討の結果、多様な現象の総合的な運動として見る 「リメイク」と翻案者の動機を含む製作過程を重視する「翻案」という視点の相違が重要と結論づけられた。
1 0 0 0 OA 日本占領下の上海における日中合作映画の製作経緯 『狼火は上海に揚る』を中心に
- 著者
- 朱 芸綺
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.52-73, 2020-12-05 (Released:2022-07-04)
- 参考文献数
- 19
太平洋戦争開戦がもたらした政策の転換によって、日本映画界では日中両国の提携による合作映画が要請されることになった。1942年から1944年にかけて、日本国内の三大映画製作会社は、相前後して日本占領下の上海へ渡り、合作映画の道を模索していたが、最終的に実現できたのは『狼火は上海に揚る』一作だけであった。本稿はこの戦時中における日中合作映画の製作経緯を解明するものである。本稿では、日中映画合作の背景を確認した上で、三社の企画の遂行過程を整理し、中国側にとって複雑な政治情勢から直接取材する現代劇よりも解釈の幅が広い時代劇が受け入れやすいことと、監督主体で企画を具体化していく方法に限界があったことを指摘した。さらに、唯一映画化を実現した『狼火は上海に揚る』の映像の中からは、日本の「国策」に順応する姿勢を示しつつも、固有の文化的文脈を利用した中国側の主体性を読み取ることができることを明らかにした。
1 0 0 0 OA 文化大革命後における香港左派映画の戦略 『碧水寒山奪命金』の風景描写を中心に
- 著者
- 雑賀 広海
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.74-95, 2020-12-05 (Released:2022-07-04)
- 参考文献数
- 23
本論文は、香港の左派映画に注目する。香港映画史における左派映画とは、冷戦期に中国共産党を支持していた映画会社とその作品を意味する。対する右派は国民党を支持し、世界中の広い市場を射程にしていた。第二次世界大戦後しばらくは順調に映画製作をしていた左派は、中国で文化大革命が起きると、その影響で苦境に立たされる。文革が終結して改革開放路線に変わると、左派は中国各地に遠征して、右派には撮影できない中国の風景を作品に取り入れようとした。その目的は、香港の観客には珍しい風景を強調するためだけではなく、右派が描く中国のイメージを実景で更新しようとしたためでもある。本論文は、左派系の『碧水寒山奪命金』と右派系の胡金銓監督作品で描かれる風景を、①人物と風景の画面構成、②アクション・シーン、③仏教思想のイメージという三つの視点から比較する。そこから導出されるのは、『碧水寒山奪命金』における、中国内地の広大さとは矛盾するような、自由を制限して身体 を束縛する風景描写である。
1 0 0 0 OA 母性幻想とレズビアン感性 『挽歌』と『女であること』における久我美子
- 著者
- 徐 玉
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.4-26, 2021-12-04 (Released:2022-07-05)
- 参考文献数
- 35
本稿は、久我美子が主演した文芸映画『挽歌』と『女であること』における疑似母娘関係に着目し、原作小説とも比較しながら、〈母性〉を介した女同士の親密な関係の映画的表現の特色を考察した。また、久我美子のスター・ペルソナとこれらの作品の関係を探った。『挽歌』については、怜子という新しい女性像、および怜子のヴォイス・オーヴァーをはじめとする女たちの「声」の分析などを通して、怜子とあき子の親密さが原作以上に強調されていることを検証した。『女であること』については、さかえのセクシュアリティの揺らぎを表現するにあたって、川島雄三の独特な空間がもたらす効果を論じたうえで、映画ではさかえの欲望がつねに市子に向けられていることを指摘した。さらに、『雪夫人絵図』以降の久我のイメージを辿り、『挽歌』と『女であること』において疑似母娘関係が強化されたことが、「特殊児童」という久我のスター・ペルソナと結びついていることを確認した。
1 0 0 0 OA 増村保造の動物的身体 『痴人の愛』を中心として
- 著者
- 中島 晋作
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.28-51, 2021-12-04 (Released:2022-07-05)
- 参考文献数
- 35
本稿は、増村保造の映画『痴人の愛』(1967年)における身体表象に着目し、原作小説との比較を通して、60年代以降の増村映画に顕著に現れる「動物性」の諸相を明らかにしようとするものである。構成としては、はじめに谷崎潤一郎による小説『痴人の愛』が、谷崎の 西洋偏重的な思想を色濃く反映させた作品であることを確認する。ここで議論の中心となるのが、小説のヒロイン、ナオミの身体性である。次に、増村保造による小説のアダプテーションにおいて、ナオミの身体表象が小説からいかに差異化されているのかを分析する。これにより、増村映画においては、ナオミに動物的ともいえる身体性が現れることを指摘する。最後に、この身体の「動物性」がいかなる意味を持つのかについて論ずる。議論から、増村にとっての身体の「動物化」は、西洋の模倣としての「近代主義」を乗り越える新たな身体として現前したものであると結論する。
1 0 0 0 OA ゴダールと歴史のモンタージュ シネ・トラクトから『われらの音楽』へ
- 著者
- 堀 潤之
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.109-127, 2007 (Released:2019-12-07)
- 参考文献数
- 15
1 0 0 0 OA 田園、直線、殺人事件 アンソニー・マン映画『国境事件』のテクスト分析
- 著者
- 川本 徹
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.58-73, 2009 (Released:2019-12-02)
- 参考文献数
- 14
- 著者
- 菅原 裕子
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.91-108, 2007
- 著者
- 大勝 裕史
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.76-91, 2012 (Released:2019-07-01)
- 参考文献数
- 31
1 0 0 0 戦間期におけるパテ・シネマ社の小型映画産業とその興亡
- 著者
- 福島 可奈子
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.28-49, 2019
第一次から第二次世界大戦までの戦間期にフランスで発売された、パテ・シネマ社製小型映画の産業技術的特徴とその経営戦略について論じる。パテ・シネマ社は、第一次世界大戦直前まで生フィルム製造販売事業で世界的覇者だったが、大戦後の大不況によってアメリカのコダック社に覇権を奪われた。その結果在庫フィルムを無駄なく再利用することで新規開拓を目指し、パテ・ベビー(9ミリ半映画)やパテ・ルーラル(17ミリ半映画)といった独自の小型映画を生み出す。だが日本の先行研究では、パテ・ベビーを中心に日本国内での小型映画文化研究が主流で、フランスでの小型映画の開発事情を含めた産業技術面から十分に議論されてきたとは言い難 い。ゆえに本稿では、二つの大戦に翻弄された二人の経営者(シャルル・パテとベルナール・ナタン)の経営手腕から、パテ・シネマ社が小型映画発売に至る経営的かつ産業技術的必然性を具体的に明らかにした。それによってパテ・ベビーを含む小型映画事業そのものが、第一次世界大戦後の大不況と軍事技術の転用なしには誕生し得なかったことを指摘した。
- 著者
- 秦 邦生
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.4-19, 2013 (Released:2019-05-01)
- 参考文献数
- 37
- 著者
- 片岡 佑介
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.44-66, 2017 (Released:2017-12-26)
- 参考文献数
- 42
本稿の目的は、黒澤明の『八月の狂詩曲』(1991)における対位法の意義を、原爆映画史および黒澤の過去作品での音楽演出との比較によって検討することにある。その際、本稿が着目したのは、この対位法演出に も看取できる聖母マリアの修辞である。原爆映画史において聖母マリアのモチーフは、特に長崎を舞台とする作品で度々用いられてきた。聖母マリアは爆心地・浦上地区のカトリック信仰を象徴する無垢な被爆者表象として機能しただけでなく、日本的なものと西洋的なものが融合したイメージとして、占領期の原爆言説とも密接な関わりをもつ。本稿では、日本で受容された対位法概念の二つの理解を参照し、黒澤が一度は般若心経の音声と聖母マリアの修辞としての薔薇の映像による対位法で冷戦後の世界の表象としての和解のイメージを構成しつつ、映画の最後に自作では異例の物語世界外の音楽を用いた対位法で核への恐怖と狂気による和解の転覆を演出していることを明らかにした。
- 著者
- 北田 理惠
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.4-21, 2009
- 著者
- 小野 智恵
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.74-91, 2009 (Released:2019-12-02)
- 参考文献数
- 38
1 0 0 0 OA 団地映画音響論
- 著者
- 今井 瞳良
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.26-43, 2017 (Released:2017-12-25)
- 参考文献数
- 36
本稿は映画音響と団地という空間に着目して、『クロユリ団地』(中田 秀夫監督、2013 年)の人間と幽霊の境界を論じていく。日本映画史に おいて、団地のコンクリートの壁は物理的な境界として、視覚的に遮る ことはできるが、聴覚的には透過性が高いという特徴を持ってきた。こ れは、音響と物語空間の問題であるとともに、フレームの問題でもある。 この特徴を活用して『クロユリ団地』では、人間と幽霊の会話は常に「フ レーム外」を通してなされ、画面において両者は断絶している。団地の 境界とフレームの境界という二つの境界を通して、人間と幽霊の境界は 「イン」の会話の不可能性として示されているのだ。その中で、人間の明 日香と「イン」の会話をする幽霊のミノルの関係を分析し、明日香が人 間と幽霊の境界を無効化する不気味な存在と化していくことを明らかにし た。そして、その不気味な明日香が「幼さ」を肯定的に捉える女性表象 に対して批評性を持つことを指摘した。
1 0 0 0 OA 若松孝二の団地
- 著者
- 今井 瞳良
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.50-70, 2019 (Released:2020-04-09)
- 参考文献数
- 58
本稿は、団地を舞台とした『壁の中の秘事』(1965年)と『現代好色伝 テロルの季節』(1969年)の分析を通して、若松孝二の「密室」の機能を明らかにすることを目的とする。若松の「密室」は、松田政男が中心となって提唱された「風景論」において、「風景(=権力)」への抵抗として重要な地位を与えられてきた。「風景論」における「密室」は、外側の「風景」に相対する「個人=性」のアレゴリーであり、「密室」と「風景」は切り離されている。しかし、若松の団地はメディアによって外側と接続されており、「風景論」の「密室」とは異なる空間であった。『壁の中の秘事』では、「密室」を出た浪人生・ 誠による殺人がメディアを介して「密室」に回帰することで、メディアの回路を提示し、『現代好色伝』は「密室」を出た後のテロを不可視化することで、メディアの回路が切断されている。若松の団地は、 脱「密室」の空間であり、メディアが日常生活に侵入している環境自体を問い直す「政治性」を持っていたのである。
1 0 0 0 OA 親子映画と非劇場映画の新しい観客
- 著者
- 藤田 修平
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.22-38, 2016 (Released:2017-02-24)
- 参考文献数
- 37