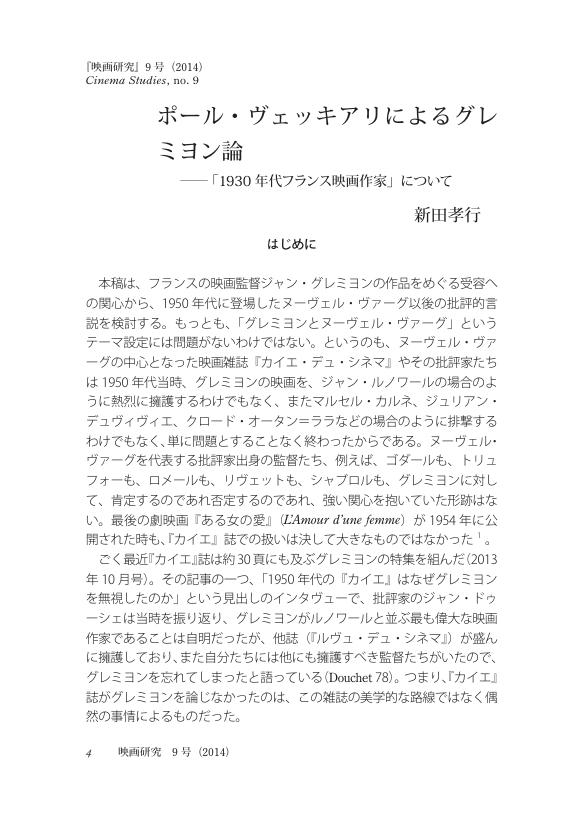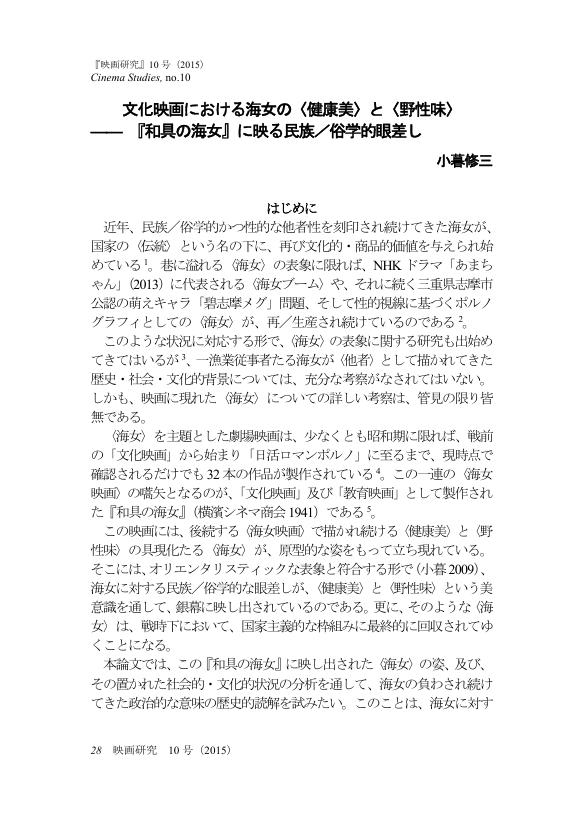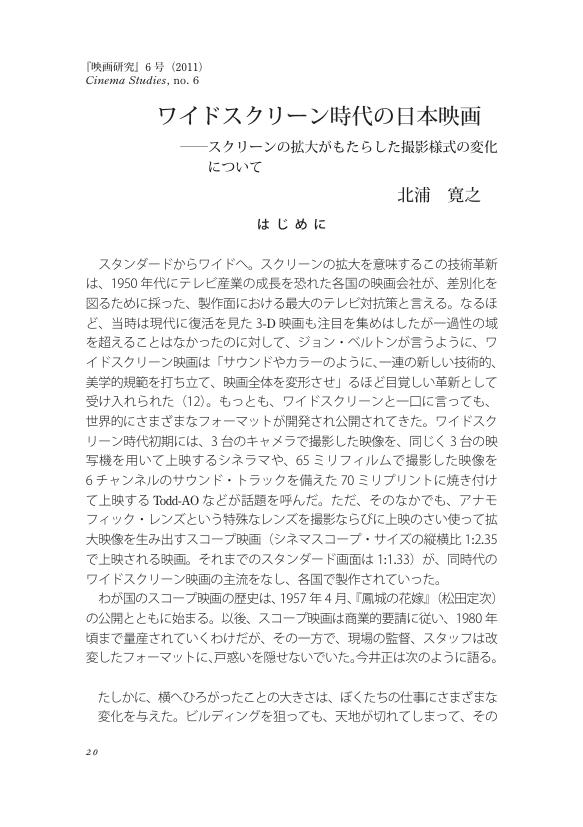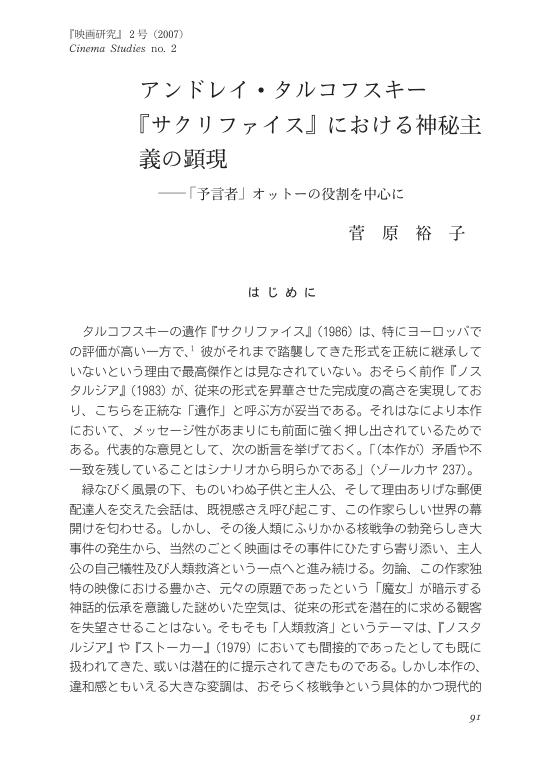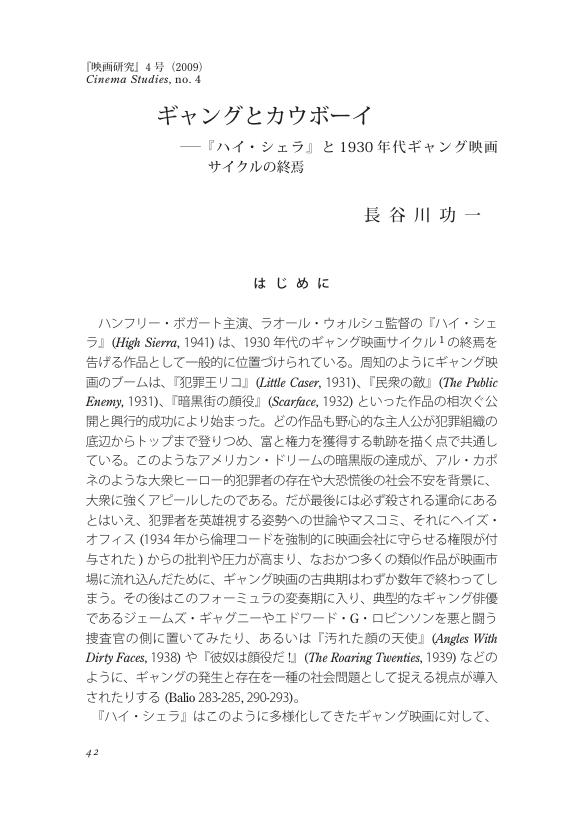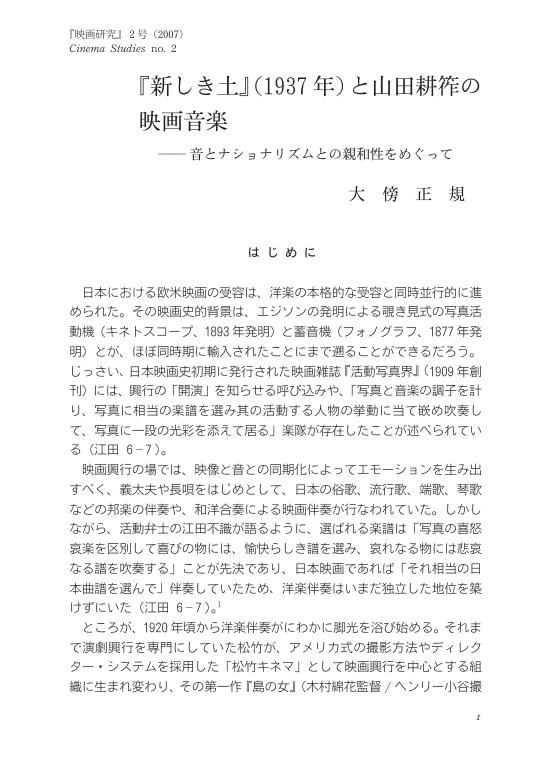15 0 0 0 OA 玩具映画の受容における視覚性と触覚性 チャンバラ映画分析からのアプローチ
- 著者
- 雑賀 広海
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.4-25, 2017 (Released:2017-12-25)
- 参考文献数
- 30
本論文が着目するのは、玩具映画と呼ばれるメディアである。玩具映 画とは、戦前の日本でこどもの玩具として販売された簡単な映写機と短 い 35mm フィルムのことを指す。これを用いてこどもたちは家庭で映画を 上映していた。本論文は、玩具映画で遊ぶこどもの視覚性に、映画館 の観客のそれとは異なり、触覚性が介入してくることを明らかにした。 戦前期において家庭の映画鑑賞に使われたメディアは、玩具映画のほ かに小型映画もあった。しかし、こどもとの関係から見ると、小型映画 は教育目的で使われることが多く、したがって、こどもは受動的な姿勢 が要求された。玩具映画の場合、それが玩具であるということによって、 こどもは能動的なアクションをとる。つまり、こどもの視覚性のなかに、 玩具に触れるという触覚性が介入してくるのである。こどもと玩具映画 が結ぶこうした遊戯的な関係性は、現代のメディア環境を考察するうえで も重要な概念となるという結論に至った。
15 0 0 0 OA 日活ロマンポルノに映る〈海女〉
- 著者
- 小暮 修三
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.40-56, 2016 (Released:2017-02-24)
- 参考文献数
- 29
6 0 0 0 OA 隠喩としての刺繍 アリ・アスターの『ミッドサマー』における女性性と偽装ケア
- 著者
- 石田 由希
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.46-64, 2022-12-10 (Released:2023-05-08)
- 参考文献数
- 27
アリ・アスター監督の長編フォーク・ホラー映画『ミッドサマー』では、人身御供を行うスウェーデン人の集団が、刺繍入りの華やかな民族衣装を着る。刺繍が加害性と隣り合わせる光景は、アスターが本作以前に監督した短編映画『ミュンヒハウゼン』や長編ホラー映画『ヘレディタリー/継承』にも見受けられる。本論の目的は、上記ふたつの先行作品で刺繍が権威的な女性性の隠喩であり、こうした含みを持つ手芸モチーフが『ミッドサマー』に引き継がれている点を明らかにすることだ。まず、 『ミュンヒハウゼン』と『ヘレディタリー』では、草花と隣接する植物模様の刺繍が登場し、その刺繍の作者である女性や刺繍と象徴的に結びつく高齢の女性が、他者を支配するためにケアを偽装する。『ミッドサマー』で刺繍入り民族衣装をまとう女性たちも、ケアラーを演じつつ他者を手中に収めるが、その中心にいる家母長的な人物の造形は、前二作の保守的な「母親」像を骨子とする。
5 0 0 0 OA ポール・ヴェッキアリによるグレミヨン論
- 著者
- 新田 孝行
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.4-20, 2014 (Released:2017-12-25)
- 参考文献数
- 29
- 著者
- 鄺 知硯
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.30-49, 2018 (Released:2019-03-15)
- 参考文献数
- 22
本稿は、1960年代前後の香港映画業界がいかに日本映画から技術を吸収したのかという経緯を踏まえ、ワイヤーアクションという技術に着目し映画の内容的な側面からこの技術吸収の意味と貢献を考察していく。1950年代から邵氏によって次第に日本から香港映画に輸入された、イーストマン・カラー、シネスコ、照明、ワイヤーアクションなどの技術的助けを得た香港北京語映画は急速に「現代化」の道を歩んで行った。 そして、香港映画業界で武術指導を務めた劉佳良と唐佳が日本映画からワイヤーアクションの技術を摂取・改良しつつ、1960年代ブームになった新派武侠映画でも応用した。この技術の活用によって、香港新派武侠映画は、技術と資金の乏しかった旧派武侠映画とは明白に区別されたジャンルとなり、市場における主流の地位を占めるようになった。このように、ワイヤーアクションに代表される技術的な成熟と香港映画におけるスペクタクル的表現との関連性が明白であることを指摘した。
3 0 0 0 団地映画音響論:『クロユリ団地』の境界を越える音
- 著者
- 今井 瞳良
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.26-43, 2017
本稿は映画音響と団地という空間に着目して、『クロユリ団地』(中田秀夫監督、2013 年)の人間と幽霊の境界を論じていく。日本映画史において、団地のコンクリートの壁は物理的な境界として、視覚的に遮ることはできるが、聴覚的には透過性が高いという特徴を持ってきた。これは、音響と物語空間の問題であるとともに、フレームの問題でもある。この特徴を活用して『クロユリ団地』では、人間と幽霊の会話は常に「フレーム外」を通してなされ、画面において両者は断絶している。団地の境界とフレームの境界という二つの境界を通して、人間と幽霊の境界は「イン」の会話の不可能性として示されているのだ。その中で、人間の明日香と「イン」の会話をする幽霊のミノルの関係を分析し、明日香が人間と幽霊の境界を無効化する不気味な存在と化していくことを明らかにした。そして、その不気味な明日香が「幼さ」を肯定的に捉える女性表象に対して批評性を持つことを指摘した。
3 0 0 0 OA 岡本喜八『日本のいちばん長い日』の天皇表象を読む
- 著者
- 羽鳥 隆英
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.4-27, 2019 (Released:2020-04-09)
- 参考文献数
- 37
本論は橋本忍の脚本を岡本喜八が監督した映画『日本のいちばん長い日』における昭和天皇表象の研究である。初めに 2019年現在の研究状況や岡本の作家的な経歴における天皇の問題を確認した上(第 I節)、劇中に張り巡らされた様々な水準のコミュニケーションに着目しつつ『日本のいちばん長い日』の長大な物語を整理した(第II 節)。次に映画大詰の玉音放送の場面を構成する映像=音響の相関性を精査し、先行の玉音放送表象などとも比較しつつ、『日本のいちば ん長い日』が試みる二重の異化と一重の相対化を指摘した(第III節)。さらに映画半ばの天皇による「大東亜戦争終結ノ詔書」の署名、玉音盤の吹込と特攻出撃の並行編集に焦点を絞り、第一に「サウンド・ブリッジ」を活用した音響設計(第IV節)、第二に天皇役の 8代目・ 松本幸四郎と特攻基地の指揮官・野中大佐役の伊藤雄之助の関係に着目しつつ(第V節)、天皇表象に暗示的に仕掛られた価値転覆性を指摘した。
3 0 0 0 OA 『夕やけ雲』(1956)における木下惠介のクィアな感性 少年同士の情動表象をめぐって
- 著者
- 久保 豊
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.44-62, 2015 (Released:2017-04-03)
- 参考文献数
- 16
2 0 0 0 OA 文化映画における海女の〈健康美〉と〈野性味〉 『和具の海女』に映る民族/俗学的眼差し
- 著者
- 小暮 修三
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.28-43, 2015 (Released:2017-04-03)
- 参考文献数
- 38
2 0 0 0 OA ワイドスクリーン時代の日本映画 スクリーンの拡大がもたらした撮影様式の変化 について
- 著者
- 北浦 寛之
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.20-37, 2011 (Released:2019-08-01)
- 参考文献数
- 28
2 0 0 0 成龍の初期作品における父子関係の転倒と自作自演の視線
- 著者
- 雑賀 広海
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.4-28, 2018
 本論文は、成龍が主演デビューしてから初監督作品『笑拳怪招』(1979) を手掛けるまでの1970年代香港映画に着目する。成龍に関する先行研究は、監督と主演を兼任する、いわゆる自作自演という点については十分に論じていない。本論文は、『笑拳怪招』を中心とする議論を通して、監督と俳優の関係、または作品内における父と子の関係がどのように描かれているか考察する。<br> 1980年代に黄金期を迎えるまでの香港映画産業では、監督と俳優の間には厳格な封建的関係が結ばれていた。しかし、1970年代の李小龍の登場から独立プロダクションのブームを経て、監督と俳優の父子関係は崩壊していく。それを象徴するのが羅維と成龍の関係性である。だが、『笑拳怪招』に見るのは父子関係の崩壊だけではなく、監督と俳優の間にある境界の曖昧化でもある。この曖昧化は黄金期を特徴づけるものであり、したがって、本作は1970年代末の転換を象徴する重要な作品であるという結論に至った。
2 0 0 0 視点 時代劇/時代もの再考――『鬼滅の刃』を一つのきっかけに
- 著者
- 菅原 裕子
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.91-108, 2007 (Released:2019-12-07)
- 参考文献数
- 17
2 0 0 0 OA 時代劇映画をめぐる《幕末イメージ》の転回
- 著者
- 羽鳥 隆英
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.51-69, 2019 (Released:2019-12-07)
- 参考文献数
- 32
1 0 0 0 OA ギャングとカウボーイ 『ハイ・シェラ』と1930年代ギャング映画サイクルの終焉
- 著者
- 長谷川 功一
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.42-57, 2009 (Released:2019-12-02)
- 参考文献数
- 30
1 0 0 0 OA 成龍の初期作品における父子関係の転倒と自作自演の視線
- 著者
- 雑賀 広海
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.4-28, 2018 (Released:2019-03-15)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 1
本論文は、成龍が主演デビューしてから初監督作品『笑拳怪招』(1979) を手掛けるまでの1970年代香港映画に着目する。成龍に関する先行研究は、監督と主演を兼任する、いわゆる自作自演という点については十分に論じていない。本論文は、『笑拳怪招』を中心とする議論を通して、監督と俳優の関係、または作品内における父と子の関係がどのように描かれているか考察する。 1980年代に黄金期を迎えるまでの香港映画産業では、監督と俳優の間には厳格な封建的関係が結ばれていた。しかし、1970年代の李小龍の登場から独立プロダクションのブームを経て、監督と俳優の父子関係は崩壊していく。それを象徴するのが羅維と成龍の関係性である。だが、『笑拳怪招』に見るのは父子関係の崩壊だけではなく、監督と俳優の間にある境界の曖昧化でもある。この曖昧化は黄金期を特徴づけるものであり、したがって、本作は1970年代末の転換を象徴する重要な作品であるという結論に至った。
1 0 0 0 OA トーキー時代の弁士 外国映画の日本語字幕あるいは「日本版」生成をめぐる考察
- 著者
- 北田 理惠
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.4-21, 2009 (Released:2019-12-02)
- 参考文献数
- 56
1 0 0 0 OA 『新しい土』(1937年)と山田耕筰の映画音楽 音とナショナリズムの親和性をめぐって
- 著者
- 大傍 正規
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.1-21, 2007 (Released:2019-12-07)
- 参考文献数
- 36
1 0 0 0 OA 女を見る女のまなざし 映画『華岡青洲の妻』における女同士の絆
- 著者
- 徐 玉
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.4-26, 2020-12-05 (Released:2022-07-04)
- 参考文献数
- 28
本稿は、増村保造の映画『華岡青洲の妻』(1967年)における女同士の欲望や絆の描き方に注目し、有吉佐和子による原作小説と比較しながら、その映画的表現の特色を考察する試みである。まず、この映画において、加恵と於継の心理や欲望が、二人のまなざしのやりとりと連動していることを検証した。続いて、欲望の三角形の概念を援用しながら、青洲、加恵、於継の三者関係を考察し、加恵の青洲への愛や献身は、於継のそれの模倣であると論じた。また、加恵と於継の愛憎を見守る女性「観客」としての小陸の視線を加え、女たちの間には、権力が奪われているがゆえに結ばれる連帯が存在していることを確認した。さらに、加恵が家制度における姑という身分と同一化するように描かれている原作に対して、映画の結末における円環構造は、一度は忘却した於継への愛の蘇生を示唆するものであり、女同士の絆を前景化させていることを指摘した。
1 0 0 0 OA 「美しい四姉妹」の生成と変容 『細雪』におけるリメイク/翻案の過程
- 著者
- 森 年恵
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.28-50, 2020-12-05 (Released:2022-07-04)
- 参考文献数
- 48
本論は、阿部豊監督作品(1950年、新東宝)、島耕二監督作品(1959年、大映)、市川崑監督作品(1983年、東宝)の三作の『細雪』を、『アダプテーションの理論』(ハッチオン)、『映画リメイク』(Verevis)による「リメイク/翻案」の概念拡大を参照しつつ検討することを目的とする。阿部作品は原作への忠実を旨としながら妙子に焦点を当て、島作品は阿部作品の基本構造を採用してメロドラマ化しつつ雪子と妙子にトラウマの主題を導入し、市川作品は原作からの新たな翻案を試みて貞之助の雪子への欲望の描写と四姉妹の描き分けを行った。三作の製作の中に、「リメイク/翻案」の両者を含む『細雪』=「美しい四姉妹の物語」の図式の生成過程を見ることができる。「リメイク」および「翻案」の概念は、近年の概念拡大によって、それぞれを「メディア内」「メディア間」の現象として理解することが困難になっているが、産業、受容の側面も含めた三作の検討の結果、多様な現象の総合的な運動として見る 「リメイク」と翻案者の動機を含む製作過程を重視する「翻案」という視点の相違が重要と結論づけられた。