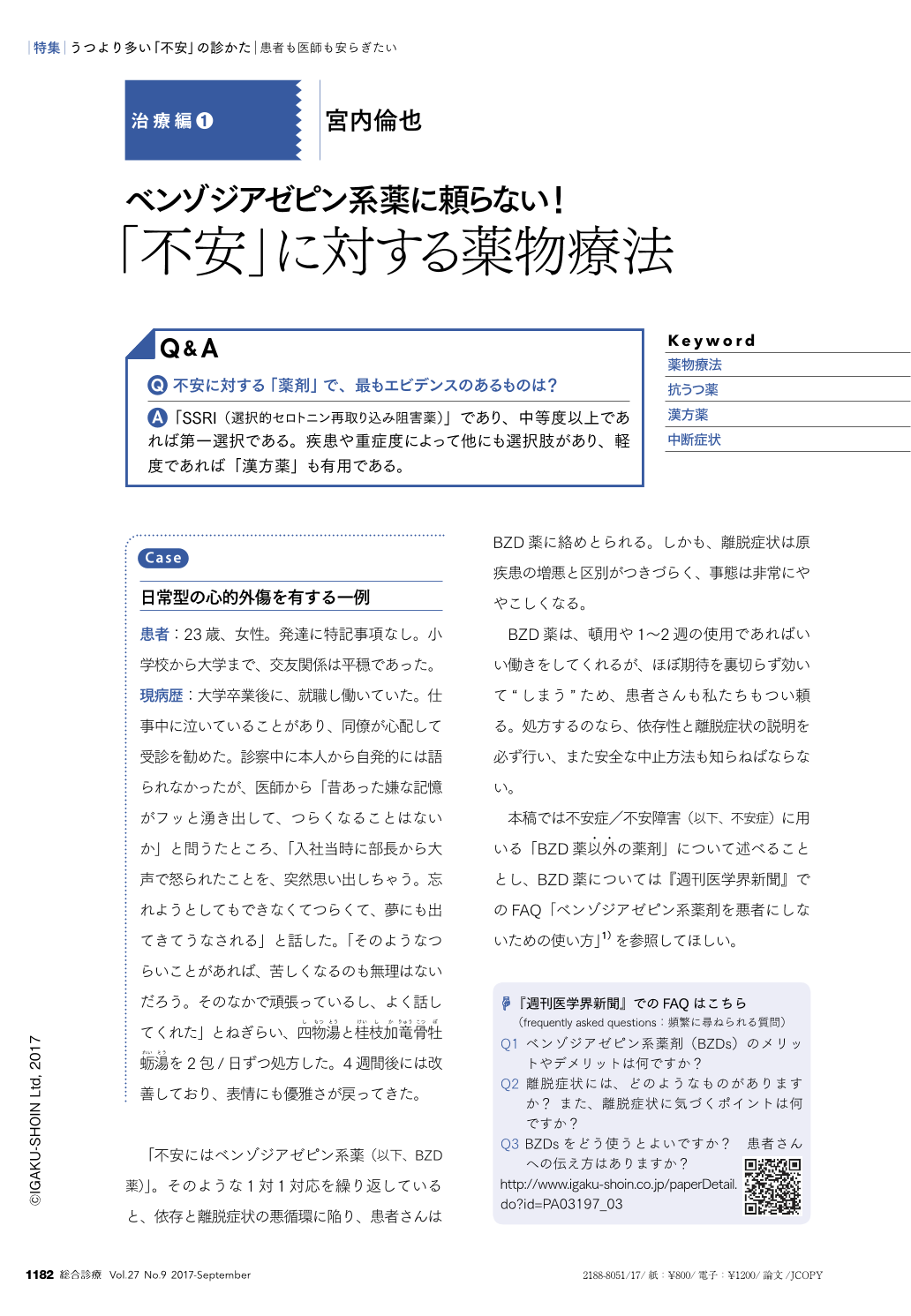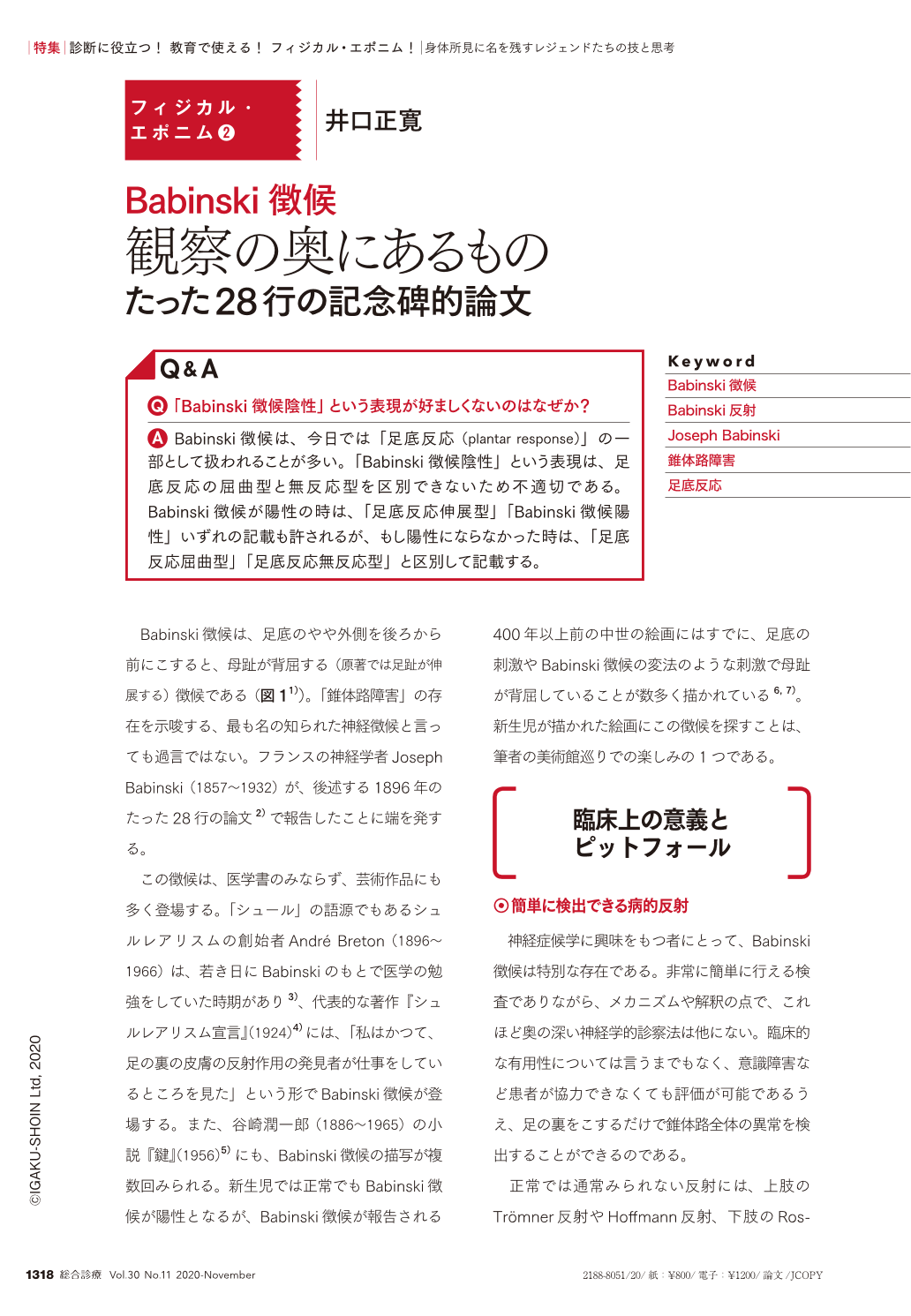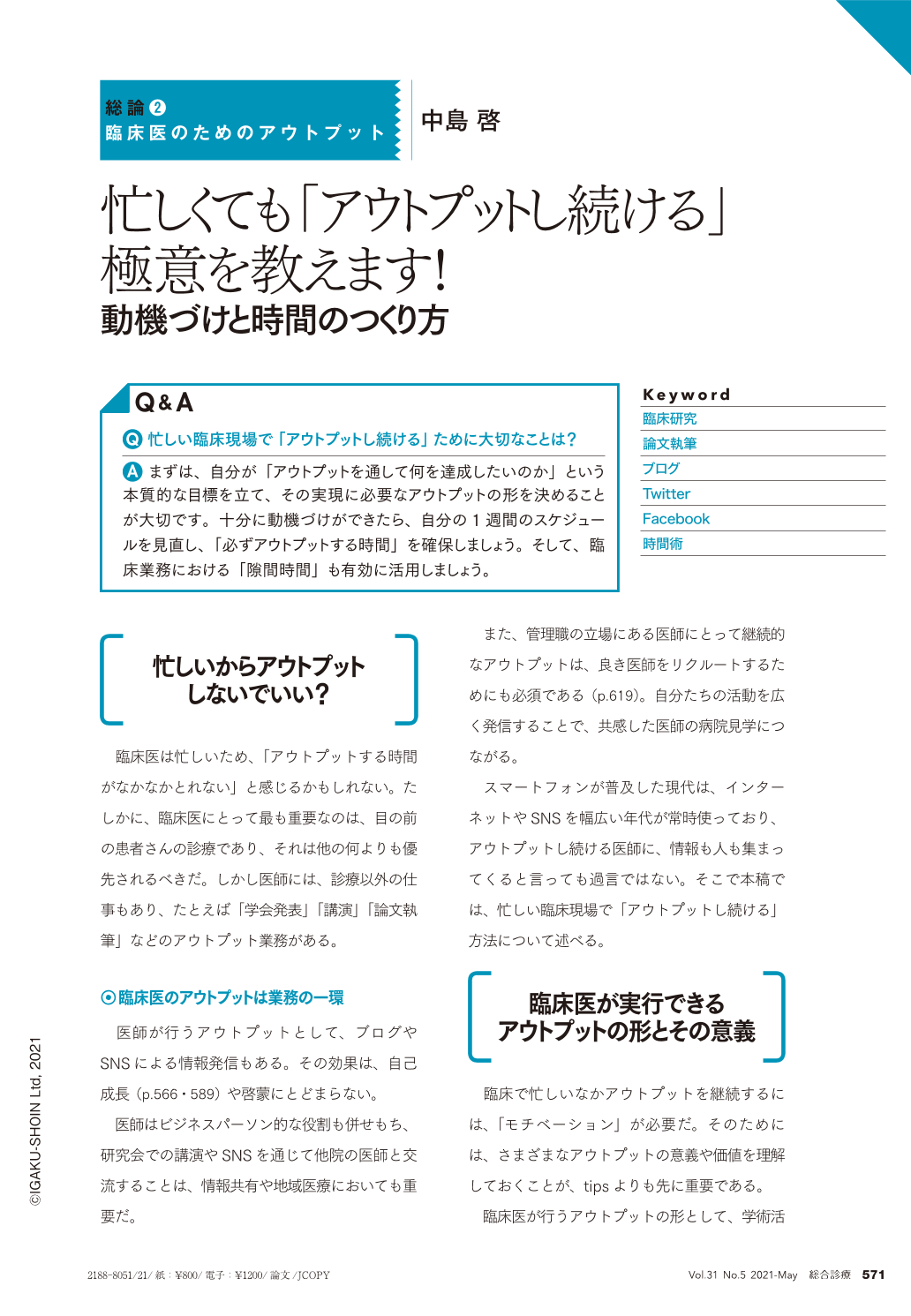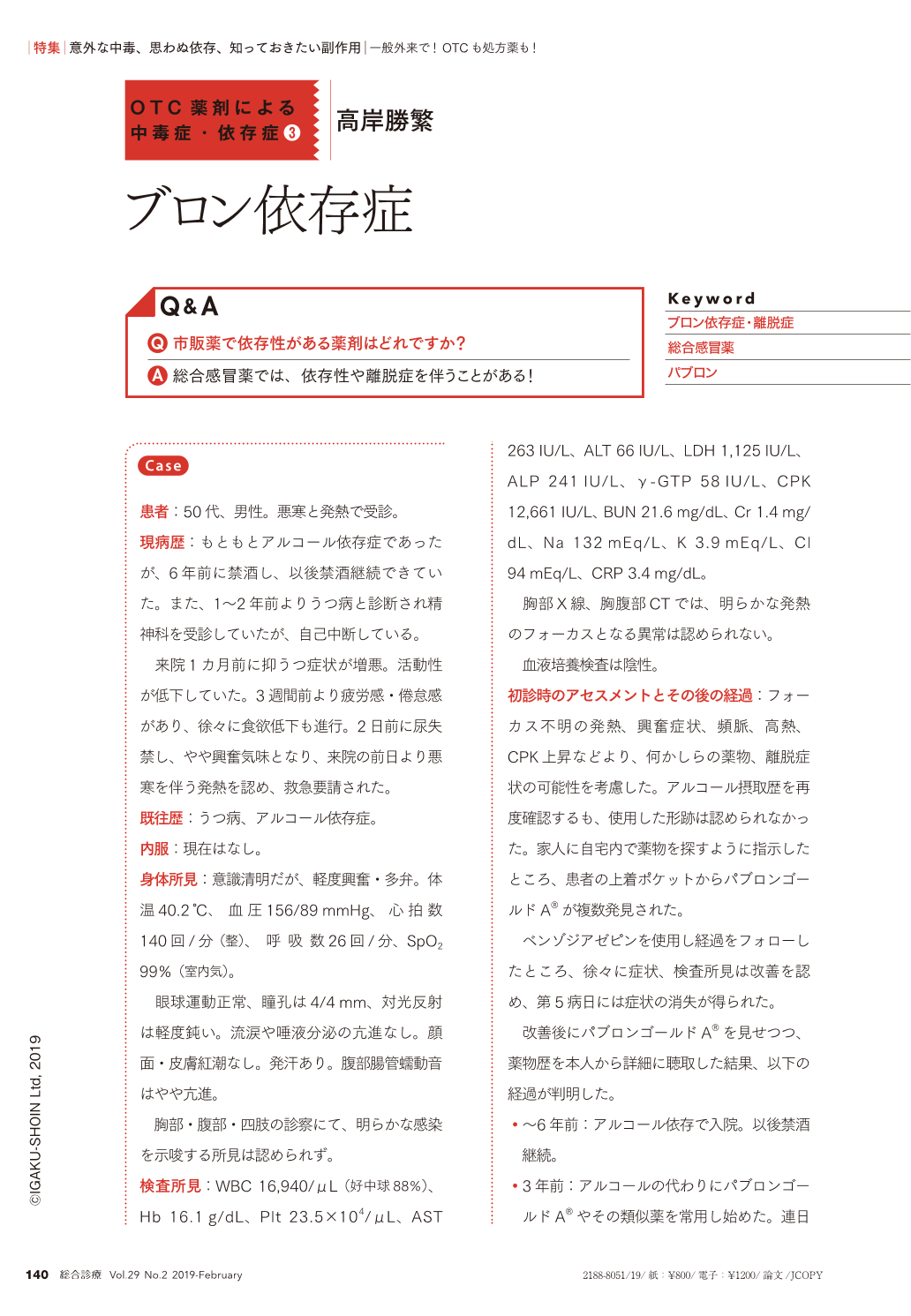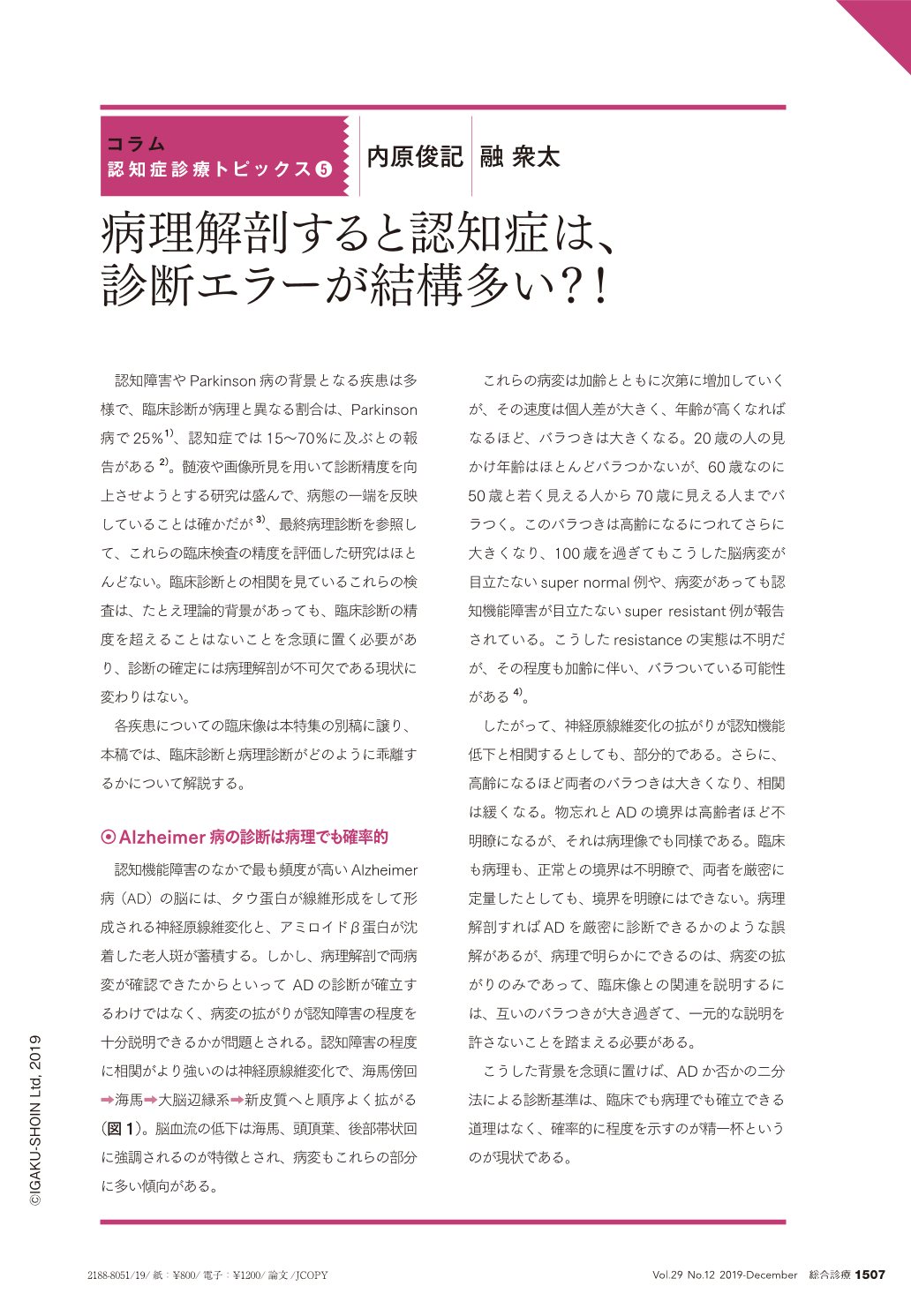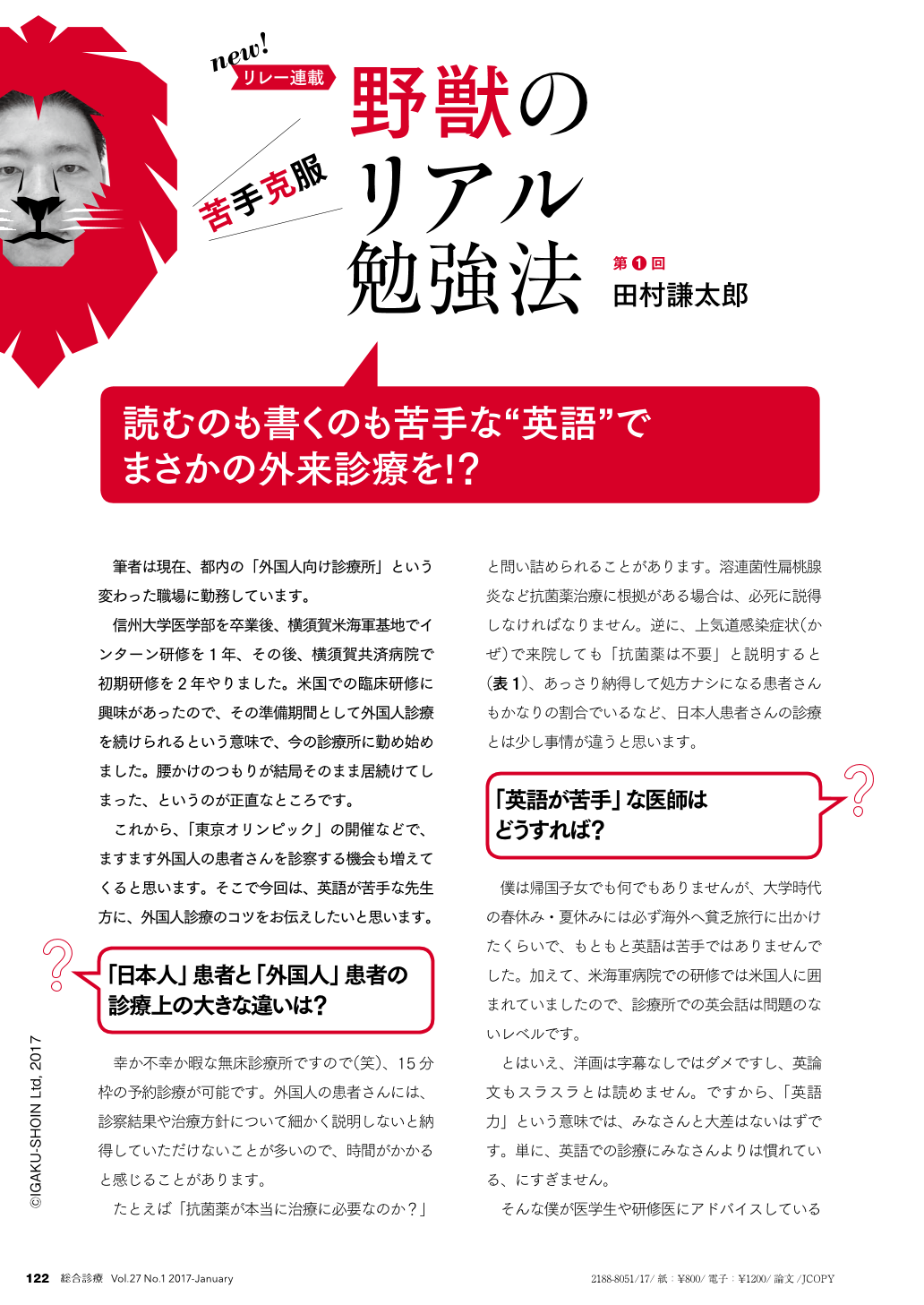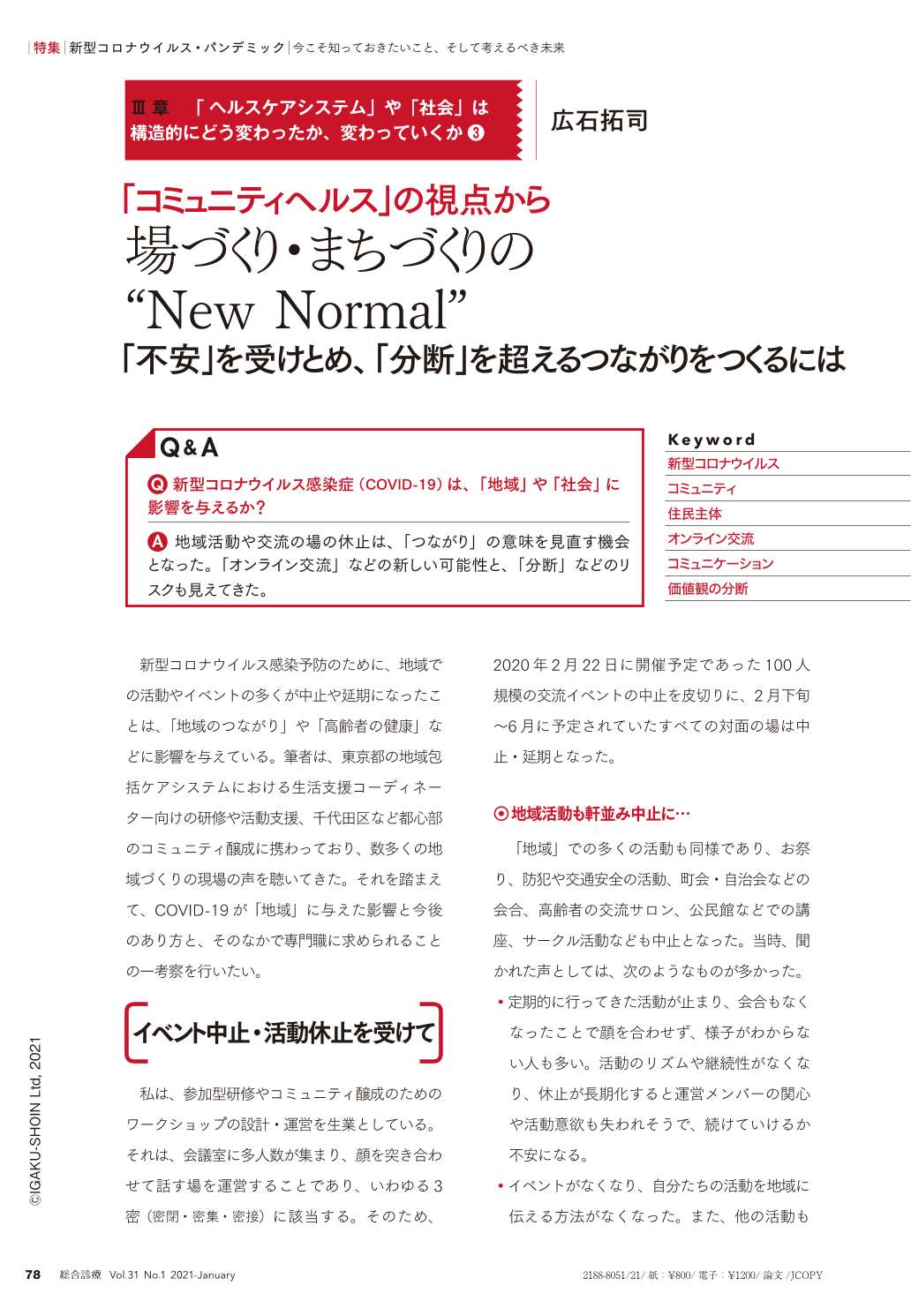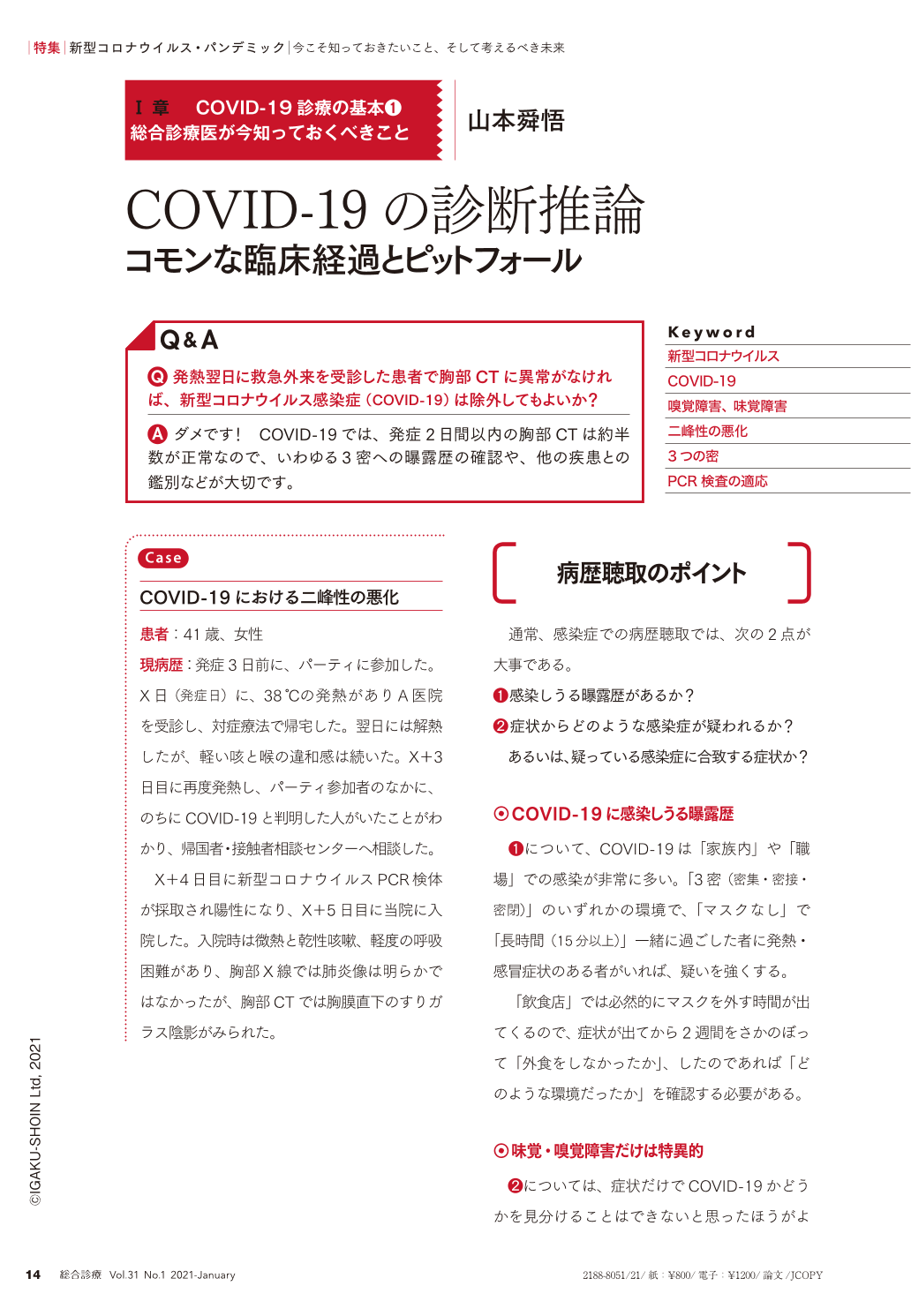8 0 0 0 —ベンゾジアゼピン系薬に頼らない!—「不安」に対する薬物療法
- 著者
- 宮内 倫也
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 総合診療 (ISSN:21888051)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.9, pp.1182-1187, 2017-09-15
Case日常型の心的外傷を有する一例患者:23歳、女性。発達に特記事項なし。小学校から大学まで、交友関係は平穏であった。現病歴:大学卒業後に、就職し働いていた。仕事中に泣いていることがあり、同僚が心配して受診を勧めた。診察中に本人から自発的には語られなかったが、医師から「昔あった嫌な記憶がフッと湧き出して、つらくなることはないか」と問うたところ、「入社当時に部長から大声で怒られたことを、突然思い出しちゃう。忘れようとしてもできなくてつらくて、夢にも出てきてうなされる」と話した。「そのようなつらいことがあれば、苦しくなるのも無理はないだろう。そのなかで頑張っているし、よく話してくれた」とねぎらい、四物湯と桂枝加竜骨牡蛎湯を2包/日ずつ処方した。4週間後には改善しており、表情にも優雅さが戻ってきた。
Babinski徴候は、足底のやや外側を後ろから前にこすると、母趾が背屈する(原著では足趾が伸展する)徴候である(図11))。「錐体路障害」の存在を示唆する、最も名の知られた神経徴候と言っても過言ではない。フランスの神経学者Joseph Babinski(1857〜1932)が、後述する1896年のたった28行の論文2)で報告したことに端を発する。 この徴候は、医学書のみならず、芸術作品にも多く登場する。「シュール」の語源でもあるシュルレアリスムの創始者André Breton(1896〜1966)は、若き日にBabinskiのもとで医学の勉強をしていた時期があり3)、代表的な著作『シュルレアリスム宣言』(1924)4)には、「私はかつて、足の裏の皮膚の反射作用の発見者が仕事をしているところを見た」という形でBabinski徴候が登場する。また、谷崎潤一郎(1886〜1965)の小説『鍵』(1956)5)にも、Babinski徴候の描写が複数回みられる。新生児では正常でもBabinski徴候が陽性となるが、Babinski徴候が報告される400年以上前の中世の絵画にはすでに、足底の刺激やBabinski徴候の変法のような刺激で母趾が背屈していることが数多く描かれている6,7)。新生児が描かれた絵画にこの徴候を探すことは、筆者の美術館巡りでの楽しみの1つである。
2 0 0 0 ブロン依存症
Case患者:50代、男性。悪寒と発熱で受診。現病歴:もともとアルコール依存症であったが、6年前に禁酒し、以後禁酒継続できていた。また、1〜2年前よりうつ病と診断され精神科を受診していたが、自己中断している。 来院1カ月前に抑うつ症状が増悪。活動性が低下していた。3週間前より疲労感・倦怠感があり、徐々に食欲低下も進行。2日前に尿失禁し、やや興奮気味となり、来院の前日より悪寒を伴う発熱を認め、救急要請された。既往歴:うつ病、アルコール依存症。内服:現在はなし。身体所見:意識清明だが、軽度興奮・多弁。体温40.2℃、血圧156/89mmHg、心拍数140回/分(整)、呼吸数26回/分、SpO2 99%(室内気)。 眼球運動正常、瞳孔は4/4mm、対光反射は軽度鈍い。流涙や唾液分泌の亢進なし。顔面・皮膚紅潮なし。発汗あり。腹部腸管蠕動音はやや亢進。 胸部・腹部・四肢の診察にて、明らかな感染を示唆する所見は認められず。検査所見:WBC 16,940/μL(好中球88%)、Hb 16.1g/dL、Plt 23.5×104/μL、AST 263IU/L、ALT 66IU/L、LDH 1,125IU/L、ALP 241IU/L、γ-GTP 58IU/L、CPK 12,661IU/L、BUN 21.6mg/dL、Cr 1.4mg/dL、Na 132mEq/L、K 3.9mEq/L、Cl 94mEq/L、CRP 3.4mg/dL。 胸部X線、胸腹部CTでは、明らかな発熱のフォーカスとなる異常は認められない。 血液培養検査は陰性。初診時のアセスメントとその後の経過:フォーカス不明の発熱、興奮症状、頻脈、高熱、CPK上昇などより、何かしらの薬物、離脱症状の可能性を考慮した。アルコール摂取歴を再度確認するも、使用した形跡は認められなかった。家人に自宅内で薬物を探すように指示したところ、患者の上着ポケットからパブロンゴールドA®が複数発見された。 ベンゾジアゼピンを使用し経過をフォローしたところ、徐々に症状、検査所見は改善を認め、第5病日には症状の消失が得られた。 改善後にパブロンゴールドA®を見せつつ、薬物歴を本人から詳細に聴取した結果、以下の経過が判明した。●〜6年前:アルコール依存で入院。以後禁酒継続。●3年前:アルコールの代わりにパブロンゴールドA®やその類似薬を常用し始めた。連日1〜2袋、咳止め液として2本程度使用していた。●1〜2年前より無気力感や抑うつ症状が出現し、精神科にてうつ病と診断。投薬も受けたが、すぐに自己中断した。●1カ月前よりさらに無気力感が強くなり、咳止め液を1日に4本使用し始めた。さすがに使用に対して不安感があり、来院の3日前からは使用しなかった。 以上の経過より、最終的に「ブロン依存症、ブロン離脱症」と診断した。
2 0 0 0 現行犯逮捕か? 状況証拠での逮捕か? : 培養・塗抹・抗原検出・核酸PCR検査 (特集 病歴と診察で診断できない発熱! : その謎の賢い解き方を伝授します。) -- (さて、この検査をしよう!)
- 著者
- 成田 雅
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 総合診療 = Journal of generalist medicine : ジェネラルに診ることが求められる時代の臨床誌 (ISSN:21888051)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.4, pp.429-433, 2017-04
2 0 0 0 ヘアーターニケット症候群
2 0 0 0 ❺病理解剖すると認知症は、診断エラーが結構多い?!
- 著者
- 内原 俊記 融 衆太
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 総合診療 (ISSN:21888051)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.12, pp.1507-1509, 2019-12-15
認知障害やParkinson病の背景となる疾患は多様で、臨床診断が病理と異なる割合は、Parkinson病で25%1)、認知症では15〜70%に及ぶとの報告がある2)。髄液や画像所見を用いて診断精度を向上させようとする研究は盛んで、病態の一端を反映していることは確かだが3)、最終病理診断を参照して、これらの臨床検査の精度を評価した研究はほとんどない。臨床診断との相関を見ているこれらの検査は、たとえ理論的背景があっても、臨床診断の精度を超えることはないことを念頭に置く必要があり、診断の確定には病理解剖が不可欠である現状に変わりはない。 各疾患についての臨床像は本特集の別稿に譲り、本稿では、臨床診断と病理診断がどのように乖離するかについて解説する。
2 0 0 0 腎臓関連 「低ナトリウム血症」の初期対応 50を超えたオッサンでもICTは使いこなせる! (特集 内科診療を劇的に変える"まとめ"の達人) -- (領域別 達人の"とっておき"まとめ)
- 著者
- 杉本 俊郎
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 総合診療 = Journal of generalist medicine : ジェネラルに診ることが求められる時代の臨床誌 (ISSN:21888051)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.10, pp.834-841, 2016-10
- 著者
- 萩原 將太郎
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 総合診療 = Journal of generalist medicine : ジェネラルに診ることが求められる時代の臨床誌 (ISSN:21888051)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.7, pp.702-705, 2015-07
- 著者
- 天野 雅之
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 総合診療 = Journal of generalist medicine : ジェネラルに診ることが求められる時代の臨床誌 (ISSN:21888051)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.11, pp.1436-1440, 2021-11
- 著者
- 藤沼 康樹
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 総合診療 = Journal of generalist medicine : ジェネラルに診ることが求められる時代の臨床誌 (ISSN:21888051)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.5, pp.608-611, 2021-05
1 0 0 0 読むのも書くのも苦手な“英語”でまさかの外来診療を!?
筆者は現在、都内の「外国人向け診療所」という変わった職場に勤務しています。 信州大学医学部を卒業後、横須賀米海軍基地でインターン研修を1年、その後、横須賀共済病院で初期研修を2年やりました。米国での臨床研修に興味があったので、その準備期間として外国人診療を続けられるという意味で、今の診療所に勤め始めました。腰かけのつもりが結局そのまま居続けてしまった、というのが正直なところです。 これから、「東京オリンピック」の開催などで、ますます外国人の患者さんを診察する機会も増えてくると思います。そこで今回は、英語が苦手な先生方に、外国人診療のコツをお伝えしたいと思います。
- 著者
- 天野 雅之
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 総合診療 = Journal of generalist medicine : ジェネラルに診ることが求められる時代の臨床誌 (ISSN:21888051)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.3, pp.356-360, 2021-03
1 0 0 0 ① 突然、指が真紫!
1 0 0 0 ⑧ 歩くと楽になる呼吸困難?
- 著者
- 武者 幸樹子
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 総合診療 = Journal of generalist medicine : ジェネラルに診ることが求められる時代の臨床誌 (ISSN:21888051)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.12, pp.1644-1647, 2017-12
1 0 0 0 COVID-19の診断推論—コモンな臨床経過とピットフォール
CaseCOVID-19における二峰性の悪化患者:41歳、女性現病歴:発症3日前に、パーティに参加した。X日(発症日)に、38℃の発熱がありA医院を受診し、対症療法で帰宅した。翌日には解熱したが、軽い咳と喉の違和感は続いた。X+3日目に再度発熱し、パーティ参加者のなかに、のちにCOVID-19と判明した人がいたことがわかり、帰国者・接触者相談センターへ相談した。 X+4日目に新型コロナウイルスPCR検体が採取され陽性になり、X+5日目に当院に入院した。入院時は微熱と乾性咳嗽、軽度の呼吸困難があり、胸部X線では肺炎像は明らかではなかったが、胸部CTでは胸膜直下のすりガラス陰影がみられた。
- 著者
- 天野 雅之
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 総合診療 = Journal of generalist medicine : ジェネラルに診ることが求められる時代の臨床誌 (ISSN:21888051)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.6, pp.744-749, 2020-06