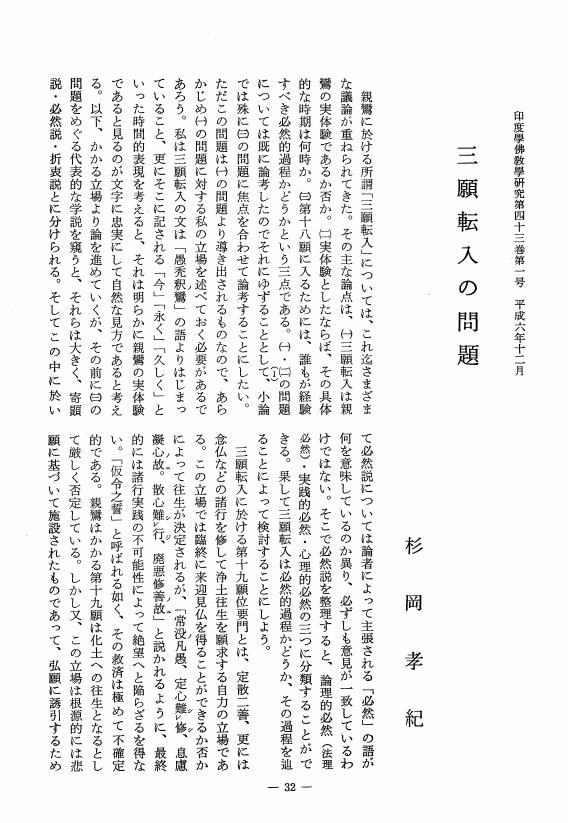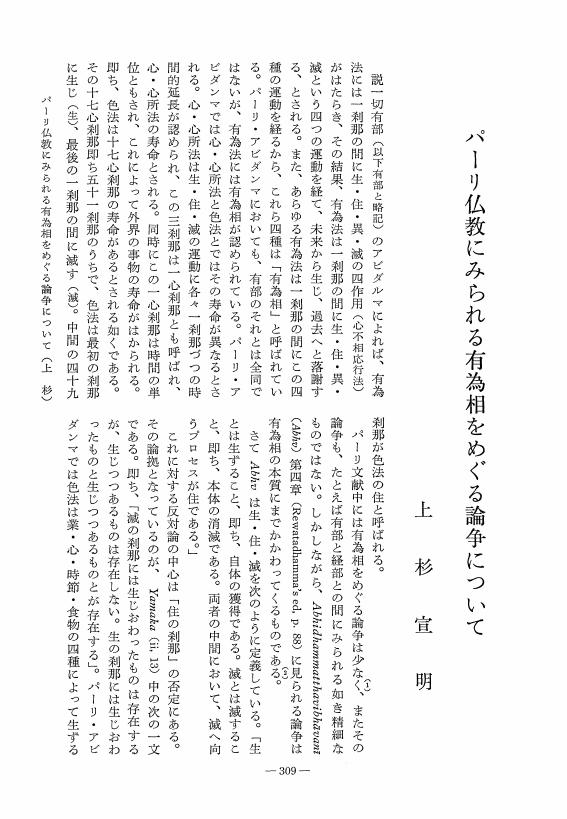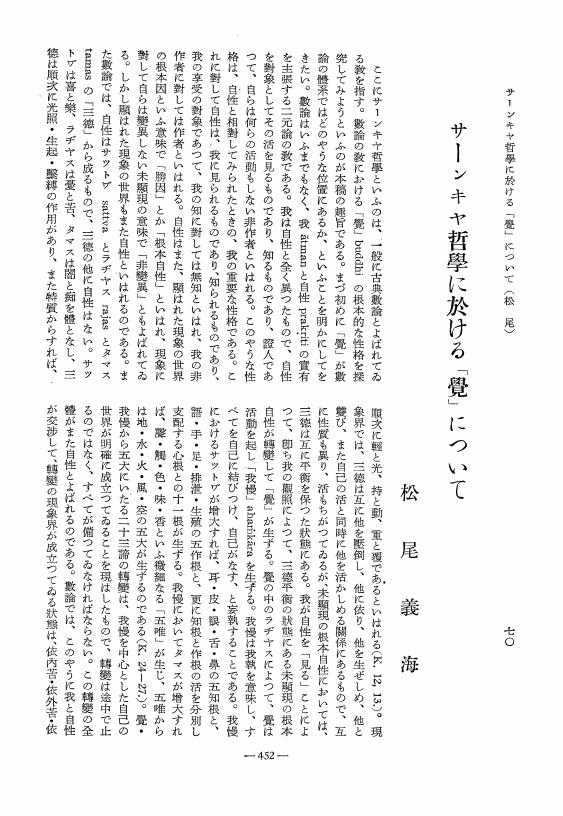1 0 0 0 OA 『頼慶記』に見られる法然
- 著者
- 長谷川 浩文
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.111-114, 2013-12-20
1 0 0 0 OA 三願転入の問題
- 著者
- 杉岡 孝紀
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.32-36, 1994-12-20 (Released:2010-03-09)
- 著者
- 鍵和田 聖子
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.604-607, 2009-03
1 0 0 0 OA Niratman と anatman
- 著者
- 村上 真完
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.550-557, 1971-03-31 (Released:2010-03-09)
- 著者
- 村上 真完
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.550-557, 1971
- 著者
- 村上 真完
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.550-557, 1971
1 0 0 0 OA indriyavrtti : 到達作用説と感官遍在説の相剋
- 著者
- 近藤 隼人
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:18840051)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.815-811, 2013-03-20
1 0 0 0 OA パーリ仏教にみられる有為相をめぐる論争について
- 著者
- 上杉 宣明
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.309-312, 1982-12-25 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 OA 中世禅宗と葬送儀礼
- 著者
- 石川 力山
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.800-805, 1987-03-25 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 OA 『サーンキヤ頌』の譬喩
- 著者
- 今西 順吉
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.837-843, 1982-03-31 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 OA サーンキヤ頌の系譜 -第七・九頌をめぐって-
- 著者
- 今西 順吉
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.566-567, 1960-03-30 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 OA 日本における『金七十論』の注釈書
- 著者
- 興津 香織
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.572-575,1292, 2006-03-20 (Released:2010-07-01)
The *Suvarnasaptatisastra, which is an important treatise of Samkhya philosophy, survives only in the Chinese translation done by Paramartha 眞諦 sometime between 548 and 569. Commentarial tradition begins with the citations from it found in the Chengweishi ulun shuji 成唯識論述記, written in Tang China, and continues with a real exegetical boom in 18th century Japan. Although the Japanese exegetes refer to the same passage cited in the Chengweishi/un shuji, they express different opinions concerning the *Suvarnasaptatisastra. I analyse the interpretations of this passage in the Kin shichiju ron biko 金七十論備考 by Gyo'o Gonzo 曉應嚴藏 (1724-1785), the Kin shichiju ron sho 金七十論疏 by Chido Hoju 智幢法住 (1723-1800), the Kin shichiju ron ge 金七十論解 by Shuro 宗朗 (?-1788), and the Kin shichiju ron so kyo 金七十論藻鏡 by Rinjo Kaido 林常快道 (1751-1810) and focus mainly upon their understanding of the relation between the prose parks of the *Suvarnasaptatisastra and Vasubandhu.
1 0 0 0 OA サーンキヤ哲學に於ける「覺」について
- 著者
- 松尾 義海
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.452-456, 1955-03-30 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 OA 根本説一切有部律系の諸本が傳える出家・受具足戒作法
- 著者
- 櫻部 建
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.496-504, 1964-03-31 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 OA バッティによるAstadhyayi 2.3.17の解釈
- 著者
- 川村 悠人
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:18840051)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.1081-1086, 2014-03-25
バッティが著した『バッティカーヴィア』(Bhk)は,ラーマ物語を描写すると同時にパーニニの文法規則を例証し,それによってパーニニ文法学を教示することを企図した作品である.川村[2013]で示したように,バッティが各文法規則に対して展開されるパタンジャリの議論を熟知していたことは疑いようがないが,彼は各規則を例証する際に必ずしもパタンジャリの解釈に従うわけではない.バッティはA2.3.17 manyakarmany anadare vibhasapranisuを例証するために,BhK 8.99においてtrnaya matva tah(「彼女達を藁だと考えて」)という表現を使用しており,このことは,彼がパタンジャリのA 2.3.17解釈に従っていないことを示している.パタンジャリによれば,A2.3.17中のanadaraという語は「単なる侮蔑」ではなく「激しい侮蔑」を意味するものとして解釈されるべきである.そして激しい侮蔑は,肯定文ではなく否定文,例えばna tva trnaya manye(「私はお前を藁だとも思わない」)のような文のみから理解される.「激しい侮蔑」を理解させる否定文のみがA 2.3.17の適用領域である.A 2.3.17中のanadaraという語は「単なる侮蔑」と「激しい侮蔑」のどちらも意味し得るから,その限りにおいてはバッティの表現も確かに成立し得る.しかし,パタンジャリの解釈に従っていないバッティの表現をバッティ以後のパーニニ文法家達がA 2.3.17の例として受け入れることはない.何故バッティはそのような表現を使用したのであろうか.この問題に対する手がかりを,我々は彼と同時代かかなり近い時代に活躍したと考えられるマーガとダンディンの作品中に見出すことができる.興味深いことに彼らもバッティと同種の表現を使用しているのである.パタンジャリが当時のモデルスピーカー達の実際の言語運用を観察して否定文のみをA 2.3.17の適用例として認めたのと同様,バッティも彼の時代の詩人達の言語慣習を考慮に入れて肯定文をA 2.3.17の適用例として提示したと考えられる.
1 0 0 0 OA 神格を区別する : ミーマーンサーにおける文脈分析の一例
- 著者
- 吉水 清孝
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:18840051)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.1124-1132, 2014-03-25
Mimamsasutra 2.1.14への註釈においてシャバラは,Jyotistoma祭でYajurveda(YV)祭官がソーマ液を捧げる神格が,その前にstotra (Samaveda (SV)の詠唱)とsastra(Rgveda (RV)の朗誦)で称えられる神格と異なる場合があると言い,stotra歌詞の実例としてRV 7.32.22冒頭を引用する.これは朝昼夕のソーマ祭のうち昼の第2回セッションに関し,YV文献がいずれも神格としてMahendraを指定しているのに,その際のstotraとsastraで用いるRV詩節ではIndraが「偉大な」(mahat)の形容なしに呼格で称えられていることに基づいている.シャバラは,MahendraがIndraとは別の神格であることを証明するために,Mahendraに捧げるソーマ一掬を表すmahendraは形容詞mahatと神格名indraと接辞aNより成ると分析できない,そう分析すると一語としての統一がとれなくなるから,と論ずる.しかしクマーリラは,もしそうであるならagnisomiyaもAgniとSomaを神格とする祭式と見なせないことになるし,パタンジャリも複合語の主要支分は外部の語を期待しつつ従属支分と複合すると認めていることを挙げて,シャバラの証明は成り立たないと批判する.そして,語の内部構造分析に終始する文法学の方法に代えて,ミーマーンサー独自の,語が文脈において果たす役割の分析を提起する.まず文は既知主題の提示部(uddesa)と,その主題に関する未知情報の陳述部(upadeya/vidheya)とに分析できるとした上で,仮に当該のYV規定文において,予め祭式に組み込まれていたIndraが主題であったなら,この規定文は既知のIndraに対し何を為すべきかという問いに,ソーマを献供すべしと答えることになる.この場合にはIndraが形容されていても,その形容は意図されたものではない.しかし実際にはこの規定文はsukra杯に汲んだソーマを主題として,それをどの神格に捧げるべきかという問いに答えており,mahatによる形容は,ここで規定されるべき神格の同定に必要不可欠であるから意図されたもの(vivaksita)である.従ってmahendraにおいて「偉大性」はIndraから切り離せないから,Mahendraは形容なしのIndraとは別神格であると結論を導く.クマーリラはこの論証において,日常の命令文においても,同じ語であっても文脈の中で意図されている場合と意図されていない場合があるという語用論的考察を行っている.
1 0 0 0 OA Abhiyuktaとは誰か? : Mimamsasutra 1.3.27を巡る問題
- 著者
- 友成 有紀
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:18840051)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.1133-1138, 2014-03-25
Mimamsasutra 1.3.27は同作品中で「文法学の論題」と通称されるセクションに位置し,この論題では主に(1)言葉には「正・不正」(sadhu/asadhu)の区別が存在するか,(2)存在するとしたらそれは何に由来するものか,(3)その区別は何に基いて知られるか,(4)正しい言葉だけでなく不正な言葉からも意味が理解されるのはなぜか,という四つの問題を扱う."abhiyukta"とはこの内(3)の問題で,ある言葉が正・不正のいずれであるのかを知る上での根拠とされる人々を指示ないし限定する語として現れる.後代の注釈や,現代の研究ではこれを「文法学者」を指すものとして解釈するのが主流であるが,シャバラの注釈を鑑みる限りでは,必ずしもその意味でのみ理解すべきではないように思われる用例がある."abhiyukta"という語と"sista"という語の関係もなお考察されねばならない.
1 0 0 0 OA Sphotasiddhi後半部における音素無常論について
- 著者
- 斉藤 茜
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:18840051)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.1139-1143, 2014-03-25
中世インドの言語哲学の発展は,文法学派が立てたスポータ理論をひとつの頂点とする.彼ら文法学派は,ことばを構成する最小のユニットとしてスポータ(sphota)を提唱した.その開顕に関して,我々はBhartrhari(5世紀)の著作Vakyapadiyaに最初の具体的な議論を見ることができる.Mandanamisra(8世紀初頭)はBhartrhariの思想を継承し,自身の著作Sphotasiddhi(SS)において,スポータ理論を完成させた.さて,SS最後1/4の部分で,対論者が音素論者(ミーマーンサー学派)から,音素無常論者(仏教)へ交代し,対論としてDharmakirti著作Pramanavarttika及びその自注(Svavrtti)(PVS)が,度々引用されるようになる(1章 Apauruseyacinta『非人為性の考察』).Mandanaが引用する対論の主張(pp.210-234)はPVS当該箇所の要約といってよい.本論文では,対論の内容をDharmakirti, Mandana,両者の視点から整理し,互いに異なる思想の中で,それぞれの特徴及び対立点を明らかにすることを試みる.仏教側の議論は,主として語を発信する側と受信する側の「意識」の問題に重きが置かれるが,話し手の側の意識の因果関係と,聞き手の側の意識の因果関係はPVSにおいて分けて記述されるため,両者の接続が妥当かどうかが議論の焦点となる.一方Mandanaの論駁においては「話者の同一性」の検証が重視され,これに関連して,普遍を有さない完全に個別的な音素が,どうやって話し手と聞き手の間で共有されるのか,という問いが対論に対して投げられる.
1 0 0 0 OA 医療臨床における僧侶の役割についての一試論
- 著者
- 打本 弘祐
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.547-542, 2009-12-20
1 0 0 0 OA チベット訳律蔵「布薩事」の内容
- 著者
- 佐々木 閑
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.338-331, 1986-12-25 (Released:2010-03-09)