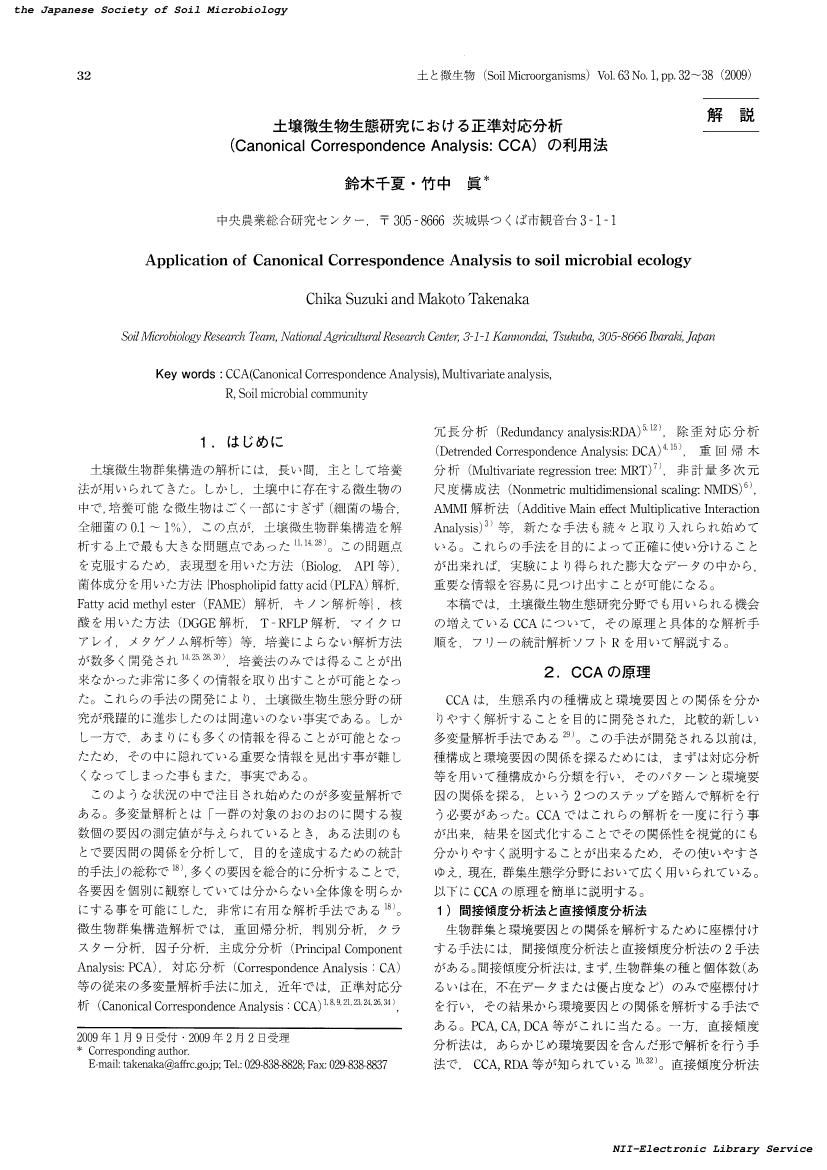1 0 0 0 OA 土壌中のウイルス(土の微生物世界)
- 著者
- 土崎 常男
- 出版者
- 日本土壌微生物学会
- 雑誌
- 土と微生物 (ISSN:09122184)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.7-11, 1993-10-01 (Released:2017-05-31)
- 被引用文献数
- 1
ウイルスは生きた細胞でのみしか増殖できないので,土壌中では植物の根,土壌微生物,土壌小動物等の中に存在している。tobacco mosaic virus等のTobamovirusは極めて安定なウイルスであるため,根から放出されたウイルスは,土壌中でもしばらくの間生存し,新たな宿主植物が植えられると機械的に根に感染を起こす。軟腐病菌等の土壌中の植物病原細菌にはバクテリオファージが感染しているが,これを細菌病の防除に使用する試みは成功しておらず,現在はファージを利用した細菌の分類,同定,検出,定量等の手段として用いられている。コムギ立枯病菌等の土壌中にある植物病原菌には,時に菌類ウイルスが感染している。菌類ウイルスの宿主である菌に対する影響,自然界での伝搬方法は殆ど明らかにされていない。コムギ立枯病菌のウイルスを例にとると,血清学的性状の異なる4群のウイルスが検出されており,しばしば同一細胞に複数のウイルスが感染することが明らかにされている。土壌伝染性植物ウイルスの媒介者として,土壌棲息菌が数種類認められているが,菌とウイルスの関係には2種類あり,1)休眠胞子中にウイルスが存在しそれより発芽した遊走子でウイルスの伝染が起こる場合,2)休眠胞子中にウイルスはなく,遊走子の表面にウイルスが吸着されてウイルスの伝染が起こる場合とがある。土壌に棲息する植物寄生性線虫の中のニセハリセンチュウ目により媒介されるウイルスとして約30種類が知られている。ウイルスを獲得した線虫は数ヵ月以上体内にウイルスを保持するが体内で増殖はしない。体内の食道等にウイルスが吸着されるが,その表面構造とウイルスの外被蛋白質との間の特異的な親和性等により,媒介の有無が決められる。
1 0 0 0 OA VA菌根菌資材の政令指定について(こんなことが,いま)
- 著者
- 伴 資英
- 出版者
- 日本土壌微生物学会
- 雑誌
- 土と微生物 (ISSN:09122184)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.80, 1998-03-01 (Released:2017-05-31)
1 0 0 0 関東および中部地方におけるキシャヤスデの大発生
- 著者
- 新島 溪子
- 出版者
- 日本土壌微生物学会
- 雑誌
- 土と微生物 (ISSN:09122184)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.15-18, 1981
1976年秋に国鉄小海線沿線をはじめとして中部山岳地帯でキシャヤスデJaponaria laminata(ATTEMS)が大発生した。キシャヤスデは日本固有種で,関東および中部地方に分布が限られ,約60年前から大発生による列車妨害の記録が残されている。秋に大発生したキシャヤスデはすべて成体で,その年の冬は10〜30cmの深さの土壌中で越冬し,翌年6月頃に交尾,産卵して一生を終える。卵は約1ケ月でふ化し,翌年から年1回つつ脱皮し,7年目に成体となる。幼虫はすべて地中で生活し,成体となった直後に群れをなして地表面をはいまわる。すなわち,気象条件や環境条件の激変がない限り,大発生の年から数えて8年目に再び大発生する可能姓が高い。このような観点から過去の記録を整理してみると,小海線浴線では8年周期でキシャヤスデが大発生していることがあきらかとなった。
1 0 0 0 OA トマトにおいて生育促進効果と青枯病防除効果を有する内生細菌の単離
- 著者
- 奈良 吉主 加藤 孝太郎 河原崎 秀志 田渕 浩康 後藤 正夫 寺岡 徹 有江 力 木嶋 利男
- 出版者
- 日本土壌微生物学会
- 雑誌
- 土と微生物 (ISSN:09122184)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.33-41, 2008-04-01 (Released:2017-05-31)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1
様々な植物を利用して,土壌から分離した植物内生細菌をトマトに接種し,青枯病発病抑制効果と生育促進効果を指標に選抜を行った。その結果選抜された3株のうち,イチゴを用いて捕捉したKSR01を種子処理した場合に,トマトの生育促進効果と青枯病発病抑制効果を併せ示すことを見出した。KSR01は青枯病菌に対する抗菌物質を産生しなかったので,青枯病発病抑制効果は,抵抗性誘導によることが示唆された。KSR01は種子処理した場合にトマト茎部から再分離されるため,組織に内生的に定着することが確認された。菌体脂肪酸組成,16S rRNA塩基配列の解析および細菌学的性質の調査から,KSR01をHerbaspiyillum huttiensisであると同定した。
1 0 0 0 土壌微生物研究会初代会長 故奥田東先生を偲ぶ
- 著者
- 山口 益郎
- 出版者
- 日本土壌微生物学会
- 雑誌
- 土と微生物 (ISSN:09122184)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.69-71, 1999
ジャガイモそうか病は北海道内全域で発生が見られるが,特に網走・釧路・根室地方の澱粉原料栽培地域での被害が顕著である。道内に分布する病原菌はStreptomyces scabies, S. scabies subsp. achromogenesと新種のS. turgidiscabiesならびに未同定のStreptomyces sp.の4種類と同定された。これら4種の病原菌の地理的分布には明かな偏りがあり,前2者は道央,道南地方に,後2者は道東地方に局在する。病原菌の識別の方法として,特異抗体の利用によるELISA法,種特異的プライマーの利用によるPCR法の利用の可能性が示された。さらに,種特異性を有する寄生性アクチノファージの利用も検討中である。今後,これらの応用による,土壌中の病原菌の定量法の開発が望まれる。土壌環境制御による本病の防除の試みの一例として,土壌水分環境の制御および土壌酸度調整の効果を検討した。土壌水分に関しては,レインガン,リールマシンなどの圃場潅水装置による防除効果が今後,期待される。土壌酸度調整による防除では,フェロサンド(硫酸第1鉄),硫酸アルミニウム,各種高蛋白質資材の効果は高いが,今後は局所施用(作条施用)による,低コストで効率的な防除方法の開発が必要である。これらの資材の第一次的な作用機作は土壌pHの降下によるものと考えられるが,その作用性ならびに実用性についてはさらに検討を要する課題である。難防除土壌病害とされる本病の防除法として,抵抗性品種の利用は不可欠である。しかし,将来的な優占菌種の変動などを考慮すると,抵抗性品種の利用と土壌環境制御および生物的防除などを組み合わせた総合的な防除体系を確立する必要がある。
1 0 0 0 OA 微生物資材開発の現状と課題
- 著者
- 野口 勝憲
- 出版者
- 日本土壌微生物学会
- 雑誌
- 土と微生物 (ISSN:09122184)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, pp.51-67, 1997-03-01 (Released:2017-05-31)
- 参考文献数
- 61
微生物資材の現状を把握するために研究の状況を整理した結果,病害防除についての研究が最も多くされており,次に脱臭・堆肥化・有機物分解が多く,特に畜産廃棄物関連の研究が多くなされており,環境問題への関心が高いのがわかる。拮抗菌については,使用菌の種類から使用法などについてまとめた。最近の特許を調査した結果,病害防除が圧倒的に多く,次いで害虫防除,生育促進,養水分吸収促進,有機物分解促進,土壌改良,除草,その他であった。次に微生物資材開発メーカー側の今後の課題として有効菌の選抜と同定, 追跡法の確立,使用菌の定着・活動条件の解明,効果維持・保存性を高めた資材化が必要であり,試験・研究機関・行政の課題として,微生物資材の基準作りとその評価法の確立,法の整備などの必要性を述べた。
- 著者
- 高木 滋樹 北村 章 丸本 卓哉 石田 大作 田中 秀平
- 出版者
- 日本土壌微生物学会
- 雑誌
- 土と微生物 (ISSN:09122184)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, pp.51-58, 1996-03-01 (Released:2017-05-31)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 3
1)種々の土壌環境下で,拮抗放線菌を含む微生物資材Aの施用が,土壌微生物相に及ぼす影響を調査した。pH5.3, 7.0, 7.8のいずれの土壌条件下においても,資材A施用により放線菌密度は高く維持されること,土壌水分量が極端に低く(20% MWHC)ない限り施用資材A中の拮抗放線菌は土壌に定着し活動すること,40℃の温度条件下で資材Aを施用した土壌において,F. oxysporumの密度は著しく低下するが,放線菌密度は影響を受けないことが確認された。また,資材Aの施用量が多いほど土壌中の放線菌密度が高くなることも明らかになった。2)資材Aの施用法とダイコン萎黄病に対する抑制効果の関係について検討した。資材Aの施用量が多いほど病害抑制効果は高くなった。また,土壌がF. oxysporumの汚染を受ける少なくとも1週間前までに資材Aを施用すると本病に対する高い抑制効果が得られること,あらかじめ土壌消毒を行った場合は土壌に速やかに資材Aを施用するとF. oxysporumの感染を遅延させ本病の防除に効果的であることが明らかとなった。3)資材Aとカニガラはともに連用によりダイコン萎黄病に対する抑制効果が高くなった。カニガラの効果は連用により徐々に高まったが,資材Aは1作目から直ちに高い効果を示し,少なくとも2作目まではカニガラよりも優れていた。4)以上の結果から,資材Aはダイコン萎黄病に対して多様な土壌環境下で抑制効果が期待できること,および施用法の工夫によってより高い効果が得られる可能性のあることが示された。
1 0 0 0 土壌の創造は何をもたらすか ―デザイナー・ソイルの可能性―
土壌はありふれた存在ながら、人工製造できない媒体だった。土壌機能(有機物を分解し無機養分を供給する機能)を人工的に再現できなかったためだ。土壌機能を再現するにはアンモニア化成、硝酸化成の2段階の微生物作用を再現する必要があるが、硝酸化成を担う微生物(硝化菌)が有機物の曝露で容易に不活性化するからだ。もし硝酸化成に成功しても、有機物と硝酸の同時併存で脱窒が活性化するため、重要な無機養分である硝酸が失われ、土壌機能を再現することが困難だった。並行複式無機化反応はこれを可能にした微生物培養技術だ。この手法で培養した微生物群を人工媒体に固定化すると、土壌機能をその媒体に付与することが可能となる。さらに最近になって、わずか3菌株(従属栄養細菌、アンモニア酸化菌、亜硝酸酸化菌)だけで土壌機能の基本であるアンモニア化成、硝酸化成を再現することに成功した。これにより、土壌の物理性・化学性・生物性のいずれについてもデザイン可能な技術が出そろった。本稿では、「デザイナー・ソイル」の可能性について紹介する。
1 0 0 0 OA 根粒菌の系統分類 : 過去・現在・将来
- 著者
- 澤田 宏之
- 出版者
- 日本土壌微生物学会
- 雑誌
- 土と微生物 (ISSN:09122184)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.39-_63-64_, 2003-04-01 (Released:2017-05-31)
- 参考文献数
- 104
- 被引用文献数
- 1
マメ科植物の根粒菌(共生窒素固定菌)を含むことが確認されている菌種は現時点(2003年2月)で12属44種(新種に相当すると考えられる4つの分離菌も含めた)に及ぶ。これらは,16SrDNA系統樹において根粒菌として1か所にまとまることはなく,AlphaproteobacteriaからBetaproteobacteriaにかけて分布する以下の9つの単系統群(1〜9)に分散すること,根粒菌以外の菌種(以下の括弧内に示した)と混在しながらそれぞれの単系統群を構成していることが認められた。単系統群1:根粒菌としてはRhizobiumおよびAllorhizobium属細菌が含まれている(非根粒菌であるAgrobacteriumおよびBlastobacter属細菌も単系統群1の構成メンバーとして混在している),2:SinorhizobiumおよびEnsifey属細菌(分類上の所属が不明とされている非根粒菌も混在),3:Mesorhizobium属細菌(非根粒菌であるAminobacterおよびPseudaminobacter属細菌も混在),4:Bradyrhizobium属細菌およびBlastobacter denitrificans(非根粒菌であるAgromonas, Nitrobactey, AfipiaおよびRhodopseudomonas属細菌も混在),5:"Methylobacterium nodulans"(非根粒菌のMethylobacterium属細菌も混在),6:Azorhizobium属細菌(非根粒菌であるXanthobacterおよびAquabacter細菌も混在),7:"Devosia neptuniae"(所属不明とされる非根粒菌も混在),8:Burkholderia属細菌(非根粒菌のBurkholderia細菌も混在),9:Ralstonia taiwanensis(非根粒菌のRalstonia属細菌も混在)。このうち,単系統群5,8および9については,いずれも単系統性が高く,多相分類学的な特徴付けも十分になされていることから,「根粒菌と非根粒菌が混在している状態の単系統群が,全体として1つの属にまとめられている」という現行の分類体系は今後とも存続していくものと思われる。それ以外の6つの単系統群に関しては,A)人為分類に基づく現行の分類体系を今後もそのまま存続させていく;B)分子系統解析の結果を重視し,単系統群全体を1つの属としてまとめる;C)単系統群の中に認められるより小さな系統ごとに属として独立させる,という3つの選択肢のうちのBあるいはCを有力候補としながら,属レベルの分類体系(定義と範囲)に関する研究・議論がこれから活発に進められていくであろう。
1 0 0 0 OA 木質バイオマス由来の廃液のメタン発酵抑制原因(2011年度大会一般講演要旨)
1 0 0 0 OA 植物葉圏における細菌群集の解析
- 著者
- 須田 亙 宍戸 雅宏
- 出版者
- 日本土壌微生物学会
- 雑誌
- 土と微生物 (ISSN:09122184)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.93-99, 2009-10-01
- 被引用文献数
- 1
葉に代表される植物体地上部の表面である葉圏には,多種多様な細菌が存在し,植物の健康維持や生態系における物質循環において重要な役割を担っていると考えられる。葉圏細菌に関する研究は,特定の機能を持つ菌を分離・培養し,それらの性質を調べる手法で行われてきた。これまで,細菌群集全体の構造や動態に関する研究は他の環境(根圏や水圏等)と比較すると著しく少なかったが,2001年以降,葉圏においても非培養法による細菌群集全体の構造解析が行われるようになり,知見が蓄積されつつある。本稿では,葉圏細菌群の生存戦略,および注目すべき機能について概説し,さらに,非培養法による細菌群集の解析によって明らかになってきた知見および今後の展望について論考した。
- 著者
- Togashi Satoshi Obana Shohei Watanabe Saori Horaguchi Satoshi Yashima Miwa Inubushi Kazuyuki
- 出版者
- 日本土壌微生物学会
- 雑誌
- 土と微生物 (ISSN:09122184)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.1, pp.3-9, 2013-04-01
Cyanobacteria were among the pioneer organisms of the early earth. They first colonized bare rock and had a strong ability to proliferate in infertile substrates, such as volcanic ash, desert sand, and rock. Cyanobacteria store enormous amounts of essential nutrients and metabolites within their cytoplasm. Those that grow in arid lands can be a very potent source of organic matter and nutrients that can be used to counteract desertification. In this study, we explored the potentiality of cyanobacterial strains collected from several regions of Asia (7 strains), Africa (3 strains), and Japan (6 strains). Some of the soils had salinity levels greater than 5 dS m-1 and an alkaline pH of 8.3-9.2. Cyanobacterial strains were screened for their potential to survive in such arid soils by quantifying individual salinity tolerance, ability to fix N2 in a medium containing 0.1M NaCl, and rates of photosynthesis and growth. The inoculation effects on the chemical properties of Alashan soils of Inner Mongolia (China) were evaluated using AL-S and Tateyama cyanobacterial strains. The soil pH of the surface and subsurface layers indicated that these strains can decrease pH to levels that are conducive to plant growth. These cyanobacterial strains have potential as anti-desertification agents for the bioreclamation of arid soils.
- 著者
- 近藤 熙
- 出版者
- 日本土壌微生物学会
- 雑誌
- 土と微生物 (ISSN:09122184)
- 巻号頁・発行日
- no.52, pp.100-101, 1998-10-01
1 0 0 0 OA Gigaspora margarita胞子の発芽に影響をおよぼす要因について
- 著者
- 小林 紀彦
- 出版者
- 日本土壌微生物学会
- 雑誌
- 土と微生物 (ISSN:09122184)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.13-28, 1988-03-01
- 被引用文献数
- 3
VA菌根菌の一種,Gigaspora margarita胞子の発芽に影響を及ぼす要因について検討した。その要因としては温度,土壌pH,燐酸カリ濃度,農薬(殺菌剤,殺虫剤,除草剤),植物根の有無,胞子の表面殺菌,土壌殺菌等の影響を調べた。また野外における本菌の胞子形成やその発芽等の季節的な変化を観察した。1.本菌の胞子発芽を大きく阻害する要因は温度と農薬であった。胞子は15℃以下の温度では全く発芽せず,最適発芽温度は25-35℃であり,40℃でも35%の胞子が発芽した。また,農薬の影響は殺菌剤の影響が大きく,とくにベンレート,ダコニールはそれぞれ有効成分の0.05, 3.75ppmで20%以下の胞子発芽率となった。これに比べて殺虫剤は同様の発芽阻害率に達するには殺菌剤より10倍程度高い。除草剤は通常の使用濃度で発芽阻害がみられた。2.土壌pH(4-8),燐酸カリ濃度,0-250ppm,植物根の有無,胞子の表面殺菌,土壌の殺菌等の処理は胞子発芽にほとんどあるいは全く影響を及ぼさなかった。3.1986年から1987にかけての野外でのメダケ自生土壌における本胞子の胞子形成や胞子発芽の季節的な変化をみると,5月に採取した胞子は野外で充分熟成していたため6日以内で発芽したが,6-8月に採取した胞子は発芽後の空か内容の貧弱な胞子が多かった。9月末には新しい胞子が採取できたが,全く発芽しなかった。10月も同様であった。11月採取のものは僅かながら発芽し,12,2月となると発芽がさらによくなった。このことから野外でも胞子は休眠期間を有していることが明かとなった。4.上述のメダケ自生土壌にシロクローバ,アルファルファ,キュウリを栽培して,栽培後3,4,6,8,10,12月と定期的に胞子を採取して調べた結果,いずれの時期の胞子も全く発芽しなかった。しかしこれらの胞子も殺菌水中か土壌中である程度の期間保存すると胞子が成熟して発芽が促進された。
1 0 0 0 OA メタゲノム解析を読む(バイオインフォマティクス解説講座(3))
- 著者
- 堀池 徳祐
- 出版者
- 日本土壌微生物学会
- 雑誌
- 土と微生物 (ISSN:09122184)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.22-26, 2012-04-01