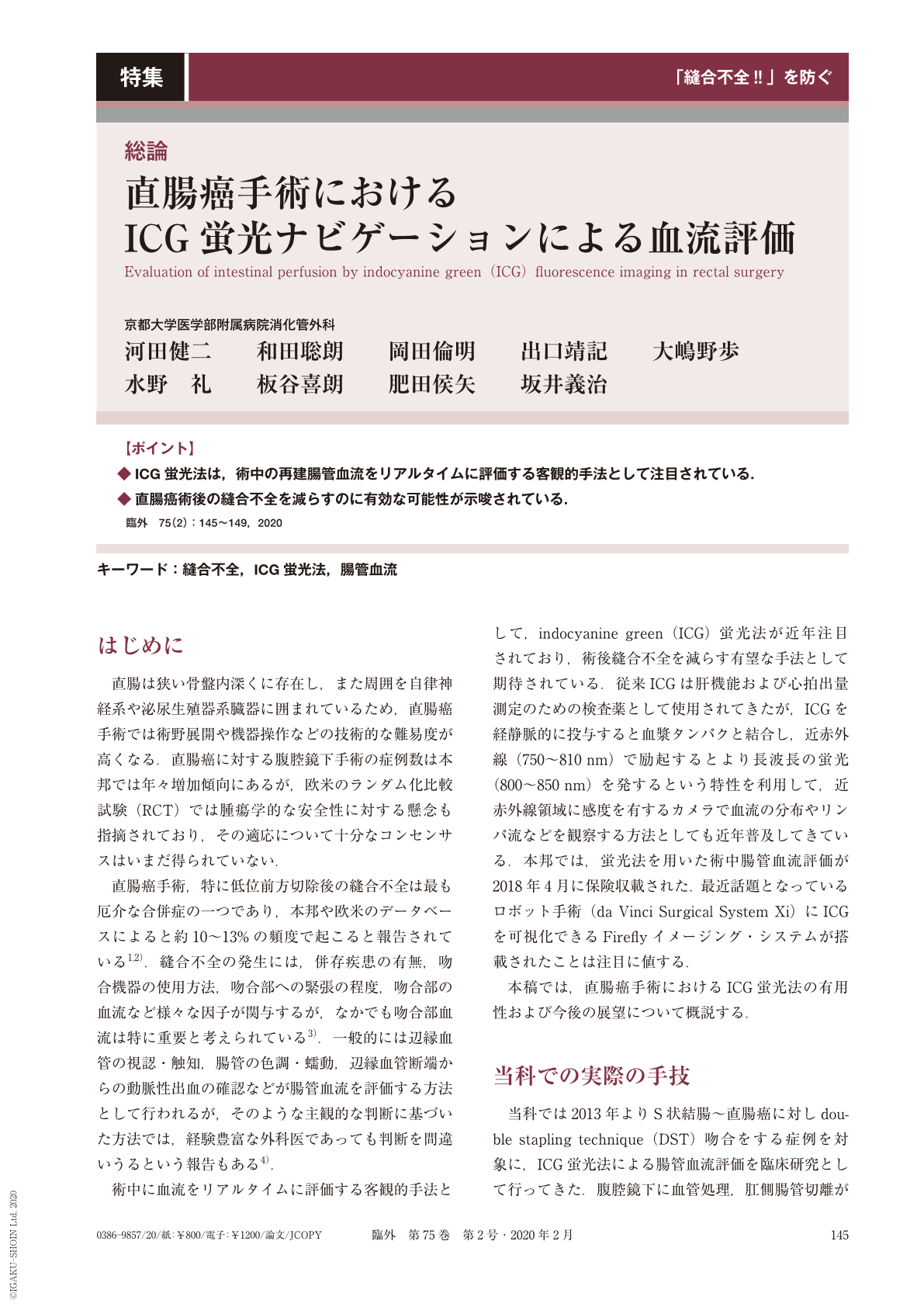35 0 0 0 気圧や気温の変化が痛みに与える影響について
- 著者
- 大森 絵美 西上 智彦 渡邉 晃久 脇 真由美 河田 健介
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, pp.A3P3054, 2009
【はじめに】日常臨床上,気象の変化による痛みの増強を訴える症例をよく経験する.これまでに,佐藤らはモデルラットを用いて気圧・気温の低下が痛み閾値を低下させることを明らかにした.また,国内で実施された「健康と気候に関するアンケート」の調査結果において,一般生活者及び慢性疾患患者の約7割が天候や季節変化による体調への影響を経験していることが報告されている.しかし,臨床現場において,実際に,気圧・気温の変化が痛みを惹起しているかは明らかでない.そこで,本研究の目的は気圧や気温が痛みに関与するか検討することである.<BR><BR>【方法】対象は本研究を理解し同意が得られ,調査期間中に他に痛みが増強する要因がなかったことを確認した本院外来通院患者21名(男性7名,女性14名,平均年齢68.3±13.0歳)とした.まず,調査初日に気象の変化が痛みに影響するかについて意識調査を行った.痛み,気圧,気温の調査は10月中旬から同年11月中旬の不連続な計10日間に行った.痛みの程度は毎回午前9時から午前10時の間にvisual analogue scale(以下:VAS)を用いて評価した.気圧・気温については気象庁ホームページより,本院から最も近い観測所のデータを参考にした.解析対象は,気圧については調査日の午前9時における気圧及び気圧変化量(午前8時の気圧から午前9時の気圧を引いた値)とした.気温については調査日の午前0時から午前8時までの間の最低気温及び気温変化量(調査前日の午後10時の気温から調査当日の午前6時における気温を引いた値)とした.統計処理はSPSS11.5Jを用いて行った.まず,VASと気圧・気圧変化量・気温・気温変化量のそれぞれの相関係数を求め,相関係数0.8をカットオフ値として2群に分割し,気象の変化が痛みに影響するかの有無とのFisherの正確確率検定を行った.また,VASを目的変数とし,気圧,気圧変化量,気温,気温変化量を説明変数としたStepwise法による重回帰分析を行った.なお,有意水準は5%未満とした.<BR><BR>【結果】気象の変化が痛みに影響すると回答したのは21名中16名であった.Fisherの正確確率検定において有意な差は認めなかった.重回帰分析によりVASに影響を与える説明因子として21名中20名に気圧を認めた.<BR><BR>【考察】気象の変化が痛みに影響を及ぼすかの意識と実際の気象と痛みの関係は乖離していた.また,佐藤らは人為的に起こした気圧低下・気温低下においてモデルラットの痛みの増強を確認しているが,自然な気象変化の中で行ったヒトにおける本研究では,気圧・気圧変化量・気温・気温変化量のうち,気圧がもっとも痛みに影響を与える因子であった.本研究から,気圧の低下が痛みを増強していることが明らかになり,理学療法実施時には十分考慮した上での評価,治療が必要と考えられる.
17 0 0 0 OA 気圧や気温の変化が痛みに与える影響について
- 著者
- 大森 絵美 西上 智彦 渡邉 晃久 脇 真由美 河田 健介
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.36 Suppl. No.2 (第44回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.A3P3054, 2009 (Released:2009-04-25)
【はじめに】日常臨床上,気象の変化による痛みの増強を訴える症例をよく経験する.これまでに,佐藤らはモデルラットを用いて気圧・気温の低下が痛み閾値を低下させることを明らかにした.また,国内で実施された「健康と気候に関するアンケート」の調査結果において,一般生活者及び慢性疾患患者の約7割が天候や季節変化による体調への影響を経験していることが報告されている.しかし,臨床現場において,実際に,気圧・気温の変化が痛みを惹起しているかは明らかでない.そこで,本研究の目的は気圧や気温が痛みに関与するか検討することである.【方法】対象は本研究を理解し同意が得られ,調査期間中に他に痛みが増強する要因がなかったことを確認した本院外来通院患者21名(男性7名,女性14名,平均年齢68.3±13.0歳)とした.まず,調査初日に気象の変化が痛みに影響するかについて意識調査を行った.痛み,気圧,気温の調査は10月中旬から同年11月中旬の不連続な計10日間に行った.痛みの程度は毎回午前9時から午前10時の間にvisual analogue scale(以下:VAS)を用いて評価した.気圧・気温については気象庁ホームページより,本院から最も近い観測所のデータを参考にした.解析対象は,気圧については調査日の午前9時における気圧及び気圧変化量(午前8時の気圧から午前9時の気圧を引いた値)とした.気温については調査日の午前0時から午前8時までの間の最低気温及び気温変化量(調査前日の午後10時の気温から調査当日の午前6時における気温を引いた値)とした.統計処理はSPSS11.5Jを用いて行った.まず,VASと気圧・気圧変化量・気温・気温変化量のそれぞれの相関係数を求め,相関係数0.8をカットオフ値として2群に分割し,気象の変化が痛みに影響するかの有無とのFisherの正確確率検定を行った.また,VASを目的変数とし,気圧,気圧変化量,気温,気温変化量を説明変数としたStepwise法による重回帰分析を行った.なお,有意水準は5%未満とした.【結果】気象の変化が痛みに影響すると回答したのは21名中16名であった.Fisherの正確確率検定において有意な差は認めなかった.重回帰分析によりVASに影響を与える説明因子として21名中20名に気圧を認めた.【考察】気象の変化が痛みに影響を及ぼすかの意識と実際の気象と痛みの関係は乖離していた.また,佐藤らは人為的に起こした気圧低下・気温低下においてモデルラットの痛みの増強を確認しているが,自然な気象変化の中で行ったヒトにおける本研究では,気圧・気圧変化量・気温・気温変化量のうち,気圧がもっとも痛みに影響を与える因子であった.本研究から,気圧の低下が痛みを増強していることが明らかになり,理学療法実施時には十分考慮した上での評価,治療が必要と考えられる.
3 0 0 0 OA 木戸孝允日記に記載された教育博物館の建設 明治初期の博物館計画に関する研究
- 著者
- 河田 健
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.739, pp.2393-2399, 2017 (Released:2017-09-30)
This paper verified the description of "Takayoshi KIDO diary" about the construction phase of the Educational Museum is as early museum building in Japan. And it revealed the relationship with Takayoshi Kido, verified for impact on construction due to the fact that he was involved. The point that became evident this is shown below. 1. It is known that the Educational museum exchanged the site with the Ueno museum just before construction. According to the Takayoshi Kido diary, prior to the exchange of this site Takayoshi Kido had confirmed the planning site and drawings. 2. According to the Takayoshi Kido diary it was confirmed that he was going 22 times to the construction site of the educational museum in August 1876 to January 1877. Not only Takayoshi Kido was in a position to lead the Japan at that time, it became clear that was deeply involved in the construction of the educational museum. 3. Key persons that has been promoting the business of the educational museum, Education Vice Minister Tanaka Fujimaro, the educational museum curator Hatakeyama Yoshinari, Ministry of Education audit Debit Murray, were not in japan during construction of the educational museum, because of they traveled to the US for the Philadelphia Expo. While responsible persons were absent, Ryuichi Kuki responded during construction. At the time Public buildings were in charge Ministry of Engineering, but after March 1876 buildings such as school had excepted from the project of them. Construction of the educational museum was ordered directly from the Ministry of Education like school. However the Ministry of Education at the time it was in a situation where there was no architectural engineers. Ryuichi Kuki asked Takayoshi Kido about the construction work. Actually Ministry of Engineering of technology bureaucracy Michiyoshi Hiraoka and Seiichi Asakura supported construction work underway. 4. For construction contents of the Educational Museum, It turned out that there was a point where Kido Takayoshi felt dissatisfied. It seems that he was dissatisfied with the design, because he seems to be unable to understand the structural one of architecture. This is because the educational museum was constructed without technicians with knowledge of Western architecture, and that Kido Takayoshi knew the European and American museum architecture through the Iwakura mission group. 5. According to the Kido Takayoshi diary design of a "window" and "floor" design was adjusted with Michiyoshi Hiraoka. resulting that window was become the similar shape as the Shinbashi station. 6. Regarding the external plan, Takayoshi Kido asked Magohachi Suzuki to design. Therefore, even though it is a Western building, outside design became a planting plan of Japanese style. For the early Meiji era of the Ministry of Education Buildings Department business was at that time still organizationally immature. The presence of Takayoshi Kido, and the support of the Ministry of Engineering by the connection between Takayoshi Kido and the former Choshu-han clan of Hiraoka Michiyoshi revealed the situation where a building with a new function called a museum was built.
- 著者
- 河田 健
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 学術講演梗概集. F-2, 建築歴史・意匠 (ISSN:13414542)
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, pp.363-364, 2011-07-20
2 0 0 0 OA 上野博物館の平面計画について
- 著者
- 河田 健
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.704, pp.2283-2289, 2014-10-30 (Released:2014-10-30)
This paper verifies the circumstances underlying the floor plan of the Ueno Museum. It also explores the relationships among the Ueno Museum, the Educational Museum, and the Kyoto Museum, planned during the early Meiji period. The floor plan of the Ueno Museum is characterized by straight lines that symmetrically divide the floor into rectangles. The divisions formed a route flow line leading visitors through all of the exhibition rooms, starting from the entrance hall.
1 0 0 0 OA 日本における音楽コンテンツ産業の変遷
- 著者
- 河田 健二 板野 敬吾
- 出版者
- 中国学園大学/中国短期大学
- 雑誌
- 中国学園紀要 = Journal of Chugokugakuen (ISSN:13479350)
- 巻号頁・発行日
- no.20, pp.29-36, 2021-06-16
音楽は人類の歴史の中で古くから存在し,現代においても日本人の生活に密着し親しまれている。また,音楽は視聴して楽しむだけでなく,儀式や宗教的な場で演奏されることもある。明治時代以降,日本では西洋音楽の存在を知るところとなり,広く楽曲視聴が普及してきた。ただし,現在ではその市場は徐々に縮小している。その理由はCD等,レコードショップ等で以前から販売してきたものや,「待ちうた」等のサービス販売が低迷してきたからである。 一方,ストリーミングによる楽曲の聴取が2013年頃から売上を伸ばしてきた。現在では,音楽コンテンツ市場全体を下支えしている状況にある。このようなストリーミングサービスが盛んになった背景には,インターネット回線の高速・大容量化とスマートフォンの普及があると考えられる。顧客層の嗜好の変化もあり,音楽コンテンツ市場は大きく変化することとなったのである。
1 0 0 0 直腸癌手術におけるICG蛍光ナビゲーションによる血流評価
1 0 0 0 OA 財団法人齋藤報恩会博物館と設計者小倉強について
- 著者
- 河田 健
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.693, pp.2373-2378, 2013-11-30 (Released:2014-07-10)
This paper analyzed the design process and contents of The Saito Ho-on kai Museum.•At the beginning,It was a building program of The Saito Ho-on kai Headquarters, Tsuyoshi Ogura was a jdging committee of competition. Next year it became a museum program, and design was requested to him.Design was able to be known 67 Drawings, the Saito Ho-on kai owns.• In planning, Not only an exhibition but library , hall ,etc were planned. It is positioned as a developmental process of The Museum Architecture which inherited from The National Museum of Nature and Science.