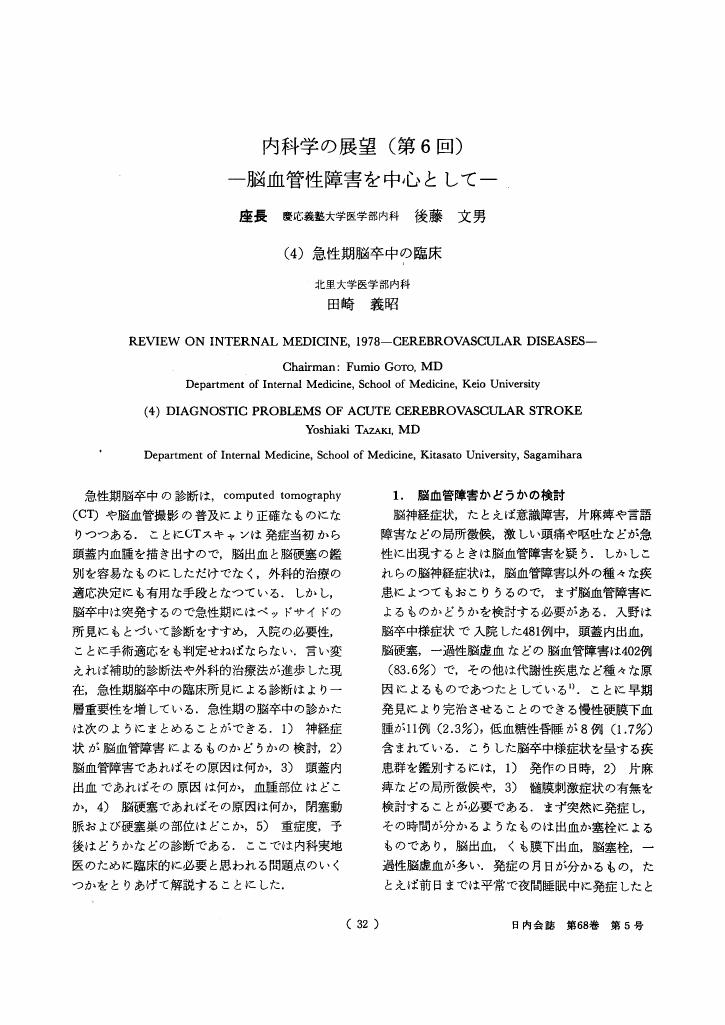3 0 0 0 OA 片頭痛と若年者脳梗塞との関係について
- 著者
- 東 邦彦 坂井 文彦 五十嵐 久佳 田崎 義昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中学会
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.5, pp.361-366, 1991-10-25 (Released:2009-09-03)
- 参考文献数
- 19
既往に片頭痛を持つ若年者に脳梗塞が発症した4例につき, 脳梗塞の危険因子としての片頭痛の意義につき検討した.症例1はmigraine with auraの発作中, 脳梗塞が発症したと考えられ, その病態としては前兆の原因となる脳血管攣縮が遷延し脳梗塞に移行したと考えられた.症例2~4の3例はmigraine without auraの患者で, 脳卒中発作は発症様式, CT, MRI所見よりはいずれも脳塞栓症と診断され, 脳塞栓症に頭痛が前駆あるいは随伴した可能性が考えられた.そのうち2例は妊娠中の発症であった.migraine without auraに脳梗塞が発症した機序としては, 片頭痛が脳梗塞に移行したというよりも片頭痛にもとづく血小板凝集能の亢進による5HT, ノルエピネフリンの放出, エストロゲソをはじめとする性ホルモンの変動による凝固系の亢進などを介して脳梗塞の危険因子となった可能性が考えられた.
3 0 0 0 OA アルコールの糖および脂質代謝に及ぼす影響
- 著者
- 衣川 秀一 中村 治雄 古和 久幸 田崎 義昭
- 出版者
- 北里大学
- 雑誌
- 北里医学 (ISSN:03855449)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.6, pp.363-369, 1974-12-31
Carbohydrate intolerance and hyperlipidemia have been known to be risk factors in atherosclerotic vascular disease. The present study was conducted to determine to what extent alcohol ingestion in man would cause the changes of plasma glucose and lipids in normal and atherosclerotic subjects. One hundred g of oral glucose tolerance tests, with and without 0.5g/kg alcohol ingestion 30 minutes prior to the test, were performed on each subject to measure glucose, immunoreactive insulin (IRI), free fatty acid (FFA), triglyceride, cholesterol, phospholipids and lipoprotein profile. Alcohol ingestion revealed a gradual increase of plasma TG with a concomitant increase of cholesterol in young and aged subjects. This would indicate that alcohol stimulates the release of pre-β lipoprotein from the liver. Under the present experimental conditions, alcohol failed to show glucose intolerance, but clearly increased plasma lipids. The result suggests that hyperlipidemia would be caused by alcohol ingestion and subsequently would result in atherosclerotic lesions.
2 0 0 0 OA 前脈絡叢動脈領域梗塞の臨床的検討
- 著者
- 日野 英忠 古橋 紀久 神田 直 田崎 義昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中学会
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.106-110, 1989-04-25 (Released:2009-07-23)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
頭部X線CTにより診断した前脈絡叢動脈領域梗塞7症例について臨床的検討を行った.神経症状として片麻痺, 半身感覚鈍麻, 半盲の三主要徴候のほか, 全例に著明な自発性低下, 記銘力障害を急性期に認めた.これらの発現機序として, 視床障害の関与を推察した.また見当識障害, 失計算も多くみられ, さらに大脳皮質症状である半側視空間失認, 病態失認も認められた.CT所見は特徴的な内包後脚全域の低吸収域のみならず, 外側膝状体に及ぶ病変も多くみられたが, 視床, 側頭葉, 中脳などのその他の灌流域での異常は認められなかった.脳血管写上, 多くの症例では本血管の主幹部または分岐部内頚動脈での狭窄所見を認めた.脳梗塞発症の原因として脳動脈瘤クリッピング, 高血圧症があげられる.その他蛋白同化ステロイド薬使用後, 再生不良性貧血, 妊娠中の発症があり, さらに性交を契機とした例もみられた.
1 0 0 0 OA (4)急性期脳卒中の臨床
- 著者
- 田崎 義昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.5, pp.498-505, 1979-05-10 (Released:2008-06-12)
- 参考文献数
- 17
1 0 0 0 OA 脳卒中急性期にみられる低カリウム血症
- 著者
- 青木 信平 五十嵐 久佳 坂井 文彦 神田 直 田崎 義昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中学会
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.175-179, 1988-04-25 (Released:2009-09-03)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
脳卒中急性期の患者を対象に血清K値の変動を観察した.対象は発症後24時間以内に来院した脳卒中患者161例 (脳出血96例, 脳梗塞65例) である.脳出血患者の平均血清K値3.63±0.05mEq/l (SE) は脳梗塞の平均値4.02±0.05mEq/lよりも有意に低値を示した (p<0.01).脳出血患者を意識レベルによりunresponsive群とresponsive群とに分け検討すると, 血清K値はそれぞれ3.43±0.76mEq/lと3.79mEq/lであり, unresponsive群が有意に低かった (p<0.01).また, 死亡群の平均血清K値3.51±0.06mEq/lは生存群の平均値3.72±0.06mEq/lよりも低く (p<0.05), 重症例では血清K値が低下することが示された.血漿エピネフリン濃度および血糖値と血清K値の間には有意な負の相関がみられ, 低K血症の発現は, ストレスに起因したKの細胞内への流入の可能性が考えられた.
1 0 0 0 OA 脳卒中急性期における血中カテコールレアミンの変動
- 著者
- 神田 直 林 英人 小林 祥泰 古橋 紀久 田崎 義昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本脳卒中学会
- 雑誌
- 脳卒中 (ISSN:09120726)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.3, pp.299-306, 1980-09-25 (Released:2010-01-22)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 4 1
脳卒中急性期の交感神経活動を知る目的で発症48時間以内の患者64例を対象に血漿カテコールアミンの変動を観察した.血漿ノルエピネフリン (NE) 値は, 脳出血, くも膜下出血, 脳梗塞の順に高く, その平均値はそれぞれ753±116pg/ml, 630±291pg/ml, 397±65pg/mlであった.脳出血の平均値は脳梗塞と対照とした非神経疾患々老19例の平均値292±2gpg/mlよりも有意に高値を示したが, 脳梗塞と対照の間には有意差を認めなかった.血漿NEの上昇はとくに大血腫, 広範な梗塞を伴う重症例で著しかった.死亡した13例の血漿NEの平均値1,199±162pg/mlは生存43例の平均値362±39pg/mlより有意に高く, 入院時の血漿NEは患者の生命予後を良く反映した.血漿エピネフリンについても同様の傾向がみられた.脳卒中急性期には交感神経系の興奮と副腎髄質機能の尤進を伴い, とくに予後不良な重症例で著しい.脳卒中急性期には脈拍,血圧,呼吸,体温などのvital signにしぼしば著しい変化がみられ,また発汗過多,消化管出血などを伴うことが少くない.これら多彩な臨床症状の発現には自律神経系が密接に関与していると推定される.さらに脳卒中患者ではValsalva試験における反応異常, 起立性低血圧, 体位変換に伴う血中ノルエピネフリン (NE) 反応の低下など自律神経機能異常がみられることが報告されている.一方最近では脳循環の調節機序における自律神経系の役割が注目され, 脳卒中急性期にみられる脳循環代謝動態の異常にも自律神経異常を伴うことが推測されるが,現在のところこれを実証するような成績は得られていない.したがって脳卒中急性期の自律神経活動についての観察は, 脳卒中の病態を解明する上でのひとつのアプローチになると考える.血中NEは主として交感神経の末端に由来し, その変動は交感神経活動をかなり鋭敏に反映すると考えられている.脳卒中患者においては尿中カテコールアミン (CA) 排泄量の増加があり, さらに血中 CAレベルが上昇することが報告されている.また交感神経刺激によりNEと共にexocytosisによって放出されるといわれるドーパミン-β-水酸化酵素 (DEH) 活性も脳卒中急性期には血中で上昇する.血清DBH活性の変動からみても, 血中NEの変化は脳卒中発症数日以内の急性期に著しいことが予想されるが, これらの報告者の成績ではその検討が十分になされていない.また血中CAレベルと臨床症状との詳細な関係についても明らかでない.最近のCA測定法の進歩は目覚しく, 特異性と感度に優れた測定法が開発されつつある.一方CTスキャンの導入により脳血管障害の診断精度は著しく向上し, 出血と梗塞の鑑別はもとより, 病巣部位までかなり正確に診断が可能となった.そこで著者らはとくに脳卒中発症後極く早期の患者を対象に血中CAの変動を観察し, さらにその臨床的意義についても検討を行った.