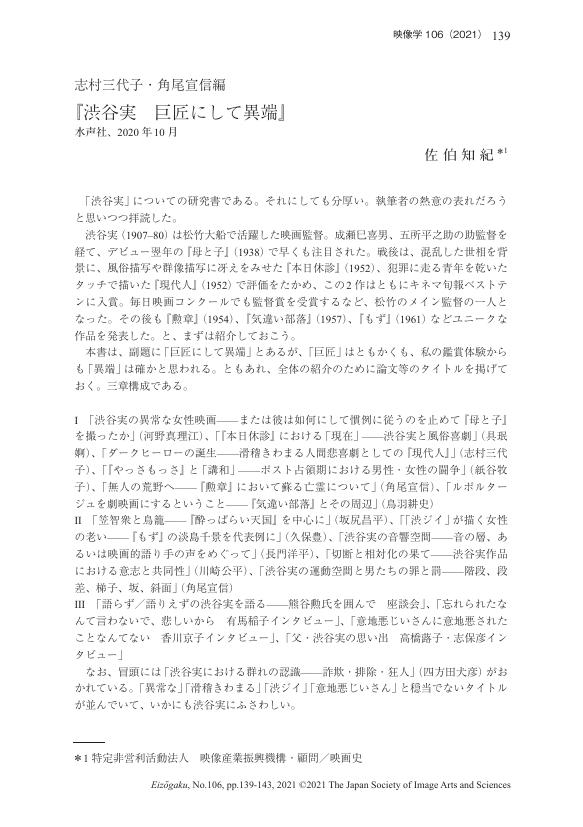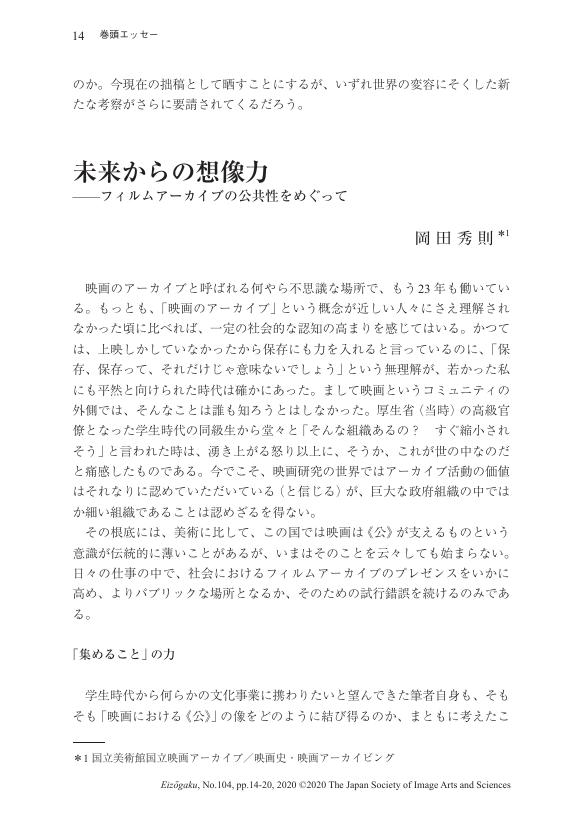- 著者
- 久後 香純
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.122-143, 2022-08-25 (Released:2022-09-25)
- 参考文献数
- 63
本稿は、1960年代後半から70年代初頭の日本において生まれた「アノニマスな記録」という写真のリアリズム言説を研究対象とする。東松照明、内藤正敏、中平卓馬、多木浩二ら戦後世代の写真家たちは、写真は個人の「表現」ではなくアノニマスな「記録」として存在するべきだと主張した。本研究では、この新しい写真概念の形成過程をたどる。その目的は、ありのままを写すとされる写真の記録性をテクノロジーに担保された必然として受け入れるのではなく、歴史的に構築されたモノとしてその言説の歴史性と政治的含意を問うことにある。まず本稿前半部分では、アノニマスな記録という言説が生まれるきっかけとなった「写真100年」展を取り上げる。そこで明らかにするのは展覧会を企画した日本写真家協会内部で、木村伊兵衛、土門拳、渡辺義雄に代表される戦中世代と先に名前をあげた戦後世代の間に明確な対立関係があったことだ。ただし、この対立を踏まえたうえで、本稿後半部分では、戦後世代が戦中世代から受け継いだ言説があったことを明らかにする。とくに注目するのは両世代ともに写真家が主体的な「観察者」であることを重要視した点である。以上の過程を通して、日本写真史におけるリアリズムの系譜を示す。
2 0 0 0 OA 須藤健太郎著『評伝ジャン・ユスターシュ 映画は人生のように』共和国、2019年4月
- 著者
- 福島 勲
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, pp.108-111, 2021-01-25 (Released:2021-02-25)
2 0 0 0 OA セル・アニメーションにおける多層化の起源としてのムーヴィング・パノラマ
- 著者
- 小倉 健太郎
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.34-56, 2022-08-25 (Released:2022-09-25)
- 参考文献数
- 47
1910年代に伝説的なアニメーターであるノーラン(Bill Nolan)によって発明されたスライド技法は、撮影台の上で背景画を引っ張ることでキャラクターや視点の移動を表現する技法である。この技法は19世紀初頭に誕生したムーヴィング・パノラマと明らかに類似している。ムーヴィング・パノラマは長尺の絵画を機械によって巻き取りながら眺める装置であり、スライド技法が誕生した1910年代には舞台や映画の背景としても用いられていた。1910年代にノーランはニューヨークで働いており、それらのムーヴィング・パノラマが身近にあった。さらに彼が発明したスライド技法自体もまた、当時の米国で一般的にムーヴィング・パノラマを指した「パノラマ」という語で呼ばれていた。そうした状況から鑑みて、ムーヴィング・パノラマはスライド技法の着想源の一つになった可能性が高い。スライド技法を用いたセル・アニメーションではレイヤーが多層化し運動視差を再現しようとする傾向が見られるが、こうした傾向は舞台装置や万国博覧会の展示に用いられたムーヴィング・パノラマにも共通して見られる。レイヤーをスライドさせるというムーヴィング・パノラマの構造の内に、多層化していく契機が含まれているのだ。
2 0 0 0 OA 戦後日本における伝統芸能のアダプテーション——内田吐夢の『暴れん坊街道』を中心に
- 著者
- 藤田 奈比古
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, pp.46-66, 2021-01-25 (Released:2021-02-25)
- 参考文献数
- 34
映画監督内田吐夢(1898-1970)は歌舞伎および浄瑠璃を原作とした時代劇映画を4本手がけ、それらは「古典芸能四部作」として知られている。本論文は、その一作目であり近松門左衛門の浄瑠璃を原作とする『暴れん坊街道』(1957年)を取り上げ、企画の成立過程と作品分析を行う。第1節では、まず敗戦後、民族主義的な言説を背景に左派的な近松の読み直しと、近松作品の映画化が進んだことについて概観する。そして内田吐夢が敗戦後満州(中国東北部)滞在において伝統芸能への郷愁を核に民族意識を変化させたことを明らかにし、左派映画人を交えて『暴れん坊街道』の企画が練られた過程を複数の台本の検討を通して論じる。第2節では、当時国文学および歴史学の分野で盛んになった封建制批判の観点からの近松解釈に沿うようにして、本作における登場人物の身分の剥奪が、自己同一性と深く関わる「名前」の与奪によって描かれ、身分の異なる者たちが街道という空間で出会い、関係しあうことを論じる。第3節では、原作の見せ場である「重の井子別れ」を含む二つの愁嘆場が、メロドラマ的な要素に満たされ、感情の抑圧と情動の爆発を伴いながら、感情的な同一化よりもむしろ人物たちの置かれた状況への知覚に観客を向けるものとして演出されていることを明らかにする。
- 著者
- 高崎 郁子
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.183-205, 2022-08-25 (Released:2022-09-25)
- 参考文献数
- 35
本論ではマイケル・パウエルとエメリック・プレスバーガーがコンビを組み「アーチャーズ」として製作したイギリス映画、『その信管を抜け!』(1949)の分析を行う。本作は「傷ついた男性性」を主題としており、その描写は同時代の他のイギリス映画と比較しても、他を圧倒するほど露骨に描かれている。そこで本論では、戦後映画という横断的な視点に『その信管を抜け!』を位置づける。そのうえで、『我等の生涯の最良の年』(1946)における第二次世界大戦後の傷ついた男性性の描写を「歴史的トラウマ」という概念から解き明かしたカジャ・シルヴァマンの考察から、作品に登場する特徴的な男性性を分析するために、映画においてとりわけ象徴的なウィスキーの瓶と爆弾のシークエンスを細かく確認し、それらがファルス的役割を持つことを明らかにした上で、本作における傷ついた男性性の特性を見出す。さらに、主人公をめぐる男性と女性の関係を、イヴ・K・セジウィックの「ホモソーシャルな欲望」を参照しながらテクスト分析することで、この作品が一見異性愛主義的なナラティヴを持ちながらも、実際は男性同士の強いつながりと、女性の徹底的な排除という特異なジェンダー構造を持つことを証明する。
- 著者
- 青山 太郎
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, pp.158-162, 2022-02-25 (Released:2022-03-31)
2 0 0 0 OA 志村三代子・角尾宣信編『渋谷実 巨匠にして異端』水声社、2020年10月
- 著者
- 佐伯 知紀
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, pp.139-143, 2021-07-25 (Released:2021-08-25)
2 0 0 0 身体による親密圏の構築
- 著者
- 中根 若恵
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, pp.5-23, 2017
<p>【要旨】<br>1990年代以降、映画制作者が、自身やその身辺の事柄を主題にするセルフドキュメンタリーの領域に、多くの女性制作者が参入するようになった。これは制作的な側面が男性によって担われることが多かった映画界に大きな変化をもたらした。本稿は、そうした女性のセルフドキュメンタリーの事例として、河瀨直美(1969年-)の作品群に注目し、その特徴と社会的意義を明らかにする。まず第一に、河瀨の作品群にはフィクションとドキュメンタリーの境界を曖昧化するようにして、自らの私生活に焦点を当てるパフォーマティヴな自己表象が一貫した特徴として見られることを指摘する。その上で第二に、そうした自己表象が物質的な身体の提示とも結び付けられながら、慣例的な家族の枠組みを超えた「親密圏」とも呼べる他者との親密な関係の構築過程が示されていることを論じる。最後にこれら2点について、出産をテーマにした2作のドキュメンタリー映画、『垂乳女 Tarachime』(2006年)と『玄牝-げんぴん-』(2010年)を事例に取り上げ、詳細に検討する。こうした考察を通して、河瀨のドキュメンタリー作品群は、一般に女性と結び付けられている行為を敢えてパフォーマティヴに見せながら具体的かつ個別的な他者とのつながりを生み出すことの重要性を見せており、それは、身体というもっとも具体的な自己を起点とした新しい形の親密圏から公共圏へのつながりを見せる点で、自己決定によるオルタナティヴな共同体のあり方を示していると結論づける。</p>
2 0 0 0 OA 未来からの想像力——フィルムアーカイブの公共性をめぐって
- 著者
- 岡田 秀則
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, pp.14-20, 2020-07-25 (Released:2020-08-25)
2 0 0 0 OA 小津安二郎『お茶漬の味』における画面外の声
- 著者
- 正清 健介
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, pp.25-47, 2017-07-25 (Released:2017-09-13)
- 参考文献数
- 21
【要旨】本稿は、小津安二郎の映画『お茶漬の味』(1952)における対話上のカッティングポイント(CP)の原則を、物語との関係において明らかにするものである。その目的は、サイレント=ハリウッドの影響下にあった小津がどのようにその規範を受け独自のトーキー規範を編み出したか、その一端を明らかにすることである。デヴィッド・ボードウェルは、表情に対する台詞の先行性というトーキーの特性から小津が台詞の後に一定の間合いを置き、CP を人物が話し終わる時(終わった後)に設定したと指摘する。しかし、本作のCP は必ずしもこの規則に従っていない。小津は時折、話し手が話し終わる前にCP を設置している。この事例は、小津がショットを「視覚的・言語的に統一されたブロック」とみなしたとするボードウェルの主張において例外として立ち現れる。小津は、時としてブロックとしてのショットの統一性を壊してでも、CP を前倒しという形で修正して台詞を聞き手のショットに被せている。それにより、話し手の音声の聞き手のショットへの侵犯という事態を浮上させ、それを物語上の人物の力関係と連動させることで、映像と音声というレベルにおいて話し手の聞き手に対する精神的圧力を表象している。その圧力は、ミシェル・シオンが「既に視覚化されたアクスメートル」と呼ぶ画面外の声が権能を振るった結果だと解釈可能である。視覚面の分析に偏向する先行研究に対し、本稿は音声とショットの関係に着目することで映画音響論として本作を再考する新たな試みである。
- 著者
- 住本 賢一
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, pp.242-251, 2020-07-25 (Released:2020-08-25)
- 著者
- 早川 由真
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, pp.75-93, 2019-07-25 (Released:2019-11-19)
- 参考文献数
- 40
本論文の目的は、縫合理論を手がかりに、リチャード・フライシャー『見えない恐怖』(See No Evil, 1971 年)における不可解なショットの分析を通じて、殺人者というキャラクターの生成(およびその不成立)のメカニズムを明らかにすることである。このフィルムにおける不可視性を活かしたサスペンスは高く評価されてきたが、クライマックスにおいてキャメラが水中からジャッコを見上げる不可解なショットに関しては、暴力や死の不可視化に関連しているにもかかわらず、これまでに論じられてこなかった。そこでまず、盲目の主人公・サラの「視点」を示すかのようなこのショットを、エドワード・ブラニガンの議論を手がかりに、〈盲者の視点ショット〉ととらえる視座を導きだす(第 1 節)。次に、縫合理論をキャラクターの生成という観点から整理しつつ、顔の見えない殺人者がクライマックスの直前でブーツをわざわざ脱ぐために、ブーツとジャッコの顔がいちども同一画面に映りこまないという事実を指摘する(第 2 節)。そして、殺人者の現れ方を分析していく過程で、ブーツとジャッコの顔の結びつき、すなわち〈身体の縫合〉には綻びがあり、ジャッコは殺人者というキャラクターとしてうまく成立しないことを明らかにする。最終的に、水中からのショットにおいては、不可視であるはずの殺人者の顔が不在(無)として画面上に露呈するという複雑な事態が生じていることが浮かびあがってくる(第 3 節)。
- 著者
- 斉藤 綾子
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, pp.274-278, 2020
2 0 0 0 OA 川崎公平著『黒沢清と〈断続〉の映画』(水声社、2014年12月)
- 著者
- 藤井 仁子
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, pp.135-138, 2016-07-25 (Released:2016-08-19)
- 著者
- 加藤 哲弘
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, pp.278-282, 2020-07-25 (Released:2020-08-25)
- 著者
- 山本 祐輝
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, pp.24-41, 2015
<p></p><p> Loudspeaker sounds, both announcements for army doctors and radio programs, are frequently inserted in Robert Altman's film <i>M*A*S*H</i> (1970). Accompanied by close-up shots of a loudspeaker, these sounds are undoubtedly diegetic; that is, they can be heard by the characters. However, none of the characters react to them, and the announcer is never seen. These sounds are located in a domain that cannot be grasped by the binary opposition of the diegetic and the non-diegetic.</p><p></p><p> This paper considers that while the loudspeaker sounds are backgrounded within diegesis, they are simultaneously foregrounded outside of the diegesis to which the spectator belongs. This activity, the collecting sounds ignored by the characters and manipulating them for emphasis, is due to the "cinematic narrator."</p><p></p><p> This cinematic narrator's activity is mimicked by the protagonists; they eavesdrop on and broadcast a sexual act of Houlihan and Burns. By sharing narrative authority with the cinematic narrator, they create and narrate an episode, which retells Houlihan as "Hot Lips." This paper demonstrates that Hot Lips' story, narrated by the protagonists, merges into the whole story of the cinematic narrator. Thus, two different narrative levels coexist without formal boundaries, as in Mikhail Bakhtin's concept of "hybrid utterance."</p><p></p>
2 0 0 0 OA 最初期の「皇室映画」に関する考察:
- 著者
- 紙屋 牧子
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, pp.32-52, 2018-07-25 (Released:2019-03-05)
- 参考文献数
- 37
【要旨】 本稿は最初期の皇室映画(天皇・皇族を被写体とした映画)に焦点をあてる。昭和天皇(当時は皇太子)が1921年に渡欧した際、国内外の映画会社・新聞社によって複数の「皇太子渡欧映画」が撮影され、それが画期的だったということは、これまで皇室研究またはジャーナリズム研究のアプローチから言及されてきた。それに対して、映画史・映画学のアプローチから初めて「皇太子渡欧映画」について検討したのが、拙論「“ 皇太子渡欧映画” と尾上松之助―NFC 所蔵フィルムにみる大正から昭和にかけての皇室をめぐるメディア戦略」(『東京国立近代美術館 研究紀要』20号、2016年、35-53頁)であった。この研究をさらに発展させ、「皇太子渡欧映画」(1921年)以前に遡ってリサーチした結果、「皇太子渡欧映画」に先行する映画として、有栖川宮威仁(1862-1913)が1905年に渡欧した際に海外の映画会社によって撮影された映画が存在すること、それらには複数のバージョンがあり、そのうちの1 本がイギリスのアーカイヴに所蔵されていることが判明した。本稿では、これらの映画がつくられた背景について明らかにすると同時に、この映画が皇室のイメージの変遷の中で持つ歴史的意味について考察した。その結果、「有栖川宮渡欧映画」は、「皇太子渡欧映画」への影響関係もうかがえるものであり、戦前期の「開かれた」皇室イメージの形成への歴史的流れを考えるうえで、きわめて重要な参照項となり得る映画であるという結論に至った。
2 0 0 0 大正期から昭和初期における齣フィルムの蒐集と文化
- 著者
- 福島 可奈子
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, pp.46-68, 2018
<p>【要旨】</p><p> 大正から昭和初期にかけての子供による映画の齣フィルム蒐集とその文化について、従来見過ごされてきたメディア機器とその多様性を実証的に再考する「メディア考古学」の視座から考察する。齣フィルムとは、明治末から昭和初期にかけて映画館や玩具店等、様々な場所で販売されたワンフレームサイズの映画フィルム(18×35mm)のことで、大正期には子供による映画の齣フィルム蒐集が大流行を迎える。その事象についてはしばしば先行研究で言及されているものの、その実情については今までほとんど明らかにされてこなかった。そのため本稿では、当時の子供の齣フィルムコレクションや齣フィルム用の実体鏡や幻燈機等の実物史料を参照しつつ、明治末から昭和初期にかけて販売された齣フィルムについて、販売業者と購入者(蒐集者)双方の視点、あるいはその相互関係から詳細に検証し、当時の日本の映画の二次産業の一端を明らかにする。</p><p> 戦前日本の映画の大半は、このように劇場公開後に切り売りされたために散逸したが、断片化した無数の齣フィルムの集積は、戦前日本のメディア文化の多様性と裾野の広さを示している。二次利用されたフィルムは、映画や幻燈のメインストリームの映像史にはあらわれない、子供の玩具世界で多彩に混淆した存在を生み出し、派生的に拡散していく。まさにこの流れは、現在加速しているデジタル一元化の流れとは対照的なのである。</p>
2 0 0 0 IR 第二次世界大戦とハリウッド・ミュージカル映画--現実逃避かプロパガンダか
- 著者
- 笹川 慶子
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- no.63, pp.38-54, 1999-11
This paper focuses on how the wartime conditions in Hollywood influenced the development of Hollywood musicals and other films during 1939-1945. The goal is to foreground a historical process in which the musicals had been incorporating the different ideologies of the times,by tracting the relationships between the studios and the political and the economical situations. Under the strong influence of the F.D.Roosevelt's Administration, the Office of War Information attempted to imbue the movies with its political ideas by distributing the Govenment Information Manual for the Motion Picture Industry to the studios. Since the OWI had no power over censorship,the studios ignored the manual. However after mid-1943 when the OWI established a coalition with the Office of Censorship, the studios suddenly became compliant, and more films were molded into what the OWI required: the propaganda of Americanism. In such a circumstance,the musicals had been considered as a mere-trivial-escapist-entertainment among the OWI and the studios. Nonetheless, it is impossible to disregard the changes of the wartime musicals. The musicals also interwove the politically different ideologies with their conventional formars, and could be functioning as the powerful propaganda during the war by reproducting the utopian images of Americanism.
2 0 0 0 堀潤之、菅原慶乃編著『越境の映画史』:書評
- 著者
- 応 雄
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, pp.52-55, 2015