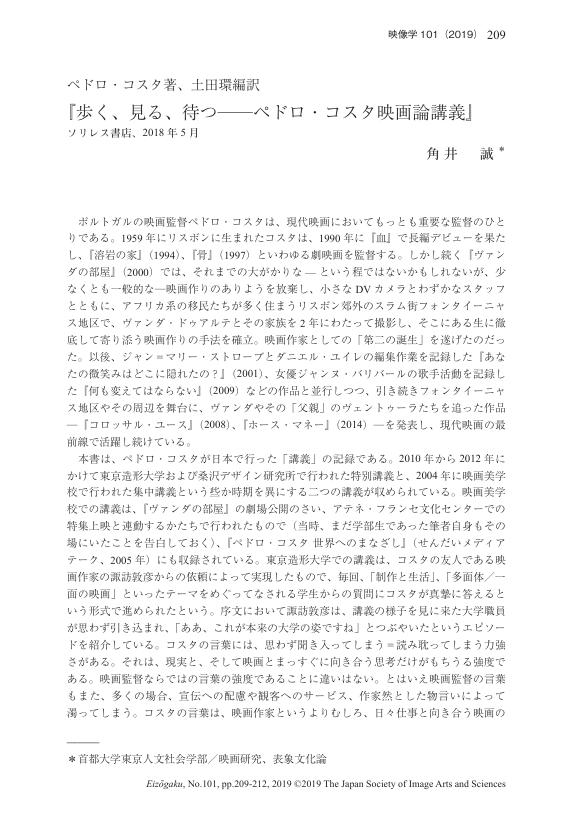15 0 0 0 OA 日活ロマンポルノと女性観客
- 著者
- 鳩飼 未緒
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, pp.27-47, 2016-07-25 (Released:2016-08-19)
- 参考文献数
- 25
【要旨】本稿は日活ロマンポルノの田中登監督作、『実録阿部定』(1975 年)を論じる。異性愛者の男性観客をターゲットに製作され、同時代的にはほぼ男性のみに受容された本作が、想定されていなかった女性観客との親和性を持ち、家父長主義的なジェンダー規範を再考させる転覆的な要素を内包することを説き明かす。背景にあるのは、ロマンポルノに関する既存の言説が男性の手による批評ばかりで学術的見地からの評価が進んでおらず、同時代的にも少数ではあれ存在し、昨今その数を確実に増やしている女性観客の受容の問題が論じられていない現状に対する問題意識である。そこで第1 節ではロマンポルノにおける女性の観客性を考察するうえでの古典的なフェミニスト映画理論の限界を明らかにしつつ、ジェンダーの固定観念を逸脱する表象の豊富さによって、ロマンポルノが異性装のパフォーマンスと呼べるような流動的な観客経験をもたらしうることを論じる。続く第2 節では『実録阿部定』の視聴覚的・物語的要素を仔細に検討し、とりわけヒロイン定の表象が保守的なジェンダー観に背くものであることを確認する。最終的には、第2 節で考察した特徴によって『実録 阿部定』が女性観客に異性装的な観客経験による映画的快楽をもたらすことを示し、さらには女性の主体的な性的快楽の追求を肯定させる仕組みがテクストに内在することを明らかにしたい。
15 0 0 0 OA サークルとしてのアニメーション文化――1960~1970年代の東海アニメーションサークルを中心に
- 著者
- 林 緑子
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, pp.39-59, 2022-02-25 (Released:2022-03-31)
- 参考文献数
- 27
本稿の目的は、1960年代後半に国内各地で複数発足したアニメーションサークルの特徴を、愛知県を中心に活動してきた東海アニメーションサークルの制作を事例として明らかにし、アニメーション文化史に位置付けることである。アニメーションが、娯楽・芸術・教育などの多様な分野にわたり日常化して久しい。このようなアニメーション文化を考えるとき、作家や産業関係者を育む土壌としてファンコミュニティは重要である。アニメーションに関する従来の研究や批評言説では、1970年代後半からのテレビアニメの人気隆盛に関連したファンコミュニティが主として「オタク」と呼ばれながら、もっぱらの注目を集めてきた。しかし、それ以前の1960年代末には既に、若者たちを中心とするアニメーションの文化サークル活動のネットワークが形成されている。先行研究では、現在のアニメーション文化にまで繋がるアニメーションサークルのネットワークの重要性や実際の制作が見過ごされてきたといえる。これに対して本稿では、東海アニメーションサークルを中心として、領域横断的ネットワーク、制作・受容・上映からなる総合的活動、文化サークルとしてのアニメーションサークルの歴史的意義の三つの観点から、アニメーションサークル初期の制作活動とネットワークについて考察する。それによりアニメーション文化史におけるアニメーションサークルの意義の一端を明らかにしたい。
15 0 0 0 OA 「メロドラマ」映画前史——日本におけるメロドラマ概念の伝来、受容、固有化
- 著者
- 河野 真理江
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, pp.73-94, 2020-07-25 (Released:2020-08-25)
- 参考文献数
- 60
本論文は、日本における「メロドラマ」の概念を探求する。「メロドラマ」は、“melodrama”の旧来からの翻訳語であるが、フィルム・スタディーズにおけるメロドラマ概念の浸透によって、現在その意味は曖昧になっている。そもそも“melodrama”がいつ日本語文脈に受容されたのかは明らかになっていない。メロドラマ映画にかんする先行研究を踏まえつつ、この「メロドラマ」の実態を明らかにすることが本論文の目的である。“melodrama”の日本語文脈への導入は、1870年代の翻訳辞典に始まり、当初はしばしば「歌舞伎」と訳されていた。1880年代には洋行者たちが「メロドラマ」の観劇体験を報告するようになり、1910年代にその知識は演劇関連の学術書に応用された。1920年代、メロドラマの言説は、映画にかんするものに集中していき、この言葉の意味は地域言語的なものへと変容していく。1930年代には、「メロドラマ」は通俗的、感傷的な劇を指す言葉となり、女性映画を含む日本映画のジャンルの一つとしても理解されていった。主な論点は以下の二点である。1. メロドラマと日本文化との出会いは、19世紀後半に位置する。2. 日本における「メロドラマ」はその固有性ばかりでなく、メロドラマ概念の普遍性を実証する。
13 0 0 0 OA スクリーンの「ニコヨン」たち―失業対策事業日雇労働者の映像文化史
- 著者
- 鷲谷 花
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, pp.31-53, 2019-07-25 (Released:2019-11-19)
- 参考文献数
- 47
1949 年の「ドッジ・ライン」実施に伴う失業危機への対策として開始された失業対策事業に就労する失対労働者たちは、「ニコヨン」の通称で呼ばれた。失業者でもあり、最低所得労働者でもある「ニコヨン」は、戦後日本の人権・貧困・労働問題の凝縮した表象として、1950 年代の映画・幻灯など「スクリーンのメディア」にたびたび取り上げられた。戦後独立プロダクション映画運動の嚆矢としての『どっこい生きてる』(1951 年)は、失対労働者の組織的協力を得て製作され、初期失対労働運動の原点としての「職安前広場」という空間の記録という機能も担った。失対労働者による文学運動の成果としての須田寅夫『ニコヨン物語』を原作とする同名の日活映画(1956 年)は、左翼組合運動からは距離を置いた視点から、失対労働者にとっての「職場」の形成と、そこでの労働組合の功罪相半する意味を映し出す。また、失対労働者たちが自作自演した幻灯『にこよん』(1955 年)は、屋外労働者・日雇労働者を男性限定でイメージする通念に抗して、失対事業における「女性の労働問題」を物語った。失対事業における「女性の労働問題」への問題意識は、望月優子監督の中編映画『ここに生きる』(1962 年)にも引き継がれる。「ニコヨン」と呼ばれた失対労働者は、労働運動・文化運動の一環として、「スクリーンのメディア」における自分たちの表象に主体的に関わり、敗戦以降の日本における失業・貧困・労働をめぐる意味の形成の一端を担ってきた。
- 著者
- 片岡 佑介
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, pp.44-64, 2017-01-25 (Released:2017-03-03)
- 参考文献数
- 40
【要旨】本稿の目的は、新藤兼人監督作『原爆の子』(1952)と関川秀雄監督作『ひろしま』(1953)のテクスト分析を通じ、両作品がいかに「無垢なる被害者」の像を生み出しているのかを明らかにすることにある。両作品はGHQ/ SCAPによる映画検閲の解除後、間もなく同一著書から製作された原爆映画であるために、これまでも比較考察がなされてきたが、従来研究は主題や製作過程、受容の観点から両作品を対照的なものと位置づけてきた。これに対し本稿は、両作品に共通する演出方法とジェンダー化された無垢の表象とに着目する。より具体的には、宝塚少女歌劇団の同期であった乙羽信子と月丘夢路がそれぞれ演じる白いブラウス姿の女教師による歌唱シーン、及び音楽のサウンドブリッジを契機に過去を想起する白血病の少女によるフラッシュバックシーンなどの場面を精査し、両作品の差異をこれらの場面での演出上の差異に由来するものとして新たに意味づける。そして両作品の語りの構造において、それぞれ画面に繋留されない女教師の歌声と沈黙する白血病の少女が主要な役割を果たしていることを浮き彫りにする。本稿では、明治以降の国民国家形成期における音楽の社会的機能にも目を配りつつ、両作品が映像と音声で構成される映画の媒体的特質に依拠した対照的な演出方法を用いながらも、しかし、共に原爆の「無垢なる被害者」と戦後の理想的な国民国家像とを構築していることを解き明かす。
11 0 0 0 OA 方法としての即興――ジョン・カサヴェテス『アメリカの影』における制作過程と俳優演技について
- 著者
- 堅田 諒
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, pp.84-102, 2022-02-25 (Released:2022-03-31)
- 参考文献数
- 23
本稿では、ジョン・カサヴェテスのデビュー作『アメリカの影』(Shadows, 1959)の制作過程とテクストの俳優演技の分析を行う。『アメリカの影』の制作プロセスにおいて実践されたカサヴェテス独自の即興とはどのようなものか、またそれは作品の俳優演技にどのような効果をもたらしたかを詳らかにすることが本稿の目的である。まず、1950年代のハリウッドにおいて支配的な演技モデルであったメソッド演技について概観する。『アメリカの影』制作以前の俳優であったカサヴェテスに焦点を当て、俳優カサヴェテスの出演作や演技を検討することで、カサヴェテスとメソッド演技の関係性を明らかにする。次に、監督や俳優の発言から『アメリカの影』の制作過程を辿ってゆく。とくにカサヴェテスたちが行った独特の即興に着目し、どのような形で俳優たちとカサヴェテスが協働作業を進めていったかを考察する。そして、制作段階でのカサヴェテス的即興が、テクストにいかなる形で痕跡を残しているかを精査する。とりわけ、どのような形で俳優のアンサンブル演技が展開されているかを検討してゆく。最終的に『アメリカの影』は、俳優カサヴェテスに代わり、監督カサヴェテスが生まれることとなった歴史的な地点であるとともに、カサヴェテスの俳優を中心にした映画作りの出発点ともなったという結論を提示する。
11 0 0 0 OA さよならをもう一度――加藤先生と「批評」
- 著者
- 藤井 仁子
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.16-20, 2022-08-25 (Released:2022-09-25)
- 著者
- 角井 誠
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, pp.209-212, 2019-01-25 (Released:2019-06-25)
- 参考文献数
- 2
- 著者
- 小河原 あや
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, pp.204-208, 2019-01-25 (Released:2019-06-25)
10 0 0 0 OA ルノワール・タッチ――『スワンプ・ウォーター』における俳優演出
- 著者
- 角井 誠
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, pp.5-21,85, 2013-11-25 (Released:2023-03-31)
Le présent article porte sur la mise en scène des acteurs de Jean Renoir dans son premier film américain, Swamp Water (1941). Durant la fabrication de ce film, le cinéaste français s’est trouvé en désaccord avec son producteur Darryl F. Zanuck, sa méthode de travail artisanale se révélant incompatible avec celles employées par un studio fortement industrialisé. Dans ces conditions, comment le cinéaste a-t-il pu imprimer sa propre marque au film? Pour répondre à cette question, notre article se focalise sur la question de l’acteur qui fut l’un des sujets importants de discussion avec Zanuck. Avant d’analyser le jeu des acteurs, nous retraçons d’abord l’évolution de leurs négociations à travers des documents d’archives. Dès la distribution des rôles, Renoir refuse les stars déjà figées par leurs succès, et insiste sur les jeunes acteurs ≪encore un peu malléables≫. Ensuite, sur le plateau de toumage, accusant toujours la prédominance des vedettes, il tente de doter tous les personnages, les figurants y compris, d’une véritable personnalité. En dépit des difficultés affrontées, ses efforts sont bien visibles dans la gestuelle des acteurs, et surtout dans les gestes de la main. Ceux-ci, peu apparents, se répètent pourtant tout au long du film comme un élément unificateur, et c’est dans ces jeux de mains qu’existe ce qu’on peut appeler la touche de Renoir.
10 0 0 0 OA コロナの写真映像?
- 著者
- 前川 修
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, pp.25-33, 2021-07-25 (Released:2021-08-25)
10 0 0 0 OA 青山太郎著『中動態の映像学 東日本大震災を記録する作家たちの生成変化』堀之内出版、2022年1月
- 著者
- 日下部 克喜
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.244-247, 2022-08-25 (Released:2022-09-25)
10 0 0 0 OA 付記
- 著者
- 伊津野 知多 土田 環
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.33, 2022-08-25 (Released:2022-09-25)
10 0 0 0 OA 「認知者」としての作品――エキソニモのUN-DEAD-LINK展を事例に
- 著者
- 水野 勝仁
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, pp.18-38, 2022-02-25 (Released:2022-03-31)
- 参考文献数
- 13
本稿は、エキソニモがUN-DEAD-LINK展に展示した初期のインターネットアート作品の映像とモノとの組み合わせを、N・キャサリン・ヘイルズの「認知者」「非意識的認知」「認知的集合体」という言葉を手がかりに考察していくものである。UN-DEAD-LINK展に展示された初期インターネットアート作品は、その特質と言える作品と体験者とのインタラクションがない状態で展示されている。この状態は、作品を死骸や残骸のように見せている。しかし、エキソニモの言葉を辿っていくと、これらの作品はインタラクションを切り落としたとしても、別のあり方で体験者の意識に現れる可能性を持つように調整されていることがわかる。この作品の別のあり方が、ヘイルズが「認知者」と呼ぶ存在である。彼女は、ヒトを含めたすべての生物とともにコンピュータも世界を解釈して意味を生み出す「認知者」だとしている。「認知者」は認知プロセスとして「物理的プロセス」、「非意識的認知」、「意識のモード」という三つのレイヤーを持っているが、エキソニモは「非意識的認知」のレイヤーで作品の修正を行い、雑多な情報が「非意識的認知」で解釈され、モニターに「意識のモード」として現れるパターンを記録する。さらに、彼らはこの認知プロセスを記録した映像をあらたな「物理的プロセス」と組み合わせて提示し、作品が単なる物質ではなく、「認知者」として現れるようにしているのである。
9 0 0 0 OA 検閲の誕生 大正期の警察と活動写真
- 著者
- 長谷 正人
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, pp.124-138,150-51, 1994-11-25 (Released:2019-07-25)
- 参考文献数
- 17
In 1917 the Metropolitan Police Board enforced "Regulations of the Moving Picture Exhibitions" in Tokyo. But these regulations are very strange in our point of view. Because they didn't attach importance to the censorship which is usually a means of repression by the police. Why didn't they so? First because the exhibition of moving pictures still retained the quality of a live preformance. For example, it was accompanied by a lecturer (benshi)'s performance and a live music performnce. This fact made it nonsense for the police to censor films. For a film changed its meaning at every projection. So the police disciplined lecturers and inhibited the chained play (which is a special form of exhibition combining play with movies) instead of censoring films. Second because spectators in that era made an indecent atmosphere in a movie theater. So they didn't devote themselves to a film. They also entertained an indecent atomospher. This made it nonsence for the police to censor films, too. For spectators received an excessive meaning from this atomosphere. So the censorship can have an effect only after modernizing the communication in movie theaters. This was impossible in that era.
- 著者
- 渡邉 大輔
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, pp.252-256, 2020-07-25 (Released:2020-08-25)
9 0 0 0 OA 敗戦のスター女優
- 著者
- 北村 匡平
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, pp.68-88, 2016-07-25 (Released:2016-08-19)
- 参考文献数
- 63
【要旨】 本稿の目的は、占領期のスターダムのなかでなぜ原節子の価値が最も高まり、どのような大衆の欲望によって彼女のペルソナが構築されたのかを、敗戦後の社会・文化的条件に即して実証的に明らかにすることにある。これまでスターを対象とする研究は映画の表象に傾斜した分析が多かったが、スター研究の視座から、スターを取り巻く言説、とりわけファン雑誌におけるイメージやテクストと映画との関係を重視し、複数のメディア・テクストにおける原節子の個性的アイデンティティ構築が、占領期のジェンダー・セクシュアリティ規範のなかでいかなる価値を形成していたのかを探究する。 原節子は、敗戦後に求められる理想的な女性像としての「理知的」で「意志」の強い主体的なイメージを戦中から準備し、戦前と戦後の連続性を引き受けることで、占領期に最も人気の高いスターとなった。彼女の映画のパフォーマンスと、雑誌のパーソナリティに通底する他者の身体から「離れている」ペルソナは、日本女性の身体をめぐるアメリカと日本の占領の言説において、文化的価値を高めることになった。彼女は戦後に現れた敗戦の歴史的トラウマを喚起するパンパンなどの「敗者の身体」とは決して重なることない〈離接的身体〉としての理想的ペルソナを言説によって構築していたのである。本稿では、占領期という歴史的コンテクストのなかで原節子がいかに価値づけされ、欲望されているのかを分析し、アメリカへの抵抗を可能にする原節子のスターペルソナを通して大衆の戦後意識を解明する。
8 0 0 0 OA テレビ番組の調査方法と作品リスト作成の意義――映画監督・森﨑東のテレビ作品を事例として
- 著者
- 木原 圭翔
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, pp.46-55, 2014-05-25 (Released:2023-03-31)
8 0 0 0 OA 映像学のアプローチ
- 著者
- 角井 誠
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.5-8, 2022-08-25 (Released:2022-09-25)
- 参考文献数
- 5
8 0 0 0 『サイコ』における予期せぬ秘密
<p>【要旨】<br> リンダ・ウィリアムズが2000年に発表した「規律訓練と楽しみ――『サイコ』とポストモダン映画("Discipline and Fun: <i>Psycho</i> and Postmodern Cinema")」は、ミシェル・フーコーによる「規律訓練(discipline)」の概念を援用しながら『サイコ』(<i>Psycho</i>, 1960)における観客の身体反応の意義を考察した画期的な論考であり、同作品の研究に新たな一石を投じた。ウィリアムズによれば、公開当時の観客はヒッチコックが定めた「途中入場禁止」という独自のルールに自発的に従うことで物語に対する期待を高め、結果的にこの映画がもたらす恐怖を「楽しみ(fun)」として享受していた。<br> しかし、『サイコ』の要である「シャワーシーン」に対しては、怒りや拒絶などといった否定的な反応も数多く証言されているように、その衝撃の度合いや効果の実態については、さらに綿密な検証を行っていく必要がある。本稿はこうした前提の下、シャワーシーンの衝撃を生み出した複数の要因のうち、従来そうした観点からは着目されてこなかったヒッチコックのテレビ番組『ヒッチコック劇場』(<i>Alfred Hitchcock Presents</i>, 1955-62)が果たした役割について論じていく。これにより、先行研究においては漠然と結びつけられていた『サイコ』と『ヒッチコック劇場』の関係を、<u>視聴者</u>/<u>観客</u>の視点からより厳密に捉え直すとともに、シャワーシーンの衝撃に大きく貢献した『サイコ』の宣伝手法(予告編、新聞広告)の意義をあらためて明確にすることが本稿の目的である。</p>