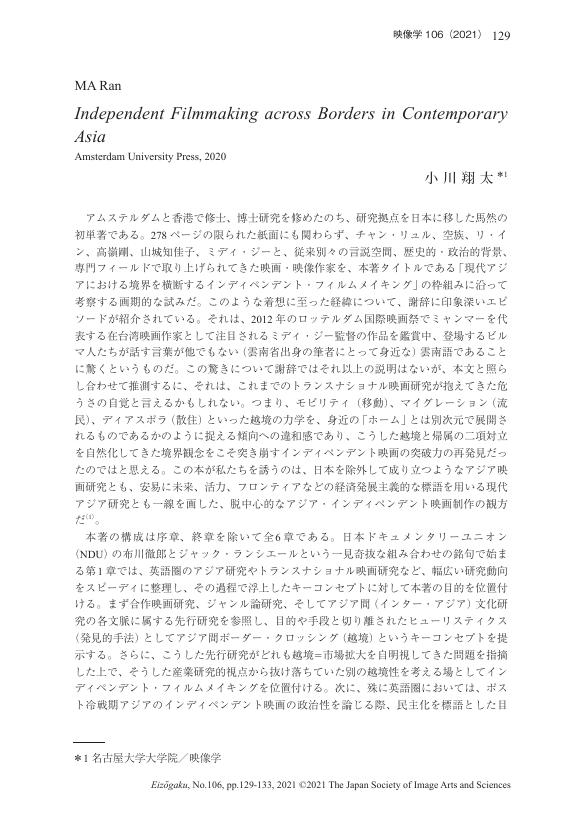1 0 0 0 OA 逡巡――批評的思考と実践におけるためらいの擁護に向けて
- 著者
- 斉藤 綾子
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.9-15, 2022-08-25 (Released:2022-09-25)
- 参考文献数
- 14
1 0 0 0 OA 視覚文化論というアプローチ――ノンヒューマンという観点から
- 著者
- 増田 展大
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.27-32, 2022-08-25 (Released:2022-09-25)
1 0 0 0 OA 『太陽』(2005年)における天皇の人間性の再考――〈見る/見られる〉、運動、演技
- 著者
- 名取 雅航
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.57-77, 2022-08-25 (Released:2022-09-25)
- 参考文献数
- 33
本稿の目的は、アレクサンドル・ソクーロフ監督による『太陽』(2005年)の新たな意義を見出すことにある。これまでの歴史研究、またメディアおよび映画研究は、近代天皇が現実のレベルと表象のレベル双方においていかに隠されるべきものとして扱われてきたかを明らかにしている。そのなかで、映画において初めて昭和天皇(裕仁)を主人公として、また人間として描いた『太陽』は賞賛を集めてきた。一方で、その人間性は、侍従に対して冗談を言い、口臭を気にし、皇后である妻に手紙を認め、最終的に「人間宣言」を行うといったわかりやすいかたちにとどまらない、複層的なものである。本稿はまずその点について、〈見る/見られる〉、運動、演技という観点からテクスト分析を行い、本作における天皇の人間性が多様な映画的な手法と密接に結びついたものであることを明らかにする。また、そのような人間性の演出は、人間が天皇であり天皇は人間であるという事実の複雑性を示すにふさわしく、また両者を往還する存在としてこの主人公を立ち現わせることを可能にしている。天皇の人間性が決して自律したものではなく、天皇という役割と不可分の関係において描かれているのである。それらの分析と考察を通じ、『太陽』の意義は、天皇の「人間化」をあくまで現実的な交渉のプロセスとして表現することによって、天皇の人間性についての議論が伴う困難を観客に伝えることにあったと結論付ける。
1 0 0 0 OA 証言映画のアーカイバル・ターン――朴壽南(パク・スナム)の映像断片の可読性をめぐって
- 著者
- 小川 翔太
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, pp.122-139, 2022-02-25 (Released:2022-03-31)
- 参考文献数
- 34
16 mmフィルムとオープンリール、そして市民運動に支えられた自主制作・自主上映体制を駆使して多様に開花したドキュメンタリー映画の背後にたたずむ膨大な尺数の「アウトテイク」素材群の存在が、制作者の老齢化とデジタル時代の映像保存実践の多元化によって近年顕在化してきた。殊に、証言映画の記念碑的作品である『ショア』(クロード・ランズマン監督、1985年)のアウトテイク素材220時間分が、米国ホロコースト記念博物館の映像アーキビストによってクロード・ランズマン『ショア』コレクションとして整理されたことを受け、証言映画とアーカイブの入り組んだ関係性をめぐる議論が再燃している。本稿は、『ショア』とアーカイブを巡る議論を一つのモデルとして参照しつつも、東アジアのポストコロニアルな空間で周縁化された語りを60年にわたり記録してきた朴壽南(パク・スナム、1935-)の表現活動を取り上げる。2019年に始動した「日韓100人による歴史の証言映像」デジタルアーカイブ企画を手がかりに、皇民化教育を受けた在日コリアン二世の作家が、脱植民地化の文脈で作品創作だけでなくアウトテイク素材のアーカイブ化を位置づけるとき、歴史史料と映画素材、アーカイヴとアーカイブ、フィルムと映像など様々な対立概念をどのように再定義することになるか。モデル未満の不確かさを含むケーススタディとして模索する。
- 著者
- 北村 洋
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, pp.140-143, 2022-02-25 (Released:2022-03-31)
1 0 0 0 OA 堀江秀史著『寺山修司の写真』青土社、2020年11月
- 著者
- 竹内 万里子
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, pp.149-152, 2022-02-25 (Released:2022-03-31)
1 0 0 0 OA 今井瞳良著『団地映画論――居住空間イメージの戦後史』水声社、2021年3月
- 著者
- 須川 まり
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, pp.153-157, 2022-02-25 (Released:2022-03-31)
- 参考文献数
- 3
- 著者
- ベルナルディ ジョアン
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, pp.163-166, 2022-02-25 (Released:2022-03-31)
- 著者
- 成田 雄太
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, pp.167-171, 2022-02-25 (Released:2022-03-31)
1 0 0 0 OA 朱宇正著『小津映画の日常――戦争をまたぐ歴史のなかで』名古屋大学出版会、2020年10月
- 著者
- 宮本 明子
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, pp.120-123, 2021-07-25 (Released:2021-08-25)
1 0 0 0 OA MA Ran, Independent Filmmaking across Borders in Contemporary Asia Amsterdam University Press, 2020
- 著者
- 小川 翔太
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, pp.129-133, 2021-07-25 (Released:2021-08-25)
- 著者
- 今村 純子
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, pp.134-138, 2021-07-25 (Released:2021-08-25)
1 0 0 0 OA 明治の国家教育をめぐる視覚メディア利用――「修身」幻燈の変遷を中心に
- 著者
- 福島 可奈子
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, pp.60-83, 2022-02-25 (Released:2022-03-31)
- 参考文献数
- 35
本論は、視覚メディア、特に幻燈が明治10年代の「修身」教育に果たした重要な役割を明らかにする。急速な近代化を進めた明治初期、日本の国家教育は、その方針をめぐって洋学・国学・儒学が熾烈な覇権争いを繰り広げていた。その際、教育の「啓蒙」ツールとして文部省が最も注目したのが、西洋から持ち込まれた最新の幻燈であったが、その内容の軸足は西洋啓蒙主義的な智識才芸を養うためのものから、儒教的な仁義忠孝を養うものへと移っていくことになる。文部省の命でいち早く幻燈製作をはじめた鶴淵幻燈舗が、はじめて日本の「修身」教育に関与したのが、明治天皇の勅命で元田永孚が編纂した『幼学綱要』スライドであるが、今回それら一式が新たに発見された。そのため筆者は、それらのスライドが製作されるに至る当時の国家教育観の思想的背景を検証する。また当時の「修身」教育は、政府が推奨した洋学や儒教にとどまらず、江戸期から民衆に浸透している実語教や石門心学による「善悪鏡」など様々な道徳観の混淆であった。そしてそれらが、江戸期からの「写し絵」製作・興行主の池田都楽、大阪の花街で西洋幻燈製作や「錦影絵」を興行していた寺田清四郎製の幻燈スライドなどとなって、その「修身」イメージが拡散されていく経過を、実物史料に基づいて歴史的かつ実証的に明らかにする。
- 著者
- 田辺 秋守
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, pp.112-116, 2021-01-25 (Released:2021-02-25)
- 著者
- 桑原 圭裕
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, pp.117-120, 2021-01-25 (Released:2021-02-25)
1 0 0 0 OA 「見ること」のインフラストラクチャー
- 著者
- 渡邉 大輔
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, pp.5-7, 2021-07-25 (Released:2021-08-25)
1 0 0 0 OA アクシデントとインフラストラクチャー
- 著者
- 近藤 和都
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, pp.8-17, 2021-07-25 (Released:2021-08-25)
- 参考文献数
- 19
1 0 0 0 OA 映画を見ること、残すこと――パンデミック渦中のフィルムアーカイブ活動
- 著者
- 石原 香絵
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, pp.18-24, 2021-07-25 (Released:2021-08-25)
1 0 0 0 OA 新藝城と徐克——1980年代の香港映画産業における監督が担う役割の変遷
- 著者
- 雑賀 広海
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, pp.67-87, 2021-01-25 (Released:2021-02-25)
- 参考文献数
- 26
新藝城は1980年に設立されると、またたく間に香港の映画市場を席捲した。新藝城の作品が劇場を支配し、新人監督がデビューする場であった独立プロダクションの作品を公開する機会はきわめて限定されてしまう。したがって、新藝城は1970年代末に期待された多様な映画製作の種を摘み取った会社として、否定的な評価を与えられることがしばしばある。また、作品の内容についても、物語やギャグが形式的で画一的であると批判される。その一方で、それまでの興行収入の記録を大幅に更新し、1980年代の香港映画産業を牽引した存在であることは確かである。本論文は、新藝城の功罪について、新浪潮を代表する監督の一人であり、新藝城の中心メンバーでもあった徐克を中心に再考する。とくに注目するのが、集団創作という新藝城の製作体制であり、この体制においては監督個人の判断で撮影することは厳しく禁じられていた。そのために、徐克は数年で脱退することになるものの、集団創作の経験は有益だったとも述べている。本論文が注目するのは、新藝城の集団創作が香港映画産業を席捲することで、俳優や監督など、映画製作におけるそれぞれの専業が入り乱れ、無制度的状態と化したことである。そして、作家主義とは相反するような新藝城の集団創作が、徐克や1980年代の香港映画産業に与えた影響を明らかにする。
- 著者
- 渡部 眞
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, pp.96-99, 2021-01-25 (Released:2021-02-25)