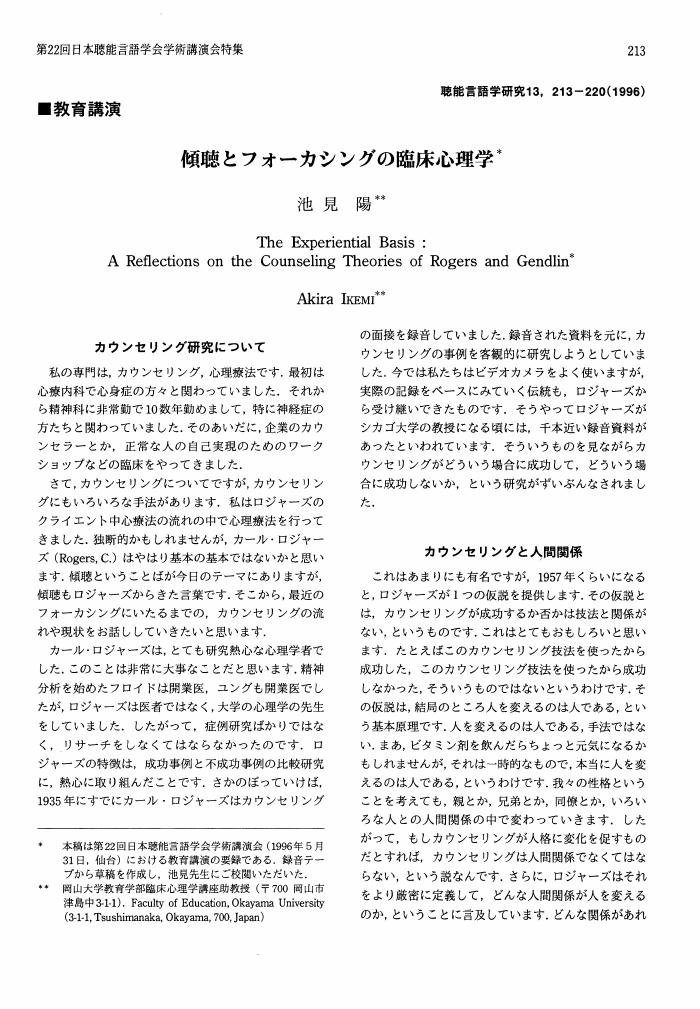24 0 0 0 OA 〈失語か非失語か-診断と治療の方向性を探る-〉精神分裂病の言語:その障害へのアプローチ
- 著者
- 古賀 良彦
- 出版者
- 日本コミュニケーション障害学会
- 雑誌
- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.86-93, 1993-04-30 (Released:2009-11-18)
- 参考文献数
- 32
精神分裂病では多彩な精神症状がみられるが,その中で,思考障害に関してはすでに多くの報告があるのに対し,言語の障害についての研究はあまり活発に行われていない.精神分裂病の言語に関するこれまでの研究をみると以下の4つに大別できる.(1)言語の研究により,思考障害の解明をめざすもの(Maher, Andreasen, Hoffman).この場合,言語は思考をうつしだす鏡として考えられる.(2)言葉による情報の伝達の障害についての研究(Cohen, Kantorowitz, Rochester).(3)言語学者による精神分裂病患者の談話の詳細な分析(Chaika, Morice).(4)精神分裂病の言語と失語症との比較を行う研究(Gerson,神山,大平).ヒトにのみ存在する精神分裂病の研究にとって,ヒトで特に発達した機能である言語は有用な研究手段となるはずであり,今後,言語についての研究が発展することにより精神分裂病症状の構造や認知障害の様相が明らかにされることが期待される.
9 0 0 0 OA 〈言語聴覚障害とその近接する領域〉高齢者施設における言語聴覚士の役割とは
- 著者
- 綿森 淑子
- 出版者
- 日本コミュニケーション障害学会
- 雑誌
- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.29-34, 2002-04-25 (Released:2009-11-18)
- 参考文献数
- 9
介護保険の導入後,STが人員基準に含まれるようになったこともあり,介護老人保健施設(老健)に勤務するSTが急増している.2001年4月,我々は全国94の高齢者施設(主に老健)を対象にアンケート調査を実施し,54施設から回答を得た.老健で働くSTの悩みの背景ば、(1)制度面の立ち遅れ,(2)STとしての技法・方法論の不足,(3)STの役割の不明確さ,(4)他職種からの理解の得られにくさの4つに集約された.STとしての立場を確立していった人達のアプローチの分析から,老健におけるSTの役割は大きく3つに分けることができると考えられた.(1)生活モデルに沿った,利用者全体に関わる働きかけ,(2)狭義のコミュニケーション障害をもつ利用者への援助,(3)他職員への教育的役割.今後は老健STについてのガイドラインの作成,対象者に適した評価法の開発,STとしての技法・技術の開発,ニーズに合わせた講習会の実施など職能団体,学術団体からの支援が求められる.
8 0 0 0 OA 第18回 日本聴能言語学会学術講演会 一般演題 B-I群:言語発達遅滞(1)
- 出版者
- 日本コミュニケーション障害学会
- 雑誌
- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.129, 1992-12-25 (Released:2009-11-18)
- 著者
- 大井 学
- 出版者
- Japanese Association of Communication Disorders
- 雑誌
- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.224-229, 2002-12-30
- 被引用文献数
- 2
最近の他者理解研究と語用論研究の進歩に支えられて,高機能広汎性発達障害をもつ個人に対するコミュニケーション支援が有望となり始めている.それには彼らの適応改善や精神障害の予防効果も期待できる.しかし,彼らの語用障害の広大さと根深さについての明確な理解なしには,専門家の努力は無効となることが懸念される.技法の妥当性に関するこの視点からの十分な吟味がないまま,伝達スキルを訓練したり会話の知識を教えたりしても,役に立たないばかりか,彼らの混乱と不安を増やすことにさえなりかねない.今のところ次の3つが実行可能なアプローチとして考えられる.(1)彼らと周囲とのコミュニケーションの崩壊の修復,(2)周囲の人々が効果的なコミュニケーション戦略を用いるよう促す,(3)高機能児・者同士の仲間体験機会の提供.いずれの場合も彼らとのコミュニケーションに関する専門家のリフレクションが重要な鍵となる.
3 0 0 0 OA 失語症者の表現を助ける五行歌の可能性
- 著者
- 小薗 真知子
- 出版者
- 日本コミュニケーション障害学会
- 雑誌
- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.87-92, 2002-08-30 (Released:2009-11-18)
- 参考文献数
- 9
失語症者の生活の質(QOL:Quality of Life)を高めるためには,本人の関心と言語レベルに合った自己表現の方法を見出すことが重要である.ブローカ失語の79歳の女性に五行歌の創作を取り入れたところ,散文では表現できない豊かな感情の表出が見られた.五行歌は定型や字数の制限なく,日常の言葉で心のうちを五行に詠む新詩型である.失語症者にとっての五行歌の利点と指導の可能性について考察した.
3 0 0 0 OA 第16回 日本聴能言語学会学術講演会 特別講演 言葉の拘束と言葉からの解放
- 著者
- 井上 ひさし
- 出版者
- 日本コミュニケーション障害学会
- 雑誌
- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.2, pp.92-97, 1990-10-31 (Released:2009-11-18)
2 0 0 0 OA 喃語における母国語の影響 成人による聴取・識別実験から
- 著者
- 市島 民子
- 出版者
- 日本コミュニケーション障害学会
- 雑誌
- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.16-21, 1988-04-30 (Released:2009-11-18)
- 参考文献数
- 15
前言語期の乳児音声における母国語の影響を調べるため,母国語の異なる日本,中国,韓国,米国の乳児の喃語を対象に,比較実験を行った.実験は,『成人による聴取・識別』という方法をとり,専門家,非専門家の2群の日本人成人が,同一月齢(6,8,10ヵ月)の言語比較対(日本-中国,日本-韓国,日本-米国)の中から,日本の乳児の喃語を聴取・識別した.この実験の全識別率(同定率)は,73.8%であったが,各条件での同定率に以下の違いを認めた.1) 言語間では,中国との比較で高く,韓国との比較で低い.2) 月齢間では,10ヵ月は両識別者群とも高く,8ヵ月は群による差がみられた.以上の結果より,喃語には,識別可能な言語間での相違があること.この相違は10ヵ月でより明瞭になり,母国語の影響のあることが示唆された.
2 0 0 0 OA 第22回 日本聴能言語学会学術講演会 教育講演 傾聴とフォーカシングの臨床心理学
- 著者
- 池見 陽
- 出版者
- 日本コミュニケーション障害学会
- 雑誌
- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.213-220, 1996-12-25 (Released:2009-11-18)
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 田原 佳子
- 出版者
- 日本コミュニケーション障害学会
- 雑誌
- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.117-123, 2001-08-30 (Released:2009-11-18)
- 参考文献数
- 7
難聴学級担当者の役割として直接的支援とともに間接的支援も行っていくことが重要であるという考えをもとに,難聴学級に通級する難聴児の通常学級の環境を整えることをねらって「難聴理解」の授業について追求した.難聴学級担当者が中心となって「難聴」について理解啓発していく授業,そして,難聴学級で学習したことを難聴児自身が中心となって健常児に広めていく授業,さらには,相手の立場に立つことを難聴児・健常児が共に考えていく授業を担任と連携しながら行った.特に,難聴児自身が難聴学級で学習したことを健常児に発信することで,難聴児が自分を見つめ,相手の理解を得たいという気持ちをもつことができた.また,健常児も具体的な場面を通して難聴による困難さについての理解を深め,お互いを認め合うことの大切さに気づいていった.
2 0 0 0 OA 〈言語聴覚障害とその近接する領域〉高機能広汎性発達障害におけるコミュニケーションの問題
- 著者
- 杉山 登志郎
- 出版者
- 日本コミュニケーション障害学会
- 雑誌
- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.35-40, 2002-04-25 (Released:2009-11-18)
- 参考文献数
- 16
高機能広汎性発達障害への言語治療について私見を述べた.自閉症児への言語治療はすでに長い歴史を有する.集中的な治療が自閉症の根本治療としてもてはやされた時代もあったが,現在では他の発達障害と同様に,自閉症にもコミュニケーション全体の改善を行う一環として行われることが多くなった.もちろん従来の構音治療や語理解訓練も重要ではあるが,自閉症の言語障害の中核が語用論的障害であることが明らかになった今日,この語用障害への言語治療ができなくては,自閉症のコミュニケーション指導にはならないであろう.新世紀を迎え,自閉症児への言語治療が新たな展開をみせることを期待するものである.
2 0 0 0 OA 漢字の障害を伴なった失名詞失語の1例
- 著者
- 内藤 真知子
- 出版者
- 日本コミュニケーション障害学会
- 雑誌
- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.108-111, 1983 (Released:2009-11-17)
1 0 0 0 OA 神経心理学における喚語困難
- 著者
- 鈴木 匡子
- 出版者
- 日本コミュニケーション障害学会
- 雑誌
- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.222-230, 1996-12-25 (Released:2009-11-18)
- 参考文献数
- 9
喚語困難は,語産生,語選択,語義の各過程およびこれらの離断によるものの4種類に分けられる.喚語困難の種類と臨床的な失語症の分類とはほぼ対応しており,それぞれの喚語困難の解剖学的基盤は異なっていると考えられる.さらにPETによる正常人の研究から,呼称をする対象のカテゴリーによって脳の活動部位が異なることが報告されている.我々の施行したカテゴリー別視覚性呼称課題では,失語群で有意に成績が低下していたが,身体部位と野菜では有意差がなかった.語想起課題では,(1)流暢性失語と非流暢性失語で有意差がない,(2)左前頭葉病変群は左前頭葉病変のない群に比べて,身体部位,甘いもの以外で成績が低下していた.また我々の経験した語義失語例では,喚語困難と単語の聴覚的理解障害がみられたが,身体部位の呼称と指示は比較的保たれていた.単語の成立基盤はカテゴリーにより異なるため解離性の喚語困難が生じると考えられる.
1 0 0 0 OA 言語障害を否認した1ウェルニッケ失語患者の事例研究
- 著者
- 手束 邦洋
- 出版者
- 日本コミュニケーション障害学会
- 雑誌
- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.34-42, 1992-04-30 (Released:2009-11-18)
- 参考文献数
- 6
事例は42歳の単身の男性であり,脳出血によるウェルニッケ失語と右不全片麻痺を持っていた.彼は不安から自己を防衛するために言語障害を否認し,その否認を他者と共有しようとした.右上肢の麻痺と失職という現実を指摘する他者によって不安を喚起させられる度に,彼らを非難し自己合理化をはかった.彼は自己防衛を確かなものとするために言語治療者を必要とした.言語治療者は失語症状の改善をはかりつつ,彼のニードを受容して治療関係を維持し,生活史を傾聴することと新しい現実に目を向けるよう彼を促すことを通して治療関係を展開した.退院後,福祉施設への適応を進める中で,不安が軽減し彼のパロル行為を動機づける主要テーマが現実に即したものへと変わったとき,言語治療は終結された.失語症の言語治療の対象は,発話主体再自立へ向けての〈失語症状を伴うパロル行為〉であり,パロル行為を動機づける心的メカニズムの理解が重要と思われた.
- 著者
- 嶋倉 優子
- 出版者
- 日本コミュニケーション障害学会
- 雑誌
- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.21-27, 1991
難聴の発見が19~30歳であった脳性マヒ者(アテトーゼ型)5例について,難聴に起因する職業生活上の問題点とその対策について検討した.これらの事例は,難聴に起因する問題のために,全例過去に自主退職や解雇を経験している.難聴に伴う職業生活上の問題を軽減するために,職業訓練場面を通し,次のような援助を行った.(1)障害の自覚を促すための,聞き誤りのフィードバック.(2)コミュニケーションの成就体験の場の保障.(3)補聴器やテレホンエイドなどの視聴覚機器の活用.(4)コミュニケーション態度の改善.この結果,4事例は難聴による問題について自己対策が立てられるようになり,再就職が可能になった.
- 著者
- 佐々木 正美
- 出版者
- 日本コミュニケーション障害学会
- 雑誌
- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.3, pp.168-174, 2001-12-25 (Released:2009-11-18)
- 被引用文献数
- 2
- 著者
- 古木 明美
- 出版者
- 日本コミュニケーション障害学会
- 雑誌
- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.106-110, 2001-08-30
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 3
聴覚障害児にとって,圧倒的に多い聴覚障害をもたない子どもたちの中で共に育っていくことは,さまざまな困難に出会うことを予測させる.本稿では,初めに幼児期のインテグレーションにおける支援を筆者の所属する施設に併設のルーテル愛児幼稚園でのインクラス指導の実践を中心に報告した.学齢期は,本人を取りまく環境への支援が大きく,学校,学級担任への情報提供や問題解決のための協力など言語聴覚士としての役割について述べ,本人や本人を取りまく環境へのさまざまな支援をまとめた.聴覚障害児が自分を認めて聴覚障害をもたない者ともかかわっていくような気持ちを育てるための幼児期・学齢期のインテグレーション支援のあり方を考察した.
1 0 0 0 OA 第13回 日本聴能言語学会学術講演会 シンポジウム4 全失語の言語治療について
- 著者
- 中西 之信 橋本 武樹
- 出版者
- 日本コミュニケーション障害学会
- 雑誌
- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.2, pp.71-76, 1987-10-31 (Released:2009-11-18)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 脳卒中後に吃音を呈した一症例
- 著者
- 林 耕司 松本 幸子
- 出版者
- 日本コミュニケーション障害学会
- 雑誌
- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.119-121, 1983 (Released:2009-11-17)
1 0 0 0 養護学校 (精神薄弱) におけるコミュニケーション指導
- 著者
- 山本 正志
- 出版者
- 日本コミュニケーション障害学会
- 雑誌
- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.96-100, 1998-08-30
- 参考文献数
- 2
精神発達遅滞児に対するコミュニケーション指導は,子どもが意欲をもって自律的に取り組むことが中心になると考えた.その方法として授業をグループで指導し,指導をゲーム化することを試みた.授業例としてオリエンテーリングやしりとり,身振り歌を報告した.この方法は子どもの意欲を引き出すことに成功し,またいろいろなレベルのコミュニケーション課題を導入するのも容易だった.しかし学習効果の測定はできなかった.
1 0 0 0 OA 第12回 日本聴能言語学会学術講演会 第3群(自閉症)
- 出版者
- 日本コミュニケーション障害学会
- 雑誌
- 聴能言語学研究 (ISSN:09128204)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.51-52, 1986 (Released:2009-11-18)