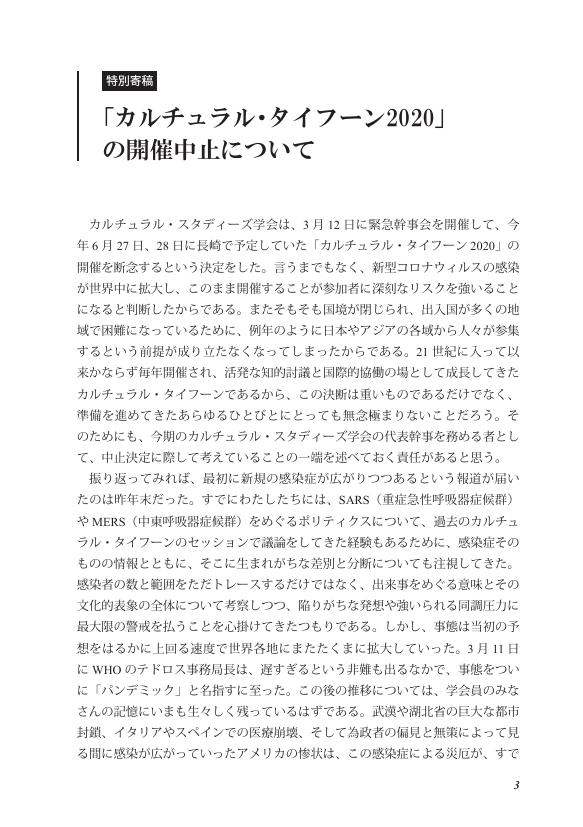3 0 0 0 OA 理論と実践の間の写真 アラン・セクーラの写真理論再読
- 著者
- 田尻 歩
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.103-124, 2018 (Released:2019-10-09)
- 参考文献数
- 30
アメリカ合衆国の写真家・批評家アラン・セクーラ(1951-2013)は、批評活動において は写真の抑圧的使用を批判しながらも、創作の方法としては「リアリズム」を擁護してき た。本論は、彼の写真理論を階級の観点から考察し直し、「リアリズム」概念を捉えなおす ことを目的とする。この作業を通じて、これまで日本のセクーラ研究においては十分に焦 点が当てられてこなかった彼のマルクス主義的な側面を明確に記述し、それとともに、写 真・表象研究における「リアリズム」の批判的な理解の可能性を探求する。彼が批評的活 動を主に行った1970 年代後半から1980 年代は、ドミナントな写真理論においては反リアリ ズム的な傾向が強かった。本論は、英国の批評家ジョン・ロバーツの議論に依拠しながら、 リアリズムという概念が、ある写真がその映した対象に関する事実を述べていると考える 実証主義と同一ではなく、その時代に応じて創り直される知の実践的形式であるという立 場をとる。そのような観点から、本論の前半部においては、1970 年代後半から勃興し、現 在の写真研究の基盤を形作ったイギリスと合衆国における写真・芸術理論の反リアリズム 的側面を概観する。本論の後半では、同時期にリアリズムを擁護しながらも批判的に写真 を考察したセクーラの写真理論を階級的な観点から再読する。セクーラの従来の研究にお いては、どのような文献に依拠して写真理論を発展させていったかが基礎的なレベル以上 には明らかにされてこなかったが、本論は、彼が依拠した言語理論と社会理論を参照しつ つ彼の写真理論の特性を明らかにする。また、ほかの論者には十分に注目されていなかった、 精神労働と肉体労働の間の分業の批判が、資本主義の文化の一部として写真を理解するセ クーラにとって、理論・実践面で根本的な課題であったことを論じる。
- 著者
- 陳 海茵
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.97, 2017 (Released:2019-10-09)
- 参考文献数
- 28
本論文は、毛沢東時代の終焉と改革開放という決定的な政治的社会的転換期1970 年代の 中国現代アートを対象に、それが「政治当局に抵抗する芸術」あるいは「欧米の後を追う芸術」 という立場をアプリオリの前提にするのではなく、(1)作品創作、(2)展示活動、(3)語り、 といった個別具体的な場面で、「政治」、「社会」、「芸術」の間にどのようなせめぎ合いが行 われたのかについて考察する。ここで念頭に置かれるのは、西欧社会の文脈から発展して きた「社会を志向する芸術実践」やアート・アクティビズムの動向である。共産圏国家に おいてアートがいかなる意味とやり方で連帯を創出しうるのかについて明らかにし、中国 現代アートの一事例をグローバルな同時代性の中に接続することを試みる。 ここでは事例として文革直後に結成された「星星画会」というアマチュア芸術家集団を 取り上げる。彼らは政府に無許可で展覧会を開き、その活動は最終的には「政治の民主化」 や「芸術の自由化」を求めるデモへと発展した。「星星画会」の芸術家たちは独自のやり方 で自分たちの正当性を主張した。一つには、民主化運動の拠点だった「民主の壁」を始め とする公共空間を展示空間に作り変えることで排除ではなく包摂の政治を要求した。また、 政府御用の芸術が持つ「技術」や「伝統」に対して、現代アートにおける「思想」と「現 代性」を指摘し、「自己表現」というプライベートな領域を開くための概念を強調すること で、それまで社会に奉仕するための道具でしかなかった社会主義的な「個体」を脱構築した。 ここでは近代個人主義ではなく、自由、民主、多様性といった反・文革的な文脈性やメッ セージ性のもとで「自己」を捉え直すことへと注意を向けさせようとしていたのである。
2 0 0 0 OA ディストピアに逃走線を創造する
- 著者
- 北村 匡平
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.175-178, 2020 (Released:2020-10-09)
2 0 0 0 OA 日大全共闘を再記録する企て ――「日大930の会」の活動を中心に――
- 著者
- 趙 沼振
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.151-173, 2020 (Released:2020-10-09)
- 参考文献数
- 13
1968年、日本大学では右翼思想団体や体育会系サークルを利用して学生活動に暴力的な統制を加えるなどしていた大学理事会による約20億円の使途不明金が、東京国税局の告発によって発覚した。日大全共闘は、私立大学の教育をめぐるこのような問題点への一つの応答として学生による運動体として形成され、大衆団交を求めて日大闘争を進めた。 このように日大全共闘が結成されて50年目を迎えた2018 年、日大のアメリカンフットボール部をめぐる「悪質タックル問題」が社会的な論議を引き起こしていた。これと時期を同じくして、「日大930 の会」事務局が日大全共闘50 年の節目に「日大全共闘結成50周年の集い」を開催しており、かつて大学運営の民主化を要求して闘争に参加した元学生らの再結集を機に、日大当局に対する見解を明らかにした。 本稿では、日大全共闘に結集した仲間たちで成り立った同窓会組織の「日大930の会」に着目し、彼らに行ったインタビュー調査の内容を通じて、日大闘争の経験を文章化する作業の一環となった記録活動の様相と意義について考察する。「日大930の会」は、日大闘争をめぐる膨大な量の記憶を檻から解放させるために、日大全共闘の当事者への呼びかけを続けながら、『日大闘争の記録――忘れざる日々』の記録本シリーズを発行した。彼らが「悪質タックル問題」に対してとった行動から、全共闘運動の記録活動が改めて意味づけられた。つまり、「日大930の会」は、あいかわらず日大全共闘として自分自身を歴史の対象として客観的に考察するための、記録作業に取り組み続けてきたことが、今日でも日大全共闘の持続性と現在性に対して自覚的に意識を向け、その系譜を提示したのである。
2 0 0 0 OA 「連帯」の光と影 第三世界都市バンドンにおける植民地主義とその脱却
- 著者
- 金 悠進
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.47-71, 2019 (Released:2019-10-21)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1
1955年、アジア・アフリカ会議がインドネシアのバンドンで開催された。植民地主義に反旗を翻す舞台となった「バンドン」は、しばしば第三世界の連帯の象徴的記号として捉えられる。本稿は、このような反植民地主義の連帯としての「バンドン」イメージを相対化し、よりローカルな文脈から、異なる都市イメージの構築を目指す。具体的には、バンドンの若者たちによる文化実践がなぜ植民地主義の残影を引きずり、いかにしてナショナル・アイデンティティを喪失しつつも西洋の模倣から脱却していったのかを論じる。主にポピュラー音楽を中心に、近代美術やイスラームなどバンドンのローカルな日常の文化実践における特殊性/多様性に着目しつつ、アジア・アフリカ会議の「裏」舞台を描く。上記分析過程を通じて、「インターアジア」におけるカルチュラル・スタディーズの分析枠組みを提示する。 脱植民地主義を掲げる戦後最大の歴史的出来事として、アジア・アフリカ会議が植民地都市バンドンで開催されたという文脈は、現在に至るまで当該都市の文化実践を規定してきた。にもかかわらず、国家の共産主義化、脱植民地主義化と乖離するかのように、バンドンの若者たちが脱イデオロギー的な西洋志向の文化実践に傾注し続ける背景を、近代美術を事例に論じる。さらに、西洋模倣型の実践形態が都市における庶民的・国民的文化の周縁化、ひいては新たな植民地主義への構造的加担に帰結する背景を1970 年代のポピュラー音楽における対抗文化的実践から明らかにする。最後に、イスラームが新たな文化実践の代替的イデオロギーとして台頭することによる「新たな連帯」の萌芽を提示する。
2 0 0 0 OA 書評『韓国ポップのアルケオロジー 1960-70年代』
- 著者
- 伏木 香織
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.193-197, 2018 (Released:2019-10-09)
- 参考文献数
- 3
2 0 0 0 OA 巻頭言
- 著者
- 有元 健
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.3-6, 2019 (Released:2019-10-21)
- 著者
- 安藤 有史
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラルスタディーズ = The annual review of cultural studies : カルチュラル・スタディーズ学会学会機関誌 (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.71-95, 2021
- 著者
- 田 泰昊
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラルスタディーズ = The annual review of cultural studies : カルチュラル・スタディーズ学会学会機関誌 (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.145-168, 2018
2 0 0 0 紫煙と社会運動 : 現代日本における大麻自由化運動
- 著者
- 山本 奈生
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラルスタディーズ = The annual review of cultural studies : カルチュラル・スタディーズ学会学会機関誌 (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.59-79, 2018
1 0 0 0 OA 戦後日本における初期ストリッパーの実践 ――「芸術」志向とまなざしの転覆――
- 著者
- 泉 沙織
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.101-123, 2022 (Released:2023-07-25)
- 参考文献数
- 50
本稿は、1947年に始まった日本におけるストリップティーズのうち初期のものについて、踊り子の労働状況と、観客のまなざしを受けた踊り子の「主体的」実践について論じている。本稿では新聞や雑誌などの一次資料から踊り子の労働状況を把握するとともに、彼女たちの言説を取り上げ、ストリップが一方的に見られるのではなく観客を「見返す」演技を行うことに着目した。 初期のストリップを演じた女性たちは、元々踊り子をしていたり、公務員や主婦であったりと、様々な背景からこの世界に飛び込んだ。ストリップは他の職業と比べて多くの給与を得ることができたため、生活のためにこの世界に入る者が多く、芸能界として捉えられながらも観客からは哀れみの目を向けられていた。その一方でなかにはストリップに芸術性を見出し、積極的な姿勢で踊りに取り組んだ者がいた。本稿は踊り子による「芸術」志向やそのための観客を見返す演技が、観客による哀れみや一方的な性的客体化をひるがえし、自らを「主体」として位置付けていくために行われていたと指摘する。踊り子は「芸術」という言葉を用いることで、他者と差異化を図り自己を規定していたと考えられる。そして、ストリップの「生」の上演空間では映画や写真と異なり観客と踊り子の視線が直接結びつき、踊り子は観客の反応によって踊りへのモチベーションを左右された。ストリップは女性が「純潔」であるべきで、「女性の性欲は男性に与えられる」という当時の性規範を逸脱する表現を可能にした。 また、当時のストリップは「パンパン」のように直接的に体を売らずに給与を稼ぐ手段を女性たちに提供したが、労働環境には覚醒剤の蔓延や悪質なブローカーの存在など問題点が多く、全面的には肯定しがたい。また、本稿で取り上げたようなメディアにおける踊り子の「主体的」な言説は、有名で金銭的に余裕のあった踊り子の声に偏っていることも指摘している。
- 著者
- 西田 梨紗
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.95-116, 2019 (Released:2019-10-21)
- 参考文献数
- 18
本研究の契機は、なぜローレンスとリーはヘンリーの悪夢のなかで、エドワードに兵隊の音頭をとるドラマーの役割を与えたのか、という疑問である。エドワードのモデルはラルフ・ウォルド・エマソンの息子エドワード・ウォルド・エマソンであり、エドワードはヘンリー・デイヴィッド・ソローを慕っていた。ヘンリーとエドワードの親しい関係は劇中で描出されている。だが、ヘンリーがみた悪夢のなかでは、エドワードには兵隊の音頭をとる役割が与えられており、彼にこの役割は不似合いであるために違和感を覚える。 この問いを明らかにするため、本研究ではまず1960年から1970年頃におけるソローの評価とともにベトナム反戦運動に着目し、Jail が執筆された時代背景を振り返った。次に、この戯曲中でアイデンティティの問題が主張されている場面と、権威に対する不服従の精神が描かれている場面を取り上げた。ここでは、ソローが生涯を通じて持ち続けたʻʻCivil Disobedienceʼʼ の精神をテーマにしたJail が、なぜこの時代に営利目的としない劇場や大学で次々と上演されていたのかをベトナム戦争における問題と関連付けながら考察し、当時求められていた精神を明らかにした。最後に、ヘンリーがみた悪夢の場面に着目し、戦場で兵隊の音頭を取るエドワードの姿はなにを意味するのかをWalden に流れるʻʻDifferent Drummerʼʼを鍵語に検証を行った。 検証の結果、エドワードに兵隊の音頭をとる役割のみならず、攻撃を受け負傷させることで、戦争がもたらす脅威を観客に訴えかけようとしたローレンスとリーの意図が明らかになった。また、彼らはヘンリーが登場人物たちに自分自身の存在を再認識させる場面を織り込むことで、当時の若者たちが模索していたアイデンティティの問題をも観客に投げ かけているといえよう。
1 0 0 0 OA 「隠された戦争」を書く カメルーンにおける抑圧された過去と文学
- 著者
- 須納瀬 淳
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.143-161, 2019 (Released:2019-10-21)
- 参考文献数
- 29
第二次大戦後から、カメルーンでは独立を求める人々とフランスとの間で戦争が行われた。独立した他のアフリカ諸国と比べたとき、この国には二つの特殊性がある。第一に、フランス植民地であった「ブラック・アフリカ」のなかで唯一、武力によって独立運動の弾圧が行われたこと。第二に、両国間で起きた戦争についての語りが、独立後のポストコロニアル国家および旧宗主国フランスの双方によって公的な場から排除されてきたということである。この意味で、それは文字通りの「隠された戦争」だった。 本稿では、カメルーンの戦争の認識をめぐるこうした困難な状況を辿った後に、国家が提示する公式の〈歴史〉に抵抗しつつ、この戦争について独自の視点から語ろうとしてきた作家たちの試みについて検討する。とりわけ、国家が歴史的な「真理」を決定してきたカメルーンのような国においては、いくつかの文学的作品は単なる「作り話」の範疇には 収まらない重要な意味を持っている。それらは、国家的〈歴史〉に対して、過去の出来事について複数の視点から為された作家たち独自の解釈による介入として読むことができる。 独立直後においては、その出来事についての語りが許されない状況下で、モンゴ・ベティは植民地主義の実態を告発するために小説を政治的ルポルタージュの代替表現として用いた。また彼より後、独立後に生まれた作家たちは、彼とは異なる観点や手法からその出来事にアプローチしているが、われわれはそこに認められる二つの特徴を重要なものとして挙げている。一つは独立闘争における女性の視点に焦点があてられていること。もう一つは過去が次世代に語り継がれる伝承が問題とされることである。 最期に、マックス・ロベの小説『打ち明け話』をとりあげ、アフロ・ディアスポラとしての主体が、戦争の過去と持つ特異な関係性を明らかにする。
1 0 0 0 OA 特別寄稿
- 著者
- 岩崎 稔
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.3-9, 2020 (Released:2020-10-09)
- 著者
- 張 碩
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.11-34, 2020 (Released:2020-10-09)
- 参考文献数
- 55
東日本大震災により東京電力の福島第一原発に深刻な事故が発生後、日本国内に留まらず、全世界の原発政策に重大な影響を及ぼしている。筆者の母国中国では、政府が同年の3月16日に原発の新規建設計画の審査・承認の暫定的凍結を決定したが、関連報道ではその後原発運行・推進に傾いたことが見受けられる。 福島原発事故が発生した際に、中国のメディアは連日事故に関する報道を流し続けた。その中で、中国中央電視台で東日本大震災と福島原発事故の情報を取得した人が74.8%に達した1)。本稿は中央電視台で放送された唯一の長篇ドキュメンタリー番組シリーズ『日本大地震啓示録』を分析することを通して、(1) 中国のテレビメディアは原発および福島原発事故をめぐる報道中に隠されたイデオロギーを解明し(2) それらのイデオロギーを維持するのに使用された言語要素を明らかにすることを目的とする。今まで、福島原発事故をめぐる中国メディアの報道に関する研究は多いが、談話分析の研究は殆どないため、本稿では、分析にあったては主にトポス(Wodak 2001,2010) と前提(Fairclough 2003) の理論枠組みを用い、『日本大地震啓示録』におけるナレーション、ジャーナリストおよび専門家などの談話 から5 つの抜粋を取り上げ、ミクロ分析を行う。それによって、福島原発事故の被害が悪化することを避けられると主張し、事故の深刻化を東京電力と日本政府に帰責する意図を解析できた。また、同番組において、専門家は原発の必要性・重要性を強調し、原発の稼働を当然視するイデオロギーも読み解かれ、さらに『日本大地震啓示録』はそれらのイデオロギーが視聴者に受け入れられやすいように使用された言語ストラテジーを明らかにした。
- 著者
- 澤田 聖也
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.101-125, 2020 (Released:2020-10-09)
- 参考文献数
- 17
本論文では、沖縄の民謡クラブ(復帰前)と民謡酒場(復帰後)のコミュニティに注目し、両者のコミュニティがどのように変化してきたのか、そのプロセスを明らかにする。一般的に、現在の民謡酒場は観光芸術の文脈で語られ、観光客が期待する「沖縄らしさ」を演出したものになっている。しかし、民謡酒場の歴史を辿ると1960年代に民謡酒場の前身である民謡クラブから始まり、そこでは、地元の演奏者と客の相互コミュニケーションを通した強いコミュニティが形成されていた。民謡クラブには、観光芸術とは無縁の空間が広がっていた。だが、1972年に沖縄が本土復帰を果たすと、沖縄には、観光客が訪れるようになったことで、民謡クラブの客層が徐々に地元民から観光客に移り、それに伴いながら民謡クラブのシステム、音楽、環境なども変化していった。 復帰前の民謡酒場が、「演奏者―客」の連帯感が強い相互コミュニケーションがあったコミュニティに対し、復帰後は、「演奏者―客」の連帯感が弱いコミュニティーになった。それは客層の変化も大きく関係しているが、それ以外にもコミュニティの紐帯を強固にしたり、緩めたりする要素が含まれている。コミュニティの形成には、人と人の関係性だけでなく、モノと人の関係性も重要であり、ANT の視点も入れながら、本論文では、復帰前後のコミュニティの変化のプロセスを明らかにする。
1 0 0 0 OA 黒人の母語と欠陥英語論 ――利害一致論からの一考察――
- 著者
- 源 邦彦
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.127-150, 2020 (Released:2020-10-09)
- 参考文献数
- 80
支配集団である白人による黒人(米国アフリカ系奴隷子孫)の母語(黒人言語)に対する科学的ディスコースの構築という観点から、黒人言語に関する研究の歴史は四つの時期―第一期:異常英語論、第二期:誤謬英語論、第三期:欠陥英語論、逸脱英語論、第四期:民族英語論、固有言語論―に分けて考えることができる。各時代は特定の社会変動と社会構造に一致し、黒人言語についての研究は、諸権利獲得と人種間平等への機運が黒人のあいだで高まり、白人の既得権益が脅かされるとパラダイムシフトする傾向にあったといえる。 本研究で扱う第三期の欠陥英語論は、東西冷戦、1954 年の公教育施設での人種隔離政策に違憲判決を下したブラウン裁判、1964 年以降の各種公民権法制定など大きな社会変動のなか、黒人による権利要求の高まり、白人による既得権益の死守などが相互作用した結果、基本的には白人側が一方的に構築した科学的パラダイムであると考える。この時代は、アフリカやアメリカの黒人社会など非白人地域に関する研究、すなわち欧米中心主義的な知識の構築に向けて、米政府や同国慈善財団が社会科学に莫大な投資を行う時期で、黒人言語の言語的病理性を説く欠陥英語論、その言語的正当性を説く逸脱英語論という、黒人言語の解釈を巡り一見相対立する立場をとる両分野に対して投資が行われていた。本稿では、利害一致論(Bell 1980, 2004)の観点から、既存社会構造の維持に貢献し、その一部は時代横断的にも見られる、欠陥英語論の五つの特徴―カラーブラインド・ディスコース、誤謬としての黒人言語、疾患としての黒人言語、排除されるべき黒人言語、逃避的相関分析―を分析する。第二次世界大戦までの生物学的決定論に立脚した近代的人種主義とはある部分では決別した欠陥英語論が、どのようなディスコースを構築し、どのように人種主義を合理化し、どのように既存の社会体制を維持しようとしていたのか、利害一致論の視座か ら論究する。
1 0 0 0 OA 書評『言語的、学術的翻訳を通して見出された 「博物館学」の未来』
- 著者
- 潘 夢斐
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.198-202, 2018 (Released:2019-10-09)
1 0 0 0 OA 特集のねらい
- 著者
- 有元 健
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.3-4, 2018 (Released:2019-10-09)
1 0 0 0 OA 幸せの倫理学
- 著者
- 金 艾瓓 鄭 優希
- 出版者
- カルチュラル・スタディーズ学会
- 雑誌
- 年報カルチュラル・スタディーズ (ISSN:21879222)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.25-46, 2018 (Released:2019-10-09)
- 参考文献数
- 23