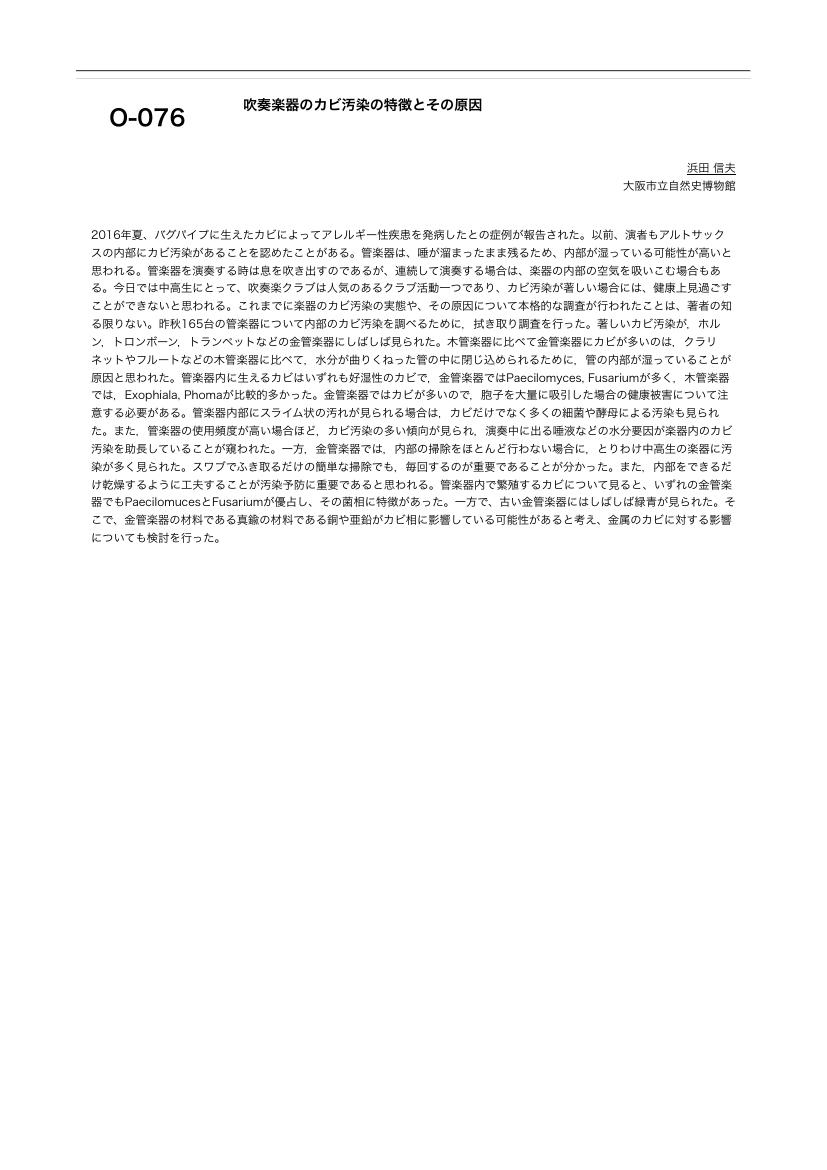8 0 0 0 OA 河川氾濫による水害に遭遇した植物標本のカビ汚染とその対策
- 著者
- 浜田 信夫 馬場 孝 佐久間 大輔
- 出版者
- 大阪市立自然史博物館
- 雑誌
- 大阪市立自然史博物館研究報告 = Bulletin of the Osaka Museum of Natural History (ISSN:00786675)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, pp.29-34, 2021-03-31
2020年 7 月に発生した豪雨による球磨川氾濫で被害を受けた熊本県の人吉城歴史館の植物標本 を,乾燥・クリーニングする過程で,汚染カビの種類や性質について,14サンプルを調べた.最も多 く繁殖していたカビは,Trichoderma で,その他に,Fusarium,Penicillium などが検出された.いずれ も貧栄養な土壌中に一般的に見られる好湿性のカビであった.保存した植物標本に生育するカビには 好乾性カビは見つからなかったことから,いずれも洪水に由来し,浸水と同時に発生したカビと思わ れる.これらの汚染カビは,十分な乾燥を数カ月行えば,消失すると思われる.あわせて,乾燥や酸 素遮断を優先するカビ被害への初期対処法の提言も行った.
4 0 0 0 OA 博物館所蔵菌類標本へのカビ汚染についてのリアルタイムPCRによる追跡
- 著者
- 浜田 信夫 田口 淳二 佐久間 大輔
- 出版者
- 大阪市立自然史博物館
- 雑誌
- 大阪市立自然史博物館研究報告 = Bulletin of the Osaka Museum of Natural History (ISSN:00786675)
- 巻号頁・発行日
- no.77, pp.29-36, 2023-03-31
博物館の乾燥菌類標本のカビ汚染について調査を行ったところ,カビはDNAとして検出されるが,現在生存していないことが明らかになった.そこで,過去に採集,乾燥,標本の作製,保存のどの段階で,どの程度カビ汚染が起きたかについて,博物館に収蔵されているAmanita属36標本のカサの部分を用いて検証した.手法としては,2種のカビの作成したプライマーを用いて,各検体のカビ数をリアルタイムPCRで測定し,その胞子数を調査した.得られた結果は次の通りであった.①両種の胞子数は標本ごとに桁違いのバラツキがあった.②検出されたA. penicillioidesの胞子数は,標本の乾重量100 mg当たり平均約1000個, Eurotium sp. は約7個であった.③結果は,採集時からの様々な過程で,湿り気が発生し,標本上にカビが一時的に発生したことを示唆している.なお,産出された胞子数は標本の古さ,あるいは目視でのカビの有無とは関係ないので,保存前の段階で汚染がしばしば起きたと推測される.
2 0 0 0 OA 吹奏楽器のカビ汚染の特徴とその原因
- 著者
- 浜田 信夫
- 出版者
- 日本菌学会
- 雑誌
- 日本菌学会大会講演要旨集 環境微生物系学会合同大会2017
- 巻号頁・発行日
- pp.84, 2017 (Released:2018-03-30)
1 0 0 0 OA 自然史博物館の収蔵庫と展示室における落下カビ調査
- 著者
- 浜田 信夫 佐久間 大輔
- 出版者
- 大阪市立自然史博物館
- 雑誌
- 大阪市立自然史博物館研究報告 = Bulletin of the Osaka Museum of Natural History (ISSN:00786675)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, pp.161-166, 2018-03-31
大阪市立自然史博物館でカビ汚染の状況をモニタリングするため,収蔵庫や展示室などで落 下カビの調査を行い,以前行った寺社の収蔵庫での落下カビの調査の結果と比較した.大阪市立自 然史博物館の落下カビ数は,寺社の場合に比べて,非常に少ないことが明らかになった.寺社の空 調を施していない部屋に比べて1/100以下に,空調のある部屋に比しても1/30以下だった.また,収 蔵庫内部で生育したとみられるカビは見られなかった.その理由として,博物館の収蔵庫は年中温 湿度が20°C,55%に自動制御されていることが原因であると思われる.
1 0 0 0 金管楽器内で生育するカビの金属耐性
- 著者
- 浜田 信夫 阿部 仁一郎 佐久間 大輔
- 出版者
- 日本防菌防黴学会
- 雑誌
- 日本防菌防黴学会誌 = Journal of Antibacterial and Antifungal Agents (ISSN:2187431X)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.7, pp.265-271, 2019-07
- 著者
- 今井 照彦 堅田 均 西浦 公章 錦織 ルミ子 浜田 信夫 濱田 薫 渡辺 裕之 成田 亘啓 三上 理一郎
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本呼吸器内視鏡学会
- 雑誌
- 気管支学
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.268-274, 1987
- 被引用文献数
- 4
症例は, 47歳男性。既往歴は42歳時肺結核, 糖尿病。61年1月10日ころより微熱, 咳, 労作時呼吸困難出現。2月5日洗面器約半分の喀血を2回繰り返し, 当院第二内科へ入院した。検査の結果, 右上葉の肺結核の遺存空洞に発生した肺アスペルギルス症と判明した。気管支鏡では右主気管支および上葉枝入口部は全体に発赤腫脹し, B^3入口部は拡大がみられ, 末梢は空洞様であった。壁は凹凸不整で全体に膜がはったようになり, 黒い部分や, 発赤, 新生血管と思われる赤い部分, 苔状物と思われる黄白色の部分が混在してみられた。アンホテリシンB空洞内注入療法により発赤部分, 黄白色の部分が次第に減少して, 治療終了後には凹凸不整がとれ平坦となり, 色調も赤みが消失して全体に一様に黒くなり, 一部線維化のごとく白くなっていた。この所見と平行して臨床症状も改善し, 胸部X線でも空洞壁が著明に薄くなり, これらの空洞壁の内視鏡所見は, アスペルギルス症の治癒過程を示していると思われる。
1 0 0 0 南千島-マリアナ海溝太平洋側への高性能地震観測網の展開
- 著者
- 山田 功夫 深尾 良夫 深尾 良夫 浜田 信生 鷹野 澄 笠原 順三 須田 直樹 WALKER D.A. 浜田 信夫 山田 功夫
- 出版者
- 名古屋大学
- 雑誌
- 国際学術研究
- 巻号頁・発行日
- 1992
我々はPATS(ポンペイ農業商業学校)や現地邦人の方々の協力を得て,平成5年3月ミクロネシア連邦ポンペイに地震観測点を開設することができた.平成4年9月の現地調査以後,手紙とファクスのみでのやりとりのため,現地での準備の進行に不安があったが,現地邦人の方々のご協力もあって,我々は計画を予定どうり進めることができた.その後,地震観測の開設は順調に進んだが,我々の最初の計画とは異なり,電話が使えない(最初の現地調査の際,電話の会社を訪ね相談したとき,「現在ポンペイ全体の電話線の敷設計画が進んでおり,間もなくPATSにもとどく.平成5年3月であれば間違いなくPATSで電話を使うことができる」とのことであったが,工事が伸びた).このため最初に予定した,電話回線を使った,観測システムの管理やデータ収集はできなくなった.近い内に電話回線を利用することもできるようになるであろうことから,観測システムの予定した機能はそのままにし,現地集録の機能をつけ加えた.そして,システム管理については,我々が予定より回数を多く現地を訪問することでカバーすることにして観測はスターとした.実際に観測初期には色々な問題が生じることは予想されるので,その方が効率的でもあった.現地での記録は130MバイトのMOディスクに集録することにした.MOディスクの交換は非常に簡単なので,2週間に1度交換し,郵送してもらうことにした.この記録の交換はPATSの先生にお願いすることができた.実際に電話回線がこの学校まで伸び,利用できるようになったのは平成6年1月のことであった.よって,これ以後は最初の予定通り,国際電話を使った地震観測システムが稼働した.観測を進める中で,いくつかの問題が生じた.(1)この国ではまだ停電が多いので無停電装置(通電時にバッテリ-に充電しておき,短い時間であればこれでバックアップする)を準備したが,バックアップ時ははもちろん,充電時にもノイズが出ているようで,我々のシステムを設置した付近のラジオにノイズが入るので止めざるを得なかった.(2)地震観測では精度の良い時刻を必要とする.我々はOMEGA航法システムの電波を使った時計を用意したが,観測システム内のコンピューター等のノイズで受信状態が悪く,時々十分な精度を保つことができなかった.結局,GPS衛星航法システムを使った時計を開発し,これを使った.このような改良を加えることによって,PATSでは良好な観測ができるようになった.この観測点は大変興味深い場所にある.北側のマリアナ諸島に起こる地震は,地球上で最古のプレート(太平洋プレートの西の端で1億6千万年前)だけを伝播してきて観測される.一方,ソロモン諸島など南から来る地震波はオントンジャワ海台と言われる,海底の溶岩台地からなる厚い地殻地帯を通ってくる.両方とも地震波はほとんどその地域だけを通ってくるので,地殻構造を求めるにも,複雑な手続きはいらない.これまでにも,これらの地域での地殻構造に関する研究は断片的にはあるが,上部マントルに至るまでの総合的な研究はまだ無い.マリアナ地域で起こった地震で,PATSで観測された地震の長周期表面波(レーリー波)の群速度を求めると,非常に速く,Michell and Yu(1980)が求めた1億年以上のプレートでの表面波の速度よりさらに速い.このレーリー波の群速度の分散曲線から地下構造を求めてみると,ここには100kmを越える厚さのプレートが存在することが分かった.一方,オントンジャワ海台を通るレーリー波の群速度は,異常に遅く,特に短周期側で顕著である.この分散曲線から地下構造を求めると,海洋にも関わらず30kmもの厚い地殻が存在することになる.これは,前に述べたように,広大な海底の溶岩台地の広がりを示唆する.同様のことは地震のP波初動の到着時間の標準走時からの差にも現れている.すなわち,マリアナ海盆を伝播したP波初動は標準走時より3〜4秒速く,オントンジャワ海台をとおる波は2〜3秒遅い.この観測では沢山の地震が記録されており,解析はまだ十分に進んでいない.ここに示した結果は,ごく一部の解析結果であり,さらに詳しい解析を進める予定である.