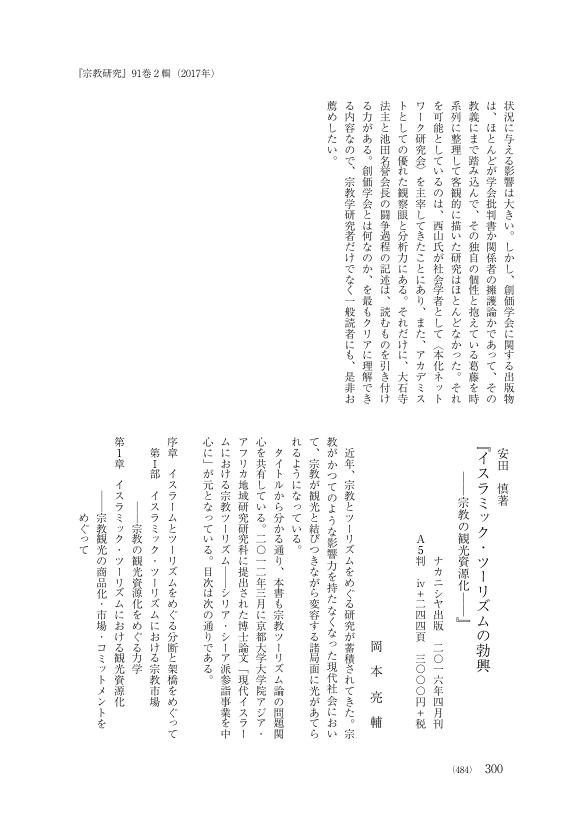- 著者
- 荒川 敏彦
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.2, pp.3-25, 2017
<p>マックス・ヴェーバーにおける宗教と経済という問題は、『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』の再解釈という性格を帯びる。その再解釈に際しては、『倫理』以外の業績と『倫理』との関係を考慮する必要がある。本稿では次の三点を指摘した。第一に、ヴェーバーは経済や法の概念とは異なり、宗教概念に対してのみその本質規定の拒否を明記したが、そこには同時代の宗教研究状況に対する彼の宗教社会学の位置が反映されている。第二に、ヴェーバーの宗教社会学には歴史的研究と理論的研究の二つの方向があるが、歴史的研究は理念型を駆使した理論的性格をもち、理論的研究には『倫理』など歴史的研究の成果が盛り込まれている。相異なる方向性をもつ諸著作は完結しているのではなく、著作間の相互連関によって問いが深化しているのである。第三に、神義論問題は経済格差の問題として解釈可能であり、経済的不平等を正当化する宗教倫理の形成と作用の問題は、現代の宗教と経済の問題を考える上で重要なヒントになる。</p>
2 0 0 0 OA 信念の倫理とプラグマティズム : ウィリアム・ジェイムズ「信じる意志」をめぐって
- 著者
- 林 研
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.3, pp.621-645, 2014-12-30 (Released:2017-07-14)
ジェイムズの学説「信じる意志」は、情的本性に基づく信仰を正当化する試みだが、何でも好きなように信じてよいということではない。想定されているのは「生きた」仮説を信じるか疑うかの葛藤状態であり、そこでの実践倫理が問題なのである。人間心理において、蓋然性と望ましさは分離し難く、証拠なしには信じない態度も実は誤謬への恐怖に基づく。その一方で、人間本性には証拠がなくとも信じる暗黙の合理性がある。それならば倫理的基準としては証拠よりも、プラグマティズムが要請する帰結の整合性の方が相応しいとジェイムズは考える。さらに、宗教は「事実への信仰がその事実を生み出す助けになりうる」命題であり、その真理性を検証するにはまず信じなければならない。つまり、ジェイムズの言う「信じる」は盲信ではなく、整合性を検証しつつ真理を生み出すことである。この場合、救いを求める者にとっては、信じることが懐疑に優越すると言うことも可能になる。
2 0 0 0 時間性の言説としての宗教進化論の系譜
- 著者
- 藤井 修平
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.1, pp.75-97, 2016
<p>本論文は、宗教進化論を特定の時間的枠組みの下に宗教事象の配列および秩序づけを行うものと定義し、その十九世紀から二十世紀に至る系譜を記述することを目的とする。従来の学説史では人類の文化が呪術から宗教へと発展し、科学へと至るという言説のみが進化論として理解されていたが、宗教進化論は時代を通してさまざまな形態をとっており、またそれは生物学的進化論との緊張により発展してきたという側面も見られる。</p><p> 本論文ではまず「進化」の概念を整理した上で、宗教進化論の再定義を行う。宗教進化論は、単一の進歩の尺度を設定し、時代を経るごとにその尺度とされる要素が増大するとみなすことによって、歴史上の宗教を特徴づけ、配列する言説として定義される。そしてそのような進化論的枠組みを有する理論として、コント、スペンサーによる枠組みの成立から、新進化論学派とパーソンズ、ベラーによる進化論の復興、そして現代の宗教進化論に至るまでの歴史を描写する。</p>
2 0 0 0 OA 宗教間対話としての東西霊性交流(第一部会,<特集>第六十六回学術大会紀要)
- 著者
- 峯岸 正典
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.4, pp.959-960, 2008-03-30
2 0 0 0 OA アッシリアにおける国家と神殿 : 理念と制度(<特集>国家と宗教)
- 著者
- 柴田 大輔
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.2, pp.269-295, 2015-09-30
現在のイラク北部を中心に繁栄した古代の領域国家アッシリアの王宮と国家神アッシュルの神殿は異なる組織によって運営されたが、両者は統治において一種の共犯関係にあった。王宮を中心とする行政機構によって統治された国土は、理念上国家神の所有とされた。その国家神は神殿において祀られていた(「扶養」されていた)が、この神の祭祀に必要な物資は、規定供物の制度を通じ、アッシリアを構成する全行政州によって共同で賄われた。さらに、規定供物の制度は、理念上で国家神の祭司を兼任した王の直属の人員によって統括された可能性が高い。
2 0 0 0 OA 現代ゾロアスター教における鳥葬の現状と課題(第十四部会,<特集>第72回学術大会紀要)
- 著者
- 香月 法子
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.Suppl, pp.484-486, 2014-03-30 (Released:2017-07-14)
- 著者
- 半田 栄一
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, pp.223-225, 2016
- 著者
- 井上 ウィマラ
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.3, pp.763-770, 2011-12-30
- 著者
- 川瀬 貴也
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.2, pp.217-241, 2015-09-30
植民地朝鮮(一九一〇-一九四五)において、植民地権力たる朝鮮総督府は、日本の諸宗教を導入する「内地延長主義」を採るのと同時に、朝鮮人の諸宗教やキリスト教宣教師などを「寺刹令」や「布教規則」などの様々な法令により管理しつつ、統治に役立たせる方向付けをしようとした。本稿は、一九一九年の「三・一独立運動」以降の、朝鮮人の諸団体の活動や出版活動への制限が緩和されたいわゆる「文化政治期」の朝鮮半島における朝鮮総督府の宗教政策および、日本仏教と朝鮮仏教の諸活動を概観する。具体的には(一)朝鮮総督府の宗教政策の基本コンセプトおよび各宗教への介入、(二)日本仏教の社会事業活動の実例および仏教関係の諸団体の活動、(三)朝鮮仏教内部での動向および朝鮮総督府や日本仏教といかなる「交渉」したのか、という問題を、いくつかの事例を挙げつつ考察する。
2 0 0 0 OA 安田 慎著『イスラミック・ツーリズムの勃興——宗教の観光資源化——』
- 著者
- 岡本 亮輔
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.2, pp.300-304, 2017-09-30 (Released:2017-12-30)
- 著者
- 川瀬 貴也
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, pp.373-374, 2015
2 0 0 0 北枕攷
- 著者
- 竹中 信常
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.p53-77, 1985-06
2 0 0 0 啓蒙の神話学 : フォントネルの神話論とその文脈
- 著者
- 高橋 駿仁
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 = Journal of religious studies (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.1, pp.105-129, 2018-06
2 0 0 0 OA 自然悪の苦しみと宗教哲学 : 神義論的問題の再編成へ向けて(<特集>災禍と宗教)
- 著者
- 佐藤 啓介
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.2, pp.299-322, 2012-09-30
本稿は、世界における悪(とりわけ自然悪)の存在を考える思索について、神の正当化を目指す狭義の神義論から区別し、悪の存在に対する抗議をおこなう思索を広義の神義論として定義し、そうした抗議の声に含まれる宗教哲学的な原資を探るものである。私たちは、自然悪について、自然への謙譲には収まらない抗議や不満を覚える。バーガーによれば、その抗議や不満の根底にあるのは、神の義から切り離してもなお要求しうるような、悪の意味の要求である。だが、この悪の意味は不明確な概念であり、アンリによれば、悪の外的な意味と受苦の内的な意味を区別すべきであり、後者の受苦は、生そのものの成立に関わる超越論的構造に組み込まれるべきものである。他方、外的な悪に対する苦しみへの宛て先のない抗議は、ネグリに従えば、悪の意味の要求ですらなく、悪を不公平と感じる尺度そのものへの反抗であり、尺度を超えた尺度の主体と世界の存在論的生成の契機なのである。
- 著者
- 山口 瑞穂
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 = Journal of religious studies (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.3, pp.569-591, 2017-12
- 著者
- 相川 愛美
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.3, pp.495-519, 2015
本論は時代やその背景とともに変遷するサティーの観念が現代においてどのように解釈されているのかを探ることを目的とする。従来、インドにおいて、サティーとは一般的に夫が死んだ際に妻が夫の遺体とともに積み薪で焼かれる慣行のことを意味する。インドにおけるサティーの観念の解釈はヒンドゥー教諸文献にも記述されており、その見解は時代的傾向と特色、また著述家の立場や地域によって異なっている。しかし、現代では寡婦殉死のみがサティーを意味するのではなく、寡婦殉死した女性が女神化したサティー女神や夫に対して献身的な女性(パティヴラター pativrata)の称号としても認識されている。筆者はインド北西部ラージャスターン州ジュンジュヌー県(Rajasthan, Jhunjhunu)に所在するサティーになった女性を女神として祀るラーニー・サティー(Rani Sati)寺院の縁起譚に着目し、その縁起譚で描かれる夫に対して貞節な理想の女性ナーラーヤニー・デーヴィー(Narayani Devi)のサティー像とこの寺院によって解釈されるサティー崇拝の解釈を試みる。
2 0 0 0 OA 「食」が形づくる出家生活
- 著者
- 藏本 龍介
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.2, pp.29-54, 2016 (Released:2017-09-15)
上座仏教の出家者は、律と呼ばれるルールによって、「食」の獲得・所有・消費方法について、種々の制限を課されている。そしてこうした律を守る出家生活こそが、上座仏教の理想を実現するための最適な手段であるとされる。しかしだからといって、出家者は霞を食べて生きていけるわけではない。ここに上座仏教の出家生活が抱える、「食」をめぐる根深いジレンマがある。それでは現実の出家者たちは、「食」をめぐる問題にどのように対応しているか。そしてそれが出家者の宗教実践をどのように形づくっているか。本論文ではこの問題について、現代ミャンマーを事例として検討する。こうした作業を通じて、宗教/世俗を二項対立的に区別する発想では捉えられないような出家者の仏教実践の一端について、具体的にはなぜ出家し、どのようなライフコースを辿るのか、そして出家者の生活の基盤である僧院組織の構造がどのように規定されているのかといった諸点を明らかにする。
- 著者
- 川上 恒雄
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.4, pp.1193-1194, 2007-03-30
2 0 0 0 OA シンクレティズム論再考 : 南アジアの聖者信仰におけるヒンドゥー教とイスラーム
- 著者
- 外川 昌彦
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.1, pp.25-43, 2006-06-30 (Released:2017-07-14)
異質な宗教文化の接触や混交は、従来「シンクレティズム」と呼ばれて説明されてきた。日本では「神仏習合」としてなじみのある「シンクレティズム」概念は、しかし宗教学者や人類学者の間で様々な批判にさらされている。本報告では、ベンガル地方の聖者信仰に見られる多元的な宗教実践が構成される条件を明らかにすることで、「シンクレティズム」概念の再検討を試みるものである。具体的には、バングラデシュ東部のモノモホン廟での多元的な宗教的実践のあり方を検討し、聖者廟をめぐる地域社会の多様な言説を検証する。特に、シンクレティックな理念を体現する聖者としてのモノモホンの宗教性を尊重しつつ、同時にイスラームの観点を強調するイスラーム知識人の見解が検討される。これらの分析から、モノモホン廟を中心としたシンクレティックな宗教世界の構成が、一方で信徒による多元的な宗教的実践を可能にする条件を与えると同時に、他方では異なる解釈を通した多元的な言説の生成をも妨げないという意味で、近代のコミュナルな対立とも容易に結びつくことが明らかにされる。
- 著者
- 葛西 賢太
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 = Journal of religious studies (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.2, pp.215-239, 2016-09