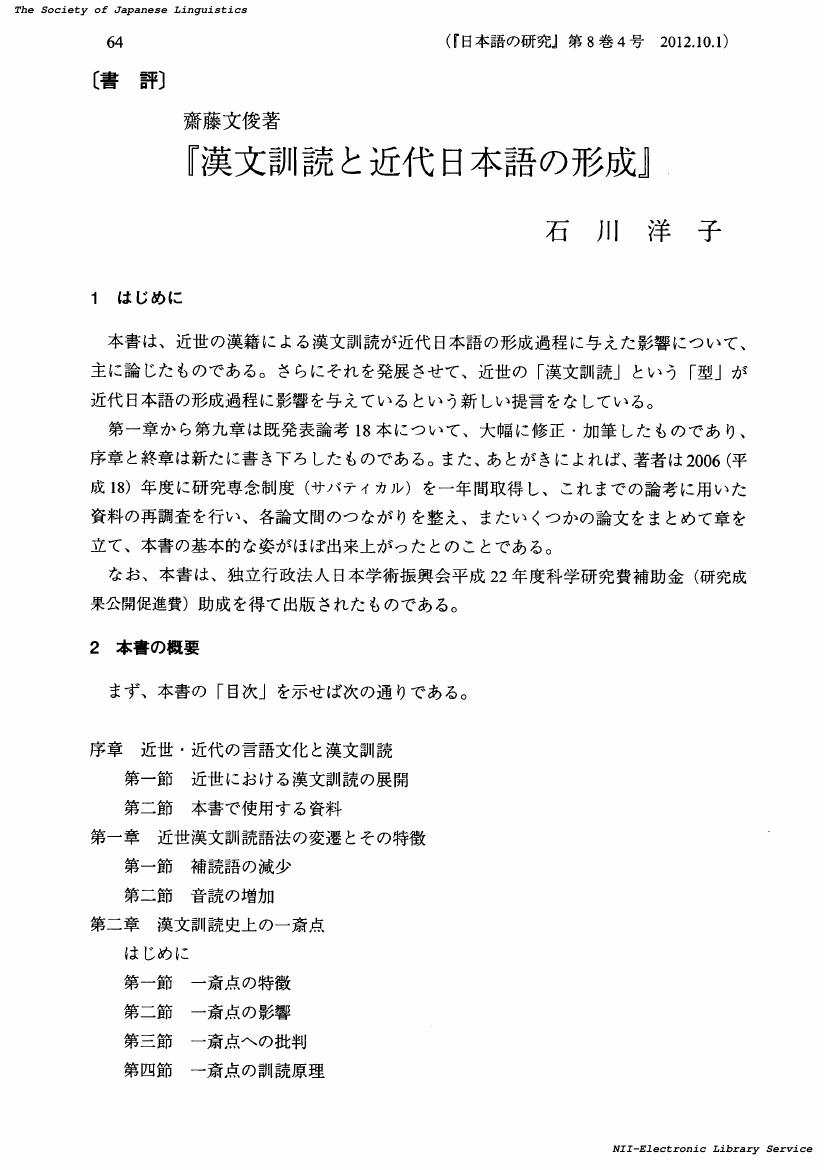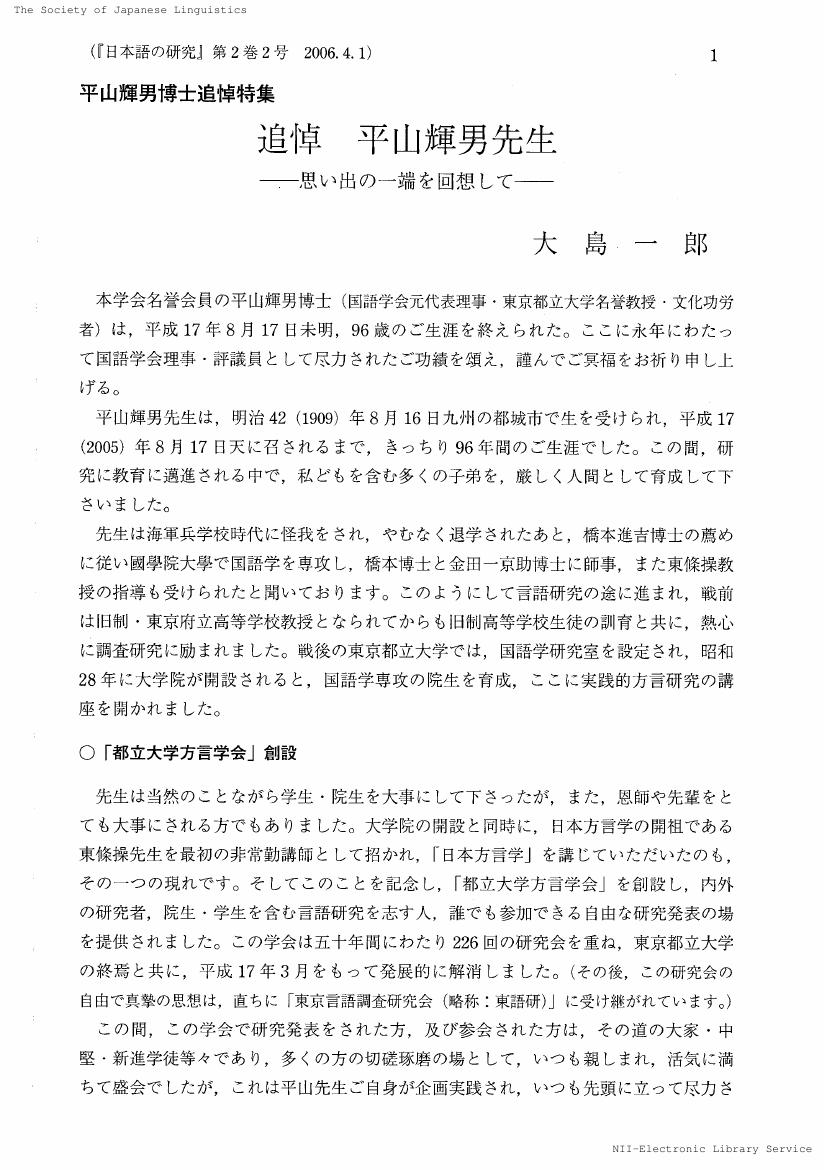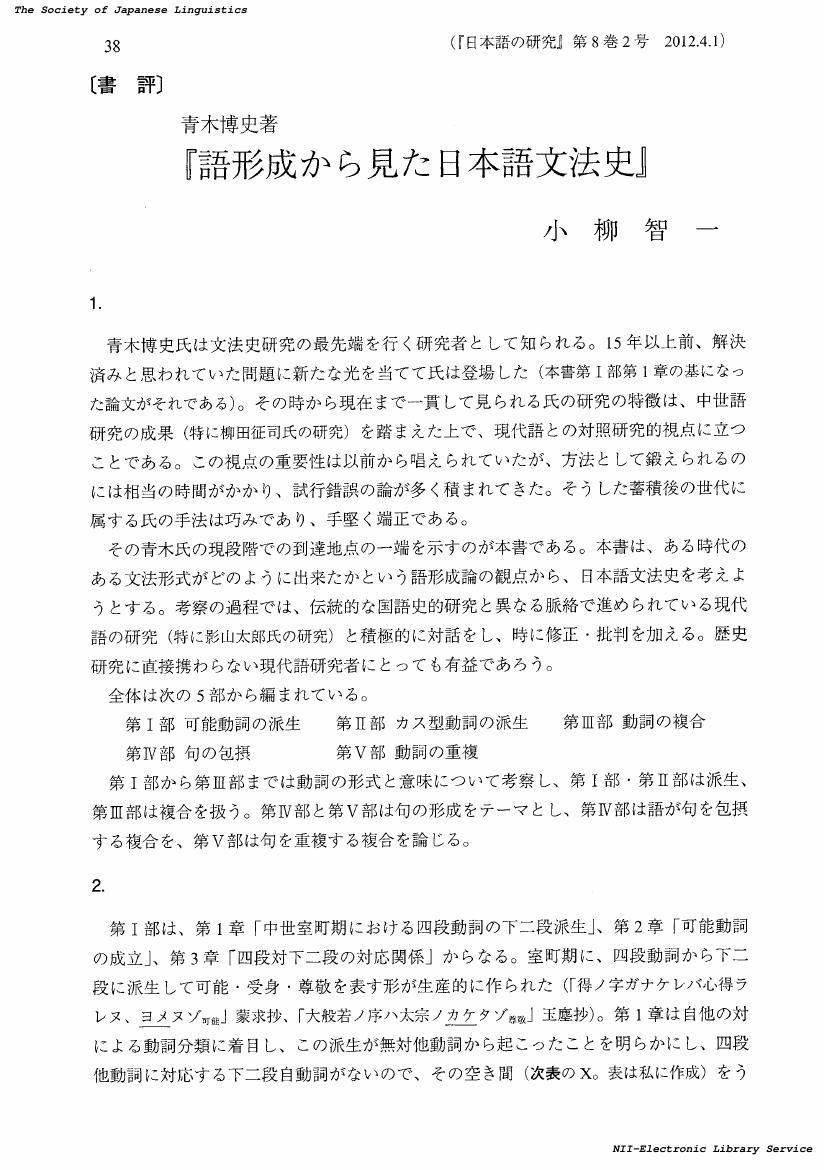- 著者
- 金水 敏
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.4, pp.70-74, 2012
- 著者
- 屋名池 誠
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.3, pp.132-138, 2009-07-01 (Released:2017-07-28)
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 石川 洋子
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.4, pp.64-69, 2012-10-01 (Released:2017-07-28)
1 0 0 0 OA 琉球語から見た日本語希求形式=イタ=の文法化経路(<特集>琉球語を見る/琉球語から見る)
- 著者
- ローレンス ウエイン
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.4, pp.30-38, 2011-10-01 (Released:2017-07-28)
琉球のいくつかの方言にみられる希求形式の使用状況から、琉球方言の=イタシ系の希求形式は生理的に不随意の身体機能を表す動詞のみと共起し、必要性を訴えるのが古い使用法であると考えられる。この=イタシは「痛みを感じるほど痛烈に感じる状態に達する」という意味から発達したとみられるものである。本土日本語の=イタシも、「甚(イタ)シ」からではなく、琉球方言と同じ文法化の経路をたどって、希求形式になったと思われ、その文法化の出だしは日琉祖語の時代に遡ると推測される。
1 0 0 0 OA 連語と交替可能な臨時的複合語の語構成 : 新聞社説における「A的なB」と「A的B」の場合
- 著者
- 蔡 珮菁
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.3, pp.17-32, 2007-07-01 (Released:2017-07-28)
「長期的な観点」に対する「長期的観点」のように,「連語」と交替可能な「臨時的な複合語」について,その語構成レベルの成立条件を解明すべく,"接尾辞「的」による派生形容動詞(「A的」)と名詞(「B」)との結びつき"に注目して,要素「A」「B」がその語種・品詞性においてどのようなくみあわせのとき,臨時的な複合語「A的B」になりやすいかを検討した。新聞の社説本文3年分における(交替可能な)「A的なB」「A的B」の使用状況を計量的に調査した結果,「A的B」が最も活発に成立するのは,「A」「B」がともに2字漢語の(非用言的な)体言類というくみあわせであること,また,このくみあわせは,4字漢語複合名詞や和語複合名詞の構成において最も優勢なくみあわせに一致・対応することが明らかとなった。このことから,連語と交替可能な臨時的複合語の成立にも,既存の(固定的な)複合語の構成のあり方が影響を与えていること,すなわち,要素のくみあわせが,既存の語構成において安定的・生産的なタイプに一致・対応するものほど,臨時的な複合語として成立しやすいのではないかとの見通しを得た。
1 0 0 0 OA 追悼 平山輝男先生 : 思い出の一端を回想して(平山輝男博士追悼特集)
- 著者
- 大島 一郎
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.1-5, 2006-04-01 (Released:2017-07-28)
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 金 銀珠
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.123-137, 2006-04-01 (Released:2017-07-28)
近代文法学における「形容詞」は,江戸時代以来の伝統的な形容詞論をスタートラインにおけば,その規定が最初は名詞修飾機能中心へと移行し,次は叙述機能中心へと移行しながら,成立したものである。このような二度の移行に関わっていたのが西洋語のAdjective解釈である。本稿は,近代文法学における「形容詞」「連体詞」概念がどのように成立したのかを,西洋文法におけるAdjectiveとの関連から考察した。近代文法学の「形容詞」概念がAdjectiveを名詞修飾だけに極度に限定していきながら成立し,その結果として,今日の学校文法における「連体詞」が登場する過程を示した。
1 0 0 0 OA 文末形式「模様だ」の成立と展開
- 著者
- 川島 拓馬
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.1-17, 2017-07-01 (Released:2018-01-01)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
本稿では、名詞「模様」が文末に位置して助動詞相当の形式として機能する用法について、その成立から定着に至るまでの歴史的展開を考察した。「模様だ」自体は明治期の新聞に出現しており、大正から昭和初期にかけて継続的に用例を見出せる。記事文体の口語化に伴って1920年代に「模様あり」という形態が衰退すると文末用法への偏りが著しくなり、これによって文末形式として「模様だ」が定着したと言える。ただし「模様」の前接要素の点から見ると未だ現代語と同様の特徴を獲得したとは言えず、助動詞化が進んだのはそれ以降と考えられる。こうした「模様だ」の成立は名詞性の捨象による通時的変化と捉えることができ、更にヨウダの構造変化との類似点および「様子だ」との関係性についても指摘した。
1 0 0 0 OA 謡伝書における五十音図 ──発音注記に着目して──
- 著者
- 竹村 明日香 宇野 和 池田 來未
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.4, pp.48-64, 2018-12-01 (Released:2019-06-01)
- 参考文献数
- 28
室町後期から江戸期にかけて作られた謡伝書にはしばしば五十音図が掲載されており,行段それぞれに謡曲独自の発音注記が付されている。本稿ではそれらの発音注記を精査し,おおよそ二系統に大別できることを明らかにした。一つは悉曇学の影響が強い系統で,行を「口喉舌唇」,段を「上音/中音/下音」の対立で捉えるものである。もう一つは,室町後期以降に権威のあった『塵芥抄』系伝書の系統であり,行を「喉舌歯腮鼻唇」,段を「ひらく/ほそむ/すぼむ」の対立で捉えるものである。『塵芥抄』系伝書の五十音図とその発音注記は,近世の謡伝書や学問書には直接引用されていないものの,処々にその影響を窺わせる記述が見られる。タ行の調音に「腮」を用いて説明している点等は『蜆縮涼鼓集』の記述とも共通しており,近世期における日本語音の把握には,『塵芥抄』系伝書の影響が少なからずあったと考えられる。
1 0 0 0 OA 九州地方における「天国」の受容史 : 宗教差,地域差,場面差
- 著者
- 小川 俊輔
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.1-14, 2012-04-01 (Released:2017-07-28)
九州地方における「天国」の受容の程度を明らかにするため,九州地方全域300地点において現地調査を行った。調査によって得られた資料から言語地図を描き,考察を行ったところ,「天国」の受容には,宗教差,地域差,場面差のあることが分かった。宗教差については,カトリックと神道の信徒が「天国」を受容しているのに対し,浄土真宗の信徒は「天国」を受容しない傾向がある。彼らは仏教語である「浄土」を持つゆえに,「天国」を受容しない傾向をみせたと推測される。地域差については,宮崎・鹿児島では「天国」の受容が進んでいるのに対し,長崎では遅れている。場面差については,大人が子どもに話しかける場面では「天国」が使用されやすいのに対し,仏教色の強い場面では「天国」が使用されにくい。
- 著者
- 永田 高志
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.43-50, 2019-04-01 (Released:2019-10-01)
- 参考文献数
- 9
1 0 0 0 OA 『和蘭字彙』電子テキスト化による『英和対訳袖珍辞書』初版の訳語の研究
- 著者
- 櫻井 豪人
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.17-32, 2013-07-01 (Released:2017-07-28)
『英和対訳袖珍辞書』初版(文久二1862年刊)の訳語は約6〜7割が『和蘭字彙』の訳語と一致すると言われてきたが、具体的にどの語が『和蘭字彙』から取られた訳語であるかを特定することがこれまで困難であった。本研究では、『和蘭字彙』の日本語部分の全てを電子テキスト化することで『和蘭字彙』の訳語を直接検索可能にし、それにより、『和蘭字彙』に見られない『袖珍』初版の訳語の例を明確に示すとともに、それらから窺われる『袖珍』初版の訳語の特色と編纂態度の一端を描き出した。
- 著者
- 小柳 智一
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.38-44, 2012-04-01 (Released:2017-07-28)
1 0 0 0 大分方言における動詞終止形の撥音化とその意味するところ
- 著者
- 江口 正
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.34-50, 2018
<p>九州各地の方言は動詞活用の組織に特徴があり,二段活用(特に下二段)が残存して古い特徴を保つ一方,一段動詞がラ行五段化するという新しい変化の方向を併せ持つ。このふたつの特徴は方向性が逆であるため,別個の説明が与えられることが多かった。本稿では,大分方言に見られる動詞終止形の撥音化現象を手掛かりに,それらの特徴はいずれも「同音衝突の回避」が関係するという仮説を提出する。</p>
1 0 0 0 OA 孫 建軍著『近代日本語の起源──幕末明治初期につくられた新漢語──』
- 著者
- 荒川 清秀
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.43-49, 2017-01-01 (Released:2017-07-01)
1 0 0 0 OA 日本語の文法化の形態論的側面(<特集>日本語における文法化・機能語化)
- 著者
- ナロック ハイコ
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.3, pp.108-122, 2005-07-01 (Released:2017-07-28)
- 被引用文献数
- 1
自立語または統語構造が付属語化,接尾辞化していくという形態的過程が文法化論の出発点となっているが,現在行われている文法化論はむしろ意味・機能面に集中している。そして,特に形態変化が豊富な日本語においては,形態変化のあり方,とりわけ形態変化の規則性は明確に記述されているとは言えない。本稿は,日本語の文法化における形態的側面に焦点を当て,動詞活用・派生体系の形態変化に基づいて四つの原則,つまり(1)(自立語の)接尾辞化,(2)形態的統合,(3)音韻的短縮,(4)活用語尾化が働いていると指摘する。こうした原則を特定するために音韻的にも厳密な形態論を使用する必要があると論じる。また,最後に,原則に反する形態変化の例を取り上げ,そこに「外適応」と「類推」のプロセスが働いていることを示す。
- 著者
- ナロック ハイコ
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.103-109, 2012-01-01 (Released:2017-07-28)
- 著者
- 井島 正博
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.58-63, 2012-04-01 (Released:2017-07-28)
- 著者
- 大島 資生
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.3, pp.133-138, 2014
- 著者
- 藤井 俊博
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.130-136, 2008-01-01 (Released:2017-07-28)