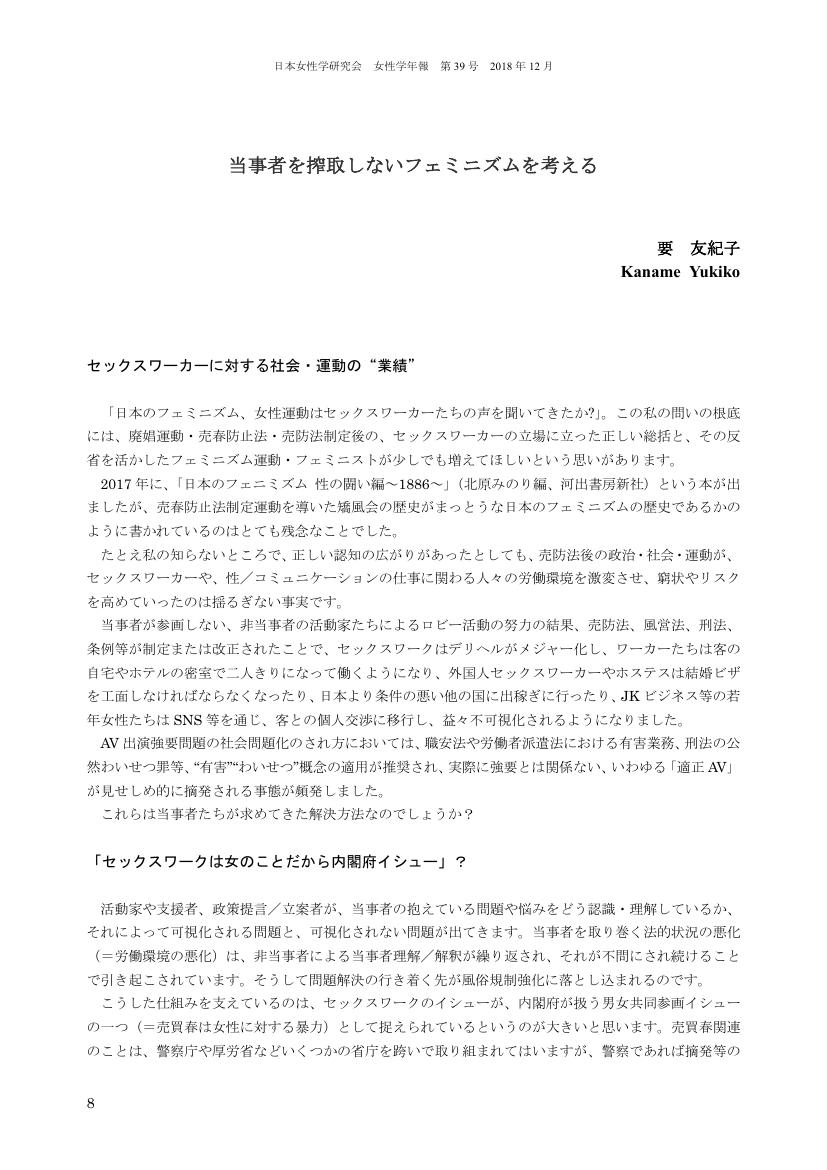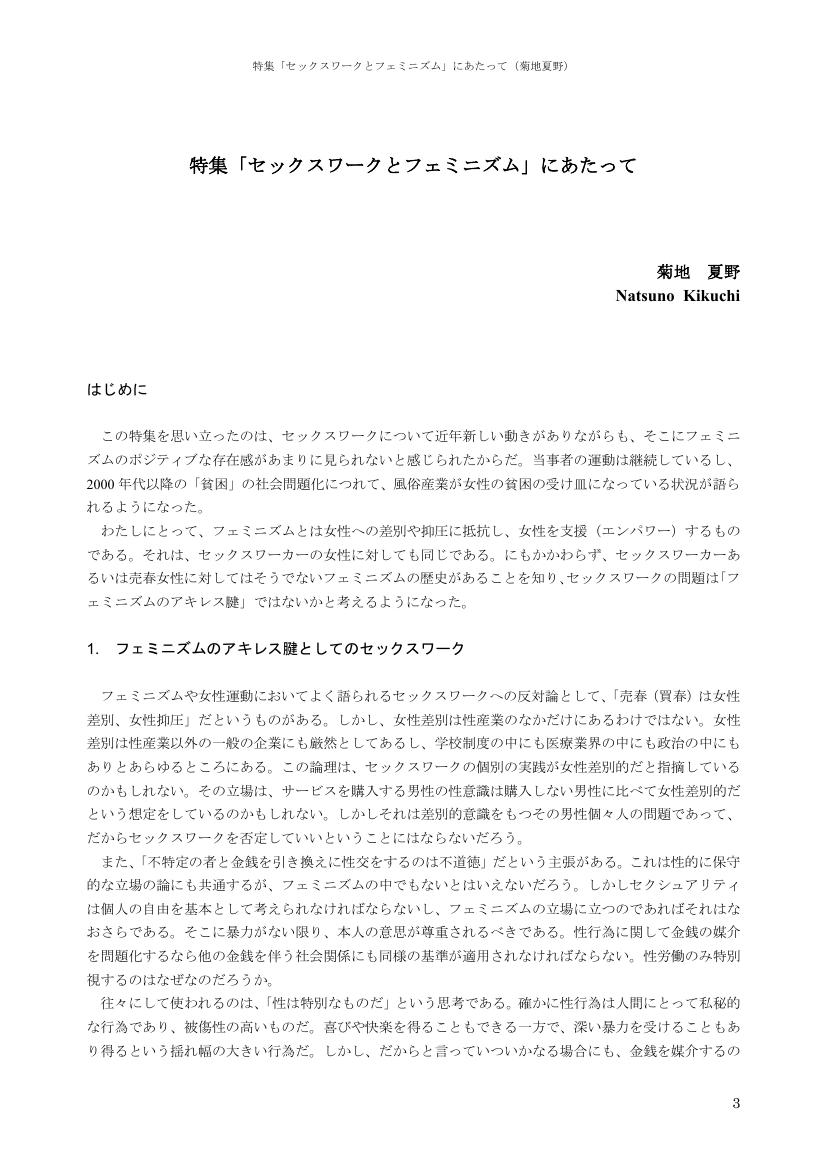114 0 0 0 OA 地方自治体によるライフプラン教育 「若い時期での妊娠・出産」奨励と、歯止めとなっていない男女共同参画
- 著者
- 斉藤 正美
- 出版者
- 日本女性学研究会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.3-22, 2020 (Released:2020-12-19)
- 参考文献数
- 31
本稿の目的は、「ライフプラン(ライフデザイン)教育」とはどのような内容や取組なのか、特色ある取組を行っている都道府県、特に高知県及び富山県を中心に、行政担当者や学校関係者等への聴き取り調査を行い、明らかになった現状と課題を指摘することにある。さらに取組が全国に浸透している要因の考察も行う。「ライフプラン教育」とは、国の少子化対策の交付金等により結婚を支援する「婚活政策」の一環で、地方自治体が中学・高校・大学生や市民に人生設計を考えさせ、若い時期での結婚や妊娠を増やそうとする取組である。 聴き取り調査の結果、ライフプラン教育には、婚活企業の関係者や国の少子化対策等の審議会委員等、婚活や婚活政策の利害関係者が関与していること、また取組内容は、早いうちの結婚や妊娠を奨励し、LGBTや独身、子どものいない生き方、ひとり親など、多様性の確保に課題があることが判明した。共働きの家事・育児を自己責任で解決するよう、モデル家族に「三世代同居」を提示するなど、性別役割分業と自助努力が強調されていることも特徴であった。 こうした課題を持つライフプラン教育だが、全国の自治体に浸透し、継続され続けている。その要因としては、「優良事例の横展開」という交付金のあり方に加え、男女共同参画との連携が交付金の採択要件とされたものの、2000年代前半の右派や自民党によるバッシングにより男女共同参画が後退し、歯止めとして機能しなくなっていたことが浮き彫りになった。さらに少子化対策として整備された少子化社会対策基本法、次世代育成支援対策推進法が、妊娠・出産や家族の役割を強調する法律であったことも影響していた。 本稿は、2000年代以降の男女共同参画政策の変遷を踏まえ、地方自治体におけるライフプラン教育の取組に関する現状と課題を提示するもので、少子化問題の解決策と個人の自由意志による生き方の尊重が相反しないあり方の検討に資するといえよう。
- 著者
- 遠山 日出也
- 出版者
- 日本女性学研究会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.23-40, 2020 (Released:2020-12-19)
- 参考文献数
- 54
- 被引用文献数
- 1
家族賃金・年功制、能力主義、競争原理、均等法、個人単位化といった概念・制度・政策には、いずれも複数の意味や方向性があり、それらの背後には複数の社会的な力(新自由主義の力、フェミニズムの力など)が存在している。しかし、日本の左派やフェミニストは、しばしば、こうした複数の意味や方向性、背後にある力を十分区別できなかった。そのために、新自由主義に対する評価が甘くなったり、フェミニズム運動の意義を十分評価できなくなったりした。以上のことと表裏一体の問題として、左派やフェミニストが、しばしば資本主義と家父長制とを統一的に把握していないという問題がある。また、「前近代」「近代」といった歴史的段階だけに注目して、それぞれの社会内部の矛盾やマイノリティの視点を軽視することも、以上のような問題と結びついている。「近代家族」概念にも複数の意味が存在しており、その真の乗り越えは、新自由主義によってではなく、公共領域と家内領域の分離をより高い段階で統一する方向性を有するさまざまな闘いによってのみ可能になる。新自由主義に対抗するためには、今後、家族賃金や能力主義といった概念の複数性についてさらに丁寧に論じていくことが必要である。
79 0 0 0 OA 当事者を搾取しないフェミニズムを考える
- 著者
- 要 友紀子
- 出版者
- 日本女性学研究会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.8-11, 2018 (Released:2019-01-22)
- 参考文献数
- 2
74 0 0 0 20世紀前半の日本における薙刀教育の女性化
- 著者
- ベレック クロエ
- 出版者
- 日本女性学研究会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.63-86, 2020
薙刀(なぎなた)とは、本来長い柄の先に反り返った長い刃をつけた武器である。20世紀半ばまでは学校教育制度外における武術流派の道場で、男性のみならず女性にも薙刀の稽古が続行されたが、1910年に師範学校の女子生徒を対象に課外活動として認められた薙刀は、やがて高等女学校・女子実業学校へと広がった。それは、第二次世界大戦の終結後、GHQの指令により学校での武道教育が廃止されるまで続いた。<br> 20世紀前半に女子教育の領域で普及した薙刀は、ジェンダーに関する新たな問題を提起している。薙刀は、相手を攻撃し、戦うための武器である。「武器」・「攻撃」・「戦う」という言葉で表現されることは、社会的には「男性らしい」と見なされているものである。にもかかわらず、薙刀は女子教育においていかなる理由で採用されたのだろうか。そして、学校教育では、社会や文化における男や女に対する期待と規範が教えられ、体育の教育も「女らしい」「男らしい」という期待に沿いながら行われている。そこで本論文では、20世紀前半の日本の薙刀教育において、「女性らしさ」に対する社会の期待の変化がどのように示されていたかを明らかにする。<br> 当時の女子生徒向けの薙刀教本では、女性らしい健康な身体に備わった女性の優美さと、薙刀との関連性がよく指摘され、薙刀教育は女子の「女性らしさ」を育成しなければならないとされた。そして、薙刀教本では、薙刀と関係がある女性の例をよく取り上げることで、女子教育と薙刀の歴史的関係を強調し、女子向け教育として薙刀を正当化するとともに、薙刀を女性らしいものにした。<br> 20世紀前半において学校教育に導入された武道の中では、薙刀だけが女子のみを対象とするものであった。薙刀を女子教育に採用することによって、女子の武道は男子の武道と差異化された。薙刀は女子武道を代表するものとされ、それによって男子との相違が強調されたのである。このように、薙刀を女子のみの武道として設定することによって、薙刀は女性化されたのであった。
72 0 0 0 OA 特集「セックスワークとフェミニズム」にあたって
- 著者
- 菊地 夏野
- 出版者
- 日本女性学研究会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.3-7, 2018 (Released:2019-01-22)
- 参考文献数
- 2
55 0 0 0 OA 中国の公共交通機関における性暴力反対運動と女性専用車両 ――香港・台湾・日本との初歩的比較も――
- 著者
- 遠山 日出也
- 出版者
- 日本女性学研究会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.21-39, 2018 (Released:2019-01-22)
- 参考文献数
- 14
本稿では、中国で2012年に活動を開始した「行動派フェミニスト」がおこなってきた公共交通機関における性暴力反対運動について考察した。その際、香港・台湾・日本との初歩的比較もおこなった。 中国における公共交通機関における性暴力反対運動も、実態調査をしたり、鉄道会社に対して痴漢反対のためのポスターの掲示や職員の研修を要求したりしたことは他国(地域)と同じである。ただし、中国の場合は、自らポスターを制作し、その掲示が断られると、全国各地で100人以上がポスターをアピールする活動を、しばしば1人だけでもおこなった。この活動は弾圧されたが、こうした果敢な活動によって成果を獲得したことが特徴である。 また、中国のフェミニストには女性専用車両に反対する傾向が非常に強く、この点は日本などと大きな差異があるように見える。しかし、各国/地域とも、世論や議会における質問の多くは女性専用車両に対して肯定的であり、議会では比較的保守的な政党がその設置を要求する場合が多いことは共通している。フェミニズム/女性団体の場合は、団体や時期による差異が大きいが、各国/地域とも、女性専用車両について懸念を示す一方で、全面否定はしてないことは共通している。中国のフェミニストに反対が強い原因は、政府当局がフェミニストの活動を弾圧する一方で、女性に対する「思いやり」として女性専用車両が導入されたことなどによる。
52 0 0 0 OA 最近の男性学に関する論争と私
- 著者
- 遠山 日出也
- 出版者
- 日本女性学研究会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.27-44, 2019 (Released:2019-12-20)
- 参考文献数
- 49
38 0 0 0 OA 書評『セックスワーク・スタディーズ』
- 著者
- マサキ チトセ
- 出版者
- 日本女性学研究会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.12-15, 2018 (Released:2019-01-22)
- 参考文献数
- 1
35 0 0 0 OA 日本における売春防止法と婦人保護事業の見直しをめぐって
- 著者
- 河嶋 静代
- 出版者
- 日本女性学研究会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.16-20, 2018 (Released:2019-01-22)
- 参考文献数
- 12
- 著者
- 武子 愛 児島 亜紀子
- 出版者
- 日本女性学研究会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.61-79, 2023-12-16 (Released:2023-12-16)
- 参考文献数
- 24
軽度の知的障害がある女性たちの性産業従事に関するこれまでの言説の多くは、彼女たちを性搾取の被害者として捉えるものであった。本研究ではその捉え直しを行うべく、性産業従事経験と婦人保護施設の入所経験があり、かつ軽度の知的障害のある女性たち2名に聞き取り調査を行った。分析枠組みとして反抑圧アプローチ(AOP)における抑圧と抵抗の概念を用いた。結果、彼女たちにとって性産業従事は、周辺化・無力化されにくい場所であり、抑圧に対して抵抗することができる、主体的な行動を発揮しやすい場所であることが明らかになった。
33 0 0 0 OA <ポルノグラフィ>批判とポルノグラフィを消費する経験との間で
- 著者
- 守 如子
- 出版者
- 日本女性学研究会「女性学年報」編集委員会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.168-182, 1999-11-25
- 著者
- 遠山 日出也
- 出版者
- 日本女性学研究会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.53-74, 2022-12-16 (Released:2022-12-16)
- 参考文献数
- 83
ダイアン・グッドマンは、マジョリティがマイノリティ差別に反対する動機として、マイノリティへの「共感(エンパシー)」、「道徳的原則、宗教的価値観」、「自己利益」の3つを挙げ、それぞれを育成すべきことを説いている。本稿は、そのうち、女性解放の男性にとっての「自己利益」を、ジェンダーによる男性特有の被抑圧性からの解放という点にとどまらず、広く「ある社会における女性解放の程度はその社会の一般的解放の尺度である」(シャルル・フーリエ)という点に見出し、その具体的状況やメカニズムについて考察する。本稿は、フーリエの言う「社会の一般的解放」を、家族(=家内領域と公共領域の分離)や国家を乗り越えて、個々人の権利を社会全体で支えあう社会の実現であると捉え、そのために不可欠である女性解放の男性にとっての利益について、主に次の5つの角度から考察する。(1)公共/男性領域における女性の権利獲得と男性との関係、(2)女性が家内領域で担ってきた再生産活動の有償化や周縁的位置づけからの脱却と男性との関係、(3)「家族」という単位を乗り越えることと男性との関係、(4)女性解放と男性マイノリティとの関係、女性マイノリティの解放と男性との関係、(5)女性解放が、以上とは直接には関係しない点を含めて資本主義的抑圧全般からの解放に寄与することと男性との関係、である。以上のように広くトータルに女性解放の男性にとっての利益を捉えることは、女性解放を、たとえ男性特権を喪失しても実現すべきものとして理解することにつながる。本稿は、女性たちの運動が男性にとっても抑圧的な状況の緩和に結びついた具体的事例も挙げ、それらをより強めるには、女性の動きに男性の側からも呼応する必要があることも述べる。
16 0 0 0 OA 20世紀前半の日本における薙刀教育の女性化
- 著者
- ベレック クロエ
- 出版者
- 日本女性学研究会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.63-86, 2020 (Released:2020-12-19)
- 参考文献数
- 21
薙刀(なぎなた)とは、本来長い柄の先に反り返った長い刃をつけた武器である。20世紀半ばまでは学校教育制度外における武術流派の道場で、男性のみならず女性にも薙刀の稽古が続行されたが、1910年に師範学校の女子生徒を対象に課外活動として認められた薙刀は、やがて高等女学校・女子実業学校へと広がった。それは、第二次世界大戦の終結後、GHQの指令により学校での武道教育が廃止されるまで続いた。 20世紀前半に女子教育の領域で普及した薙刀は、ジェンダーに関する新たな問題を提起している。薙刀は、相手を攻撃し、戦うための武器である。「武器」・「攻撃」・「戦う」という言葉で表現されることは、社会的には「男性らしい」と見なされているものである。にもかかわらず、薙刀は女子教育においていかなる理由で採用されたのだろうか。そして、学校教育では、社会や文化における男や女に対する期待と規範が教えられ、体育の教育も「女らしい」「男らしい」という期待に沿いながら行われている。そこで本論文では、20世紀前半の日本の薙刀教育において、「女性らしさ」に対する社会の期待の変化がどのように示されていたかを明らかにする。 当時の女子生徒向けの薙刀教本では、女性らしい健康な身体に備わった女性の優美さと、薙刀との関連性がよく指摘され、薙刀教育は女子の「女性らしさ」を育成しなければならないとされた。そして、薙刀教本では、薙刀と関係がある女性の例をよく取り上げることで、女子教育と薙刀の歴史的関係を強調し、女子向け教育として薙刀を正当化するとともに、薙刀を女性らしいものにした。 20世紀前半において学校教育に導入された武道の中では、薙刀だけが女子のみを対象とするものであった。薙刀を女子教育に採用することによって、女子の武道は男子の武道と差異化された。薙刀は女子武道を代表するものとされ、それによって男子との相違が強調されたのである。このように、薙刀を女子のみの武道として設定することによって、薙刀は女性化されたのであった。
- 著者
- 坪井 優子
- 出版者
- 日本女性学研究会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.3-24, 2022-12-16 (Released:2022-12-16)
- 参考文献数
- 30
本稿では、戦後日本においていけばなを稽古した既婚女性たちに焦点を当て、趣味としていけばなを実践した女性稽古者たちが、主婦という立場で家庭生活を担うことと家の外で社会参加することをどのように主体的に実践し、どのように意味づけたか、その意味づけがどのように変遷したかを明らかにする。具体的には1955年から1973年までの期間、兵庫県いけばな協会が発行する会員誌『いけばな兵庫』に掲載された稽古者たちの投稿を分析した。 女性稽古者たちは当初、いけばなを稽古する目的を明るい家庭生活のためだと語り、投稿からは主婦として家庭生活を担っている様子がうかがわれた。しかし1963年以降、彼女たちはいけばなの意義を家庭生活ではなく自己や社会と結びつけ、そこで培った縁の価値を語るようになっていく。 この変化の要因として、女性稽古者たちの投稿に頻繁に登場した稽古仲間や先生との交流によって築かれた、家族以外との紐帯があげられる。彼女たちは稽古以外にも、協会が主催する研修や旅行に参加することで知見を深め、家庭の外で人脈や見聞といった資本を得るとともに、長年の稽古の結果として免状や花展への出品といった資本も獲得した。こうした家の外での経験や、家元制度のなかで実践される長年の稽古の積み重ねによってこそ獲得できる紐帯は、主婦である女性稽古者たちに自信を与え、やがては自己実現へと導いてくれる大きな要因のひとつだったといえよう。
- 著者
- 牧野 良成
- 出版者
- 日本女性学研究会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.41-62, 2020 (Released:2020-12-19)
- 参考文献数
- 57
フェミニズムの歴史が語られるとき、〈波wave〉という概念に頼った区分の方法がしばしば用いられる。典型的には、1960年代なかばから70年代初頭にかけて運動が高まりをみせた時期が、19世紀なかばから20世紀初頭にかけての〈第一波〉に次ぐ〈第二波second wave〉と捉えられる。遅くとも1960年代アメリカにさかのぼるこうした用法については、〈第三波〉なる自称が現われた90年代以降の英語圏では、批判的な検討が始まっている。同時代の運動の昂揚とともに運動史への関心もまた高まる現在、日本語圏においても〈波〉概念が帯びる文脈性を踏まえたうえで歴史記述の方向性を探る必要は増していると思われる。そこで本稿では、1970年代以降のフェミニズムの歴史が語られるとき、日本語圏では〈波〉という区分がいかにして用いられてきたかを検証する。注目すべきは、70年代にはアメリカなど諸外国の動向を紹介する文脈で用いられていた〈波〉概念が、80年代なかばには日本語圏の動向をも指し示すものへと転じたことである。ここからは、女性学‐フェミニズムの観点を打ち立てるべく奮闘した者たちが、地域や争点を異にする同時代の運動や先行する運動をにらみながら選び取った、自己呈示と戦略とでも言うべきものが読み取れる。
- 著者
- 遠山 日出也
- 出版者
- 日本女性学研究会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.40-60, 2023-12-16 (Released:2023-12-16)
- 参考文献数
- 62
筆者はこれまで、近代家族は、その基底的特徴である家内領域と公共領域の分離を高い段階で再び統一することによって乗り越えられると論じてきた。「高い段階」と言う理由は、前近代の共同体に戻るのではなく、自立した個人の家族や国家を超えた相互扶助を実現するからである。 公私の両領域の高い段階での統一は、新自由主義がもたらす社会的変化とは方向が逆である。しかし、ナンシー・フレイザーは、第二波フェミニズムと新自由主義の親和性を指摘している。筆者自身も、日本の左派とフェミニズムの一部にある程度そうした傾向が見られること、その背景には、資本主義と家父長制との二元論的理解があることを述べてきた。本稿の第1章では、近代家族論の専門家でありながら「官製婚活」を肯定する山田昌弘にもまたそうした傾向があることを論じる。また、江原由美子のフレイザーに対する応答に関しても、フレイザーの持つ資本主義批判の視点をより生かすことによって、より的確なものになることなどを述べる。 また、家内領域と公共領域の分離の乗り越えは、高い段階の「統一」である必要がある。すなわち、平等主義規範が家族の壁を打ち破るだけでなく、相互扶助を家族や国家の枠を超えて広げることが必要である。さらにそれを人類の枠を超えて「自然」にまで広げるためにはエコロジカル・フェミニズムが重要だが、エコフェミは現在の日本では発展していない。本稿の第2章では、その原因を1980年代のエコフェミ論争に遡って検討し、当時、青木やよひを批判した側が、青木のエコフェミの独自の意義を捉えていなかったことを述べる。さらに、その後のエコフェミの発展も踏まえて、エコフェミを含めた、女性が先覚的におこなってきた社会的再生産のための運動は、近代家族の乗り越えやフェミニズムにとって独自の意味があることやその発展のプロセスを示す。 今後の課題は、一部の左派やフェミニズムにおける新自由主義との親和性の問題とエコフェミの立ち遅れの問題とがどのように関連しているかについて、より具体的に明らかにし、それを通じて、今後のジェンダーをめぐる理論と運動のあり方を考えることである。
- 著者
- 染谷 泰代
- 出版者
- 日本女性学研究会「女性学年報」編集委員会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- no.25, pp.1-19, 2004
- 著者
- 北村 夏実
- 出版者
- 日本女性学研究会「女性学年報」編集委員会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- no.31, pp.32-55, 2010
12 0 0 0 OA 発達障害とジェンダー/フェミニズム ふたつの当事者性から考えてみる現在地
- 著者
- 松本 澄子
- 出版者
- 日本女性学研究会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.3-26, 2021 (Released:2021-12-28)
- 参考文献数
- 60
わたしには、発達障害のある子どもが2人いる。わたしは20代でフェミニズムや女性学を知り、1978年に日本女性学研究会に入会した。その後、おぼろげながらも「フェミニズム」というアイデンティティがあって、そこに、30代で、(ある意味いやおうのない)「障害のある子どもの母親」というアイデンティティが発生した。子育ての過程や、「親の会」や学校など地域で活動する中で、「発達障害のある当事者」である子どもの代弁者であること、かつ「親当事者」であることのいろいろな意味での経験知を獲得し、発言・発信もしてきた。そして発達障害とフェミニズムやジェンダーとの接点を模索し、「女性と発達障害」について考える中で「発達障害のある女性」という領域にもジェンダーの視点を向けるようにもなった。 本稿では「発達障害とジェンダー」に関わる問題意識について、「女性」という当事者性からは「発達障害のある女性とジェンダー/フェミニズム」に焦点を当て、また「わたし=親当事者」ということからは「発達障害のある子どもの子育てとジェンダー/フェミニズム」に焦点を当てて、わたしの現在地としての考察を試みている。特に、フェミニズムの「自己選択・自己決定」「自己実現」「ジェンダー平等」という理念と、「発達障害のある女性当事者」及び「障害のある子どもの母親当事者」の葛藤(渦巻きの渦中にあること)を言語化してみることで、次の「何か」、「わたし」からのフェミニズム=女性「解放」とは「何か」をさぐるきっかけとしたい。
12 0 0 0 OA 書評 田中亜以子『男たち/女たちの恋愛:近代日本の「自己」とジェンダー』
- 著者
- 前川 直哉
- 出版者
- 日本女性学研究会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.52-56, 2019 (Released:2019-12-20)