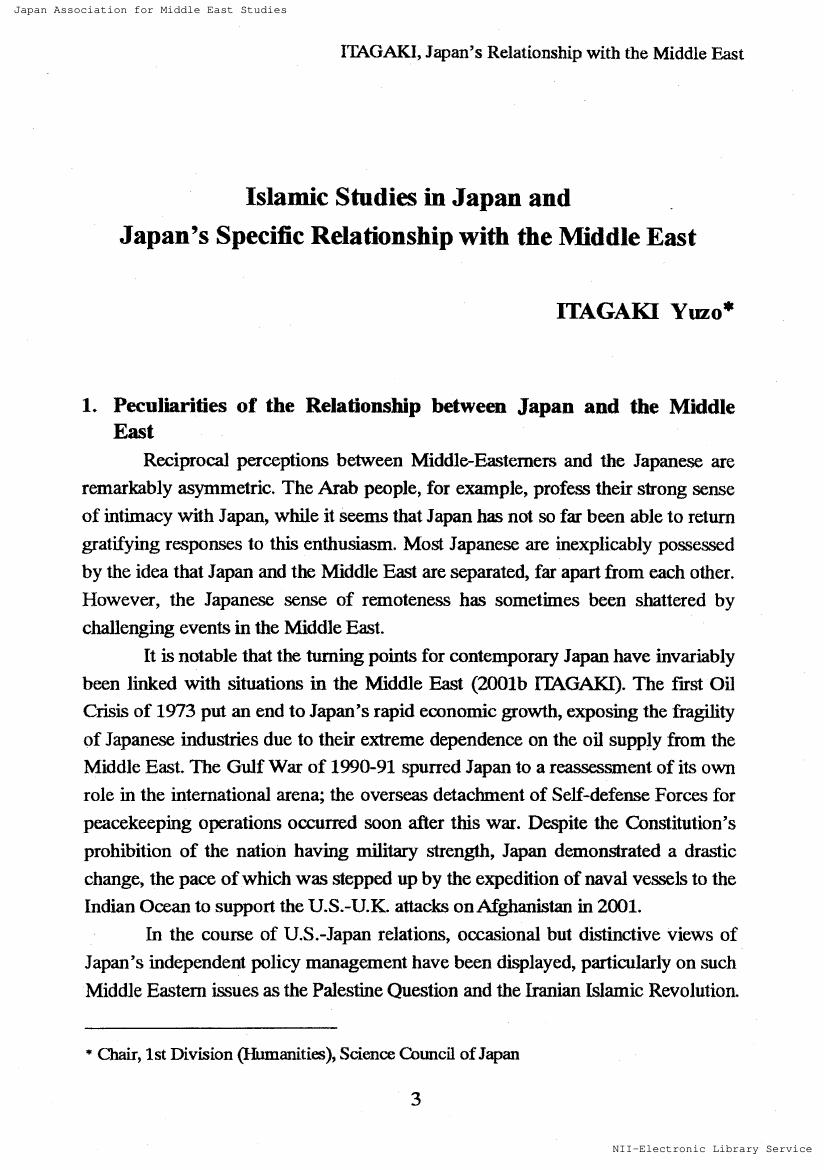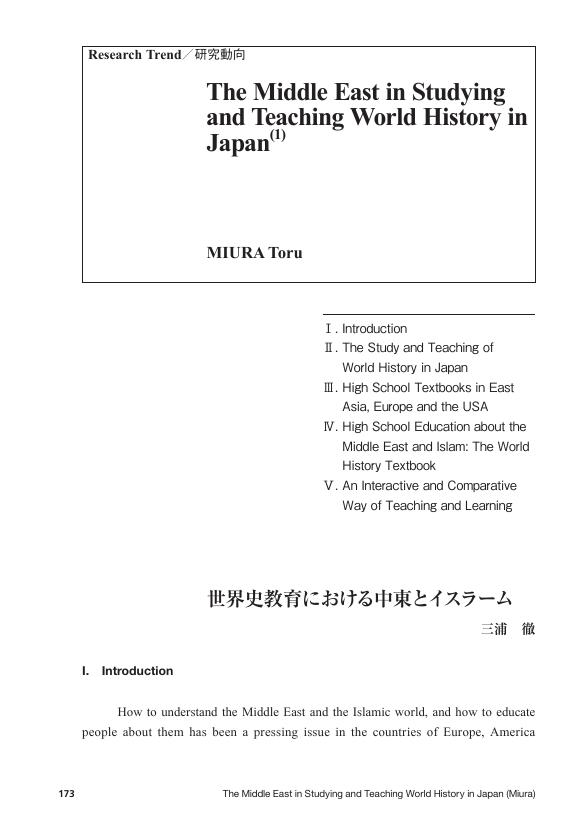12 0 0 0 OA The Dynamics of Nomad-Sedentary Conflict in Afghanistan: The Kuchi-Hazara Confrontation in Hazarajat
- 著者
- Abbas FARASOO
- 出版者
- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.1-37, 2017-07-15 (Released:2018-08-31)
In recent years, disputes between mainly Pashtun nomadic tribes and sedentary Hazaras in the provinces of Wardak, Ghazni and Bamyan have escalated into an organized armed conflict with significant national political repercussions. This article seeks to explain why, since 2001, this particular local conflict, originating in the central part of the country, has gained national and political significance. It uses a relational theory to explain dynamics of the conflict and argues that it intensified and gained significant political dimensions as a result of interaction of cognitive, relational and environmental mechanisms, most notably social boundary activation, memory mobilization, brokerage operation, and sharpening claim-making performances over resources. Relational mechanisms explain the dynamics of the violent nomad-sedentary conflict at the local level and its intensification at the national level in the context of political contention based on ethnic appeals. Furthermore, the article shows that nomad-sedentary conflict in Afghanistan is not only a conflict over resources. Rather, it has a complex historical dimension. Consequently, explanation of the conflict requires greater attention to be paid on historical processes of contentious interactions in the country. The historical dimensions of contention show that the nomad-sedentary conflict is rooted in state formation processes and still remains a contentious enigma. Therefore, this article, challenges resource-based analysis, and contends that a broad historical analysis of the conflict shows historical processes of state formation in Afghanistan in which the nomad-sedentary conflict is rooted.
7 0 0 0 OA イラン石油国有化運動期のテヘラン・バーザールにおける抗議活動
- 著者
- 貫井 万里
- 出版者
- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.1-34, 2012-07-15 (Released:2018-03-30)
1951年にイラン政府は、20世紀初頭以来、イギリス系アングロ・イラニアン石油会社(AIOC)の支配下にあった石油産業の国有化を宣言した。石油国有化を目指して一般民衆をも巻き込んでイラン全土で展開した、このナショナリズム運動は、石油国有化運動と呼ばれている。運動を率いたモサッデク博士をリーダーとする国民戦線は、石油産業の国有化を通して、外国の影響力を排除し、国家の独立と民主主義制度の確立の実現を主張し、多くの一般民衆を惹きつけ、運動に動員することに成功した。中でも、バーザーリーと呼ばれる、イランの伝統的商業区域、バーザールで働く商人や職人たちが、この運動に積極的に係わったことが多くの先行研究で指摘されてきた。先行研究を分類すると、バーザーリーの石油国有化運動参加の動機として、宗教指導者との密接な関係やバーザーリーの敬虔さを理由に宗教的要因を重視する説(宗教要因説)と、功利主義的な立場からバーザーリー自身による経済的利益の追求に注目する説(経済要因説)の二つに分けることができる。しかし、従来の説は、バーザール内の多様性を十分に考慮しておらず、また、バーザーリーの政治活動に関する具体的なデータに基づいて分析されていないという問題点を指摘することができる。従って、本稿は、バーザールの中でも、経済的にも政治的にも重要性の高いテヘラン・バーザールで働く人々(バーザーリー)に焦点をあて、上記の二説を実証的に検討することを目的とする。具体的には、ペルシア語紙『エッテラーアートEṭṭelā‘āt』新聞及び『バーフタレ・エムルーズBākhtar-e Emrūz』新聞から、モサッデク政権期(1951年4月~1953年8月)中にバーザーリーの参加した抗議活動を収集し、抗議活動の主催者及び共催者、クレイム(抗議イベントの中で唱えられた主張)に類型化した。収集された二つのデータセット、(1)バーザールの閉鎖(24件)、(2)バーザーリーの参加した抗議活動(321件)は、それぞれ第2節と第3節で考察し、クレイムと抗議活動が生じた際のイランの政治・社会状況を手掛かりに、バーザーリーによる抗議活動参加の動機を探究した。データ分析の結果、テヘラン・バーザールの多数派を構成する「商人・アスナーフ・職人連盟 Jāme‘e-ye Bāzargānān va Aṣnāf va Pīshevarān、アスナーフ連盟と略」は、テヘラン・バーザール閉鎖の権限を持ち、自律的な政治アクターであったことが判明した。同組織は、目的実現のための一手段として、宗教的権威を使用することもあったが、石油国有化運動の二大リーダー、世俗的政治家のモサッデク首相と宗教指導者のカーシャーニー師の対立が深まると、国民戦線の世俗政党と協力してモサッデク政権を最後まで支援し続けた。また、バーザーリーの参加した抗議活動の背景には、第二次世界大戦後の貿易自由化策及びパフラヴィー朝の経済政策によって富裕化した貿易商や企業家からなる「アスナーフ連合Etteḥādīya-ye Bāzargānān」と、伝統産業に携わる中小商人・職人からなるアスナーフ連盟の対立関係が浮かびあった。モサッデク政権は、国内産業の保護育成政策によって、中下層のバーザーリーに経済的恩恵のみならず、国政参加の機会をもたらした。政治・経済権益を巡るアスナーフ連盟とアスナーフ連合の主導権争いは、既得権の復活を目指すアスナーフ連合の王党派商人をモサッデク政権打倒工作に深く関与させる結果となった。本研究を通して、これまでの研究では、充分に明らかにされてこなかった石油国有化運動におけるバーザーリーの政治参加の実態を実証的に解明することが可能となろう。
- 著者
- 磯貝 健一
- 出版者
- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.259-282, 2011-07-15 (Released:2018-03-30)
本稿は、2009年に廃止された旧国立ウズベキスタン諸民族文化・美術史博物館所蔵の7通のファトワー文書に依拠しながら、20世紀初頭にサマルカンド州の或るイスラーム法廷に持ち込まれた訴訟の顛末を詳細に跡付け、さらに、革命前の中央アジア・イスラーム法廷で採用された裁判システムにおけるムフティーの役割を解明しようとするものである。現存する中央アジアのファトワー文書の大半は、裁判の進行過程において当事者である原告ないし被告が自己に有利な判決を獲得するために、カーディーに提出したものである。ただし、ファトワー文書は関連する訴状、判決文、ないし、同一の裁判において発行された他のファトワー文書を伴わず、単一の文書として伝存する場合が殆どである。これに対し、本稿で取り扱う7通のファトワー文書は全て同じ裁判の審理過程において提出されたものであり、極めて貴重な事例であるといえる。また、7通の文書の内、3通は原告、残り4通は被告により提出されている。問題の訴訟は、Ustā Mawlām Bīrdīなる人物の相続人数名が、自分達が相続すべき財産を取り戻すため、共同相続人であるUstā Raḥmān Bīrdīを相手取り提起したものである。これらの文書からは、原告・被告の双方が、①既存の裁判の審理中に、被告が原告を相手取って提起した別件の訴訟の有効性、および、②被告による訴訟代理人任命の有効性、の二点において対立していたことが読み取れる。また、最後に提出された文書では、この訴訟が両当事者による和解をもって解決されたはずであるにもかかわらず、被告が一旦成立した和解の破棄を申し立てたことが記録される。これら7通の文書は少なくとも7名以上のムフティーによって作成されたが、内3名のムフティーは原告と被告の双方にファトワーを供給している。このことは、当時のムフティーが、適当な法学説を取捨選択しながらファトワーの内容を依頼者の意向に合致させようとしていたことを物語っている。
- 著者
- 太田 敬子
- 出版者
- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.87-116, 2004-03-31 (Released:2018-03-30)
本稿の目的は、アッバース朝カリフ・マームーンの治世末期に起こった下エジプトのバシュムール地方の反乱に焦点を当てて、アッバース朝支配下のエジプトにおけるキリスト教徒社会の情況を検討し、エジプトにおけるイスラーム化の進行とキリスト教社会の衰退の歴史的展開について一考察を行うことにある。エジプトのキリスト教徒(コプト)社会に対するムスリム政権の統制が本格的に強化され始めたのはウマイヤ朝後半のことと考えられる。その後アッバース朝時代にかけて、政府の徴税強化と徴税官の圧迫に抵抗するコプト反乱が繰り返し記録に現れるようになる。その最後で最大の武力蜂起といわれるのがバシュムール反乱である。第1章では、バシュムール反乱に至る抗租運動の軌跡を辿り、ムスリム支配の強化に伴う抗租運動におけるコプトとアラブ・ムスリムの関係を分析した。第2章ではバシュムール反乱の原因とその経緯、反乱後の状況を史料に基づいて再現し、第3章においてこの時代のコプト社会の状況に関して、コプト社会内部の情況に注目して考察を行った。結論として、この時代に表面化してくるコプト教会と一般信徒との間の軋轢や利害の不一致が、コプト社会の変化と衰退を考察するに際して非常に重要な要因となっていることを検証した。コプト社会の内部変化という観点から、バシュムール反乱はエジプトのイスラーム化において1つの重要な転機であったいうことができると考えられる。
4 0 0 0 OA ファフルッディーン・ラーズィーと哲学としてのオカルト諸学
- 著者
- 大渕 久志
- 出版者
- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.1-33, 2018-07-15 (Released:2019-10-01)
イスラームの哲学的神学(philosophical theology)についてイブン・スィーナー(アヴィセンナ、1037年没)の影響力が一般的に強調されるが、哲学的神学形成の立役者とされるファフルッディーン・ラーズィー(1210年没)は、イブン・スィーナーおよびアブルバラカート・バグダーディー(1152年没)の哲学のみならず、占星術や魔術のようなオカルト諸学にも造詣が深かった。これまでの研究は、これらオカルト諸学が自然学系の哲学として当時見なされていたにもかかわらず、ラーズィーの神学において占めるその価値を評価してこなかった。本論文は13世紀初頭における哲学的神学の実態を明らかにする研究の一部として、オカルト諸学を含む哲学がラーズィーの神学へどのように摂取されているかを考察する。第Ⅰ節の序論に続き、第Ⅱ節において彼の神学著作を時系列に沿って精査し、彼自身がどのような思想体系を哲学と認め、実際に受容したのかを検討する。すでに知られているように、ラーズィーはシャフラスターニー(1153年没)がその代表作『諸信条と諸宗教』(al-Milal wa-l-niḥal)においてサービア教徒内の分派、霊魂崇拝者のものとして記述していた宇宙論を、預言者を天使の下位に位置づける「哲学者」の教説として批判していた。霊魂崇拝者はヘルメスという神話的存在の権威を認め、占星術や宇宙霊魂を仲介とした魔術などのオカルト諸学を実践していたが、彼らの宇宙論をラーズィーが最晩年の『神学における崇高な課題』(al-Maṭālib al-‘āliya min ‘ilm al-ilāhī)では一転して自らの学説として採用している事実を筆者は新しく指摘する。第Ⅲ節では、ラーズィーが受容したところの「哲学者」すなわち霊魂崇拝者の由来を問う。近年の研究が明らかにしているように、サービア教徒と関連づけられてきたヘルメスという神話的人物が、シャフラスターニーを端緒としてイスラーム思想に積極的に取り入れられた。ラーズィーもこのアラビア・ヘルメス主義の興隆という時代に活動していた点を筆者は確認し、彼が認めた「哲学者」はこうした秘教的由来を有していることを指摘する。最後に第Ⅳ節では『神学における崇高な課題』をさらに読み、先の霊魂崇拝者の宇宙論のみならず、占星術や関連する天体魔術(‘ilm al-ṭilasmāt)などオカルト諸学の理論を神学へ受容していること、また彼がここで天体魔術師(aṣḥāb al-ṭilasmāt)を「古代の哲学者」と呼びあらわしていることを示す。ラーズィーは天体魔術師の思想を彼自身の神学へと受容した結果としてイブン・スィーナーと対照的に、流出(fayḍ)ではなく痕跡(athar)を鍵概念にする普遍霊魂論を採用し、人間のあいだの種(naw‘)を認める。霊魂崇拝者と天体魔術師はともにヘルメスの権威を認め、宇宙霊魂を仲介として地上に魔術的事象を実現することができると信じる。ラーズィーが両者を同一視していたか否かは断言できないが、彼はアヴィセンナ哲学の構造・概念をある程度保持しながらも代替となるべきものとして、オカルト諸学と通常呼ばれるような「哲学」を「神学」に統合したのである。
3 0 0 0 OA ある日本人アジア主義者のイスラム観:大川周明の場合
- 著者
- 臼杵 陽
- 出版者
- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.59-84, 2013-01-05 (Released:2018-03-30)
本論文は大川周明の生涯を通して彼のイスラームへの関心の変化を論じる。大川は右翼のアジア主義者として知られているが、イスラーム研究者でもあった。彼は東京帝大時代スーフィズムに関心をもった。しかし、彼は 1913年、内的志向の精神的イスラームから外的志向の政治的イスラームその関心を転換させた。同時期、「コーランか剣か」を預言者ムハンマドの好戦的表現だと考えていた。しかし、オスマン帝国崩壊後はイスラームに関して大川は沈黙を保った。約20年後の1942年、大川は著名な『回教概論』を刊行した。同書は読者の期待に反して、日本の戦争宣伝を意図するものではなかった。同書は日本的オリエンタリストの観点から理念型的なイスラームとイスラーム帝国絶頂期の理想化されたイスラーム国家の姿を描いたものだったからである。戦後、東京裁判の被告となったが精神疾患のため免責された。大川は松沢病院でクルアーンの翻訳を行なう一方、完全な人格としての預言者ムハンマドへの崇敬を通してイスラームへの関心を取り戻した。晩年の大川は開祖を通してキリスト教、イスラーム、仏教などの諸宗教を理解する境地に達したのである。
- 著者
- Yuzo ITAGAKI
- 出版者
- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.3-16, 2002-03-31 (Released:2018-03-30)
- 著者
- 岩本 佳子
- 出版者
- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.69-95, 2017-01-15 (Released:2018-06-01)
本稿は、枢機勅令簿やワクフ総局所蔵台帳といった、遊牧民の定住化に関して発布された命令の記録を含むオスマン語公文書史料を基本史料として、17世紀末から18世紀初頭にかけてのクルド、テュルク系遊牧民のシリア北部、特にラッカ地域への大規模定住化政策を分析した研究である。 17世紀末の軍事および財政改革の中で、クルドやテュルク系遊牧民は、ラッカ北部地域を中心とした地域の農地開発のために定住化させられるようになった。その背景には、この時期に、遊牧民の夏営地・冬営地間の季節移動そのものを問題視し、農耕民として定住化させることを是とするように、遊牧民に対する認識が変化したことがあった。この点で、17-18世紀は、オスマン朝における対遊牧民政策の転換点であると見なすことができる。しかしながら、全ての遊牧民が強制的に定住化させられたわけではなく、イスタンブルに位置するウスキュダル地区のヴァーリデ・スルタン・モスクのワクフに属する遊牧民や自発的に定住化した遊牧民が、強制的な定住から免除される事例も存在した。 遊牧民への定住化政策においては、主な定住先はシリア北部、特にラッカ一帯であり、次点がキプロス島であった。また定住地から逃散して叛徒化した諸部族をラッカへ定住化させる、数度にわたって逃散や叛徒化を繰り返した部族に定住化を命じるなど、処罰としての定住化命令という側面も見られた。一度逃散した部族に対しても、以前に定住を命じた土地と同じ場所へ再度の定住することを命令し、命令に従わない部族を武力で制圧するなど、元の命令を実行することに固執する傾向が強くあった。このことは逃散と再定住化というパターンの固定化へとつながっていった。そのため、17世紀末から18世紀にかけて相次いだ遊牧民の定住化令は、遊牧民の逃散や叛徒化による治安の悪化に対する有効な手立てではなく、むしろ、逃散や山賊の固定化をもたらし、さらには、シリア北部のみならずアナトリアにも及ぶ地域の変化の一因にもなりえていたのである。
2 0 0 0 OA 環境意識から見る現代イランの社会文化的様相
- 著者
- 阿部 哲
- 出版者
- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.35-62, 2018-07-15 (Released:2019-10-01)
本稿は、イラン都市部における環境問題に焦点を当て、近年同国で現出している環境をめぐる独自の環境言説およびその実践について人類学的考察を行うものである。具体的には、イランにおける近年の環境問題の傾向を明らかにするとともに、イラン人の環境問題へ対する多様なアプローチを検証することにより、現代イランの社会文化的様相を描き出すことを試みる。 イランはイスラーム革命(1979年)以後、米国との国交断絶、イラン・イラク戦争、欧米主導の経済制裁等により経済基盤を失い、1990年代以降は、経済の復興に傾注してきた。制裁下で、イラン政府は石油産業をはじめ、農業や製造業分野へ積極的な投資を行いながら一定の経済成長をおさめ、中東における軍事経済大国の地位を確立するに至った。経済発展は一方で、イラン国内でさまざまな二次的弊害を引き起こし、国民生活に多大な影響を及ぼしている。とりわけ、大気汚染や土壌汚染をはじめとする環境問題は近年深刻化の一途をたどり、環境対策の重要性が年々増している。 イラン政府による環境政策では、科学的手法で環境問題の原因を特定する環境科学が全国的に展開され、科学的アプローチが広く適用、実践されている。環境科学を通して拡張しているこの科学的パラダイムの興起は、イランにおける西洋近代科学知識の普及を意味する。特徴的であるのは、近代西洋の科学的パラダイムが同国の文化歴史的脈絡の中で独自に「翻訳(translation)」されている点である。すなわち、イラン人が環境問題に取り組む上で、科学的パラダイムとともに他の概念枠に基づいた環境アプローチが見られるのである。ナショナリスティックな情操を媒介させた環境言説や、昨今宗教指導者層によって奨励され始めたイスラーム教義に根ざした環境言説は、イランの環境運動における同国の文化歴史的脈絡をとくに反映させている。現代イランの環境問題をめぐる人類学的視座による考察は、同国の社会文化についての知見を深める上で示唆を与えるものである。
1 0 0 0 OA 世界史教育における中東とイスラーム
- 著者
- 三浦 徹
- 出版者
- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.173-197, 2013-01-05 (Released:2018-03-30)
- 著者
- Akira USUKI
- 出版者
- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.195-214, 2008-01-28 (Released:2018-03-30)
This paper examines the roles played by Hajime Kobayashi (1904-1963) in Middle Eastern and Islamic studies in Japan. Although he is one of the forgotten Japanese scholars in this academic field today, he can be considered as a good example of the researchers who represent the continuation of the studies before and after World War II. Kobayashi was one of those who engaged in the establishment of the first academic research institution of Islamic studies (Kaikyoken Kenkyujo) in Japan in 1938. He was also appointed as professor at the preparatory Army Academy of the Imperial Army before World War II. After the war, Kobayashi exerted himself in 1956 for the establishment of Middle East Research Institute of Japan (Chuto Chosakai) which was an auxiliary organization of the Japanese Ministry of Foreign Affairs. This paper concludes that the reason why Kobayashi has been forgotten might be Kobayashi's versatility with the times; Kobayashi was not only a researcher but also a coordinator of Middle Eastern and Islamic studies in Japan before and after the war. In other words, he committed to the war or politics or even collaborated with the military establishment during the war as an ardent nationalist during the war.
- 著者
- ステケヴィチ ヤロスラヴ
- 出版者
- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.145-169, 2014-01-15 (Released:2018-03-30)
20世紀のアラブモダニズムと何世紀にもわたる古典アラブ詩の伝統との複雑な関係を提示する試みの1つとして、本研究は2人のモダニスト詩人による、同一の表題タルディイヤ(狩猟詩)を持つアラブ詩を考察する。2人とは、アラブ自由詩の草分けともいえる、イラク人のアブド・アルワッハーブ・アルバヤーティー(1926-1999)とエジプト人のアフマド・アブド・アルムゥティー・ヒジャージー(1935-)である。両詩人は詩をタルディイヤと名付けることによって、その文学的な決まり事や形式的・主題的な期待とともに、同名の古典アラブ詩の様式(genre)を喚び起こしている。第1部では、まず序論において狩猟の主題になくてはならない背景を提示する。初期(西暦6~7世紀)の古典アラブ詩(カシーダ)において狩猟は主題的に2つの主要な役割を持つ。1つ目は最初の移行的な旅の部分で、そこでは獲物―オリックスあるいはオナガー―が主人公であり、狩人と彼の猟犬は必死で獲物を追うものの、逃がしてしまうという詩の伝統である。2つ目は馬上の勇敢な追跡を祝う最終の部分である。短編の抒情的様式(genre)である狩猟詩(タルディイヤ)が初めて現れたのはウマイヤ期(西暦8世紀初頭)の終わりであり、それが形式的、審美的頂点に達したのはアッバース朝最盛期(西暦9~10世紀)のことであった。主要部分において成功をともなう英雄的狩猟がカリフ時代の宮廷アラブ・イスラーム文化へと形を変えたのである。そこでは、狩猟遠征の装具や狩猟に関わる動物―猟犬、ハヤブサ、ヒョウ、そして獲物―は、ガゼル、野ウサギ、キツネ、サケイなどまで含まれる。数世紀の間、忘れられた後に、狩猟詩は2人のモダニストアラブ自由詩人、アルバヤーティーとヒジャージーによってよみがえったのである。第2部は、アルバヤーティーによる1966年の革新的なモダニスト詩集Alladhī Ya’tī wa lā Ya’tī〔来たりて来たらざる者〕に収録されているタルディイヤのテクストとその翻訳で始まる。この第2部で主張することは、詩人が、古典的伝統に則った様式(genre)と形式に束縛される脚韻と韻律を備えた抒情詩を、獲物である野ウサギの劇的で悲劇的なイメージの形式的に自由な探求へと変容させたということである。この野ウサギのイメージは近代に生きる者の政治的、文化的苦境へのメタフォーである。このメタフォーを通して、アルバヤーティーはヘミングウェイからガルシア・ロルカまでの20世紀モダニズムを特徴づける、これと同様の近代における実存的悲劇の表現を成し遂げたのである。第3部では、自ら課したパリでの異郷生活を送る間に、ヒジャージーが1979年に作詩したタルディイヤを考察する。このタルディイヤは1989年の詩集Ashjār al-Isman〔セメントの木々〕の一部として、al-Bārīsiyyāt〔パリの詩〕に収録された。詩のテクストと翻訳で始まる第3部は、伝統的狩猟詩に表された身を切るように辛い抒情を、詩人がいかに自分の政治的国外追放と詩的着想にもとづいた個人的経験の表現へと変容させているかを提示している。巧みに逃れるがゆえに最後まで捕らえきれないサケイを止むことなく追うという伝統的狩猟モティーフを用いながら、ヒジャージーは国外追放者として、そして詩人としての実存的疎外感を映す夢物語を作り上げたのである。アルバヤーティーのタルディイヤは、追い回され、迫害される獲物が詩人として近代人としてのメタフォーとなっている。一方で、ヒジャージーのタルディイヤではメタフォーが逆である。話し手すなわち狩人が詩人を表し、サケイすなわち獲物が手に入れることのできない政治的、詩的な夢のメタフォーである。
1 0 0 0 OA 中国ムスリムに対するキリスト教宣教
- 著者
- 松本 ますみ
- 出版者
- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.147-171, 2005-09-30 (Released:2018-03-30)
中国ムスリムに対するキリスト教宣教は、19-20世紀半ば、福音主義宣教会の中では大きな課題となった。中国のムスリム人口は当時3000万人とも言われ、インドについで第2位といわれた。植民地主義の時代、他地域のムスリムの大多数が西欧の支配下、すなわち、「キリスト教徒の支配者」の下にあったが、「異教徒」の政権下の中国ムスリムは、福音から最も遠いという点において「問題」であると考えられた。植民地主義がピークに達した1910年のエジンバラ世界宣教会議以降、中国ムスリムに対する宣教も本格化、さまざまなパンフレット、宣伝文書、ポスターの作成が行なわれた。それに対し、ムスリム側も、論駁書、啓蒙書の発行、学校設立などイスラーム復興に着手して対抗を図った。ただ、両者の対立が深刻化しなかったのは、多文化多宗教の共存を旨とする中国ムスリム側の伝統による所が大きい。また、宣教師にもイスラームに深い共感を示した者が存在したことも大きい。
- 著者
- 臼杵 陽
- 出版者
- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.1-35, 1994-03-31 (Released:2018-03-30)
本論は,1950年から1951年の2年間にほとんどがイスラエルに移民したイラク・ユダヤ人に関して,1941年にバグダードで起こったファルフードと呼ばれているユダヤ人襲撃事件,ファルフードが契機となって活発化したイラクにおけるシオニスト地下運動,共産主義者とシオニストとの相互関係,そしてイラクからイスラエルへのユダヤ人大規模移民の研究動向を整理する試みである。議論の際に依拠するのは,主にイスラエルにおけるヘブライ語および英語による最近の研究成果であるが,必要に応じてアラビア語による研究にも言及することになろう。イスラエル人研究者(圧倒的にイラク出身者)による研究および記述は概して,シオニズムのイデオロギーを前提として議論を展開する。すなわち,ユダヤ人はファルフードを契機としてイラク社会への同化は不可能となり,ファルフードのような「ポグロム」の再発に対する防衛措置としてシオニスト地下運動が展開された。しかし,パレスチナ問題の展開に対応してイラク政府がユダヤ人に対して抑圧的な政策をとったため,結局,ユダヤ人はイスラエルへの移民の道を選ばざるを得なくなったという説明である。ところが,約12万人のユダヤ人が移民せざるをえなくなった事態はイラクのユダヤ人コミュニティ内部を見ただけでもより複雑な過程を取ったといえる。そこで,大量移民への過程の一端を明らかにするため,シオニスト地下運動のみならず,ユダヤ人共産主義者とシオニストの関係をも検討する。シオニズム以上に若いユダヤ人知識人を動員することのできた共産主義運動はシオニストが提唱するような,移民によってユダヤ人の直面する問題を解決することには反対し,イラク社会への同化による問題解決の方向性を堅持した。しかし,ソ連による国連パレスチナ分割決議への支持(1947年11月)を契機に共産主義者とシオニストとの協力関係の土壌が生まれた。結局,共産主義者はイスラエル国家設立(1948年5月)を機にシオニストと協力してイラクのユダヤ人コミュニティの防衛に当たり,そのほとんどがイスラエルに移民した。イラク社会への同化の立場は伝統的なユダヤ人指導者屑にも共通した考え方であった。しかし1950年3月のイラク政府による国籍剥奪法の制定を契機として,多くのユダヤ人が出国登録をした。その最中,ユダヤ人に対する爆弾爆発事件が起こった。この事件はユダヤ人の出国登録を加速度的に促進することになったが,本論の最終章でこの事件をめぐる議論を紹介して,イラク・ユダヤ人におけるシオニズム運動,共産主義,そして大量移民に関する今後の研究課題を提示したい。巻末に,今後の研究の便宜のため,イラク・ユダヤ人のシオニズム運動,共産主義運動,および大量移民に関するヘブライ語,アラビア語,英語による主要な関係文献のリスト(論文も含む)を,筆者が実際に入手しえた範囲内で付すことにする。
1 0 0 0 OA マフディー・アーミルによる宗派主義国家の理論
- 著者
- 早川 英明
- 出版者
- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.41-69, 2018-01-15 (Released:2019-03-15)
本稿は、レバノンのマルクス主義思想家マフディー・アーミル(Mahdī ‘Āmil, 1936-1987)による宗派主義に関する理論を、アーミルがいかに国家というものを捉え、その宗派主義との関係を論じたかに特に注意しながら辿る。その上で、レバノンの左派における「世俗主義」の意味を巡る議論、およびアラブ知識人によるアラブ文化をめぐる議論の文脈に位置付けることで、新たな示唆を得ることを目指す。 アーミルはレバノン共産党の重要な知識人として主に1970-1980年代に活躍した。1975年にレバノン内戦が勃発し、共産党も宗派主義廃絶を掲げて参戦すると、アーミルは宗派主義や内戦について論じる著作を多く発表する。 アーミルは宗派主義を「ブルジョアジーが階級支配を実践する政治体制の特定の歴史的形態」、宗派を「従属諸階級と支配階級を結びつける政治的関係」と定義する。彼によれば、宗派主義はブルジョワ国家の体制であるから、宗派主義廃絶は社会主義への移行によってしかあり得ない。従って、内戦において宗派主義廃絶を掲げ戦った共産党の行動も、反ブルジョワ国家的行動と理解される。アーミルはまた、レバノンの資本主義の発展の遅れによって宗派主義が旧時代から残存したという見方を否定し、むしろ、資本主義的な社会構造において、ブルジョワ国家の体制としての機能を果たすことによって存在しているとした。旧時代の遅れた要素と考えられていた宗派主義が、実は近代ブルジョワ国家によって維持されていると主張したのである。 アーミルの宗派主義論を読むことで二つの示唆が得られる。第一に、レバノンの左派の「世俗主義」を、単なる「政治と宗教の分離」という主張ではなく、近代レバノン国家の再編成を目指すものとしても理解できる。これにより、レバノンの左派における「世俗主義」と「宗派主義」「近代」との複雑な関係も認識できるだろう。第二に、多くの現代アラブの思想家によってしばしば「後進的」と捉えられたアラブ地域の文化と、近代以降の国家との関係を批判的に再検討し、「近代」と「文化的遺産」を同時代の互いに絡み合ったものとして捉えるという、現代アラブ思想史におけるアーミルの位置付けを見出すことが出来るだろう。
- 著者
- オットマン エスタ・ティーナ
- 出版者
- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.1-28, 2016-03-15 (Released:2018-03-30)
戦争と暴力が健康に及ぼす影響、とりわけ精神的健康に及ぼす影響については世界保健機構の年次報告書でもしばしば強調されてきた。しかしイスラエル・パレスチナ紛争では、紛争当事者たちは、住民たちが物質的にも精神的にもすこやかに暮らすために必要な政治的・領土的妥協を行うことを延々と拒み続け、紛争は「解決不能な紛争(イントラクタブル・コンフリクト)」と呼ばれるほどに長期化している。そしてこの状況に非当事者たちは当惑状態にあるとも言える。暴力が中東・北アフリカ一帯に広がる現在においては、こうした当惑はいっそう強まっている。公式レベルでの紛争解決プロセスも断続的に行われてきたとはいえ、過去から現在に至るまでその主眼は国家間の平和構築にあった。たとえ「国家対被占領実体」という非対称な構図であっても、国家間の平和構築がモデルとなっている。他方、紛争のエートスは、紛争当事者の語りや民族/国民的(ナショナル)な言説によって決定づけられている。こうした語りや言説では、多大なる苦難と破壊を作り出してきた破局の出来事の歴史とは「例外的」なものだとする主張が繰り返されている。個人・集団いずれのレベルでも、こうした主張を繰り返す人びとは、深刻な精神的抗争状況の内に閉じ込められており、それはある形での集合的トラウマの存在を暗示するものとなっている。この点は、和平支持者たちが反発を受けて締め出されることが頻発し、和平のための更なる政治的取り組みが実質的に妨げられている点にも表れている。集合的トラウマとは、戦争のトラウマ以上の射程を持つ概念だと言い得るものであり、それが和平への大きな障壁として検討される必要は明らかである。この問題を迂回しての和平の進展はない。しかし、「トラウマ」とは、それ自体進化過程にある、矛盾を抱えた記号表現(シニフィアン)である。すなわち「トラウマ」とは、存在論的かつ認識論的論争の主題なのだ。本論文は、トラウマをめぐる認識論および「集合的トラウマ」の社会的構築、ならびにトラウマの世代を超えた継承の理論の批判的分析を狙いとし、かつ、これらトラウマにかかわる諸問題が、イスラエル・パレスチナ紛争においてはナチスによるホロコーストとパレスチナ人の経験したナクバと複雑な関係性をもつなど、独特な形で連関している点についての評価を行う。この長きにわたるパレスチナ・イスラエル紛争についての研究の大半は、歴史的な係争事案となってきた資源の分割を志向している。しかし、苦しみを抱えたものたちがその苦悩が抱える病的な循環構造を再考するなどして、トラウマは過去についての理解の破損だと捉え直し、トラウマとは記憶のもつ傷だと解釈されるならば、そのときこそ紛争の根源にあるものはひび割れた記憶だということになる。紛争当事者たちの姿勢を心理的・集合的トラウマの重なり合いという視座のもとに位置づけることは、当事者たちのトラウマ的病状ゆえにいかに紛争それ自体が永続的な閉塞状況に閉じ込められているのかという点を決定的に照らし出す。広く言うなれば、紛争のエートス(あるいは複数の紛争のエートス――というのは当該地域にはパレスチナ人の代表を自己主張するパレスチナ政府が二つあるためである)とは、トラウマゆえに事態を進展させられない一連の諸アクターの間で作られるものだとして理論化するか、あるいはトラウマの結果として間接的ないしは無意識にトラウマをシニカルな形で言説として利用する一連の諸アクターの間で作られるものだとして理論化することができる。いずれの理論も、政治的な和平合意の交渉能力に対して大きなインパクトをもつ。こうした新たなアプローチは、ある国際的な研究者たちから支持を得ている。かれらは「トラウマをもたらす出来事の理解、およびトラウマをもたらす出来事が経験され、感知され、知覚され、記憶され、忘却される方法に関心を抱くようになっており、同様に、それらの出来事が世界政治のなかの複数の規範、アイデンティティ、そして利害関心に影響し、かつ影響される方法にも関心を抱くようになった。」(Resende and Budryte, 2014, loc. 245)それゆえ本論考はこうした新たなアプローチのなかに位置づくものである。
- 著者
- Tarek Chehidi
- 出版者
- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.175-207, 2001-03-31 (Released:2018-03-30)
アラブ世界における近代化問題に関する論争は,多くの関心を集めてきた。その結果,アラブ社会とその近代化の試みに関する研究(特にエジプトのムハンマド・アリー期以降)が多数生み出されてきた。その研究の多くは,アラブおよび非アラブの思想家たち(彼らの思想は,彼らと同世代および後の世代が近代化を認識して望まれるべき社会・政治的再建が行われるに至ったスペクトルを形成したと考えられる)に焦点を当てている。その思想家たちの関心と行動を形成したとされる基本的仮定としては,(a)その知識層はイスラームの環境によって生み出され,且つ,彼らの動機は2つの最も大きな一神教であるキリスト教とイスラームの果てなき衝突の枠組みで発展したと考えられること,そして,(b)その思想家たちの社会的影響は統治エリートを通して表れたこと,が挙げられる。しかしながら,チュニジアでは近代化をイスラームとの衝突と見なさず,統治者と特権層を思想と書物の唯一の対象とはしなかった思想家が現れた。アル=ターヒル・アル=ハッダード(al-Tahir al-Haddad,以下ハッダード)である。彼は思想家であると同時に熱烈な活動家であり,一言語使用者であった。彼は,本来イスラームは,社会の全ての成員(特権層も貧困層も同様に)による純然な協力によって実現され得る永続的発展を求めていることを主張した。アル=ウンマ・アル=トゥーニシーヤ(al-ummah al-tuuisiyyah)の発展と幸福は彼の至上目標であった。多くの者は,彼の目標をイスラームの教えに背く現世への熱望であると考えたが,ハッダードはそのような考えに反駁した。彼は,物質的快楽の実直な追求は,アッラーの意志に反するものではなく,生きる価値ある生活への専心は崇拝につながっていると考えたのである。しかし,宗教的立証が多大な影響を与えた社会において,ハッダードは自分の思想をイスラーム的適合性で補う必要があった。よって,彼は明白に,全てのムスリムにとって自助,思想の自由および平等性はイスラームの定めであることを論証した。それらの導きを守ることにより,ウンマは賞賛されるべき生活への条件が整えられるようになった。1899年生まれのハッダードは自らの思想を生き甲斐にし,自らの思想によって闘争的思想家の範例となり,1935年にその生涯を終えた。本論では20世紀初頭30年間のチュニジア社会に関するハッダードの著作を基に,彼の思想の宗教的・世俗的要素を明らかにすることを試みる。さらに,同時代のチュニジア人たちの悪しき状況の改善を提案したハッダードの方法を述べる。そして,宗教,思想的自由の概念,およびその概念と社会解放との関連(労働者や女性を含む貧困層の教育問題解決のための基本要因として)に係わる思想家の言説を提示する。よって,他の著名なムスリム思想家を時折参照することになるが,本論では,彼らの思想とハッダードの判断の比較に関する言及は最小限にとどめ,それについては読者の思慮に委ねることとする。但し,ハッダードがそれらの思想家と区別できる点を示しておくと,それは,啓示に関する彼の認識,来世と現世の関係の概念,変化と発展に関する洞察,自らの思想への絶対的な責務である。その一例としては,ハッダードはイジュティハード(ijtihad)の新しい解釈(アブドゥフが要求したような)は求めるべきでないとし,人間生活の本来の特徴である変化を考慮に入れ,必要な場合には不適切な裁断の破棄と代案を要求したことを挙げることができる。