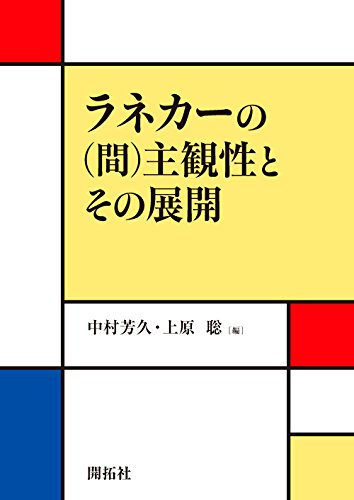- 著者
- 上原 聡介 伊藤 智則 吉井 英樹 鶴丸 和宏 小松 尚久
- 雑誌
- 研究報告グループウェアとネットワークサービス(GN)
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, no.5, pp.1-6, 2011-05-12
本稿では,携帯端末の搭載機能として標準採用されつつある三軸地磁気センサ (電子コンパス機能を含む) から取得できる地磁気データの特徴を示し,徒歩,電車,バス,自動車といった人物移動手段の推定に利用可能かどうか検討を行う.ここで,三軸地磁気センサが搭載されている携帯端末にはアップル社製のスマートフォンである iPhone 3GS を用い,特徴量としては平均と分散を検討した.A geomagnetic sensor is becoming a standard feature for mobile phone. In this paper, we show characteristics of geomagnetic data by using a three-axis geomagnetic sensor (including an electronic compass function) in a mobile phone, and suggest effectiveness of geomagnetic data to estimate person mobility. Person mobility means which kind of way a person takes to move from one geographical point to another. In this paper, we check four types of person mobility, which are walking, train, bus, and car. We use Apple's smartphone-iPhone 3GS as a mobile phone equipped with a three-axis geomagnetic sensor. Also, as feature value, we investigate average and variance.
1 0 0 0 OA 北九州学術研究都市におけるネットワークの構築と運用
- 著者
- 佐藤 敬 上原 聡 福永 泰之
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告インターネットと運用技術(IOT)
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, no.82(2002-DSM-026), pp.19-24, 2002-08-23
理工学系の大学・研究機関を集積した北九州学術研究都市では,キャンパス内に整備された情報ネットワークの一体的な管理運営を行っている.小稿では,学術研究都市におけるネットワーク構築と運用に関する先駆的な取り組みについて紹介する.また,その取り組みの一つであるコンピュータウイルス対策を通じて,これまでに明らかになったネットワークの問題点を述べるとともにその解決策を探る.最後に,本ネットワークの抱える課題について議論を行う.
- 著者
- 宮崎 武 荒木 俊輔 上原 聡 野上 保之
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告 = IEICE technical report : 信学技報 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.114, no.470, pp.97-102, 2015-03-02
素体上のロジスティック写像は,一般的に実数上で定義されるロジスティック写像を素体上で定義し,入力値と写像値を素体の元として計算機上で演算しやすい繰り返し写像である.この写像より得られる擬似乱数系列は,低い演算精度でも十分な乱数性を有していることを示したが,その系列については,まだ十分な解析がなされていない.本稿では,素体上のロジスティック写像における自己相関値により,演算精度に近い周期を持つループの存在を示し,そのループの種類を分類する.また,素体を構成する素数がメルセンヌ素数である場合は,それらのループが同じ種類になることを実験的に示す.
1 0 0 0 OA MRI IDEAL IQによる肝内鉄沈着の評価が有用であった肝ヘモクロマトーシスの1例
- 著者
- 鈴木 康秋 伊藤 啓太 上原 聡人 上原 恭子 久野木 健仁 藤林 周吾 芹川 真哉
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.5, pp.923-930, 2018-05-10 (Released:2019-05-10)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1 1
68歳,男性.肝障害精査にて当科受診.トランスフェリン飽和度,血清フェリチンが高値のため,鉄過剰症が疑われた.肝MRI(magnetic resonance imaging)IDEAL(Iterative Decomposition of water and fat with Echo Asymmetry and Least-squares estimation)IQのR2*MapによるR2*値が著明に高く,高度の肝内鉄沈着所見を呈した.肝組織生検の鉄染色では,肝実質細胞内に高度の鉄沈着をびまん性に認め,肝ヘモクロマトーシスの診断となった.MRI IDEAL IQによる新たな鉄測定法は,ヘモクロマトーシスの非侵襲的検査法として有用である.
1 0 0 0 OA 社会的判断における感情の機能と構造の分析
- 著者
- 上原 聡 ウエハラ サトシ Satoshi Uehara
- 雑誌
- 嘉悦大学研究論集
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.1-14, 2010-10-25
消費者行動研究では、消費者をコンピューターに見立てた情報処理アプローチが1970年代における主要な研究パラダイムであった。情報処理アプローチのような、認知過程を中心に展開された消費者意思決定モデルの中では、感情は認知過程の付随的要素として扱われてきた。しかし、さまざまな領域で感情の研究が進展したことを受け、1980 年代から現在にかけて、消費者行動研究のテーマとしての感情研究の重要性は徐々に高まっている。 このように、感情研究の重要性は認められてはいるが、その機能および構造が体系化された先行研究がみられないことが問題点として指摘できる。 そこで本稿の目的は、人間が日常的に行う社会的判断(意思決定)に焦点を絞り、感情を考慮した消費者行動研究を拡充していくための理論的基盤として、感情がどのような機能を果たしているか、さらに、感情をどのような構造として理解すべきかを解明することにある。そして、感情の機能と構造を解明するために社会心理学や感情心理学の知見を導入している。 結論として、感情構造を「快楽-覚醒」の2 軸により分類し、これにポジティブ感情とネガティブ感情を対応させ、それぞれをムードと情動に区分した上で、4 つの感情タイプ別に感情機能を説明することができた。最後に、この仮説を裏づけるため、社会的判断の場面である購買行動について実際にフィールド調査を実施し、データによる実証分析から、選択され易い認知処理方略を含む購買行動特性を感情タイプ別に明らかにしている。
1 0 0 0 顧客満足に対するサービス品質の影響に関する考察
- 著者
- 上原 聡
- 出版者
- 嘉悦大学
- 雑誌
- 嘉悦大学研究論集 (ISSN:02883376)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.1-15, 2009-10-01
- 被引用文献数
- 2
1990 年代以降、マーケティング研究における中核的な概念として顧客満足(CustomerSatisfaction)が再認識されることとなった。このような顧客満足に関する先行研究においては、利益面の経営成果に対して顧客満足が直接的に影響することが示されていることが特に重要な視点となる。先行研究の中では、期待と経験値のギャップが顧客満足に及ぼす影響を扱ったギャップモデルが多く散見されると同時に、顧客満足に対する期待水準自体の直接的な効果も提起されている。本稿では、サービス・プロフィット・チェーンのような有効な理論モデルが提唱され、特に今後の産業構成上に占めるウェイトがより高まることが予想されるサービス企業に焦点をあてる。サービス企業を研究の調査対象とするため、顧客満足に先行する要因としてサービス品質を考慮する。具体的なサービス企業としてホテル業を選んで実証分析を行い、SERVQUAL モデルに立脚した分析枠組みを用いてサービス品質と顧客満足間の関係を調査した。実証分析の結果、期待水準および期待-経験値間ギャップの双方が顧客満足に影響を与えることを明らかにしている。
1 0 0 0 ラネカーの(間)主観性とその展開
1 0 0 0 OA 社会的判断における感情の機能と構造の分析
- 著者
- 上原 聡
- 出版者
- 嘉悦大学
- 雑誌
- 嘉悦大学研究論集 (ISSN:02883376)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.1-14, 2010-10-25
消費者行動研究では、消費者をコンピューターに見立てた情報処理アプローチが1970年代における主要な研究パラダイムであった。情報処理アプローチのような、認知過程を中心に展開された消費者意思決定モデルの中では、感情は認知過程の付随的要素として扱われてきた。しかし、さまざまな領域で感情の研究が進展したことを受け、1980 年代から現在にかけて、消費者行動研究のテーマとしての感情研究の重要性は徐々に高まっている。 このように、感情研究の重要性は認められてはいるが、その機能および構造が体系化された先行研究がみられないことが問題点として指摘できる。 そこで本稿の目的は、人間が日常的に行う社会的判断(意思決定)に焦点を絞り、感情を考慮した消費者行動研究を拡充していくための理論的基盤として、感情がどのような機能を果たしているか、さらに、感情をどのような構造として理解すべきかを解明することにある。そして、感情の機能と構造を解明するために社会心理学や感情心理学の知見を導入している。 結論として、感情構造を「快楽-覚醒」の2 軸により分類し、これにポジティブ感情とネガティブ感情を対応させ、それぞれをムードと情動に区分した上で、4 つの感情タイプ別に感情機能を説明することができた。最後に、この仮説を裏づけるため、社会的判断の場面である購買行動について実際にフィールド調査を実施し、データによる実証分析から、選択され易い認知処理方略を含む購買行動特性を感情タイプ別に明らかにしている。
- 著者
- 宮崎 武 荒木 俊輔 上原 聡 今村 恭己
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. ISEC, 情報セキュリティ (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, no.396, pp.29-33, 2005-11-08
情報セキュリティ技術の様々なシステムにおいて、組み込まれた擬似乱数生成器の乱数出力を攻撃者が予測できないという擬似乱数の安全性はシステム全体の安全性を保つ上で重要である。その安全性を評価する場合、擬似乱数が予測できない値を出力していることを確かめるため、擬似乱数の統計的性質を調べる乱数検定を行うことが一般的である。しかし、統計的性質だけでは擬似乱数の安全性を評価できない。本稿では、擬似乱数の乱数検定とは異なる安全性評価の一つとして、全数探索攻撃に耐性がある乱数種の選択範囲(乱数種長)を考える。攻撃者が想定できる情報を元に、全数探索攻撃によって乱数種を求める計算量を考え、これをブロック暗号の鍵を全数探索攻撃する計算量と比較することで評価する。この実例として、ロジスティック写像による擬似乱数生成器について、短い長さしか持たない乱数種への全数探索攻撃実験を行う。そして、この攻撃に耐性のあるようにするには、乱数種長を最低限どの程度にする必要があるのかを、この結果から推測する。
- 著者
- 上原 聡 並木 正義
- 出版者
- 一般社団法人日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.249-255, 1994-03-01
雑誌掲載版サイトカインのインターロイキン-/(IL-1)の胃機能および胃粘膜防御系に及ぼす作用について,体重約200gのWistar系雄性ラットを用いて多角的な検討を加えた。その結果,IL-1の粘膜保護効果は主として胃分泌と胃固有運動性に対する阻止作用に依ることが示唆された。しかし胃におけるプロスタグランディン系統を含む他の機構がIL-1の抗瘍に貢献しうるということがありうる。すべて,これらの資料は,胃潰瘍が単なる胃の局所性疾患ではなく,脳は言うに及ばず免疫系統さえふくむ全身病であることを示唆している
- 著者
- 上原 聡 SANDERS ROBERT 上原 聡
- 出版者
- 東北大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2003
本研究では、北京・台湾の標準中国語間の差異について、特に話者が同一の声調を持つ母音を発音する際に、・この2言語地域の間にどのような音韻学的・音響言語学的相違が規則的に現れるか・それぞれの言語地域内においてどのような社会言語学上のバリエーションが見られるかの2点に関して調査するため、両地域の被験者計83名(北京:54名、台北:29名)を対象にフィールド調査を実施し、現代標準中国語において可能な音節1,275種の発音を、各被験者につき約1時間分の音波ファイルという形で収集した。その後、本研究期間終了時の平成17年3月に至るまでに、計18名分(北京:5名、台北:13名)の音声ファイルに関して、各ファイルの一連の音波を個々の音節に分割し、音節毎の音響学的分析を進めた。従って、現在はデータ全ての分析に基づいた研究成果について結論づけて述べられる段階ではないが、これまでの対照分析の結果、台湾の標準中国語話者の声調について以下のような特に注目すべき点が存在することが判明した。すなわち、(1)台湾話者の第3声は不安定な場合があり、約3%の音節が第二声または第四声として発音されていた。(2)第三声として発音された音節の大半が、通説となっている第三声のピッチパターン、いわゆる半声調と呼ばれる短時間の落ち込み(2-1-1)を示さず、長時間の3-1型下降パターンになっていた。同時に、通常5-1の下降パターンを持つ第四声は、5-3というパターンをとっているケースが多数見られた。従来から標準中国語には地域的差異が存在しないという論理的前提があり、声調各声のピッチパターンについてもそれは同様であるが、この現象は明らかにそれへの反証であり、台湾の標準中国語の声調が独自の内部相関的体系を有していることを窺わせる。以上の考察を、さらにデータ処理・分析を進め、サンプル数を増やすことによって検証して行くことが今後の課題となる。
1 0 0 0 OA 生成語彙意味論に基づく語彙情報と事象構造の融合的研究
本研究は、語彙意味論モデルと構文研究を基に語彙情報と事象構造の融合に関する日英語の比較対照研究を行うものである。中心課題は次の3つに集約される。(1)生成語彙意味論によるレキシコン研究の推進。生成語彙意味論モデルのクオリア(語彙情報)が事象構造の解釈をどのように決定するかという問題の解決を目指す。(2)言語における主観性(subjectivity)問題の解明。主観性が事象構造の解釈(例えば、心理状態述語など)にどのように影響するか。そして、構文選択にどのように影響するか。(3)語彙化・文法化における語彙情報と構文の融合についての新たな提案。語彙情報が構文に融合しさらに文法化していく過程には、類型論的に捉えるべき普遍性があることを示す。