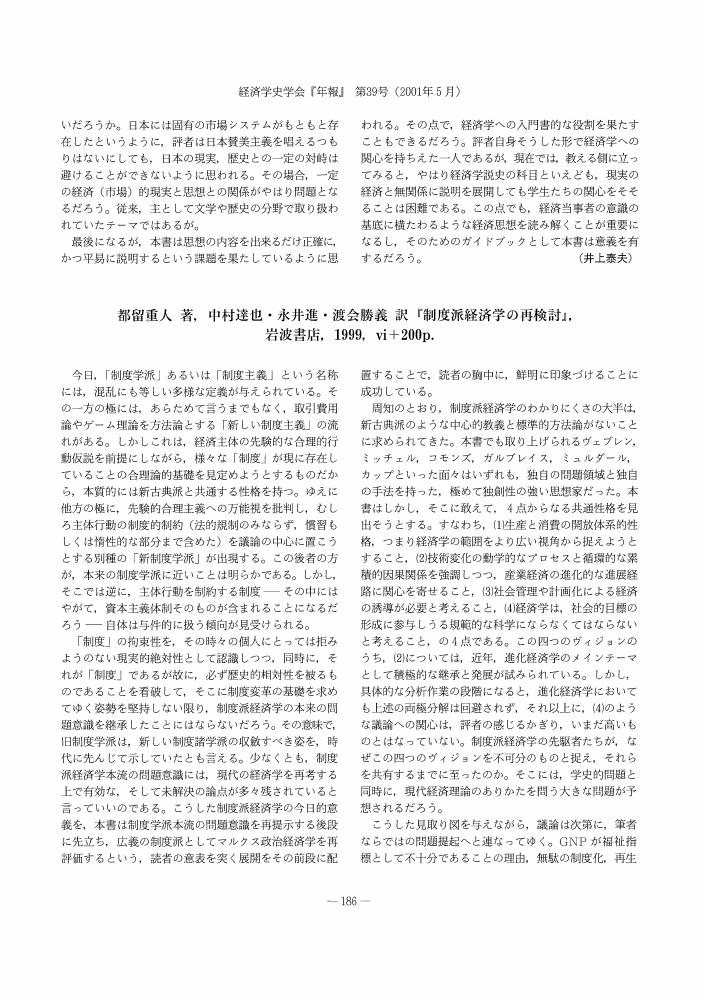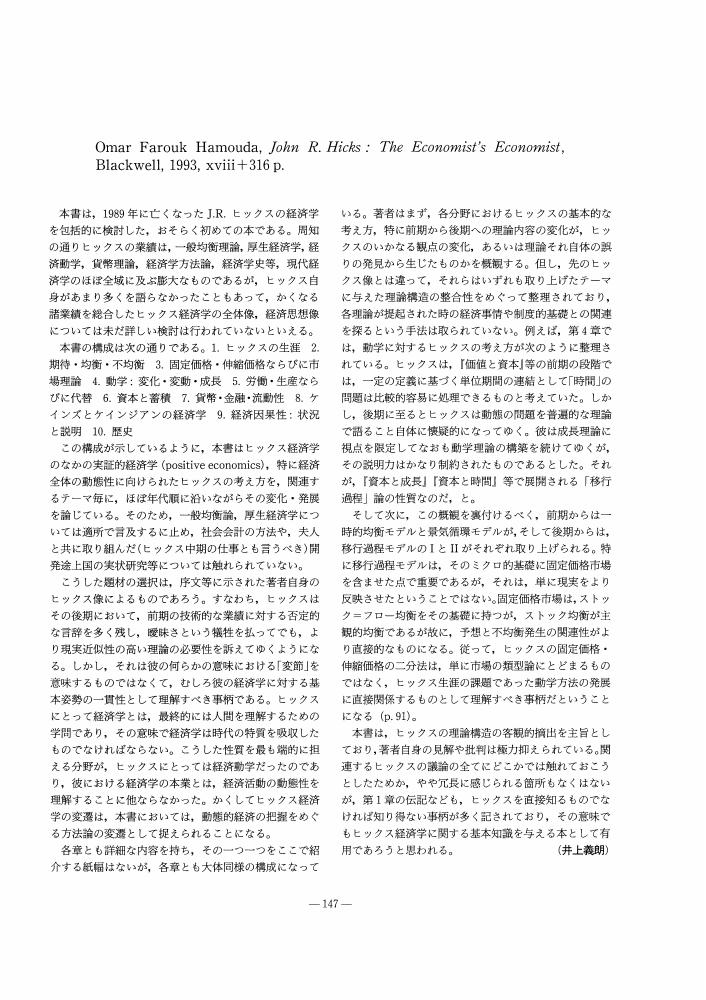2 0 0 0 OA 進化経済学
- 著者
- 井上 義朗
- 出版者
- The Japanese Society for the History of Economic Thought
- 雑誌
- 経済学史学会年報 (ISSN:04534786)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.42, pp.95-105, 2002 (Released:2010-08-05)
- 参考文献数
- 58
The purpose of this paper is to provide a brief survey of the recent development of Evolutionary Economics. This paper addresses four representative approaches of Evolutionary Economics—Neo-Austrians, Neo-Schumpeterians, Modern Institutionalism, and Structural Dynamics—and investigates their recent theoretical progress and policy implications.The essential points are as follows: Neo-Austrians have gradually tended to shift their central concern from the market process theory to the cognitive or knowledge structure of the subject. It seems that their aim is to deepen the bounded rationality or the conception of subjectivity through the assistance of adjacent disciplines. It is not evident whether this tendency actually produces a new foundation for the alternative market theory. However, judging from the common interests with a faction of the Neo-Schumpeterians which introduces Genetic Programming, it is likely that this will become one of the more popular research programs of Evolutionary Economics.Neo-Schumpeterians seem to have diverged in recent years. Therefore, this paper focuses on the development of replicator dynamics. However, it is also argued that replicator dynamics points out some faults of a newly fashioned laissez-faire principle which seems to be based on Evolutionary Economics. Replicator dynamics turns our attention to the contradictory relationship between innovation and market mechanism through a new perspective on the role of ‘variety.’Modern Institutionalism has two types of cumulative causation; the one is theoretical and policy intended, and the other is methodological and philosophical. This paper indicates the recent shift from the former to the latter in Modern Institutionalisms' concerns.Lastly, it is argued that Structural Dynamics seems to have revived some policy implications of Pasinetti's original model. The policy implication of that model was to apply the growth of productivity to the reduction of input materials including working time, not to increase of amount of goods as usual. This paper investigates some attempts to revive such a forgotten theme, and explores their implications for Evolutionary Economic Policy.
2 0 0 0 能動分岐型チャネルを用いた流れの選択的分岐操作
- 著者
- 細川 尊史 斉藤 淳之助 平田 雄志 井上 義朗
- 出版者
- 公益社団法人 化学工学会
- 雑誌
- 化学工学会 研究発表講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, pp.310-310, 2007
1 0 0 0 OA 利己心の系譜学
- 著者
- 太子堂 正称 井上 義朗 間宮 陽介 桑田 学 原谷 直樹 野原 慎司 高橋 泰城 板井 広明 江頭 進 小沢 佳史 佐藤 方宣 笠井 高人 高橋 聡 村井 明彦
- 出版者
- 東洋大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2015-04-01
本研究は、現代の経済理論が前提としている人間像について、その思想的系譜を解明することを目指して行われた。スコットランド啓蒙における「経済学の成立」から現代の行動経済学・神経経済学へと至るまでの野党な経済学者、理論の分析を通じて、効用や利潤の最大化を図る利己的人間観が登場してきた過程だけではなく、それぞれの経済思想家の主張の背後には、利他性や社会性を含む多様な人間像が含まれていたことが明らかとなった。
- 著者
- 朝山 光太郎 井上 義朗 雨宮 伸 大山 建司 加藤 精彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本糖尿病学会
- 雑誌
- 糖尿病 (ISSN:0021437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.51-57, 1983
肥満児において, 赤盈球インスリン受容体結合 (IB) とヘパリン負荷後血中リボ蛋白リパーゼ (LPL) および肝性トリグリセライドリパービ (HTGL) 活性を測定し, 高TG血症との関連性を解析した.IBはGambhirらの方法に準拠して測定し, LDLおよびHTGL活性の測定は免疫化学的測定法によった.ヘパリン負荷量は10単位/kg体重と, Allenらの循環血液量算出法に基づく補正投与量を用いた.5~16歳の顕性糖尿病を認めない肥満児35名を対象とした.<BR>肥満児には高TG血症を高頻度 (20/35) に認めたが, 著明な高コレステロール (chol.) 血症, 低HDLchol.血症はなかった.IBは肥満児では低値であり, 空腹時インスリン値 (n=18), OGTT時のインスリン面積 (n=18), 血清TG値 (n=20) のそれぞれの対数値と負相関を示した.LPL値は10単位/kg負荷時 (n=13), 補正投与量負荷時 (n=12) のいずれも小児正常値と差がなかった.血清TG値は空腹時インスリン値 (n=29) およびインスリン面積 (n=20) と正相関した.相対体重はIB, 血清脂質とは相関せず, 空腹時インスリン値 (n=29) およびインスリン面積 (n=20) と相関した.<BR>肥満児においては, 肥満度に依存しないインスリン感受性低下とそれにともなう高インスリン血症が高TG血症の成立に関与しており, TG処理障害の明らかな関与は認めなかった.
- 著者
- 井上 義朗
- 出版者
- 経済学史学会
- 雑誌
- 経済学史研究 (ISSN:18803164)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.165-166, 2016 (Released:2019-11-29)
- 著者
- 井上 義朗
- 出版者
- 経済学史学会
- 雑誌
- 経済学史研究 (ISSN:18803164)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.124-125, 2012 (Released:2019-10-30)
1 0 0 0 OA 佐藤方宣 編『ビジネス倫理の論じ方』 ナカニシヤ出版,2009,vii+282 頁
- 著者
- 井上 義朗
- 出版者
- 経済学史学会
- 雑誌
- 経済学史研究 (ISSN:18803164)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.114-115, 2009 (Released:2019-08-08)
1 0 0 0 OA 中村隆之『ハロッドの思想と動態経済学』 日本評論社,2008,xiii+238 頁
- 著者
- 井上 義朗
- 出版者
- 経済学史学会
- 雑誌
- 経済学史研究 (ISSN:18803164)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.115-116, 2009 (Released:2019-06-22)
- 著者
- 井上 義朗 都留 重人
- 出版者
- 経済学史学会
- 雑誌
- 経済学史学会年報 (ISSN:04534786)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.39, pp.186-188, 2001 (Released:2010-08-05)
- 著者
- 井上 義朗 緒方 俊雄
- 出版者
- 経済学史学会
- 雑誌
- 経済学史学会年報 (ISSN:04534786)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.34, pp.152-153, 1996 (Released:2010-08-05)
1 0 0 0 OA Omar Farouk Hamouda, John R. Hicks: The Economist's Economist, Blackwell, 1993, xviii+316p.
- 著者
- 井上 義朗
- 出版者
- The Japanese Society for the History of Economic Thought
- 雑誌
- 経済学史学会年報 (ISSN:04534786)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.32, pp.147, 1994 (Released:2010-08-05)
- 著者
- 大川 和男 中元 崇 井上 義朗 平田 雄志
- 出版者
- The Society of Chemical Engineers, Japan
- 雑誌
- 化学工学論文集 (ISSN:0386216X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.5, pp.352-360, 2005
- 被引用文献数
- 6 7
三次元屈曲チャネル内での流体層の分割,180°回転,再合流・重ね合せを組み合わせて流体を多層化する静止型マイクロミキサーの単位エレメントの構成則を求め,それに基づいてY字分岐と120°と60°の屈曲チャネルからなるY型平板静止マイクロミキサーを開発した.正方形のチャネル断面をもつY型ミキサーを用いてヨウ素の脱色実験を行い,混合完了に必要な単位エレメント数<i>n</i>を測定した.レイノルズ数<i>Re</i>が低い場合には<i>n</i>は<i>Re</i>の増加とともに増加した.1単位エレメント通過ごとに厚さが1/2となる流体層内の混合過程をモデル化し,<i>n</i>を表す関数関係を導出し,この関係に基づいて<i>Re</i>が低い場合の<i>n</i>の実験結果を相関した.<i>Re</i>が高い場合,<i>Re</i>の増加とともに<i>n</i>は減少した.この場合の<i>n</i>については上記の関数に用いられる変数を用いて実験的に相関した.<i>Re</i>を50まで変化させてCFD解析を行い,<i>Re</i>の影響を調べた結果,<i>Re</i>=50では流体層は三次元屈曲チャネル内で発生する二次流によって大きく変形していることがわかった.この界面の変形が混合速度を加速させ,<i>n</i>を減少させる.さらに,ミキサーを構成するチャネルのアスペクト比<i>a</i>/<i>b</i>の影響をCFD計算によって検討した.<i>a</i>/<i>b</i>が2.0以上では流体界面の湾曲が大きく,<i>a</i>/<i>b</i>が0.2以下では分岐チャネルで流体が均一に分割されない.したがって,本研究で開発した平板静止型ミキサーにおいて理想的な流体層の分割・再合流を進行させるためには,できるだけ正方形に近いアスペクト比をもつ流路断面を採用することが望ましい.