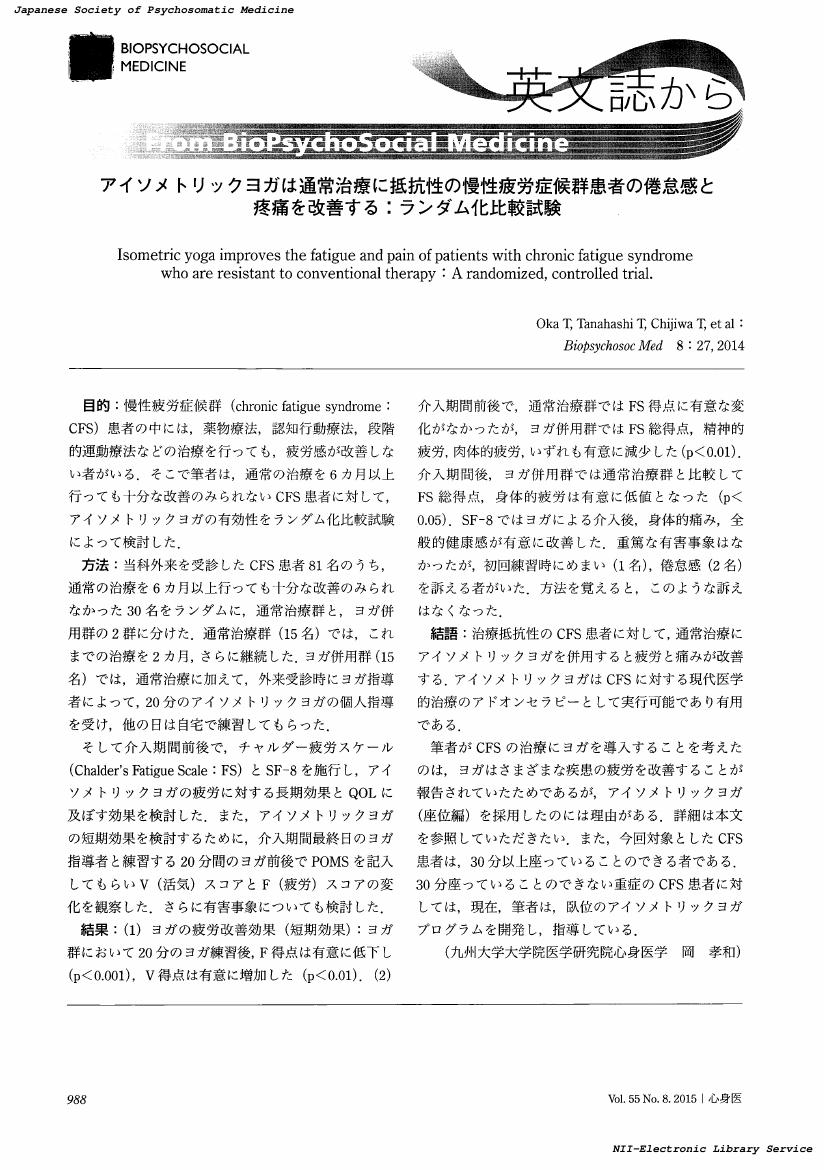22 0 0 0 OA 六君子湯・補中益気湯の副腎皮質機能・自律神経機能に及ぼす影響の検討
- 著者
- 岡 孝和 小宮山 博朗 中川 哲也 松浦 達雄 岡 佳恵
- 出版者
- The Japan Society for Oriental Medicine
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.3, pp.439-446, 1993-01-20 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 22
六君子湯および補中益気湯の血清コルチゾル値および心電図R-R間隔変動係数 (CVR-R) に及ぼす影響を検討した。両剤をそれぞれ23例の Non-ulcer dyspepsia 患者および18例の不定愁訴患者に, 一日7.5g, 4週投与した。1) 六君子湯投与群では, 午前9時血清コルチゾル値は, 高値だった7例では有意に低下し (p<0.05), 低値の2例では逆に増加したが, 正常範囲内であった14例は不変であった。補中益気湯投与群では, 低値の3例, 正常範囲内の12例では増加した (p<0.05) が, 高値の3例では低下した。2) 副交感神経機能を表わすCVR-Rは六君子湯投与群では不変であったが, 補中益気湯投与群では, 投与前, 年齢に比して低値であったが, 投与後増加した (p<0.05)。以上の結果は, これらの漢方薬は副腎皮質および自律神経機能に対して調整的に作用し, この作用はストレス性疾患に対しては有用な作用と考えられた。
13 0 0 0 OA 心因性発熱 (機能性高体温症) に対する非薬物療法と薬物療法
- 著者
- 岡 孝和
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.234-240, 2020 (Released:2020-04-01)
- 参考文献数
- 7
私の行っている心因性発熱ないし機能性高体温症の治療について概説した. 心因性発熱の治療で重要なのは, 見通しのない経過観察や検査の繰り返し, 解熱薬の投与ではなく, 患者の抱えるストレスに対する個別の処方箋である. そのため単一の治療法では不十分で, 多面的なアプローチが必要となることが多い. 具体的には病態説明, 生活指導, 環境調整, 言語的・非言語的心理療法, 精神生理的技法 (リラクセーショントレーニング), 薬物療法, 併存疾患に対する治療, などを必要に応じて組み合わせて行う. 筆者は, まず患者に対して 「体温が上がると, どのようなことで困るのか」 質問し, 高体温に伴って生じる苦痛を理解するようにしている. さらに, 患者が心因を否認したい場合や, 心因性という病名が患者や患者家族のスティグマとなりそうな場合は, 心因性発熱ではなく, 機能性高体温症という病名を用いて, 病状説明をしている.
- 著者
- 岡 孝和
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.8, pp.988, 2015-08-01 (Released:2017-08-01)
4 0 0 0 OA 心因性発熱に関する最近の研究の発展 —特に日本人研究者の貢献について—
- 著者
- 岡 孝和
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.5, pp.407-415, 2021 (Released:2021-07-01)
- 参考文献数
- 28
心因性発熱に関する最近の基礎研究と, その中で日本人研究者が果たしてきた役割について紹介した. 特に実験動物におけるストレス性高体温を抑える薬理学的検討, ストレス性高体温を生じる脳内機序と感染性発熱を生じる脳内機序の違い, 慢性ストレスが体温調節に及ぼす影響について焦点を当てて概説した. さらに心因性発熱患者では, 実際にストレッサーに曝露されなくても, ストレス面接によって心因性発熱を再現できる症例があることを紹介した.
4 0 0 0 OA 「失体感症」概念のなりたちと,その特徴に関する考察
- 著者
- 岡 孝和 松下 智子 有村 達之
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.11, pp.978-985, 2011-11-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 3
失体感症とは心身症患者にみられる特徴として,1979年に池見酉次郎により提唱された概念である.しかしながら,その定義は必ずしも明確でない.そこでわれわれは,失体感症の概念を明確にするために,まず池見が失体感症概念を提唱するに至った経緯と背景を検討した.次に池見による著書から,失体感症に関する記載を抜粋し,失体感症を構成する要素を整理した.失体感症において気づきが鈍麻している感覚には,(1)空腹感や眠気などの,生体の恒常性を維持するために必要な感覚,(2)疲労感などの,外部環境への適応過程で生じる,警告信号しての感覚,そして(3)身体疾患に伴う自覚症状,などが挙げられた.池見は,失体感症では,これらの感覚に対する気づきが鈍麻しているだけでなく,それを表現したり,適切に反応することも困難であるとした.また自己破壊的なライフスタイルを送ったり,自然の変化に対する感受性や自然に接する機会も低下するとした.
2 0 0 0 OA 発熱
- 著者
- 岡 孝和
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.204-208, 2018 (Released:2018-03-01)
2 0 0 0 アカツキ病の1例
- 著者
- 岡 孝和 松岡 洋一 小牧 元 三島 徳雄 中川 哲也
- 出版者
- 一般社団法人日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.5, pp.405-409, 1991-06-01
- 被引用文献数
- 2
A case of Akatsuki disease was reported. Akatsuki disease which was named and reported first by Dr. Sakamoto in 1964 is defined as the skin lesions that are induced by neglect of skin hygiene and based upon certain psychological mechanisms. A 58 year-old female diagnosed as Akatsuki disease was referred to our department by a bermatologist. She had not been able to bathe for more than seven years because she felt burning sesations on her face when she took a bath. When she was admitted to our hospital, her cheeks looked red. When she put her hands into hot water, her face became more red and that state lasted over ten hours. However, endocrinological studies could not explain her complaints. As she was in a hypochondriacal state and also suspected to be in a hypersensitive state of the vasomotion of her face, Autogenic Training as well as the image therapy called "Nanso no Hou" were introduced in addition to supportive psychotherapy and congnitive, behavioral modification. As the result, the redness of her cheeks disappeared and she became able to take a hot shower in two months, and was discharged from the hospital.
1 0 0 0 OA ヨガ
- 著者
- 岡 孝和
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3, pp.265-269, 2023 (Released:2023-05-01)
- 参考文献数
- 9
1 0 0 0 OA 失体感症尺度(体感への気づきチェックリスト)の開発 : 大学生を対象とした基礎研究
- 著者
- 有村 達之 岡 孝和 松下 智子
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.8, pp.745-754, 2012-08-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 6
目的:失体感症を評価する質問紙である失体感症尺度を開発し,信頼性と妥当性の検討を行った.方法:415名の大学生を対象にして,失体感症尺度予備尺度およびToronto Alexithymia Scale-20(TAS-20)への記入を依頼した.結果:項目分析により「体感同定困難」「過剰適応」「体感に基づく健康管理の欠如」の3つの下位尺度,合計23項目からなる失体感尺度が開発された.失体感症尺度は,総得点および下位尺度のいずれにおいても,内的整合性が高く(α=0.70〜0.84),再検査信頼性も十分であった(r=0.71〜0.81).失体感症尺度の総得点と下位尺度は,そのほとんどがTAS-20と有意に相関していた.結論:失体感症尺度は失体感症を評価するためにはじめて標準化された質問紙である.大学生における信頼性は高く,ある程度の妥当性も示唆され,失体感症の研究や臨床応用に有望な心理テストであると考えられる.
本年度は以下の2つの実験を行った.実験には雄ウイスターラット(300-350g)を用い,侵害受容閾値の測定にはプランターテストを用いた.[1] インターロイキン-1β(IL-1β)を視床下部視索前野(POA)に投与したときに生じる痛覚過敏におけるNOの関与の検討.実験1週間前に麻酔下でガイドカニューレとスタイレットをPOAの1.0mm上まで埋め込み,実験当日,薬物を目的部位に注入しpaw-withdrawal latencyの変化を観察した.IL-1β10pgをPOAに投与すると15-30分後にpaw-withdrawal latencyは短縮したが,IL-1β+N^G-monomethyl-L-arginin(10μg)を同時投与すると短縮効果が抑制された.POAにおいてIL-1βはNOを介して痛覚過敏を生じると考えられた.[2] Lipopolysaccharide(LPS)全身投与によって生じる痛覚過敏/鎮痛作用におけるプロスタグタンジン(PG)の関与の検討.LPS1-100μg/kgを静脈内投与したところ,投与45-60分後にpaw-withdrawal latencyが短縮した.一方,120分の観察時間内ではpaw-withdrawal latencyの延長はみられなかった.シクロオキシゲナーゼ-2阻害剤であるNS-3981.0ng/0.3μlを両側POA内に局所投与したところpaw-withdrawal latencyの短縮が抑制されたが,腹内側核,室傍核内への投与では抑制効果がみられなかった.細菌感染症にかかった時に生じる痛覚過敏にPOAでのPG産生が関与すると考えられる.
- 著者
- 岡 孝和 小山 央
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.25-31, 2012-01-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
自律訓練法は不安,抑うつ,怒りなどの陰性感情を低下させ,自己認知を積極的なものに変化させ自己受容を促すという心理的効果がある.練習中,中心後回などの手足の感覚に関連する部位に加えて,前頭前皮質や島皮質など,内部感覚や情動に関連する皮質機能の活動が亢進する.両腕が「重たい」,「温かい」という公式を裏づけるように,骨格筋の弛緩と末梢皮膚温の上昇が生じる.交感神経活動に対しては抑制的に作用する.迷走神経活動に関しては,心臓迷走神経活動を賦活する一方で,消化管を支配する迷走神経機能亢進状態に対しては抑制的に作用する.さらに視床下部-下垂体-副腎皮質系を抑制し,機械的疼痛閾値を上昇させる.
1 0 0 0 OA いわゆる心臓神経症患者における胸背部過敏点の臨床的意義の検討 -特に診断的意義に関して-
- 著者
- 岡 孝和 松浦 達雄 三島 徳雄
- 出版者
- The Japan Society for Oriental Medicine
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.103-108, 1989-10-20 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 12
いわゆる心臓神経症患者にみられる胸背部過敏点の臨床的意義を検討し, 以下の結論を得た。心臓神経症患者では, 第4, 5, 6胸椎棘突起上, 左第4, 5胸肋関節上に高頻度に過敏点を認めた。同部位は健常人においても出現頻度が高かったが, 患者群では有意に高頻度であった。また, 過敏点の出現頻度と神経症傾向, 顕在性不安との間に有意な相関関係は見出せなかった。胸部過敏点では, 圧迫により過敏性疼痛を示したにすぎなかったが, 背部過敏点では, 圧迫により胸痛, 動悸, 胸部圧迫感等の自覚症状を訴えた者が多く, 背部過敏点を検索することは, 患者の愁訴を理解する上で有用な身体所見であると考えられた。第4, 5, 6胸椎棘突起レベルには厥陰兪, 心兪, 督兪が配されていることと比較すると興味深い結果と考えられた。
- 著者
- 岡 孝和 小山 央
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.25-31, 2012
- 参考文献数
- 30
自律訓練法は不安,抑うつ,怒りなどの陰性感情を低下させ,自己認知を積極的なものに変化させ自己受容を促すという心理的効果がある.練習中,中心後回などの手足の感覚に関連する部位に加えて,前頭前皮質や島皮質など,内部感覚や情動に関連する皮質機能の活動が亢進する.両腕が「重たい」,「温かい」という公式を裏づけるように,骨格筋の弛緩と末梢皮膚温の上昇が生じる.交感神経活動に対しては抑制的に作用する.迷走神経活動に関しては,心臓迷走神経活動を賦活する一方で,消化管を支配する迷走神経機能亢進状態に対しては抑制的に作用する.さらに視床下部-下垂体-副腎皮質系を抑制し,機械的疼痛閾値を上昇させる.
1 0 0 0 OA Tandospironeの投与と心身医学的治療が有効であった心因性発熱の1例
- 著者
- 倉 尚樹 岡 孝和 安藤 哲也 石川 俊男 久保 千春 吾郷 晋浩
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.4, pp.297-303, 2004-04-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 18
症例は21歳女性,37℃台の微熱が主訴であった.諸検査で発熱の原因となる身体的疾患を認めなかったこと,心理的ストレス状況下で症状が出現・増悪したこと,慢性疲労症候群の診断基準を満たさないことから心因性発熱と診断した.治療としてtandospirone 60mg/dayの投与と自律訓練法などの心身医学的治療を併用したところ,体温は徐々に正常化した.serotonin(5-HT)作動性の抗不安薬であるtandospironeは,5-HT_<1A>受容体を刺激し,5-HT_<2A>受容体の密度を低下させることで抗不安・抗うつ作用を示すといわれている.これらの5-HT受容体に対する作用は,体温を低下させる方向にも作用すると推測され,tandospironeは心因性発熱の治療薬の1つとして有用である可能性が考えられた.
1 0 0 0 OA 心因性発熱に関する, これまでの研究をふり返る —序文に代えて—
- 著者
- 岡 孝和
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.200-202, 2020 (Released:2020-04-01)
- 著者
- 岡 孝和 岡 佳恵 堀 哲郎 久保 千春
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.supiementII, pp.135, 1998-05-27 (Released:2017-08-01)
1 0 0 0 心因性発熱の機序解明のための臨床および基礎研究
ストレス性体温上昇反応の機序を解明するために以下の実験を行なった.(1)発熱の主要媒介物質であるプロスタグランディンE2(PGE2)による発熱反応に関与する脳内部位調べるために,EP3受容体ノックアウト(KO)マウスとワイルドタイプ(WT)マウスにリポポリサッカライド(LPS)10μg/kgを腹腔内注射し,2時間後の体温と,Fos-like immunoreactivityの発現する脳内部位を比較した.LPS投与2時間後,WTマウスでは約1℃の発熱を生じたが,EP3受容体KOマウでは発熱は生じなかった.WTマウスでは脊髄中間質外側核(IML)に多くのFos陽性細胞が見られたが,EP3受容体KOマウスではほとんど見られなかった,延髄孤束核,視索前野腹内側部(VMPO),室傍核,後部視床下部,中脳水道周囲灰白質,青斑核,raphe pallidus nucleus(RPa)では,両マウスともに多くのFos陽性細胞が見られた.(2)心理的ストレスによる体温上昇反応時にLPS発熱反応に関与する脳内部位(VMPOとRPa)が活性化されるかどうかをラットを用いて検討した.ケージ交換ストレスを加えると,体温はケージ交換20分後に0.9℃上昇した.ケージ交換1時間後,Fos陽性細胞はRPaには発現したがVMPOでは観1察されなかった.(3)ヒトの心因的ストレスによる体温上昇反応にPGE2,サイトカインが関与するかどうかを検討する1目的で,当科を受診した心因性発熱患者15名で,(1)アスピリン660mgを1日2回服用した時の体濫と,服用しない時の体温を比較したが,アスピリンを内服しても体温は低下しなかった.(2)高体温1時(平均腋窩温37.6℃)と体温が正常範囲内の時(36.8℃)とで,発熱性サイトカイン(IL-1,IL-6,MIP-1α,)と解熱性サイトカイン(IL-10)の血中レベルを測定し比較したが,両群で差はなかった.(3)これらの患者に選択的セロトニン再取込み阻害薬である塩酸パロキセチンを4週投与したところ,腋窩温は37.6±0.2℃から36.8±0.2℃へと有意に低下した.したがって心理的ストレスによる体温上昇にはVMPO,サイトカイン,PGE2は関与せず,遷延化した1高体温には脳内セロトニン系の機能低下が関与すると考えられる.
- 著者
- 岡 孝和
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.7, pp.631-636, 2008-07-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 15
ストレスが恒温動物の深部体温に及ぼす影響に関して概説した.拘束ストレスをはじめ,多くの心理的,身体的ストレスは動物の深部体温を一過性に上昇させる.このストレス性体温上昇反応は感染,炎症によって生じる発熱反応と異なり,発熱物質である炎症性サイトカインやプロスタグランディンE_2非依存性の機序によって生じる.コミュニケーションボックスにより,連日,心理的ストレスを負荷したラットでは,非ストレスラットに比べ,昼夜ともに体温が高くなる.その一方で,強い拘束ストレスを受けたラットの体温は低下する.これらの動物実験の成果をもとに,心因性発熱,慢性ストレス状況で生じる原因不明の微熱の機序について考察した.
1 0 0 0 心理社会的ストレスにより誘発された蕁麻疹の1例
- 著者
- 林田 草太 岡 孝和 兒玉 直樹 橋本 朋子 辻 貞俊
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.10, pp.907-913, 2006
- 参考文献数
- 10
症例は35歳,女性.全身に紅斑・膨疹とかゆみが出現・消褪を繰り返すようになり,近医で蕁麻疹と診断されさまざまな抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬を処方されたが,症状は不変で,心因の関与が疑われ当科入院となった.負荷試験として鏡映描写試験と暗算負荷試験を行ったところ,試験直後より紅斑・膨疹を伴ったかゆみが出現し約2時間持続.このとき血漿ヒスタミン値は上昇した.職場や姑の話をした直後にも同様の蕁麻疹が生じた.支持的精神療法に加え,心身相関の気づきを促すためにかゆみの程度を記録,自律訓練法の指導,パモ酸ヒドロキシジンの内服により,増悪・寛解因子を理解し,症状が出現しない工夫ができるようになり,その結果蕁麻疹は改善し,鏡映描写試験後の血漿ヒスタミン値の上昇も軽度となった.慢性蕁麻疹のうち心理的要因により難治化しているものに対しては,心身医学的アプローチが有効であると考えられる.
- 著者
- 岡 孝和 松岡 洋一 三島 徳雄 中川 哲也
- 出版者
- 一般社団法人日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.293-300, 1993-04-01
- 被引用文献数
- 6
The effects of conducting Autogenic Training (AT) on autonomic nervous functions were studied by using non-invasive autonomic nervous function tests. We used the coefficient values of the R-R intervals of ECG (CVR-R) as a parameter of the parasympathetic nervous function, while the coefficient values of the wave heights of digital plethysmograph (CVwH100) were used as a parameter of α-adrenergic sympathetic nervous function. In addition, β waves of thenar microvibration (MV) were used as a parameter of parasympathetic and θ waves of MV were used as a parameter of sympathetic nervous function. Forty healthy volunteers underwent AT for 5 minutes in the supine position after a sufficient observation period. Blood pressure (BP), pulse rate (PR), CVR-R. CVWH1OO and MV were all checked before, during and after undergoing AT. Results : (1) The well trained group (n=10) showed a significant increase of α2 waves of MV both during and after the AT. CVR-R and CVWH100 did not show any significant change. The beginners group (n=30) showed a significant decrease of θ waves of MV but CVR-R and CVWH1OO did not show any significant change. BP and PR did not show any alteration in either group. (2) The group whose trait anxiety (STAI) increased (n=6) did not show any significant change in CVR-R, CVWH100,MV, BP and PR. On the other hand, the group whose trait anxiety (STAI) decreased (n=34) showed a tendency of increased CVR-R as well as CVWH1OO by practicing AT, a significant increase in α2 waves and a tendency of decrease in θ waves of MV after undergoing AT although no significant change was observed in either BP or PR. (3) A dominant waxing and waning phenomenon of the digital plethysmograph was also observed during the sessions in those whose skin temperature was increased by AT. These results indicate that sympathetic nervous function as well as parasympathetic nervous function are both activated and the vasomotion of peripheral vessels is also activated when AT can be successfully administered.