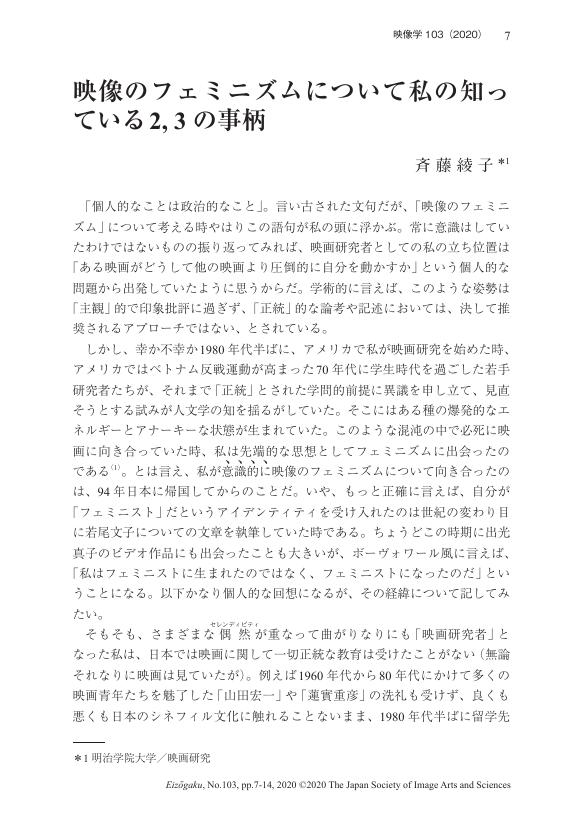132 0 0 0 OA 映像と音の同期―「動画先行の原則」の根拠と応用
- 著者
- 桑原 圭裕
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, pp.54-74, 2019-07-25 (Released:2019-11-19)
- 参考文献数
- 39
アニメーション制作の現場では、動画と音の同期に関して「動画は音より2フレーム前にすると仕上がりが良い」という「動画先行の原則」が語られてきた。たとえば映像と音楽の一体をテーマに 1929 年から 10 年間にわたって制作されたディズニーの短編アニメーション映画シリーズ「シリー・シンフォニー(The Silly Symphony)」の諸作品をコンピューターで解析すると、確かに時代がくだるにつれて動画を先行させるようになってきた事実を確認することができる。しかし、この動画先行の原則は、あくまで映像制作者たちの経験則に基づいており、その科学的な根拠はこれまで十分には解明されてこなかった。実写かアニメーションかを問わず映像制作の現場において、我々が映像と音を知覚する際に双方のずれを感ずるのは、3 フレーム以上、時間にしておよそ 0.1 秒以上といわれている。したがって、「動画先行の原則」について論じるためには、感覚刺激が脳に到達するまでの問題として知覚心理学の理論を援用する必要がある。本稿の目的は、このようなフレーム処理が一部の実制作の現場で採用されるようになった経緯の背景にある理論的根拠を提示するとともに、このように時間を先取りする手法が、アニメーションに限らず映像全般において、その芸術としてのダイナミズムをもたらしていることを、具体的な作例の分析を通して明らかにすることにある。
72 0 0 0 OA 北村匡平著『24フレームの映画学――映像表現を解体する』晃洋書房、2021年5月
- 著者
- 重政 隆文
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, pp.144-148, 2022-02-25 (Released:2022-03-31)
55 0 0 0 OA 映像のフェミニズムについて私の知っている2, 3の事柄
- 著者
- 斉藤 綾子
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, pp.7-14, 2020-01-25 (Released:2020-02-25)
54 0 0 0 OA 「「演じる」のではなく朗誦する」とは何か――ストローブ゠ユイレ『階級関係』における発話の生成過程
- 著者
- 行田 洋斗
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, pp.109-127, 2023-02-25 (Released:2023-03-25)
- 参考文献数
- 25
本論文は、演出の観点からストローブ゠ユイレ作品における俳優の発話について論じる。これまでの先行研究では、その不自然なアクセントや休止を伴った特異な俳優の発話について「音楽的」や「異化効果」といった言葉とともに論じられてきたが、抽象的かつ曖昧なかたちでしか考察されてこなかった。本稿では、作家のインタビューや演出時のリハーサル映像、メモが残された脚本等の資料を使用し、その生成過程を探ることで、ストローブが「朗誦」と呼ぶ発話を具体的に分析することを目的とする。そのため、まず第一節ではフランツ・カフカの『失踪者』の翻案作品である『階級関係』(1984年)を例にとり、監督のリハーサル前の構想を確認する。第二節では、そのリハーサル映像に基づいて、特定の語が実際にどのように演出され、俳優に身体化されているのかを分析する。続く第三節では、前節までに確認した発話が、作品のなかでいかに形成され、どのような役割を担っているのかを確認する。そして最後に俳優の身体とテクストの両方を重視する、反復という方法論について論じたい。以上の考察から、ストローブが「朗誦」と呼ぶものとは、俳優固有の声と、テクストに内在する情動を結びつけることであると結論づける。
54 0 0 0 OA 稲畑勝太郎のリュミエール兄弟宛て書簡4通の発見について
42 0 0 0 OA ジュディ・ガーランドを愛するということ——キャンプ、ドラァグ、フェミニズム
- 著者
- 菅野 優香
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, pp.15-21, 2020-01-25 (Released:2020-02-25)
36 0 0 0 初期映画における「鍵穴映画」の変容
- 著者
- 森村 麻紀
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- no.69, pp.42-58, 2002
35 0 0 0 OA 映画の新たな生――デジタル時代の映画分析
- 著者
- 堀 潤之
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, pp.21-26, 2022-08-25 (Released:2022-09-25)
35 0 0 0 OA #MeToo的映画史のために
- 著者
- 木下 千花
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, pp.22-28, 2020-01-25 (Released:2020-02-25)
34 0 0 0 OA ポジ編集からネガ編集へ――1920年代ドイツ語圏におけるポストプロダクションの変容
- 著者
- 常石 史子
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, pp.49-67, 2023-02-25 (Released:2023-03-25)
- 参考文献数
- 23
無声映画は、タイトル(中間字幕)を入れ替えるだけでさまざまな言語の版を作成できる、際立って国際性なメディウムであった。染色・調色・ステンシルカラーといった無声映画特有の着色は、色変わりごとにスプライス(つなぎ目)が生じるのが難点だったが、タイトル挿入のための編集作業が必要な状況ではさほど障害にならず、豊かに花開いた。着色された各断片とタイトルを組み合わせて上映用プリントを1本ずつ手作業で仕上げるポジ編集のプロセスは、ドイツ語圏においては1920年代前半まで主流だった。1920年代半ばから後半にかけて、機械現像の導入と扱えるフィルムの長さの伸長により、上映用プリント1巻分をスプライスなしに仕上げることが可能になった。またネガの複製に特化したフィルムの登場で、単一のオリジナルネガから各言語版のネガを複製しても十分な画質が得られるようになった。こうして近代的なネガ編集のシステムが完成すると、これにともなって着色はポストプロダクションのプロセス全体を阻害する要素となり、色変わりの頻度は減少した。単色染色は部分的に残ったが、やがて完全に消滅する。そしてこのネガ編集こそ、1929年前後に起こったトーキー化の必須条件だった。トーキー化は音声の記録のみに関わる技術革新ではなく、映画フィルムを手工芸品から工業製品へと変貌させる、編集、複製、現像それぞれの領域における数年がかりの歩みがあってこそ、はじめて可能になったのである。
30 0 0 0 OA 『空の大怪獣ラドン』における特撮の機能
- 著者
- 真鍋 公希
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, pp.25-45, 2018-01-25 (Released:2018-06-11)
- 参考文献数
- 31
【要旨】 円谷英二が特技監督を務めた『空の大怪獣ラドン』(1956 年、以下『ラドン』)は、公開当時から高く評価されている作品である。しかし、特撮映画に関する先行研究は『ゴジラ』(1954 年)ばかり注目してきたため、本作はほとんど分析されてこなかった。本稿では、トム・ガニングの「アトラクション」概念を補助線とし、本作の特異性と映画史的・文化史的意義を明らかにすることを試みる。「アトラクション」とは、物語を伝達する機能と対照的で、ショックや驚きなどの直接的刺激によって特徴づけられる性質だと紹介されてきた。しかし、『ラドン』における「アトラクション」的側面は、ショックによる直接的な態度よりもむしろ、特撮に注意を払う反省的な態度によって特徴づけられる。この態度はその後のオタク的な観客心理につながるものであり、この点で『ラドン』は、特撮映画をめぐる観客性の転換点に位置づけられる作品なのである。 これを示すために、第1 節では円谷の演出理念を検討する。円谷は特撮によって物語的な効果を引き出すことを第一に考えていたが、他方で特撮の痕跡が残ることを許容してもいた。ここに特撮が効果を逸脱し「アトラクション」として立ち現れる可能性を見ることができる。次に第2 節で、こうした円谷の演出理念が、『ラドン』ではどのように表出しているのかを考察する。円谷の演出理念は、ラドンが西海橋や福岡に現れる一連のシーンに色濃く反映しており、同時にこれらのシーンはテクスト全体の中でも自立的に機能している。最後に第3 節では、観客が『ラドン』の特撮に注意を払った反省的な態度で受容していたことを、当時広く普及していた「技術解説記事」を考察することで明らかにする。
29 0 0 0 日活ロマンポルノに現れた「団地妻」―白川和子と団地妻イメージ―
- 著者
- 今井 瞳良
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, pp.137-154, 2019
<p>本稿は、白川和子が主演した日活ロマンポルノの団地妻シリーズ『団地妻昼下りの情事』( 西村昭五郎監督、1971 年 ) と『団地妻 しのび逢い』(西村昭五郎監督、1972 年)の分析を通して、「団地妻」が「密室に籠る団地妻」からの解放を模索していたことを明らかにする。団地妻は憧れのライフスタイルであるとともに、社会から隔絶され、孤立した「密室に籠る団地妻」としてイメージされてきた。ところが、団地妻イメージとして絶大な影響力を持った白川主演の「団地妻映画」は、「密室に籠る団地妻」からの解放を模索する「団地妻」と、会社に組み込まれた不安定な「団地夫」の夫婦を定型としている。「団地妻映画」は、「密室に籠る団地妻」というイメージにはあてはまらない作品であったのだ。ところが、結婚して本物の団地妻となり引退した白川和子は、「団地妻映画」と「密室に籠る団地妻」という相反するイメージを接続させ、遡行的に団地妻イメージの起源となっていく。白川が「団地妻」を演じた『昼下りの情事』と『しのび逢い』は、「密室に籠る団地妻」からの解放を模索する「団地妻映画」であったにもかかわらず、団地妻イメージの起源として捏造されたのである。</p>
28 0 0 0 OA 《プラネット映画資料図書館》の上映活動――1975~1988年まで
- 著者
- 田中 晋平
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, pp.89-108, 2023-02-25 (Released:2023-03-25)
- 参考文献数
- 23
1974年に大阪で安井喜雄たちが創立した《プラネット映画資料図書館》は、映画のフィルムや関連資料の収集・保存に加えて、自主上映活動を続けてきたグループである。本論では、筆者が〈神戸映画資料館〉で担当した《プラネット》に関する資料(自主上映会のためのチラシや機関誌など)の整理作業を踏まえ、1970年代半ばから1980年代後半までに開催されたその上映活動の歴史的な役割を考察する。具体的には、《プラネット》の上映を実現してきた人間およびモノのネットワークに注目し、自主上映と新たに勃興したミニシアターなどの映像文化との差異を明らかにしたい。まず《プラネット》の前身となる上映活動として、1960年代末に結成された《日本映画鑑賞会OSAKA》の時代に遡り、関西における自主上映の地層を検討する。次にフィルム・コレクターや他の上映グループとの関係性を構築しながら、《プラネット》の活動が展開され、国内外で製作された古典的映画、アニメーション、ドキュメンタリー映画、実験映画・個人映画におよぶ多様な作品が上映されてきた経緯を確認したい。また論点として、自主上映グループが、モノとしてのフィルムをいかに確保し、活動を行ってきたのかに着目する。さらに1980年代後半に《プラネット》が関わった「OMSシネデリック」のシリーズなどを取り上げ、自主上映の活動とミニシアター文化との差異について論じる。
25 0 0 0 OA 木下千花著『溝口健二論 映画の美学と政治学』(法政大学出版局、2016年5月)
- 著者
- 畠山 宗明
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, pp.68-72, 2017-07-25 (Released:2017-09-13)
- 著者
- 長谷 正人
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- no.94, pp.61-65, 2015-05-25
20 0 0 0 OA 新理研映画時代の松本俊夫——前衛記録映画論の形成過程
- 著者
- 阪本 裕文
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, pp.114-136, 2020-07-25 (Released:2020-08-25)
- 参考文献数
- 37
映画監督・映像作家の松本俊夫は前衛記録映画論を提唱し、新理研映画に在職していた期間(1955~1958)に実質的な初監督作品として『銀輪』(1956)、正式な監督作品として『マンモス潜函』(1957)、『伸びゆく力』(1958)、『日本原子力研究所第二部——JRR-2』(1960、松本の参加は1958年末まで)を監督した。これまで『銀輪』以外の作品は所在不明であり、新理研映画時代の松本の仕事は不明な部分が多かった。しかし本論に係る調査により『マンモス潜函』と『日本原子力研究所第二部』は現存が確認され、『伸びゆく力』は別の監督によって改作された改訂版の現存が確認された。本論はこれら新発見作品を主な分析の対象とする。まず第1節にて、新理研映画時代に併行して起こった教育映画作家協会での政治的論争と新理研映画の労働争議が、松本の中で結びついていたことを論証する。続く第2節にて、新発見作品の演出を個別に分析し、前衛記録映画論を提唱する以前の松本の映画の中に、前衛的な記録的手法の兆候があったことを論証する。最後に第3節にて、実験工房とのコラボレーションである『銀輪』の中で、松本の演出が強く表れている箇所を分析し、『銀輪』と新発見作品の間に連続性が存在することを論証する。これにより本論は、前衛記録映画論の形成過程を明示するという目的を達成する。
20 0 0 0 OA 石原香絵著『日本におけるフィルムアーカイブ活動史』(美学出版、2018年3月)
- 著者
- 岡田 秀則
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, pp.201-203, 2019-01-25 (Released:2019-06-25)
19 0 0 0 OA 証言映画としての『チリの闘い』――闘争の記憶を継承するために
- 著者
- 新谷 和輝
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, pp.34-55, 2021-07-25 (Released:2021-08-25)
- 参考文献数
- 33
映画作家パトリシオ・グスマンは母国チリの記憶をテーマにこれまで数々の作品を発表してきた。グスマンの作品における記憶の表象を扱った先行研究の多くはピノチェト独裁時代の被害の記憶を扱う1990年以降の作品を対象にしている。そのため彼の初期代表作である『チリの闘い』は「記録」の側面が重視され、「記憶」の視点から検討されてこなかった。本論文は、人々の証言によって構成される「証言映画」として『チリの闘い』を捉えることで、この映画が映し出す特異な記憶の様態を明らかにするとともに、この作品から証言映画の系譜に新たな視点を導き出すことを目的とする。第1節では証言映画の系譜の整理として、「表象不可能」な被害の記憶について『ショア』が提起した1980年代以降の議論と、同時期にラテンアメリカで起こった「証言の文化」を結びつけ、その流れに1990年代以降のグスマンの作品を位置付ける。第2節では1960~1970年代のラテンアメリカ映画運動における証言映画の働きを分析し、1980年代以降の証言映画との差異と共通の問題点を明らかにする。両時期の証言映画がこれまで別々に論じられ、『チリの闘い』はそれらの時期のはざまに生まれた作品であることを示したうえで、第3節では『チリの闘い』の制作経緯や証言の構成を考察し、当時の闘争を物語る人々の証言が、グスマンの主観性と結びつきながら新たな協働の可能性へつながれていくことを明らかにする。
18 0 0 0 OA 日活ロマンポルノに現れた「団地妻」―白川和子と団地妻イメージ―
- 著者
- 今井 瞳良
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, pp.137-154, 2019-07-25 (Released:2019-11-19)
- 参考文献数
- 55
本稿は、白川和子が主演した日活ロマンポルノの団地妻シリーズ『団地妻昼下りの情事』( 西村昭五郎監督、1971 年 ) と『団地妻 しのび逢い』(西村昭五郎監督、1972 年)の分析を通して、「団地妻」が「密室に籠る団地妻」からの解放を模索していたことを明らかにする。団地妻は憧れのライフスタイルであるとともに、社会から隔絶され、孤立した「密室に籠る団地妻」としてイメージされてきた。ところが、団地妻イメージとして絶大な影響力を持った白川主演の「団地妻映画」は、「密室に籠る団地妻」からの解放を模索する「団地妻」と、会社に組み込まれた不安定な「団地夫」の夫婦を定型としている。「団地妻映画」は、「密室に籠る団地妻」というイメージにはあてはまらない作品であったのだ。ところが、結婚して本物の団地妻となり引退した白川和子は、「団地妻映画」と「密室に籠る団地妻」という相反するイメージを接続させ、遡行的に団地妻イメージの起源となっていく。白川が「団地妻」を演じた『昼下りの情事』と『しのび逢い』は、「密室に籠る団地妻」からの解放を模索する「団地妻映画」であったにもかかわらず、団地妻イメージの起源として捏造されたのである。
18 0 0 0 OA 語られる「団地妻」——ロマンポルノ言説の戦後史
- 著者
- 今井 瞳良
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, pp.95-113, 2020-07-25 (Released:2020-08-25)
本稿は、日活ロマンポルノの団地妻シリーズが性別役割分業を前提とした「団地妻」イメージの起源でありながら、固定化された「団地妻」言説を批評するシリーズでもあったことを明らかにする。ロマンポルノ裁判をきっかけに興隆した映画評論家や批評家によるロマンポルノ言説は、低俗な娯楽とみなされるロマンポルノを称揚するために、芸術的創造の主体としての監督を必要とした。そのため、複数の監督によって製作された団地妻シリーズが批評的な評価を得ることは、ほとんどなかった。ところが、団地妻シリーズの第1作『団地妻 昼下りの情事』(西村昭五郎監督、1971年)は、専業主婦として家にいる女性と仕事で通勤している男性を分割するジェンダー化された空間である団地を舞台に、性別役割分業を前提とした中流階級の安定性を支える高度経済成長期以後の戦後史の語りに組み込まれることで、「団地妻」イメージを室内で退屈する専業主婦として固定する「団地妻」言説を生み出していった。しかし、その後の団地妻シリーズは人気シリーズとしてマンネリの打破やメディア状況の変化、他社製作などに対応しながら1971年から1987年まで全29作も作り続けられたことによって、多様な「団地妻」を描き出し、固定化された「団地妻」言説に対する批評性を獲得していることを明らかにした。