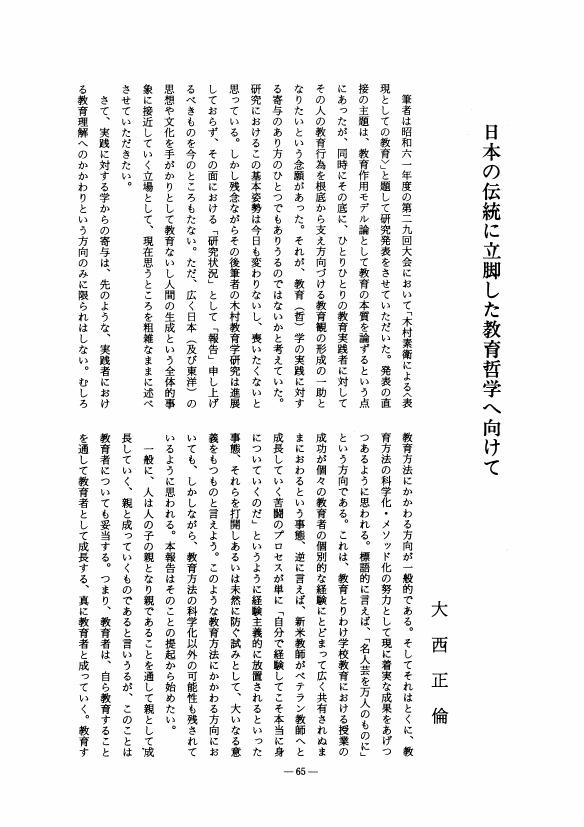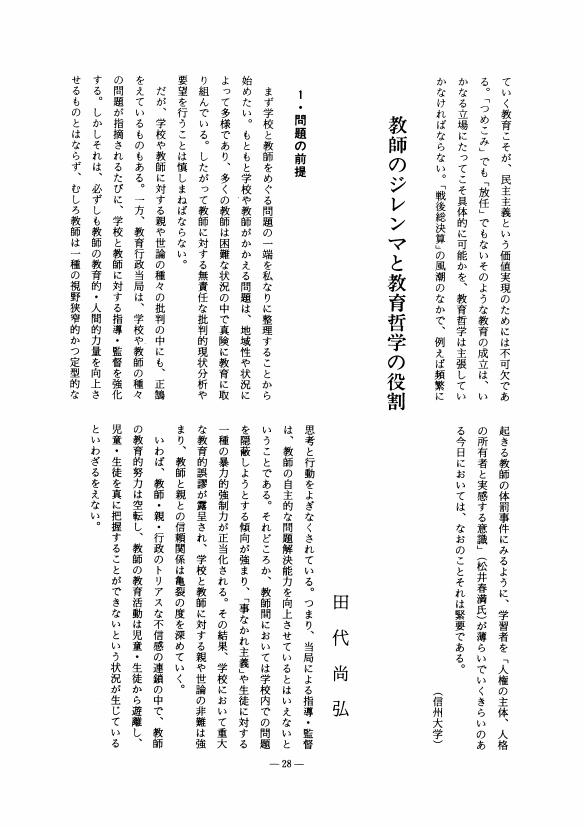1 0 0 0 OA 教育改革の理念を問う 教育学的責任の視座から
- 著者
- 高橋 洸治
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1988, no.57, pp.22-27, 1988-05-10 (Released:2009-09-04)
1 0 0 0 OA 教育改革の理念を問う
- 著者
- 西村 晧
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1988, no.57, pp.27-31, 1988-05-10 (Released:2009-09-04)
1 0 0 0 OA 課題研究に関する総括的報告
- 著者
- 長井 和雄 岡田 渥美
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1988, no.57, pp.32-39, 1988-05-10 (Released:2009-09-04)
1 0 0 0 OA 後期シェリング哲学の教育学的意味について その出会い論を中心にして
- 著者
- 池田 全之
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1988, no.57, pp.54-67, 1988-05-10 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 40
In this paper I investigate the progress in Schelling's thought which started with a philosophy of identity (Identitätsphilosophie) and ended up in insisting on the difference between negative philosophy (negative Philosophie) and positive philosophy (positive Philosophie) paying special attention to the change of principles which thus occurred. From the beginning to the end, he continued trying to solve the problem 'How can we recognize the Absolute ?'. At first Schelling thought it was by intellectual intuition that we could recognize it. However as his thought deepened, the appropriateness of intellectual intuition became doubtful to him, and because of the failure of his middle philosophy, finally it was abandoned. Contrary to his early philosophy, in which he had maintained the possiblity of knowing the Absolute, his later philosophy insisted that it is impossible for us to know the Absolute directly. In his later philosophy he adopted ecstasy (Ekstase) as a new principle. Hence, Schelling changed his methodological principle completely during the development of his thought. Therefore, I examine the meaning of this change from an anthropological-pedagogical point of view to arrive at some valuable clues reflecting on the nature of encounter (Begegnung) in educational practice.
1 0 0 0 OA 日本の伝統に立脚した教育哲学へ向けて
- 著者
- 大西 正倫
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, no.56, pp.65-68, 1987-11-10 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA 上智大学中世思想研究所編集『教育思想史』
- 著者
- 村田 昇
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, no.56, pp.69-75, 1987-11-10 (Released:2009-09-04)
わたくしは、ギリシア・ローマの教育思想については、まったく門外漢である。もちろん、時にはプラトンやアリストテレスの翻訳書や研究書をひもとき、また、石山脩平・稲富栄次郎両博士らのギリシア教育思想に通暁された先撻による通史に接し、西洋教育思想の源流に立ち還ることは怠っていない心算である。とはいっても、それは、西洋教育思想を研究する者としては当然のことであろうし、わたくしのギリシア・ローマ教育思想の理解は、きわめて常識的なものにすぎない。したがって、永年にわたって研究された専門家の筆になる『ギリシア・ローマの教育思想』について論評を行うなどということは、まったくおこがましいし、わたくしにはその資格も能力もない。ただ、編集子の求めに応じ、読後感を述べるにすぎない。
- 著者
- 沼田 裕之
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, no.56, pp.75-79, 1987-11-10 (Released:2009-09-04)
1 0 0 0 OA 森田尚人著『デューイ教育思想の形成』
- 著者
- 峰島 旭雄
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, no.56, pp.80-84, 1987-11-10 (Released:2009-09-04)
1 0 0 0 OA 藤 武著 『アメリカ幼児教育思想の研究』 デューイ思想を基軸として
- 著者
- 杉浦 宏
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, no.56, pp.85-88, 1987-11-10 (Released:2009-09-04)
1 0 0 0 OA 稲葉宏雄著『実験的知性の教育-デューイ教育思想研究序説-』
- 著者
- 斎藤 勉
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, no.55, pp.95-98, 1987-05-10 (Released:2009-09-04)
1 0 0 0 OA 蜂屋慶編『教育と超越』
- 著者
- 下山田 裕彦
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, no.55, pp.99-102, 1987-05-10 (Released:2009-09-04)
本書は、蜂屋慶氏 (京都大学名誉教授・光華女子大学学長) 退官記念論集である。編者の藤本浩之輔氏の「あとがき」によると、 (一) 一つのテーマのもとに、教育人間学研究のステップとなるような一冊にする。口執筆者は、蜂屋先生の謦咳に親しく接している者に限ること。 (三) テーマは、先生が主張されている教育における超越の問題とすること、という編集の意図によって本書は出版された。
1 0 0 0 OA 教育と教育を越えるもの ヤスパースにおける実存と教育
- 著者
- 吉村 文男
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, no.56, pp.1-14, 1987-11-10 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 10
人間が対象的に取り扱かわれることがますます一般的となり、一人一人のかけがえのなさがともすれば忘れられがちな現代において、教育の領域で、子どもや青年一人一人の個性の尊重とか、一人一人の子どもや青年を生かすといったことが主張されるのには、十分な理由があると思われる。ただ、そうした主張が有意義であるためには、「実存は、その自由の根底から、他の実存と本質的に相違している (wesensverschieden) 」といわれるような、他との比較を絶した自己自身としての実存という人間理解にまで至らねばならないのではないだろうか。小論は、そうした問題意識を背景にして、実存を哲学することの中心に置いたヤスパースの実存哲学から、教育を問いかえそうとする一つの試みである。
1 0 0 0 OA デューイ教育哲学における「個性 (individuality) 」の機能
- 著者
- 立山 善康
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, no.56, pp.15-28, 1987-11-10 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 52
本稿の目的は、デューイ (John Dewey1859-1952) の教育理論を、その哲学的人間観の基底において把え、そこには、一定の「個人主義的」な脈絡があり、「個性」こそが、教育という営為の能動性と受動性とを統合的に把える、デューイの人間主義的な教育の力動性を有効に展開させている一つの機能的な原理であるのを論証することにある。そこで本論では、まずデューイの「個性」の機能としての「動態的な自己 (dynamic self) 」の概念を検討し、ついで、こうした自己の「個性」が契機となって、自然や社会と相互媒介的に、共有されている意味を開示してゆく一定の脈絡を明らかにする。最後に、個性尊重の立場からはどうしても対峙せざるをえない学問中心主義の立場に触れ、そうした立場に前提されている知の「客観主義的な理想」に対する人間主義的な知識の成立基盤としての「個性」を、デューイの教育哲学における機能的側面から位置づけたい。
1 0 0 0 OA 現代教育における「信頼」の意義 M・ブーバーを中心に
- 著者
- 原 弘巳
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, no.56, pp.29-41, 1987-11-10 (Released:2010-05-07)
- 参考文献数
- 21
Though mutual 'trust' between the child and the educator is the prerequisite of education, it has never been the main topic of research. This paper aims at questioning the problem of 'trust' in depth in the light of the comtemporary situation by relying on M. Buber. Children can respond with their entire self to the demands of contemporary society only when in an eminent sense of trust between the child and the educator has been established. This trust can be understood at several levels. At each of those levels the educator especially must make a constant effort to trust the child, to trust oneself and the other being. In this effort the educator in turn, can be richly rewarded by the child. Therefore the quest for trust turning into the quest of mutual formation of the child and the educator must reach an ever deeper dimension. But this will be the object of further research.
1 0 0 0 OA 人間は技術的に対象化されうるか M・ハイデッガーを手がかりとして
- 著者
- 砂原 由和
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, no.56, pp.42-54, 1987-11-10 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 37
The purpose of this paper is, taking hints from Heidegger's thought, to examine the meaning of objectivating man technically, thus trying to advance to the point of questioning the essence of technology. The paper consists of the following parts.I. Looking at the tendency of contemporary technology to include in its objects not only simple matter, but also language and knowledge.II. According to the technology theory of Heidegger, all being (Seiendes) can become the object of technology. Hence, if man is also a being, he, too, can become technologically speaking an object.III. However, at the time when Heidegger wrote “Sein und Zeit”, he did not consider man as a simple being. IV. But in front of contemporary technology man is merely a being. When Heidegger realised this fundamentally, he indicated a new relation between the being (Seiendes) and to be (Sein).
1 0 0 0 OA 教育哲学を考える
- 著者
- 久木 幸男
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, no.56, pp.55-56, 1987-11-10 (Released:2009-09-04)
1 0 0 0 OA 山鹿素行の教育論について 武教を中心に
- 著者
- 内山 宗昭
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, no.56, pp.57-60, 1987-11-10 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 7
1 0 0 0 OA 教師による学習者理解の今日的意味
- 著者
- 清水 毅四郎
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, no.55, pp.24-28, 1987-05-10 (Released:2009-09-04)
1 0 0 0 OA 教師のジレンマと教育哲学の役割
- 著者
- 田代 尚弘
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, no.55, pp.28-32, 1987-05-10 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA 「人間」を尚ぶ思想の再構築
- 著者
- 松井 春満
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1987, no.55, pp.33-38, 1987-05-10 (Released:2009-09-04)
主題に対しては先ず、教育学と教育哲学のアプローチの仕方の違いを私なりに明らかにしておくことが必要であろうが、その前に、教育改革論議自体について少し述べておきたい。