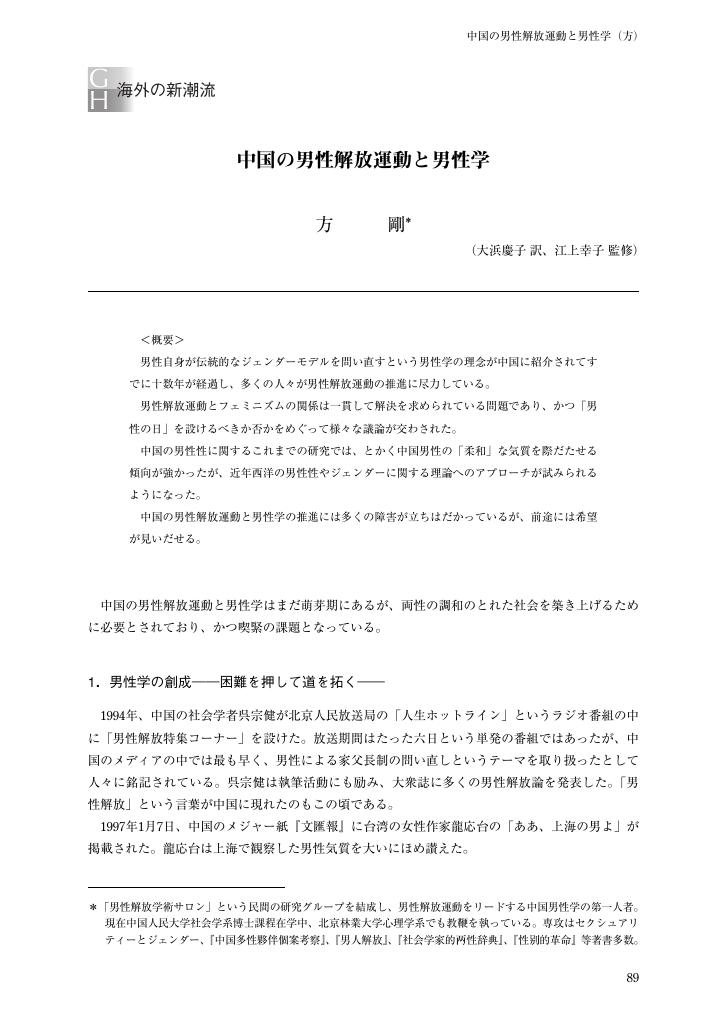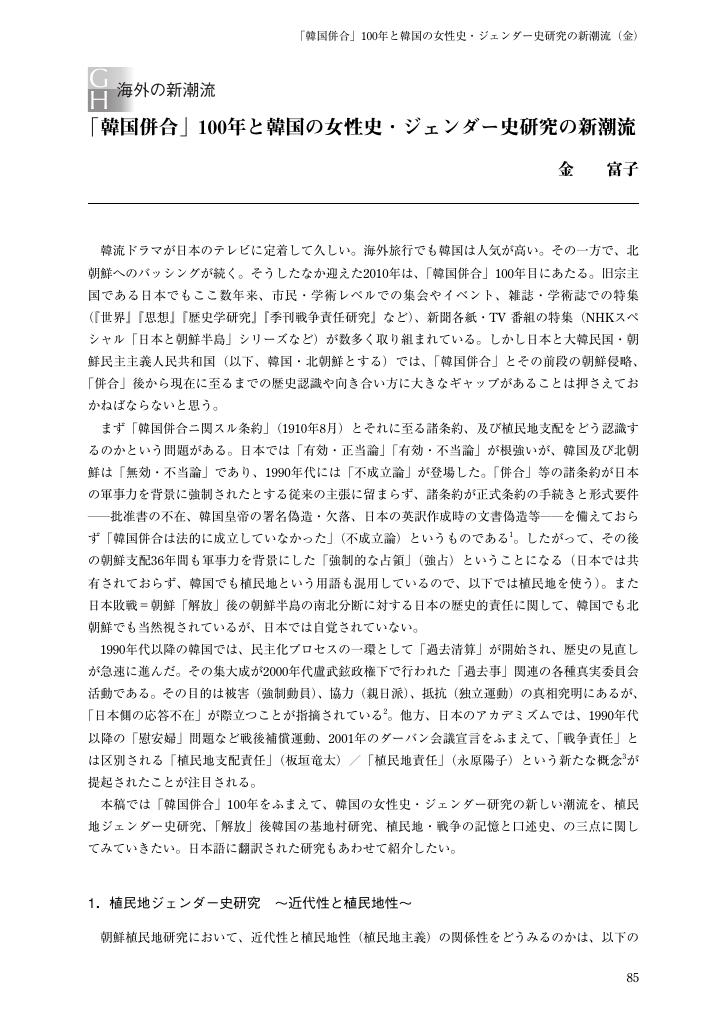- 著者
- 岩島 史
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.37-53, 2012 (Released:2013-11-30)
- 参考文献数
- 35
本稿は、戦後の民主化政策の一環として行われた生活改善普及事業を「農村女性政策」ととらえ、その政策展開の特徴を生活改良普及員のジェンダー規範を通して明らかにすることを目的とする。本稿の課題は、1950~60年代に農林省が発行した生活改良普及員の事例集の分析から、普及員が働きかける対象領域の設定にみられるジェンダー規範と、その領域設定の背後にある女性の役割に対する規範を明らかにすることである。事例集において、1950年代に最も多くとりあげられた「問題」は農村の「古さ」や女性の過労であったが、生活改善課題として最もとりくまれたのはかまど・台所改善と料理講習であり、食・台所の領域に偏っていた。これは普及員にとって台所が女性の苦難の象徴であったこと、そして普及員が女性であったために男性優位の農村のジェンダー秩序の中で口を出せる領域が限られていたためと考えられる。1960年代には主婦の労働時間の長さが「問題」とされたが、同時に家事をしないこと、子どもに気を配らないことも「問題」とされた。兼業化の進展によって農村女性は農業生産の主要な担い手となっていたが、普及員は主婦を「家庭管理の責任者」と位置づけた。これは、農業のみならず社会や家族関係の近代化を目標とする基本法農政と、人口学的に女性の「主婦化」が進んでいた時代背景とに起因すると考えられる。生活改善普及事業の展開の特徴として、1950年代は家事労働の効率化、無駄の排除、農繁期の生活調整が農林省の設定した目標であるが、女性である普及員を介在することで農村のジェンダー秩序が政策理念を制限した。1960年代には、農林省は健康維持、生活の合理化、育児と家庭教育、家族関係の民主化を改善目標として設定し、個々の農家の範囲を超えて地域社会での生活改善がめざされたが、家庭管理に重点をおく普及員のジェンダー規範によって政策理念は転換されたといえる。
3 0 0 0 OA 低所得者への食料支援とジェンダー ――大恐慌期のアメリカにおけるフードスタンプ制度――
- 著者
- 佐藤 千登勢
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.17-29, 2022-10-14 (Released:2023-10-13)
- 参考文献数
- 34
アメリカでは今日、連邦政府による貧困対策としてさまざまな所得維持政策が実施されているが、なかでもフードスタンプ制度1は、4,150万人(人口の12%)が参加する最大規模のプログラムとなっている。この制度は、農務省の食料・栄養サービス局が管轄しており、原則として所得が貧困線(2021年に3人家族で年収約2万2,000ドル)の130%以下であれば、年齢や子どもの数、健康状態などに関わらず、だれでも参加資格を得られる。平均受給額は、1世帯で月444ドル、1人当たり233ドルであり、フードスタンプを用いて、酒類とタバコ以外のあらゆる食料品を購入することができる。フードスタンプ制度は、重要なセーフティーネットとしてアメリカ社会で広く受け入れられている。その理由としては、低所得の家庭の子どもを飢餓や低栄養から救い出す役割を果たしていると評価されていることや、フードスタンプが農産物や食料品の消費拡大に貢献しているため、農業団体や食品業界が強く支持していることがあげられる。フードスタンプ制度は、農務省の下で、現金ではなく食料品の購入に特化したスタンプを支給しているという点において、他の社会福祉プログラムとは異なる特殊な性格を有している。生活困窮者が支給されたスタンプを用いて消費行動をし、それによって食生活を向上させるという仕組みは、大恐慌による余剰農産物の処理との関連で1930年代に考案された。本稿では、こうしたフードスタンプ制度の歴史的な起源を、消費行動の主体とされた貧困女性に着目しながら検討し、プログラムに内在していたジェンダー規範を明らかにしていく。消費と結びついたフードスタンプ制度をジェンダーの視点から見ることで、福祉国家の多様なあり方やアメリカ的な特殊性を考察することが本稿の目的である。これまで、フードスタンプ制度については、政策史や経済的な効果といった観点からいくつかの研究がなされてきた(Waugh, Hoffman, Gold 1940; Herman 1940; Herman 1941; Harvey 1941; Kreager 1942; Coppock 1947; Poppendieck 2014)。また、フードスタンプと消費に着目し、食品業界を中心とした経営者団体との関連でフードスタンプ制度を論じた研究もある(Moran 2011)。しかし、消費の主体としての貧困女性の役割やジェンダー規範を検討した研究はこれまでなされていない。本稿ではまず第1 節で、大恐慌の到来により飢えが社会的な問題として捉えられるようになったことを論じ、第2節で、1933年以降、フランクリン・D・ローズヴェルト政権の下で余剰農産物の処理と貧困者を対象にした食料支援が結びつけられたことを見ていく。第3節では、余剰農産物の配給制度が持つ弱点を克服するためにフードスタンプ制度が導入され、消費者として貧困女性が前景化されたことを明らかにする。第4節では、栄養学との結びつきを論じ、農務省家政局の下で、貧困女性がフードスタンプで入手した食材を用いて、栄養学的な知見に基づいた料理を習得することが期待されたことを検討していく。
2 0 0 0 OA 天皇を「生ましました」産婆 ─産婆・岩崎直子にみる天皇家と産婆職─
- 著者
- 木村 尚子
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.21-35, 2012 (Released:2013-11-30)
- 参考文献数
- 54
岩崎直子(1868-1950)は、明治政府による新しい産婆教育のもとで養成された産婆として、はじめて天皇家にかかわった産婆である。彼女は、のちの大正天皇の子四人の出生介助にあたり、これによって産婆界内外で特異な地位を手に入れる。1910年代から1920年代は産婆職の興隆期であり、また正常産に介入する医師との間に競合が増す時期である。本稿は、岩崎という一人の産婆の著述を軸に、産婆が、天皇家とのかかわりを強調することで自らの権威を高めようとする経緯を明らかにする。岩崎は、その持ち前の熱意に加え、幼い子どもと夫を相次いで失ったことから産婆職に情熱を傾け、妊産婦に啓蒙を図るほか、産婆団体においても指導的立場に立つ。この時期、衛生行政からの要請と大正デモクラシーを背景に産婆の職能集団が形成され、さらに産婆たち自身が、その職の権益を守り業務の独自性を主張して産師法(産婆法)制定運動と呼ばれる運動を展開しはじめる。岩崎はこの運動において天皇家との関係を精神的支柱とし、さらにそれは、その後の戦時下人口管理体制のもとに産婆・助産婦を集結するにあたり大きな効果を及ぼしていく。天皇を「生ましました」産婆・岩崎は、1910年代半ばの新中間層に天皇家の母に象徴される「母性」への関心を「生まし」、また続く1920年代には、天皇を頂点とする国家に「御奉公」する産婆やその職能団体を「生ましました」産婆であった。岩崎にとって産婆職は生計を立てる手段という以上の大きな意味をもち、天皇家に関与したことは彼女の誇りや自信であった。同様の努力、あるいは総体としての産婆職の資質向上を、岩崎が必須と感じたのは無理からぬことであった。岩崎が主導した産婆の運動は男性医師や衛生官僚に対抗する女性の権利確立を目指すものであったが、同時に彼女の主張は、その職を通じて天皇家を支え、そのことによって産婆や妊産婦らに天皇家の存在意義を強く印象づける役割を果たしたのである。
2 0 0 0 OA 岩手におけるウーマンリブの思想と活動 ─麗ら舎の〈おなご〉たちのライフストーリーから─
- 著者
- 柳原 恵
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.55-73, 2012 (Released:2013-11-30)
- 参考文献数
- 59
本稿では岩手に「内発」したリブの存在とその思想の内実について、当事者のライフストーリーを中心として考察する。岩手の農村部において性差別への批判的視座を持ち活動してきた人物の一人としてまず、女性達の読書・学習サークル「麗ら舎読書会」を主宰する詩人・小原麗子(1935-)を取り上げ、麗ら舎設立までの経緯をライフストーリーから追う。小原は経済的に自立し、読み書きできる時間と場所を持つことを指す「自活」を目指してきた。小原らの活動の舞台となる麗ら舎は、小原の「自活」が実現できる場として設立された。小原と活動を共にしてきた読書会会員・石川純子(1942-2008)は、民主的な家庭の中にあるジェンダー構造を問題化した。岩手は封建的「家」と近代的「家庭」が並存している地域であり、こうした地域性がリブ思想を醸成する契機ともなった。石川と小原は「家」と「近代家族」の連続性を看破し、共通する問題からの解放を模索していった。石川は女性の身体とセクシャリティをめぐる問題にも取り組んだ。「孕み」と「お産」を通じて自分を東北の「農婦」であると認識し、疎外された〈女〉の経験と身体性を取り戻そうとする。その思想は、都市部のリブとも通じるが、決定的な差異は取り戻す対象として「東北」という場所性が含まれることである。麗ら舎読書会の主軸の一つに、戦没農民兵士とその母を弔う千三忌がある。千三忌は性差別・植民地主義などの複合差別の様相を認識し、それを乗り越えようとする小原の思想を背景として開催されている。以上、小原と石川は〈女〉であることを起点とし、民主的「家庭」が内包する抑圧性を批判し、女の身体性と母性を問い直し、複合差別への抵抗を実践してきた。近代が作り上げてきたジェンダー構造を疑問視し、問い直していく彼女らの思索と活動は岩手におけるリブであると評価できる。
- 著者
- 西野 瑠美子
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.67-73, 2013
2 0 0 0 OA 高等女学校における「衛生」と身体への管理 ――「女子特別衛生」が意味したもの――
- 著者
- 斉藤 利彦
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.55-65, 2017-10-20 (Released:2018-11-01)
- 参考文献数
- 25
近代日本における「衛生」の導入が、国民国家の形成にいかなる役割をはたしたのか、そしてそれがどのように身体への管理に結びついていったのかについては、すでに様々な視点からの研究が蓄積されている。ところで、戦前期の高等女学校や女子師範学校で行なわれていた「女子特別衛生」は、これまでの先行研究では全く取りあげられてこなかった。その対象は女学校という発達段階の特性から、特に「月経」に焦点化されていたが、具体的にどのような実態をもち、いかなる背景と論理をもって生み出されたものであったのか。それは、女生徒の身体への管理ととらえられるべきものなのか、あるいは月経時の女生徒の身体への保護を目的とした正当で必要な配慮というべきものなのかが明らかにされなければならない。その際、この「女子特別衛生」が、個々の高等女学校で個別的に案出されたものではなく、明治30年代における国家による月経への着目という事態の中で成立したものであったということが重要である。本稿では、1900(明治33)年の文部省訓令第六号による月経への取扱方を分析し、それが各地の高等女学校での「特別衛生心得」の制定へと具体化されていった実態を明らかにする。そこに現れていたのは、「良妻賢母主義」の身体的具体化であり、「 衛生」の啓蒙と脅迫的なトーン、そして月経時の過剰な指導であった。さらに、1919(大正8)年の文部省による全国調査「月経に関する心得方指導、月経時に於ける生徒の取扱」の検討を行う。そこでは、国家的規模での詳細な月経への調査が実施され、教師による日常的な観察を通して、何が「正常」な月経で、何が「異常」なのかを国家と学校が規定する、いわば他律的な「規格化」が行なわれていたのである。はじめに近代日本における「衛生」の導入が、国民国家の形成にいかなる役割をはたしたのか、そしてそれがどのように身体への管理に結びついていったのかについては、すでに様々な視点からの研究が蓄積されている。
2 0 0 0 OA 「イスラームと女性」研究の新動向 ─東南アジア・インドネシアから─
- 著者
- 服部 美奈
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.97-104, 2012 (Released:2013-11-30)
- 参考文献数
- 29
2 0 0 0 OA 現代台湾における女性運動の動向 ―「性権派」と「婦権派」の対立を中心に―
- 著者
- 黄 齡萱
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.87-93, 2007 (Released:2011-11-01)
- 参考文献数
- 15
2 0 0 0 OA 中国の男性解放運動と男性学
- 著者
- 千葉 慶
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.5-19, 2017-10-20 (Released:2018-11-01)
- 参考文献数
- 14
現在、「戦後民主主義」は危機に瀕しているが、わたしたちはまだ、「戦後民主主義」とは何なのか、何を受け継いでいくべきかを適切に検討できてはいないのではないか。本稿は、以上の問題意識に立ち、「戦後民主主義」表象の中でも、もっとも影響力を持った表象の一つである『青い山脈』を取り上げ、そこに何が「戦後民主主義」の要素として刻まれたのかを抽出し、同作品のリメイクおよび同一作者原作映画の中にその要素がどのように時代を経て、変容を伴いながら受け継がれていったのかを考察することによって、「戦後民主主義」の受容形態の一端を確認し、かつ、今何を「戦後民主主義」の遺産として継承すべきなのかを考える契機とするものである。『青い山脈』が、「戦後民主主義」のエッセンスとして描いたのは、第一に「自己決定権の尊重」であり、第二に「対話の精神」「暴力否定」である。前者は、1980年代に至るまで一貫して描かれてきた。他方、後者には1960年代以降、疑義が唱えられるようになり、特に「暴力否定」についてはほぼ描かれることはなくなってしまった。ただ、これをもって「戦後民主主義」が衰退したとすべきではない。この推移は、「対話の精神」を突き詰め、より時代に見合った民主主義の作法を模索した結果ともいえるからである。また、ジェンダー史的観点からすると、今回取り上げた作品群には、一様に男性優位、女性劣位のジェンダー構造に固執した表現が目についた。ただし、すべてがこのような限界性に囚われているとするのは早計である。なぜならば、作品群の精査によってそれらの中に、暴力性を拒絶する男性像や、男性優位の構造を内破しようとする女性像の描写を見つけることができたからである。今、わたしたちがすべきことは、「戦後民主主義」を時代遅れのものとして捨て去ることではなく、長い年月の中ではぐくまれてきたその可能性を見出し、受け継いでいくことではないだろうか。
2 0 0 0 ジェンダーの視点から見た韓国民主化
- 著者
- 宋 連玉
- 出版者
- The Gender History Association of Japan
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.5-22, 2013
朴正煕独裁体制の崩壊には70年代の女性労働者の闘いが大きな役割を果たした。1980年代には70年代の民主化運動の潮流を受けて、知識人を中心とした女性運動が幅広く展開され、民主化運動の一翼を担った。<BR> 1987年の民主化宣言と同時に、女性諸団体を統括する韓国女性団体連合が結成され、男女雇用平等法の実現にこぎつけた。<BR> 1990年代に入るとさらに制度的民主主義が進捗、ジェンダー政策においても、北京の世界女性会議の精神を受け継ぎ、性差別撤廃のシステム作りを推進した。<BR> 1987年に民主的な憲法が採択され、5年ごとの直接大統領選挙が決まると、女性たちは大統領選挙を活用して、候補者に女性政策を選挙公約に掲げるように圧力を加えた。<BR> それが功を奏し、金泳三政権(1993~1997)では女性発展基本法の制定、金大中政権(1998~2002)では女性政策を主管する女性部が創設され、第1代、第2代長官に女性運動のアクティビストが抜擢された。また2000年には女性議員数のクォーター制が導入され、5.9%から2012年には15.7%にまで女性議員比率が伸びた。同じく女性公務員もクォーター制導入により飛躍的に伸びた。<BR> 1962年から展開されてきた家族法改正運動も民主化以後に大幅改正され、2005年には遂に戸主制撤廃にこぎつけた。女性の再婚禁止期間の廃止など、日本の家族法より先行する内容も盛り込まれた。<BR> 2004年には性売買に関連する二法が制定され、性売買が不法であるという認識を確立した。<BR> ジェンダー主流化のための制度的保障はある程度なされたが、残された課題も多い。IMF経済危機を克服するために進めた構造改革は結果的に貧富の格差を大きくし、とりわけ女性間の格差を拡大し、非正規雇用の女性たちに負担を強いている。<BR> また、南北分断による徴兵制の維持が、性差別是正の妨げとなっている。兵役義務を果たした男性に公務員試験受験で加算点を与える制度は1991年に廃止されたが、保守政権のもとで再びこれを復活する動きがある。
2 0 0 0 ジェンダーの視点から見たミャンマーの民主化プロセス
- 著者
- 土佐 桂子
- 出版者
- The Gender History Association of Japan
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.23-38, 2013
本稿は、ミャンマーの民主化運動を1988年の民主化運動勃発から現在に至るまで続く民主化プロセスととらえ、この一連のプロセスを、ジェンダー視点からとらえなおすことが目的である。民主化運動勃発時期には、まず一党独裁政権をいかに止めるか、民主主義をいかに育てていくかに重点が置かれ、特にジェンダーに関する議論は生じていない。ただし、ジェンダー視点が重要でないわけでなく、軍事政権時代に入り政府はミャンマー母子福祉協会、ミャンマー国家女性問題委員会等の女性組織を作り、重職に軍人の妻たちを配置した。これはアウンサンスーチーをはじめ国民民主連盟(NLD)らの女性動員力を意識し、その取り込みが図られていたことを示す。一方、NLDはスーチーの自宅軟禁や党員の逮捕など厳しい弾圧のなかで、情報発信や影響力は限られたものとなりがちであった。これを補っていたのが、亡命した民主化運動家、元学生たちが海外で作った女性団体と考えられる。彼らは出稼ぎや国内から逃れてきた女性を支援しつつ、国際社会と国内に情報と見解を発信してきた。2000年代に入ると、こうしたディアスポラによる外部団体や国際NGOとの連携で、ススヌェという村落女性が政府関係者を告訴し、政府への法的な抵抗が行われた。また、国内でも仏教を核とする福祉協会など、草の根レベルからのNGOや緩やかなネットワークが形成され、軍事政権下で手薄になったとされる福祉政策、特に女性、子供、貧困者や災害被害者等弱者支援を補完したと考えられる。一方、テインセイン大統領に率いられる現政権は次々に改革を行い、検閲制度が撤廃され、言論の自由も相当確保された。また、補欠選挙にNLDが参加し、アウンサンスーチーをはじめ女性議員が増加し、女性閣僚も誕生した。今後、スーチーが参加の意向を示す次期大統領選の行方はジェンダーという観点から極めて重要である。また、前掲草の根レベルのネットワークやディアスポラによる女性団体の活動を、今後国内のジェンダー政策がどれほど組み込めるかも課題となろう。
2 0 0 0 植民地支配とジェンダー:──朝鮮における女性植民者──
- 著者
- 広瀬 玲子
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.17-32, 2014
1945 年の敗戦時日本帝国の支配は東アジア・東南アジア・太平洋地域に及んでいた。朝鮮半島もその一地域である。そこに約75 万人の日本人が移動・定着して家族を形成し、植民地での特権的生活を送った。35 年間の植民地支配の過程で、植民者一世・二世(あるいは三世)という世代形成がなされた。<br>本稿は、朝鮮で植民者として暮らした日本女性に焦点を当てた。被植民者に対し抑圧者・支配者であった女性に関する研究は少ない。まず、朝鮮における日本女性の人口・職業構成を明らかにし、彼女たちの植民地での位置を概観した。続いて、女性たちのあり様を、一世の経験としての愛国婦人会の結成と活動を通して考察する。朝鮮における愛国婦人会の結成は併合以前の1906 年であり、それも内地の愛国婦人会結成と歩みを揃えて行われた。これは日本の支配層が植民地化推進に女性の力を不可欠としたことを示している。愛国婦人会は「文明化の使命」の理念を掲げ、朝鮮王室や支配層の女性の多数を組織しながら活動を展開していった。<br>さらに女性たちのあり様を、二世の経験としての女学校生活という側面から明らかにした。具体的には京城第一公立高等女学校生の植民地経験をとりあげた。朝鮮で生まれ育った彼女たちは高等女学校生として「幸せな」学園生活を送るが、それは支配者としての特権の享受のうえに成り立っていた。彼女たちの大半は、自らが「植民者= 侵略者」であるという自覚なしに生活した。そこには支配を支配と感じさせない暴力、被植民者を不可視化する暴力が働いていていた。日本の敗戦により、「自分が侵略者であった」とつきつけられ、引揚げたのちに、内なる植民地主義をいかに解体するのかが課題となるが、いまだに果たされたとは言えない。<br>さいごに、少数ではあるがこの課題に応えようとする女性植民者の事例を紹介し、植民地主義解体の可能性について考察した。
- 著者
- 平井 和子
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.5-16, 2014
2001 年の「9.11 事件」に端を発する、対イラク戦争開始に当たって、ジョージ・W・ブッシュ大統領は、過去の数ある占領の中から、民主化の成功例として「日本モデル」を取り出して、占領を正当化しようとした。攻撃に際しては、「女性解放のため」という理由が付け加えられた。これを、わたしは日本の女性史研究が大きく問われていると受け止めた。<br>アメリカによる日本占領をひとたび、敗者‐勝者の男性間で取引された女性たち(占領軍兵士へ「慰安」の提供をさせられた売春女性たち)の体験から見直せば、軍事占領と女性解放を安直につなげることの矛盾は明らかである。具体的にいえば、敗戦直後、日本政府によってつくられたRAA(Recreation and Amusement Association)などの占領軍「慰安所」や、冷戦期に激化した基地売春下で、女性たちが強いられた性管理の実態は、日米合作による軍隊維持のための組織的性暴力であった。<br>さらに、売春禁止運動を担った廃娼運動家や女性国会議員・地域婦人会の女性たちと、売春女性たちの間には大きな分断があり、これが米兵の買春行為と矛盾しない売春防止法を生み出す要因の一つとなった。つまり、二分化された女性たちの対立と反目が、結果として軍事化(日米安保体制・軍事基地)を支えることにつながった。ここに、女性を、「護られる女性=『良家の子女』」と、売春女性(「転落女性」「特殊婦人」)に二分化する男性中心的な「策略」の罠がある。米兵の買春行為の激しさは、朝鮮戦争勃発とリンクする。そのため、軍事組織は売春女性を「活用」して、兵士の性をこそコントロールする必要があったのである。
- 著者
- 髙橋 裕子
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.5-18, 2016
<p>本稿では、2015年12月に開催されたジェンダー史学会年次大会シンポジウム「制度のなかのLGBT- 教育・結婚・軍隊」での報告を纏めるとともに、セブンシスターズの5女子大学が女子大学としての大学アイデンティティを重視しながらも、もはや「女性」という「性別」を一枚岩的に捉えることができなくなってきた現状を紹介する。さらに、とりわけ誰に出願資格があるのかを決定する判断の背景にある、女子大学自体の大学アイデンティティの問題を考察しつつ、2014年から15年にかけて発表された新たなアドミッションポリシーを概観した。この問題は、いわば21世紀に女子大学が直面しているもう一つの「共学」論争とも言える。20世紀後半に経験した「共学」論争との違いはどこにあるのか、その点にも着目しながら、性別二元論が女子大学における入学資格というきわめて現実的な問題としてゆらぎをみせていることとともに、米国における今日の女子大学の特色をあぶり出すことを試みた。</p><p>トランスジェンダーの学生や、ノンバイナリーあるいはジェンダー・ノンコンフォーミングというアイデンティティを選び取る学生が増えていることは、女子大学が、「常に女性として生活し、女性と自認している者を対象とする」高等教育機関であるとあえて明示しなければならなくなったことに反映されている。それにも拘わらず女子大学のミッションが、すなわちその必要性や存在意義がよりいっそう強く再確認されていることに注目した。女性が社会で、そして世界で、多様な分野で参画できる力と自信を、大学時代に身に付ける場として、女性がセンターに位置づく経験をする教育の必要性が、このトランスジェンダーの学生の受け入れを巡ってのディスカッションを通していっそうクリティカルに再確認されたとも言える。</p><p>大学教育という実践の場において、ジェンダー的に周縁に位置するセクシュアルマイノリティの学生をめぐって、アドミッションポリシーを文書化し、具体的に「女子大学」と名乗るのかどうか、さらには「よくある質問(FAQ)」で「女性とは誰のことなのか」という質問に詳細にわたって回答し、ジェンダー的に流動的な(gender fluid) 学生に対応しているこの局面に、21世紀のアメリカにおけるセブンシスターズの女子大学が果たしている新たな先駆的役割を見て取れる。</p>
2 0 0 0 「原子力の平和利用」と近代家族
- 著者
- 加納 実紀代
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.5-19, 2015
<p>日本の原発導入は、1953 年12 月のアイゼンハワー米大統領の国連演説「原子力の平和利用」に始まるが、その年は日本の「電化元年」でもあった。テレビ放映が始まり、家庭電化製品が相次いで売り出された。54 年3 月には「原子力の平和利用」は国策として動き出すが、それにともなって電化ブームがおこり、55 年にはテレビ、電気洗濯機、電気冷蔵庫が「三種の神器」としてもてはやされる。</p><p>その背景には、占領下において流布した原爆の威力への肯定的評価やアメリカ文化の紹介によってかき立てられた電化生活への憧れがあった。1952 年4 月の独立後、原爆の人体への被害が報道されるようになるが、物理学者武谷三男は被爆国だからこそ「平和利用」すべきだという原発推進の論理を展開、『読売新聞』を中心とするマスメディアも、アメリカと協力して「平和利用博覧会」を主催するなどキャンペーンにつとめた。</p><p>その一方、54 年3 月のアメリカの水爆実験によるビキニ事件をきっかけに、女性を中心に原水爆禁止署名運動が盛り上がり、55 年8 月には国民の3 分の1 以上という多数の署名が集まっている。原発導入と原水爆禁止運動は両立・同時進行したことになる。</p><p>それを可能にした一因として、「原子力の平和利用」という経済発展は男性、原水爆禁止という平和運動は女性というジェンダー分業があげられる。電化生活による近代化、産業構造の高度化により、社員・主婦というジェンダー分業を柱とする近代家族が普遍化したが、それは家庭内にとどまらず、進歩・発展は男性、ケアや後始末は女性という社会的分業をも定着強化した。</p><p></p>
- 著者
- 嶽本 新奈
- 出版者
- The Gender History Association of Japan
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.43-53, 2011
開国以降に海外へ出稼ぎに行った女性たちを「からゆき」と総称するが、「からゆき」の渡航に際してどのような人間が関わっていたのかを当時の九州メディアである『福岡日日新聞』、『門司新報』、『東洋日の出新聞』3紙を用い、主に「密航婦」検挙に関する記事から渡航幇助者を抽出したうえでジェンダーと役割を検討した。その結果、渡航幇助者の多面的なネットワークと、そこでの男女の役割の異同が明らかになったが、まず、渡航幇助の役割上では周旋業と国外就航船乗船までの宿泊場所提供に関しては男女の別なくどちらも役割を担っていた。一方、ジェンダー的役割に注目すると、「からゆきさんあがりの誘拐者」が自分の身をもって経済的に「成功」した実例とすることで渡航を促す役回りであったり、奉公口探しは主に同郷出身の同性に依頼するという縁故利用の習慣によって、女性という〈性〉が機能する役割があったことを確認できた。こうした属性は個々に独立したものではなく重なることもあり、女性たちが〈出稼ぎ〉目的の渡航をする際のネットワークの端緒にこのようなジェンダー的役割が組み込まれていたからこそ、数多くの女性たちが海を渡っていったといえる。<BR>このことは誘拐者とは男性であり加害者であり、「からゆき」とは女性であり被害者であるといった一面的な捉え方を排すが、同時に、女性がいかなる役回りで渡航幇助に関わっていたのかを見極める必要がある。女性もある種の加害性を帯びているのかに関しては、紙面の都合上、表象レベルにおいて新聞報道が男性幇助者と女性幇助者とでは異なり、とりわけ「からゆきさんあがりの誘拐者」は自身の過去を別の密航婦に引き継ぎしているに過ぎない受動的な主体として表象されており、その点で女性は女性の抑圧者になりきれていないことを指摘するに留めておく。
1 0 0 0 OA 共感の女性君主 ――ヴィクトリア女王が拓いた可能性――
- 著者
- 井野瀬 久美惠
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.5-19, 2020-10-20 (Released:2021-09-01)
- 参考文献数
- 37
As we saw in the enthronement ceremony in 2019 as well as the abdication message of the Emperor (now Emeritus) in 2016, the phrase “always staying together with the people” is characteristic of the Japanese constitutional system called symbolic monarchy. But we must be careful in interpreting what that phrase really means to the Emperor system in Japan.This paper will discuss this phrase in reference to the change in the British constitutional monarchy, partly because the British monarchy was and has been an ideal or model for the Japanese symbolic monarchy after 1945, and partly because both Emperors, Hirohito and Akihito, once confessed that they had been influenced by the British constitutional monarchy, particularly that of King George V (1910-1938). The important point is what types of monarchy George V had inherited under a constitutionally organized government from his father, Edward VII (1901-1910).In Britain, the phrase “staying together with the people” or “sympathy to the people” became widely applied to the monarchy during the reign of Queen Victoria (1837-1901), especially after the mid 1870s. This is usually discussed in relation to the idea of “the invention of tradition”, represented by the Golden (1887) and Diamond Jubilee (1897) of Queen Victoria. But the critical moment resulting in “the invention of tradition” and changing the essence of the monarchy, was during the 1860s, when the British monarchy lost one future that might have existed by the sudden death of the Queenʼs beloved husband, Prince Albert, and the Queenʼs withdrawal from public life to mourn him. This period led Walter Bagehot to write his farsighted essay on monarchy which was to be collected in his famous book, the English Constitution (1867). In addition, the peopleʼs feeling towards the monarchy also dramatically changed at that time. Since then, the importance of the monarchʼs popularity, as well as the sympathy between a monarch and the people, has grown.The monarchy the two Japanese Crown Princes observed while they visited Britain, in 1921 and 1953 respectively, and thought ideal under the new Japanese Constitution when they were Emperors, had been the one personalized and de-masculinized, even if we do not call it “feminization of the monarchy”.
1 0 0 0 OA 「韓国併合」100年と韓国の女性史・ジェンダー史研究の新潮流
- 著者
- 金 富子
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.85-91, 2010 (Released:2011-10-01)
- 著者
- 伊東 久智
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.5-18, 2019-10-20 (Released:2020-11-21)
- 参考文献数
- 28
This paper focuses on the “cultural cradle” that gave rise to a distinctive idea of masculinity and counter-culture as seen in records of day laborers’ own monologues preserved in a collection of workers’ diaries. The main material for the paper comes from the ‘Diaries of day laborers’ (total of two volumes) collected and compiled by the Bureau of Social Affairs of the city of Tokyo in the early Showa period. As for the masculinity of day laborers, the peculiar “expression” style was symbolized in discourses on “drinking, gambling, and prostitution.” On the other hand, in order to grasp the day laborers’ expressions of masculinity in relation to the totality of masculinity, this paper focuses the discussion on the “cultural cradle” = various elements that promoted these “expressions”. Concretely, this paper examines (1) the actual conditions of daily laborers and their consciousness, (2) their awareness of “others”, and (3) the forms of entertainment and culture favored by day laborers, correlating the various factors.The results can be summarized in the following three points. First, what formed the “cultural cradle” of the masculinity and counter-culture of day laborers was the ambivalent consciousness of “frightened” and “resentment” leading to an inverted form — “frightened masculinity (frightened but masculine)”. This consciousness was formed during the depression years and in “not sociable” relationships with “others” such as intermediate contractors, Korean laborers and women. Second, the appeal of this counter-culture was not constant. We can see this in the fact that there were a significant number of day laborers with academic backgrounds who tried to stand outside of the counter-culture as well as the Korean laborers who also stood outside of this counter-culture. Third, the “cultural cradle” of their masculinity was amplified or eliminated in the context of femininity. This can be clearly seen from their reactionary remarks against “Modern girls” and the reality of a form of “sociable” entertainment called “Yasugi-bushi” which was popular among day laborers.