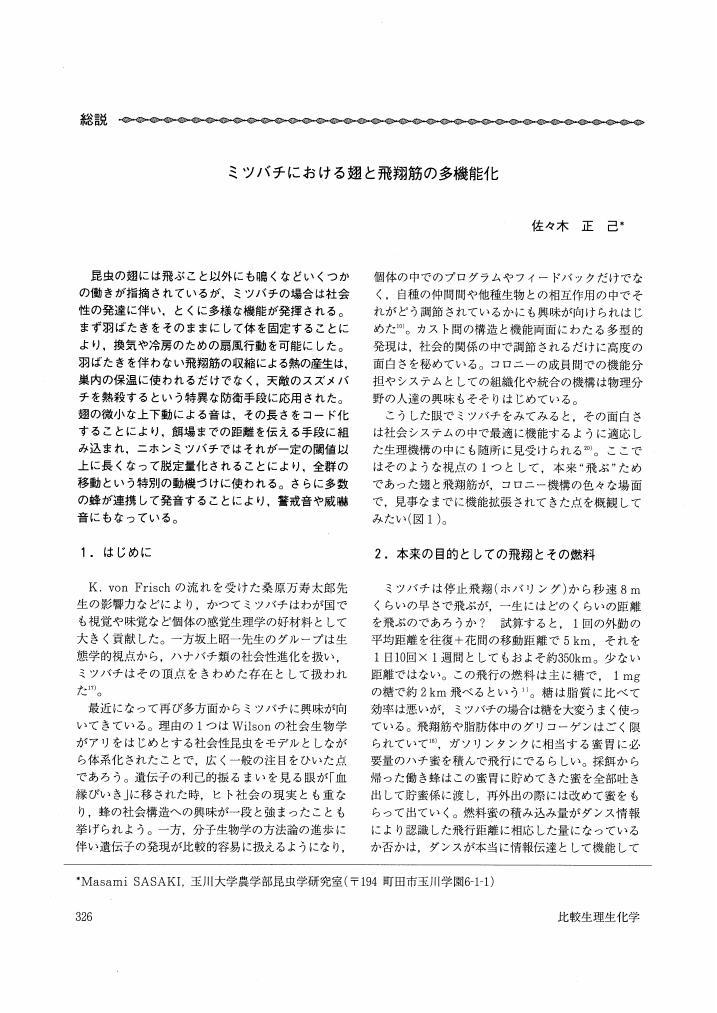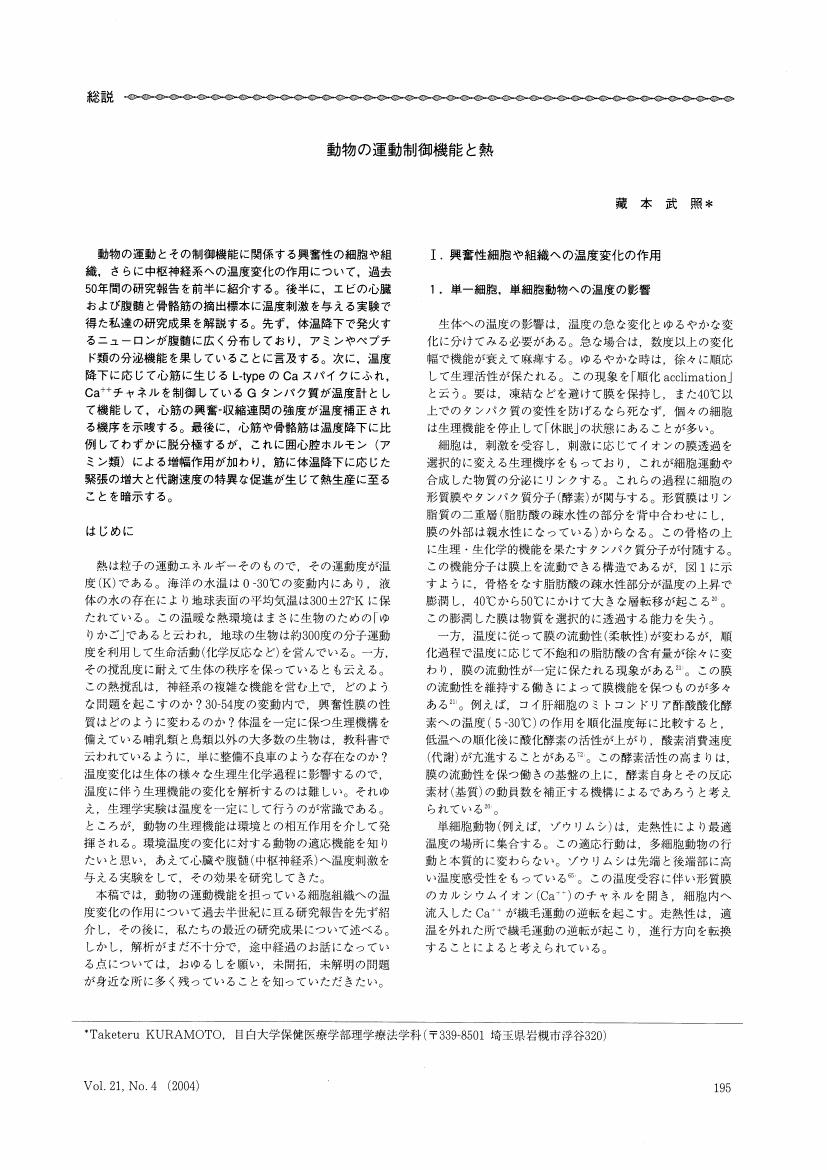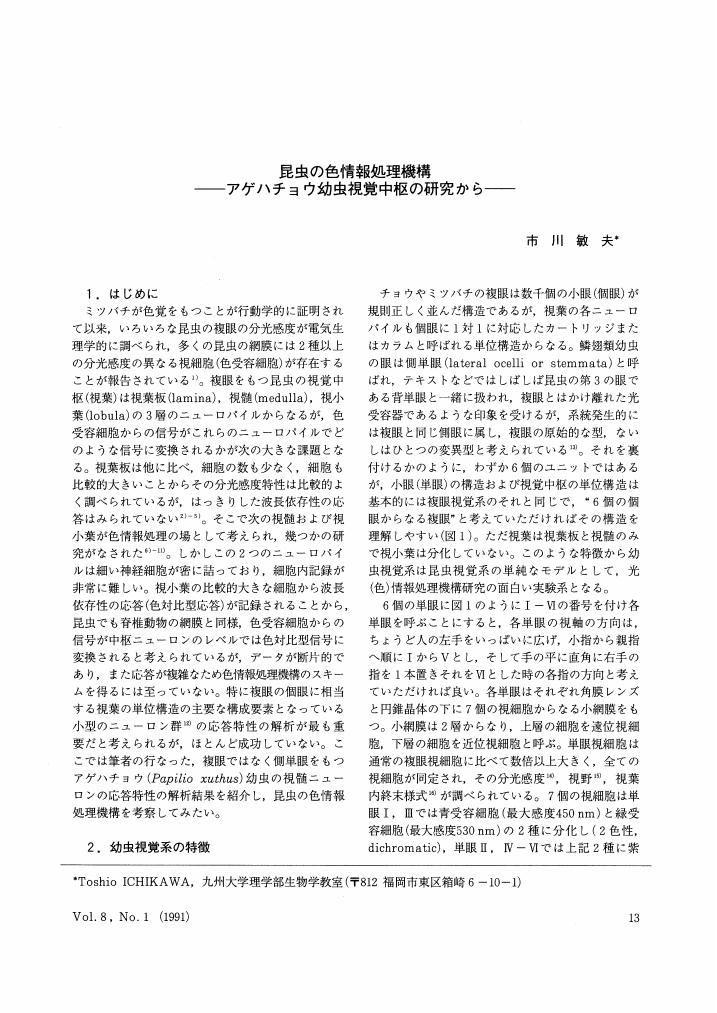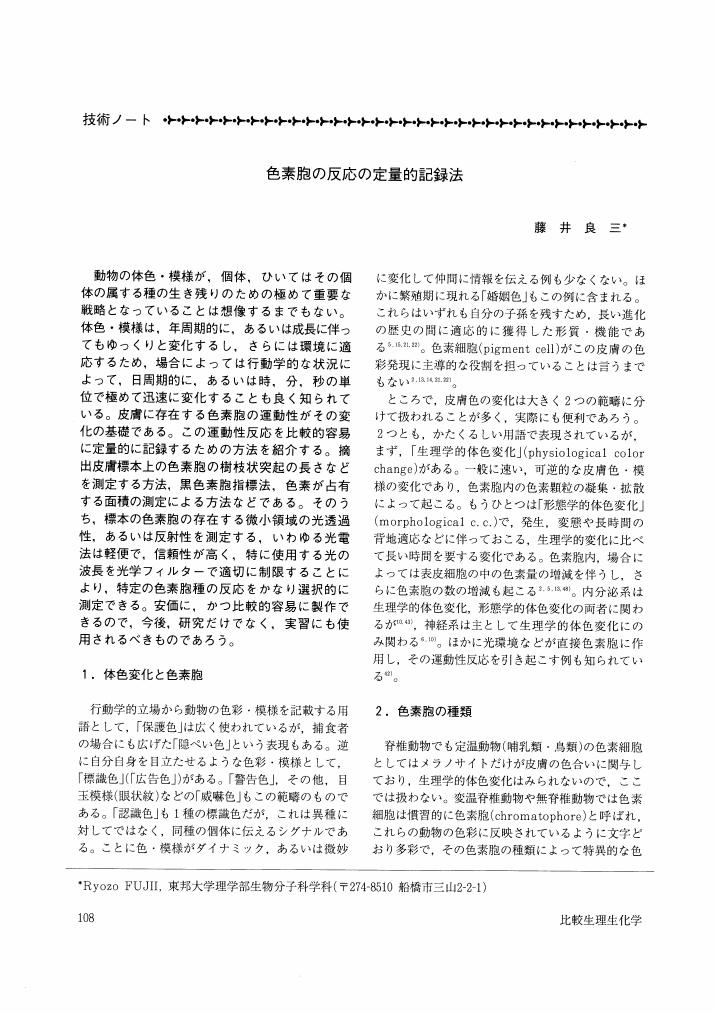1 0 0 0 OA QTL解析: 基礎理論と行動遺伝学への応用
- 著者
- 石川 明 鈴木 亨 海老原 史樹文
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.49-58, 1998-03-10 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 4
- 著者
- 寺北 明久
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.3-9, 2006-01-30 (Released:2007-10-05)
- 参考文献数
- 27
脊椎動物の視覚の光受容体ロドプシンは, G蛋白質共役型受容体 (GPCR) の一種であり, 唯一3次元立体構造が決定されるなど, GPCRの中で最も研究の進んでいる蛋白質の1つである。一方, 他のGPCRがアゴニストと呼ばれる外来性の化学物質 (ホルモンや神経伝達物質) を結合して活性化されるのと対照的に, ロドプシンは分子内にインバースアゴニスト (アンタゴニスト) と呼ばれる不活性化物質11-シス型レチナールを結合しており, 光エネルギーを使ってそれをアゴニストである全トランス型レチナールに変換して活性状態になる。著者らは, 頭索動物ナメクジウオの光受容体が, 脊椎動物のロドプシンと同様にアンタゴニストと結合して光で活性状態になるのみならず, アゴニストである全トランス型レチナールを直接結合して活性化される能力も持っていることを発見した。このロドプシンが示す一般のGPCR様の性質と光受容体としての性質とについて詳細に解析した結果, ロドプシンの分子進化過程で備わった視覚の暗ノイズを低下させるための分子機構についての知見も得られた。また, ナメクジウオロドプシンの新しいロドプシンモデルとしての可能性についても考察する。
1 0 0 0 OA ショウジョウバエメスの性行動の神経遺伝学的研究
- 著者
- 坂井 貴臣
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.225-230, 2011 (Released:2011-08-30)
- 参考文献数
- 48
神経遺伝学は動物の本能行動の研究に利用されている。特定の行動を支配する遺伝子を同定することができれば,その行動にかかわる神経回路の同定やその生理学的メカニズムの解明に役立つ。キイロショウジョウバエは古くから行動実験に利用されてきたが,その中でも特に性行動の研究が盛んに行われ,多くの研究者によって雌雄の複雑な性行動が詳細に報告されてきた。また,分子生物学的解析が容易なことから,性行動にかかわる多くの遺伝子が同定されてきた。オスの性行動の研究では遺伝子を同定するにとどまらず,性行動を制御する脳神経細胞・回路が同定され,さらにそれらの神経活動と性行動の関係も明らかにされつつある。一方,未交尾メスの性行動にかかわる遺伝子も報告されているものの,メスの性行動を制御する脳機構はいまだ不明な点が多い。本稿では,キイロショウジョウバエメスの性行動の研究手法とこれまでに報告された遺伝子や神経遺伝学的研究を紹介するとともに,これまでに得られた知見からその分子・生理機構について議論する。
1 0 0 0 OA ショウジョウバエ幼虫を動かす神経回路機構
- 著者
- 高坂 洋史
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.93-99, 2018-08-01 (Released:2018-08-15)
- 参考文献数
- 52
我々ヒトも動物であるので,動物が動くのを見てもそれほど驚きを感じない。しかし,動物の身体の中で起こっていることに目を向けると,動物が動くことはそれほどあたりまえではないことに気が付く。動物は,体全体に配置された筋肉を巧みに制御することで運動する。その運動制御を主に担うのが,多数の神経細胞が複雑につながった中枢神経系である。複雑な神経ネットワークが,いかにして適切な運動制御を実現するのかというのは,全く自明な問いではなく,神経科学における重要な研究課題である。本稿では,神経回路がどのように運動制御を担うかについて,細胞レベルでの解析が進んでいるショウジョウバエ幼虫を用いた研究を紹介する。ショウジョウバエ幼虫は,体軸方向に体節がつながった構造をしており,各体節の筋収縮パターンによって前進,後進,屈曲などを示す。我々の研究グループを含む世界中の研究者により,これらの多様な運動パターンを担う介在神経細胞が明らかにされてきている。この神経回路機構を,他の動物種の運動回路機構と比較することで,運動制御機構の共通性を探る。
1 0 0 0 OA ミツバチにおける翅と飛翔筋の多機能化
- 著者
- 佐々木 正己
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.4, pp.326-336, 1997-12-31 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 26
1 0 0 0 OA 深海生物チューブワームのヘモグロビン
- 著者
- 高木 尚
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.51-59, 1991-06-30 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 30
1 0 0 0 スズメガで知る昆虫飛行の多様性
- 著者
- 安藤 規泰
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.108-118, 2018-08-15
- 被引用文献数
- 1
<p>飛行は,昆虫を特徴づける行動の1つであるが,飛行の研究は昆虫に限らず,動物一般の運動制御にとって重要な発見をもたらしてきた。運動制御機構の研究のモデルとなる動物には,主にサバクバッタ,ハエ,そしてスズメガが用いられてきたが,なかでもサバクバッタは中枢パターン発生器の発見で有名であり,昆虫飛行の代表的なモデルである。ハエは小さいながらも極めて優れた飛行能力を有しており,それを支える感覚運動系の研究に多く用いられてきた。特にショウジョウバエは,近年の遺伝子工学の進歩により,飛行の神経メカニズムの解明になくてはならない存在である。一方,スズメガは,サバクバッタと並ぶ大型の実験昆虫で,ハエに匹敵する高い運動能力を備えている。そして,形態も内部メカニズムも両実験昆虫の中間的な特徴を有しており,飛行の多様性を知るうえで無視できない存在である。本稿では,このスズメガを中心に,筆者らがこれまで進めてきた自己受容器による感覚フィードバック経路の解析,自由飛行における飛翔筋活動と羽ばたき運動計測,そして飛翔筋活動による胸部外骨格の変形の解析という,互いに密接に関連した研究の概要を紹介する。さらに,他の研究グループから近年報告されたユニークな飛行のメカニズムの話題を合わせて紹介する。最後に昆虫飛行の研究の今後の展望として,統合的な理解を進めるために何をすべきかを議論する。</p>
1 0 0 0 OA ウニの棘の運動
- 著者
- 高橋 景一
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.185-193, 1997-09-30 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 27
1 0 0 0 OA 低分子有機化合物による細胞内浸透圧調節
- 著者
- 松島 治
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.3-12, 1997-03-15 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 67
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 魚介類筋肉の死後におけるATPの代謝とその周辺
- 著者
- 横山 芳博 坂口 守彦
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.193-200, 1998-09-30 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 73
- 被引用文献数
- 2
- 著者
- 大西 憲幸 久原 篤
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.112-120, 2012-09-20 (Released:2012-10-17)
- 参考文献数
- 42
感覚や記憶・学習といった高次神経活動を制御する神経情報処理の基本原理の解明は,現代神経科学の重要な課題である。神経情報処理の解明に向けたアプローチとして,わずか302個からなるシンプルな神経回路を持つ線虫Caenorhabditis elegans(C. elegans)をモデル系とした解析が行われている。C. elegansは,シンプルな神経回路をもちいて,様々な外部刺激を感知し,多様な応答行動をとることができる。それらの行動が線虫から高等動物まで高度に保存された神経情報処理メカニズムにより制御されていることが次第に明らかとなってきている。これまで,線虫の神経系の解析は主に分子遺伝学的手法を用いて行われていたが,近年,神経活動のin vivo光学イメージング技術や神経活動をリモートコントロールできる最新の光技術の発達により,従来は困難であった生理学的解析も可能となっている。これらの技術を駆使した解析により,温度走性を制御する分子基盤や回路が明らかになっただけでなく,感覚ニューロンと介在ニューロンの間の情報処理における新しい概念が発見されてきた。本稿では,線虫の温度に対する応答行動に焦点をあて,主に分子生理学的解析により新たに発見された神経情報処理メカニズムについて,最新の論文を中心に概説する。
1 0 0 0 OA 動物の運動制御機能と熱
- 著者
- 藏本 武照
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.195-204, 2004-12-31 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 74
1 0 0 0 OA GFPを用いた蛍光カルシウムプローブG-CaMPの開発
- 著者
- 中井 淳一 大倉 正道
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.135-145, 2002-08-31 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 28
1 0 0 0 OA 昆虫の色情報処理機構
- 著者
- 市川 敏夫
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.13-21, 1991-03-31 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 28
1 0 0 0 OA 色素胞の反応の定量的記録法
- 著者
- 藤井 良三
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.108-118, 1999-06-30 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 50
1 0 0 0 OA 線虫の化学感覚と行動
- 著者
- 松浦 哲也
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.10-19, 2006-01-30 (Released:2007-10-05)
- 参考文献数
- 55
- 被引用文献数
- 1
線虫はわずか302個のニューロンから構成されており, それらすべての接続が明らかになっている。そのため, 感覚の受容とその処理過程が比較的容易に理解できる。また, 全ゲノムの塩基配列が明らかとなっているため, 遺伝子レベルの解析も可能である。線虫は行動とその神経基盤, 分子機構を結び付けることのできる数少ない生物の1つであるといえる。本稿では, 線虫の化学感覚と化学走性行動に関する神経基盤および分子機構について紹介する。線虫は周囲に存在する特定の化学物質に対して化学走性行動を発現する。この行動の発現には, 線虫頭部や尾部に存在するアンフィド感覚器やファスミド感覚器での化学情報の受容が重要であることが分かっている。最近では, 化学物質とエサの有無を関連付けた連合学習など線虫行動の可塑性や, 化学走性時の個体間の相互作用について新たな知見が得られつつある。
1 0 0 0 生き物あふれる研究室で
- 著者
- 土佐 靖彦
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.4, pp.339-340, 2011-12-20
1 0 0 0 OA 周期的に張力を変動させる膜
- 著者
- 谷 知己
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.128-134, 2002-08-31 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 11
- 著者
- 松尾 亮太
- 出版者
- THE JAPANESE SOCIETY FOR COMPARATIVE PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.253-258, 2011-10-31
哺乳類の脳は,ひとたび損傷を受けると再生することが非常に難しく,また脳の構成要素であるニューロンは,最終分化を果たしていて細胞周期は停止した状態である。一方、軟体動物腹足類であるナメクジの中枢神経組織は、損傷や欠損を受けても自発的に構造レベル、機能レベルでの回復を遂げることができる。例えば触角は,切断を受けてもそこに含まれる神経組織を含めてほぼ完全に再生することができる。同時に,大小二対存在する触角は,互いに機能レベルでの冗長性も有している。また,脳の左右に一対存在し,高次嗅覚機能を担っている前脳葉と呼ばれる部位は,損傷や欠損を被った際,自発的に組織レベル,機能レベルでの回復を遂げることができる。そして前脳葉自体も,常に左右いずれか片方ずつが機能するという,ある種の機能的冗長性を有している。さらに,ナメクジのニューロンは,物質合成能を高める必要がある場合には自身のゲノムDNA量を増やすことさえできる。本稿では,こういった,我々哺乳類には到底不可能な,さまざまな離れ業を示すナメクジの神経組織について紹介する。
1 0 0 0 OA 代謝生態論:比較生理と生態学をつなぐ新たな代謝スケーリング
- 著者
- 八木 光晴 及川 信
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.20-27, 2014-03-14 (Released:2014-03-28)
- 参考文献数
- 81
- 被引用文献数
- 1
個体レベルで生物の体の大きさとエネルギー代謝速度の関係(代謝スケーリング)を探る比較生理研究の歴史は古く,生理,薬理,農,水産そして生態学など様々な学問分野で基礎をなしてきた。近年,個体レベルの代謝則(クレイバー則)を個体群,群集,そして生態系レベルまで当てはめて横断的に展開する代謝生態論が注目されつつある。本稿では,代謝生態論の基礎である個体レベルの代謝スケーリングについてその理論的枠組みと,実証研究から明らかとなった生態学的意義を述べる。最後に,個体から生態系へとスケールアップする新しい代謝スケーリング研究の動向と展望について紹介する。