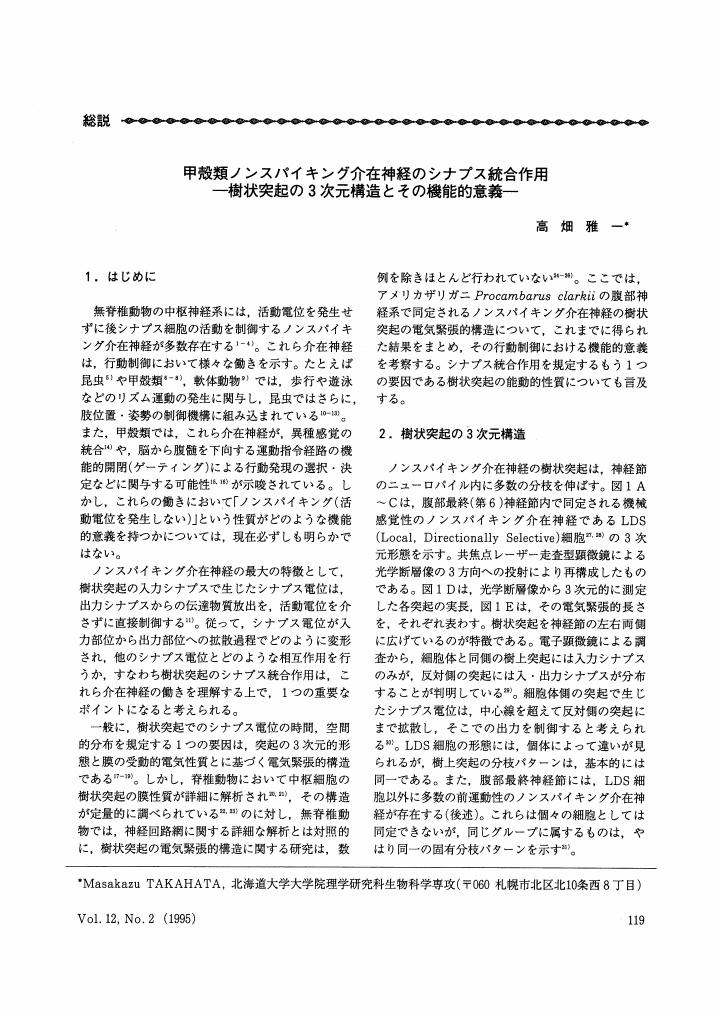154 0 0 0 OA バイオミメティクスのすゝめ
- 著者
- 下澤 楯夫
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.98-107, 2016-09-29 (Released:2016-10-17)
- 参考文献数
- 28
生物の生きる仕組みの動作原理をヒトの技術へ転化するバイオミメティクスを紹介する。生物の機能の全ては,特定の構造に裏付けられている。生きる仕組みの理解を目指す生理学では,「構造の無い機能は幽霊,機能の無い構造は死体」である。生物は全ての機能的(適応的)構造を,極ありふれた元素のみから作る。コガネムシが金の原子を1個も使わずに常温常圧で金色の鞘翅を作り上げる能力は,技術と呼ぶにふさわしい。ガルバーニが,金属との接触でカエルの筋肉が攣縮する仕組みを追い求めたことが,電池の発明を惹き起こして世界を一変させた。パソコンでクリックした際に動作するシュミットトリガー回路は,イカの巨大神経軸索のパルス発生機構に由来し,現実の世界経済を支えている。サカナの眼のレンズは単に球形なのではなく,中心部の屈折率が高い屈折率分布レンズで,球面収差が補正されている。生理学ではマーティセン比として知られるこの結像原理の二次元版が光ファイバであり,現在の光通信を支えている。物理学が人間の英知で解き明かし制定したかのように言い触らしている法則の多くは,生物が既に十分に使いこなして物作り技術にまで高めていた自然の性質の1億年遅れの再発見に過ぎない。
138 0 0 0 OA 鳥類におけるメラニンを用いた体色発現システムの分子機構
- 著者
- 織部 恵莉 吉原 千尋 高橋 純夫 竹内 栄
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.3-11, 2009 (Released:2009-07-09)
- 参考文献数
- 55
- 被引用文献数
- 2
動物の体色には驚くほどの多様性がみられる。これは,体色が自然淘汰の様々な淘汰圧を受ける,生態学的に重要な形質であることを反映している。脊椎動物では,メラニンを用いた体色発現システムが,隠蔽,警告,性的提示などの生存戦略に関与し,体の色や色パターンに多様性を生じさせている。このような体色の多様性を創出する分子機構とはどのようなものであろうか。体色の進化や多様性の創出にも遺伝的な背景があり,原因となる遺伝子変化がある筈である。近交系マウスの毛色遺伝学の発展は,体色発現システムに関わる遺伝子の詳細な情報を提供するとともに,体色発現システムの分子レベルでの比較生物学を可能にした。本稿では,鳥類の羽色発現システムの分子機構に関する最新の知見を紹介する。羽色遺伝子座遺伝子の同定と性格付けによって,メラニンを用いた体色発現システムが鳥類と哺乳類との間で基本的に保存されていること,個々の羽や羽装にみられる複雑かつ多彩な色パターン形成に,局所性メラノコルチンシステムが重要な役割を果たしている可能性が示唆された。メラノコルチンシステム構成遺伝子の発現制御の変化が,哺乳類との体色の違いを創出する原因の一つになっている可能性が考えられる。
41 0 0 0 OA 甲殻類ノンスパイキング介在神経のシナプス統合作用
- 著者
- 高畑 雅一
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.119-129, 1995-06-30 (Released:2011-03-14)
- 参考文献数
- 71
- 被引用文献数
- 1 1
34 0 0 0 OA 捕食者スズメバチに対するニホンミツバチの防衛行動 −蜂球内でのスズメバチの死の原因解明−
- 著者
- 菅原 道夫
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.68-75, 2013-05-10 (Released:2013-07-10)
- 参考文献数
- 25
ニホンミツバチが,捕食者であるスズメバチを蜂球に閉じ込め殺す仕組みを明らかにした。スズメバチが蜂球に捕捉されると,蜂球内では温度だけでなく湿度も急速に上昇する。5分後には温度は46℃に,湿度は90%以上になる。この時,蜂球内の炭酸ガス濃度は4%に達する。多くのスズメバチは,蜂球内では10分で死ぬ。スズメバチの死をもたらす要因を,蜂球内の湿度とCO2濃度を変え致死温度を測定することで考察した。実験に使用した4種のスズメバチのいずれにおいても,CO2濃度3.7%(ヒトの呼気環境)では,2℃以上も致死温度が低下した。相対湿度が90%以上になると,さらに致死温度が低下した。ヒトの呼気環境中では,大気中に比べCO2は増加し酸素は減少するが,酸素を補っても致死温度は変わらなかった。ニホンミツバチは,蜂球中のスズメバチを酸素欠乏によって窒息死させるのでなく,高温,高湿,高濃度のCO2,の環境中でスズメバチの致死温度を下げることで殺していると考えられた。
32 0 0 0 OA ミドリゾウリムシにおける細胞内共生研究の現状と課題
- 著者
- 早川 昌志 洲崎 敏伸
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.108-115, 2016-09-29 (Released:2016-10-17)
- 参考文献数
- 64
- 被引用文献数
- 1
ミドリゾウリムシは,共生クロレラと呼ばれる単細胞緑藻類を細胞内共生させている繊毛虫類の一種である。ミドリゾウリムシは,共生クロレラを除去する「白化」と,共生クロレラの「再共生」が容易に行えることから,細胞内共生研究における有用なモデル生物であり,以下のように多くの研究がなされている。ミドリゾウリムシには,宿主由来の共生クロレラのみだけでなく,別株や別種の宿主に由来する共生クロレラや,自由生活性の藻類,さらには酵母や細菌などの微生物も共生させることができる。共生クロレラに特徴的な生理学的特性として,外液が酸性の条件で細胞外にマルトースを放出する性質がある。共生クロレラはPV膜と呼ばれる生体膜によって近接して包まれており,PV膜の内部が酸性環境に維持されていると考えられており,共生と関連したクロレラからの糖の放出システムが構築されていることが予想されている。PV膜には宿主ミトコンドリアが密着・融合しており,細胞内共生において何らかの役割を果たしている可能性がある。ミドリゾウリムシは分子生物学的な研究は遅れているが,比較トランスクリプトーム解析などが行われており,共生と関連して発現が変動する遺伝子も報告されている。
27 0 0 0 OA 神経系の起源と進化:散在神経系よりの考察
- 著者
- 小泉 修
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.116-125, 2016-09-29 (Released:2016-10-17)
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 1
私は,動物界で最も単純な刺胞動物の散在神経系の構造・機能・発生を分子レベルから個体レベルにわたり総合的に研究してきた。そしてその知見を他の集中神経系(哺乳類に至る背側神経系と昆虫や軟体動物頭足類に至る腹側神経系)と比較して,神経系進化の一番底から,2つのルートを眺めて,神経系の起源と進化を考えてきた。その結果,現在,「発達程度は低いとしても,刺胞動物の散在神経系は,神経系の要素の全てを持ち合わせている」と考えている。この点は,中枢神経系に関しても同様ではないかと予想している。この総説では,散在神経系の研究より見えてきた神経系の起源と進化について議論する。
27 0 0 0 OA 連載解説: 生物学のための情報論
- 著者
- 下澤 楯夫
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.85-89, 2005-06-30 (Released:2011-03-14)
24 0 0 0 OA 魚類における恐怖・不安行動とその定量的観察
- 著者
- 吉田 将之
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.4, pp.317-325, 2011 (Released:2012-01-11)
- 参考文献数
- 60
恐怖や不安は,動物の生命存続のためになくてはならない情動であり,様々な情動のうちでも比較的研究が進んでいる。魚類における恐怖や不安の神経機構を調べる上で,それらの情動を再現し,定量的に計測するための有効な方法が不可欠である。最近,従来の動物心理学的な手法に,エソロジカルな考え方も取り入れた魚類の不安の定量化法が導入されつつある。代表的な例のひとつが「新奇環境テスト」であり,これは不安を惹起するような新しい環境(水槽)に魚が遭遇したとき,どのように対処するかを定量的に観察する方法である。もう一つが明暗(白黒背景)選好性テストであり,背景が暗いほうが安心するという魚の習性を利用した不安の定量法である。一方,恐怖については,古典的恐怖条件付けや回避条件付けなどの手法で定量化できるほか,警報物質や捕食者に対する生得的な恐怖反応を利用する方法も開発されている。これらの恐怖・不安定量化法を利用して,情動のメカニズムに関する行動神経科学的,生物医学的研究が進められている。 魚類は多様な環境に適応放散しているが,そのごく一部が研究対象となっているにすぎない。今後,興味深い不安・恐怖行動を示す魚種が発見され,情動メカニズムの進化の解明に寄与することを期待する。
23 0 0 0 OA 昆虫の聴覚器官 ―その進化―
- 著者
- 西野 浩史
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.26-37, 2006-04-20 (Released:2007-10-05)
- 参考文献数
- 62
- 被引用文献数
- 1
広い動物界にあって聴覚を有し, これを同種間コミュニケーションに役立てている動物は前口動物の頂点に位置づけられる昆虫と, 後口動物の頂点に位置づけられる脊椎動物に限定される。系統的に大きく隔てられたこれらの動物が聴覚を発達させていることは, 収斂進化の典型例とみなされてきた。しかし近年の研究からは, 音を処理する感覚細胞は動物間共通の分子機構を持つことが明らかとなってきている。むしろ収斂進化のもっとも顕著な部分は音エネルギーを効率良く感覚ニューロンに伝えるための体構造の修飾にある。鼓膜がその良い例である。本稿では最近10年の聴覚研究の新発見を広くとりあげ, 昆虫の聴覚器官の進化について論じてみたい。
20 0 0 0 OA スズメガで知る昆虫飛行の多様性
- 著者
- 安藤 規泰
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.108-118, 2018-08-01 (Released:2018-08-15)
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 1 1
飛行は,昆虫を特徴づける行動の1つであるが,飛行の研究は昆虫に限らず,動物一般の運動制御にとって重要な発見をもたらしてきた。運動制御機構の研究のモデルとなる動物には,主にサバクバッタ,ハエ,そしてスズメガが用いられてきたが,なかでもサバクバッタは中枢パターン発生器の発見で有名であり,昆虫飛行の代表的なモデルである。ハエは小さいながらも極めて優れた飛行能力を有しており,それを支える感覚運動系の研究に多く用いられてきた。特にショウジョウバエは,近年の遺伝子工学の進歩により,飛行の神経メカニズムの解明になくてはならない存在である。一方,スズメガは,サバクバッタと並ぶ大型の実験昆虫で,ハエに匹敵する高い運動能力を備えている。そして,形態も内部メカニズムも両実験昆虫の中間的な特徴を有しており,飛行の多様性を知るうえで無視できない存在である。本稿では,このスズメガを中心に,筆者らがこれまで進めてきた自己受容器による感覚フィードバック経路の解析,自由飛行における飛翔筋活動と羽ばたき運動計測,そして飛翔筋活動による胸部外骨格の変形の解析という,互いに密接に関連した研究の概要を紹介する。さらに,他の研究グループから近年報告されたユニークな飛行のメカニズムの話題を合わせて紹介する。最後に昆虫飛行の研究の今後の展望として,統合的な理解を進めるために何をすべきかを議論する。
17 0 0 0 OA その1:細胞はいかにして電気を発生するか
- 著者
- 酒井 正樹
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.26-32, 2012-01-31 (Released:2012-10-17)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 3
私は,ながらく岡山大学で教鞭をとり,退職後も現在特命教授として教育に従事している。しかし,それもそろそろ終わりになりつつある。それで,これまで自分がやってきた講義のなかで,学生からよく出た質問や学生が陥りやすい誤りなどについて,書き残しておきたいと思っていた。かって十数年前,私が本誌編集長をしていたとき,大学での講義について,指導方法や教材などを紹介してもらう欄を企画したことがあった。そういうものを復活してもらえないかと考えていた折も折,私たちの学会で教育の向上をはかるための議論がおこってきた。そこで,黒川編集長と相談のうえ,ここに書かせて頂くことになった。
15 0 0 0 OA その2:細胞はいかにして興奮するか
- 著者
- 酒井 正樹
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.76-86, 2012-04-30 (Released:2012-10-17)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 2 1
今回は細胞の興奮をとりあげる。興奮とは,生理学では細胞が活動電位を発生することと同義である。生きている細胞は,すべて静止膜電位をもっているが,体をつくる多くの組織細胞,たとえば肝細胞や上皮細胞などは活動電位を発生しない。一方,神経細胞(ニューロン)や筋細胞などは活動電位を発生する。活動電位とは,細胞内電位が一定の値よりも浅くなったとき,それに続く一過性の大きな電位変化のことである。活動電位発生のしくみは,静止電位のしくみを理解しておれば,さほど難しいものではない。しかし,学生には静止電位のときと同じく,知識不足や誤解があり,また誤ったイメージをもっている者がいる。それらは,高校の「生物」によるところが大きく,ぜひ正しておかねばならない。では授業をはじめよう。5つのコラムは,必要のない方にはとばしていただいて結構である。
15 0 0 0 OA ゲノム情報に支えられたより堅固な生命科学へ:軟骨魚のオプシンを題材として
- 著者
- 山口 和晃 工樂 樹洋
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.170-179, 2020-12-01 (Released:2020-12-24)
- 参考文献数
- 48
全ゲノム配列情報が整備された生物種が増えてきたが,脊椎動物の中でとくに板鰓類(サメ・エイ類)ではその動きが大きく停滞していた。板鰓類は軟骨魚類の大部分を占め,約1,200種と種数では硬骨魚類に到底及ばないものの,約4億年という哺乳類や鳥類とは比べ物にならない長い時間をかけて地球上の生態系に定着した系統である。筆者らは,水族館との連携により試料を確保し,DNA シークエンスデータの取得および解析の全工程を最適化することにより,サメ3種の全ゲノム情報を読み取り,多面的な解析を行った。全ゲノム情報に基づいて遺伝子の有無を論じる際,その完成度が信頼性を左右する。また,同定した遺伝子について生物種間の対応関係を把握するには,分子系統解析によりオーソロジーを判定する必要がある。こういった点に留意してオプシン遺伝子を調べたところ,サメ類は視覚への依存度が低く,ロドプシン以外の多くのオプシン遺伝子レパートリを失ったことが明らかとなった。ロドプシンの吸収スペクトルの分光測定によって,深海に生息するサメのロドプシンは海水中で減衰しにくい480 nm 付近の波長の光を最も効率良く受容する性質をもつ可能性が示された。 今後,生体組織試料に依存しないこういった手法が,他の希少海棲動物の生態を明らかにする助けになるかもしれない。
14 0 0 0 OA チョウ成虫の採餌行動と嗅覚情報物質
- 著者
- 大村 尚
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.134-142, 2006-08-20 (Released:2007-10-05)
- 参考文献数
- 88
チョウ成虫の多くは花蜜を食物としており, 花色は訪花 (採餌) 行動の解発因子として重要である。同様に花香も訪花行動に作用するが, 解発因子は物質レベルで明らかにされていなかった。吸蜜植物の花香成分に対する応答を調べたところ, モンシロチョウやアカタテハは特定の芳香族化合物に高い選好性を示し, 口吻伸展反射や賦香造花への定位行動が観察された。これらの花香成分は様々な植物に含まれており, チョウの訪花行動を刺激する普遍的な嗅覚情報物質と考えられる。一方, 花香成分には訪花行動を抑制するものもあり, キンモクセイに含まれるγ―デカラクトンをモンシロチョウの忌避物質として同定した。滲出樹液や腐敗果実を食物とするルリタテハやアカタテハは, エタノールや酢酸など発酵産物の臭いを頼りに採餌行動を行った。花蜜しか利用しないタテハチョウは発酵産物の臭いに対する選好性が低く, チョウは食性によって異なる嗅覚情報物質を利用することがわかった。
14 0 0 0 OA アゲハが見ている「色」の世界
- 著者
- 木下 充代
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.4, pp.212-219, 2006-11-20 (Released:2007-10-05)
- 参考文献数
- 48
我々ヒトは, 感覚情報の8割を視覚に頼っているといわれている。視覚の大切な機能のひとつに色覚がある。色覚は, 多くの動物に共有される感覚であると考えられている。ある動物の見ている色世界は, 行動実験によってのみ示すことができる。著者は, これまで鱗翅目昆虫であるナミアゲハの色覚能力について, 求蜜行動を指標にした学習弁別実験によって明らかにしてきた。アゲハは, 色覚だけでなく, 色の恒常性を持つ。単色光を学習したアゲハで測定した求蜜行動の感度は, 網膜にある色受容細胞の感度の高い波長域で高くなる。さらに, Y迷路を用いてアゲハが色を知覚できる最小サイズを測定すると, 学習した色に限らず約1度であった。複眼の空間分解能を規定する個眼間角度が約1度であることを考えると, アゲハの色覚では個眼ひとつが色知覚の最小ユニットになっているのかもしれない。
14 0 0 0 OA ザリガニに見る自発性行動制御の神経回路機構
- 著者
- 加賀谷 勝史
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.3-10, 2012 (Released:2012-02-17)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 2 1
動物行動は,特定の外部感覚刺激に応答して開始するだけでなく,自発的にも開始する。このような自発的(随意的)な行動開始の神経機構はどのようなものだろうか。我々はアメリカザリガニにおいて,自発性歩行に動員される脳内ニューロンを多数同定した。とりわけ,自発的な歩行開始に先行すること1秒以上前にスパイク活動が増加するニューロンを発見した。これらのニューロンの活動は,脊椎動物の脳で記録される随意行動開始に先行する活動,すなわち準備活動に相当するものであると考えられる。また,歩行の継続中あるいは停止時に賦活されるニューロンを同定した。以上から,自発性歩行は,組織化された下行性信号によって開始,継続,停止が制御されることが判明した。さらに,これらの下行性信号がどのような神経回路機構で生成されるのかを明らかにするために,細胞内記録・染色法によって脳内神経細胞を調べた。その中で,準備活動ニューロンを同定することに成功し,準備活動が内発的興奮性によってではなく,逐次的な興奮性・抑制性シナプス入力によって形成されることが分かった。同定された多数の脳内ニューロンのシナプス活動,樹状突起投射部位を解析した結果から,自発性歩行制御に関わるシナプス賦活が前大脳内側部と後大脳とで構成される回帰性神経回路で起こるモデルを本稿で提案する。
13 0 0 0 OA ナメクジの脳が持つしたたかさ ―再生能力,頑健性,そして柔軟性―
- 著者
- 松尾 亮太
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.253-258, 2011 (Released:2011-11-08)
- 参考文献数
- 47
哺乳類の脳は,ひとたび損傷を受けると再生することが非常に難しく,また脳の構成要素であるニューロンは,最終分化を果たしていて細胞周期は停止した状態である。一方、軟体動物腹足類であるナメクジの中枢神経組織は、損傷や欠損を受けても自発的に構造レベル、機能レベルでの回復を遂げることができる。例えば触角は,切断を受けてもそこに含まれる神経組織を含めてほぼ完全に再生することができる。同時に,大小二対存在する触角は,互いに機能レベルでの冗長性も有している。また,脳の左右に一対存在し,高次嗅覚機能を担っている前脳葉と呼ばれる部位は,損傷や欠損を被った際,自発的に組織レベル,機能レベルでの回復を遂げることができる。そして前脳葉自体も,常に左右いずれか片方ずつが機能するという,ある種の機能的冗長性を有している。さらに,ナメクジのニューロンは,物質合成能を高める必要がある場合には自身のゲノムDNA量を増やすことさえできる。本稿では,こういった,我々哺乳類には到底不可能な,さまざまな離れ業を示すナメクジの神経組織について紹介する。
12 0 0 0 OA メラトニンとエイジング
- 著者
- 服部 淳彦
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.2-11, 2017-03-29 (Released:2017-04-11)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
エイジングに伴って,様々な器官に衰えが生じることは避けられない。特に,睡眠障害や記憶力の低下,骨粗鬆症による骨折などは,高齢者のQOL(Quality of Life)低下につながり,その予防や改善策は喫緊の課題である。メラトニンは松果体から夜間にのみ分泌される「夜の時刻情報の伝達物質」であるが,その分泌量は加齢とともに激減する。近年,メラトニンは松果体以外の様々な器官においても合成されること,フリーラジカルや活性酸素を消去する抗酸化物質としての性質を併せ持つことが明らかとなった。そこで,この加齢に伴って減少するメラトニンを補充するという長期投与実験がなされ,マウスやラットでは寿命を延ばすことが報告されている。ヒトでも,閉経後骨粗鬆症の進行を抑制し,アルツハイマー病に対しても通常の治療薬との併用ではあるが,進行を抑制することが報告され,一段とアンチ(ウェル)エイジング効果に期待が集まりつつある。最近我々は,メラトニンの学習・記憶増強作用が,メラトニンの脳内代産物であるN-acetyl-5-methoxykynuramine (AMK)の長期記憶誘導作用に起因していることを見出し(特願2016-42875),老化によって長期記憶形成力が低下したマウスやコオロギにおいて,AMKの単回投与が記憶力の有意な改善をもたらすことを明らかにした。また,我々が見つけたメラトニンの破骨細胞(骨溶解)抑制作用を期待して,国際宇宙ステーション「きぼう」実験棟において実験を行い,宇宙でもメラトニンが破骨細胞を抑制することを確認した。
11 0 0 0 OA 昆虫の偏光コンパスの神経機構
- 著者
- 佐倉 緑
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.4, pp.195-204, 2015-12-15 (Released:2015-12-29)
- 参考文献数
- 59
多くの昆虫は天空の偏光パターンから方向を検出する。偏光のe-ベクトル方向の情報は,複眼の偏光受容に特化した領域[dorsal rim area(DRA)]で検出される。DRAで検出されたe-ベクトル情報は,その後,視葉の視髄(medulla)で3種類の情報に収斂されることから,人間の3色型色覚のように3種類の異なるニューロンの応答比率によって符号化される(即時型検出;instantaneous method)と考えられる。Medullaの3種類の情報から任意のe-ベクトル方向を符号化するニューラルネットワークを構築し,その動作を検証した結果,様々な自然条件の刺激に対して高い精度で体軸方向を検出できることが明らかとなった。また,コオロギ脳内神経細胞からの細胞内記録により,ネットワーク構築の際に想定したものと同じ応答特性を持つニューロン群が見つかった。これらのニューロンは特定のe-ベクトル方向に対して強い興奮性の応答を示し,脳内でコンパスの働きをすることが示唆される。さらに,ミツバチの吻伸展反射を利用して偏光刺激のe-ベクトル方向を弁別させる学習実験を行った結果,彼らが偏光刺激をスキャンすることなく90°異なるe-ベクトル方向を弁別することが明らかとなった。これらの一連の結果は,昆虫がinstantaneous methodに基づく偏光視システムを持つことを強く示唆している。
11 0 0 0 OA 昆虫における栄養恒常性と摂食行動の意思決定
- 著者
- 利嶋 奈緒子
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.46-52, 2017-06-15 (Released:2017-07-03)
- 参考文献数
- 53
生物が健康的な生活を維持するためには,適切な栄養素の摂取が重要である。味覚,嗅覚,視覚など様々な感覚システムを用いて,外界に存在する必要な栄養素を探索し,摂取しなければならない。空腹の生物にとってエネルギー源となる糖や脂肪の味覚感覚は摂食行動を誘引するが,それらの栄養素の過剰な摂取は肥満や糖尿病などの問題を引き起こす。生体活動の維持には,他にもタンパク質やイオンなど様々な栄養素がバランスよく必要とされる。体内の適切な栄養環境を維持するためには,「何」を「いつ」,「どのくらい」摂取するのかを意思決定をする必要があるのである。意思決定のプロセスを介した摂食行動は,哺乳類から無脊椎動物まで保存されている。中でも昆虫は比較的単純な神経構造を持っていながら,複雑な摂食制御機構を有し,また哺乳類と共通の遺伝子も多く存在することから,意思決定の遺伝学的・神経生物学的研究のための有用なモデルの一つである。本稿では,摂食行動の意思決定についての行動学的研究から分子神経学的研究まで,主にキイロショウジョウバエ(Drosophila melanogaster)をモデルとした最新の知見を紹介する。