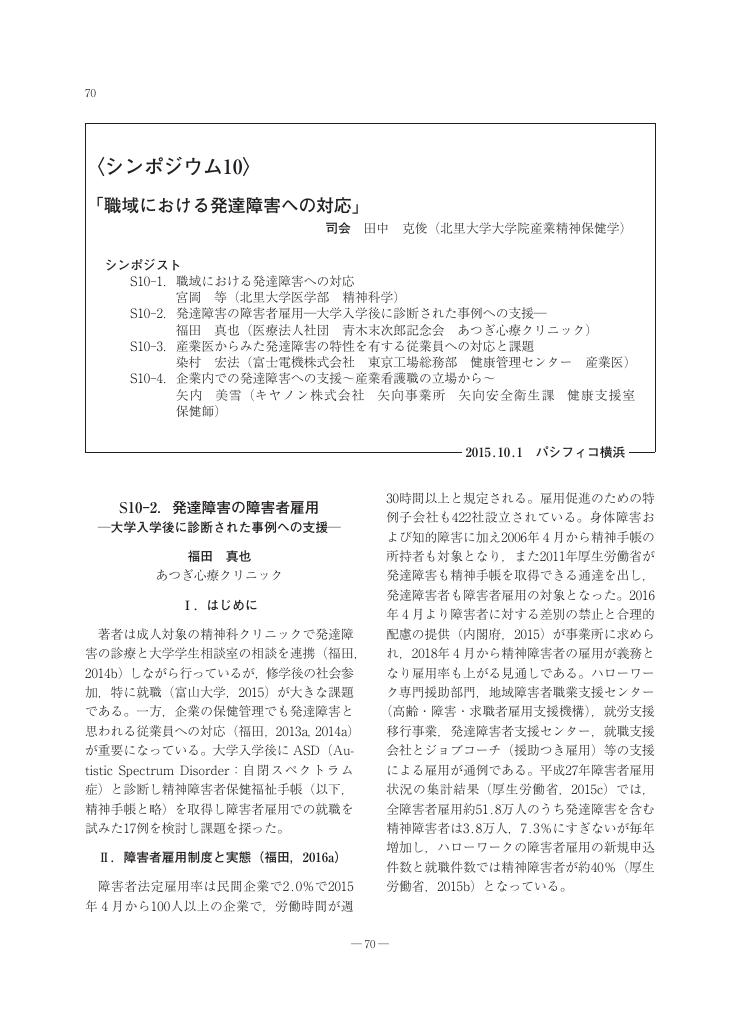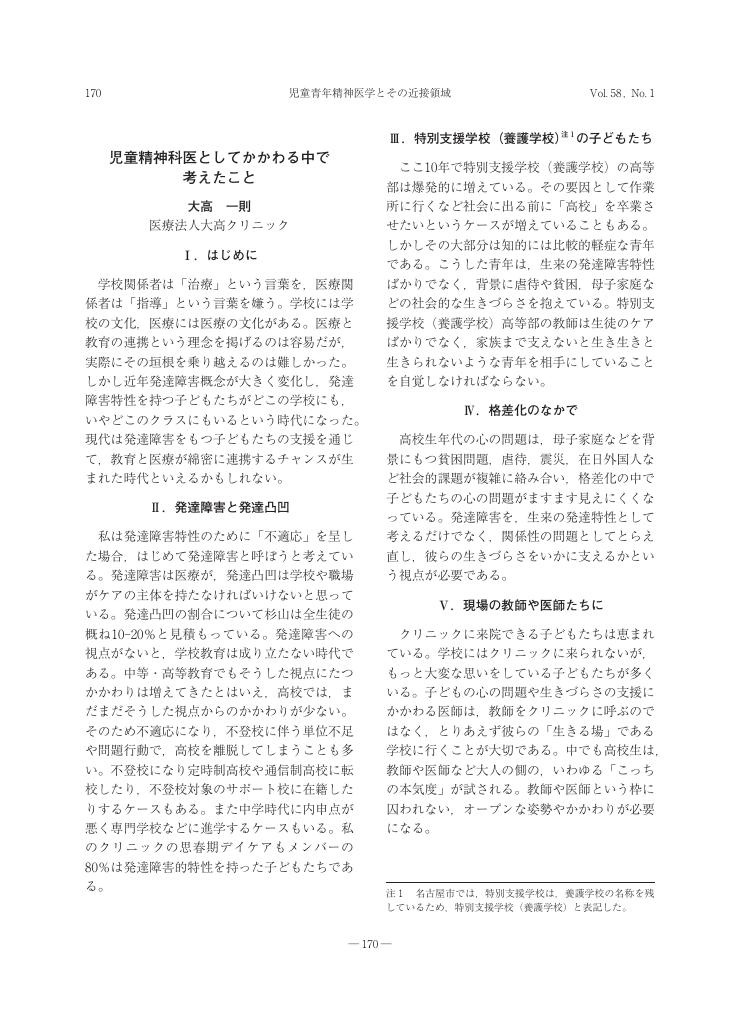6 0 0 0 OA 被虐待児へのトラウマケア
- 著者
- 亀岡 智美
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.5, pp.738-747, 2016-11-01 (Released:2017-05-17)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
近年, 虐待された子どもたちを, トラウマの視点から評価しケアすることの重要性が, 国際的にも強調されている。Trauma-focused cognitive behavioral therapyは, 被虐待児のトラウマへの第一選択治療として推奨され, 国際的に最も効果が検証されている認知行動療法である。わが国における実施可能性も検討され, 報告されている。本稿では, わが国での実施症例を提示することによって, プログラムの概要を紹介するとともに, 被虐待児ケアにおけるPTSD評価とトラウマ治療の重要性について考察した。
6 0 0 0 OA S01-4.ADHDと愛着障害
- 著者
- 友田 明美
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.5, pp.623-627, 2017-11-01 (Released:2019-08-21)
- 参考文献数
- 16
6 0 0 0 OA S01-3.血中ラジカル消去活性に着目した自閉症エネルギー代謝異常の研究
- 著者
- 松﨑 秀夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.359-363, 2018-08-01 (Released:2019-08-21)
- 参考文献数
- 22
6 0 0 0 OA S10-2.発達障害の障害者雇用
- 著者
- 福田 真也
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.70-75, 2017 (Released:2017-07-04)
- 参考文献数
- 15
5 0 0 0 OA S1-2.自閉症スペクトラム児の自殺関連行動
- 著者
- 尾崎 仁 渡辺 由香
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.489-496, 2016-08-01 (Released:2017-05-17)
- 参考文献数
- 7
- 著者
- 田宮 聡 岡田 由香 小寺澤 敬子
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.450-457, 2016 (Released:2019-08-21)
- 参考文献数
- 23
多言語環境が子どもの言語発達に及ぼす影響についての理解を深めるために,日英のバイリンガル環境で生まれ育ったA(女児)の言語発達について報告した。Aは生下時から日英両語に暴露されうる環境で生活していたが,両語の発達はともに遅れていた。その遅れがバイリンガル環境のためと説明されたこともあったが,保護者はAの発達を心配し,小学1年生で帰国して児童精神科を受診した。Aには言語発達遅滞以外に,社会性やイマジネーションの困難さとともに知的能力障害も見られ,自閉症スペクトラム障害と診断された。Aの日本語の発達については,語彙の乏しさ,単語の形態の誤り,文法の誤り,会話のかみ合わなさなどが観察された。これらの問題を,バイリンガル特有の言語特性である,転移,プロフィール効果,コードスイッチングとの関連で考察した。Aの日本語の遅れはバイリンガル環境によるものではなく,発達の問題であると考えられた。
5 0 0 0 OA S3-2.東日本大震災後の子どものケアにおけるTF-CBTの実践
- 著者
- 八木 淳子
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.544-552, 2016-08-01 (Released:2017-05-17)
- 参考文献数
- 4
- 著者
- 岡田 智
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.2-6, 2019-02-01 (Released:2020-02-28)
- 参考文献数
- 11
4 0 0 0 OA LDへのICT活用の効用と限界
- 著者
- 福本 理恵 平林 ルミ 中邑 賢龍
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.379-388, 2017-06-01 (Released:2019-08-21)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
ICT機器の普及はLD児の障害機能の代替を可能にしている。それと同時に法律と社会インフラの整備により,教科書など子どもたちが使用する紙の印刷物をアクセシブルな形でLD児に提供可能になった。これによりLD児の読み書きの負担は低減してきている。しかし,こういった技術発展と制度整備があるにも関わらず,特別支援教育やリハビリテーションは,治療訓練するアプローチが中心でICTを活用した代替に移行できないでいる。治療訓練は子どもによっては大きく効果を上げる場合もあるが全ての子どもに有効な訳ではない。効果のない訓練が学習の遅れをさらに拡大し,それが子どものモチベーションを低下させ,自己効力感を消失させることになる。一方,ICTを早期から導入することでLD児が高等教育に進学する事例が出てきている。ただし,ICT活用にも限界はある。それは,学習に大きな遅れが生じ,学習へのモチベーションを失っている場合は,ICTを導入したところで問題が解決するわけではない。こういった子ども達を学習に戻す事は容易ではなく,別のアプローチが必要となる。本稿では彼らのモチベーションを高め,現状の能力で学べる教材と場所を提供する取り組みを紹介し,今後のLD児への教育に求められる視点を展望した。
4 0 0 0 OA S01-4.mTOR阻害薬を用いたASDの薬物治療
- 著者
- 水口 雅
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.363-367, 2018-08-01 (Released:2019-08-21)
- 参考文献数
- 17
3 0 0 0 OA ASEBA行動チェックリスト(CBCL:6-18歳用)標準値作成の試み
- 著者
- 船曳 康子 村井 俊哉
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.175-184, 2017 (Released:2017-07-04)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 3
目的:ASEBA(Achenbach System of Empirically Based Assessment)の原本に従い,CBCL(Child Behavior Checklist)/6-18の行動チェックリストについて,日本語版による標準値作成を試みた。方法:参加者3,601人を,男児・6-11歳群(924人),男児・12-18歳群(849人),女児・6-11歳群(880人)および女児・12-18歳群(948人)の4グループに分けて,素点をもとに「不安/抑うつ」,「引きこもり/抑うつ」,「身体愁訴」,「社会性の問題」,「思考の問題」,「注意の問題」,「規則違反的行動」,「攻撃的行動」の症状群尺度,内向尺度,外向尺度および全問題尺度のT得点を算出した。信頼性と妥当性は,Cronbachのα係数,尺度間相関とASSQ(The high-functioning Autism Spectrum Screening Questionnaire)との基準関連妥当性を検討した。8症状群への性および年齢群の影響を重回帰分析を用いて検討した。結果および考察:α係数は良好で,尺度間の相互相関は全て有意であり,ASSQとも正の有意な相関を示して,尺度としての妥当性に問題は認めなかった。また,重回帰分析の結果からは,男児は「注意の問題」と「規則違反的行動」において問題を生じ,女児は「不安/抑うつ」と「身体愁訴」に問題を生じる傾向があった。年齢では,低年齢群が「不安/抑うつ」,「社会性の問題」,「思考の問題」,「注意の問題」,「規則違反的行動」および「攻撃的行動」に問題を生じており,高年齢群は特に「引きこもり/抑うつ」に問題を生じる傾向があった。
3 0 0 0 OA S08-3.産婦人科医による若者の自殺予防
- 著者
- 上村 茂仁
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.11, 2018-02-01 (Released:2019-08-21)
3 0 0 0 OA 喋れなくても言葉はある,わからなくても心はある ─自閉症当事者とのコミュニケーション─
- 著者
- 山登 敬之
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.4, pp.507-513, 2017-08-01 (Released:2019-08-21)
- 参考文献数
- 10
3 0 0 0 OA 思春期の4年間を病棟で過ごした摂食障害女児の治療経過 ─こころが自由になること─
- 著者
- 黒江 美穂子 宇佐美 政英 渡部 京太 齊藤 万比古
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.458-470, 2016 (Released:2019-08-21)
- 参考文献数
- 15
10歳で神経性無食欲症を発症した女児の,長期入院治療を経験したのでここに報告する。女児の強固な拒食病理や完璧主義的思考により,経過は一進一退であったが,徐々に心身の健康と年齢相応の自立志向性を獲得していった。女児の症状形成過程および入院治療が長期化した背景にある精神病理を考察し,治療においては身体管理や生命の保護のみならず,治療スタッフの関わりによる基本的信頼感の構築,さらに同年代仲間集団との交流といった複合的な機能を担った児童思春期専門病棟の意義について述べた。また家族療法の導入により,治療者が多角的,重層的な視点から症例を捉えられたこと,両親が親としての支持機能を回復し,特に母親が活き活きと情緒的応答性を取り戻したことが,回復の鍵となった。
3 0 0 0 OA 児童青年期から通院を継続している自閉症スペクトラム障害患者の就労状況について
- 著者
- 武井 明 鈴木 太郎 土井 朋代 土井 準 富岡 健 廣田 亜佳音 泉 将吾 目良 和彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.5, pp.742-756, 2017-11-01 (Released:2019-08-21)
- 参考文献数
- 27
高機能の自閉症スペクトラム障害(ASD)患者が成人後に示す就労状況については十分検討されていない。そこで,今回われわれは,児童青年期から経過観察できた高機能のASD患者が示す成人後の就労状況を明らかにするための調査を行った。対象は18歳以下で当科を初診した高機能のASD患者のうちで,成人後も通院を継続している56例(男性21例,女性35例)である。調査時の平均年齢は24.1歳で,経過観察期間は平均9.3年であった。DSM-IV-TRによる診断では自閉性障害8例(14.3%),アスペルガー障害19例(33.9%),特定不能の広汎性発達障害が29例(51.8%)であった。最終学歴は高校卒業以上が39例(69.6%)を占めていた。併存症状は初診時に56例全てに認められ,最も多かったのは不登校で48例(85.7%)であった。一方,成人後の併存症状は32例(57.1%)に認められ,最も多かったのはひきこもりで15例(26.8%)であった。成人後の就労状況では,就労している者が15例(26.8%)(正規雇用は5.4%),就労支援事業所などに通所している者が17例(30.4%),無職者が24例(42.8%)であった。また,就労している者では併存症状を有している者が有意に少なかった。以上の結果から,成人後まで通院を継続しているASD患者では,知能が高くても正規雇用され自立した生活を送ることのできる者はきわめて少ないことが明らかになった。また,併存症状の有無が転帰に影響を与える可能性が示唆された。したがって,通院を継続している高機能のASD患者に対しては,青年期以降も切れ間のない継続した支援が成人期まで必要であると考えられた。
3 0 0 0 OA 児童青年期精神科における薬物療法の実際2
- 著者
- 宇佐美 政英
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.146-156, 2017 (Released:2017-07-04)
- 参考文献数
- 49
- 著者
- 二宮 有輝 松本 真理子
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.5, pp.597-613, 2018-11-01 (Released:2020-02-28)
- 参考文献数
- 42
【問題と目的】日本の大学生を対象にSNSの活動データを収集し,抑うつ症状を伴う青年におけるSNS上の特徴を明らかにすることを目的とした。【方法】Twitterを利用している大学生158名(男性94名,女性63名,不明1名,平均年齢18.89,SD=0.90,有効回答率73.8%)を分析対象として,抑うつ得点に基づき,正常群(57名),軽度群(75名),中程度以上群(26名)に群分けした。各参加者のTwitterから1カ月分の活動データを収集し,群間の差異を検討した。【結果および考察】Twitter活動データについて群間の差異を検討した結果,正常群に比して,軽度群および中程度以上群の方が午前中のオリジナルツイート(独り言)の割合が高くなる傾向が認められた。午前中のオリジナルツイート1,919件を対象にテキストマイニングを用い,対応分析により抑うつ群変数と抽出語との関連を検討した結果,「現実生活の多忙さ」と「現実生活からの逃避」の2成分が得られた。また,対応分析の布置図から,軽度群では学業などの現実生活の多忙さが表現されやすく,中程度以上群では学業からの逃避態度や,躁的な防衛と考えられる特徴がTwitter上に表現されやすいことが示された。今後は午前中のツイートだけでなく,対象とする投稿の範囲を広げ,本研究で得られた示唆が投稿全体に認められるのかどうかを検討する必要があるだろう。
3 0 0 0 OA 児童・青年期の非自殺性自傷 ─嗜癖と自殺との関係から─
- 著者
- 松本 俊彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.158-168, 2019-04-01 (Released:2020-02-28)
- 参考文献数
- 28
非自殺性自傷とは,感情的苦痛の緩和や他者に対する意思伝達や操作などの,自殺以外の意図からなされる,故意の身体表層に対する直接的損傷行為を指す。この行動は,DSM-Ⅳ-TRの時代までは,境界性パーソナリティ障害の一症候としてのみ認識されてきたが,DSM-5では,この行動は境界性パーソナリティ障害とは独立した診断カテゴリーとなった。このことは,従来の,自傷を限界設定の対象と見なす考え方から,自傷それ自体を治療の対象とする考え方と,治療理念の変化が生じたことを意味する。本稿では,まず非自殺性自傷に関する臨床概念の歴史的変遷を振り返り,今日における非自殺性自傷の捉え方へと至る過程を確認したうえで,物質使用障害などの嗜癖,ならびに自殺との異同を論じ,最後に,DSM-5における非自殺性自傷の診断カテゴリーの意義と課題について筆者の私見を述べた。
3 0 0 0 OA 児童精神科医としてかかわる中で考えたこと
- 著者
- 大高 一則
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.170-170, 2017 (Released:2017-07-04)
3 0 0 0 OA 子どもシェルターの現場から
- 著者
- 坪井 節子
- 出版者
- 一般社団法人 日本児童青年精神医学会
- 雑誌
- 児童青年精神医学とその近接領域 (ISSN:02890968)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.132-133, 2017 (Released:2017-07-04)