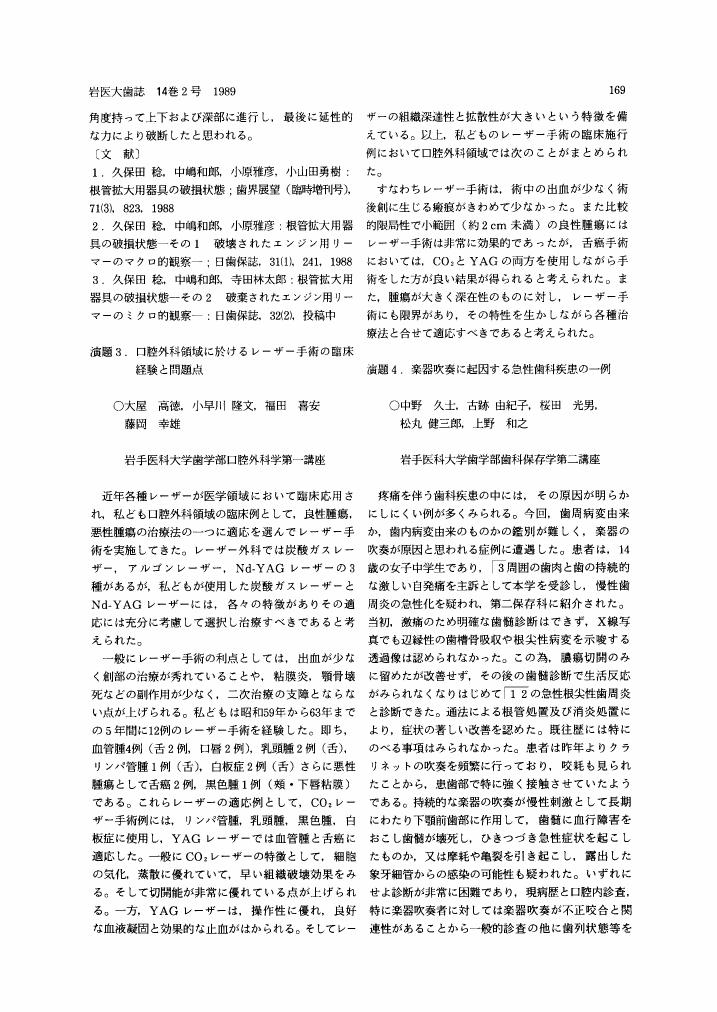1 0 0 0 OA 口腔機能の障害は脳機能活動にどのように現れるか
- 著者
- 小林 琢也 近藤 尚知
- 出版者
- 岩手医科大学歯学会
- 雑誌
- 岩手医科大学歯学雑誌 = Dental journal of Iwate Medical University (ISSN:03851311)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.88-97, 2015-01
1 0 0 0 OA 薬物誘発性歯肉増殖症の基礎と臨床
- 著者
- 國松 和司 尾崎 幸生
- 出版者
- 岩手医科大学歯学会
- 雑誌
- 岩手医科大学歯学雑誌 (ISSN:03851311)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.1-10, 2007-04-25 (Released:2017-03-20)
- 参考文献数
- 60
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 東日本大震災における身元確認作業
1 0 0 0 OA デジタルスキャニングデバイスを用いたインプラントアバットメントの位置再現性の検討
- 著者
- 味岡 均 鬼原 英道 大平 千之
- 出版者
- 岩手医科大学歯学会
- 雑誌
- 岩手医科大学歯学雑誌 (ISSN:03851311)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.1-13, 2015-04-23 (Released:2017-03-05)
- 参考文献数
- 33
本研究の目的は,デジタルスキャニングデバイスである口腔内スキャナーと歯科技工用スキャナーを用いてインプラントアバットメント間の距離の真度と精度を比較し,その有用性を評価検討することである.インプラント実習用顎歯模型に外側性六角構造を有する2本のインプラント体を埋入した.それぞれのインプラント体にボールアバットメントを装着し,ボールの中心間の距離の測定を行った.接触式三次元座標測定機による測定値と,口腔内スキャナーであるLava COSとTRIOS,歯科技工用スキャナーであるARCTICAの測定値を比較し,それぞれの距離の真度と精度を評価した.真度に関して,Lava COSはTRIOS,ARCTICAと比較して有意な差(p<0.05)を認めた.また精度に関しては,Lava COSとARCTICAの間に有意な差(p<0.05)を認めた,真度と精度の偏差はARCTICAが最も小さく,Lava COSが最も大きかった.さらに,口腔内スキャナーによる測定誤差は,術者によっても有意な差(p<0.05)が認められることがあった.本研究の結果より,歯科技工用スキャナーは一度に広範囲の撮影が可能なため,安定した真度と精度を有すると考えられる.一方,口腔内スキャナーは小さな三次元画像をつなぎ合わせることでデータの結合を行なうので誤差が蓄積しやすいと考えられる.そのため口腔内スキャナーは長い区間の撮影において誤差が増大する傾向がみられたが,口腔内スキャナーの中には歯科技工用スキャナーと同等の真度と精度を有するものも存在した.口腔内スキャナーは印象材の歪みや石膏膨張の影響を受けないという特徴より真の値に近い寸法再現性が期待されたが,上記結果から,口腔内スキャナーは従来の印象法に比較して,真度の点でわずかに劣る可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA 同一歯のエナメル質表層における各種フッ化物のとりこみ量についての検討
- 著者
- 飯島 洋一 松田 和弘 田沢 光正 三浦 陽子 高江洲 義矩
- 出版者
- 岩手医科大学歯学会
- 雑誌
- 岩手医科大学歯学雑誌 = DENTAL JOURNAL OF IWATE MEDICAL UNIVERSITY (ISSN:03851311)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.68-78, 1978-03-15
1 0 0 0 OA 4.ショートインプラント上部構造装着後3年経過症例に関する臨床的調査
1 0 0 0 OA 硬組織石灰化についての最近の知見
- 著者
- 名和 橙黄雄
- 出版者
- 岩手医科大学歯学会
- 雑誌
- 岩手医科大学歯学雑誌 = DENTAL JOURNAL OF IWATE MEDICAL UNIVERSITY (ISSN:03851311)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.119-129, 1981-11-30
1 0 0 0 OA 顔面形態と顎関節における運動ならびに形態との関連性
- 著者
- 小笠原 和志
- 出版者
- 岩手医科大学歯学会
- 雑誌
- 岩手医科大学歯学雑誌 (ISSN:03851311)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.197-206, 1997-12-30 (Released:2017-06-05)
- 参考文献数
- 35
An aim of this study was to clarify the relationship between the difference in facial types and the movements, and the morphology of the temporomandibular joint (TMJ). The subjects were 46 persons (32 males and 14 females) aged from 22 to 34 years, who had no particular abnormality about the masticatory system. Facial types were classified into three: Brachyfacial type (B), Mesofacial type (M), and Dolichofacial type (D), by tracing the lateral roentogenographic cephalograms. The movements of mandibular condyle were recorded by the condylar movements recording system (CADIAX®), Gamma CO. Ltd., Wien, Austria), and the movements of articular disc were analyzed by using a magnetic resonance imaging (MRI). Morphology of the TMJ was also measured by using a computed tomography (CT) and standardized radiographs of TMJ. The results obtained were as follows:1. No difference in quantity of condylar translation in protrusive movement at the most protruded position (QCTP) was shown between the three. But the inclination of sagittal condylar path (ISCP) was steeper in B than in D.2. Quantity of condylar translation in opening and closing movement at the maximum opening position (QCTO) and quantity of the maximum condylar rotation in opening and closing movement (QCRO) were larger in B than in D.3. B was larger than D in quantity of non-working side condylar translation in lateral movement (QCTL) at the eccentric position.4. Quantity of articular disc movement was larger in B than in D.5. Maximum cross-sectional area (MCSA), horizontal condylar angle (HCAN) and angle of posterior slope of the articular eminence (APSE) were larger in B than in D.6. Some significant TMJ correlation was found between items of movement and items of morphology.These results suggest that facial types will be related to TMJ movements and its morphology.
1 0 0 0 OA 演題4.楽器吹奏に起因する急性歯科疾患の一例
- 著者
- 中野 久士 古跡 由紀子 桜田 光男 松丸 健三郎 上野 和之
- 出版者
- 岩手医科大学歯学会
- 雑誌
- 岩手医科大学歯学雑誌 (ISSN:03851311)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.169-170, 1989-08-31 (Released:2017-11-19)
1 0 0 0 OA 造血幹細胞移植後に再発した白血病に対し再移植を行った患者の口腔管理の1例
- 著者
- 阿部 晶子 千葉 舞美 熊谷 佑子 赤松 順子 岸 光男
- 出版者
- 岩手医科大学歯学会
- 雑誌
- 岩手医科大学歯学雑誌 (ISSN:03851311)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.109-119, 2018-02-09 (Released:2018-03-11)
- 参考文献数
- 15
背景岩手医科大学血液腫瘍内科では,造血幹細胞移植中における口腔粘膜障害の発症予防を目的に,造血幹細胞移植チームに歯科医師・歯科衛生士が加わり移植患者の口腔管理を行っている. 今回,移植後に白血病が再発し,再移植を行なった患者について,初回と再移植時の口腔管理を行う機会が得られたので,比較して報告する. 症例と臨床経過 症例は初回移植時41 歳の女性で,2013 年8 月に急性骨髄性白血病のため末梢血幹細胞移植を施行した. その後再発を認め,2014 年6 月に再移植で骨髄移植を施行した. 再移植後,生着が確認されたが,同年9 月,全身状態の悪化により死亡した. 口腔粘膜炎と介入 口腔管理の介入は,移植前処置の施行前から開始し,初回移植および再移植時には,口腔内の状態に応じて,保湿剤,含嗽剤おび軟膏の処方,P-AG 液の服用指導,セルフケアの支援を行った. 再移植では口腔粘膜障害のリスクが高いことを予測し,予防的管理を行ったが,粘膜障害は重症化し,生着し白血球数増加後も口腔粘膜障害が長期間残存した. 口腔粘膜障害が重症化した要因としては,第一に 前処置に全身放射線照射が加わったこと,第二に骨髄抑制時期が長期化したこと,第三に初回の移植による移植片対宿主病が残存していたことなどが考えられた. 結論 再移植では開口障害,粘膜炎による疼痛,全身状態の悪化などにより患者本人のみならず,我々医療スタッフの口腔管理への技術的・精神的負担も大きなものであった. 口腔管理が困難であった今回の症例において、介入を継続するうえで、初回移植時から構築した患者や多職種との信頼関係が大きな力となった。本症例より、患者を含むチーム医療の重要性を再認識することができた。
1 0 0 0 義歯による口蓋の被覆がヒトの脳内味覚応答に及ぼす影響
- 著者
- 久保田 将史 小林 琢也
- 出版者
- 岩手医科大学歯学会
- 雑誌
- 岩手医科大学歯学雑誌
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.51-68, 2015
高齢者人口の増加に伴い,味覚障害患者が増加している.味覚障害の病態と原因は多岐にわたり,歯科領域では口蓋を被覆する床義歯を装着した患者がしばしば味覚障害を訴えることがある.しかし,その因果関係は未だ明らかでない.本研究で義歯装着による味覚障害の原因を明らかにすることを目的に,従来までの主観的評価による検討ではなく,上位中枢より客観的評価が可能な非侵襲的脳マッピング法の1つであるfunctional Magnetic Resonance Imaging (fMRI)を用いて,口蓋の被覆が味覚応答に及ぼす影響を脳機能応答の観点から検討した.実験は,口蓋単独での味覚応答を脳機能応答として捉えるため,右利き健常有歯顎者15名を対象とし,口蓋に限局した味刺激を与えた.次に,口蓋被覆が味覚応答に及ぼす影響の検討を行うため,右利き健常有歯顎者14名に口蓋を被覆しない状態(コントロール)と口蓋を被覆した状態(口蓋被覆)で味刺激を与えた.両実験は,味刺激試液として各被験者の認知閾値に設定したキニーネ塩酸塩,洗浄用試液として人工唾液(25mM KCl, 25mM NaHCO_3)を用いた.本研究より,口蓋へ限局した苦味刺激により一次味覚野の島と前頭弁蓋部に賦活が認められた.また,口蓋被覆時の刺激では,コントロールと同様に一次味覚野の島と前頭弁蓋部,そしてさらに二次味覚野の眼窩前頭皮質に賦活が認められた.しかし,両条件間の脳活動範囲と脳活動量を比較したところ,口蓋被覆により一次味覚野と二次味覚野での賦活範囲は有意な減少が認められ,脳活動量においても一次味覚野で有意な減少が認められた.以上より,口蓋での味覚刺激応答が上位中枢で行われていることを客観的に捉えることができた.また,義歯による口蓋粘膜の被覆が,脳内の味覚応答を低下させることが明らかとなり,床義歯装着が味覚障害を惹起させることが示唆された.
1 0 0 0 下顎の偏位が脳機能応答に及ぼす影響
- 著者
- 櫻庭 浩之 小林 琢也
- 出版者
- 岩手医科大学歯学会
- 雑誌
- 岩手医科大学歯学雑誌
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.1-13, 2014
不適切な下顎位で補綴治療が行われると, 咬合の不調和を引き起こし咬合接触の異常や下顎運動の異常を生じ, ひいては全身機能に影響を及ぼすとされている. 下顎偏位がストレス反応を介して, 不快や痛みのネットワークを賦活させることはこれまで報告されているが, その偏位方向や運動の種類による賦活の差に関しては検討されていない. そこで本研究は, 下顎偏位が脳機能に及ぼす影響を明らかにするために, 下顎を水平的偏位させた状態で Tapping 運動と Clenching 運動を行い, 非侵襲的脳マッピング法の1つである functional Magnetic Resonance Imaging ( fMRI ) を用いて脳機能応答の変化を観察した.<br> 実験は右利きの健常有歯顎者10名に咬頭嵌合位 (コントロール) と前方,左方および右方の下顎偏位条件でTapping運動とClenching運動の2種類の課題を行わせた. 画像解析を行い賦活部位の同定を行った後, コントロール条件と偏位条件での脳活動量の比較を行った. その結果, Tapping 運動時に,下顎偏位条件ではコントロール条件で賦活が認められなかった扁桃体に賦活が認められた. 扁桃体における脳活動量を比較すると, コントロールと比較して各水平的偏位条件で有意に活動量が増加していた. 一方, Clenching運動時には,下顎偏位条件ではコントロール条件で賦活が認められなかった腹内側前頭前野と扁桃体に賦活が認められ, これらの部位における脳活動量もコントロールと比較して各水平的下顎偏位条件で有意に増加していた.<br> これらの結果より,下顎の水平的偏位は偏位方向や運動の種類によらず不快を引き起こし, とりわけClenching運動においてより強い不快応答を伴うと推測される.
1 0 0 0 OA 表情筋に分布する下歯槽神経の枝
- 著者
- 藤澤 慶子 島田 崇史 小幡 健吾 鈴木 莉絵 安藤 禎紀 藤原 尚樹 藤村 朗
- 出版者
- 岩手医科大学歯学会
- 雑誌
- 岩手医科大学歯学雑誌 (ISSN:03851311)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.69, 2015-04-23 (Released:2017-03-05)
1 0 0 0 表情筋に分布する下歯槽神経の枝
1 0 0 0 OA 新しい診査基準による乳幼児期の咬合診査と歯科保健指導
- 著者
- 亀谷 哲也 三浦 廣行 中野 廣一 八木 實 清野 幸男 猪股 恵美子
- 出版者
- 岩手医科大学歯学会
- 雑誌
- 岩手医科大学歯学雑誌 (ISSN:03851311)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.144-151, 1988-08-30 (Released:2017-11-19)
- 参考文献数
- 19
新しい診査基準を用いて, 岩手県紫波郡矢巾町の0歳から6歳までの咬合診査を行った。その結果, 不正咬合は, 1歳6カ月児から46.2%という高い頻度で認められ, とくに乳歯咬合の完成に近い2歳児では49.1%とさらに高い頻度でみられた。不正要因は, discrepancy要因のものが1型, 2型とも多く, 年齢群では, 1歳6カ月児, および2歳児が最も多かった。他の骨格型や機能型は各年齢群を通じて大きい変動はなく, 全体として出現頻度は低いが, 骨格型では6歳児で13.9%に認められた。重症度は, A, B, の段階までが約90%を占めていたが, Cと診断される不正咬合の保有者も少数ではあるが認められた。以上の結果に基づく保健指導は, とくに顎骨の発育を促進させるような食生活の指導を補強する必要があると考えられた。治療に関する指導では重症度を参考に骨格型, discrepancy型を中心に治療開始の適当な時期を見逃さないように指摘しておくことが重要であると思われた。
- 著者
- 鈴木 鍾美
- 出版者
- 岩手医科大学歯学会
- 雑誌
- 岩手医科大学歯学雑誌 = DENTAL JOURNAL OF IWATE MEDICAL UNIVERSITY (ISSN:03851311)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.3, pp.226-227, 1985-11
1 0 0 0 IR 東日本大震災における身元確認作業
1 0 0 0 OA わが国における舌癌剖検症例の統計的検討(第VI報)
- 著者
- 佐藤 方信 及川 優子 古屋 出
- 出版者
- 岩手医科大学歯学会
- 雑誌
- 岩手医科大学歯学雑誌 (ISSN:03851311)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.53-64, 2005-04-25
- 被引用文献数
- 2
Autopsy cases of tongue cancer in Japan were statistically analyzed. Autopsy cases were collected from the Annual of Pathological Autopsy Cases in Japan over the past five years (1997-2001). Tongue cancer was reported in 321 autopsy cases(M:241, F:79, Unknown: 1). The autopsy rate was 6.0% of 5,320 patients who died of tongue cancer in Japan. 103 of the autopsied patients (32.2%) were in their seventh decade, 74 (23.1%) were in their eighth decade, and 54 (16.9%) were in their sixth. Histologically, almost all the cases showed squamous cell carcinoma (96.8%). The cancer arose most frequently in the lateral borders (66.1%) of the tongue. Multiple primary cancers, affecting both the tongue and other organs, were found in 113 cases. The mean ages of only the autopsied cases of squamous cell carcinoma excluding the cases of multiple primary cancers were 63.8±10.1 (1997), 57.7±12.3 (1998), 65.4±13.6 (1999), 61.7±15.4 (2000) and 62.1±14.9 (2001) years old. However, the mean ages of multiple primary cancers, affecting both the tongue and the other organs, were 69.2±9.9 (1997), 70.5±11.2 (1998), 66.6±10.2 (1999), 68.2±11.6 (2000) and 69.9±15.5 (2001) years old. In cases of double cancers including tongue cancer, commonly occurring cancers were lung, liver, esophagus, thyroid and adrenal. Metastasis to other organs was frequently found in the tracheobronchus and lungs, liver, heart and aorta, bones, adrenals and thyroid. Metastasis to the lymph node was found in the cervix, lung hilum, periesophagus and peritrachea, left supraclavicula, and axilla. The most common cause of death was pulmonary infection.