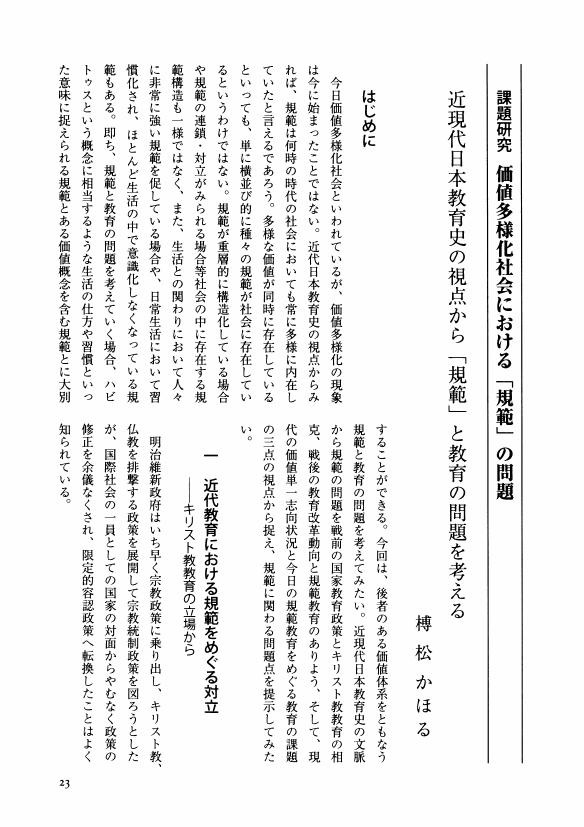2 0 0 0 OA 透明な言語・不透明な知性 コメニウス『光の道』における光のメタファー
- 著者
- 北詰 裕子
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, no.96, pp.22-41, 2007-11-10 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 68
This paper examined J. A. Comenius' The Way of Light as a theory of language in the metaphor of light, one that is crucially related of cognition of things.In The Way of Light, Comenius expresses the world and human beings in a metaphor of light. External light illuminates all things and clarifies every thing. It overcomes every darkness in the world. On the other hand, Internal light means intellectual light in particular. This light overcomes darkness of ignorance in soul, and intellect has an opaque characteristic. Opaque intellect receives light, blocks its further penetration, keeps the truth of things within itself, and reflects and scatters it around the world again. It can be said that working of this intellect is a function of the language. From the point of view of human history, Comenius said that the scatter of light spreads through cognition, conversation, a meeting of a church, books, printing and the art of navigation. Furthermore, this process is expansion of education to give light for human mind.Comenius considers the cognition of things from the perspective of light because he has an assumption that every visible thing in the world has truth of God. And ideal universal language is designed as a medium to represent the truth of things.In other words, what is considered as the language in Comenius has triplex meanings : a language that articulates the light as opaque intellect, a language as the world itself has, and a transparent language that represents the world. These triplex meanings of language are deeply related to the educational thought of Comenius.
- 著者
- 平田 仁胤
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, no.95, pp.71-88, 2007-05-10 (Released:2010-05-07)
- 参考文献数
- 20
In recent years, “representation learning, ” which assumes that knowledge presupposes representation, has been criticized. In this criticism “Wittgenstein'sparadox” has been used to point out the logical impossibility of “representation learning” : as long as the notion of “representation” is assumed, the paradox would happen inevitably and spoil “representation learning.” However, the paradox HERE is considered to be merely a theoretical fiction for it does not happens in normal cases, and hence, does not spoil learning. In view of the criticism, this paper attempts to show, by analyzing elaborately Wittgenstein's rule-following considerations, that “Wittgenstein's paradox” can not be seen simply as a fiction. In Wittgenstein's rulefollowing considerations, the notion of “inner-binding” and that of “outer-binding” are crutial. The former is a disposition that is built through “training”. This disposition enables one to judge the “sameness” and to be convinced of the necessity of that sameness. The latter is “institution” that is established through the repetition of “peaceful accordance”. The two bindings sometimes do not conflict with each other.This is exactly the case in which rule-following operates.“Inner-binding” has not been formed yet in an earlier stage of “rule” learning.Therefore “outer-binding” conflicting with the inner does not appear. But the two can come to differentiate themselves from each other as learning progresses and as the inner has been formed. The conflict between the inner> and the outer is equivalent to the case which “Wittgenstein's paradox” describes. Accordingly the possibility of differentiation exists latently and the paradox is not a theoretical fiction.The latent possibility of “Wittgenstein's paradox” indicates that learners are not in a position to distinguish the two. This suggests that learning is uncertain and learning theories are not transparent to learners.
2 0 0 0 OA 希望、この無気味なるもの O・F・ボルノウ「希望の哲学」再考
- 著者
- 井谷 信彦
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.94, pp.1-20, 2006-11-10 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 36
本稿は、現代ドイツの教育学者ボルノウと、彼の思想に深い影響を与えた哲学者ハイデガーについて、両者の思索の関わりを問い直す研究の一環として位置づけられるものである。ハイデガー哲学からの影響を認めながらもボルノウは、その思想の根幹である「存在への問い」が開き示す可能性については、それを繰り返し排除あるいは無視し続けてきた。しかしながら、この拒絶がそもそも或る種の誤解に基づくものであったとすればどうだろうか。むしろその点に、ボルノウ自身によっては主題的に論じられることのなかった別なる思索の可能性が潜在しているのではないか。ハイデガーによる「存在への問い」についての考察を通じて、ボルノウによる人間学的な教育学がもついっそう豊かな可能性を解き放つことが、本研究に与えられた最終的な課題である。特にその端緒として本稿では、ボルノウによる「希望の哲学」をハイデガーによる「不安の分析論」をふまえて問い直すことが試みられる。
2 0 0 0 OA 「新優生学」と教育の類縁性と背反 「他者への欲望」という視座
- 著者
- 森岡 次郎
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.93, pp.102-121, 2006-05-10 (Released:2010-01-22)
- 参考文献数
- 74
The purpose of this paper is to examine new eugenics and education.For the last several years, such ideas as “Designers Baby” and “Perfect Baby” have been discussed in terms of “New Eugenics”. This idea means the artificial production of babies by genetic technology according to the desire of parents. If educational values can be realized to some extent by genetic technology, new eugenics will necessitate our views on education to change. From this perspective, this paper examines the implications of new eugenics for education.First of all, the history of eugenics is surveyed and new eugenics is positioned historically. Here, new eugenics can be positioned in an eugenical trend after the 1970s. Next, the theoretical features of new eugenics are clarified in its contrast to old eugenics. This makes it clear that new eugenics is based on the principle of selfdetermination and on the principle of scientific validity. (2) Then, the criticisms of new eugenics are reviewed. Here, by considering Glen McGee's and others' arguments, it becomes clear that any fatal criticism of new eugenics does not exist yet. However, in the argument by Jürgen Habermas, education and new eugenics are distinguished in view of the existence of “others.” It enables us to find out a positive value to the conditions of “others” in education that cannot be fully satisfied. (3) Finally, it is clarified from the standpoint of the system theory of Niklas Luhmann that children as “others” are indispensable as the media in an educational system. Based on Emmanuel Levinas' concept of “désir”, I present the point of view of “the desire for others”, one that gives a positive value to the “existence of others”. (4) “New eugenics” and education have affinity in terms of operational intervention in children. However, from the point of view of “the desire for others”, it becomes clear that both are fundamentally in conflict.
2 0 0 0 OA 森田伸子著『文字の経験-読むことと書くことの思想史-』
- 著者
- 丸山 恭司
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.93, pp.151-157, 2006-05-10 (Released:2009-09-04)
いまこの文章を読んでくださっている皆さんであれば、すでに文字をめぐるさまざまな経験をお持ちだろう。書店あるいは図書館の膨大な文献を前にして目のくらむような思いをされたことはなかっただろうか。あるいは、慣れない横文字と格闘しながら「読み」にともなう摩擦を実感されたこと、買ったばかりのペンで何度も自分の名前や恋い焦がれるひとの名前を白い紙に書き連ねてみた経験。もちろん、文字のない文化に生まれ育ってもひとはまっとうに生きていけよう。一方、文字を持ってしまったわれわれには、もはや文字は-意識しようがしていまいが-われわれの身体と感情と思考と願望を方向付ける枠組みの一つとなっている。文字はわれわれの生活を制限付けるとともに豊かにもしてくれているのだ。本書は、文字に生きたひとびとに著者自身が寄り添いながらそうした生活の豊かな広がりを描き出した作品である。森田氏は本書について次のように言う。「本書は、ここ数年来私の研究関心を占めてきた、言語、とりわけ文字言語が人間にとって持つ意味について考察をまとめたものです」 (二七五頁) 。本編には、既発表論文四篇が全体構成にあわせて裁断され書き直されて組み込まれているものの、「全体としてはほぼ書き下ろしといっていいもの」である。四篇の論文のうちには古くは一九八七年に発表されたものもあり、森田氏がこのテーマに長く関心を寄せられていたことがうかがえる。それどころか、「文字の人」であったご両親への想いが綴られているように (二七七頁以降) 、氏の研究関心はパーソナルな強い思いに裏打ちされている。氏が「本書は研究書として書かれたというよりは、私の自由な考察を述べたものになりました」 (二七六頁) と言うのも、本書が専門家に留まらず広い読者に向けて書かれたからだけでなく、文字に生きたひとびとへの共感があるからであろう。また、本書のねらいについて森田氏は次のように言う。「本書では、文字をめぐるさまざまな思索と経験について書かれたテクストを取り上げ、できる限りその思索と経験を忠実に追体験してみることに努めてみたい」 (iV頁) 。そして、読者は森田氏に誘われてさまざまな物語を追体験することになる。フランシス・コッポラ監督の映画『アウトサイダー』に描かれたジョニーとダラスの死に立ち会い、パリの裏町を舞台にした映画から、親になかば捨てられたユダヤ人少年モモとトルコ移民の老人イブラヒムとの交流を見守る。二人の「文盲」、一八世紀フランスの羊飼いデュヴァルと二〇世紀イタリアの羊飼いガヴィーノの自伝。ドラッグとセックスの日常を生きる若者を描いた小説『レス・ザン・ゼロ』の主人公クレイの救い。フィクションであれ、ノンフィクションであれ、固有名を持つ個人の多様な生が文字をめぐる人生として確認されるのである。こうした人生の追体験を縦糸にして、さまざまなリテラシー観、啓示・啓蒙・聾教育・国民形成における文字思想の検討を横糸として本書は編まれている。
2 0 0 0 OA D・W・ウィニコットにおける「戯れ」としての自我 対象関係という視座から
- 著者
- 波多野 名奈
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, no.92, pp.77-95, 2005-11-10 (Released:2010-05-07)
- 参考文献数
- 40
H. Guntrip said that Freud's Ego has two types of thinking, “System Ego” and “Person Ego”, and that D. W. Winnicott the leading figure of the Independent School and the Object- Relations Theory in England deepened the latter. This paper examines his concept of Ego which inherited and further developed Freud's Ego. The author will discuss his theory about Ego with the term “playing” as related from two aspects of the diachronic- developmental and the synchronic- structural.From the perspective of child- development, Ego comes from the primary world of omnipotence. In this primary world, Me and Not Me are not divided but are merged, so that the relations with objects as Not - Me have not started yet. After the separation of Me and Not- Me, Ego is established. Until Ego takes shape the object- relations do not start.Ego is the “potential space” which is born in the place between two worlds, the primary world of omnipotence and the existent world of objects. Ego not only divides but also unites both worlds. This paradox has not been resolved in Winnicott's theory. At this point, he uses the term “playing”.Winnicott's Ego from the synchronic aspect appears as the fusion of the primary world of omnipotence and the world of objects. This fusion shows itself at cultural activities, especially at play. With Freud's case of “Cotton Reel” play or Winnicott's transitional objects, we can find a primitive form of the symbol which reproduces the primary world of omnipotence in the existent objects. These primary symbols have the ambivalent functions; to reproduce the primary world, on one hand, and to promote the separation from it, on the other. That is to say, Winnicott's Ego appears as “playing” in the duality.
2 0 0 0 OA 〈意味による生成〉への奉仕 フランクル臨床哲学の再解釈による教育理解深化の試み
- 著者
- 岡本 哲雄
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, no.92, pp.40-58, 2005-11-10 (Released:2010-05-07)
- 参考文献数
- 16
Dieser Aufsatz ist ein Versuch, die klinische Philosophie V. E. Frankls, die “Logotherapie und Existenzanalyse” genannt wird, als den Dienst (therapeía) an “das Werden durch den Sinn (logos)” zu beurteilen, und dann dadurch die Bedeutsamkeit der Erziehung zu vertiefen.Die Frage nach dem Sinn des Lebens liegt immer schon auf den Boden der menschlichen und zwischenmenschlichen Tätigkeit. Seine klinische Philosophie kann so verstanden werden, daß sie den Begriff “Sinn” “auf die Stätte einer fortwährenden Begegnung des Endlichen mit dem Unendlichen” setzt, und aus diesem Stützpunkt heraus die Menschwerdung zu erläutern versucht. Die “Logotherapie und Existenzanalyse” hat die Bestimmung, seinen eigenen Sinn finden zu lassen. Also hat sie auch die “Besinnung” und “Gesinnung” den Alltag durchsichtig zu machen nämlich durch ihn hindurch sehen zu lassen auf das Ewige und dann auch sehen zu lassen, wie dieses Ewige auf das Zeitliche (das Alltägliche) zurückverweist.Der Begriff “Sinn (logos)” ist immer schon mit “Leiden (pathos)” unterteilbar in der Wirklichkeit seiner praktische Philosophie. Beide sind zwei Brennpunkte seiner Anthropologie. Aber niemand hat bis jetzt verstanden daß beide “immer schon unterteilbar” sind. Also richten wir hier unseren Buick darauf und versuchen daraus seine Philosophie umzudeuten. Danach werden wir zum Wesen seines Glaubens geführet. “Die Bezogenheit auf ein Unbeziehbares” so erklärte er es in paradoxer Weise. Dieses paradoxe Verhältnis zum Transzendentalen liegt immer schon auf dem Grund der Alltäglichkeit die wir auch mit Kinders zusammen leben. So, was ist im tiefsten Sinn die Gesinnung der fränkische praktischen Philosophie? “Man müsse der Vorsehung eine Chance geben” so sagte Frankl. Das muß der Kern der Gesinnung aller Berufe sein, die die Bestimmung menschlicher Unterstützung haben. Aber in der Zeit der Spezialisierung und des Empirismus wird sie vergissen, auch auf dem Feld der Erziehung.
2 0 0 0 OA 近現代日本教育史の視点から「規範」と教育の問題を考える
- 著者
- 榑松 かほる
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, no.91, pp.23-28, 2005-05-10 (Released:2010-01-22)
- 参考文献数
- 12
2 0 0 0 OA ルドルフ・ラサーン著平野智美・佐藤直之・上野正道訳『ドイツ教育思想の源流-教育哲学入門』
- 著者
- 坂越 正樹
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, no.87, pp.102-103, 2003-05-10 (Released:2009-09-04)
本書は、Rudolf Lassahn; Einfuhrung in die Pädagogik, 8.erg.Auflage, Uni-Taschenbücher;178, Quelle & Meyer, 1995.を訳出したものである。ドイツでは、一九七四年の初版以来、すでに八版を重ねており、教育学の全体領域を見通し、研究動向を的確に把握することのできる優れた教育学入門書として評価を得ている。部分的には一九世紀にさかのぼって論究しつつ、ほぼ二〇紀初頭から一九七〇年代までのドイツを中心とした教育学の状況が、次のような章構成によって見渡されている
- 著者
- 真壁 宏幹
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, no.85, pp.106-113, 2002-05-10 (Released:2009-09-04)
2 0 0 0 OA 小笠原道雄編著『精神科学的教育学の研究-現代教育学への遺産-』
- 著者
- 舟山 俊明
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1999, no.80, pp.105-106, 1999-11-10 (Released:2010-01-22)
2 0 0 0 OA エーリカ・マン著/田代尚弘訳『ナチズム下の子どもたち-家庭と学校の崩壊-』
- 著者
- クラウス ルーメル
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.77, pp.133-134, 1998-05-10 (Released:2009-09-04)
2 0 0 0 OA 戦前・戦後の「教育」概念への問い
- 著者
- 俵木 浩太郎
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1997, no.75, pp.23-27, 1997-05-10 (Released:2009-09-04)
2 0 0 0 OA 西平 直著『エリクソンの人間学』
- 著者
- 鬢櫛 久美子
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1994, no.69, pp.116-121, 1994-05-10 (Released:2009-09-04)
2 0 0 0 OA 「学ばない権利」の確立に向けて
- 著者
- 井上 坦
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1989, no.59, pp.5-10, 1989-05-10 (Released:2009-09-04)
2 0 0 0 OA 小笠原道雄著『現代ドイツ教育学説史研究序説』 ヴィルヘルム・フリットナー教育学の研究
- 著者
- 神力 甚一郎
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1974, no.30, pp.63-69, 1974 (Released:2009-09-04)
2 0 0 0 OA ドイツ的意味における政治と教育
- 著者
- 長井 和雄
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1977, no.35, pp.1-8, 1977-05-20 (Released:2009-09-04)
2 0 0 0 OA 現代ドイツ教育学における根本思想の変化 教育関係の解釈をめぐって
- 著者
- クレメンス メンツェ
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1980, no.42, pp.73-93, 1980-11-25 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 11
伝統的なドイツの陶冶思想 (Bildungsdenken) と現代の教育学の大勢との間には、種々の著しい食い違い (beträchtliche Verschiedenheiten) があって、それは教育思想のあらゆる領域に及んでいる。第二次大戦後、教育学は、さまざまな伝統的教育観・陶冶観と批判的な対決を行なうことによってみずからの資格をあかししようと努め、耐久性があり、しかもそれまでに蒙った数々の経験を考慮に入れた新しい出発点を探し求めたのであるが、現在では教育上のことがらを、従来とは異なったいろいろな前提から考え始めている。伝統的な種々の立場に対する批判は、今やただ事のついでにのみなされており、それも、異議を唱えるという形の批判であれ、否定するという形の批判であれ、もはや建設的な意味を何ひとつ持っていない。このような発展状況は、見受けるところ、伝統的な教育思想を等閑視しているように思われる (Die Entwicklung, so scheint es, ist über dieses Denken hinweggegangen.)。だから、この伝統的な考え方は、現代と全く関連のない、ただ歴史的なものを過度に重視する考察のなかでのみ (nur noch in rein historisierenden Betrachtungen) 思い浮かべることの可能な、いわば歴史のファイルに整理され収められたもののひとつ、と見なされている。しかしながら、明らさまにであれ、またそれを明言しないままであれ-後者の場合には、なおさらそうであるが-、そのように伝統的なドイツ教育学と絶縁してしまう場合、そこでは、すでに片づいた無用のものとして簡単に脇へ押しやることのできないさまざまの問題が、生き埋めにされている (Gleichwohl liegen in der direkten und mehr noch in der indirekten Absage an die überlieferte deutsche Pädagogik Probleme verschüttet, die nicht einfach als abgetan beiseitegeschoben werden können.) 。ひとりひとりの人間の個性、規範性、人間の意味と使命への問と結びついた陶冶、古典的立場からみた人間学と人間像、これらについての従来の説明は、合理性が新しく捉え直され、科学の概念が以前とは大きく異なって規定され (ein vielfach anders bestimmter Wissenschaftsbegriff)、根本的な哲学的立場が変わってしまい、教育思想にとっての政治的・社会的状況がかつてより強く強調される (eine nachdrücklichere Betonung politischer und gesellschaftlicher Umstande für pädagogisches Denken) ようになって、もはや最近の学問観に適合しない、と言われるからといって、すでに時代遅れになってしまったわけではない。なるほど伝統的な答は、以前と違った風に立てられた問にふさわしく答えてはくれない。しかし、昨今世上を賑わしている答もまた、かつての問に適切に答えはしない。察するところ、教育上のことがら全般の概念規定に、ある根本的変化が起ったのであり、そのために「古い立場」と「新しい立場」とを一致させることがもはや不可能に思われるのだ。だからこそ、一方が他の立場に対して持つ種々の不足についても、もはや有意義に語ることができないし、まして、両者の基本的立場を相互に対決させ、その決済ができるなどとは、思いもよらないのだ。このような現在も進行中の変化は、教育関係をどう評価するか、を軸にして探ってみると、範例的に明らかにすることができる (Exemplarisch lassen sich die eingetretenen Voränderungen an der Einschätzung des pädagogischen Bezugs verdeutlichen.)。以下、これを実際に展開する場合にふむべき順序としては、まず、ある特定の教育学が持つ個々の特殊性には留意せずに、教育関係の伝統的な基本構造を描出する。次いで、教育関係にはもはや如何なる地位をもあてがわない、現下のいろいろな教育学の思想傾向について論究する。そして最後に重要なのは、このような教育思想の状況から生じざるをえない諸々の帰結に、注意を喚起することである (schließlich gilt es, auf Konsequenzen zu Verweisen, die sich aus einer solchen Situation des Pädagogischen Denken sauhdrängen.)。
2 0 0 0 OA 天野正治著『現代ドイツの教育』学事出版 一九七八年
- 著者
- ルーメル K
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1978, no.38, pp.55-59, 1978-01-31 (Released:2010-05-07)