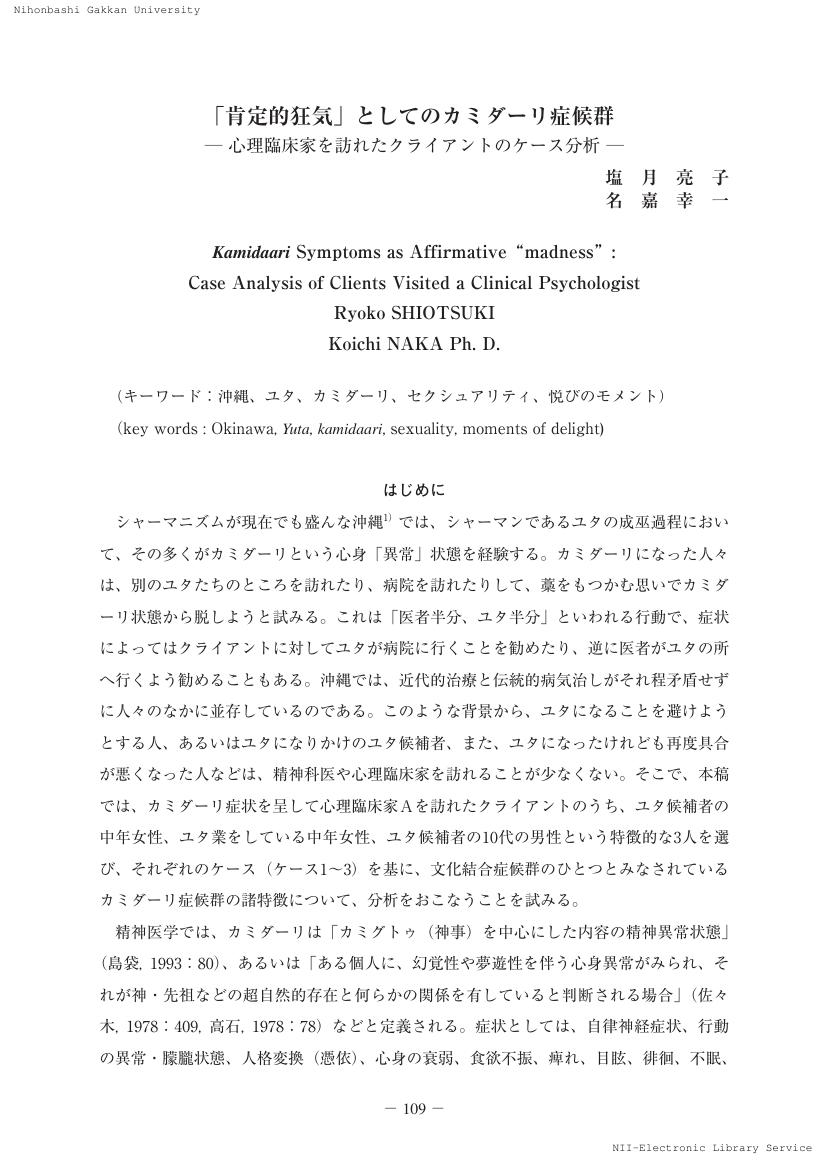11 0 0 0 OA 「肯定的狂気」としてのカミダーリ症候群 : 心理臨床家を訪れたクライアントのケース分析
- 著者
- 塩月 亮子 名嘉 幸一
- 出版者
- 学校法人 開智学園 開智国際大学
- 雑誌
- 日本橋学館大学紀要 (ISSN:13480154)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.109-123, 2002-03-30 (Released:2018-02-07)
- 著者
- 塩月 亮子
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.4, pp.1035-1036, 2006-03-30 (Released:2017-07-14)
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA 沖縄における死の現在 : 火葬の普及・葬儀社の利用・僧侶への依頼
- 著者
- 塩月 亮子
- 出版者
- 学校法人 開智学園 開智国際大学
- 雑誌
- 日本橋学館大学紀要 (ISSN:13480154)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.49-65, 2008-03-01 (Released:2018-02-07)
本稿では、沖縄における死の変容を、火葬の普及、葬儀社の出現、葬儀時の僧侶への依頼という3つのファクターから考察することを試みた。その結果、沖縄では近代化が進むなか、特に1972年の本土復帰以降、火葬場が多数設置されて火葬が広まり、土葬や洗骨の風習が廃れていったこと、および、今ではその多くが入棺が済むとすぐ火葬場へ行き、そこに隣接する葬祭場で告別式をおこなうという順番に変わったことを明らかにした。また、葬儀社の出現が、葬儀の均一化・商品化、仏教との提携をもたらしたことを指摘した。さらに、このような変化は、伝統的に死の世界を扱い、憑依などを通して人々に生々しい死を提示してきた民間巫者であるユタと、それらの慣習を否定し、新たに死の領域に介入し始めた僧侶との深刻なコンフリクトを生じさせていることも示した。沖縄におけるこのような葬儀の本土化・近代化は、すべて生者の側からの利便性・効率性の追求、換言すれば、死者や死の世界の軽視にほかならない。そのため、沖縄でも、これまでみられた生者と死者の密接な関係が失われ、今後は日本本土と同様、死の隠蔽・拒否が強まるのではないかということを論じた。
- 著者
- 塩月 亮子 名嘉 幸一
- 出版者
- 学校法人 開智学園 開智国際大学
- 雑誌
- 日本橋学館大学紀要 (ISSN:13480154)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.109-123, 2002
2 0 0 0 IR 【研究ノート】造り酒屋の地域貢献活動―群馬県長野原町浅間酒造の事例から―
- 著者
- 塩月 亮子
- 出版者
- 跡見学園女子大学
- 雑誌
- 跡見学園女子大学観光コミュニティ学部紀要 = Atomi Tourism and Community Studies (ISSN:21899673)
- 巻号頁・発行日
- no.3, pp.99-111, 2018-03
本稿では、地域を活性化するうえで地元企業はどのような地域貢献をおこなうことが望ましいかを考察するため、地元の名家が手掛けることの多い造り酒屋に焦点をあて、その歴史と現在の活動を追った。事例には、八ッ場ダム建設の影響で地域の分断や人口減少等が起き、町の再生が急務とされる群馬県長野原町にある浅間酒造株式会社を取りあげ、歴代の社長が長野原町長になるなど政治家として地元のために活躍してきたこと、多角経営をおこない地元に必要な産業を興し、地元の雇用を促進してきたこと、さらに、現在も土産物販売をおこなう浅間酒造観光センターで地元農家の製品を販売することや「酒造納涼祭(夏祭り)」を当センターで地元向けに開催すること、自社田として休耕地を借り、そこを酒田にして保全することなどを通して、地元に貢献している様子を明らかにした。このような浅間酒造の地域貢献を地域貢献活勤の6分野に照らし合わせてみると、浅間酒造は主に①経済の振興に関する活勤②文化・環境に関する活勤③敦育に関する活勤、④雇用に関する活勤の4分野に腐心してきたことがわかった。また、⑤治安・安全・防災に関する活勤や⑥保健・医療・福祉に関する活動も、長野原町長など政治家として、あるいは孤児を養育した櫻井傳三郎や、戦時中に米を地元の人々に分け与えた櫻井かねのように個人として、櫻井家が担ってきたものであったこともわかった。最後に、浅間酒造観光センターは観光客の集まる拠点でもあるので、観光客を活用し、当該地域の伝統文化の保全や再生、創造に寄与するよう、地元の人々が工夫していくことも大切だと指摘した。そして、浅間酒造が今後地元から最も望まれる地域貢献は、地域で貴重な老舗製造業であるという強みを生かし、地域の人々と協力しながら地元にふさわしい、地元の人が誇りとするような地域ブランドを創造・確立していくことであろうと結論づけた。\n
- 著者
- 塩月 亮子
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.4, pp.1035-1036, 2006-03-30
- 著者
- 塩月 亮子
- 出版者
- 日本橋学館大学
- 雑誌
- 日本橋学研究 (ISSN:18829147)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.51-62, 2008-03-31
本稿では、東京・日本橋のなかでも花街として有名な芳町(よし町)の歴史を概観し、そこに住む三味線店主や理髪店主の話等をもとに、芳町と職人の関係、および町の推移について考察した。その結果、江戸時代に吉原遊郭があり、それが移転した後も芝居小屋が近くにあった芳町は、芸妓が多数居住する場所となり、明治、大正時代には花街として活況を極め、それが昭和30年(1955)初めまでは続いたことがわかった。芳町の職人たちも花柳界において大切な役割を担い、共存共栄関係を保っていた。ことに理髪店は銭湯と対の関係として、芸者たちの日常生活を支えてきたことも明らかとなった。しかし、明治期に始まる近代化により隅田川は汚染され始め、戦後は高度経済成長期に高速道路や高層ビルの建設、防潮堤設置等が進み、景観が損なわれた。それが原因のひとつとなり、芳町花街は衰退した。芳町は従来、都市の変化を映す盛り場のひとつとして、多様性や演劇性といった特徴を兼ね備え、さらに河川という空間性も加わり、自然の景観を重視した由緒ある街として機能してきた。芳町の今後を考える上では、そのことを再認識し、河川をはじめとする景観の再生にむけて力を注いでいくべきであろう。
2 0 0 0 OA 「戦後沖縄文学」の社会学:文化表象論と文学制度論からの接近
本研究では、戦後沖縄における「文学表象」と「文化的実践の場」の構造に関する社会学的分析を行うことを課題としてきた。沖縄において「文学」は、政治的状況の強い規定力と、文化的・言語的な固有性に影響されながら、「弱い自律性」を特徴とする文化的実践の場を形成している。地域に固有の制度的布置の中で、文学は、この地域の歴史現実を表象する重要な媒体でありつづけている。本研究では、戦後沖縄を代表する何人かの作家たちについて、社会的状況と文学的実践を結ぶ、その多面的な媒介の論理を明らかにすることができた。
1 0 0 0 OA インターネットにみる今日のシャーマニズム : 霊性のネットワーキング
- 著者
- 塩月 亮子 佐藤 壮広
- 出版者
- 学校法人 開智学園 開智国際大学
- 雑誌
- 日本橋学館大学紀要 (ISSN:13480154)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.79-88, 2003-03-30 (Released:2018-02-07)
1 0 0 0 OA 沖縄の洞窟信仰と観光 : 民俗知活用の可能性を探る
- 著者
- 塩月 亮子
- 出版者
- 明治学院大学社会学会
- 雑誌
- 明治学院大学社会学・社会福祉学研究 = The Meiji Gakuin sociology and social welfare review (ISSN:13494821)
- 巻号頁・発行日
- vol.133, pp.1-30, 2010-03
1 0 0 0 OA 沖縄における生理用品の変遷 : モノ・身体・意識の関係性を探る研究にむけて
- 著者
- 塩月 亮子
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:24240508)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.464-469, 1995 (Released:2018-03-27)
- 著者
- 塩月 亮子
- 出版者
- 跡見学園女子大学
- 雑誌
- Atomi観光マネジメント学科紀要 (ISSN:21860696)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.69-73, 2014-03
- 著者
- 塩月 亮子
- 出版者
- 日本橋学館大学
- 雑誌
- 紀要 (ISSN:13480154)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.109-118, 2004-03-30
1 0 0 0 OA 沖縄における死の現在 : 火葬の普及・葬儀社の利用・僧侶への依頼
- 著者
- 塩月 亮子
- 出版者
- 日本橋学館大学
- 雑誌
- 紀要 (ISSN:13480154)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.49-66, 2008-03-01
本稿では、沖縄における死の変容を、火葬の普及、葬儀社の出現、葬儀時の僧侶への依頼という3つのファクターから考察することを試みた。その結果、沖縄では近代化が進むなか、特に1972年の本土復帰以降、火葬場が多数設置されて火葬が広まり、土葬や洗骨の風習が廃れていったこと、および、今ではその多くが入棺が済むとすぐ火葬場へ行き、そこに隣接する葬祭場で告別式をおこなうという順番に変わったことを明らかにした。また、葬儀社の出現が、葬儀の均一化・商品化、仏教との提携をもたらしたことを指摘した。さらに、このような変化は、伝統的に死の世界を扱い、憑依などを通して人々に生々しい死を提示してきた民間巫者であるユタと、それらの慣習を否定し、新たに死の領域に介入し始めた僧侶との深刻なコンフリクトを生じさせていることも示した。沖縄におけるこのような葬儀の本土化・近代化は、すべて生者の側からの利便性・効率性の追求、換言すれば、死者や死の世界の軽視にほかならない。そのため、沖縄でも、これまでみられた生者と死者の密接な関係が失われ、今後は日本本土と同様、死の隠蔽・拒否が強まるのではないかということを論じた。