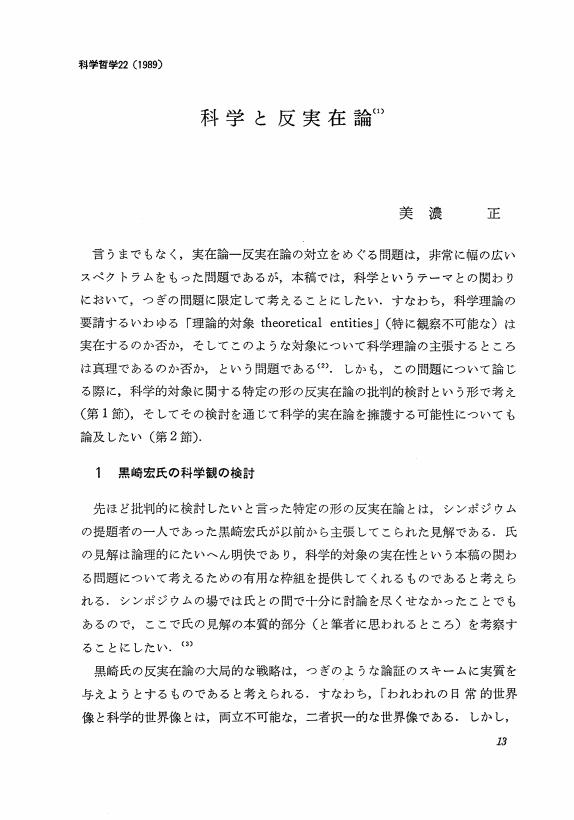1 0 0 0 OA 科学的実在論の擁護
- 著者
- 美濃 正
- 出版者
- 科学基礎論学会
- 雑誌
- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.4, pp.161-166, 1990-03-25 (Released:2010-01-20)
- 参考文献数
- 12
私は, 確信のない実在論者であり, 科学的実在論者であるので, 本稿(1)では, 科学的実在論を擁護するためには, どのような方針に基づいて, どのような問題に答えねばならないか, という点についての自分なりの見通しを述べることにしたい。言うまでもないことであろうが, 一般に, 実在論-反実在論の対立について論じる場合には, つぎの二つの問題を区別することが肝要である。(1) 存在ないし真理の本性は何か, という問題と,(2) 何が存在し, 何が真理であるのか, また, われわれはある対象の存在主張ないしある言明の真理の主張に対しどのような認識論的根拠をもつか, という問題である。私の見るところでは, 科学的実在論は, 主として第二の問題のコンテキストで論じられるべき事柄である。しかしながら最近, 第一の問題のコンテキストにおいて, 有力な反実在論の論陣が張られているので, はじめにこの立場に対して簡単にコメントし, 第一の問題, つまり存在ないし真理の本性をめぐる問題にどのような答えが与えられるかに関わらず, 第二の問題が重要な哲学的問題として残ることを確認しておきたい。最近の有力な反実在論の立場と呼んだのは, 言うまでもなく, ダメット-パットナムによって展開されている立場の事である。
1 0 0 0 OA 思考のありか:信原説への疑問
- 著者
- 美濃 正
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.43-56, 2000-11-25 (Released:2009-05-29)
- 参考文献数
- 9
In this paper I shall critically examine a rather bizarre view which Prof. Nobuhara has recently propounded concerning connectionism. The thrust of his view is this: In the Classicist-Connectionist debate, Classicists are definitely the winner, since Connectionists cannot solve the 'Systematicity of cognitive abilities' problem posed by Fodor and others.; nevertheless, our brain is a wholly connectionist cognitive system, since every cognitive activity that shows the 'Systematicity' in question (typically, thinking activity) needs symbols external to our brain and therefore is performed totally outside it. Against this view, I first point out that Prof. Nobuhara fails to give some Connectionists ('Approximationists') their due in his appraisal of the Classicist-Connectonist debate. Secondly, I argue that he can't be a Connectionist with regard to our brain, while endorsing the Classicist's solution to the 'Systematicity' problem.
1 0 0 0 OA クオリアなんて怖くない クオリア・マニフェスト(哲学ヴァージョン)1
- 著者
- 美濃 正
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.39-51, 1999-11-10 (Released:2009-05-29)
- 参考文献数
- 12
The main aim of this paper is to argue for the following two theses: (1) so-called qualia are irreducibly non-physical properties of certain brain states, and (2) in spite of (1), qualia can be legitimately accommodated into a broadly physicalistic framework. On behalf of (1), what might be regarded as a variation of F. Jackson's 'knowledge-argument' is put forward and also a refutation of P. M. Churchland's objection that qualia are but physical properties (of certain brain states) as they are introspectively accessed is attempted. On behalf of thesis (2), the idea of qualia's supervening and nomologically depending upon brain states' physical properties is deployed. A radical criticism of some sceptical arguments concerning qualia is also included.
1 0 0 0 OA 科学と反実在論
- 著者
- 美濃 正
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.13-25, 1989-11-10 (Released:2009-05-29)
- 被引用文献数
- 4
1 0 0 0 西洋哲学における懐疑論の形態と理論
昨年度に続いて本年度も各研究分担領域で「壊疑」のもつそれぞれの意味と役割を究明し, 西洋哲学における壊疑論の歴史的変遷を跡づけることに努めた. 古代ギリシアでは後期に懐疑派が現れるが, この派の哲学の全体的特徴はセクストス・エンペイリコス著『ピュロン哲学の概要』に述べられている. それによれば懐疑哲学では判断保留とそれに伴う平静な悟脱の心境が問題とされ, 特にその判断保留の十箇の方式をめぐってはその著の第14章で詳述されている. 教父哲学ではアウグスティヌスによる新アカデミア派の懐疑論克服が問題とされるが, 彼の『自由意志論』第2巻では「神の存在論証」と相俟って真理の超越的独存性が立証され, 真の認識の成立根拠が確証される. 彼の影響下にある中世哲学では基本的には懐疑の問題は主要な関心事とはならなかった. このような哲学としてはトマスの哲学が取り上げられ, 彼のessentia概念の二義性が抽象説との関係において論じられる. 近世ではデカルトが一切のものに対して徹底して懐疑を行なった末にcogito ergo sumという不可疑的な真理の発見に到るが, これに対するストローソンの批判が考察される. 彼のデカルト批判によれば, cogito ergo sumを成立させる「私」という個体の存在は「私」以外の他の個体の存在を既に前提とする. つまり, 個体指示表現が有意味であるためには, 個体とそれ以外の個体との識別可能性の原理の働くことを認めねばならないと言えよう. 現代の英米哲学においても懐疑論に関係する多くの問題がみられる. その一つに, 経験的認識の証拠による不十分決定underdeterminationの問題が挙げられる. 今日の反実在論の多くはこの「証拠による不十分決定」に依拠している点である意味での懐疑論の変種とみなすことも不適切とは言えない. 又, 懐疑論・弁証法・解釈学・ニヒリズム相互の関係も本研究において深く問題としてきた哲学的・倫理的課題である.
1 0 0 0 OA 現代的な知覚研究のための哲学的基礎づけとその体系化
1 0 0 0 コネクショニズムの哲学的意義の研究
われわれはコネクショニズムと古典的計算主義の対比を行ないつつ、コネクショニズムの哲学的意味の解明を行なった。美濃は、ホーガン&ティーンソンのアイディアを援用し、古典的計算主義を超えつつも、いくつかの点で古典的計算主義と前提を共有する立場の可能性を模索した。服部と金子はコネクショニズムにおける表象概念(すなわち分散表象)がはたして「表象」と呼ぶに値するかということを研究し、その有効性の度合を明らかにした。金子はどちらかといえば、分散表象を肯定的に評価し、服部は否定的に評価しているので、この点についてはさらに具体的な事例に即した研究が必要であることが明らかとなった。柴田と柏端は、「等効力性」議論を検討することを通じて、「素朴心理学」的説明による人間の行為の説明が真ではないとする主張の意義を研究し、柏端は、コネクショニズムが素朴心理学の消滅よりはむしろその補強に役立ついう評価をするに至った。他方、柴田は、条件つきではあるものの、素朴心理学は科学的心理学を取り込んだ形で生き残るか、道具主義的な意味で残るであろう、と結論するに至った。戸田山と横山はコネクショニズムが認知の新しい理論であると言われるときに正確には何が言われているのかということを研究した。特に横山は、コネクショニズムを科学についてのより広いパースペクティヴから見なければならないと結論した。大沢は、古典的計算主義における古典的表象のみならずコネクショニズムにおける分散表象もともにある種の限界をもつと論じ、それに代えて新たに像的表象の概念を提案し、そこでの論理を具体的に提案した。しかし、この点はまだ十分に展開しきれてはいないので、今後も引き続き研究する必要のあることが判明した。