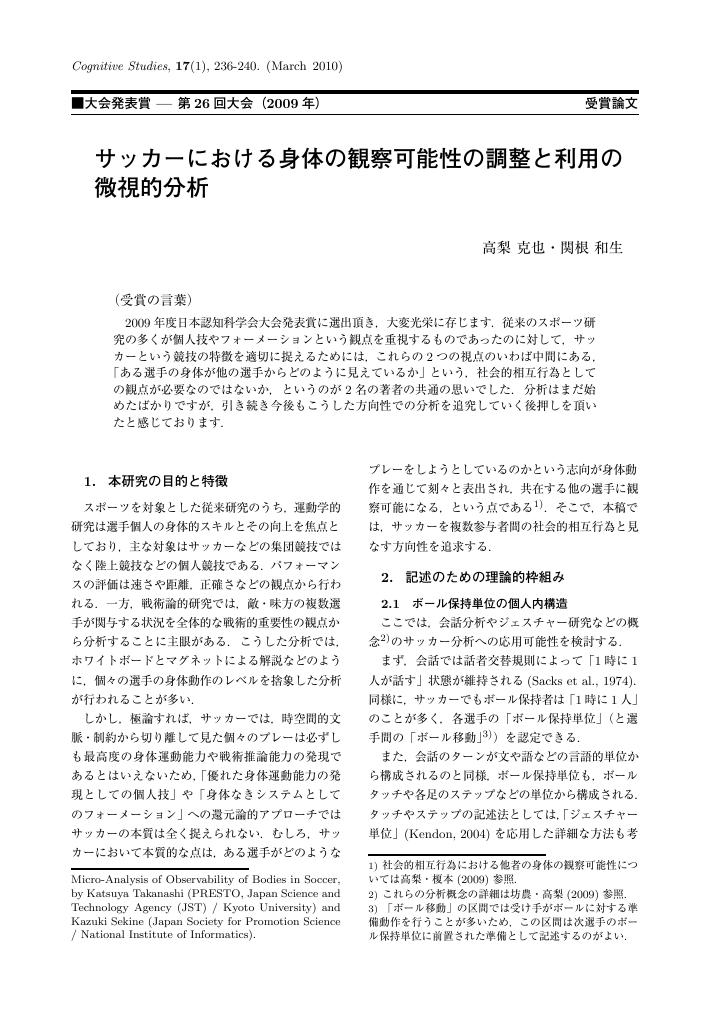10 0 0 0 OA Levenshtein距離を用いた日本語フリースタイルラップにおける韻の同定
- 著者
- 野村 亮太 関根 和生
- 雑誌
- 第84回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2022, no.1, pp.33-34, 2022-02-17
フリースタイルラップバトルは争覇的な協調場面であり、その歌詞には複雑な引用関係が観察される。本研究では、日本語の頭韻および脚韻がそれぞれ子音および母音の共通性により実現されていることに着目し、編集距離から歌詞の韻を同定した。まず、ラップバトルの歌詞テキストの句読点を削除したうえで形態素分析を行い、自立語と付属語の組み合わせとして句を作った。その後、読み仮名をローマ字に変換し、句のペアごとに標準化Levenstein距離を求めた。その結果、トップレベルのラップバトルにおいては、個人内だけではなく個人間で韻を踏むことで引用関係が生じていることが可視化された。韻の統計量は、観客の盛り上がりとの相関分析にも応用できる。
6 0 0 0 OA サッカーにおける守備側選手が攻撃側選手との時間的と空間的ズレを埋めるための手がかり
5 0 0 0 OA サッカーにおける身体の観察可能性の調整と利用の微視的分析
- 著者
- 清水 大地 児玉 謙太郎 関根 和生
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 A (ISSN:09135707)
- 巻号頁・発行日
- vol.J104-A, no.2, pp.75-83, 2021-02-01
上演芸術の一つの魅力として,複数名の演者間に生じる複雑な関わり合いが挙げられる.近年では,この関わり合いの特徴を同期・協調の理論を適用し,定量的に検討する試みが営まれつつある.以上の研究は,主に単独の表現チャンネル(頭のリズム運動,歌声,腕の運動等)を対象とし検討を行ってきた.一方で上演芸術では,表情,ジェスチャー,リズム運動等のように複数の表現チャンネルを通して演者達が関わり合う様子が観察されており,その過程に魅力が含まれるとする理論的提案もなされつつある.本研究では,以上の複数の表現チャンネルを通した関わり合いの探索的・定量的検討を試みた.具体的には,近年演者間の同期・協調の検証対象として着目されている競争的場面としてフリースタイルラップバトルを対象とし,熟達したラッパー2名の関わり合いを手,頭,腰の同期・協調の様相に着目して測定・解析した.結果,複数の表現チャンネルにおいて演者間の同期が生起する様子,手では同位相同期,頭・腰では逆位相同期と演者間の同期の様相がチャンネルにより異なる様子,手と頭・腰を異なる役割を担うチャンネルとして利用していた様子,が観察された.
1 0 0 0 OA フリースタイルラッパーのストレス耐性に関する予備的調査
- 著者
- 関根 和生 牧 恒平 満石 寿
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第86回大会 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.2PM-036-PG, 2022 (Released:2023-07-07)
1 0 0 0 OA 小学校の一斉授業における教師と児童の視線配布行動(<特集>相互作用のマルチモーダル分析)
- 著者
- 伊藤 崇 関根 和生
- 出版者
- 社会言語科学会
- 雑誌
- 社会言語科学 (ISSN:13443909)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.1, pp.141-153, 2011-09-30 (Released:2017-05-02)
- 被引用文献数
- 2
言語表現のみならず,参与者の身体的表現に着目することは,授業の実際の展開を理解する上で重要である.特に視線は,参与者が聞き手としてその場に参与する仕方を明らかにする上で有効な行動指標である.本研究では,小学1,3,5年生による一斉授業を対象に,教師と児童による視線配布行動を検討した.3学年各2学級,1時間ずつの国語の授業の映像・音声資料から抽出した3分間ずつのシークエンスについて,教師と児童の視線の向き先について1秒ごとのタイムサンプリングを実施し,コーディングを行った.その結果,次の3点が明らかになった.(1)教師の視線配布行動は,発言する児童を頻繁に見る,発言していない児童を頻繁に見る,黒板を頻繁に見るという3つのスタイルに分けられた.(2)児童の視線配布行動には,同学年内で一貫して共通する側面と,同学年内でも学級間で一貫しない側面とがあった.(3)教師と児童の視線配布行動の相互行為的な関連については,教師を見ていた児童が教師の見る対象に視線を向け直すという連鎖と,教師を見ることなく自律的に視線を動かすという連鎖の,少なくとも2つの連鎖パターンがあった.これらより,児童が授業に参与する上で教師の視線は有効な手がかりとなる可能性と,学年が上がるにつれて児童が参与構造を自律的に組織化する可能性を論じた.最後に,これらの結果の教育実践への示唆,および結果を解釈する上での限界について議論した.
1 0 0 0 児童期における談話の発達 : 身振りと発話による検討
本研究の目的は,身振りは幼児期から発話生成に影響を及ぼしているのか,また,身振りの使用が言語発達と共にどのように変化するのか,ということを実証的に検討することである。この目的を遂行するため,最終年度では,以下の4点の研究活動を行った1.平成21年度に行った研究1「談話構築における身振りの使用とその変化」と平成22年度に行った研究2「児童期における空間利用の変化」の結果から,児童期における身振りと空間利用の発達段階を提案した。また,自然状況下での談話場面のデータを収集・分析した。その結果,実験的場面から得られたデータを支持するものとなった。2.本研究の理論的貢献となる"身振りと発話の変化に関する説明理論"と,"発達段階ごとの身振りの産出モデル"を構築した。3教育心理学会や,データ収集を行った小学校で研究成果を報告し,現場の教師からフォードベックをいただいた。それをもとに,実践的貢献となる研究結果の教育場面への応用を提案した。身振りの空間利用の仕方が談話発達の予測することから,身振りが指標となるという提案である。4.最後に,本研究の問題点や限界点を総括し,今後の課題や研究の方向性を検討した。以上の研究活動から,児童期後半から,談話知識とともに人物参照のための身振りが出現することが明らかになった。この現象は,教室場面や自然会話場面など,幅広い文脈でみられるものであった。これらの知見は,談話構築がマルチモーダルに達成されていることを明らかにするデータであり,これまで言語を中心に分析してきた談話研究に対して,新たな理論的・実践的観点を提供するものである。