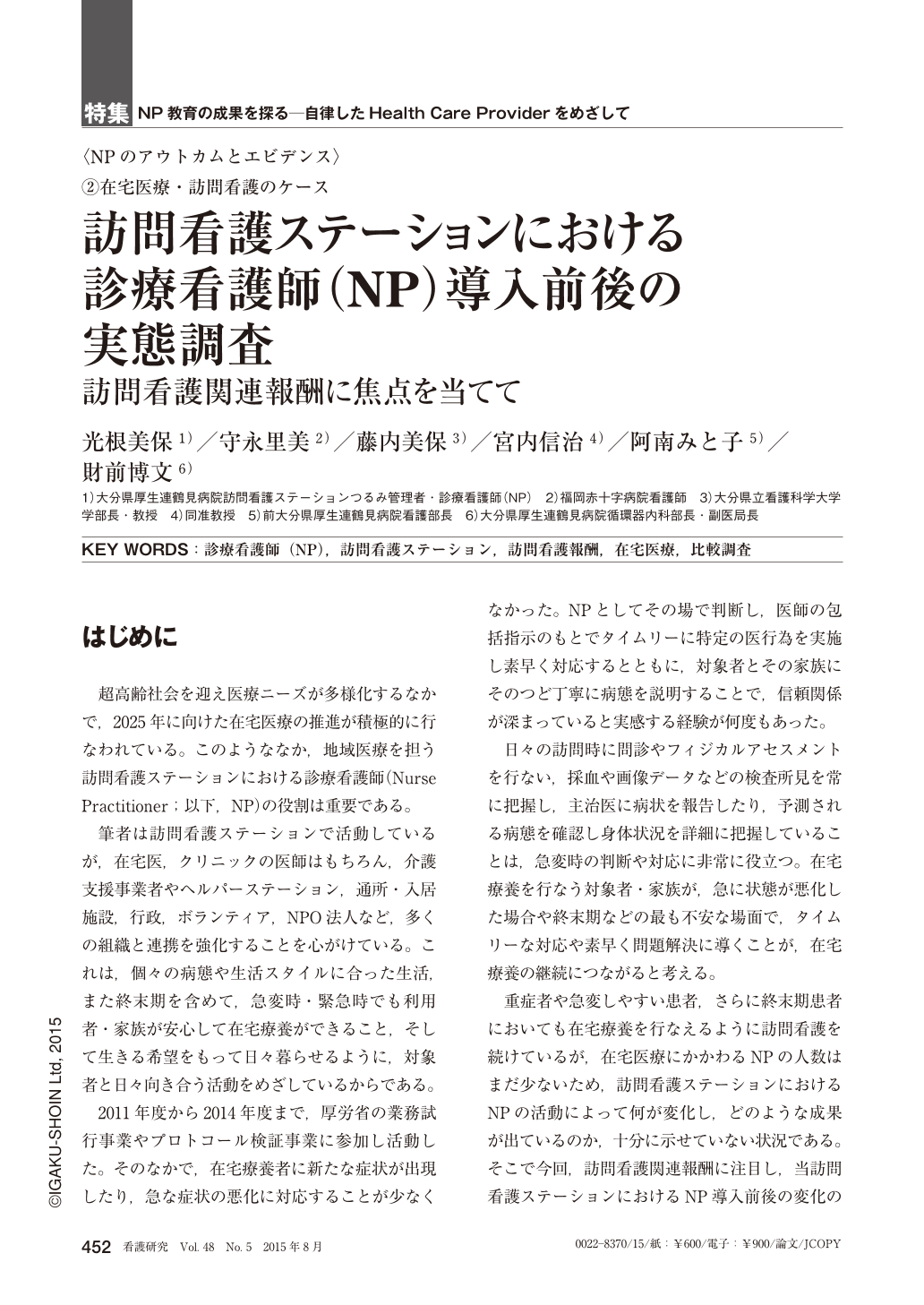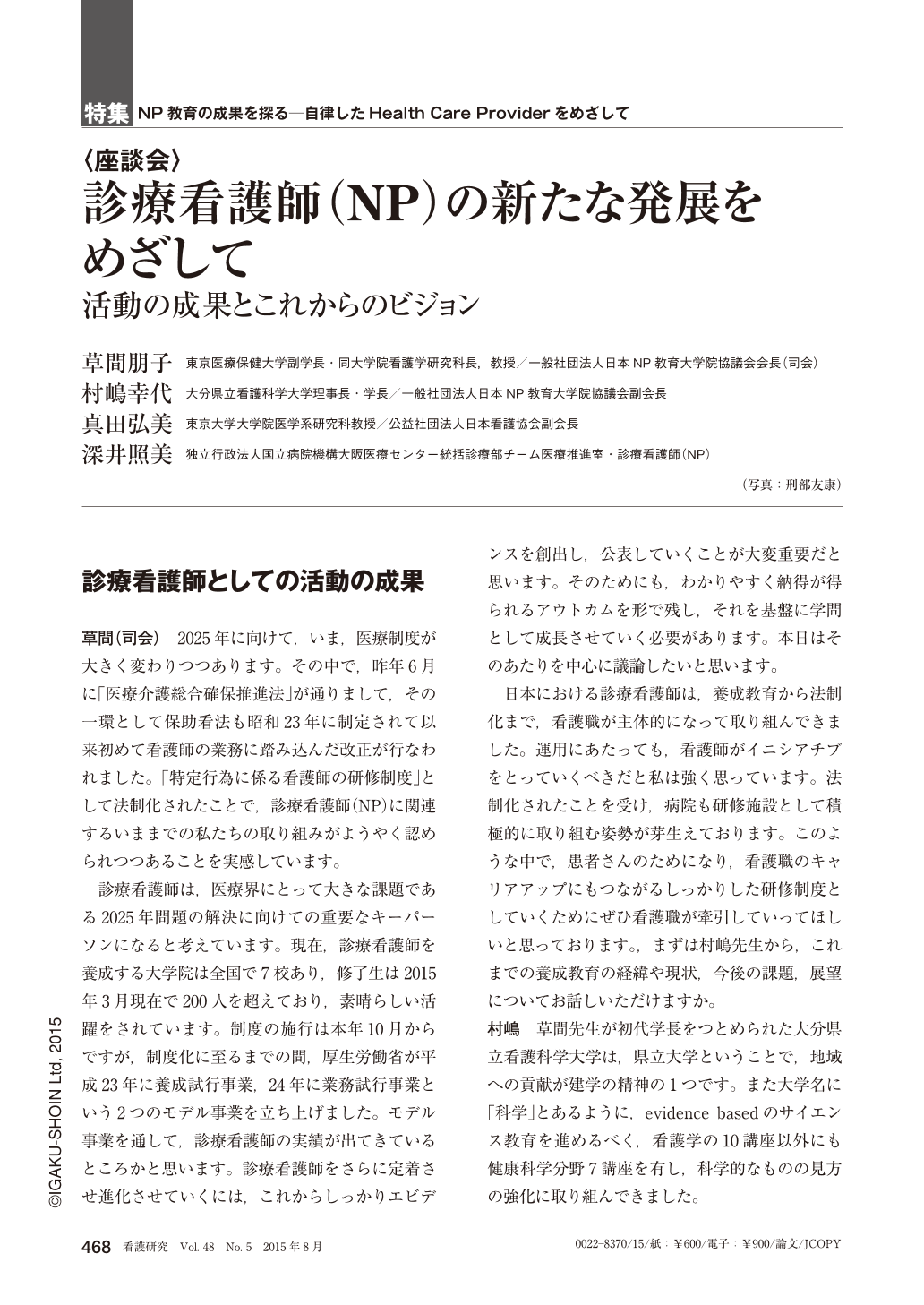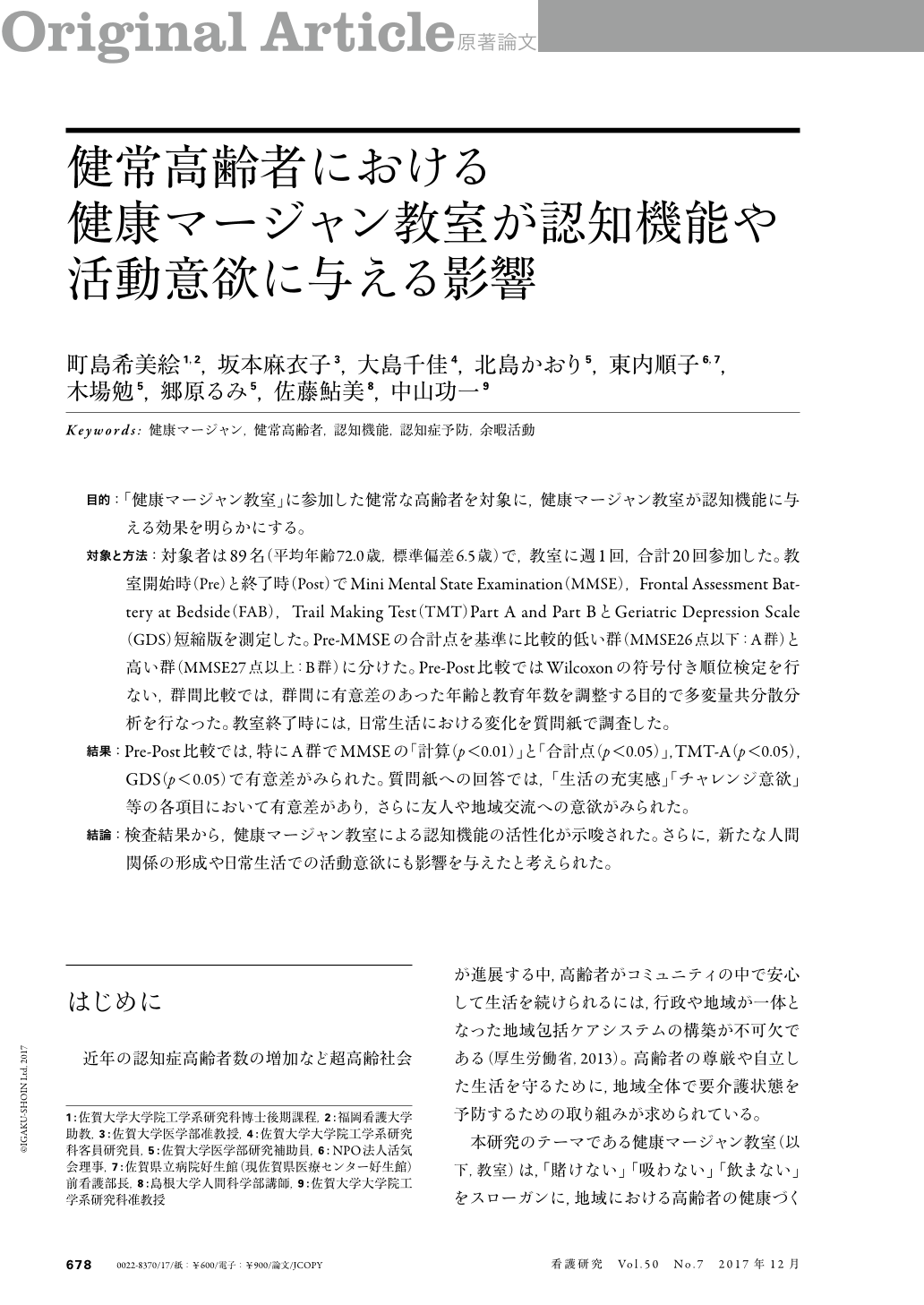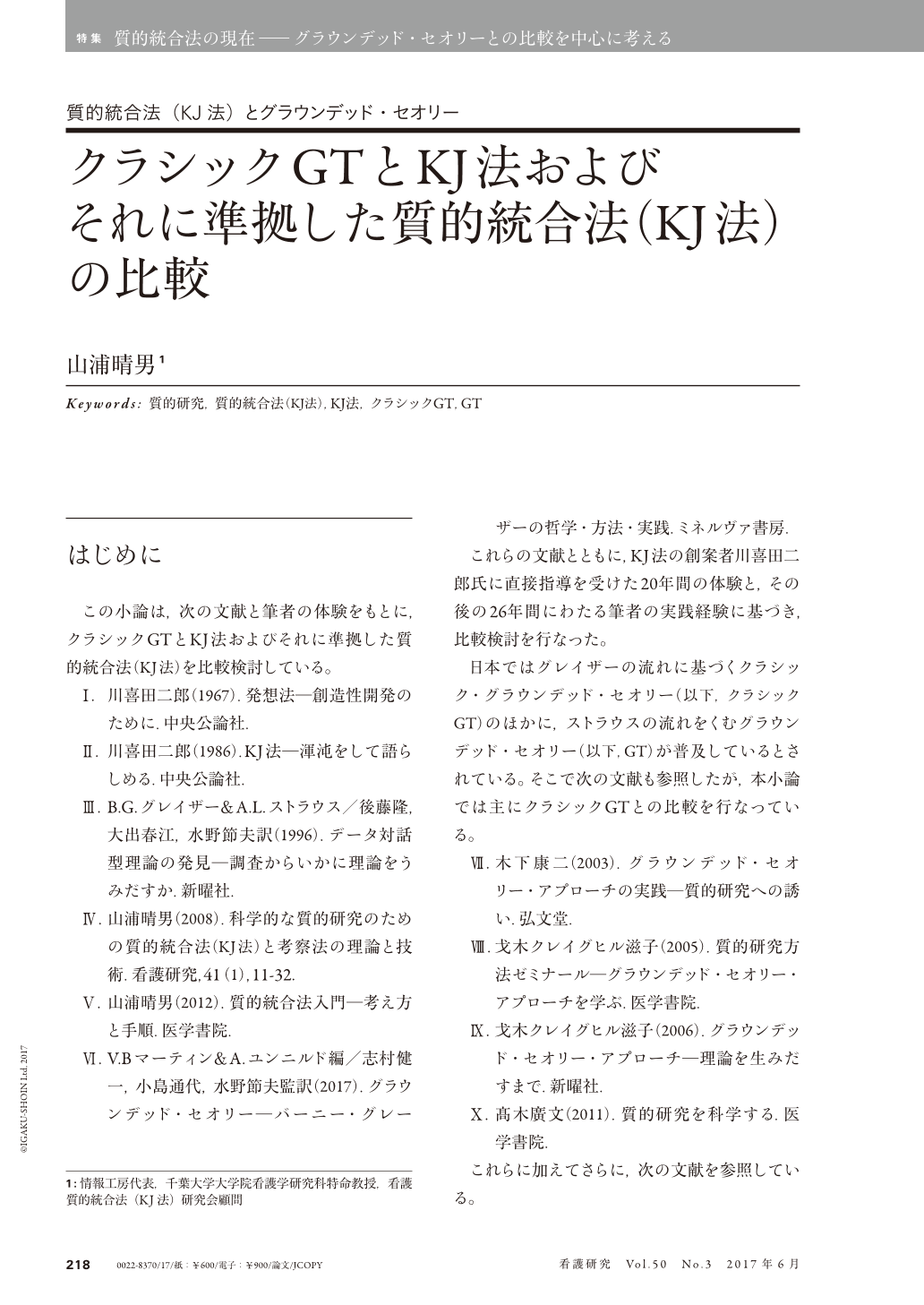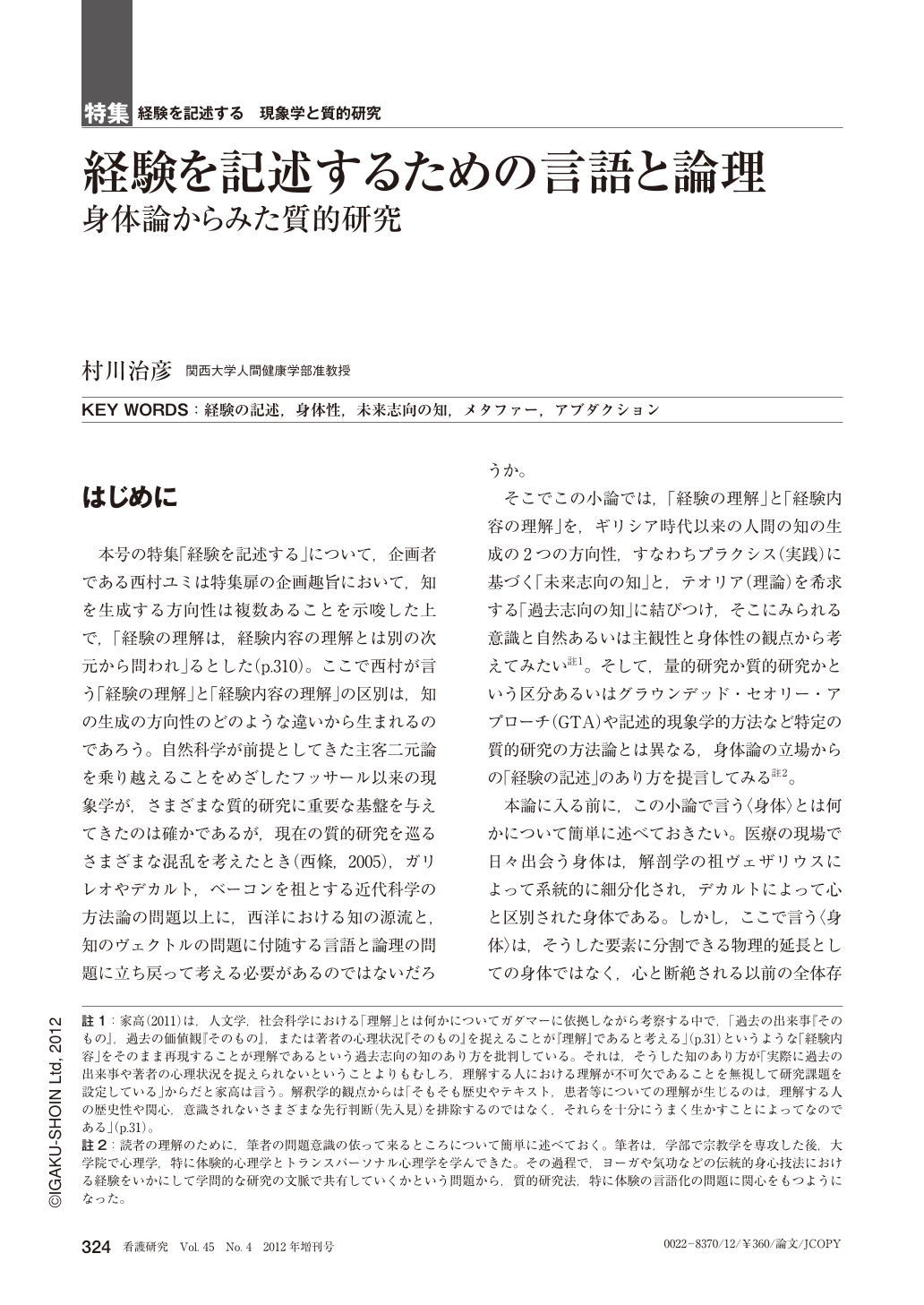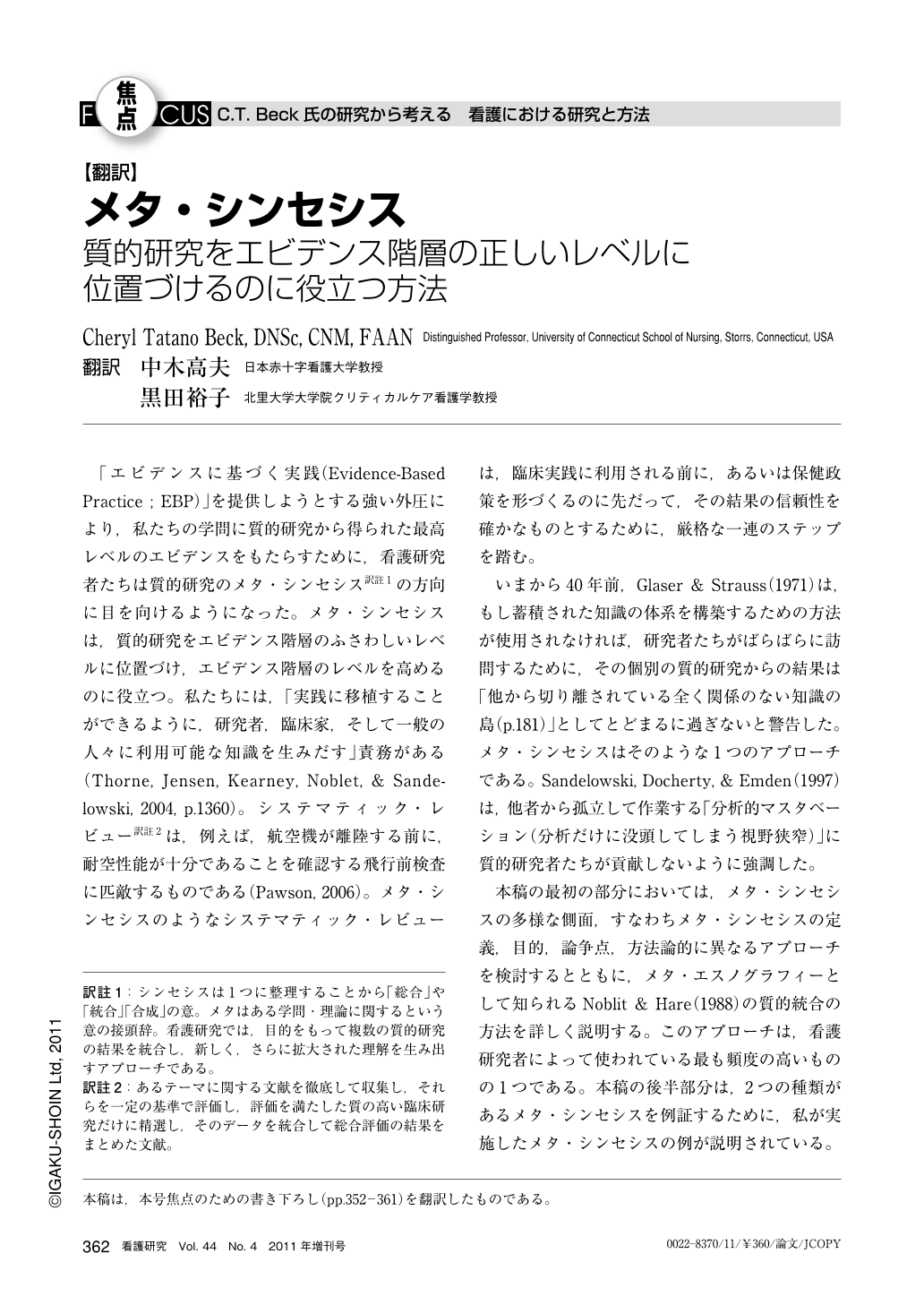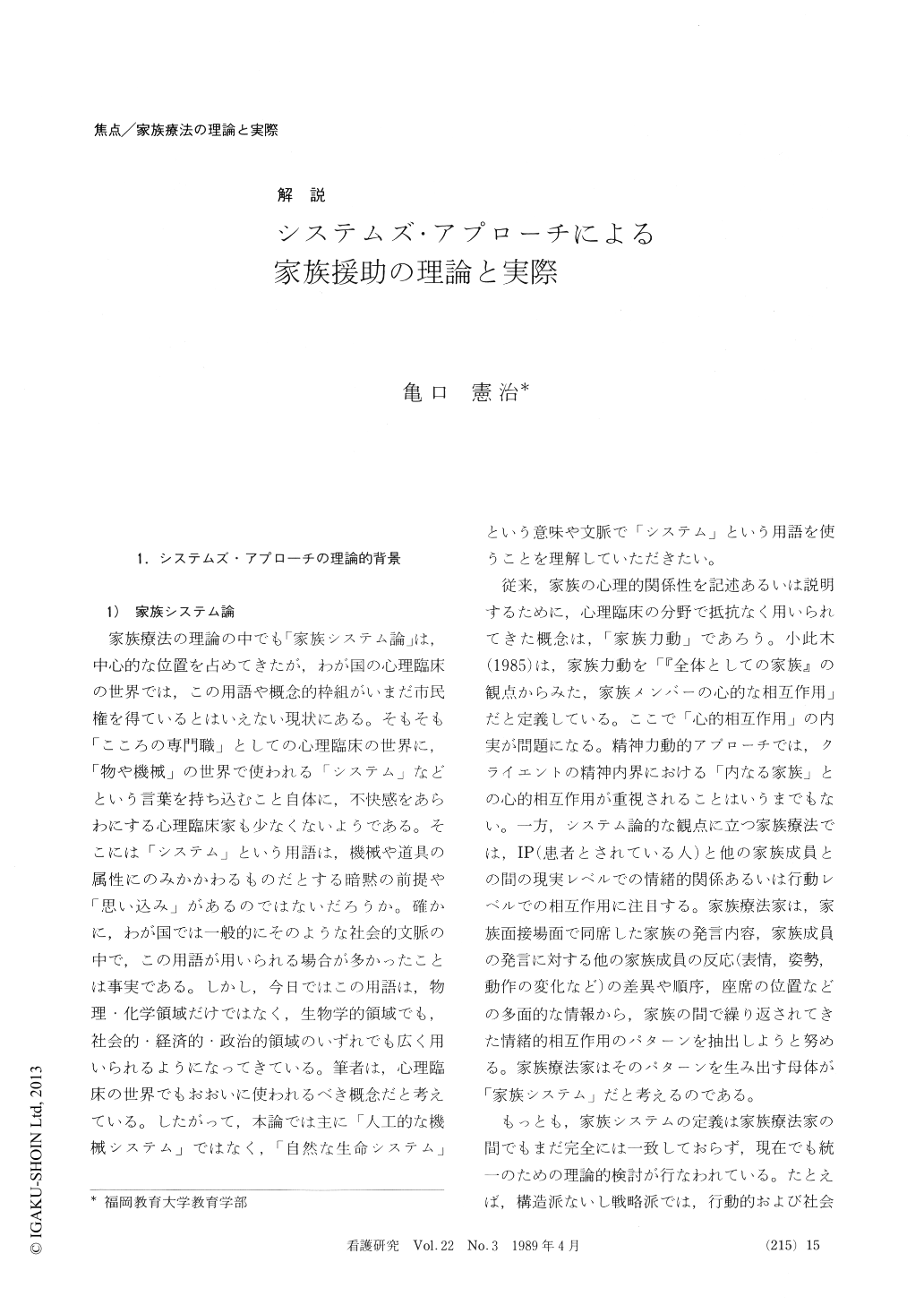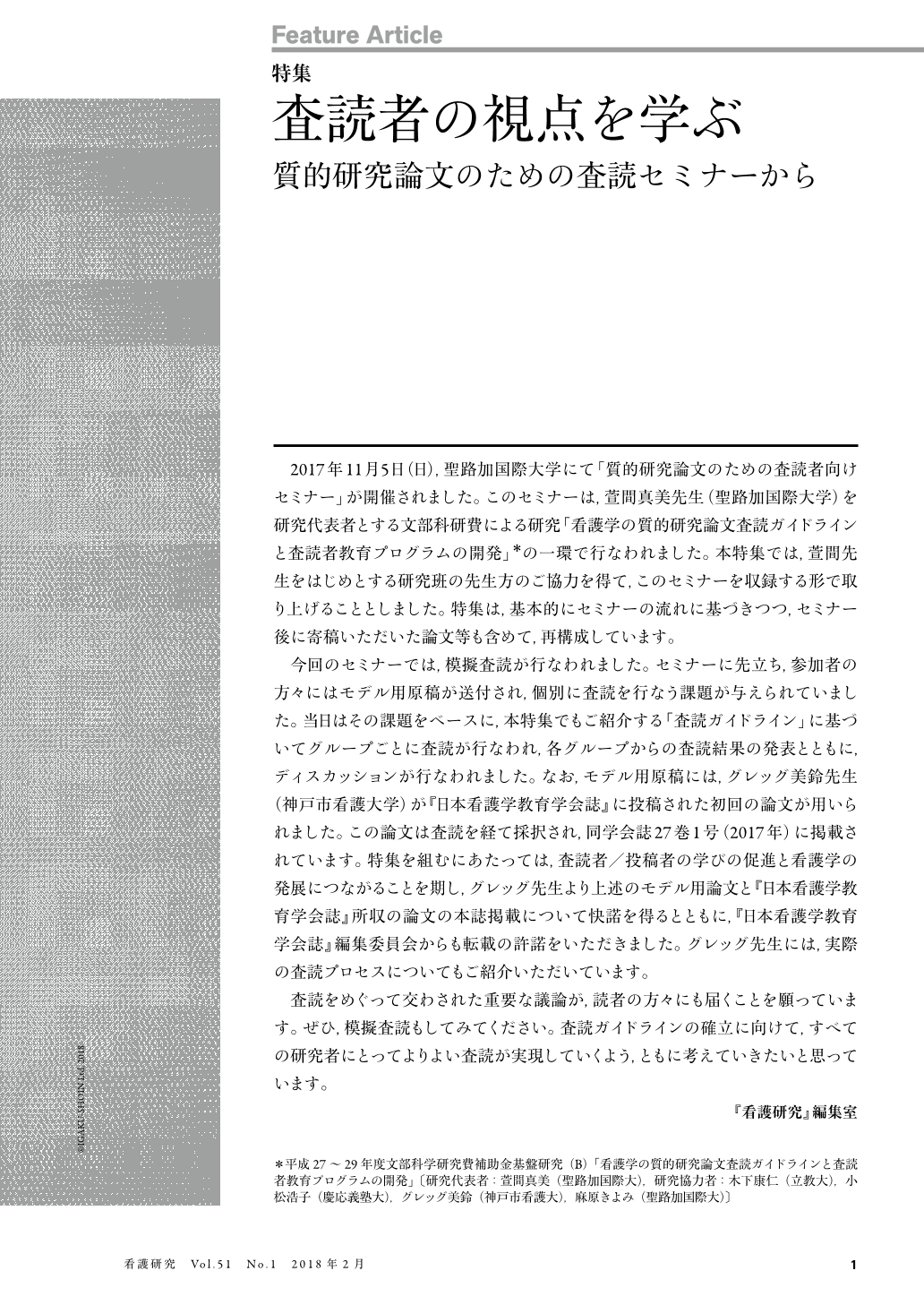15 0 0 0 多変量解析の魅力に引き込まれる随一のテキスト
- 著者
- 小松 浩子
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 看護研究 (ISSN:00228370)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.175, 2018-04-15
本書の発刊を知り,すぐに頭に浮かんだ言葉は,「待っていました!」です。すでに,研究室の本棚には多変量解析に関するテキストブックが複数並んでいますが,どれもきれいなままで,複雑な数式やピンと来ない例題にギブアップした形跡があります。本書は看護研究を学ぶものにとって,かゆいところに手の届く格好のテキストブックといえます。私のお気に入りの点を挙げながら,特徴を紹介します。 第1は,看護研究のもどかしさを紐解く統計手法を,わかりやすく解説している点です。統計学のイロハといえるデータ,変数,仮説,分布といった統計学の基本的知識を,看護研究の観点からわかりやすく積み上げ式で学べます。長年,看護学生や看護研究者に統計学を教えている著者だからこその解説,例示が満載です。難しい統計学が「わかった!」となっていくので,どんどん読み進めることができます。
- 著者
- 光根 美保 守永 里美 藤内 美保 宮内 信治 阿南 みと子 財前 博文
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 看護研究 (ISSN:00228370)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.5, pp.452-455, 2015-08-15
はじめに 超高齢社会を迎え医療ニーズが多様化するなかで,2025年に向けた在宅医療の推進が積極的に行なわれている。このようななか,地域医療を担う訪問看護ステーションにおける診療看護師(Nurse Practitioner;以下,NP)の役割は重要である。 筆者は訪問看護ステーションで活動しているが,在宅医,クリニックの医師はもちろん,介護支援事業者やヘルパーステーション,通所・入居施設,行政,ボランティア,NPO法人など,多くの組織と連携を強化することを心がけている。これは,個々の病態や生活スタイルに合った生活,また終末期を含めて,急変時・緊急時でも利用者・家族が安心して在宅療養ができること,そして生きる希望をもって日々暮らせるように,対象者と日々向き合う活動をめざしているからである。 2011年度から2014年度まで,厚労省の業務試行事業やプロトコール検証事業に参加し活動した。そのなかで,在宅療養者に新たな症状が出現したり,急な症状の悪化に対応することが少なくなかった。NPとしてその場で判断し,医師の包括指示のもとでタイムリーに特定の医行為を実施し素早く対応するとともに,対象者とその家族にそのつど丁寧に病態を説明することで,信頼関係が深まっていると実感する経験が何度もあった。 日々の訪問時に問診やフィジカルアセスメントを行ない,採血や画像データなどの検査所見を常に把握し,主治医に病状を報告したり,予測される病態を確認し身体状況を詳細に把握していることは,急変時の判断や対応に非常に役立つ。在宅療養を行なう対象者・家族が,急に状態が悪化した場合や終末期などの最も不安な場面で,タイムリーな対応や素早く問題解決に導くことが,在宅療養の継続につながると考える。 重症者や急変しやすい患者,さらに終末期患者においても在宅療養を行なえるように訪問看護を続けているが,在宅医療にかかわるNPの人数はまだ少ないため,訪問看護ステーションにおけるNPの活動によって何が変化し,どのような成果が出ているのか,十分に示せていない状況である。そこで今回,訪問看護関連報酬に注目し,当訪問看護ステーションにおけるNP導入前後の変化の実態調査を行なった。誌面の都合によりその一部を報告する。
3 0 0 0 先端科学研究のメッカ:米国国立衛生研究所(NIH)について
- 著者
- 前田 ひとみ
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 看護研究 (ISSN:00228370)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.23-29, 2000-02-15
はじめに アメリカ合衆国の首都であるワシントンD.C.に隣接するメリーランド州ベセスダに,米国国立衛生研究所(National Institutes of Health:略称NIH)のメインキャンパスがある。NIHは衛生機関の1つであるが,アメリカ合衆国最大の生物医学研究所でもある。昔,ゴルフ場だったというベセスダのキャンパスは300エーカー(1.2km2)以上の広さをもち,木々や芝生の緑に囲まれ,りすや鹿も訪れる自然豊かなところである。 NIHには博士取得者が約6,000人働き,年間7,000以上の論文が世に送り出されていると言われる。NIHは,ベセスダ以外にもフレデリック,バルチモア,ロッキーマウンテン等にも研究施設をもち,おそらく世界最大規模の生物医学研究機関といっても過言ではないであろう。また外国人研究者として日本人研究者も常に400人以上がNIHで働いていることから考えると,日本人にとってもNIHは最大の生物医学研究施設と言えるのではないだろうか。
はじめに 多くの国立大学大学院博士後期課程の学位認定として用いられる基準に,英語論文の採択が挙げられている。おそらくこれは,博士の学位を取得する上で大きな難題になっている。かく言う私も,修士課程時にトントン拍子で2つの英語論文が採択された経験から,博士後期課程でもそのハードルを問題なくクリアできるだろうと高を括っていたところ,足元をすくわれることとなった。13回ものRejectを受けたのである。当然,論文の質が原因ではあるが(研究手法しかり,文章の書き方しかり…),それでもさすがに13回のRejectを受けると,次のジャーナルの選択において路頭に迷うことになる。 世界には数多くのジャーナルがあり,その質は玉石混淆である。これまでさまざまな形で論文投稿を重ねてきた私自身の経験から,実際どのようなジャーナルを探していたか,そして,最低限どのような基準をクリアするジャーナルならば選択して問題ないかについて,主にこれから研究者をめざそうとする大学院生を意識しつつ,述べていきたいと思う。
2 0 0 0 消化器外科病棟における診療看護師(NP)の役割と成果
- 著者
- 飯野 雅子 鈴木 英之
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 看護研究 (ISSN:00228370)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.5, pp.440-448, 2015-08-15
診療看護師(NP)としての役割と成果 飯野雅子 はじめに 昨今,わが国では医療の質,医療の安全性を問う国民の声が大きくなってきている。医療の現場に目を向けると,医療の高度化・複雑化に伴う業務の増大や高齢化による合併症患者の増加などにより,わが国の医療は疲弊してきている。このような現状のなか,「チーム医療」の重要性が謳われている。 そこで2010年3月,厚生労働省はチーム医療の推進を図るための1つとして,看護師の業務拡大の必要性をあげ,特定看護師(仮称)の設置,法制化に向けての素案を示した。このような社会背景を踏まえ,クリティカルケア領域でも対象患者の高齢化,疾病の複雑さにより,医療者の業務は増大している。そのため,周術期の患者管理においても多職種によるチーム医療の必要性が高まっている。 チーム医療の一員にナースプラクティショナー(Nurse Practitioner;NP)が存在できるのであれば,NPの特性である医療的,看護的の両側面からアプローチすることで,タイムリーかつ質の高い医療を患者に提供でき,患者や医療者の満足度も上げることにつながると考える。 今回,所属する消化器外科病棟の看護師に対し,診療看護師(NP)の活動についてのアンケート調査を行なった。その結果から得られたNPの成果について述べる。
- 著者
- 草間 朋子 村嶋 幸代 真田 弘美 深井 照美
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 看護研究 (ISSN:00228370)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.5, pp.468-477, 2015-08-15
診療看護師としての活動の成果 草間(司会) 2025年に向けて,いま,医療制度が大きく変わりつつあります。その中で,昨年6月に「医療介護総合確保推進法」が通りまして,その一環として保助看法も昭和23年に制定されて以来初めて看護師の業務に踏み込んだ改正が行なわれました。「特定行為に係る看護師の研修制度」として法制化されたことで,診療看護師(NP)に関連するいままでの私たちの取り組みがようやく認められつつあることを実感しています。 診療看護師は,医療界にとって大きな課題である2025年問題の解決に向けての重要なキーパーソンになると考えています。現在,診療看護師を養成する大学院は全国で7校あり,修了生は2015年3月現在で200人を超えており,素晴らしい活躍をされています。制度の施行は本年10月からですが,制度化に至るまでの間,厚生労働省が平成23年に養成試行事業,24年に業務試行事業という2つのモデル事業を立ち上げました。モデル事業を通して,診療看護師の実績が出てきているところかと思います。診療看護師をさらに定着させ進化させていくには,これからしっかりエビデンスを創出し,公表していくことが大変重要だと思います。そのためにも,わかりやすく納得が得られるアウトカムを形で残し,それを基盤に学問として成長させていく必要があります。本日はそのあたりを中心に議論したいと思います。
- 著者
- 山崎 喜比古
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 看護研究 (ISSN:00228370)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.7, pp.479-490, 2009-12-15
はじめに 健康生成論およびSOC概念・尺度の提唱と本稿の目的 20世紀後半,特に最後の四半世紀,健康・病気と保健医療の世界においてパラダイムシフト,すなわち,それまでの健康・病気と保健医療に関する伝統的支配的な見方・考え方に代わる新しい見方・考え方の提唱と普及が進んだ。 その1つに,ユダヤ系米国人の保健医療社会学者アーロン・アントノフスキー(Aaron Antonovsky)博士(社会学)が,1979年と1987年に刊行した2大著作で世に問うた健康生成論(salutogenesis)とストレス対処・健康保持力概念SOC(sense of coherence)がある。書名を和訳すれば,1作目が『健康,ストレス,そして対処─心身の健康への新しい見方』(Antonovsky, 1979)であり,2作目が『健康の謎を解く─ストレス対処と健康保持のメカニズム』(Antonovsky, 1987/山崎・吉井監訳,2001)である。 Antonovskyによれば,従来の医学は,予防医学や公衆衛生も,基本的には,疾病生成論(pathogenesis)的な観点から,疾病を発生させ増悪させる危険因子(リスクファクター;risk factor)と,その軽減もしくは除去の方策について,膨大な知識と実践を蓄積してきた。それに対して健康生成論は,疾病生成論とは180度転回した角度,すなわち,健康はいかにして回復され,保持され,増進されるのかという観点から,その要因を健康要因(サリュタリーファクター;salutary factor)と呼び,健康要因の解明と支援・強化がめざされる理論である。 さらにAntonovskyは,人々の健康を守り改善するためには,疾病生成論と健康生成論が相互補完的に,車の両輪のように発展させられなくてはならない,にもかかわらず,健康生成論は,疾病生成論に比べてあまりにも大きく立ち遅れてきたという。 SOCは,直訳すれば首尾一貫感覚,すなわち,自分の生きている世界(生活世界)は首尾一貫している(coherent),つまり,筋道が通っている,腑に落ちるという感覚である。我々は,SOCの日本語との呼称としては,わかりやすさの点から,日本に紹介した当初より,何をどのように感じている感覚なのかを表現する「首尾一貫感覚」ではなく,何に対してどのような働きをする感覚なのかを表現する「ストレス対処・健康保持能力」または単に「ストレス対処能力」のほうを用いてきた。しかし,それも,「能力」とするか,それとも単に「力」とするかについては,正直,ずっと迷い続けてきた。本号焦点でも,基本的には従来通り,「能力」を用いているが,本稿では,あえて「能力」の代わりに,包括性のより高い「力」のほうを使わせていただくこととした。両者のニュアンスの違いについては,簡単にではあるが後述する。 SOCは,Antonovskyが,上述した健康生成論的な観点から,極めてストレスフルな出来事や状況に直面させられながらも,それらに成功裏に対処し,心身の健康を害さず守れているばかりか,それらを成長や発達の糧にさえ変えて,明るく元気に生きている人々のなかに見いだした,人生における究極の健康要因であり,健康生成論の要の概念である。 Antonovskyの健康生成論的な発想と見方・考え方は,その後,世界の保健,医療,看護や心理などヒューマンサービスに関わる広範な分野の学問と実践にパラダイムシフト的なインパクトをもたらした。また,SOC概念がAntonovskyの2作目の著作(Antonovsky, 1987/山崎・吉井監訳,2001)において尺度化され,SOC尺度が提案されることによって,この20年あまりの間に,SOCと健康生成モデルの実証研究が大いに促進され,年々,幾何級数的な増加を示し,世界の学術雑誌に掲載されたSOC実証研究論文だけでも,今日までに千数百本にものぼっている。健康生成モデルとは,SOCはどのような働きをするのか,SOCは何によって育まれるのかということについての理論モデルのことである(図1)。 本稿では,以下,こうしたSOCとその着想のもとになった健康生成論とはどういう概念であり理論なのか,特に,SOCはどういう感覚なのか,人生における究極の健康要因として,ストレスフルな出来事や状況に直面して,どのような働きをする,どういう力なのかということについて,Antonovskyの提唱した理論をベースに,その後の実証研究の成果も踏まえて,概説してみたい。筆者らが2008年に出版した『ストレス対処能力SOC』(山崎・戸ヶ里・坂野編,2008)の第1章「ストレス対処能力SOCとは」とも重なるところが少なくはないが,本稿では,さらに整理と深化を随所で図ったつもりである。
目的:「健康マージャン教室」に参加した健常な高齢者を対象に,健康マージャン教室が認知機能に与える効果を明らかにする。 対象と方法:対象者は89名(平均年齢72.0歳,標準偏差6.5歳)で,教室に週1回,合計20回参加した。教室開始時(Pre)と終了時(Post)でMini Mental State Examination(MMSE),Frontal Assessment Battery at Bedside(FAB),Trail Making Test(TMT)Part A and Part BとGeriatric Depression Scale(GDS)短縮版を測定した。Pre-MMSEの合計点を基準に比較的低い群(MMSE26点以下:A群)と高い群(MMSE27点以上:B群)に分けた。Pre-Post比較ではWilcoxonの符号付き順位検定を行ない,群間比較では,群間に有意差のあった年齢と教育年数を調整する目的で多変量共分散分析を行なった。教室終了時には,日常生活における変化を質問紙で調査した。 結果:Pre-Post比較では,特にA群でMMSEの「計算(p<0.01)」と「合計点(p<0.05)」,TMT-A(p<0.05),GDS(p<0.05)で有意差がみられた。質問紙への回答では,「生活の充実感」「チャレンジ意欲」等の各項目において有意差があり,さらに友人や地域交流への意欲がみられた。 結論:検査結果から,健康マージャン教室による認知機能の活性化が示唆された。さらに,新たな人間関係の形成や日常生活での活動意欲にも影響を与えたと考えられた。
- 著者
- 山浦 晴男
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 看護研究 (ISSN:00228370)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.218-227, 2017-06-15
はじめに この小論は,次の文献と筆者の体験をもとに,クラシックGTとKJ法およびそれに準拠した質的統合法(KJ法)を比較検討している。 Ⅰ. 川喜田二郎(1967).発想法─創造性開発のために.中央公論社. Ⅱ. 川喜田二郎(1986).KJ法─渾沌をして語らしめる.中央公論社. Ⅲ. B.G.グレイザー&A.L.ストラウス/後藤隆,大出春江,水野節夫訳(1996).データ対話型理論の発見─調査からいかに理論をうみだすか.新曜社. Ⅳ. 山浦晴男(2008).科学的な質的研究のための質的統合法(KJ法)と考察法の理論と技術.看護研究,41(1),11-32. Ⅴ. 山浦晴男(2012).質的統合法入門─考え方と手順.医学書院. Ⅵ. V.Bマーティン&A.ユンニルド編/志村健一,小島通代,水野節夫監訳(2017).グラウンデッド・セオリー─バーニー・グレーザーの哲学・方法・実践.ミネルヴァ書房. これらの文献とともに,KJ法の創案者川喜田二郎氏に直接指導を受けた20年間の体験と,その後の26年間にわたる筆者の実践経験に基づき,比較検討を行なった。 日本ではグレイザーの流れに基づくクラシック・グラウンデッド・セオリー(以下,クラシックGT)のほかに,ストラウスの流れをくむグラウンデッド・セオリー(以下,GT)が普及しているとされている。そこで次の文献も参照したが,本小論では主にクラシックGTとの比較を行なっている。 Ⅶ. 木下康二(2003).グラウンデッド・セオリー・アプローチの実践─質的研究への誘い.弘文堂. Ⅷ. 戈木クレイグヒル滋子(2005).質的研究方法ゼミナール─グラウンデッド・セオリー・アプローチを学ぶ.医学書院. Ⅸ. 戈木クレイグヒル滋子(2006).グラウンデッド・セオリー・アプローチ─理論を生みだすまで.新曜社. Ⅹ. 髙木廣文(2011).質的研究を科学する.医学書院. これらに加えてさらに,次の文献を参照している。 Ⅺ. マイケル・ポランニー/高橋勇夫訳(2003).暗黙知の次元.筑摩書房. Ⅻ. 伊藤邦武(2016).プラグマティズム入門.筑摩書房. なお,筆者はクラシックGTおよびGTの直接的な体験がなく,文献ならびに小島通代氏の講義と口頭での学びの範囲での理解であり,そこに理解の限界があることを申し添えたい。また,以降の本文中の引用については,一部を除いて,上に挙げた文献番号を示す形とさせていただきたい。
- 著者
- 山口 厚子
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 看護研究 (ISSN:00228370)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.5, pp.399-411, 2003
- 著者
- 稲葉 光行 抱井 尚子
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 看護研究 (ISSN:00228370)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.25-36, 2016-01
1 0 0 0 経験を記述するための言語と論理―身体論からみた質的研究
はじめに 本号の特集「経験を記述する」について,企画者である西村ユミは特集扉の企画趣旨において,知を生成する方向性は複数あることを示唆した上で,「経験の理解は,経験内容の理解とは別の次元から問われ」るとした(p.310)。ここで西村が言う「経験の理解」と「経験内容の理解」の区別は,知の生成の方向性のどのような違いから生まれるのであろう。自然科学が前提としてきた主客二元論を乗り越えることをめざしたフッサール以来の現象学が,さまざまな質的研究に重要な基盤を与えてきたのは確かであるが,現在の質的研究を巡るさまざまな混乱を考えたとき(西條,2005),ガリレオやデカルト,ベーコンを祖とする近代科学の方法論の問題以上に,西洋における知の源流と,知のヴェクトルの問題に付随する言語と論理の問題に立ち戻って考える必要があるのではないだろうか。 そこでこの小論では,「経験の理解」と「経験内容の理解」を,ギリシア時代以来の人間の知の生成の2つの方向性,すなわちプラクシス(実践)に基づく「未来志向の知」と,テオリア(理論)を希求する「過去志向の知」に結びつけ,そこにみられる意識と自然あるいは主観性と身体性の観点から考えてみたい註1。そして,量的研究か質的研究かという区分あるいはグラウンデッド・セオリー・アプローチ(GTA)や記述的現象学的方法など特定の質的研究の方法論とは異なる,身体論の立場からの「経験の記述」のあり方を提言してみる註2。 本論に入る前に,この小論で言う〈身体〉とは何かについて簡単に述べておきたい。医療の現場で日々出会う身体は,解剖学の祖ヴェザリウスによって系統的に細分化され,デカルトによって心と区別された身体である。しかし,ここで言う〈身体〉は,そうした要素に分割できる物理的延長としての身体ではなく,心と断絶される以前の全体存在としての〈身体〉である。メルロ=ポンティに依拠する西村(2001)はこの〈身体〉を,「生きられた世界経験の具体的な出発点」であり,「世界とのつながりであり,〈身体〉があるからこそ,世界との対話が可能となる」と表現している。この小論で言う〈身体〉も,メルロ=ポンティが示したこの世界とのつながりとしての〈身体〉であり,それはたんにデカルト以前の心とひとつになった身体ではなく,主体と客体という二元論によって人間存在を理解するはるか以前,ギリシア時代に主観性の哲学が立ち現われる以前の〈存在〉を指している。 では,この主観性の哲学以前の〈存在〉とはいかなるものであろう。ギリシア哲学者の日下部吉信(2005)は,「西洋形而上学は全体として主観性の哲学」であり「存在の真理を隠蔽してきた」という反省から,ソクラテス以前のギリシア自然哲学に着目し,根源概念としての〈自然概念〉(ピュシス)を見いだした。日下部はこの「ピュシス」が「ギリシア人にとっては意識の対象ではなく,ある意味性を帯びた意識そのものであった」(p.78)とし,それを主観性の哲学によって説明することは「原則不可能」であることを強調している。そして,「にもかかわらず,そういった根源概念である自然概念(ピュシス)の解明がなお可能だとするなら,それはその概念が自ら現れ出る現場を差し押さえる現象学的方法によって以外ではありえないであろう」(p.75)とした。このピュシスが「自ずから現れ出る現場」こそが,古代ギリシア人にとってはテクネー(技術)の世界であった。日下部によれば,「テクネーの志向性は物事に即したそれである。ギリシア的テクネーの知はいわば物事との応答の内に開示される存在の思索なのである」(p.55)。 このように,ソクラテス以前のギリシア自然哲学の特徴は,テクネー性の重視にあり,その特徴を日下部は,「技術は物事の本質に対して無関心なのである。テクネーをベースとする命題には原理・本質に対する無関心性,冷淡さがつきまとう。というより,それがテクネーの本性なのであって,テクネーは物事の本質には係わらない。そのありように係わるだけである」註3としている。テクネーの人の代表者であるプロタゴラスが示した「絶対的・客観的知識の穏やかな,しかし断固とした拒否」と「神に関しては判断停止」の態度がこうしたテクネー性そのものであり,「プロタゴラスもまた存在の一表現となった人物」としている。このように私たちの〈身体〉は,ギリシア時代に主観性原理が確固たる地位を占める以前に人々が依拠した存在(自然概念)へと導いてくれる。 東西の身体論についての第一人者であった湯浅泰雄(1993)もまた,ギリシア時代のプラクシス(実践,行動)に対するテオリア(理論,観察)の優位こそが,近代がもたらした問題の根源にあることを次のように指摘している。「技術の進歩が科学を追い抜いたという現代の状況は,日常性と科学性の関係について,あらためて考え直す必要をわれわれに教えている。というのは,技術は本来,日常的経験の場面に根拠をもつ営みであるからである。言いかえればわれわれは,近代とは逆に,日常的経験の立場から出発して科学的認識というもののあり方について考えてゆかなくてはならない」(pp.63-64)註4。 日下部の言う存在としての〈自然概念〉(ピュシス)の喪失から主観性原理の確立,湯浅が言うプラクシスに対するテオリアの優位が成立した経緯は,知の方向性という観点からは,哲学者の大出晃(2004)の言う「未来志向の知」から「過去志向の知」への転換と位置づけられるだろう。この小論では,古代オリエントからギリシア時代にかけて起こった知の方向性の転換におけるこの2つの知のあり方,つまり技術的な知恵を主とする「未来志向の知」と事象の依って来る由縁に関心をもつ「過去志向の知」を,西村の言う「知を生成する複数の方向性」と捉えてみる。そして,存在としての〈身体〉が生み出す「未来志向の知」という観点から,「経験の記述」のあり方について考えてみる。
1 0 0 0 ナラティブ・ベイスト・メディスンと事例研究
事例がセミナーの中で非公式に紹介されたにせよ,症例検討会の中でいつもの形で発表されたにせよ,どんな場合であっても,臨床科学のデータを発表する方法は私にとっておなじみのものだった。その内容は必然的に新しいもの─報告された症状と観察され測定された所見から組み上げられたパズル─だったが,患者の病気についての記述や,医師による診断と治療についてのそれは,私が専門とするところだった。それは物語,つまり,医師と患者という個別の人間達の行動や動機に関する物語的記述であり,彼らはそれぞれの形で状況に不満を抱いたり,その努力が報いられたり,運命に悩まされたりしている。物語を病院内で見いだすことになるとは,私には思いもよらなかった。医学は科学ではないのか? (Hunter, 1991/斎藤,岸本監訳,2001)
1 0 0 0 現代女性の月経血量および月経随伴症状に関する研究
目的:本研究の目的は,正常周期女性の月経状態および月経随伴症状を明らかにすること,および1周期あたりの月経血量を実測し,月経血量の多寡に関する自己の認識を明らかにすること,さらに月経血量と月経随伴症状との関連を分析することである。 方法:19~39歳の女性184名の1周期の月経血量を実測した。初経年齢や月経周期日数,月経持続日数,月経血量に対する自己の認識,月経随伴症状について質問紙を用いて調査した。 結果:質問紙の回収率は168部で,正常周期133名,正常周期でない者27名(稀発月経,頻発月経など)だった。正常周期女性の1周期の平均総月経血量は77.4gであった。その中には,過少月経が4名,過多月経が11名いた。月経血量は月経開始後2日目にピークがあり,その後は急激に減少するパターンを示した。月経血量に対する自己の認識は,「少ない」17名,「ふつう」104名,「多い」11名だった。月経時の下腹部痛を自覚している者が74.7%,腰痛が54.9%であった。月経血量と腰痛との間には有意な関係が認められた。 考察:184名の女性の1周期の月経血量を測定した。正常周期月経にある女性の月経状態を明らかにした。月経血量の多寡を正しく自己判断することの困難さが示唆された。
- 著者
- Cheryl Tatano Beck 中木 高夫 黒田 裕子
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- pp.362-370, 2011-07-15
「エビデンスに基づく実践(Evidence-Based Practice ; EBP)」を提供しようとする強い外圧により,私たちの学問に質的研究から得られた最高レベルのエビデンスをもたらすために,看護研究者たちは質的研究のメタ・シンセシス訳註1の方向に目を向けるようになった。メタ・シンセシスは,質的研究をエビデンス階層のふさわしいレベルに位置づけ,エビデンス階層のレベルを高めるのに役立つ。私たちには,「実践に移植することができるように,研究者,臨床家,そして一般の人々に利用可能な知識を生みだす」責務がある(Thorne, Jensen, Kearney, Noblet, & Sandelowski, 2004, p.1360)。システマティック・レビュー訳註2は,例えば,航空機が離陸する前に,耐空性能が十分であることを確認する飛行前検査に匹敵するものである(Pawson, 2006)。メタ・シンセシスのようなシステマティック・レビューは,臨床実践に利用される前に,あるいは保健政策を形づくるのに先だって,その結果の信頼性を確かなものとするために,厳格な一連のステップを踏む。 いまから40年前,Glaser & Strauss(1971)は,もし蓄積された知識の体系を構築するための方法が使用されなければ,研究者たちがばらばらに訪問するために,その個別の質的研究からの結果は「他から切り離されている全く関係のない知識の島(p.181)」としてとどまるに過ぎないと警告した。メタ・シンセシスはそのような1つのアプローチである。Sandelowski, Docherty, & Emden(1997)は,他者から孤立して作業する「分析的マスタベーション(分析だけに没頭してしまう視野狭窄)」に質的研究者たちが貢献しないように強調した。
はじめに 筆者らは,Catherine Pope,Nicholas Mays,そしてJennie Popayによる書籍『Synthesizing Qualitative and Quantitative Health Evidence : A guide to methods』(2007)を翻訳する機会を得て,医学書院より日本語版タイトル『質的研究と量的研究のエビデンスの統合─ヘルスケアにおける研究・実践・政策への活用』(Pope, Mays, & Popay, 2007/伊藤,北監訳,2009)として出版した。本書は,英国における医療制度と,エビデンスに基づくヘルスケア政策とマネジメントという文脈において執筆されたものであり,英国を発祥とするEvidence Based Medicine(以下,EBM)の情報インフラストラクチャー(コクランライブラリー)のシステマティックレビューに,質的研究を含めてゆくためのさまざまなアプローチがまとめられている。その目的は,質的研究と量的研究から得られたエビデンスを,政策や臨床実践場面での意思決定に活用できる形に統合してゆくことにある。 日本の看護界においても,質的研究・量的研究の量と質を確保することと平行して,それら両方の研究から産み出された成果を活用され得る形にまとめ上げていく気運が高まっている。そのあらわれは,例えば2010年にPatersonらによる『Meta-study of qualitative health research a practical guide to meta-analysis and meta-synthesis』(2001)が邦訳され,『質的研究のメタスタディ実践ガイド』(Paterson, Thorne, Canam, & Jillings, 2001/石垣,宮﨑,北池,山本監訳,2010)として紹介されたこと,さらに2011年,第37回日本看護研究学会学術集会が黒田裕子大会長(北里大学看護学部教授)のもと,「エビデンスに基づいた看護実践を! 現場の研究熱を高めよう」というメインテーマで開催され,メタ分析およびメタシンセシスに関する研究手法を積極的に実践しておられるC.T. Beck博士の招聘講演が行なわれたこと,それに伴い,博士の論文「Meta-synthesis : Helping Qualitative Research Take Its Rightful Place in the Hierarchy of Evidence」(Beck, 2011)(邦題「質的研究をエビデンス階層の正しいレベルに位置づけるのに役立つ方法」)が,本誌『看護研究』44巻4号に収録されたことなど,枚挙にいとまがない。こうした状況の中で,改めてPope博士らによる本書を読み返してみると,質的研究を看護実践のエビデンスとして位置づけるためのさまざまな方略を俯瞰することができるという点で,私たちにさまざまな可能性を示してくれるように思う。 本稿では,第30回のJRC─NQRでの発表内容をもとに,本書の書かれた背景,すなわち質的研究から得られたエビデンスをシステマティックレビューに含めていこうとする統合アプローチの背景と,Pope博士らがその著書で提示している内容から,システマティックレビューにおける「統合」の位置づけ,さまざまな統合アプローチ,および質的方法論を基盤とする解釈的アプローチについて概説する。
1 0 0 0 システムズ・アプローチによる家族援助の理論と実際
1.システムズ・アプローチの理論的背景 1)家族システム論 家族療法の理論の中でも「家族システム論」は,中心的な位置を占めてきたが,わが国の心理臨床の世界では,この用語や概念的枠組がいまだ市民権を得ているとはいえない現状にある。そもそも「こころの専門職」としての心理臨床の世界に,「物や機械」の世界で使われる「システム」などという言葉を持ち込むこと自体に,不快感をあらわにする心理臨床家も少なくないようである。そこには「システム」という用語は,機械や道具の属性にのみかかわるものだとする暗黙の前提や「思い込み」があるのではないだろうか。確かに,わが国では一般的にそのような社会的文脈の中で,この用語が用いられる場合が多かったことは事実である。しかし,今日ではこの用語は,物理・化学領域だけではなく,生物学的領域でも,社会的・経済的・政治的領域のいずれでも広く用いられるようになってきている。筆者は,心理臨床の世界でもおおいに使われるべき概念だと考えている。したがって,本論では主に「人工的な機械システム」ではなく,「自然な生命システム」という意味や文脈で「システム」という用語を使うことを理解していただきたい。
1 0 0 0 OA 扉
2017年11月5日(日),聖路加国際大学にて「質的研究論文のための査読者向けセミナー」が開催されました。このセミナーは,萱間真美先生(聖路加国際大学)を研究代表者とする文部科研費による研究「看護学の質的研究論文査読ガイドラインと査読者教育プログラムの開発」*の一環で行なわれました。本特集では,萱間先生をはじめとする研究班の先生方のご協力を得て,このセミナーを収録する形で取り上げることとしました。特集は,基本的にセミナーの流れに基づきつつ,セミナー後に寄稿いただいた論文等も含めて,再構成しています。 今回のセミナーでは,模擬査読が行なわれました。セミナーに先立ち,参加者の方々にはモデル用原稿が送付され,個別に査読を行なう課題が与えられていました。当日はその課題をベースに,本特集でもご紹介する「査読ガイドライン」に基づいてグループごとに査読が行なわれ,各グループからの査読結果の発表とともに,ディスカッションが行なわれました。なお,モデル用原稿には,グレッグ美鈴先生(神戸市看護大学)が『日本看護学教育学会誌』に投稿された初回の論文が用いられました。この論文は査読を経て採択され,同学会誌27巻1号(2017年)に掲載されています。特集を組むにあたっては,査読者/投稿者の学びの促進と看護学の発展につながることを期し,グレッグ先生より上述のモデル用論文と『日本看護学教育学会誌』所収の論文の本誌掲載について快諾を得るとともに,『日本看護学教育学会誌』編集委員会からも転載の許諾をいただきました。グレッグ先生には,実際の査読プロセスについてもご紹介いただいています。