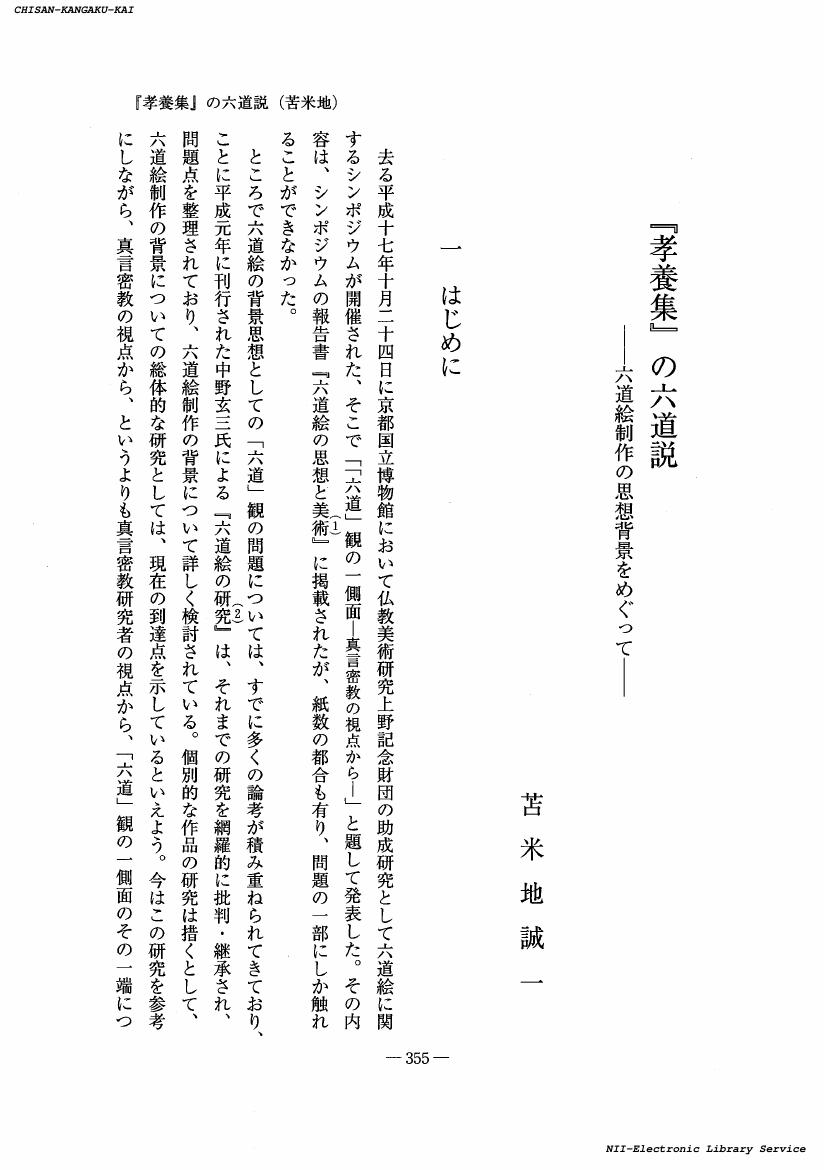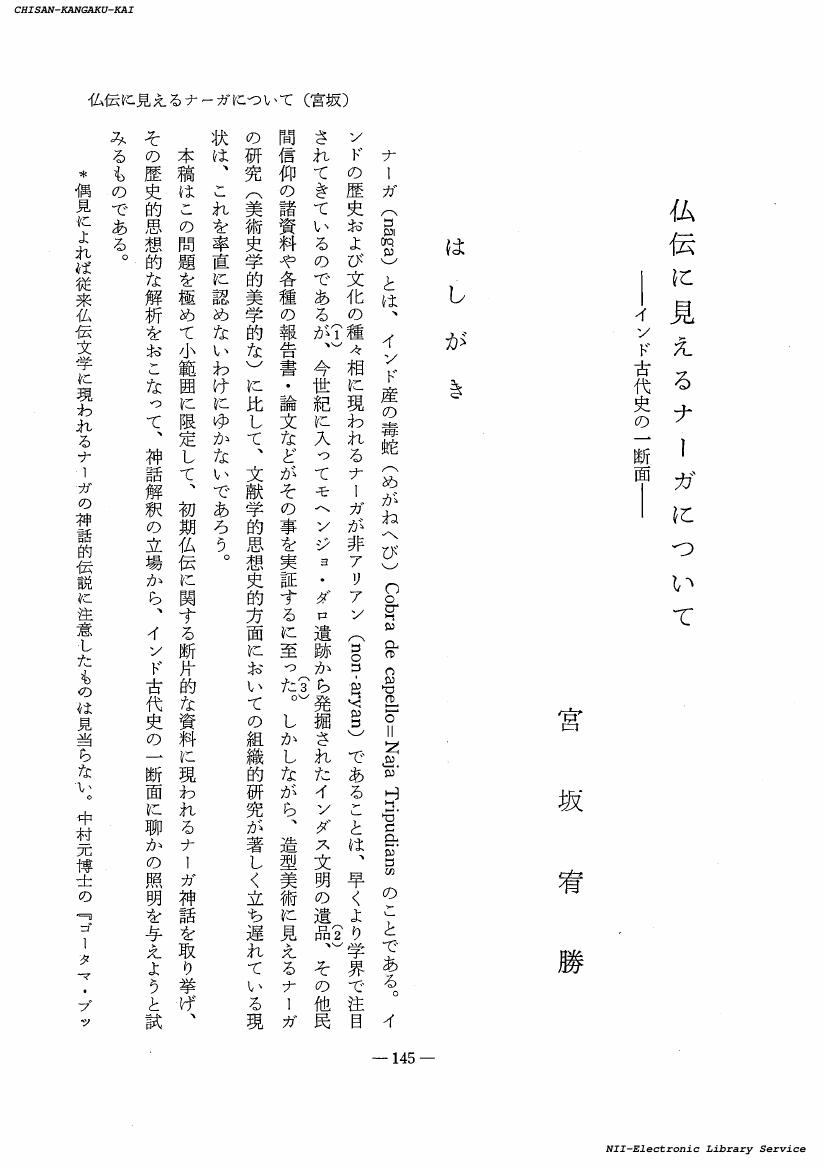1 0 0 0 OA 明恵と食物 ―霊供作法を基調として―
- 著者
- 小宮 俊海
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, pp.145-167, 2019 (Released:2021-01-29)
- 参考文献数
- 59
現在、京都府右京区に位置する栂尾山高山寺を中興開山したとされる明恵房高弁(一一七三〜一二三二)は鎌倉初期を代表する学僧であり、主に華厳教学を学び、真言密教を修行の実践に用いたとされる。本稿では、明恵と真言密教との関わりを考察する一端として、真言密教事相における明恵相伝の口決を取り上げる。特には霊供作法を取り上げ、霊供作法の相伝になぜ明恵が関わることになったのかについて考える。そして、明恵相伝としての成立を考察する前段階として、明恵自身の言説としての著作や後世伝承された明恵像を描く伝記資料を扱う。さらに、霊供作法に欠かせない「食物」、とくには「米」を中心に明恵との関わりを読み解きたい。そして、それらが明恵の修行においてどのような意味を持ったのかについて考察し、霊供作法の明恵相伝とされる蓋然性についてアプローチしたい。
1 0 0 0 OA 旃陀羅の史的考察(一)
- 著者
- 宮坂 宥勝
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山學報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, pp.37-57, 1992-03-31
チャンダーラ(Candala漢訳:旃陀羅)は古代インドにおいて前五世紀頃の初期仏教の時代以後に登場する。古典的な四階級(caturvarnya=varna種姓)以外の最下層の存在として、である。大乗仏教では第四階級に含まれるものとするのと、階級に組みこまれないところのいわゆるアウト・カースト(out-caste)とするものとの、二つの立場が認められる。初期仏教以来大乗仏教、密教に至るまで、全仏教史の展開のなかで、チャンダーラはいかなる意味においても常に無視すべからざるものであった。というのもチャンダーラ観は仏教の人間観と深く関わってきたからである。(1)階級批判もしくは社会的差別の否定の対象としての存在。(2)救済譚における存在。(3)出家についての比喩として。(4)差別是認または社会的差別さらには蔑視の対象。(5)尊格化。(6)その他。本論文で取りあげる主要テーマはこのうちの(1)と(2)とである。
1 0 0 0 OA 諸宗の制度的兼学と重層的(包摂的)兼修
- 著者
- 苫米地 誠一
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, pp.141-158, 2016 (Released:2019-02-22)
- 参考文献数
- 41
奈良・平安期の日本仏教界における諸宗兼学は、大きく分けて「制度的な問題としての兼学」と「重層的(包摂的)な兼修という事態」とが存在する、と考える(実質的には鎌倉期まで含まれるが、室町期以降については、現在の筆者には把握できていないので、今は取り上げない。ただし「制度的な兼学」が機能しなくなっていたとしても「重層的(包摂的)な兼修という事態」は近世末まで継続していたと思われる)。ここでいう「制度的な兼学」とは、太政官符などによって知られる朝廷の律令制度(格)上の問題として規定される諸「宗」を兼学することである。しかし一方では、それとは異なる形で諸「宗」を重層的(包摂的)に位置づけた諸宗の兼学・兼修という事態が存在する。この問題については「宗」の語の意味を含めて、まだ十分な議論・認識がなされていないと思われる。この問題については、筆者も以前に少しく述べたことがあり(1)、また堀内規之氏(2)も触れておられるが、今回はそれらを踏まえた上で些か再考したい。 ところで日本史学では、仏教が日本に伝えられた当初に「三論衆」「法相衆」と呼ばれていたものが、後に「三論宗」「法相宗」に変ったと説明されることがある。これは「宗」と「衆」とが同じ意味であることを前提とする。しかしこのような説明は、日本の史料の中のみで作られた理解であり、仏教が中国から伝えられたことや、当時の中国仏教界で「宗」の語がどのような意味であったのか、という問題を無視した議論と言えよう。或いは当時の日本人が、新しく伝えられた中国仏教について、その教理についても、教団的在り方についても、全く理解できなかったと言うのであろうか。少なくとも中国仏教において「宗」は教の意味であり、衆徒を意味する用法は見いだせない。即ち「三論衆」「法相衆」とは「三論宗(を修学する)の衆徒」「法相宗(を修学する)の衆徒」の意味、その省略形であり、そのことは当時の日本においても十分に了解されていたと考える。 既に田中久夫氏(3)は鎌倉時代の仏教を区別するに当り「鎌倉時代に天台宗といえば、天台の教学を意味し、教団の意ではない。それゆえに、天台宗・真言宗などと呼び、教団史的に区別するのは実態に相応しない」として「現実に存在したのは、南都北嶺と真言密教の教団(寺院)と地方におけるそれらの末寺である」と指摘しておられる。もっとも南都(東大寺・興福寺)は真言宗僧が顕教諸宗を兼学する寺院となっており、決して南都と真言密教の教団(寺院)とを区別することは出来ない。どちらにしても諸宗の兼学は奈良時代の南都仏教に固有の問題ではない。平安時代から江戸時代に至るまで、以下に論ずる「制度的な兼学」と「重層的(包摂的)な兼修」の問題は別にして、諸宗の兼学・兼修は、全ての僧尼にとって日常的なものであった。そもそも「宗」が教理・信仰の意味であることを前提として、初めてこの諸宗の兼学・兼修ということが理解できる、と考える。 「宗」を人(衆=教団)と見る理解は、明治時代に西洋的法概念が導入され、そこで定められた宗教法人法によって規定された宗派教団に対する現代的常識によって成立した理解であろう。明治期以降の宗派教団は「法人」の概念によって、夫々に独立した組織(宗教法人)を形成し、その教団名として「宗」の語を冠した。このことが古代における「宗」概念にも影響を及ぼし、何ら反省されることなく適用されてきたのであろう。しかし江戸期以前の日本仏教界では、そのような概念も組織も存在しなかった。存在したのは「宗」を同じくする者の寺院の本末関係であり、本寺が末寺を支配する、その関係が「宗」を同じくするが故に「宗=教団」が存在するように見えるのかも知れない。しかし「出家得度の儀礼に拠って入門する教団」という意味において「教団」というものを捉える時、その「教団」は四方僧伽としての出家教団でしかありえない。中国・日本において「宗」の相違は問題とはされず、同じ四分律による授戒が行われてきた。たとえ叡山の大乗戒壇が允許され、大乗菩薩戒(金剛宝戒)によって大僧(比丘)に成ることが認められたとしても、四分律か菩薩戒か、の相違によって「宗」が異なることにはならなかった。則ち「宗」毎に別箇の教団が存在する訳ではない。インド仏教において、部派によって異なる律を受持し、授戒が行われたとしても、全国を遊行した彼等は、同じ精舎に同宿し、同じ托鉢の食事を分け合っている。ただ夏安居の終りに行われる自恣のみは、同じ部派の者同士が、精舎内の別々の場所に集まって行ったとされる。これは受持している律の本文・内容が部派によって異なるからではあるが、それ以外の場面において、部派の相違が「教団」的な相違を示すことはない。それは同じ「四方僧伽という教団」内の派閥的・学派的相違に過ぎないからであろう。確かに日本では、沙弥(尼)戒・具足戒の受戒制度が崩れ、その意味では正しい四方僧伽への加入が成立し得ていないという問題が存在するかもしれない。それにしても朝廷によって補任される僧官(僧綱)は、諸宗の相違を越えて僧尼全体を統制する機関であった。僧綱位が後に名誉職化して僧綱組織の実体が無くなり、仏教界における権威(又は単なる名誉)としての機能しか持たなくなったとしても、その補任に「宗」の相違を問うことはない。
- 著者
- 苫米地 誠一
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.355-378, 2007-03-31 (Released:2017-08-31)
1 0 0 0 OA 「光明真言七種秘印」小攷
- 著者
- 小宮 俊海
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, pp.169-181, 2015 (Released:2017-03-10)
- 著者
- 字都宮 啓吾
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, pp.199-220, 2013
1 0 0 0 OA 慈雲尊者の如意宝珠観 ―「十種神宝」を中心として
- 著者
- 松下 年光
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, pp.327-345, 2020 (Released:2021-04-06)
- 参考文献数
- 9
江戸時代後期に活躍した真言僧の慈雲(一七一八~一八〇四)は悉曇学を大成し、又戒律の復興を目指し、釈迦在世当時の正法律を唱導、更に空海が唐より伝えた十善戒を戒体として道俗問わず、人となる道を説くなど、教学に努めた学匠であり、神道もその一環であった。彼は、特に晩年70代近くになり記紀などの神道研究に専念するようになった。 空海(七七四~八三五)が入唐時に、恵果阿闍梨から直伝された能作性(如意)宝珠は承和元年(八三四)の真言院での「後七日御修法」による鎮護国家祈願、玉体安穏、五穀豊穣の祈願法会を初めとして、如意宝珠による修法は広まっていったが、又、空海は嵯峨天皇より、入唐後に、伊勢神宮にて「十種神宝図」を写し、特にこの神宝の中で生玉は能作性宝珠とするように勅令を受けた。 本稿では、雲伝神道の伝授の「十種神宝図」を基に、慈雲の聞書他の著作からその慈雲の日本神話の神々と道教、易経、儒教、陰陽五行説等を融合した両部曼荼羅的解釈を検証し、慈雲の晩年における如意宝珠観を考察したい。
1 0 0 0 報身報土について ―真言密教の論義書を中心に―
- 著者
- 北川 真寛
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, pp.257-277, 2020
<p> 高野山(南山)では、『釈摩訶衍論』に関する論義が法会として現在でも続けられているが、総合的な学術研究はほとんどなされていない。論義とは、問答などによって諸宗の教学と真言教学、あるいは真言密教の諸流派や諸山の法門の義理を分別するものであるが、問答を通して自宗の教学がいかなるものかを学ぶ、一種の学修システムとしての側面もある。</p><p> 本論で取り上げる「報身報土」の論義は、釈論西方論義十條中の一題であり、阿弥陀の身土が報身報土か化身化土かを論じる論題である。阿弥陀の仏身仏土論については、すでに中国仏教界において論じられていて、日本においても浄土宗では報身報土、天台宗では化身化土を主張している。</p><p> 真言宗においても、古義・新義を問わず阿弥陀の身土を報身報土と規定しているが、その理由として『釈論』自身や浄土門の教説に依ること、そして天台宗との対弁を主張していることも考えられる。</p>
1 0 0 0 OA 大円鏡智成立の背景の諸相 ーその試論的論考ー
- 著者
- 河波 昌
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, pp.1-14, 2016 (Released:2019-02-22)
- 参考文献数
- 22
仏教は智慧と慈悲との宗教である。両者は相互に不可分に交渉しながら知慧論は智慧論として、慈悲論は慈悲論として限りなく深められていった。 智慧論も釈尊の正覚の事実の上に展開せられてゆくことになり、それはやがて顕教における四智として、また密教における五智論として展開せられていった。四智とはいわゆる大円鏡智、平等性智、妙観察智、成所作智の四であり、密教における五智はこれら顕教の四智を統合する法界体性智を加えて智の体系を構成する。この五智は金剛界曼荼羅の立場において展開される。 大円鏡智は四智、五智を貫いてその根幹をなすものと考えられる。 大円鏡智を含めて四智等の成立は名義的ないし概念的にはインド大乗仏教史の展開においても比較的後期に成立した『仏地経』 Buddhabhūmisūtraにおいて初めて登場する。(玄奘訳『仏説仏地経』大正十六巻所収)。 一般に四智論は唯識思想の立場において論じられる場合が殆どであるが、四智論自体は恐らくそれとは無関係に、そして唯識関係に対しては先行する形で成立していたことが考えられる。『仏地経』には唯識思想の展開がまだ考えられず、むしろそれ自体として成立している。とはいえ瑜伽唯識を実践する人たちにとって、かかる提示された四智はそのまま実践の目標となってゆくのであり、それがやがていわゆる「転識得智論」(『成唯識論』等)として展開されてゆくことになる。 もちろん四智論等は唯識関係にとって重要であることはいうまでもないが、『仏地経』の展開にもみられるように四智論はむしろ、それ自体として独立に考えられるべきであろう。 本論は四智論、中でも「大円鏡智」自体をその生成、成立において考えようと試みるものである。その際、左のような成立の背景ないし展望が考えられる。本論はそれらを左記のような章において考えようと試みるものである。 第一章 釈尊における大円鏡智成立の原型 第二章 『仏地経』以前の先行経典における大円鏡智思想の展開 第三章 大円鏡智成立の風土論的背景 第四章 東西文化の出会いを背景として成立した無限円 (大円鏡智) 第五章 近代における大円鏡智論の展開ー山崎弁栄の場合 以下はその論考である。
1 0 0 0 OA 明恵房高弁における「土砂加持」理解
- 著者
- 佐々木 大樹
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, pp.279-307, 2020 (Released:2021-04-06)
- 参考文献数
- 13
土砂加持とは、土砂を真言陀羅尼で加持する密教儀礼であり、土砂を遺体などに散ずることにより、往生できると信じられた。日本では光明真言による土砂加持が広く行われてきた。本論では、インドや中国における土砂加持に関する研究を踏まえ、日本において土砂加持信仰を宣揚した僧として明恵房高弁を取り上げた。具体的には、明恵房高弁の土砂加持に関する著作を網羅的に調べ、その理解や実践について六つのテーマを設けて研究した。その結果、明恵は、経典や儀軌の記述を踏まえながらも、土砂の選定や土砂加持の手段、また在家者にすすめる受持方法において特異な解釈を施していることが確認された。また、明恵房高弁は、土砂加持や呪砂の本質を説明する際、多く弘法大師空海の思想(『即身成仏義』『声字実相義』等)を援用していることが判明した。
1 0 0 0 OA 『声聞地』の不浄観 ―諸経論との関係性をめぐって―
- 著者
- 阿部 貴子
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, pp.0119-0139, 2020 (Released:2021-04-06)
- 参考文献数
- 48
本稿は『声聞地』の成立背景を探るために、不浄観に関する所説を考察するものである。特に、他の経論との接点が認められる体内の36種、死体の10種、墓場の4種、内外の観察という観点について、阿含経典、阿毘達磨論書、禅経典と比較した。 これにより、『声聞地』の不浄観は、『念処経』(Smṛtyupasthānasūtra)に基づきながら、細部の解説や法数については『雑阿含経』や『集異門足論』『法蘊足論』『婆沙論』と近い語句を用いていることが分かった。 不浄観をはじめとする五停心観という枠組みは、これまで禅経典の影響が指摘されてきたが、その内容は―五停心観の他の瞑想方法と同様―ほとんど相応しない。むしろ、阿含経典の所説を取り上げ、『法蘊足論』『集異門足論』『婆沙論』などの初期阿毘達磨論書と同様の法数や語句で補強しながら自説を展開しているといえる。
1 0 0 0 かくし念佛と祕事法門の混同
- 著者
- 高橋 梵仙
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.57-61, 1955
1 0 0 0 妙見信仰と道教の真武神 : 附天正写本「霊符之秘伝」
- 著者
- 吉岡 義豊
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.103-138, 1966
- 著者
- 片野 真省
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, pp.123-136, 2016
もう30年以上前のことだが、1990年にアメリカのアカデミー賞で9部門を独占した映画に「アマデウス」がある。御存じの方も多いだろう。アマデウスとはご承知のとおり、ヴォルフガンク・アマデウス・モーツアルトの生涯を綴った作品である。プーシキンの「モーツアルトとサリエリ」を題材に脚本・映画化したもので、初めにブロードウエイで舞台上演されたものが映画化された。モーツアルトを描いたこの作品の主人公は、モーツアルトではなく彼と対比されるサリエリである。この映画には「神の名の元にすべては平等か?」という問いかけが基底に流れている。つまり「秀でた才能が、誰にでも平等に与えられはしない。それが現実。」ということでもある。この作品は、モーツアルトが周囲に暴言を吐き、酒に溺れ、父の面影に怯え、レクイエムを書きあげながら死に到り共同墓地に粗雑に葬られる。そんなショッキングなシーンが続く。そしてラストには、自殺しきれずに生きながらえたサリエリが施設で「全ての凡庸なるものに幸あれ」と呟き、微かな笑みを浮かべてエンドロールを迎える。<br> 神とは何か? 信仰とは? そして、人間は天才と凡庸に分かつのか? このように、我々が日々の暮らしで当たり前に抱く問いかけを、この映画は投げかけてくる。生まれによって差別されるのではなく、行為によって差別される。そんなことは分かっていても、我々凡庸なる者は、時に自らの運命を嘆き、その非力さ故に幾度となくあきらめを余儀なくされる。この社会はそんなキレイゴトを飲み込んで、いつも惨たらしい現実を我々に突き付けてくる。しかし、そうして突き付けられた現実に、唯々諾々と流されてしまうなら、我々は自らの凡庸さを受け容れるしかないのである。現実を前にして、登る坂道は向かい風でも、この坂を登らなければ、その向こうにあるまだ見ぬ風景を目にすることは叶わない。その先には真っ青な空が拡がり、雲が浮かび流れ、ひょっとしたら彼方に虹が見えるかもしれない。自身の内にある可能性を見出すにはこの坂を登らなければならない。この坂とは何か? 我々にとっては、百千萬劫にも遭いおうこと難き教え、つまり仏の教えである。<br> 我々は真言宗の寺院に生まれ、または何かしらの縁で今この寺院と関わりあった。遭うこと難き寺院とご縁が結ばれ、それが真言宗の寺院であるという運命は、その寺院のご本尊さまのおはからい以外何物でもないだろう。その得難き縁は、釈尊から連なり、宗祖弘法大師と中興興教大師の尊くも篤き想いを汲むものである。それを「選ばれた者」と受け止めるか「単なる偶然の賜物」と受け止めるのか……。しかし、我々仏教徒、真言行者はもはや前者に身を置くこと以外に選択肢はないはずである。「良く保つ」との言葉を口にした瞬間に、真言密教の世界に生きることは運命づけられた。釈尊から両祖大師へと連なるこの教え。寺院に赤々と灯されてきた法灯を絶やすことなく、次の世代へ、未来へ受け継ぐために身を粉にして励むこと。そうして与えられた場が寺院である。我々自身はあくまで凡庸なる者かもしれない。しかし、遭い難き教えを受け継ぐ運命に出会った以上、その教えを担う役割を我々はこの時代に課せられた。それを喜びと感じ、寺院において法悦を檀信徒とともに味わうすべての凡庸なるもの。そのあり方、一側面を考察するのが本論の試みである。アマデウスの映画の最後にモーツアルトのピアノコンチェルト40番第2楽章「ロマンス」が流れる中、サリエリが浮かべる笑み。その意味をここで考えてみたい。
- 著者
- 渡辺 照宏
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.1-14, 1957
1 0 0 0 OA 支那佛教 : 唱導文學の生成(續)
- 著者
- 澤田 瑞穗
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.1940, no.14, pp.65-98, 1940-12-17 (Released:2017-09-01)
1 0 0 0 OA 法隆寺貝葉『般若心経』写本についての一報告
- 著者
- 矢板 秀臣
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.A7-A16, 2001-03-31 (Released:2017-08-31)
1 0 0 0 OA 藤原為忠の事歴とその子常盤の三寂の出家をめぐって
- 著者
- 鈴木 佐内
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.171-189, 1988-03-31 (Released:2017-08-31)
丹後守藤原為忠とその子たち、特に常盤の三寂、為業寂念、為経寂超、頼業寂然の事歴を、白河院の近臣受領という方面から追い、三寂の発心が、院が特に心をかけた待賢門院一流の勢力の衰退に関わることを考察した。藤原為忠の事歴については、井上宗雄氏が「常盤三寂年譜考 附藤原隆信略年譜」でふれておられるが、表題の示すとおり、為忠の子常盤の三寂についての事歴が主であり、白河院の近臣受領としての為忠をみるには十分ではない。知綱以来、白河院と強い縁で結ばれてきた常盤一族の盛衰が、白河院勢力のそれと深いかかわりをもつのも当然であって、本稿は、為忠の近臣受領としての姿をあきらかにする意味で、井上氏の年譜を拠り所とし、同氏が記述されなかった事歴をも加え、私見を付し、更に、これによって、近臣受領の子という、その子たちの消息から、特に出家の動機を探ってみたい。
1 0 0 0 OA 仏伝に見えるナーガについて : インド古代史の一段面(那須博士古稀記念論文集)
- 著者
- 宮坂 宥勝
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.12.13, pp.145-163, 1964-11-21 (Released:2017-08-31)
- 著者
- 宮坂 宥勝
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.145-163, 1964