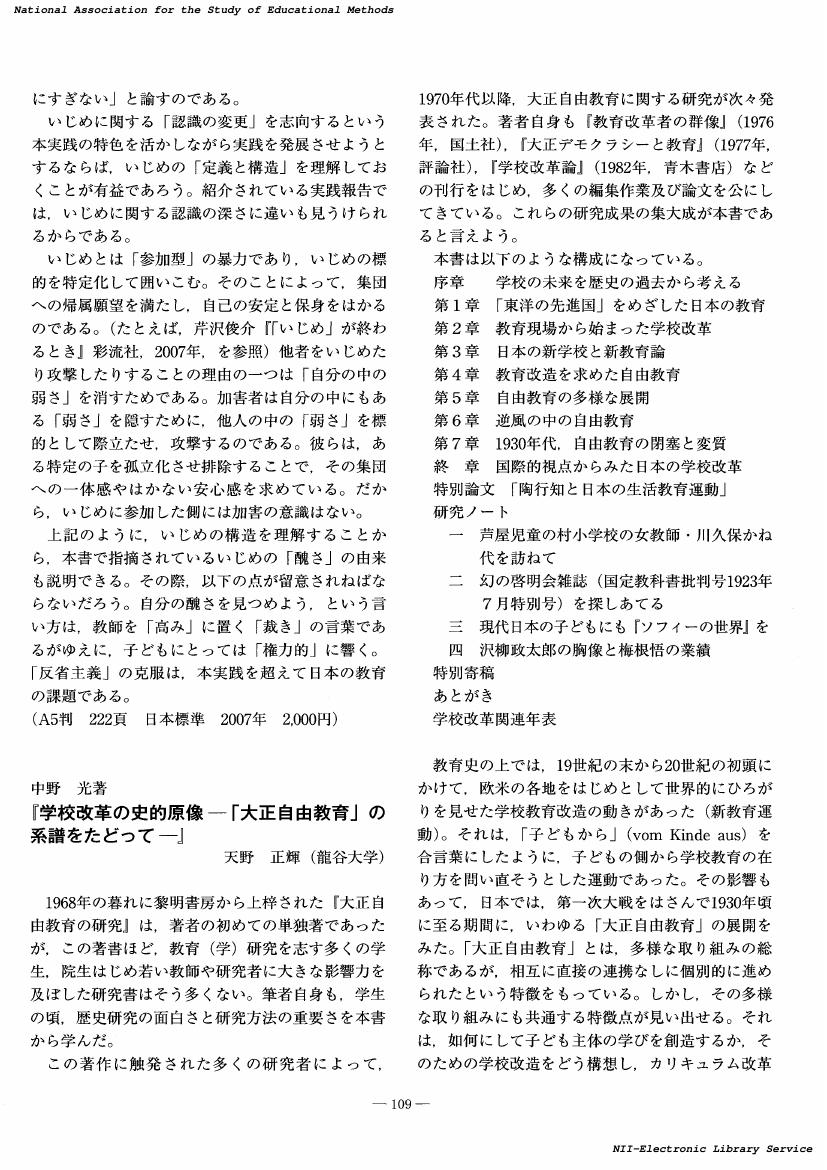- 著者
- 塩路 晶子
- 出版者
- 日本教育方法学会
- 雑誌
- 教育方法学研究 : 日本教育方法学会紀要 (ISSN:03859746)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.49-57, 1998-03-31
The purpose of this paper is to study the principle of children's recognition, understanding focused on G. H. Mead's Interactionism. This study will be the starting point for clarifying the dynamism of teaching in "teacher-student" educational relationship. The theory of G. H. Mead in this paper is one in the early 20th century. Through studying Mead's theory, I may examine the scientific knowledge in the interaction between "experience" and "science", and draw suggestion about the principle of children's "understanding". Anyone knows that Mead was one of the American Pragmatists around the turn of the century and had great influence later on the Symbolic Interacionism. As yet one have researched on Mead's theory in the field of philosophy or sociology. In the pedagogical field, only Mead's self-formative theory is quoted a little. It's important to study early works for searching possibility of Mead's educational theory, because the self theory may be based on the early educational works of Mead. Then,in order to grasp the principle of children's understanding, this paper brings focus into, firstly, the criticism to the separation of "science" and "experience", secondly, the generation of meaning in the interacion of "science" and "experience", and of student and teacher. This aims to grasp the educational fundamental perspective and draw the suggestion for the principle of understanding.
- 著者
- 多和田 真理子
- 出版者
- 日本教育方法学会
- 雑誌
- 教育方法学研究 : 日本教育方法学会紀要 (ISSN:03859746)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.83-94, 2003-03-31
本稿の目的は,上田万年の『作文教授法』(1895年)を素材に,言語と教育の結びつきを検討することにより,上田が明治期の小学校における作文教育に付与しようとしていた役割を論じることである。上田は「普通教育」と「国語」という2つの概念の関わりにおいて「作文教授」を構想していた。上田は「普通教育」に,「社会」における「人民の教育」と,「国家」における「国民教育」という,2つの側面を見出していた。それは「国語」がもつ2つの側面,すなわち「社会」の変化に応じて改良可能な「道具」としての面と,「国民」に与えられるべき固定的な「道具」としての面とに相互に関係していた。小学校の作文教育に対して上田が提起した新しい観点は,第1に,従来の教養に価値を認めず,かわりに<思想→言葉→文字>の変換に価値をおくということである。第2に,「言葉」や「文体」の多様性を認め,他者の「言葉」を聴き,「文章」を読むことによって他者の存在を認識することである。だがそれらは,上田が提起した第3の点,すなわち言語に一定の「標準」を求め,その「標準」に近づく階梯と子どもの「心理発達」とを結びつけ学校教育の段階として位置づけることにつながった。言語の共有という上田の理念が,「作文教授」論をつうじて,言語の標準化へと結びついたのであった。
- 著者
- 小川 博久
- 出版者
- 日本教育方法学会
- 雑誌
- 教育方法学研究 : 日本教育方法学会紀要 (ISSN:03859746)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.134-136, 2000-03-31
- 著者
- 寺岡 英男
- 出版者
- 日本教育方法学会
- 雑誌
- 教育方法学研究 : 日本教育方法学会紀要 (ISSN:03859746)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.107-108, 2009-03-31
- 著者
- 天野 正輝
- 出版者
- 日本教育方法学会
- 雑誌
- 教育方法学研究 (ISSN:03859746)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.109-110, 2009-03-31 (Released:2017-04-22)
1 0 0 0 OA 他者と出会えない子どもたちに関する予備的考察 : 現代における自己形成の難しさ
- 著者
- 生越 達
- 出版者
- 日本教育方法学会
- 雑誌
- 教育方法学研究 (ISSN:03859746)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.1-9, 2000-03-31 (Released:2017-04-22)
Children have come to withdraw softly by degrees into themselves from the society. It seems to us that they are hoping to have to do with others but that they are afraid of being involved in others from the bottom of their heart. These soft withdrawals are caused by avoidance of others and as a resutl of that, shallow selves. In this thesis, two episodes are picked up: a 14 years' boy who killed young children bizarrely in Kobe and high school girls who look themselves in the looking glass elaborately in the train. In the first place, I interpret the crime statement of a 14 years old murderer. He describes himeself as the transparent being. It means his ego who lives in a different world from others and cannot communicate with others. In the second place, I explicate high school girls and show that they are seeking for others' sight but that they will not pay no attention to others' feeling. These episodes show commonly that some children demand and refuse others at the same time. Behind such their contradictory attitudes, weak or shallow selves of children are hidden. Children produce a variety of communication styles adaptative to their way of being. Many children go along easily with others' principles. They represent these accomodations as dependence and tuning. Or they refuse or neglect others. The result is that such attitudes are not the essence of the problems but only symptoms and that we have to pay attention to the anxiety of being themselves. Therefore it is important for us to accept their being.
1 0 0 0 OA 成城小学校におけるドルトン・プラン受容をめぐる対立の構造
- 著者
- 足立 淳
- 出版者
- 日本教育方法学会
- 雑誌
- 教育方法学研究 (ISSN:03859746)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.105-115, 2010-03-31 (Released:2017-04-22)
本研究は,成城小学校における教育方法改革の史的再検討の一環として,同校におけるドルトン・プラン受容をめぐる対立の構造を明らかにすることを目的とする。これまで一般的に,成城小においてドルトン・プランは,同校でそれまで独自に実践されていた自学法と高い親和性をもつ教育法として受容されたと理解されてきた。しかしながら,近年,新たな知見が提出されており,成城小の自学とドルトン・プランとが,同校の人びとが理解したように必ずしも一致するものではなかったことが示唆されている。このことを念頭において成城小におけるドルトン・プラン受容に貢献した主要な人物たちの言説を検討してゆくと,実際には,彼らのなかにドルトン・プランに対する異なる見解が存在したことに気づく。そこで本研究は,まず,沢柳政太郎の自学論の内実を検討し,成城小における自学の背景についてみた。次に,奥野庄太郎と赤井米吉の言説を対比的に分析することで,彼らのドルトン・プランに対する見解が異なるものであったことを論じた。そして,両者の見解の相違が,単なるドルトン・プランの解釈上の違いにとどまるものではなく,教育の目的観の対立構造に根ざすものであったことを明らかにした。
- 著者
- 水野 正朗
- 出版者
- 日本教育方法学会
- 雑誌
- 教育方法学研究 (ISSN:03859746)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.1-12, 2009-03-31 (Released:2017-04-22)
本論文では,文学テクストを教材とした国語の授業において,児童生徒から提出される多様な解釈をどのように扱うべきかという問題を,現代文学理論や記号論を手がかりに理論的に検討した。その結果,イーザーの読書行為論から,文学テクストは多様な解釈への潜在的な可能性を持つが,その可能性の幅はテクストに内在する戦略によって一定の幅に制限されていること,エーコの記号論から,文学テクストは文化的・社会的共同体における間主観的な合意の原理によって意味が規定されること,フィッシュの「解釈共同体」の理論から,解釈間の相互規定関係が重要であることが示唆された。さらに,スコールズの文学教育理論から,広義の「読み」のプロセスの中に「読むこと」「解釈」「批評」という3層が含まれ,それらが相互にかかわり合いながら,読みを動的に発展させていくことが示された。学級という学習共同体のなかで営まれる読みにおける個人思考と集団思考の関係は,必要となる読みの課題の特性によって動的に変化しつつ発展する。児童生徒と教師が,多様な解釈の可能性を前提にして討論することで,個々の認識を包含しつつ高いレベルで調和した読みが社会的に構成される。そして,その共同体内で開示され共有されたテクストの経験が,学習者の経験の蓄積に組み込まれることで,学習者それぞれの自己発見や自己変容を誘い,一人ひとりの主体的な読みを開くのである。
1 0 0 0 OA 現代における「訓育的教授」の実践課題 : 陶冶論・訓育論・制度論の統合の試み
- 著者
- 住野 好久
- 出版者
- 日本教育方法学会
- 雑誌
- 教育方法学研究 (ISSN:03859746)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.57-66, 1994-03-31 (Released:2017-04-22)
- 被引用文献数
- 1
"The educative Instruction", presented by J. F. Herbart in 19th century, has been pursued als what instruction is till these days, though it was misinterpreted by Herbartians. But today, some problems concerning the educational praxis in schools undermines the existential basis of the school as the educational institution, and requests the reexamination of modern educative instruction theory. So, in this paper, the educative instruction, which has been examined only from instructional and educative viewpoint, is added to the investigation from the viewpoint of the school and institutional theory. For this purpose, at first, I investigate the theory of Herbart who developed the study of the educative instruction from the viewpoint of the school and institutional theory in the turningpoint from the feudal society to civil society in 19th century, and through critical succeeding his modern educative instruction theory, determine the practical problem of the educative instruction in these days. Today, I'm sure, it is possible to realize the educative instruction, only when we take up the paradigm of the integration of instructional, educative and institutional theory.
1 0 0 0 OA イギリスのドラマ教育における「専門家のマント」の展開
- 著者
- 渡辺 貴裕
- 出版者
- 日本教育方法学会
- 雑誌
- 教育方法学研究 (ISSN:03859746)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, pp.15-26, 2015 (Released:2017-07-19)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
「専門家のマント」とは,専門家の役になった学習者が架空の依頼を受け,その課題に取り組む活動を通してさまざまな内容の学習を行うという手法である。この手法は,日本では,授業において用いることができる一つの技法という認識が一般的であった。しかし,この手法を発展させたドロシー・ヘスカットにとって,これは,カリキュラムの再構成をも伴う,より大きな可能性をもったものであった。ヘスカットが考える「専門家のマント」は,まず,単発ではなく複数回の授業を必要とするもので,また,常に教科横断的な学習を想定するものである。ヘスカットは,専門家の役になる際の間接性を重視する。また,架空の設定には「事業」「依頼人」「問題」という要素が必要であり,「事業」の確立が保障されなければならないとする。 ヘスカットが考えていたこうした「専門家のマント」の可能性は,2000年代に入ってからの,学校全体の規模でのこの手法への取り組みの出現により,実現した。ビーリングス小学校やウッドロー小学校はその一例である。これらの学校では,「専門家のマント」を通した教科横断的な学習が,カリキュラムの主要部分として組み込まれている。こうした新たな展開を支えたのが,ルーク・アボットと,彼が中心となって設立したMoE ドットコムというネットワーク組織である。アボットおよびこの組織はウェブサイトの運営や研修機会の提供を通して,この新展開に貢献している。
1 0 0 0 OA リテラシー形成理論における「批判」概念と実践構想の比較検討
- 著者
- 竹川 慎哉
- 出版者
- 日本教育方法学会
- 雑誌
- 教育方法学研究 (ISSN:03859746)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.13-24, 2004-03-31 (Released:2017-04-22)
本研究の目的は,リテラシー形成理論と実践構想の比較検討をとおして,リテラシー形成における「批判」の意味を考察することにある。ここでは,アメリカにおいて,相互に議論を交わしている批判的思考論文化的リテラシー論そして批判的リテラシー論をとりあげる。リテラシー形成理論において,「批判」という言葉は多義的である。批判的思考論において,批判的であるということは,客観的・論理的・政治的に中立的になっていくことを意味し,それを支えるスキルの獲得が何より重視される。文化的リテラシー論は,アメリカ国民として政治的・文化的に生活するために必要な選ばれた知識の獲得が,批判的な思考を可能にすると強調する。しかし,前者において,スキルの強調は,学ぶ内容の無視へとつながり,学問の境界や支配的文化に無批判になってしまっている。そして,後者においては,ナショナル・アイデンティティとしての共通知識の強調が支配的文化への同化を促すものになっている。それらと対照的に,批判的リテラシー論によれば,「批判」とは,個人の私的な問題とされるものを社会構造の公的な問題として位置づける意識を持ち,その関係を問い直すこととして理解されている。さらにそれは,文化の差異性やこれまで排除されてきた他者のF声」に対する応答も含むものである。このような政治的かつ倫理的な意味において,「批判」がリテラシー形成に組み込まれることが求められている。
- 著者
- 渡部 竜也
- 出版者
- 日本教育方法学会
- 雑誌
- 教育方法学研究 (ISSN:03859746)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.85-96, 2004-03-31 (Released:2017-04-22)
本研究の目的は,社会問題学習には,科学主義社会科の延長上に位置付く実在型社会問題学習と,科学主義社会科とは別の観点から生み出された唯名型社会問題学習の二つが存在することを踏まえつつ,なぜ,合衆国の社会科教育において,今日後者が注目されるのか,その原理的説明を試みることである。この目的を達成するために,(1)科学主義社会科に向けられた批判にはどのようなものがあり,(2)唯名型(ここでは特にハーバード社会科に注目する)はその問題点をどのように克服しているのか,を明らかにする。本研究で導き出された科学主義社会科の問題点4つのうち主なものと,それに対する唯名型社会問題学習の克服手法を示すと,以下のようになる。1)科学主義社会科の問題の第一は,多様にある学説の中からどれを教えればよいのか,内容編成の基準を明確に示せない点にある。唯名型社会問題学習は,多種多様な見解を持つ人間の論争に注目するので,対立する学説・見解を,時間の許す限り全て授業に持ち込むことができ,この問題を克服できる。2)問題の第二は,この社会科が事実上ある研究者の見解の教え込みをする学習になっている点にある。唯名型社会問題学習は,論争を通して多種多様な見解を比較するために,それらの見解同士を対象化して見ることができるので,これを克服できる。
- 著者
- 進藤 聡彦
- 出版者
- 日本教育方法学会
- 雑誌
- 教育方法学研究 (ISSN:03859746)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.95-105, 2003
社会科の歴史領域は暗記科目などと言われることがある。このことから,多くの学習者は機械的な暗記による学習方略を採用していると考えられる。そして,そのような学習方略の採用は,学習項目間の繋がりを欠き,有意味性を感じにくくさせるために,学習者にとっておもしろい学習とはなりにくいと予想される。そこで,調査Iでは歴史学習の好悪と学習方略の関連が調べられた。その結果,歴史の学習が好きだったとする者は嫌いだったとする者に比べて,メタ認知的な学習方略を採用していることが明らかになった。このことは,機械的な暗記による学習方略が歴史の学習を嫌いなものにすることを示唆する。学習者に歴史学習をおもしろいものとして捉えさせるための方法として,知識の構造化による有意味化が有効だと考えられる。そして,構造化のための前提として疑問が生成されることが必要だと推定される。すなわち,断片化された知識の関連についての不十分な知識は,疑問という形で意識される必要があるからである。こうした観点から,調査IIでは疑問の生成を保証するのは理解のモニターや既有知識との関連をつけようとするようなメタ認知に関わる学習方略の採用だとする仮定の下に,疑問の生成能力とメタ認知能力の間の関連が探られた。その結果,疑問の生成能力とメタ認知能力の間に相関関係が確認され,メタ認知的な方略の育成が構造化された知識の前提になり,そのことが知識の構造化による歴史学習の有意味化につながると考察された。
- 著者
- 石井 英真
- 出版者
- 日本教育方法学会
- 雑誌
- 教育方法学研究 (ISSN:03859746)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.47-58, 2003
本稿は「改訂版タキソノミー」(以下「改訂版」と略す)に関する論稿である。「改訂版」は,かつてブルーム(B. S. Bloom)らによって開発された「教育目標の分類学」(以下ブルーム・タキソノミーないしは初版)の認知領域を改訂したものである。本稿では,初版との比較を通して「改訂版」の意義を探った。まず,本改訂における変更点について考察した。そして,特に注目すべき構造上の変化として,知識と認知過程の二次元構成を取り上げ,その中身について論じた。次に,初版の意義と限界を明らかにするために,初版における目標構造化の論理(タキソノミーの構造に内在している授業改善の方向性)を抽出し,その背後にある学習観についても検討した。最後に,「改訂版」の学習観と目標構造化の論理について分析を加えた。以上より,次のようなことが明らかになった。初版と「改訂版」との間には,学習観における重大な差違があり,「改訂版」の学習観(構成主義,領域固有性)は,初版の学習観を転換させるものである。そして,この学習観の転換がカテゴリー構成のレベルで具体化された結果,「改訂版」は初版にはない二つの視点(知識習得の質を問い直す回路,高次の認知目標を支える知識を問う回路)を生み出している。こうして,初版から「改訂版」への改訂は,目標構造化の論理を再構築する過程として捉えることができるのである。
1 0 0 0 OA 学習者の自生的な誤りの修正に関する教授-学習心理学的研究
- 著者
- 進藤 聡彦
- 出版者
- 日本教育方法学会
- 雑誌
- 教育方法学研究 (ISSN:03859746)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.57-64, 1993-03-31 (Released:2017-04-22)
On evaluating teaching-learning processes, it is effective that learners' recognition and teaching materials are able to be expressed one-dimensionally by using the ruleg system. Especially ru, a constituent of the ruleg system, is a key concept in considering the reformation of erroneous criteria. Ru is a learner's judgement criterion and it is erroneous and autogenetic in its characteristic. In the first section, the characteristics of various kinds of ru's are explained with some concrete examples. In the second section, the instructional strategies of reforming ru's are discussed from a point of view of the presentation sequences of focus instances. Two different presentation sequences are taken up. One is what shift from focus instances learners misjudge as exceptions to these they can recognize as correct instances. Another is what is in the reverse order. The effectiveness of the instructional strategy, which take the grounds of learners' ru's into consideration, are also discussed in this section. In the third section, it is described that learners are not aware of the attributes in themselves or the value of attributes which they use as foundation of their judgements on ru's. This thing occasionally causes learners the formation of a kind of ru's, which they apply the correct rule only to a limited extent. The instructional strategy, which makeslearners form the instances they misjudged as the exceptions for themselves and verify them, brings effects on reforming this sort of ru's.
- 著者
- 楠見 友輔
- 出版者
- 日本教育方法学会
- 雑誌
- 教育方法学研究 = Research journal of educational methods : 日本教育方法学会紀要 (ISSN:03859746)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.25-36, 2020
- 著者
- 楠見 友輔
- 出版者
- 日本教育方法学会
- 雑誌
- 教育方法学研究 (ISSN:03859746)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.49-59, 2018
<p>本稿では,社会文化的アプローチの視点から学習者の主体性に基づく教授と授業のあり方についての議論を行った。社会文化的アプローチにおける学習者の「媒介された主体性」という概念は,個人の有能さではなく,文脈や環境に埋め込まれた主体の意思や行為する力を示すものである。このような観点からは学習者を同質的な主体性を有する集団と捉えたり,教師の教授と学習者の学習を対立的に捉えたりする見方は否定され,授業が教師と個々の学習者の主体性による複雑な相互活動の過程とみなされる。学習者と教師の主体性の関係の二者択一を解消するために重要となるのが教師の教授におけるコンティンジェンシーである。コンティンジェンシーへの注目は学習者の主体性を教師の教授の起点とし,学習者の主体性の発現を促し,授業に学習者の生活世界の文脈を導入することを可能にすることが示された。個々の学習者と教師が授業において主体として相互活動を行うためには授業を対話的構造に転換することが必要であると言われている。筆者は主体性に基づく教授と授業を行うためには,授業の具体的文脈における学習者の主体性に基づき,個々の学習者の主体性が実現されるような多様な教授や授業の方法や形式について議論することが必要であることを指摘した。</p>
1 0 0 0 OA 山本宣治の「人生生物学」講義の意義と限界 : 学生のレポート分析を通して
- 著者
- 柴本 枝美
- 出版者
- 日本教育方法学会
- 雑誌
- 教育方法学研究 (ISSN:03859746)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.121-132, 2006-03-31 (Released:2017-04-22)
日本において性教育に関する議論がなされるようになったのは,明治末期のことである。以降,公娼制度や性病蔓延の問題など性に関する問題が社会問題として顕在化するに従って,性教育の必要性が論じられるようになった。本稿で検討する山本宣治(1889-1929)は,同志社大学予科において,「人生生物学」と名づけた性教育を実践していた人物である。本稿では,当講義で与えられていた評価課題を検討し,受講生が作成したレポートを分析することを通じて,実践としての「人生生物学」講義の意義と限界を明らかにする。山本が講義の目的としたのは,学生が自らの人生に対する理解を深めるための科学的な知識を提供することであり,人生に関係の深い分野の知識を選択し,排列して講義を進めていた。講義において山本は,レポートと筆記試験で評価を行っている。レポートでは,学生が文献に示されている理論を読み込むことで,まずは科学的な知識を習得することが期待されていた。実際に学生が書いたレポートの大半は,遺伝学や進化論,科学概論の文献を要約あるいは一部抜粋したものであり,山本がめざしていた「推理思索法」が必ずしも実現されていたとはいえない。しかし,文献を読み科学に対峙している点では,山本が「人生生物学」講義でめざした性教育における第一段階の目的,つまり性に関する科学的な知識を与えることは実現されていたと評価することができる。
1 0 0 0 OA 教室における科学的認識の構成過程 : ドライバーの「文化的道具」を中心に
- 著者
- 村瀬 公胤
- 出版者
- 日本教育方法学会
- 雑誌
- 教育方法学研究 (ISSN:03859746)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.29-37, 2000-03-31 (Released:2017-04-22)
Referring to findings of sociology of science, R. Driver and her colleagues identified both a community of science learners and a community of scientists with a scientific community, which constructs scientific knowledge. From this perspective they defined learning science as a process of "enculturation" using scientific knowledge as "cultural tools". But their concept of "enculturation" has difficulty in analyzing the reciprocal process of constructing scientific recognition at classroom. To overcome that difficulty, this paper aims to reconceptualize "cultural tools" and to understand the reciprocal process in the classroom referring to the J. V. Wertsch's analysis of science classroom. In Wertsch's analysis, one student appropriated her peers' utterances to make her own utterance and other students also did same. These sequential appropriation is essential to make meaning. Thus "cultural tools" are also to be appropriated sequentially because the scientific community evolves scientific knowledge day by day. The process of constructing scientific recognition should be regarded as a sequential and reciprocal process.
- 著者
- 石井 恭子
- 出版者
- 日本教育方法学会
- 雑誌
- 教育方法学研究 (ISSN:03859746)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, pp.35-45, 2012
本研究は,日本の理科教育における「探究の過程」の導入とその問題点を明らかにするためにアメリカの改革プログラムが日本に導入された経緯を当時の文献を基に検討したものである。2008年の答申では,知識・技能の育成と考える力の育成が対立的にとらえられてきたが,これらを相互に関連させながら伸ばすことが重要とされ,特に理科教育においては,系統学習と探究(問題解決)学習の対立が常に論じられながら今日に至っている。これは,教育の現代化と呼ばれた1960年代,「探究」や「科学の方法」ということばを表面的に受容したことに原因があると言われている。そこで本研究では,主として1960〜70年代の「探究の過程」受容の経緯と問題点を,アメリカの科学教育改革の導入,特に「現代化」という視点から検討する。研究の方法としては,当時の日本の理科教育雑誌等における言説分析による。特に学習指導要領の執筆に関わった人物の言説に注目する。その結果,以下の三点が明らかになった。第一に,現代化の導入に際して,知識偏重教育の否定と子どもの自発性を強調するあまり,教師が教え込まずに子どもが理解することをめざすという趣旨が,教師は教えなくてよいという論調に変化したことである。第二に,紹介から導入までの時間が短く,十分な検討ができなかった点である。第三に,実践研究の知見がカリキュラム編成に生かされなかった点であり,教育課程編成のあり方の課題でもある。