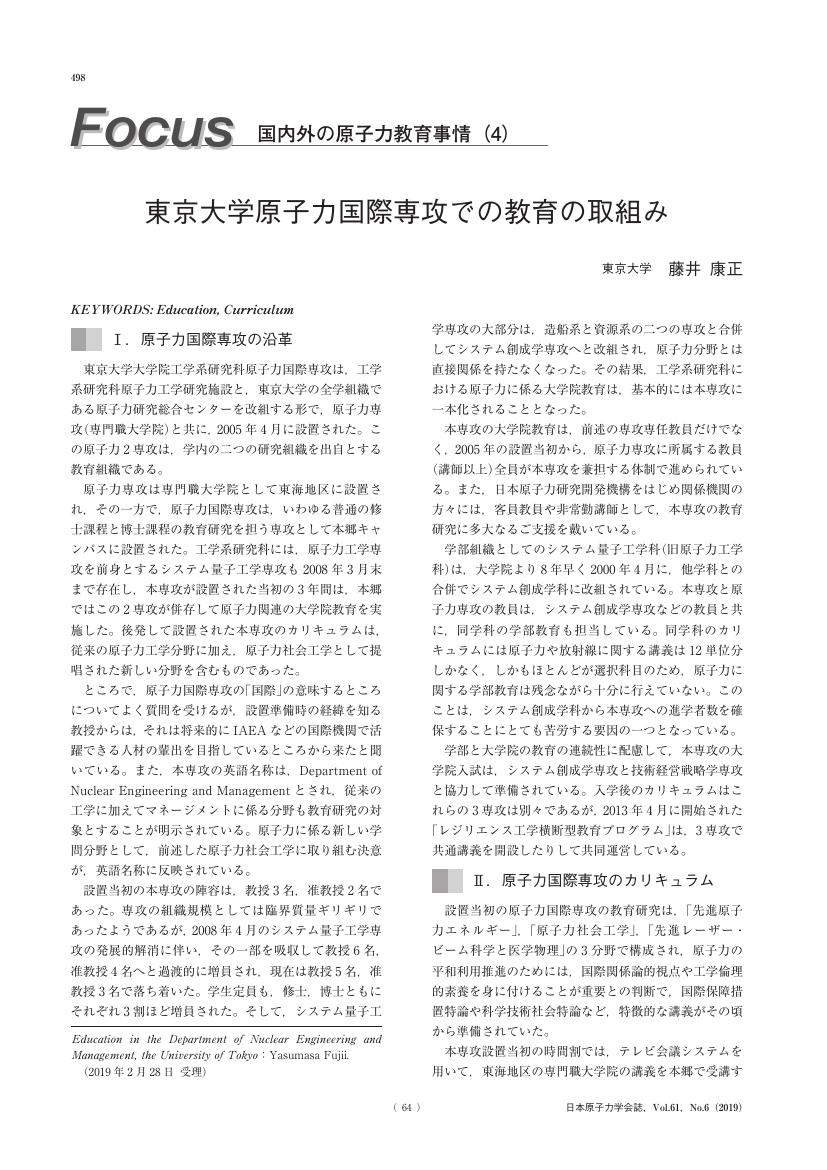1 0 0 0 グレタ・トゥーンベリさんの国連スピーチに対する各国の医学生の反応
- 著者
- 妹尾 優希
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.29_2, 2020
- 著者
- Dunzik-Gougar Mary Lou
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.8, pp.561-562, 2021
1 0 0 0 今後の研究開発に関する視点
- 著者
- 藤田 玲子
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.7, pp.509-510, 2021 (Released:2021-07-10)
- 参考文献数
- 7
1 0 0 0 OA 電力系統の安定運用のために 再生可能エネルギー大量導入時の基幹系統への影響
- 著者
- 北内 義弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.7, pp.535-539, 2019 (Released:2020-04-02)
- 参考文献数
- 2
電力系統の安定運用のためには,系統セキュリティの維持が重要である。本稿では,まず交流送電と発電機および系統セキュリティを維持するために必要な三つの要素(周波数,電圧,系統安定度)について概説し,大容量発電機の系統セキュリティへの貢献について述べる。さらに大容量電源脱落時の周波数低下および再生可能エネルギー発電大量導入時の電力系統の系統安定度に与える影響について,電力系統シミュレータを用いた試験結果について紹介する。
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3, pp.217, 2012
- 著者
- 澤田 哲生
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.1-2, 2021 (Released:2021-02-10)
1 0 0 0 OA 米国原子力発電シンポジウムから学ぶ
- 著者
- 尾本 彰
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.5, pp.256-257, 2013 (Released:2019-10-31)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 小型モジュール炉(SMR)を巡る国際動向とそのインパクト
- 著者
- 田中 隆則
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.7, pp.382-386, 2018
<p> 近年,海外において小型モジュール炉(SMR)の開発に向けての様々な取り組みが行われている。特に,米国,英国,カナダにおいては,政府も積極的に開発を支援する動きがみられており,IAEAやOECD/NEAなどの国際機関においても,SMRに関連する報告書が取りまとめられるなど,国際的にSMRへの関心が高まっている。このようなSMRの特性を分析し,今後,世界のエネルギー需給に与える影響を考察する。</p>
1 0 0 0 OA 国内外の原子力教育事情(4) 東京大学原子力国際専攻での教育の取組み
- 著者
- 藤井 康正
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.6, pp.498-499, 2019 (Released:2020-04-02)
1 0 0 0 OA 米国における燃料破損ゼロ化活動
- 著者
- 黒崎 健 山中 伸介
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.6, pp.449-450, 2011 (Released:2019-09-06)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 拡大している中国原発及び海外進出
- 著者
- 郭 四志
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.12, pp.752-753, 2014
1 0 0 0 OA 広島,原爆投下(その1) トルーマン声明
- 著者
- 中根 良平
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.12, pp.895-896, 2009 (Released:2019-06-17)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA 内部被ばく実験棟とプルトニウム内部被ばく研究<一研究者の回想録>
- 著者
- 小木曽 洋一
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.5, pp.350-355, 2015 (Released:2020-02-19)
- 参考文献数
- 2
福島第一原発の事故以降,全国の原発は全て停止し,再稼働に向けた動きも始まっているが,容易ではない状況にある。また,我が国の原子エネルギー政策の基幹である核燃料サイクルは稼働できない状態が長きにわたって続いている。原子力産業が右肩上がりであった1980年代から90年代にかけて,核燃料サイクルの中心に位置づけられるプルトニウムの生物影響リスクを評価するために,我が国で初めての動物実験施設「内部被ばく実験棟」が放射線医学総合研究所に建設され,実験研究が行われた時期があった。その一翼を担った研究者の立場から,実験棟の設計,建設,運用に携わった経緯を織り交ぜながら,プルトニウムを実験動物に吸入曝露あるいは注射投与して発がんのリスクを評価する研究を進めていった体験を概説する。
1 0 0 0 OA チェルノブイリから25年 クルチャトフ研究所 ベリホフ総裁 レベル7の事故を語る
- 著者
- 桜井 久子
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.10, pp.701-702, 2011 (Released:2019-09-06)
平成23年6月中旬,日本原子力産業協会は協力協定を有するロシア国立研究センター「クルチャトフ研究所」のエフゲニー・パーブロビッチ・ベリホフ総裁(=写真)が来日したのを機に,東京都内で「チェルノブイリ事故から25年―福島第一原子力発電所事故への教訓」と題する講演会を開いた。4号機の事故の収束に大きな力を発揮した同研究所の実績を紹介するとともに,「チェルノブイリ原発事故は原子力産業の発展のみならず多方面に影響を及ぼした。が,事故に備え,対策を講じることは事故前にもできたはずである」と述べ,国際原子力事象尺度(INES)でレベル7を記録した同事故を述懐した。
1 0 0 0 感謝をこめてもてなす「復興五輪」
- 著者
- 服部 美咲
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.7, pp.377_2, 2020
1 0 0 0 OA LNT再考 放射線の生体影響を考える
- 著者
- 真鍋 勇一郎 中村 一成 中島 裕夫 角山 雄一 坂東 昌子
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.11, pp.705-708, 2014 (Released:2020-02-19)
- 参考文献数
- 15
マラーのショウジョウバエの実験以後,放射線のリスクは,総線量で決まることが示され,LNT(直線しきい値なし(仮説))が放射線防護の基礎となった。しかしながら,後にラッセルらによって,線量率効果の存在が示された。これらの異なった種に対する結果を,統一的に理解し,それをヒトまで援用する手法として数理モデルを提案する。更にスケーリング則を導入すると,様々な種の実験データを統一的に理解できる。これは放射線リスク評価に新しい知見を加えるだろう。
1 0 0 0 OA みんなでわかろうシリーズ クロスカップリング入門 基本的な考え方と応用
- 著者
- 秋山 勝宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.7, pp.499-502, 2011 (Released:2019-09-06)
- 参考文献数
- 5
「パラジウム触媒によるクロスカップリングの発展への寄与」の功績により根岸英一,鈴木 章,R. E. Heck先生らが2010年にノーベル化学賞を受賞した。クロスカップリングは1970年代から盛んに研究され,有機合成ではこの分野は日本のお家芸といえるほど,日本人の貢献が大きい。今回はクロスカップリングについて,その基本的な知識や考え方を解説する。まず総論としてクロスカップリングの反応形式や反応機構について説明し,医薬品やエレクトロニクス材料への用途について述べる。各論として代表的な反応である熊田―玉尾カップリング,根岸カップリング,鈴木―宮浦カップリングと溝呂木―Heck反応について反応の特徴や問題点について解説する。最後に,最近の研究として固定化触媒の開発や安価な鉄触媒を使用する研究を紹介する。
1 0 0 0 OA 新型コロナウイルスとスロバキア
- 著者
- 妹尾 優希
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.8, pp.436_1, 2020 (Released:2021-02-01)
1 0 0 0 OA 論点「原子力」を考える 自然エネルギー発電の可能性と限界 過大な期待への警告
- 著者
- 林 勉
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.91-96, 2012 (Released:2019-10-31)
- 参考文献数
- 4
わが国の自然エネルギー発電はどれだけ有効かについて,導入目標,導入可能ポテンシャル等から評価したが,最大導入可能量は総発電量の15%ぐらいが限度であることを示した。現実にはこれを達成するためには高いハードルがあることおよび自然エネルギーを導入する上での様々な問題点やドイツの例も踏まえた政策上の問題点についても考察した。電源別構成は当面,原子力,火力,水力が主体であり続けるというのが結論である。
- 著者
- 遠藤 哲也
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.9, pp.561-567, 2014
<p> レーガン政権の下でようやく始まった日米原子力協定交渉は難航した。米側は,日本の原子力活動に包括事前同意方式を認めることには同意したものの,具体的な個々の点については厳しく,また行政府部内でもさまざまな異論が出てきた。何とか正式に署名にこぎつけたものの,その後の議会審議は波乱の連続であった。</p><p> プルトニウム空輸に対するアラスカ州からの反対,核不拡散強硬派からの反対などで審議は予断を許さなかった。この波瀾を何とか乗り切ったのは,レーガン大統領の決断,レーガン・中曽根の信頼関係によるところが大きかった。この協定が発効したのは,1988年7月であり,正式交渉が始まってから6年もの年月が経っていた。</p>