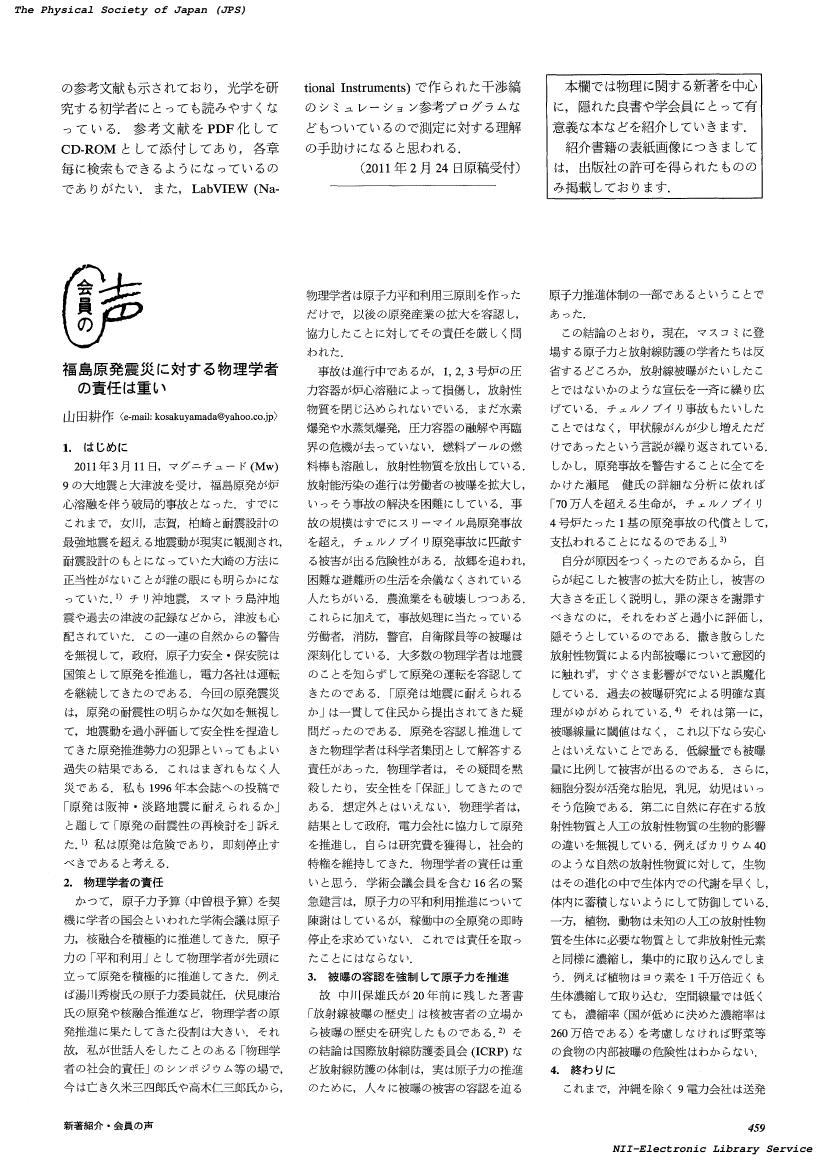1 0 0 0 OA 福島原発震災に対する物理学者の責任は重い(会員の声)
- 著者
- 山田 耕作
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.6, pp.459-460, 2011-06-05 (Released:2018-08-08)
1 0 0 0 OA 1軸性ひずみによる物性制御
- 著者
- 鹿児島 誠一 前里 光彦 加賀 保行 近藤 隆祐
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.12, pp.969-974, 1999-12-05 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 17
さまざまな物性が演じられる舞台は, 原子や分子の配列が作る物質構造である. これを変化させる新たな手段として, 1軸性ひずみの方法を開発した. 装置の基本構造を示し, これによって作られる物質のひずみが1軸性であることを検証する. 実際の研究への適用例として, 2種類の2次元性有機導体の電子状態に与える1軸性ひずみの効果を紹介する. 有機導体に限らず多くの物質において, 1軸性ひずみは, 静水圧や従来の1軸性加圧では実現できない新たな物質構造をもたらす. この実験手法によって, 新規な物性の発見が期待できる.
1 0 0 0 OA 階層構造なしに生物を理解することはできない (<特集>『階層のある系の物理学』)
- 著者
- 美宅 成樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.4, pp.255-262, 1995-04-05 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 12
私たち自身が生物なので,その構造の複雑さについては誰でもある程度は知っている.実際,生物は大変複雑で,深い階層構造を持っている.ここでは,生物を特徴づける三つの側面について述べ,その最も重要な階層構造について話をすすめる.そして,階層構造の例として,筋肉の構造,神経系の構造を簡単に紹介した後,生体高分子の構造形成と,細胞集団がつくる高次構造のメカニズムを議論する.
1 0 0 0 OA 強磁性体における核磁気共鳴
- 著者
- 長岡 洋介
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.162-163, 1960-03-05 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 7
- 著者
- 長岡 洋介
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.124-125, 1998-02-05 (Released:2019-07-05)
- 著者
- 長岡 洋介
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.7, pp.537-538, 2001-07-05 (Released:2019-04-12)
1 0 0 0 OA グラフェンにおける巨大な軌道反磁性(最近の研究から)
- 著者
- 越野 幹人
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.1, pp.21-25, 2010-01-05 (Released:2020-01-18)
- 参考文献数
- 27
近年,単層のグラファイトであるグラフェンが実験的に作成されその性質が大きな注目を集めている.本稿ではグラフェンの軌道反磁性に関する最近の研究を紹介する.ギャップの無いバンド構造に起因して,グラフェンの反磁化率は通常の物質と比較して非常に異なり,それにより1原子層からなる物質にも関わらず巨視的な力を生ずることを見る.
1 0 0 0 中間子論誕生記念碑建立始末
- 著者
- 谷川 安孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.223-226, 1986
1 0 0 0 宇宙からの謎の電波突発現象,高速電波バースト(最近のトピックス)
- 著者
- 木坂 将大
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.9, pp.600-601, 2014
- 著者
- 國枝 秀世
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.12, pp.925-932, 2001
「あすか」の一番大きな特徴は, 初めて10keVまでの撮像観測ができたことである.2-10keVのエネルギー帯域でこれまでの「ぎんが」に比べ2桁高い感度が実現され, 遠方の暗い銀河まで観測可能になった.高いエネルギーの観測では, 吸収体に隠された天体も検出でき, 近傍の銀河に潜む活動的銀河核も次々見つかった.「あすか」のもう一つの特徴は焦点面に置かれたCCDカメラによる分光である.スペクトルに見られる吸収構造, 輝線構造を分光することで, 大質量ブラックホールを持つ活動的銀河核近傍の, 強い重力場と強い放射場における物理現象が明らかにされた.この問題は, 最近観測を始めたChandra, Newtonの二大X線天文衛星でさらに大きく展開されようとしている.またもう一歩踏み込んだ研究にはAstro-E2の登場が待たれる.
1 0 0 0 ブラックホール磁気圏
- 著者
- 高橋 真聡 冨松 彰
- 出版者
- 一般社団法人日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.10, pp.835-842, 1991
- 被引用文献数
- 3
クエーザーやセイファート型銀河などに分類される活動的銀河は, 中心核領域から相対論的速度でプラズマのジェット流を放出するなど, 非常に激しい活動性を示しています. この活動性のエネルギー源を説明するものとして, 超大質量のブラックホールの存在が強く示唆されています. その強重力はプラズマを集積し, 磁気圏を形成しますが, この磁気圏はブラックホールの回転エネルギーを抽出する窓口として重要な機能を担っていることが理解されるようになってきました. 本解説では, ブラックホール磁気圏の構造とはどのようなものか, ブラックホールと電磁場とプラズマの相互作用によってどのような物理過程が起こるのかについて解説します.
1 0 0 0 OA 反磁性原子の電気双極子モーメントで探る新物理
- 著者
- 山中 長閑 吉永 尚孝 旭 耕一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.6, pp.382-387, 2018-06-05 (Released:2019-02-05)
- 参考文献数
- 15
夜空に輝く星々や我々人間を構成する電子と原子核,つまり物質は実際宇宙の主成分の一つをなしている.しかしながらそもそも宇宙に物質が多く存在し反物質がほとんど存在しない,というこの一見当たり前の事実は,実は非自明な現象である.CP対称性とよばれる対称性の破れがあってこその現象なのであり,観測から導かれる物質の量は,素粒子物理の標準模型に組み込まれたCPの破れで説明できる量をはるかに超えている.加えて宇宙には,標準模型内の粒子ではないと考えられる粒子(暗黒物質)や未知のエネルギー(暗黒エネルギー)が存在する.標準模型は現在までに地上で行われた加速器実験の結果のほとんど全てを説明する強力な素粒子物理模型であるにもかかわらず,その奥に私たちの知らない新しい物理が控えているのではないかと,多くの研究者が期待を胸に新物理の探索に挑戦している.新物理の候補のうち,多くの研究者に有望視されていた電弱スケールの超対称標準模型は,超対称粒子が期待される質量領域に見つからないことから最近その特別な地位を譲りつつある.新物理の解明へのこれまでの指針が変更を余儀なくされ,次第に新物理の証拠探しはエネルギーを上げた加速器実験によって新粒子の直接検出を目指す「エネルギーフロンティア」から,標準模型で禁止されているはずの物理過程に新物理の効果を探索する「超精密フロンティア」へと,その重心を移しつつある.この際に鍵となるものの一つは上述のようにCPの破れである.スピン方向に沿って定常的に生じた粒子の電気分極を電気双極子モーメント(Electric Dipole Moment, EDM)と呼ぶ.EDMはスピンに沿って定義されているのに,空間反転と時間反転に関してスピンとは異なる変換性を示すという奇妙な物理量.時間反転に関するこの性質は,CPT定理を通じてEDMがCP対称性の破れに関係する観測量であることを物語っている.新物理は標準模型とは異種のCPの破れを含むはずである.標準模型のCPの破れはフレーバー混合に関わるものであるため,フレーバー対角な観測量であるEDMには低次で現れず,観測にかからない.もし実験で大きな値のEDMが見つかったなら,それは間違いなく新物理に由来するものである.EDMの研究は現在,スピンを持つ様々な粒子―中性子,反磁性原子,常磁性原子,ミュオン,陽子・重陽子―を対象に世界中で探索実験が実施または計画されている.理論的にも検討が進み,これら異なる粒子のEDMがそれぞれどのような新物理に感度を持っているのか,それらの実験データが得られた時にどのような解析をすればよいのかもわかってきた:各々の新物理が生み出すCP非保存相互作用は低エネルギーでは限られた個数のパラメータで表され,これらのパラメータはハドロン物理・核物理・原子物理の過程を通じて様々な素粒子・複合粒子にEDMを生じさせる.これを逆に辿ると,測定されたEDMから各パラメータの値が求められ,その値が新物理の存在の証拠を与えることとなる.我々は,キセノンや水銀などの反磁性原子のEDMが素粒子からハドロン,原子核,原子の各階層を繋げて新しい物理を解明する際に持つ感度を明らかにしてきた.こうして今後実験の進展によりEDMが,それもただ一例ならず決定されるようになれば,提案されているいずれの模型が描く新物理が実際に現れるのかを判別する道が拓かれることになる.
1 0 0 0 OA 平川浩正教授を悼む
- 著者
- 西川 哲治
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3, pp.286-287, 1987-03-05 (Released:2020-04-16)
1 0 0 0 機械学習によるハミルトニアン推定
- 著者
- 田村 亮 長谷 正司 福島 孝治
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.10, pp.652-657, 2021-10-05 (Released:2021-10-05)
- 参考文献数
- 11
「物質のハミルトニアンを知りたい」,物性研究者なら誰でも思うことだろう.しかし,対象物質の実験結果を説明できるハミルトニアンを構築するのは,一筋縄にはいかない.ハミルトニアンの関数系,含まれるパラメータ値を決定するためには,多くの試行錯誤が必要となるためである.この煩雑な作業を回避するにはどうしたらよいだろうか.近年注目されている機械学習をはじめとしたデータ駆動手法の利用が一つの道筋だろう.我々は機械学習を利用することで,実験・観測データからハミルトニアンを推定する手法を開発した.ハミルトニアンを推定するために,実験データが与えられた際のハミルトニアンの事後確率を定義する.ベイズ推定を利用することで,この事後確率は,ハミルトニアンが与えられた際の測定ノイズを含めた実験データの尤度(計算物質科学手法により評価可能)および事前分布で表すことができる.事前分布は,推定するハミルトニアンに対する事前知識を表し,推定対象に適した分布を導入する必要がある.このようにして定義された事後確率を最大とするハミルトニアンが最も実験・観測データを説明できると推定される.しかしながら,この事後確率の最大条件探索は,使用する計算物質科学手法によっては簡単ではない.あるパラメータの組における事後確率の値は,対象とする物理量を計算物質科学手法により評価することで得られる.そのため,計算に時間がかかる場合,最大条件を見つけるのは困難である.これを克服するために,機械学習が使える.機械学習を利用することでできるだけ少ない試行回数でよりよい条件を探索することができるベイズ最適化を,事後確率の最大条件探索に利用した.テストケースとして,1次元量子スピン系に対して適用した.ベイズ最適化を用いることで,物理学でよく利用されるマルコフ連鎖モンテカルロ法や勾配法よりも物理量の計算回数が少なくても,よりよい最大条件を見つけ出せることがわかった.一方で,ベイズ最適化を用いると実験データを説明できるハミルトニアンを高速に導出することはできるが,事後確率の最大条件だけでは,観測ノイズを見積もることはできない.そこで,マルコフ連鎖モンテカルロ法によって事後確率を詳しく解析することで観測ノイズを求め,推定されたハミルトニアンに誤差をつける手法を開発した.このように開発された手法の有用性を示すために,実際の実験系への適用として,低次元量子スピン系KCu4P3O12に対して高磁場測定で得られた磁化過程および帯磁率の実験結果から,スピンハミルトニアンを推定した.その結果,推定されたスピンハミルトニアンは,実験データをよく再現できた.また,磁気的相互作用の誤差も見積もることができた.推定されたスピンハミルトニアンを用いることで,実験室レベルでは直接見積もることが難しい,スピンギャップや磁気エントロピーなども予測することができる.つまり,“高価”な実験なしに物質を理解できるため,ハミルトニアン推定は物質開発のコスト削減に繋がり,新物質の発見を加速させるだろう.また,この手法は,ハミルトニアンが定義でき,入力する実験・観測データを計算できる計算手法があれば利用することができる.物理学における様々な分野において,広く応用できる手法である.
- 著者
- 那須 奎一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, 2004
<p></p>
1 0 0 0 OA 物理学者の国籍
- 著者
- 広重 徹
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.6, pp.443-445, 1972-06-05 (Released:2020-10-30)
1 0 0 0 会告
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.2, pp.157-161, 2015
■第70回年次大会の宿泊・交通等の案内(今回は旅行業者による取扱いはありません) ■第14回代議員懇談会開催のお知らせ ■第95回定時総会開催のお知らせ ■ 2015年1月1日付新入会者 ■第71~72期代議員選挙(信任投票)のお願い
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.2, 2013
1 0 0 0 KEK‐神岡間長基線ニュートリノ振動実験K2Kと次世代計画
- 著者
- 西川 公一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.5, pp.332-337, 2003
K2Kグループは2001年7月までのデータを解析した.長基線実験が可能であることを示すとともに,世界初の加速器実験により,ニュートリノ振動の存在を99%以上の確率で検証した.またデータはニュートリノ振動に固有なニュートリノエネルギースペクトルの歪みを示唆している.加速器実験によるニュートリノ振動実験の現在と将来について述べる.
1 0 0 0 太陽内部のカオスから秩序を生み出す
- 著者
- 堀田 英之
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.11, pp.762-766, 2016
<p>太陽内部で,カオス的速度場・磁場から秩序だった構造を作り出すメカニズムの発見について解説する.太陽には黒点という強磁場領域があり,この黒点の個数は11年の周期を持って変動している.黒点は,太陽内部で乱流によって生成された磁場が表面に浮き出た断面と考えられている.黒点には様々な極性や向きに関するルールがあり,90%以上の黒点がこのルールに従う.黒点は3万km程度の構造であり,円周440万kmの太陽から見ると局所的な構造であるにも関わらず,ただランダムに黒点が現れるのではなく,大局的なルールを持っているということは太陽内部に全球スケールの大規模磁場が存在することを示唆している.</p><p>太陽内部の外側30%である対流層は,お湯を沸かしたように熱対流不安定な状態にあり乱流で満ち溢れている.その巨大なシステムサイズと低い粘性によって,乱流を駆動する空間スケールと散逸するスケールに非常に大きな差があることが知られている.いくつかの仮定が必要だが,理論的にはこの二つのスケールには10<sup>7</sup>ほどの比があると見積もることができる.磁場は小スケールでの生成が短い時間スケールを持っており,与えられた乱流の中で磁場を生成することを考えると,太陽では乱流の最小スケールであるcmスケールの磁場のみが卓越し,観測される大規模な磁場はできないと考えられる.このスケールギャップを如何にして埋め得るかが,本記事の主題である.</p><p>この考察の妥当性は,すでにアメリカやカナダのグループによる数値計算で確かめられている.2010年頃に達成した解像度の数値計算では,大規模磁場やその磁場の周期性を確認できたのだが,計算の高解像度化が進むにつれて,太陽で予想されるような大規模磁場が作られにくくなっていってしまった.これは高解像度化によって自由度が増え,小スケールの乱流が大規模磁場を破壊してしまったことが原因なのであるが,太陽は言うなれば超高解像度のプラズマ流体であるので,どのようにして,大規模磁場を生成・維持しているかは大きな謎になっている.</p><p>この状況を解決しようと,筆者らはこれまでにない高解像度計算に挑戦した.超高解像度化したときのみに現れる物理現象を見逃しているのだろうと考えたのだ.大規模計算機を扱うための新しい計算手法,低粘性・低磁気拡散の計算スキーム,そしてスーパーコンピュータ「京」によってこの高解像度化は実現した.計算の結果を見ると,これまでの研究で実現できている範囲ならば,高解像度化したときに大規模な磁場エネルギーは小さくなり,過去研究と調和的であった.しかし,さらに高解像度化を進めると,大規模な磁場が再度強くなるという現象を発見した.今回達成した解像度では,小スケール乱流による磁場生成能力が非常に効率的になり,小スケールで磁場のエネルギーが運動エネルギーよりも大きくなった.この結果,小スケールの乱流が強く抑制され,大規模な磁場を破壊していた運動を避けることができたのだ.今回の発見では強い粘性を仮定しなくてよく,実際の太陽でも起こりうる重要な発見であると考えている.</p>