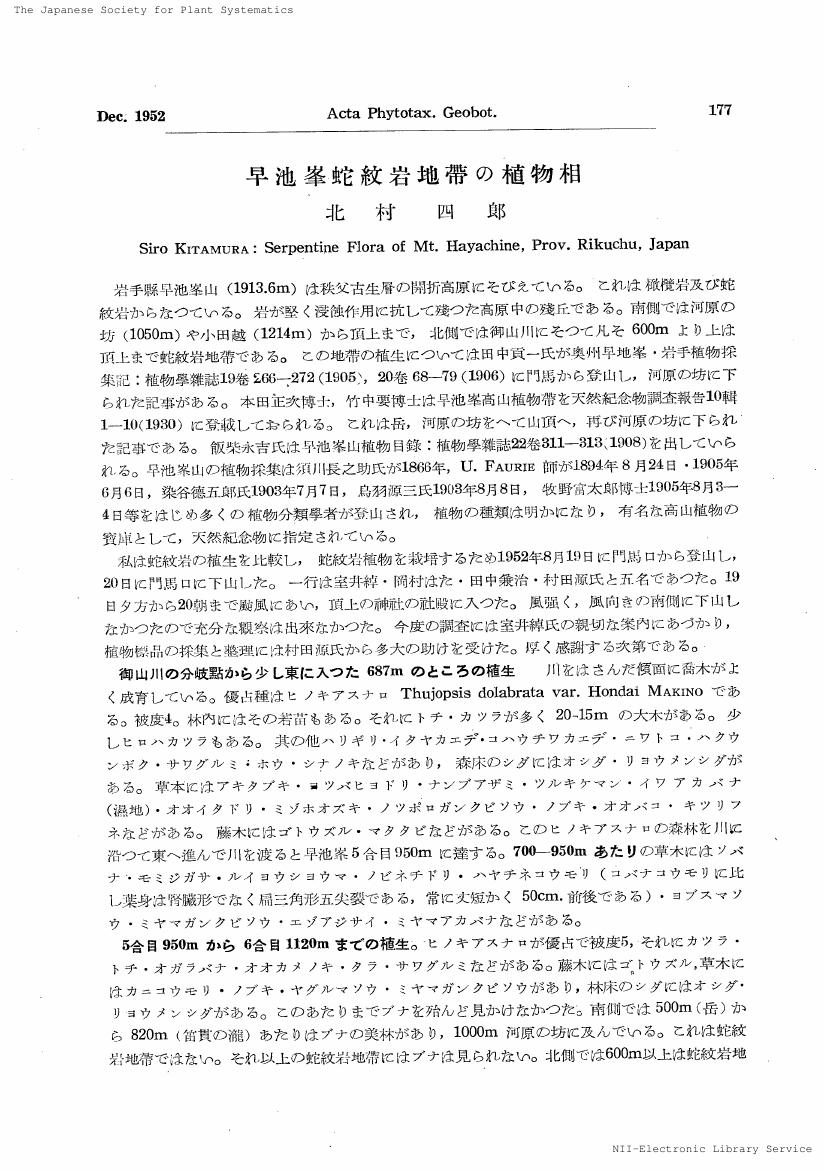1 0 0 0 OA 腐生植物サクライソウの核型分析と分類学的示唆
- 著者
- 田村 実 高橋 弘
- 出版者
- Japanese Society for Plant Systematics
- 雑誌
- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.49-56, 1998-07-28 (Released:2017-09-25)
- 参考文献数
- 28
腐生植物のサクライソウ属Petrosaviaはマレーシア,インドシナ,中国南部から日本にかけての熱帯雨林,常緑広葉樹林,落葉広葉樹林,針葉樹植林,竹林などの林床に生育し,互いにほとんど合着しない心皮をもち,しばしば原始的な単子葉類と考えられるが,その類縁は明らかでない。Beccari (1871), Huber (1969), Dahlgren et al. (1985), Thorne (1992)はこの属をシュロソウ科Melanthiaceae(広義のユリ科Liliaceae s. lat.)に含めたが,Deyl (1955), Stant(1970), Cronquist (1970, 1988), Tomlioson (1982), Takhtajan(1997)はこの属を同じく腐生殖物のホンゴウソウ科Triuridaceaeに近縁とした。Hutchinson(1959)はこの属をホロムイソウ科Scheuchzeriaceaeとホンゴウソウ科の中間に位置づけた。本研究ではサクライソウ属の類縁を探るために長野県木曽郡南木曽町柿其と岐阜県可児市久々利に産するサクライソウPetrosavia sakuraiiの体細胞染色体を観察した。その結果,サクライソウは2n=60の四倍体で,間期染色体は球形前染色体型,分裂前期染色体は基部型であった。分裂中期の各染色体の長さの測定値は柿其のもので1.1-3.6μm,久々利のもので1.1-3.0μmであり,サクライソウの染色体は比較的小型であることがわかった。核型は8対の次中部型染色体と22対の中部型染色体からなっていた。広義のシュロソウ科に含まれるキンコウカ科Nartheciaceaeはx=13-16,長さ0.7-3.5μmの体細胞中期染色体をもち,特にチシマゼキショウ群Tofieldia-Pleea-Harperocallis complexの染色体の基本数とサイズはサクライソウのものとほぼ一致している。一方,ホンゴウソウ科はx=11,12,14で比較的大きい染色体をもち,ホンゴウソウ科に近縁なLacandoniaceaeはx=9でやはり大型の染色体をもつので,これらの科の染色体の特徴はサクライソウのものと著しく異なっている。ホロムイソウ科はサクライソウと同じく小型の染色体をもつが,x=11で染色体基本数が異なっている。従って,染色体の特徴からはBeccari(1871)らの「サクライソウ属はシュロソウ科に含められる」とする見解が支持される。
1 0 0 0 OA 早池峰蛇紋岩地帶の植物相
- 著者
- 北村 四郎
- 出版者
- 日本植物分類学会
- 雑誌
- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.6, pp.177-180, 1952-12-20 (Released:2017-09-25)
1 0 0 0 故植物分類学者の生没年について
- 著者
- 北村 四郎
- 出版者
- 日本植物分類学会
- 雑誌
- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.5, 1989
1 0 0 0 東亜植物誌資料(承前)
- 著者
- 大井 次三郎
- 出版者
- 日本植物分類学会
- 雑誌
- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.25-36, 1933
112)チシマルリサウ チシマルリサウは碧色の花の美しい海岸植物で南千島の色丹島から得撫島にかけて分布する,その学名は巴里博物館のH.HUMBERT教授の厚意に依ってSteenhammera pterocarpa TURCZ. を改めたMertensia pterocarpa (TURCZ.) TATEWAKI et OHWIと成らねばならぬ事が明らかに成った.従来はMertensia rivularis DC. の変種と考えられていたが此の植物は沿海州産のもので小果の周縁に鋸歯がある別種でHULTEN氏が勘察加植物誌に図解して居る.又著者の一人は誤って色丹植物誌中にMertensia kamtscbatica DC.の名を用いたが此れは北千島から勘察加に分布するタカヲカサウの異名であって小果の形ちは似て居るが全体に多少の絨毛があり,萼列片の形ちも質も少々違う別種である.113)チシマイハブキ 真のSaxifraga panctata LINN. は本邦では朝鮮の北部にのみ産する花序の疎な茎葉に軟毛のある種類であってチシマイハブキにあてるのは正しくない.チシマイハブキは北米北部に生するSaxifraga Nelsoniana DON に最も近似して居るがそれよりも花序が密でないのと葉身や葉柄に密毛の無い点が違う.チシマイハブキは北海道,千島,樺太及び勘察加に分布して居るが本州及び朝鮮では未知のものに属する,従って朝鮮産の真のS. punctata LINN. には和名がなくなるので新しくテフセンイハブキと呼ぶことにする.114)リウキウヒエスゲ 琉球の国頭郡佐手で小泉博士が採取せられたヒエスゲ近似の新種で,本州四国等の南海岸に分布するアヲヒエスゲに酷似して居るものであるが雌花鱗片が卵状三角形で漸尖頭であるのと果〓が平滑で脈が多いのとその肩の部分が急に狭まらぬ点が違う,又果〓の脈が多い点等台湾産のタツタカスゲとも似て居るが果〓が平滑でその側面が膨れて居る事や痩果の頂部に円盤状の付属物がある点が違う.Carex xollifera OHWIと呼ぶ.
1 0 0 0 東亜植物考察10.
- 著者
- 大井 次三郎
- 出版者
- 日本植物分類学会
- 雑誌
- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.2, pp.81-87, 1934
168) ヤマイチゴツナギ 本州,四國,及び朝鮮に分布するトボシガラの芒の無くした樣な外形のものであるが此れはその外尚台灣の山地にも産する. 169) シバカモノハシ,ヤエヤマカモノハシ 松村任三氏植物名鑑には Ischaemum muticum LINN. の名が出て居るが本田博士に從へばそれはオニシバに過ぎず眞の此の學名の植物ではない,從つて琉球の此の植物は本邦に於ける初めての記録と成る,他の Ischaemum に比べて隨分違つたもので芒が全くなく,葉が短かくて一見オニシバを少し大形にした樣なものである,吾が近隣地方では比律賓にある. 170) ヒメネヅミノヲ 台灣の新竹州,十八尖山で島田彌市氏が一見ネヅミノラを小形にして穂に赤味を帶びさせた樣な植物を採集せられた,台灣の對岸,福建及び廣東に知られて居た Sporobolus Hancei RENDLE で和名は島田彌市氏がヒメネヅミノヲと名付けられた,本邦のフロラには新品である.171) カニツリグサ 之れも台灣では未記録であつたが同地のピアナン鞍部,太平山等で採集した,ピアナン鞍部ではリシリカニツリと混じて附近の草原に可なり澤山あつた,此のカニツリグサは歐洲産の Trisetum flavescens BEAUV. 及びその變種で本邦北部や中部の山地等にあるチシマガニツリとは明かな別種であつて,容易に出來る區別點としてはカニツリグサでは護頴の先端の二個の裂片が針状に尖る事と葯が楕圓形又は長楕圓形で護頴の長さの1/5-1/6に過ぎぬ(チシマカニツリ及び Trisetum flavescens BEANV. では2/3-2/5.その形ちは線形披針形であるが上部の花のものではそれよりも多少短かい)點等を擧げる事が出來る. 172) イヌフト〓 Scirpus littoralis SCHRAD. の新和名である,琉球本島の産でフト〓に似て痩果の剛毛に比較的長い毛がある,莖は三稜形である.
1 0 0 0 OA 日本産チャルメルサウ属 : 摘要
- 著者
- 大井 次三郎
- 出版者
- Japanese Society for Plant Systematics
- 雑誌
- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.61-65, 1932-04-20 (Released:2017-09-25)
チャルメルサウ屬は亞細亞及北米の暖帶及至亞寒帶に分布する虎耳草科の多年生草本で世界に約二十數種を産し北米に最も多く分布してゐる。兩大陸に共通な種は唯マルバチャルメルサウ一種だけで他は北米及本邦の特産に屬する。本邦領内では北は北海道,朝鮮,から南は臺灣の高山まで産するが比較的南方に種類が多い。本邦産チャルメルサウ屬植物は餘り澤山の種類はなく總計八種に過ぎぬが閑却された傾きがあるので此所に檢索表をあげ檢定に便宜な様にした。§子房と花托は殆んど癒合せず,雄蕋は10個又は5個,5個の場合は蕚裂片と對生。*雄蕋は5個,花瓣は分裂せず,莖上に1-3個の葉あり。…1)エゾノチャルメルサウ *雄蕋は10個,花瓣は羽状に分裂す,莖には葉なきか又は唯一個小形のものあり。…2)マルバチャルメルサウ §子房は大部分花托と癒合す,雄蕋は5個花瓣と對生す。 *葉の幅は長さと殆んど等長,花序は花數少なく多くは10個以下,花糸は花托上に坐す,花柱は二個,全縁なり。…3)コチャルメルサウ *葉の幅は長さより短かし,花は通常數多し,花糸は花瓣の基脚に坐す,花托は二個短かく且肥厚し,先端2-4裂す。 1)葉柄及葉身の下面は平滑なり。…4)モミヂチャルメルサウ 2)葉柄及葉身には毛茸あり。 I) 蕚裂片は花時直立し卵状三角形。△)花糸は葯より三倍長し,葉は鋭頭。…5)アカゲチャルメルサウ △)花糸は葯より短かし,葉は多くは鈍頭…6)チャルメルサウ II) 蕚裂片は花時開張し偏平なる三角形をなす,花糸は葯より短かし,葉は鋭頭又は鈍尖頂。 △)托葉は多くは縁毛あり,葉柄には短毛あり,花柱は頂端四裂す,種子は表面稜起せる縱線あれども突起なし。…7)オホチャルメルサウ △)托葉は多くは全邊,葉柄には長き毛茸あり,花柱は頂端二裂す。種子は背部に乳頭状突起あり。…8)ツクシチャルメルサウ Mitella japonica の名はMAXIMOWICZ, MIQUEL, MAKINO 三氏の名前によつてチャルメルサウ,コチャルメルサウ,オホチャルメルサウ三種に用ひられたが,その根本のMitellopsis japonica SIEB. et ZUCC. なる植物及び最初に之をMitella屬に移したMAXIMOWICZ氏の標本の一部は私の云ふオホチャルメルサウに相違ないので此の學名はオホチャルメルサウに冠するのが當然である。尚Mitella triloba MIQ. も同じ植物を指したものであつてモミヂチャルメルサウではない。チャルメルサウの學名はMitella stylosa BOISS. よりもMitella longispica MAKINOの方が早いが残念ながら記載がないので後者は用ひる事が出來ぬ。尚詳細な分布や異名等は歐文欄を參照して頂きたい。
1 0 0 0 OA 日本産シャクナゲ類の葉の表皮系に見られる特徴
- 著者
- 釘貫 ふじ 村田 源
- 出版者
- 日本植物分類学会
- 雑誌
- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.349-358, 1987-09-25 (Released:2017-09-25)
An attempt was made as to the epidermal system of both adaxial and abaxial surfaces of foliage in some species of Rhodoendron which has been scarcely investigated. Using our original method, an observation of wide scope can be made concerning the epidermal layers of leaves by the light microscope from the polar view. The epidermal cells of the adaxial surface are found to be amoeboid in shape in R. aureum, R. brachycarpum and R. makinoi, while those to be not amoeboid but polygon in shape in R. metternichii var. metternichii, R. metternichii var. hondoense, R. yakushimanum and R. degronianum. In R. brachycarpum, the epidermal system of the adaxial surface is observed to be 2-layers near midrib, but to become one layer at the margin of leaves. there is sporadically an aggregate of cells which are well stained by fuchsin. In R. aureum, the hair stalks which are multicellar are observed in the abaxial surface of leaves. In R. brachycarpum, the base of hairs is found to be 2 cells, while that in the other species examined to be 2-4 cells. Considering the unique mode of the distribution and the density in stomata and hairs, and the epidermal cells being elliptic polygon, R. yakushimanum is thought to be clearly distinguished from R. metternichii and R. degronianum.
1 0 0 0 ウイーンランド氏, 南洋杉化石林
- 著者
- KOIDZUMI G
- 出版者
- 日本植物分類学会
- 雑誌
- 植物分類,地理
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, 1936
1 0 0 0 アリューシャン列島産の紅藻フチトリベニ属二種
- 著者
- 増田 道夫
- 出版者
- 日本植物分類学会
- 雑誌
- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.6, pp.149-156, 1978
北海道大学探検部アリューシャン列島踏査隊によって採集された紅藻フチトリベニ属 Rhodophysema 二種について報告した.Rhodophysema elegans (C_<ROUAN> frat. ex J. A_G.) D_<IXON> には四分胞子体の他に雄性配偶体が確認され,本種の精子嚢形成について報じた.キクイシコンブ Thalassiophyllum clathrus の茎状部に着生していたものを新種 Rhodophysema nagaii M_<ASUDA>, sp. nov. として記載した.本種は千島列島の海藻を研究した故永井政次博士が Rhododermis parasitica B_<ATTERS> (和名,コブノハナ) としたものと同種であるが,真の R. parasitica (=Rhodophysema elegans) とは四分胞子嚢が長い柄細胞列を持つこと及び,側糸が長いことで異なる.これらの形質において, R. nagaii は R. africana J_<OHN> et L_<AWSON> 及び R. feldmannii C_<ABIOCH> に似ているが,種々の点で区別される.
- 著者
- 菅原 敬
- 出版者
- Japanese Society for Plant Systematics
- 雑誌
- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.1-17, 1998-07-28 (Released:2017-09-25)
- 参考文献数
- 17
1996年新潟県北部の荒川流域で奇妙なカンアオイ属植物が確認された。この植物は,同地城周辺から従来報告されていたコシノカンアオイ(Asarum megacalyx F.Maek.),あるいはユキグニカンアオイ(A.ikegamii [F.Maek.ex Y.Maek.] T.Sugaw.)によく似るが,花の形態はそれらの中間型のようにみえる。一方,新潟県西部から富山県東部の地域には未記載種クロヒメカンアオイ(Heterotropa yoshikawai nom. nud.)が知られていた。この植物もコシノカンアオイに近縁と見なされてきたが,いまだその実体は充分に解明されていない。そこでこれら問題の植物の分類学的位置づけ,ならびに既存の2種との関連を明らかにするため,花の形態ならびに染色体からの比較研究を進めた。その結果,未記載種クロヒメカンアオイは独立種とみなしうることが判明したので,Asarum yoshikawae T. Sugaw.の学名で正式な記載を行った,また荒川流域の問題のカンアオイ属植物はユキグニカンアオイの新変種と位置づけられ,アラカワカンアオイ(A. ikegamii var. fujimakii T. Sugaw.)として記載した。クロヒメカンアオイは萼筒が上方に狭まった筒形で,萼筒口が径4mm以下と著しく狭く,萼筒内壁の襞は著しく複雑化する。また中期染色体でも4本の次中部型染色体を含む固有の核型をもつ特異な種である。一方新変種のアラカワカンアオイは狭義のユキグニカンアオイ(var. ikegamii)に比べて萼筒がより大きく,口環もより発達して目だつ。また,花柱附属突起はユキグニカンアオイのように萼筒口の高さにまで達することはなく,常に萼筒内におさまっている。この新変種は荒川流域に沿って新潟県関川村から山形県小国町付近まで分布する。
地球上最古の被子植物として一九二三年J. H. HOSKINS氏は北米の石炭紀最下部よりAngiospermophytonを發見せりと云ひしもA. C. SEWARD教授によれば,之はMedulosaの葉柄にしてMyeloxylonなりと云はれ,被子植物の最古のものは矢張りH. THOMAS氏がYorkshireの侏羅紀より發見せる一種の果實是なりと云ふ,然るに1929年G. R. WIELAND氏はアルゼンチンの三疊紀最上部のレ-チツク層よりトネリコ屬(Fraxinus)近似の被子植物の果實を發見したりと稱し,之をFraxinopsis minor及びF. majorの二種として記載せり.若し果して此新屬植物の果實が被子植物のものなりとせば,地球上最古の被子植物は又更に遡りて三疊紀最上部を起源となす事になる.大石氏はWIELAND氏のFraxinopsis果實は一種子双子葉のものに非ずしてPodozamitesのCycadocarpidiumの如く二種子を保有するものと考へたく,之こそWIELAND氏の所謂Hemi-Coniferなるべしと云ふ,それで地球上最古の双子葉植物は又侏羅紀へとひきあがれり.WIELAND氏は又Fraxinopsisと共に産する一のTaeniopteroid leaves亦双子葉植物のものなるべしと云へり.大石氏は此植物の所屬は不明なれども双子葉植物には非るべくStangeria やTaenitisに類せる裸子植物か羊齒類似の植物なるべしと云ひ,南米アルゼンチン,亞弗利加,印度等の三疊紀最上部(レ-チツク)より侏羅下部(リアス)に亙り生存せるものにてRhaetic Post-Gondwana Floraの要素として著甚なるものとし東北大學矢部教授の記念としてYabeiella屬を設立し,次の諸種を包括せしめたり.Yabeiella mareyesica (Geinitz) Oishi. アルゼンチン Y. brackebusohiana (Kurtz) Oishi. 南亞弗利加 Y. Wielandii Oishi. アルゼンチン Y. spathulata Oishi. アルゼンチン Y.? dutoiti Oishi. 南亞弗利加 Y.? crassinervis (Feist) Oishi. 南亞弗利加,印度,濠州(?),新西蘭土(?)
1 0 0 0 染井吉野桜の天生地分明かす
1 0 0 0 ヤマウパノカミノケとしてのサイハイタケ属の諸菌
- 著者
- 小林 義雄
- 出版者
- 日本植物分類学会
- 雑誌
- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, pp.201-205, 1982
Pollen tetrads of 36 species belonging to 26 genera of Japanese Orchids were observed in details. The results are as follows : 1) Confirmation of types of the pollen tetrads and morphological variation in each type of them ; The arrangement of the four young pollens in the tetrads is variable within 36 species observed, although they could be classified into six types such as tetrahedral, square, decussate, rhomboidal, T-shaped and linear ones. Throughout the species observed the pollens constituting a tetrad were intact, and aberrantly large or small ones in the aberrant tetrads were not recognized. 2) Estimation of mixing ratios in each type of the pollen tetrads ; All six types of the pollen tetrads were recognized in 30 among 36 species observed. The ratios in each type of the pollen tetrads are shown in Table 1. The decussate tetrads show the highest ratio, about 50% throughout the species except Habenaria radiata and Goodyera maximowicziana. Values of the ratios of each type decreased from the decussate tetrads in sequence of rhomboidal, tetrahedral, square, T-shaped and linear ones. Detailed observation on the ratios among the pollen tetrads in each type of Calanthe discolor showed that the ratios were similar through five individuals collected from three different localities ( Table 2). In Goodyera maximowicziana, higher ratios of the T-shaped tetrads and linear ones were observed in extremely slender basal part of the pollinium than those of T-shaped and linear ones of the other part of the pollinium. 3) Ontogenetical observation on each type of the pollen tetrads ; All tetrads observed were produced by simultaneous membrane formation. The course of the tetrad formation was proceeded in the pollen mother cells which were gathered into parenchymatously compact mass. The courses of the pollen tetrad formation of each type are schematically shown in Fig. 1 with photographs in Figs. 2 and 3. It seems that different types of the pollen tetrads are caused by the different forms of the pollen mother cells and by the difference of the direction of the two axes of the second nuclear divisions. It is concluded that the species in the Orchidaceae observed have several types of pollen tetrads within a single pollinium which all develop normally and that the types of pollen tetrads in this family would be determined by the direction of axis of cell division and the forms of pollen mother cells. The forms may be correlated to those of the pollinia and to the parenchymatously compact gathering of the pollen mother cells throughout the course of the tetrad formation.
1 0 0 0 コシキギク
- 著者
- 北村 四郎
- 出版者
- 日本植物分類学会
- 雑誌
- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.4, 1970
1 0 0 0 オオバキスミレとエゾキスミレの一群
- 出版者
- 日本植物分類学会
- 雑誌
- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.23-29, 1961
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 四國石立山の植物相
石立山の植物相の大要は上は述べた如くであるが,斯様な事實から,(1)此の山は未だ亜高山帯に達しないが區系的に注意すべき事は寒地性の依存分布があり,(例えばイワウサギシダ,ムシトリスミレ,その他)或は隔離分布を爲す著しい例が見られ,(例えばヒメフウロ,コウシユウヒゴタイ,その他)又一般に希少な植物がよく成長している事(例えばギンロバイ,イワユキノシタ,その他),(2)これらの植物は石灰岩地では可成り低い所まで見られる(例えばホソバシユロソウは500mまで),(2)石灰岩露出地の區系的組成乃至は植相は他の他の地方の蛇紋岩地帯とよく似た點が多い事(例えば群落が多く灌木叢林状でイワガサ,キハギ,イワツクバネウツギが優占的になる事など,その他)などが此の山でもうかがえる。斯様な點は石灰岩地帯に見られる特徴であり(植物研究雑誌XXVII, 33, 1952)區系地理學上意義が深い。今後更に精細な調査を行なう事によつて,或は更に新しい事實を見出し得るかも知れない。終りに本報文を草するに當つて,御教示をいたゞいた北村教授に厚く感謝する。又調査に際し種々御便宜をはかられた高知營林局和田豊洲氏高知大學の鎌倉五男氏に感謝する。
1 0 0 0 ブータンの淡水藻類2
- 著者
- 平野 実
- 出版者
- 日本植物分類学会
- 雑誌
- 植物分類,地理 (ISSN:00016799)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.44-48, 1966