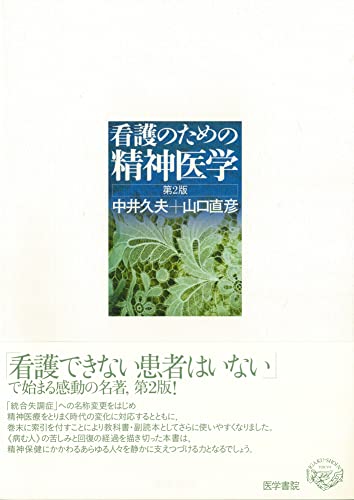20 0 0 0 OA 黒糖の抗酸化性について
- 著者
- 山口 直彦 山田 篤美
- 出版者
- Japanese Society for Food Science and Technology
- 雑誌
- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.6, pp.303-308, 1981-06-15 (Released:2011-02-17)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 5 2
11種類の糖及び16種類の蔗糖の抗酸化力を測定し,次のような結果を得た。(1) 11種類の糖類について抗酸化力を測定した結果,五炭糖,六炭糖は酸化を促進し,また,それらの二糖類はリノール酸の酸化安定性にほとんど影響しないか,やや抗酸化的に作用する。一方,黒糖は著しい抗酸化的作用を示した。(2) 16種類の蔗糖のリノール酸の酸化安定性に及ぼす影響を試験した結果,グラニュ糖の抗酸化力はほとんど認められず対照区と同じか,やや酸化促進的な作用を示した。また,三温糖には顕著な酸化促進性が認められ,さらに黒糖は著しい抗酸化力を示した。三温糖の酸化促進性,また黒糖の抗酸化力は,これら蔗糖に含まれる微量成分(鉄,銅,アミノ態窒素,全窒素及び着色物質)のバランスの上に成立すると推論した。(3) 粗糖,グラニュ糖及び廃糖蜜の抗酸化力を測定した結果,グラニュ糖<粗糖<廃糖蜜の順であった。(4) 黒糖(L)の非透析物のDEAE-セルロースによる分画の結果,6つのピークに分別された。それら各ピークの抗酸化力を420nmの吸光値当りで比較した結果,ほとんど同じ程度の効力を示した。(5) 黒かりん糖(黒糖使用)は白かりん糖(上白糖使用)に比較して著しく安定であった。
1 0 0 0 OA 味噌の抗酸化機能について
- 著者
- 山口 直彦
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.10, pp.721-725, 1992-10-15 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 5 2
味噌の食品機能が注目されるようになったが, 幾つかの機能の中で, 抗酸化機能は特に重要である。酸化されやすいビタミンAも味噌の中では極めて安定している。最近, 味噌を摂取した場合に, 肝臓内での酸化防止効果が認められた。味噌の抗酸化機能を支えるものとして, 褐変色素のメラノイジン及びペプチドの果す役割について解説していただいた。
1 0 0 0 果実及び野菜の加熱に伴う抗酸化性の変化
- 著者
- 中川 泰代 大澤 真由美 早川 美幸 山口 直彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.59, pp.299, 2007
目的 植物にはポリフェノール化合物が広く存在しているが、この化合物は酵素的酸化で、褐色色素へと変化すると共に、その抗酸化性は大きな影響を受ける。この酸化酵素は熱によって容易に失活することはよく知られている。抗酸化性の評価を、DPPH還元力測定の他に、リノール酸に対する抗酸化性をも測定したので報告する。方法 _丸1_試料はリンゴ、ごぼうなど7種類を使用。みじん切りしたものを2本の100ml三角フラスコに5gづつ精秤した後、1本は電子レンジで1分間処理し加熱区(H)、他の1本はそのまま1時間常温放置し、生区(L)とした。これらに40%エタノールを加え抽出液を得た。抽出液の_丸2_DPPH還元力測定、_丸3_過酸化物価はロダン鉄法にて測定し、その値が3.0に達するに要する日数を誘導期間とした。_丸4_リノール酸に対する抗酸化性は含水系(pH7.0)で測定し、50℃の恒温器中にて保存実験を行った。結果 _丸1_紅玉など4種のリンゴ(皮)のH区の全フェノール量は286~226mg/100gの範囲内であったが、L区のそれは204~118mg/100gと少なかった。一方、抗酸化性をみると紅玉のH区の効力は著しく強いが、他の3種のH区の抗酸化性は大変弱い。さらに、L区の効力がH区に比較して大きく減少するのは紅玉のみであった。_丸2_産地の異なるごぼう3種のH区の全フェノール量は宮崎:402mg、北海道:250mg、及び中国:134mg/100gであった。一方、L区のそれは186mg、126mg、及び96mg/100gへと減少した。H区とL区の抗酸化性を比較すると、宮崎産と北海道産はその誘導期間が減少したが、中国産は殆ど変化しなかった。
1 0 0 0 OA 魚干物の酸化安定性
- 著者
- 川口 治子 溝崎 久美子 山口 直彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集 59回大会(2007年)
- 巻号頁・発行日
- pp.114, 2007 (Released:2008-02-26)
〔目的〕いわし,あじなど赤身魚は高度不飽和脂肪酸であるEPA,DHAなどを含み大変酸化を受け易いと思われる。また,その干物は乾燥工程あるいは流通過程などでは急速な酸化の進行が危惧される。そこで私達は市販干物(あじ,いわし及びししゃも)の酸化度を実態調査すると共に,酸化度が著しく高かったいわしについて試作試験を行ったので報告する。 〔方法〕1,干物は,それぞれ5点,豊橋及び岡崎市内で購入した。2,いわし(鮮魚)は岡崎市中央市場で購入した。3,いわし干物の試作は鮮魚をカテキン,トコフェロール及び味噌などの溶液に一定期間浸漬した後,乾燥した。4,酸化度は酢酸-イソオクタン法で過酸化物質(POV)を測定した。 〔結果〕1,市販干物のPOVをみると,あじでは,天日干しと表示してある1点のみ99と高い値を示したが,他4点の平均値は11.5±6.6であった。次いでいわしは5点共にPOVは50以上と高く,その平均値は111.9±58.7を示した。さらにししゃも5点の平均値は18.4±5.3であった。これらの結果からいわし干物の酸化度が著しく高いことを知った。いわしの干物の試作試験の結果,2,カテキン製剤(茶葉抽出物10%含有)0(対照区),0.1及び0.5%溶液にいわしを浸漬後,乾燥した干物を5℃,5日間保存し,そのPOVで比較すると,対照区:118,0.1%区:119及び0.5%区:69であった。3,トコフェロ-ル製剤(トコフェロール8.5%含有)についても同様に試験し,5日目のPOVで比較した結果,対照区:160,0.1%区:157及び0.5%:100であった。4,豆味噌の効力を測定した結果,7日目のPOVは対照区:217,1%区:76.6,3%区:79.0及び6%区85.6であった。5,さらに,カテキン及びトコフェロール製剤と豆味噌との併用試験などを行っている。
1 0 0 0 包装技術によるカロチノイド含有食品の劣化防止について
- 著者
- 中川 泰代 山口 直彦 大澤 真由美
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.37, 2004
[目的]近年の健康志向から緑黄色野菜を主原料としたデザート類が多く市場に出回っている。しかし、これらの食品に含まれるカロチノイド系色素は光に弱く、退色に伴う返品がしばしば発生、問題となっている。本実験では包装技術による光と酸素とを制御することによって、その商品寿命の延長を図る目的で行った。〈BR〉[方法]_丸1_野菜入りゼリー菓子、トマトを含有する乾燥モデル食品及びβーカロテンを吸着させたろ紙を調整し、光透過度(T%)及び酸素透過度の異なるフィルムで包装し、明暗所常温保存試験を行った。_丸2_着色度は日本電色工業(株)製 COLOR DIFFERENCE METER MODEL 1001DPで測定し、ハンター表示値で示した。また、劣化度は保存0日のa値に対する保存野菜ゼリーのa値の割合を求めa値の残存率として示した。〈BR〉[結果]_丸1_T%の異なるAl-蒸着フィルムで野菜入りゼリー菓子を包装し、明所常温保存の結果、2_から_5のT%であっても35日目にはa値の残存率は50%以下となり商品価値を失った。しかし、T%:0のAl -蒸着フィルムのそれは107日間の保存によっても50%以上の残存率を示した。_丸2_酸素バリア性の異なる3種の無印刷プラスチック(酸素透過度:2_から_3cc、8_から_10cc及び30_から_50cc/_m2_/24hr)を用い脱酸素剤封入包装されたゼリー菓子の袋内の酸素濃度は1日目には0%台となり、その保存期間中も0%台で推移し、55日間の明所常温保存によっても、a値の変化は殆ど認められなかった。_丸3_乾燥モデル食品に抗酸化物質を添加し明所常温保存の結果、その効果はトコフェロール>ビタミンC>カテキンの順であった。
1 0 0 0 看護のための精神医学
- 著者
- 中井久夫 山口直彦著
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- 2004
- 著者
- 山口 直彦 加納 正男 池田 公子 木島 勲
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.114-119, 1984
- 被引用文献数
- 4
西洋わさび粉,芥子粉の抗酸化力及びトコフェロール製剤に対する相乗性を試験し,次の結果を得た。<BR>(1) 芥子粉は西洋わさび粉に比較して強い抗酸化力を示した。<BR>(2) 酵素ミロシナーゼを失活し,アルキル芥子油の生成を抑えると,芥子粉,西洋わさび粉の双方に抗酸化力の増大が認められた。<BR>(3) 芥子油配糖体の主成分であるシニグリンには抗酸化力が認められるが,その効力は弱い。<BR>(4) 芥子粉の脂質は抗酸化力を示さなかった。しかし,脱脂によって,芥子粉の抗酸化力は約2倍の増大が認められた。<BR>(5) 芥子たんぱく質は芥子たんぱく質分離液より抗酸化力が強い。しかし,芥子たんぱく質は芥子粉より効力が弱かった。<BR>(6) 芥子粉(加熱)はトコフェロール系抗酸化剤の2倍以上の抗酸化力を示した。<BR>(7) 芥子粉(加熱)は味そとは相加的に,トコフェロールとは相乗的に作用し,抗酸化力の著しい増大が認められた。<BR>(8) 芥子粉(加熱)を添加したビスケットを試作し,保存試験を行った結果,芥子粉添加ビスケット中のラードの酸化安定性は著しく向上した。
- 著者
- 山口 直彦 管村 昇
- 出版者
- 情報処理学会
- 雑誌
- 研究報告 音楽情報科学(MUS) (ISSN:21862583)
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, no.10, pp.1-6, 2011-02-04
既存の音楽理論を計算機科学の立場からとらえなおし,理論化しなおそうとする 「計算論的音楽理論」 の研究が進められてきたが,これらはいずれもクラシック音楽理論を中心に考えられてきた.ジャズ音楽理論に基づいて作曲された楽曲が数多く流通する昨今,ジャズ音楽理論を計算論的音楽理論として再構築する試みが必要であると考えられる.そこで筆者は F.Lerdahl の提唱した TPS(Tonal Pitch Space) に着目した.TPS は和声学の知識を和声間距離という概念を用いて定式化し,計算機上に実装できるようにした興味深い理論である.しかしながら TPS もまたクラシック音楽理論を基礎としており,そのままではジャズ音楽理論が扱う複雑な和音に対応することができない.本発表では、TPS を拡張する形で,ジャズ音楽理論を計算論的音楽理論として記述する手法を提案する。Reconstruction of "Music Theory", namely from traditional music theory to computational music theory, has become important in recent years. However these theories are based on classical music. Nowadays, popular music are composed using jazz music theory. Reconstructing computational music theory from jazz music theory is required. In this paper, computational music theory from jazz music theory, by extending TPS(Tonal Pitch Space) proposed by F.Lerdahl, is described.
- 著者
- 山口 直彦
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 精神医学 (ISSN:04881281)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.7, pp.p701-706, 1995-07
- 被引用文献数
- 4
- 著者
- 山口 直彦 棟朝 雅晴 赤間 清 佐藤義治
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.7, pp.2359-2367, 2002-07-15
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
インターネットに代表されるパケット通信ネットワークにおいて,ネットワーク資源を有効に使用するという観点から,遺伝的アルゴリズムを用いて複数の経路を生成し,それらの代替経路間で負荷を分散するアルゴリズムが提案されている.本論文では遺伝的アルゴリズムを用いた負荷分散ルーティングに対し,評価の高速化によりネットワークの状態観測を迅速に行うため,経路の評価にリンクの負荷を考慮したメトリックを導入し,さらにそれを用いてネットワークの負荷状態を反映した代替経路生成を行う遺伝的操作の実装を行う.ネットワークシミュレータを用いたシミュレーション実験により提案する手法の有効性を検証した.In packet switching networks such as the Internet,to utilize network resources effectively,routing algorithms with genetic algorithms have been proposed which generate alternative routes by genetic operators to balance loads among them and prevent congestions.This paper proposes adaptive genetic operators based on link load metric for the genetic routing algorithms in order to realize rapid evaluations of network load status and effective generations of alternative routes.Through simulation experiments performed on a network simulator,we show the effectiveness of the proposed method.