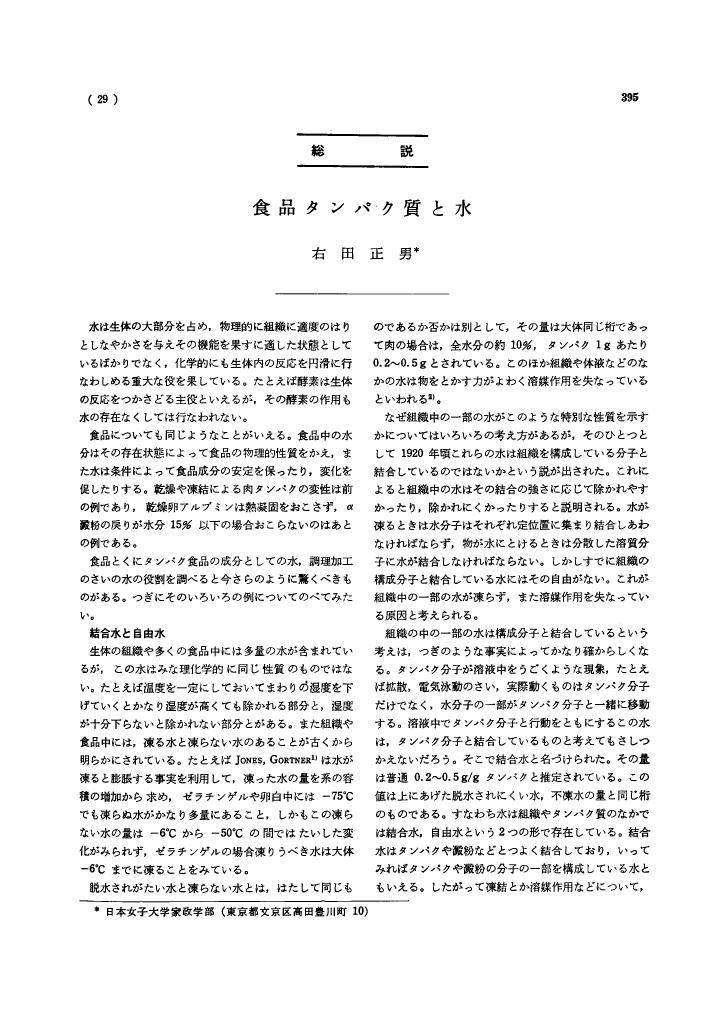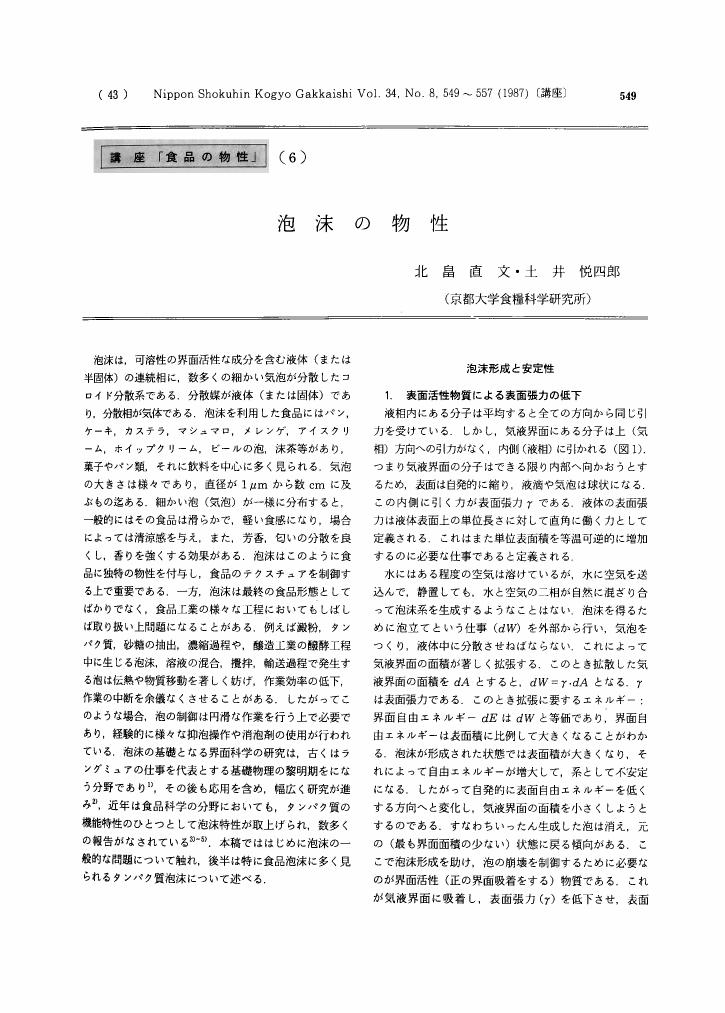14 0 0 0 OA ゲルの物性(測定法)
- 著者
- 西成 勝好
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.61-68, 1987-01-15 (Released:2009-04-21)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 1
9 0 0 0 OA コホート研究と症例対照研究
- 著者
- 杉浦 実
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.12, pp.608-609, 2011-12-15 (Released:2012-01-31)
- 参考文献数
- 3
疫学は,実験動物や培養細胞ではなく,実際の人口集団を対象として,疾病とその規定要因との関連を明らかにする科学であり,明確に規定された人間集団の中で出現する健康関連のいろいろな事象の頻度と分布およびそれらに影響を与える要因を明らかにして,健康関連の諸問題に対する有効な対策樹立に役立てることを目的とする.疫学研究のデザインには大きく分けると,地域相関研究·断面研究·症例対照研究·コホート研究·無作為割付臨床試験(介入研究)などがあり,因果関係を明らかに出来るという点においては一般にコホート研究や介入研究ほど信頼性の高い情報が得られると考えられる.また研究の規模や調査の精度により,得られた情報の評価は異なる.
- 著者
- Tomoya Nagano Kaori Hayashibara Manabu Ueda-Wakagi Yoko Yamashita Hitoshi Ashida
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- Food Science and Technology Research (ISSN:13446606)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.489-494, 2015 (Released:2015-09-10)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 13
We previously reported that the intake of black tea promotes translocation of the insulin-sensitive glucose transporter (GLUT) 4 in skeletal muscle. In this study, we investigated whether black tea polyphenols (BTP) promote GLUT4 translocation in L6 myotubes. BTP promoted glucose uptake accompanied by GLUT4 translocation in L6 myotubes. As the molecular mechanism, BTP induced the phosphorylation of insulin receptor substrate-1, atypical protein kinase C, Akt Thr308, Akt substrate 160, and AMP-activated protein kinase (AMPK), but did not affect that of Akt Ser473. BTP increased glycogen accumulation through inactivation of glycogen synthase kinase 3β (GSK-3β). Theaflavin, one of the major components in black tea, also promoted the glucose uptake accompanied by GLUT4 translocation observed with BTP in L6 myotubes. These results indicate that BTP activates both PI3K- and AMPK-dependent pathways to promote GLUT4 translocation and glycogen accumulation in skeletal muscle cells. Moreover, theaflavin is one of the active components in BTP.
8 0 0 0 OA ロスマリン酸を多く含むシソ抽出物のラットでの血糖値上昇抑制作用
- 著者
- 東野 英明 木下 孝昭 栗田 隆 濱田 寛 江藤 浩市 福永 裕三
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.4, pp.164-169, 2011-04-15 (Released:2011-05-31)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 2
経済的余裕や農業生産技術の普及・発展により食質と食量が豊富で過剰となり,それによって生活習慣病が増加し,現今ではその克服が現代人の最大関心事になりつつある.生活習慣病の中でも,治療困難性と致死的続発症から糖尿病治療が緊急の課題になってきている.2型糖尿病は原因遺伝因子保有者の過食による肥満が原因で,高血圧,動脈硬化,心筋梗塞,腎障害,脳卒中などの続発症を招来する.食後の血糖値をα-グルコシダーゼ阻害薬を用いて上昇抑制すると,ある程度改善できるが副作用の報告も多い.その点,古くから食物の色付け,匂いつけ,食欲増進,防腐,抗酸化,抗アレルギー,心臓血管保護作用物質として用いられてきた安全性の高いシソには,α-グルコシダーゼ阻害作用を持つロスマリン酸が含まれている.そこで,ロスマリン酸を多含有するシソ抽出物製造法を工夫し,正常および糖尿病誘発ラットを用いてin vitro, in vivoで酵素学的,生理学的にその糖代謝に及ぼす影響を総合的に実験観察した.その結果,ロスマリン酸多含量シソ抽出物希釈液は,生体に悪影響を与えずに,α-グルコシダーゼ阻害作用,直接的なブドウ糖吸収抑制作用,遷延的作用で有意な食後血糖値上昇抑制作用を示すことが証明された.この結果は,シソ抽出物のこれまでの単純な食品添加物以外の利用,つまりは健康維持面での利用拡大が図れることを示唆している.
8 0 0 0 OA うどん調理における放射性セシウムの動態解析
- 著者
- 八戸 真弓 内藤 成弘 明石 肇 等々力 節子 松倉 潮 川本 伸一 濱松 潮香
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.34-38, 2014-01-15 (Released:2014-01-31)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 4 3
太さの異なる2種類のうどん生麺,太麺(2.5 mm × 3 mm)と細麺(1.5 mm × 1.5 mm)を作成し,それぞれにおいて茹で時間を変えて調理し,麺の太さと茹で時間が放射性セシウムの動態に及ぼす影響を評価した.太麺,細麺ともに茹で調理により,放射性セシウムが有意に低減されることが分かった.しかし,茹で時間の延長による加工係数の変化は,太麺で20分間まで,細麺で4.5分間までは有意に低下したが,それ以降は茹で時間の延長による有意な低下は認められなかった.残存割合は太麺では10分間で,細麺では3分間までは有意な低下が認められたが,それ以降は有意な低下は認められなかった.これらのことから,喫食に適する茹で時間(太麺では20分間,細麺では3-4.5分間)の調理において,茹で麺と茹で湯間の放射性セシウムの濃度勾配が小さくなり,それ以上の茹で時間の延長では,茹で麺の放射性セシウム濃度の有意な低下は起こらないことが明らかとなった.また,細麺のほうが太麺よりもより短い茹で時間で放射性セシウムの低減効果が得られるが,両茹で麺とも茹で調理により80 %以上の放射性セシウムが除去された.
7 0 0 0 OA 経口免疫寛容
- 著者
- 後藤 真生
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.9, pp.526-526, 2006-09-15 (Released:2007-09-29)
- 参考文献数
- 3
免疫系は,病原体などの異物を自分自身を傷害することなく排除する非常に精巧なシステムである.一方で,摂取された食物のように異物でありながら明らかに無害なものについては,食物アレルギーなどを除き,通常,免疫応答を起こさない.実際には抗原の経口投与によってその抗原に対する全身免疫系の応答は減少するが,粘膜面での防御応答は増加する.よって免疫系は経口的に摂取した異物に特異的に応答を制御していることが理解できる.この現象を経口免疫寛容という.漆職人が漆かぶれの予防に漆を飲む,ネイティブアメリカンがツタウルシかぶれを防ぐためにツタウルシを食べる,など様々な民間伝承もあり,現象としては古くから知られていたようである.しかし,科学的な解析が始まったのは1911年にはWellsによって,鶏卵蛋白をあらかじめ餌として投与したモルモットで全身アナフィラキシーが抑制される現象が報告されたことをもって開始されてからである.経口免疫寛容のメカニズムは解析が進むほど非常に複雑であることが判明し,その全容は解明されているとは言えないが,現在のところ,T細胞が大きな役割を果たしており,抗原の投与方法,特に投与量によって,クローナルデリーション,アクティブサプレッション,アナジーの大きく三つに分けられる異なる寛容誘導メカニズムが働いていることが強く示唆されている.大容量の抗原投与で誘導され,経口抗原特異的な末梢T細胞がアポトーシスによって減少する機構がクローナルデリーションと呼ばれる.抗体は抗原特異的CD4 T細胞が対応するB細胞に産生させるため,T細胞が減少することで,抗体の産生も抑制される.一方,少・中程度の抗原経口投与ではクローナルデリーションは誘導されず,免疫抑制活性を持つ経口抗原特異的なT細胞が出現する.これらによって誘導される免疫抑制をアクティブサプレッションと呼ぶ.実際に,経口免疫寛容を誘導した際に,抗原特異的に抑制的サイトカインを産生するT細胞が腸管膜リンパ節に出現することが発見されている1).また,近年,制御性T細胞と呼ばれる一部の末梢CD4T細胞が,自己免疫疾患の発症を抑制していることが明らかになった.この抑制は主に制御性T細胞と自己応答性T細胞の接触で入る抑制性シグナルによると考えられている.制御性T細胞が食物などの外来抗原に応答するかは不明であるが,多量の抗原の経口摂取によってアクティブサプレッション活性を持つT細胞が腸管パイエル板に出現し,それらには制御性T細胞の特徴が見いだされた.これらから,経口免疫寛容には末梢で分化した経口抗原特異的な制御性T細胞が関わる可能性が示唆されている.またT細胞が抗原刺激に効率よく応答するためには,抗原刺激以外の共刺激を必要とする.共刺激のない状態でT細胞が抗原刺激を受けると,その抗原に対して不応答状態(アナジー)になり,IL-2によって回復することが知られているが,経口寛容誘導マウスの不応答T細胞をIL-2処理すると同様に応答能が回復するため,経口免疫寛容のメカニズムにT細胞のアナジー化が含まれることが示唆されている2).近年,自己免疫疾患やアレルギーの治療,移植時の拒絶反応の抑制などに経口免疫寛容を利用する気運が高まっている.抗原特異的でないステロイド剤や免疫抑制剤は副作用の危険性が高いが,特定抗原への応答のみを抑制する経口免疫寛容は,治療に応用できれば,副作用の危険性がより少ないと考えられている.動物実験では一定の成功を見ており,食物アレルギー3)などで行われたヒト臨床試験で好成績を収めた例も報告されている.しかし,効果が見られなかったケースや病態が悪化したケースもあり,経口免疫寛容を実際に治療に応用するにはまだ課題が多いと考えられる.
7 0 0 0 OA 豆腐の食味に及ぼす大豆リポキシゲナーゼの影響
- 著者
- 島田 和子 野村 寛美 原 由美 藤本 房江 喜多村 啓介
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.122-128, 1998-02-15 (Released:2009-05-26)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 7 9
豆腐の食味に及ぼすLOXの影響について検討するために,普通大豆とLOX欠失大豆を用いて調製した豆腐の各種成分含量と官能評価との関係について調べた.普通大豆としてスズユタカ,LOX欠失大豆として各々スズユタカを反復親として育成されたゆめゆたか(2,3欠)といちひめ(全欠)を使用した.(1) スズユタカの豆腐はいちひめ(全欠),ゆめゆたか(2,3欠)の豆腐と比べて有意に甘味が感じられた.こく味の程度はスズユタカ,いちひめ(全欠),ゆめゆたか(2,3欠)の順で感じられ,スズユタカが最もこく味があるとパネルにより判断された.不快味程度は3種の豆腐間で違いは認められなかった.(2) 豆腐中の水分含量,タンパク質含量,総脂質含量は各豆腐間において大きな差は認められなかった.(3) 甘味を呈する遊離糖のスクロース,スタキオース,ラフィノース,グルコース含量は各豆腐間において差がなかった.(4) 不快味成分であるイソフラボン組成と各含量は各豆腐間で大きな差はなかった.(5) カルボニル化合物とヘキサナールは,普通大豆スズユタカの豆腐においてLOX欠失大豆の豆腐よりも多く含まれていた.上記の他成分量に豆腐間の差はなかったことから,官能評価で認められた豆腐のこく味を示す成分の一つはLOXによる脂質酸化生成物であると推察された.さらに,脂質酸化生成物が豆腐の甘味を増強する可能性も示唆された.
7 0 0 0 OA 餅の物理的品質評価
- 著者
- 山崎 彬 山本 和弘 山田 明文
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.5, pp.369-375, 1995-05-15 (Released:2009-05-26)
- 参考文献数
- 25
餅の劣化は製造後の熱的環境に大きく依存することが知られている.これは熱により,餅の中の水の存在状態が変化し,復元性が喪失されるものと考えられる.本研究は餅の熱による劣化度を,温度と導電率との関係により数値化しようとしたものである.製造直後の餅から60℃, 1時間の熱処理の繰り返しにより,劣化度の異なる4種類の餅のサンプルを作成し,0℃以下で凍結させながら導電率を測定した.その結果,水分が41.5-44.0%の場合,凍結により導電率の急減する温度点が離水による劣化の程度と密接に関係し,餅の劣化を示す指標となることを確認した.また,離水状態の確認のために行なったDSC, DTA,および酸に対する溶解度もこの傾向を裏付けるものであった.さらに,無添加で製造された種々の餅について食味テストで判断した結果,3回の熱履歴を受けたサンプルが品質限界と考えられ,このサンプルの導電率の急減開始温度点は,-6.0±0.5℃であった.
- 著者
- Kazuki Iwashita Motoki Sumida Kazuya Shirota Kentaro Shiraki
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- Food Science and Technology Research (ISSN:13446606)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.6, pp.743-749, 2016 (Released:2016-12-28)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 11
Surimi wash-water (SWW) contains a high concentration of protein resulting in a negative environmental impact and high disposal costs. Isoelectric point precipitation has been used for protein recovery from SWW. Here, we show an improved protein recovery method combining pH shift and heat treatment for Alaska pollock SWW. In a laboratory-scale experiment, a pH shift from neutral to pH 5 precipitated 63% of the SWW protein and subsequent heat treatment at 60°C precipitated almost all of the remaining protein. In a factory-scale experiment, the optimized pH shift and heat treatment yielded a 21% protein pellet with a 79% moisture content. The SWW protein gel thus obtained showed suitable quality as a surimi product as determined by the similar whiteness and strength as gel prepared from low-grade surimi. The optimized method combining pH shift with heat treatment improves the protein yield from SWW and prevents environmental pollution.
5 0 0 0 OA 中華麺の物性,構造に及ぼす乾熱卵白添加の影響
- 著者
- 舘 和彦 小川 宣子 下山田 真 渡邊 乾二 加藤 宏治
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.9, pp.456-462, 2004-09-15 (Released:2009-02-19)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1 3
乾熱卵白を生中華麺に添加した時の影響について力学物性値の測定と官能試験の結果より評価した.また走査型電子顕微鏡を用いて中華麺の表面および断面構造を解析することにより,以下の結論を得た.(1) 中華麺に乾熱卵白を添加することで茹で伸びを抑制し,破断応力,瞬間弾性率は上昇し,硬さおよび弾力性に改善が見られた.さらに付着性の低下より舌触りが良くなること,引っ張り時の歪率の上昇から伸長が良く切れにくくなっていることが推測された.(2) 官能試験の結果より,乾熱卵白を添加した中華麺は噛みごたえ,弾力性,つるみ感,伸長度において無添加麺や乾燥卵白を添加した麺よりも良い評価となり,且つ高い嗜好性を示した.(3) 走査型電子顕微鏡による観察結果より,乾熱卵白を添加した麺の表面構造は,無添加麺や乾燥卵白を添加した麺と比較して隙間が狭く,滑らかであった.また乾熱卵白を添加した麺の断面構造も,蛋白質によって構成される網目構造が細かく,密であった.
5 0 0 0 OA 米糠含有成分の機能性とその向上
- 著者
- 谷口 久次 橋本 博之 細田 朝夫 米谷 俊 築野 卓夫 安達 修二
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.7, pp.301-318, 2012-07-15 (Released:2012-09-04)
- 参考文献数
- 131
- 被引用文献数
- 4 21
Consuming rice as the staple, 0.95 million tons of rice bran is produced annually in Japan as a by-product from the rice milling process. Bran is used in several applications such as animal feed and fertilizer for mushroom cultivation, but most of it has been discarded as an agricultural waste although it contains various functional substances, such as γ-oryzanol, ferulic acid, sterol, wax, ceramide, phytin, inositol and protein. It could be considered a scarcely used but promising resource. As such, continuous efforts have been dedicated to exploring its effective utilization. In this context, functionalities of the substances contained in the bran are summarized, and our attempts for improving functionality, improving ease of use, and exploring new applications are presented.
5 0 0 0 鰹節だし継続摂取による眼精疲労改善効果
- 著者
- 本多 正史 石崎 太一 黒田 素央
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 : Nippon shokuhin kagaku kogaku kaishi = Journal of the Japanese Society for Food Science and Technology (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.8, pp.443-446, 2006-08-15
- 被引用文献数
- 7 23
本評価では,(1) 1日4時間以上VDT作業を行っている労働者であり,(2) 11名中9名が「眼が疲れる」「眼がかすむ」「肩,腰がこる」を感じており,(3) 平均年齢が45.7±7.8歳のパネル11名(男性)を対象に解析を行い,以下2点が明らかになった.<BR>(1)鰹節だしの4週間継続摂取により,自覚症状に関して,眼精疲労にみられる「眼が疲れる」「眼がかすむ」「涙がでる」「眼が赤くなる」などの項目が初期値に比べて主に摂取3週目,4週目で改善傾向を示した.<BR>(2)フリッカーテストの結果,主に夕方のフリッカー値が初期値に比べて摂取4週目で有意に上昇した.前観察期間のフリッカー値のΔ(朝-夕方)の平均値を基準に層別解析を行った結果,平均以上のパネルでは,顕著にΔ(朝-夕方)が低下した.平均以下のパネルでは,ほとんど変化しなかった.<BR>以上の結果から,鰹節だし摂取により眼精疲労が改善される可能性が示唆された.
4 0 0 0 OA 大豆種子の組織破壊が加水加熱時のトリプシンインヒビター失活に及ぼす影響
- 著者
- 盛永 宏太郎
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.6, pp.416-421, 2001-06-15 (Released:2010-01-20)
- 参考文献数
- 11
大豆種子の組織を破壊した後,加水膨潤と加熱を行い組織破壊の程度がTIの熱失活に与える影響を調べて次の所見を得た.(1) 膨潤丸大豆と磨砕大豆に0.05Mリン酸緩衝液(pH 7.6)を加えて沸騰水浴中で20分間加熱したところ,いずれも膨潤丸大豆に残存するTI活性の方が磨砕大豆のTIよりも小さい値になった.そしてその値は120℃ 30分間加圧加熱したときの磨砕大豆の残存TI活性値に匹敵するものであることを認めた.(2) 丸大豆と破砕大豆微粉にリン酸緩衝液を加えて吸水膨潤後に沸騰水浴中で加熱したところ,加熱約5分までは微粉のTIの方が急激に熱失活した.そして両者共に,加熱5分後のTI活性は大豆1mg当たり,生大豆の約1/10相当する数単位になった.しかしそれ以後は微粉のTIは下げ止まりの傾向を示すのに対して,丸大豆はさらに減少し加熱20分後には破砕大豆のTIの約1/2にまで減少した.(3) リン酸緩衝液を加えて吸水膨潤した丸大豆と破砕大豆微粉を20分間加熱したところ,80℃以下の温度では,TI活性減少率は微粉の方が大きかったが,80℃以上では,丸大豆の方が大きくなった.(4) 破砕大豆にリン酸緩衝液を加えて吸水膨潤後に沸騰水浴中で20分間加熱したところ,微細に粉砕した大豆のTIほど熱失活しなくなった.しかし粒径1mm程度で限界に達し,それ以上に粉砕してもさらなる差異は生じなかった.(5) 圧扁大豆にリン酸緩衝液を加えて吸水膨潤後に沸騰水浴中で20分間加熱したところ,圧扁の程度が増すほどTIは熱失活しなくなった.(6) 剥皮した大豆を150℃ 20分焙煎すると剥皮処理を行うことでTIが熱失活しなくなる傾向が見られた.しかし湿式加熱ではこの傾向は認められなかった.また大豆をナイフで切断した大豆にリン酸緩衝液を加えて吸水膨潤後に沸騰水浴中で20分間加熱したところ,分割の程度が少ない大豆では,TIの熱失活しなくなる傾向は認められなかったが,8分割以上に細かく分割した大豆では,有意にTIが熱失活しなくなることが認められた.以上(1)-(6)までの結果,大豆種子は湿式加熱においても,焙煎加熱で見られたように,組織破壊の程度に応じてTIは加熱しても熱失活しなくなることが明らかになった.従来,大豆加工や調理においては食味向上を兼ねて大豆組織が充分に軟らかくなるまで煮熟するのが一般である.しかし以上の結果から,単に大豆のタンパク質の消化向上を目的とする場合は,過度の煮熟は必要なく,また加熱前に大豆を挽き割ったりすり潰したりする処理も不要であるように思われた.
4 0 0 0 OA 加熱によらない殺菌技術
- 著者
- 伊藤 均
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.72-77, 1991-01-15 (Released:2010-01-20)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 1
4 0 0 0 OA 大腸腺腫発症モデルマウスにおける食餌性ナガイモおよびナガイモ入り青汁の効果
- 著者
- 木下 幹朗 柚木 恵太 得字 圭彦 川原 美香 大庭 潔 弘中 和憲 大西 正男
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.53-55, 2009-01-15 (Released:2009-02-28)
- 参考文献数
- 11
食餌性ナガイモの大腸腺腫発症に与える効果を他のイモ類と比較しつつ,1,2-ジメチルヒドラジン投与マウスを用いて調べるとともに,ナガイモを利用した商品モデル(ナガイモ入り青汁)の効果についても検証した.その結果,ナガイモ以外のイモ類においても上記の実験動物モデルにおいて大腸腺腫抑制効果が観察されたが,腺腫数の平均はナガイモ群が一番低かった.また,商品モデルであるナガイモ入り青汁ついても腺腫抑制効果が観察された.
3 0 0 0 OA 食品タンパク質と水
- 著者
- 右田 正男
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.9, pp.395-401, 1966-09-15 (Released:2010-01-20)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA 泡沫の物性
- 著者
- 北畠 直文 土井 悦四郎
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.8, pp.549-557, 1987-08-15 (Released:2009-04-21)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 6 4
3 0 0 0 湯葉皮膜の組織とその形成
- 著者
- 渡辺 研 岡本 奨
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.7, pp.325-330, 1975
- 被引用文献数
- 3
大豆グロブリンの湯葉状皮膜の組織と生成過程を走査型電子顕微鏡観察,呈色反応などで検討した。<BR>(1) 皮膜は水分含量が60~80%であるが,凍結乾燥によって上部に氷結晶の跡が認められない組織化の比較的進んだ層と,下部に組織化の低い層をもち,後者は肥厚しながら約40μまでは経時的に前者に移行する。ミロン試験とキサントプロテイン試験で皮膜表面は鮮明な呈色反応をし,裏面はほとんど反応しなかった。また大豆グロブリンのペーストを加熱して得られるゲルはミロン試験で微紅色にとどまり,湯葉状皮膜と加熱ゲルの組織の相異が示された。<BR>(2) 成膜初期に気液界面に形成される層をモデル固相,たとえばアセチルローズ,セロファン,ニトロセルローズ,フィブロインあるいは羽毛ケラチンなどのフィルムでおきかえても,この固液界面に皮膜を生成することができた。表面での水分蒸発速度が0.049mg/cmcm<SUP>2</SUP>・min以下のフィルム面では成膜しなかった。モデル固液界面で生成した皮膜は従来の製法による湯葉皮膜と同様の組織をもつことが観察された。またこの皮膜は湯葉独特の表面のシワがなく,セロファン面で得られたものでは破断強度が従来の製法のものより大きくなった。<BR>なお,7Sおよび11Sグロブリンは分子構造や皮膜 強度において顕著な差異があるにもかかわらず,皮膜の組織においてはきわだった差異がみられなかった。
- 著者
- Hasan Tanguler
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- Food Science and Technology Research (ISSN:13446606)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.5, pp.772-772, 2017 (Released:2017-10-27)
3 0 0 0 OA 生元素安定同位体比解析によるコシヒカリの産地判別の可能性
- 著者
- 鈴木 彌生子 中下 留美子 赤松 史一 伊永 隆史
- 出版者
- 社団法人 日本食品科学工学会
- 雑誌
- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.5, pp.250-252, 2008-05-15 (Released:2008-06-30)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 10 14
コメの産地偽装問題が起きており,コメの産地を科学的根拠に基づいて判別する技術が必要とされている.本研究は,日本産,豪州産,米国産コシヒカリを用いて,炭素・窒素・酸素安定同位体比解析を行い,安定同位体比解析によるコメの産地判別の可能性を検証した.解析の結果,日本産のコメの安定同位体比は,平均値で,炭素では米国産よりも0.7‰,窒素では豪州産よりも3.8‰低く,酸素では豪州産と米国産よりもそれぞれ12.6‰,3.5‰低い値を示した.安定同位体比から,日本産のコメは,他国産のコメと識別できることが明らかになった.安定同位体比解析は,DNA判別や微量無機元素測定などの他の技術と相補的に利用すれば,強力な産地判別技術になる可能性がある.