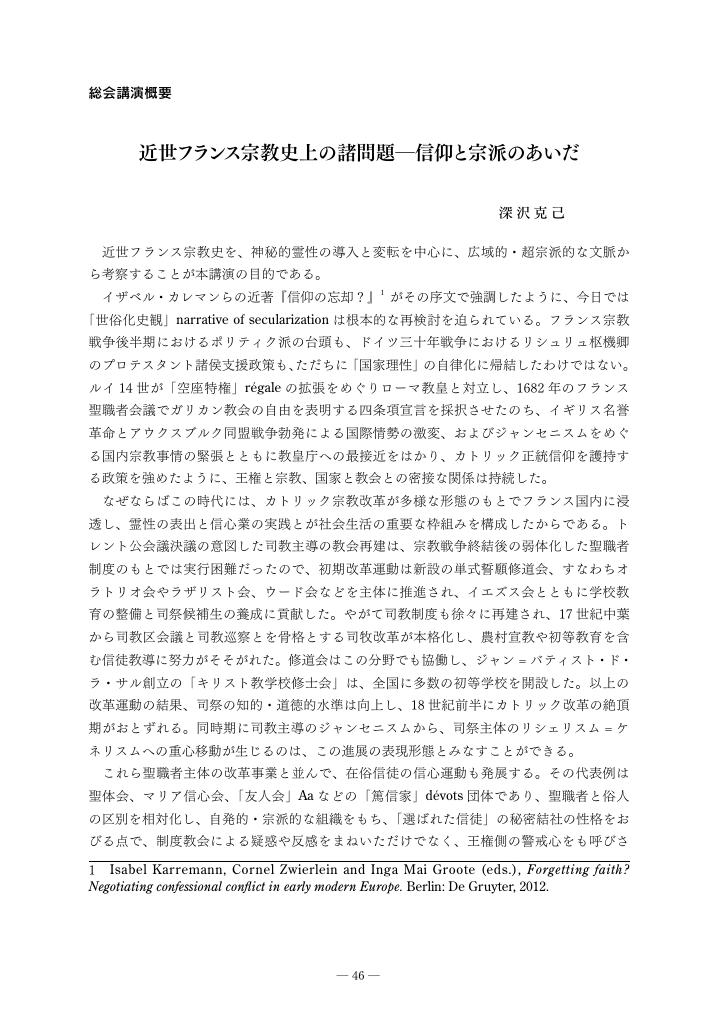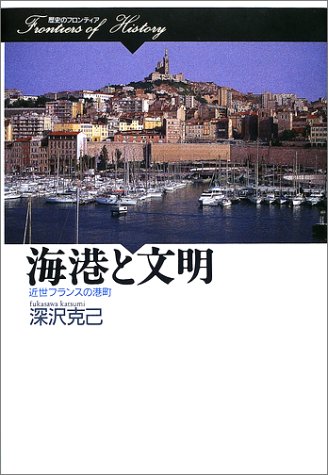27 0 0 0 OA フリーメイソン団成立史研究の現状と論点
- 著者
- 深沢 克己
- 出版者
- 日本学士院
- 雑誌
- 日本學士院紀要 (ISSN:03880036)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.1, pp.1-25, 2020 (Released:2020-11-13)
I. Introduction: the Japan Academy and Freemasonry Freemasonry, though not well known to Japanese people, is an initiatic society which has played an important part in the formation of modern Occidental civilization since the eighteenth century. So that historical connections are not absent between this fraternal association and the Japan Academy. Firstly, two of the founding members of the Academy, Amane Nishi and Mamichi Tsuda, had been initiated into Freemasonry at Leiden as early as 1864. Secondly, its equivalent in the United Kingdom being the Royal Society of London, the Japan Academy developed exchange, notably after the Second World War, with this British institution whose close relations with Freemasonry were known since its foundation in 1660, starting with Elias Ashmole and Sir Robert Moray. Lastly, just as the Japan Academy maintains intimate relations with the Imperial House, so British Freemasonry has been placed under the protection of the royal family since the early nineteenth century. All this justifies the subject of the present paper.(View PDF for the rest of the abstract.)
10 0 0 0 OA 高校世界史と大学の歴史教育とを結ぶもの
- 著者
- 深沢 克己
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.10, pp.10_24-10_27, 2011-10-01 (Released:2012-02-15)
- 参考文献数
- 7
- 著者
- 深沢 克己
- 出版者
- 立教大学
- 雑誌
- 史苑 (ISSN:03869318)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.1, pp.57-76, 2011-12
1 0 0 0 OA 総会講演概要 近世フランス宗教史上の諸問題―信仰と宗派のあいだ
- 著者
- 深沢 克己
- 出版者
- 日仏歴史学会
- 雑誌
- 日仏歴史学会会報 (ISSN:24344184)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.46-48, 2017 (Released:2020-03-28)
- 著者
- 深沢 克己
- 出版者
- 日本西洋史学会
- 雑誌
- 西洋史学 (ISSN:03869253)
- 巻号頁・発行日
- vol.221, pp.59, 2006 (Released:2022-04-01)
1 0 0 0 IR 深沢克己教授退職記念対談 : フランスとアイルランド : 共通の歴史、差異の歴史
- 著者
- 深沢 克己 勝田 俊輔 深沢先生・勝田先生大学院ゼミ生 深沢先生大学院ゼミ生 勝田先生大学院ゼミ生
- 出版者
- 東京大学大学院人文社会系研究科西洋史学研究室「クリオの会」
- 雑誌
- クリオ
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.1-44, 2014-05
1 0 0 0 フリーメイソン団成立史研究の現状と論点
- 著者
- 深沢 克己
- 出版者
- 日本学士院
- 雑誌
- 日本學士院紀要 (ISSN:03880036)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.1, pp.1-25, 2020
I. Introduction: the Japan Academy and Freemasonry<br> Freemasonry, though not well known to Japanese people, is an initiatic society which has played an important part in the formation of modern Occidental civilization since the eighteenth century. So that historical connections are not absent between this fraternal association and the Japan Academy. Firstly, two of the founding members of the Academy, Amane Nishi and Mamichi Tsuda, had been initiated into Freemasonry at Leiden as early as 1864. Secondly, its equivalent in the United Kingdom being the Royal Society of London, the Japan Academy developed exchange, notably after the Second World War, with this British institution whose close relations with Freemasonry were known since its foundation in 1660, starting with Elias Ashmole and Sir Robert Moray. Lastly, just as the Japan Academy maintains intimate relations with the Imperial House, so British Freemasonry has been placed under the protection of the royal family since the early nineteenth century. All this justifies the subject of the present paper.(View PDF for the rest of the abstract.)
- 著者
- 深沢 克己
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.12, pp.2162-2163, 1998-12-20 (Released:2017-11-30)
1 0 0 0 高校世界史と大学の歴史教育とを結ぶもの
- 著者
- 深沢 克己
- 出版者
- Japan Science Support Foundation
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.10, pp.24-27, 2011
1 0 0 0 海港と文明 : 近世フランスの港町
本研究では、近世・近代のヨーロッパにおける宗教的寛容と不寛容の生成・展開について考察することを主たる目的としながらも、イスラム世界・ヨーロッパ中世の専門家を交えることで、この問題を比較史的にも検討することを課題とした。この研究テーマについて各研究分担者がそれぞれにおこなった調査研究の成果を年二回の研究会において全体で討議し、その結果として、次のような共通理解に到達することができた。宗教改革を契機として成立した近世ヨーロッパの宗教的寛容は、国家の役割に従って分類するならば、宗派別の住み分け、法令による異宗派の共存、法律の制定を伴わない実質的な寛容の三つに類型化できる。しかし寛容の堅固な基礎は日常的次元での共存と相互理解にあり、それを可能にする社会の意識改革あるいは文化変革にある。宗教的寛容の歴史的研究においては、この問題への国家による対応のみならず、社会的次元での寛容の実践のあり方、またそれを支える人々の内面的根拠にも分析のメスを入れることも重要であり、両者を総体として論じることが要請される。このように考えるならば、歴史としての宗教的寛容という問題は、近世近代のヨーロッパのみならず、イスラム世界やアジアをも含めた世界史の問題として、あるいは古代・中世という近代的寛容の精神をいまだ知ることのない歴史世界についての考察にも応用可能であるばかりか、まさに宗教的不寛容が蔓延する現代社会において、その解決法を歴史的に探るという意味でもまた有益である。
1 0 0 0 OA フランス近代作家の歴史意識
- 著者
- 中地 義和 月村 辰雄 塚本 昌則 野崎 歓 シモン=及川 マリアンヌ 深沢 克己 新田 昌英 畑 浩一郎 本田 貴久
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2011-04-01
本研究は、19世紀初頭から現代までのフランス文学史の尾根をなす作家のうち、その創作が歴史的出来事の経験や歴史をめぐる深い省察に根ざしている例を精選し、彼らがいかに歴史を内面化しながら作品を創出しているかを探ることを目的とした。またその様態を、各時代の文学理念、言語美学、人文知と関連づけながら、独自の視点からの文学史的通観の構築をめざした。対象になりうる事例の数はおびただしく、個々の事例は作家の生涯に根を張っているため、本格的に扱う対象の数を限らざるを得なかったが、第二帝政期から第三共和政初期、第二次世界大戦期、戦後のポストコロニアル期の文学を中心に、当初の計画に見合う成果が得られた。
1 0 0 0 OA ヨーロッパ・地中海世界における異宗教・異宗派間の相剋と融和をめぐる比較史研究
- 著者
- 深沢 克己 齊藤 寛海 黒木 英充 西川 杉子 堀井 優 勝田 俊輔 千葉 敏之 加藤 玄 踊 共二 宮野 裕 坂野 正則 辻 明日香 宮武 志郎 那須 敬 山本 大丙 藤崎 衛
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 基盤研究(A)
- 巻号頁・発行日
- 2009
当初の研究計画に即して、国際ワークショップと国際シンポジウムを3年連続で組織し、第一線で活躍する合計14名の研究者を世界各国から結集して、キリスト教諸宗派、イスラーム、ユダヤ教などを対象に、広域的な視野のもとで異宗教・異宗派間の関係を比較史的に研究した。これにより得られた共通認識をふまえて、研究者間の濃密な国際交流ネットワークを構築し、研究代表者を編集責任者として、全員の協力による共著出版の準備を進めることができた。