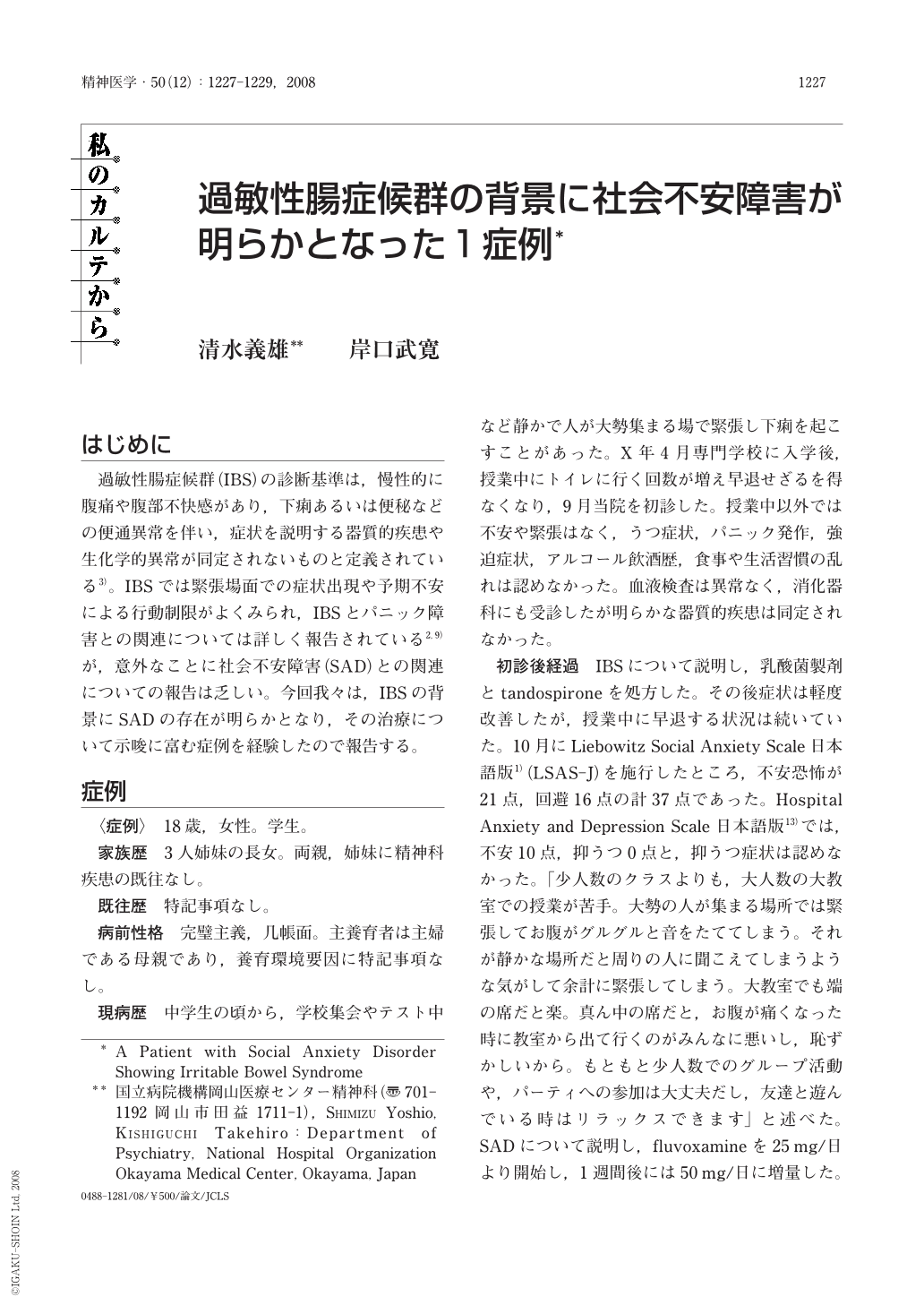2 0 0 0 OA カモ類における相利共生的および寄生的採餌混群
- 著者
- 清水 義雄 中村 雅彦
- 出版者
- The Ornithological Society of Japan
- 雑誌
- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.17-30,64, 2000-07-25 (Released:2007-09-28)
- 参考文献数
- 26
鳥類の混群形成の意義には,相利共生,片利共生,寄生の3種類がある.カモ類の採餌混群では,随伴種は中核種の採餌行動により利用可能となった餌を採餌することで採餌効率を上げ,中核種は随伴種による明確な悪影響を受けないことから,混群形成の機能的な意義は片利共生とされてきた.渉禽類やスズメ目鳥類の混群では,混群サイズの増加にともない餌をめぐる競争や攻撃頻度が増大するため,随伴種のみならず中核種も採餌効率が下がること,人為給餌による餌量の増加は混群形成を抑制することがわかっている.しかしカモ類では,実験的に餌量を操作し,餌量の違いが混群形成の様式,混群サイズ,種間順位,各構成種の採餌行動に与える影響を明らかにした研究はない.そこで本研究は,非繁殖期に混群を形成するコハクチョウ,ホシハジロ,オナガガモに人為給餌を施し,人為給餌前後の混群形成の様式,採食行動,社会行動を比較することにより,餌量が混群形成の機能的意義に与える影響を明らかにすることを目的とした.調査は1996年10月15日から12月28日まで長野県南安曇郡豊科町の犀川貯水池で行なった.貯水池の一部に実験区を設定し,約30kgのイネの種子やもみがらを1日3回与え,餌量を操作した.群れは,単独,同種群,コハクチョウとホシハジロの2種混群,コハクチョウとオナガガモの2種混群,ホシハジロとオナガガモの2種混群,3種混群の6つのタイプに分け,人為給餌前後で各群れタイプの個体数を記録した.人為給餌前後の追従関係,混群タイプの構成割合,採餌割合,攻撃頻度を比較するため,コハクチョウ25個体,ホシハジロ22個体,オナガガモ21個体を一個体当たり8~13分間連続してビデオカメラで録画し,行動を分析した.各種の採餌テクニックや採餌頻度は,群れタイプで異なることが予想されたので,各群れタイプに属するコハクチョウ109個体,ホシハジロ91個体,オナガガモ79個体を一個体につき約5分間ビデオ録画し,人為給餌前後で採餌テクニックと採餌頻度を分析した.採餌混群は,人為給餌前後とも,コハクチョウが首入れ採餌をする前に水中を脚で頻繁にかき回すときに形成された.脚のかき回しにより水底に沈むイネやぬかがわき上がり,ホシハジロはコハクチョウの直下に潜水採餌,オナガガモはわき上がった餌を両種の周囲で採餌した.各種の追従行動から,3種混群の中核種はコハクチョウ,追従種がホシハジロとオナガガモであり,オナガガモはコハクチョウに追従するホシハジロに追従することがわかった.追従頻度は人為給餌後に増加し,その結果3種混群の混群形成率が増加し,群れサイズは約2倍に上昇した.この時,構成種の76%がホシハジロだった.採餌割合は,人為給餌後の3種混群時に3種とも増加した.人為給餌前のコハクチョウの首入れ採餌頻度は3種混群時が最も高く,ホシハジロも3種混群時及びコハクチョウとの混群時に潜水時間を短縮することで潜水採餌の頻度を高めた.オナガガモは3種混群時のみ,ついばみ採餌,首入れ採餌,こしとり採餌の3種類の採餌テクニックを併用し,こしとり採餌では移動距離を短くすることにより採餌頻度を高めた.人為給餌前は3種とも3種混群において採餌頻度を高めているため,採餌混群の機能的意義は相利共生といえる.人為給餌後の3種混群では,コハクチョウだけが採餌頻度を下げ,ホシハジロに対する攻撃頻度を増加させた.これに対しホシハジロとオナガガモは人為給餌前と同様に採餌頻度を高めていた.したがって人為給餌後の採餌混群の機能的意義は,宿主がコハクチョウ,寄主がホシハジロ,オナガガモの寄生関係といえる.3種混群のコハクチョウにとって,ホシハジロの適度な個体数は,自らの採餌頻度を高めるのに有効だが,人為給餌による過度の群れサイズの増加はコハクチョウの採餌行動の混乱,攻撃頻度の増加をもたらし,採餌頻度は減少する.このことから,随伴種であるホシハジロの個体数が採餌混群の適応的意義を決定する主因と考えた.人為給餌の餌は3分以内に水中に沈み,沈んだ餌はコハクチョウが脚でかき回すことではじめてホシハジロ,オナガガモが利用可能となる.それゆえ,カモ類の混群では,与えた餌の絶対量ではなく,中核種により開発され随伴種が利用可能になった餌量が混群形成に影響を与えると考えた.
2 0 0 0 OA 繊維製品のCAD/CAM技術の現状と展望
- 著者
- 太田 健一 渋谷 惇夫 今岡 春樹 清水 義雄
- 出版者
- The Society of Fiber Science and Technology, Japan
- 雑誌
- 繊維学会誌 (ISSN:00379875)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.9, pp.P510-P523, 1994-09-10 (Released:2008-11-28)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 2 3
1 0 0 0 OA 着圧レッグウエアの生理心理的効果に関する研究
- 著者
- 伊藤 綾野 細谷 聡 清水 義雄 武田 大輔
- 出版者
- 日本感性工学会
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.285-289, 2009-01-20 (Released:2016-01-25)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
The purpose of this study was to estimate the usage and comfort levels of wearing sectional pressure socks, and sectional pressure pantyhose through psycho-physiological responses. Experiment samples are socks of sectional pressure, normal socks, pantyhose of sectional pressure and normal pantyhose. The subjects were 20 female university students. Each sample was measured over the same period of time, one day, and checked using electrocardiogram measurement to determine psychological comfort and a questionnaire to determine physiological comfort. From results of electrocardiogram measurement, normal socks decreased psychological comfort more than socks of sectional pressure over time. Moreover, the difference in the psychological comfort between in pantyhose, normal pantyhose or pantyhose of sectional pressure could not be discerned by the questionnaire. From the results of the questionnaire, both socks and normal socks increased knots and discomfort as time passed, but socks of sectional pressure brought down knots and remained at a comfortable level. In pantyhose, pantyhose of sectional pressure felt more comfortable than normal pantyhose for all regions of the leg. However, as comparing thigh to ankle and calf, pantyhose of sectional pressure of comfortable sensation value exhibited discomfort, and physiological comfort showed no significant difference between pantyhose of sectional pressure and normal pantyhose after 6 hours. Therefore, we assumed that comfortable sensation for pressure of clothes was impaired, comparing thigh to ankle and calf. Consequently, we conclude that psycho-physiological comfort for pantyhose of sectional pressure was influenced by pressure of clothes on the thigh.
1 0 0 0 OA 表面筋電図による精神的ストレスの計測方法の提案
- 著者
- 柳沢 国之 菅原 徹 上條 正義 佐渡山 亜兵 清水 義雄
- 出版者
- 自動制御連合講演会
- 雑誌
- 自動制御連合講演会講演論文集 第48回自動制御連合講演会
- 巻号頁・発行日
- pp.257, 2005 (Released:2006-01-01)
精神負荷は中枢系の疲労を生じさせるが、筋電位の発生メカニズムから考えて、表面筋電図に中枢系疲労の影響が出ても不思議ではない。しかし、精神負荷が筋電位に与える影響を研究した例はほとんどない。この両者の関係を明らかにすることは、筋電図の理解や筋電図を用いた新たなストレス評価指標の提案につながる重要な要素である。表面筋電図を用いたバイオフィードバック法によって上腕二頭筋の単一運動単位活動を非侵襲的に計測し、精神負荷の有無によるパルスの発射間隔、振幅、周波数、筋線維伝導速度への影響について検討した。
1 0 0 0 カモ類における相利共生的および寄生的採餌混群
- 著者
- 清水 義雄 中村 雅彦
- 出版者
- 日本鳥学会
- 雑誌
- 日本鳥学会誌 = Japanese journal of ornithology (ISSN:0913400X)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.17-30, 2000-07-25
- 参考文献数
- 26
鳥類の混群形成の意義には,相利共生,片利共生,寄生の3種類がある.カモ類の採餌混群では,随伴種は中核種の採餌行動により利用可能となった餌を採餌することで採餌効率を上げ,中核種は随伴種による明確な悪影響を受けないことから,混群形成の機能的な意義は片利共生とされてきた.渉禽類やスズメ目鳥類の混群では,混群サイズの増加にともない餌をめぐる競争や攻撃頻度が増大するため,随伴種のみならず中核種も採餌効率が下がること,人為給餌による餌量の増加は混群形成を抑制することがわかっている.しかしカモ類では,実験的に餌量を操作し,餌量の違いが混群形成の様式,混群サイズ,種間順位,各構成種の採餌行動に与える影響を明らかにした研究はない.そこで本研究は,非繁殖期に混群を形成するコハクチョウ,ホシハジロ,オナガガモに人為給餌を施し,人為給餌前後の混群形成の様式,採食行動,社会行動を比較することにより,餌量が混群形成の機能的意義に与える影響を明らかにすることを目的とした.<br>調査は1996年10月15日から12月28日まで長野県南安曇郡豊科町の犀川貯水池で行なった.貯水池の一部に実験区を設定し,約30kgのイネの種子やもみがらを1日3回与え,餌量を操作した.群れは,単独,同種群,コハクチョウとホシハジロの2種混群,コハクチョウとオナガガモの2種混群,ホシハジロとオナガガモの2種混群,3種混群の6つのタイプに分け,人為給餌前後で各群れタイプの個体数を記録した.人為給餌前後の追従関係,混群タイプの構成割合,採餌割合,攻撃頻度を比較するため,コハクチョウ25個体,ホシハジロ22個体,オナガガモ21個体を一個体当たり8~13分間連続してビデオカメラで録画し,行動を分析した.各種の採餌テクニックや採餌頻度は,群れタイプで異なることが予想されたので,各群れタイプに属するコハクチョウ109個体,ホシハジロ91個体,オナガガモ79個体を一個体につき約5分間ビデオ録画し,人為給餌前後で採餌テクニックと採餌頻度を分析した.<br>採餌混群は,人為給餌前後とも,コハクチョウが首入れ採餌をする前に水中を脚で頻繁にかき回すときに形成された.脚のかき回しにより水底に沈むイネやぬかがわき上がり,ホシハジロはコハクチョウの直下に潜水採餌,オナガガモはわき上がった餌を両種の周囲で採餌した.各種の追従行動から,3種混群の中核種はコハクチョウ,追従種がホシハジロとオナガガモであり,オナガガモはコハクチョウに追従するホシハジロに追従することがわかった.追従頻度は人為給餌後に増加し,その結果3種混群の混群形成率が増加し,群れサイズは約2倍に上昇した.この時,構成種の76%がホシハジロだった.採餌割合は,人為給餌後の3種混群時に3種とも増加した.<br>人為給餌前のコハクチョウの首入れ採餌頻度は3種混群時が最も高く,ホシハジロも3種混群時及びコハクチョウとの混群時に潜水時間を短縮することで潜水採餌の頻度を高めた.オナガガモは3種混群時のみ,ついばみ採餌,首入れ採餌,こしとり採餌の3種類の採餌テクニックを併用し,こしとり採餌では移動距離を短くすることにより採餌頻度を高めた.人為給餌前は3種とも3種混群において採餌頻度を高めているため,採餌混群の機能的意義は相利共生といえる.人為給餌後の3種混群では,コハクチョウだけが採餌頻度を下げ,ホシハジロに対する攻撃頻度を増加させた.これに対しホシハジロとオナガガモは人為給餌前と同様に採餌頻度を高めていた.したがって人為給餌後の採餌混群の機能的意義は,宿主がコハクチョウ,寄主がホシハジロ,オナガガモの寄生関係といえる.<br>3種混群のコハクチョウにとって,ホシハジロの適度な個体数は,自らの採餌頻度を高めるのに有効だが,人為給餌による過度の群れサイズの増加はコハクチョウの採餌行動の混乱,攻撃頻度の増加をもたらし,採餌頻度は減少する.このことから,随伴種であるホシハジロの個体数が採餌混群の適応的意義を決定する主因と考えた.人為給餌の餌は3分以内に水中に沈み,沈んだ餌はコハクチョウが脚でかき回すことではじめてホシハジロ,オナガガモが利用可能となる.それゆえ,カモ類の混群では,与えた餌の絶対量ではなく,中核種により開発され随伴種が利用可能になった餌量が混群形成に影響を与えると考えた.
1 0 0 0 OA 粒子系モデルによる衣服圧推定に関する研究
- 著者
- 堀場 洋輔 乾 滋 高寺 政行 清水 義雄
- 出版者
- 社団法人 繊維学会
- 雑誌
- 繊維学会誌 (ISSN:00379875)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.12, pp.304-313, 2010 (Released:2011-01-17)
- 被引用文献数
- 2 3
In this paper, we discussed the particle based mechanical model for numerical simulation of clothing pressure. Human body and clothing were represented as an elastic body by particle system, collision between human body and clothing was represented by impulse force based model. The two simulations were conducted to evaluate the validity of the suggested model. In the first simulation, clothing pressure on the elastic cylinder covered with cloth was predicted to evaluate the precision of static clothing pressure prediction. As a result, it was confirmed that it had the accuracy of 0.08 kPa, but there was a room for improvement to predict on the edge of cloth. Although it is considered that the mesh resolution (particle distance) caused the problem, it is important to decide a suitable mesh resolution for purpose because it is directly with calculation time. In the second simulation, we conducted the simulation that winding elbow with sleeve to evaluate the precision of dynamic clothing pressure prediction. As a result, it was observed that clothing pressure changed with elbow flexion. However it was not able to obtain the accurate result caused by numerical instability in the case of fast elbow flexion. It is considered that time step and collision model between clothing and human body on the simulation caused numerical instability. Improvement and implementation of the simulation considering whole body motion for dynamic clothing pressure prediction are our future work.
1 0 0 0 過敏性腸症候群の背景に社会不安障害が明らかとなった1症例
はじめに 過敏性腸症候群(IBS)の診断基準は,慢性的に腹痛や腹部不快感があり,下痢あるいは便秘などの便通異常を伴い,症状を説明する器質的疾患や生化学的異常が同定されないものと定義されている3)。IBSでは緊張場面での症状出現や予期不安による行動制限がよくみられ,IBSとパニック障害との関連については詳しく報告されている2,9)が,意外なことに社会不安障害(SAD)との関連についての報告は乏しい。今回我々は,IBSの背景にSADの存在が明らかとなり,その治療について示唆に富む症例を経験したので報告する。
1 0 0 0 OA 平織物の光透過異方性
- 著者
- 矢崎 美彦 高寺 政行 清水 義雄
- 出版者
- 社団法人 繊維学会
- 雑誌
- 繊維学会誌 (ISSN:00379875)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.10, pp.281-286, 2004 (Released:2006-02-09)
- 被引用文献数
- 4 4
Light transmission property of plain woven fabrics was studied in order to perform the fabric design considering the transmission. A light transmission measurement apparatus which could change incidence and receiving direction of light was developed and the change of the transmission factor by light direction was measured for plain woven fabrics. Because structures of the fabrics are anisotropy, the light transmission property showed anisotropy. The anisotropy of transmission factor was remarkable in large incidence angle, and the minimum or maximum values were showed every Pai/4 cycle. An approximation curve of anisotropy was proposed and the anisotropic light transmission factor was estimated from a measurement at front of a fabric and structure of the fabric based on crimp theory of Peirce.
1 0 0 0 手触り及び肌触り評価のための接触特性計測システム開発に関する研究
[目的と内容]本研究では、衣服の着心地の快適性の一要因である服地の肌触りを評価するための肌触り計測装置を構築し、着衣時における衣服と人体との接触に伴う着心地が評価できるシステムの開発を目的として、圧力分布センサと3軸加速度センサを指先に装着したグローブ型センサを作成して指先の触診動作の特定と3次元力覚センサアレーによる接触子の試作を行った。布の風合い評価時における指先の圧力と加速度を計測し、弁別能力に優れた人間の接触動作から材料特性を検知評価するための特有の触診動作を特定した。力覚センサを2次元に配列し、紙やすりやRTVゴムを試料として摩擦特性、圧縮特性、やわらかさについて測定可能であるか調査した。[成果]触診動作の特定について、下記の知見が得られた。加速度センサを触診動作特徴検出に利用した場合の出力特性を捉え、触診動作を細かく分類し、規定した基本動作と加速度、荷重の変化パターンを対応づけることができた。風合いの評価項目及び被験者ごとの触診動作の違いが指先の総荷重、荷重中心総移動距離を定量的指標として比較することによって明らかになった。接触子の試作実験において、摩擦試験では、試料に3種類の粗さのヤスリを用いて行い、平均摩擦係数、摩擦係数の平均偏差を算出することができた。圧縮試験では、RTVゴムを試料として用い、加圧時と除圧時の荷重値を測定した。相対的な指標として、圧縮エネルギ、圧縮特性による線形性、圧縮のレジリエンスを導出した。やわらかさ試験では、圧縮試験と同様にRTVゴムを試料として用い、センサに加わる摩擦力と圧縮反力の合力をやわらかさの指標として、市販の硬度計で測定したやわらかさの数値と比較した。結果、高い相関関係が得られ、この指標は材料のやわらかさを評価する上で有効であることが分かった。こうした一連の動作をセンサ、もしくは試料にさせることによって、1つのセンサによって、風合いに関する複数の情報を測定できる性能を得た。
1 0 0 0 先進繊維技術科学に関する研究
平成10年度から5年間の先進繊維技術科学に関する研究拠点形成について、研究業績、拠点形成、国際ネットワーク形成等についてまとめ、21世紀COE先進ファイバー工学研究教育拠点への移行を進めた。研究業績面では、8班による研究により、多くの研究論文、特許、事業化を行い、このような基礎研究がナノファイバーテクノロジーの開発、ハイパフォーマンス繊維の開発、新バイオファイバーの開発、オプトエレクトロニクス繊維およびデバイス化技術、環境・ヘルスケア機能繊維開発、特殊機能系、不織布およびそれらの生産システム開発、繊維生産ロボティクス、感性産業要素技術開発など新しい繊維総合科学技術に向けての実績を得た。本COE研究では、萌芽・基礎研究、応用研究から事業化・起業化へ向けての産学連携プロジェクト研究までを行ってきたが、開発研究を行う産学連携拠点としては研究交流促進法の全国で2例目になる、アサマ・リサーチエクステンションセンター(AREC)をキャンパス内に設置し、平成13年2月より稼動させ、5テーマの開発研究に着手した。さらに、国際ネットワークの形成としては、平成14年度は11月に第2回先端繊維上田会議、第2回アジア若手繊維科学技術会議、第1回日米欧3極会議を上田市内のホテルおよび信州大学繊維学部内で開催した。8月にはアジア繊維学会発会式を韓国大邱市嶺南大学で開催し、本拠点が事務局となることを決定した。