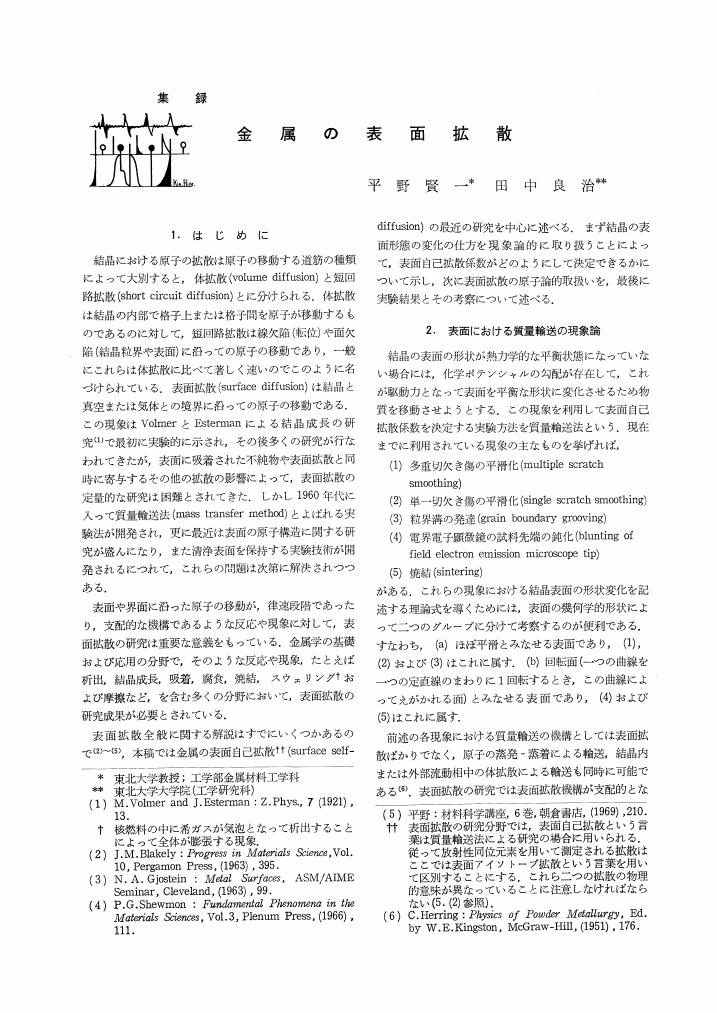2 0 0 0 OA 金属の表面拡散
- 著者
- 平野 賢一 田中 良治
- 出版者
- 社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- 日本金属学会会報 (ISSN:00214426)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.6, pp.341-358, 1970-06-20 (Released:2011-08-10)
- 参考文献数
- 95
- 被引用文献数
- 3 4
2 0 0 0 OA インフォグラフィクスとしてのデータベース・インターフェイスデザイン
- 著者
- 関口 敦仁 田中 良治 高橋 裕行 細谷 誠
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 日本デザイン学会 第64回春季研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- pp.42, 2017 (Released:2017-06-29)
データベースのインターフェイスデザインとして、インフォグラフィクスの考え方を導入することは、視点を明らかにしていく方法論として、効果的な手法である。 そのグラフィックそのものがインターフェイスとしてデータの意味的特徴を明らかにすることで、データグラフィクスの可能性を示すことになる。本研究ではその一例として、h27-28年度の行なった、文化庁メディア芸術連携促進事業「日本のメディアアート文化史構築研究事業」において作成されたデータベース・インターフェイスデザインに基づいたドキュメンテーションのデータデザインとしてのアプローチを示す。
- 著者
- 野本 保夫 川口 良人 酒井 信治 平野 宏 久保 仁 大平 整爾 本間 寿美子 山縣 邦弘 三浦 靖彦 木村 靖夫 栗山 哲 原 茂子 浜田 千江子 佐中 孜 中尾 俊之 本田 雅敬 横田 眞二 須賀 孝夫 森 典子 下村 旭 金 昌雄 今田 聰雄 田中 良治 川西 秀樹 枝国 節雄 福井 博義 中本 雅彦 黒川 清
- 出版者
- The Japanese Society for Dialysis Therapy
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.4, pp.303-311, 1998-04-28 (Released:2010-03-16)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 25 25
硬化性被嚢性腹膜炎 (sclerosing encapsulating peritonitis, SEP) はCAPD療法における最も重篤な合併症の1つである. 平成7-9年度にわたり, 厚生省長期慢性疾患総合研究事業慢性腎不全研究班に参加した『CAPD療法の評価と適応に関する研究班』にてこの病態に焦点をあてSEPの診断基準, 治療のガイドラインを作成し検討を重ねてきた. 今回平成7-8年度の成果を土台に1年間経験を各施設より持ち寄りその実際的な問題点を明らかにし, 改訂するべき事項があればさらに検討を続けることを目的として叡知をあつめ, 平成9年度硬化性被嚢性腹膜炎コンセンサス会議を開催した.今回は主に診断指針の見直しおよび治療および中止基準の妥当性に焦点をあて検討し改訂案を作成した. 診断基準に関しては昨年度に提示した定義に根本的な変更点はなかった. しかし, 治療法に関し若干の手直しを行った. 栄養補給は経静脈的高カロリー輸液 (TPN) を主体に行うが, 具体的投与量を提示した. 一部症例にステロイド薬 (含パルス療法) がSEP発症直後の症例に著効を示した症例に加えて, 一方不幸な転帰をとった症例も報告された. また, 外科的腸管剥離についても再検討を行った. 中止基準に関しては一部の手直しと小児症例に関するガイドラインも新たに加えた.以上当研究班で3年余にわたる作業を行ってきたが, 現時点での諸家のコンセンサスを得たSEP診断治療指針 (案) を上梓することができた. しかしながら本病態の多様性, 治療に対する反応性の相違から基本的な治療方針の提示にとどめた. 今後さらに中止基準を含んだSEP予防法の確立や生体適合性の良い透析液の開発が重要であることはいうまでもない.
- 著者
- 菅野 重樹 田中 良治 大岡 俊夫 加藤 一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.4, pp.339-353, 1985
- 被引用文献数
- 13
これからのロボットは, '力作業'だけでなく'情報作業'をも行う能力をもつ必要がある.そこでこの研究では, 鍵盤楽器演奏可能な人間形知能ロボットを開発することにより, 情報作業に必要となる機能である巧緻性, 高速性, 高度の知的能力などを実現することを目的としている.本論文では, そのためのロボットの4肢構成とその制御に焦点をおき開発した鍵盤楽器演奏ロボット'WABOT-2'の運動系について述ベる.<BR>このロボットは, 5本指をもつ両手と, ペダル操作用両足の4肢からなり, その自由度は合計で50である.このような多自由度ロボットは他に例がなく, その制御法が問題となり, また自律制御を行ううえでは, 楽譜情報から4肢の軌道を決定する方法が重要となる.<BR>以上のような制御問題を解決するために, WABOT-2運動系では53個のマイクロプロセッサからなる3重階層構造のコンピュータシステムを構成した.その上位コンピュータシステムは, 楽譜情報処理を担当し, 3種類に分類した知識, (1) 作業対象物, (2) 作業内容, (3) ロボット機構部仕様をもとに, 視覚系より転送される楽譜データから運指・手首位置の決定, 指・腕・足の各関節角度計算を行う.中位コンピュータシステムは, 上位コンピュータシステムで計算された軌道をもとに, 制御用データを下位コンピュータシステムへ出力し, また必要に応じて各自由度の状態をモニタすることにより協調制御を行う.そして, 下位コンピュータシステムは, 各自由度に1チップマイクロコンピュータが置かれており, ソフトウエアサーボをかけている.このようなコンピュータシステムにより, 50自由度の効率良い制御を実現した.<BR>以上の結果, WABOT-2は電子オルガン中級程度の曲について, 楽譜情報を入力するだけで自動的に演奏が可能となった.
1 0 0 0 OA 指と腕の協調制御手法
- 著者
- 菅野 重樹 田中 良治 大岡 俊夫 加藤 一郎
- 出版者
- 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.4, pp.343-352, 1986-08-15 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 6
人間は指と腕とを巧みに使い分け, 協調させることによって複雑な作業を可能にしている.そこで, ロボットが作業を行う際にも, 人間と同じように, その作業内容に応じて指と腕の特性を生かした指と腕の使い分けをし, 協調させて作業することが効果的であるといえる.本論文では, ロボットが行う作業として, その内容がロボットの指先における連続位置決め点の変化列として記述できる作業をとりあげ, この作業実行上でのロボットの指・腕協調制御の1手法を提案する.次に実際の作業例として, 鍵盤楽器の演奏をとりあげ, 楽譜から指・腕協調制御手法により自動的に指と腕の運動計画を決定する方法について述べる.このような協調を考慮した指・腕運動計画を決定するための評価量としては, ロボットの運動に関する物理量のうち, 時間に関する項を含まない位置 (角度) 変化量を採用した.評価関数は, 各指各関節の変化角, 手先姿勢変化量, 手先姿勢予想変化量, 手首位置移動量, 手首位置予想移動量の5種類の変化量により構成した。この評価関数において, 腕の姿勢変化よりも指の姿勢変化が多くなるように重み付けを行う.次に, 作業実行のためのロボットの行動計画内における指と腕の協調動作の設定方法であるが, ロボットの腕が作業中に単独で高速な動きとなることをさけ, 腕が動く必要がある場合には, 可能な限り指との協調動作となるような行動計画を選定するための評価関数を定めた.以上の方法を, 5本指 (14自由度) と腕 (7自由度) からなる多自由度人間形ロボットに鍵盤楽器演奏作業を行わせる場合に適用した.その結果, 人間の演奏に近いなめらかな指・腕協調動作を含む軌道を自動的に生成することができ, また実際に演奏を実現した.