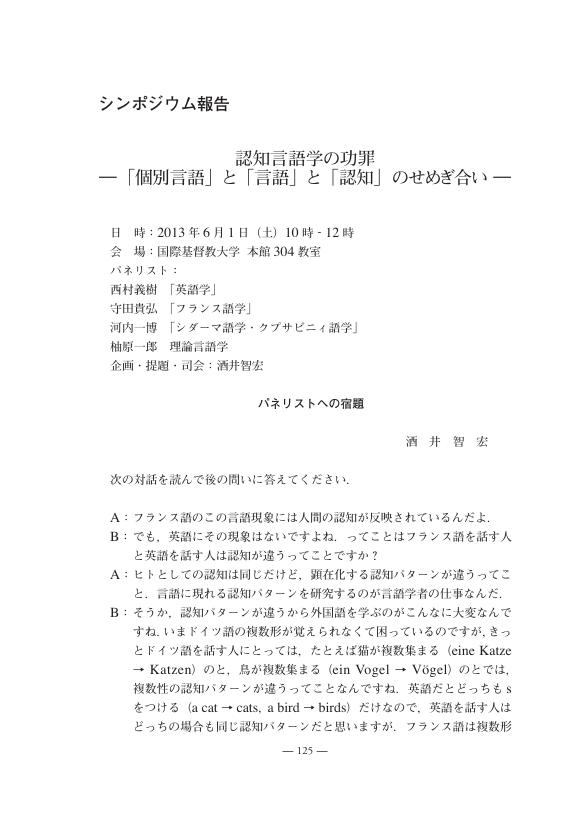4 0 0 0 OA 認知言語学と哲学 ―言語は誰の何に対する認識の反映か―
- 著者
- 酒井 智宏
- 出版者
- 日本言語学会
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.144, pp.55-81, 2013 (Released:2022-03-08)
- 参考文献数
- 41
「言語は人間の世界認識の反映である」という認知言語学的な主張(以下,主張P)は次の二つの問題を提起する。(i)人間が何を認識するのか。(ii)誰が世界を認識するのか。(i)に関して,認知言語学では,外的世界と内的世界の二元論が前提とされる。しかし,認知言語学者が外的世界に関する事実と呼ぶものは,実際にはわれわれが解釈したかぎりでの世界の記述にすぎず,同じことを一元論のもとで述べなおすことができる。それゆえ,認知言語学の二元論は十分に正当化されているとは言えない。(ii)に関して,主張Pを受け入れれば,言語間の変異はすべて話者の世界認識の違いによるという結論に至る。しかし,この結論は逆説的にも「話者の認識から独立した意味」という客観主義的意味観を帰結しうる。かくして,主張Pと対照言語学とのあいだに緊張関係が生じることになる。
- 著者
- 酒井 智宏
- 出版者
- 日本言語学会
- 雑誌
- 言語研究 = Journal of the Linguistic Society of Japan (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- no.144, pp.55-81, 2013-09
2 0 0 0 意味論的外在主義と語用論的調整の関係に関する研究
本研究の目的は、言語表現の意味(に関する知識)が外的環境に依存するとする意味論的外在主義と、言語表現の多義性が個人の心の中にネットワークの形で表象されるとする語用論的調整の考え方を統合することである。ごくわずかな例外を除き、哲学では外在主義が当然視され、逆に言語学では内在主義が当然視されてきた。本研究は、正反対に見える二つの立場がそれぞれの領域で当然視される理由・経緯をいかなる論点先取も犯すことなく追究し、「内在主義を出発点としない内在主義」と「外在主義を出発点としない外在主義」がそれぞれどこまで可能であるかを見定め、どの立場に立ったとしても有効な意味論を構築する。
2 0 0 0 IR メンタル・スペース理論と認知言語学
- 著者
- 酒井 智宏
- 出版者
- 東京大学大学院人文社会系研究科・文学部言語学研究室
- 雑誌
- 東京大学言語学論集 (ISSN:13458663)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.277-296, 2014-09-30
この論文の目的は、メンタル・スペース理論が、表面上は認知言語学の理論の一つであるとされながら、実際には認知言語学者によって敬遠され、認知言語学の概説においても取りあげられることが少ない原因を明らかにすることである。メンタル・スペース理論の主たる研究対象は、自然言語そのものではなく、自然言語を手がかりにして作り出される認知的構築物である。この認知的構築物の構成要素であるメンタル・スペースは、定義が不明確で、明確に定義しようとすればするほど明確な定義から遠ざかるというジレンマを抱えている。また、この認知的構築物がもつとされる性質や制約は、実はわれわれの自然言語に関する理解を密輸入したものであり、独立の根拠によって正当化されたものではない。これらの点で、メンタル・スペース理論の枠組みでの研究は、言語現象をよりよく理解されている認知過程によって直観的に分かりやすいやり方で説明するという標準的な認知言語学の研究手法とは大きくかけ離れている。これが、メンタル・スペース理論が認知言語学者によって敬遠される原因にほかならない。論文 Articles
2 0 0 0 OA 非存在言明のパズルと単称命題
- 著者
- 酒井 智宏
- 出版者
- 東京大学大学院人文社会系研究科・文学部言語学研究室
- 雑誌
- 東京大学言語学論集 (ISSN:13458663)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.., pp.131-151, 2015-09-30
論文 Articles
2 0 0 0 OA トートロジーの主観性の源泉でないもの
- 著者
- 酒井 智宏
- 出版者
- 東京大学大学院人文社会系研究科・文学部言語学研究室
- 雑誌
- 東京大学言語学論集 (ISSN:13458663)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.195-214, 2010-09-30
論文 Articles
2 0 0 0 IR トートロジーにおける等質化概念の混乱とその解消 : 意味の共有をめぐる幻想
- 著者
- 酒井 智宏
- 出版者
- 東京大学大学院人文社会系研究科・文学部言語学研究室
- 雑誌
- 東京大学言語学論集 (ISSN:13458663)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.269-286, 2011-09-30
論文 Articles藤田(1988)および坂原(1992, 2002)に始まる等質化(あるいは同質化)によるトートロジー分析はトートロジー研究の標準理論とさえ言えるまでになっている。この論文では、こうした研究で用いられている等質化概念が混乱に陥っていることを指摘し、その混乱が意味の共有という幻想に根ざしていることを論じる。等質化に基づく理論では、「PであるXはXでない」と「PであってもXはXだ」が対立する場面において、「PであるX」(p)がXであると仮定しても、Xでないと仮定しても、矛盾が生じる。この見かけ上のパラドックスは、Xの意味を固定した上で「pはXなのか否か」と問うことから生じる。実際には、この対立は「Xの意味をpを含むようなものとするべきか否か」という言語的な対立であり、pの所属をめぐる事実的な対立ではない。そのように解釈すればどこにも不整合はなくなる。逆に、そのように解釈しない限り、不整合が生じる。「猫」のような基本語でさえ、話者の問でその意味が常に共有されていると考えるのは、幻想である。そしてこれこそが「言語記号の恣意性」が真に意味していることにほかならない。The homogenization-based approach to the tautology of the form X is X (even if P) contradicts itself regarding whether "X with P", evoked prior to its utterance, falls within the category of X or not. This paradox can be dissolved if we do not consider the meaning of the word X to be shared between speakers when X is X is uttered. This type of sentence does not express a factual proposition but a grammatical proposition about the very definition of X. Such freedom of definition is, we argue, what the arbitrariness of the sign is all about.
1 0 0 0 OA 認知言語学の功罪 「個別言語」と「言語」と「認知」のせめぎ合い
1 0 0 0 IR トートロジーの主観性の源泉でないもの
- 著者
- 酒井 智宏
- 出版者
- 東京大学大学院人文社会系研究科・文学部言語学研究室
- 雑誌
- 東京大学言語学論集 (ISSN:13458663)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.195-214, 2010-09-30
この論文の目的は主観性に基づくトートロジーの分析(主観性仮説)を解体することである。主観性仮説は、(i)一般に文が表す主観性はその文が持つ情報量に反比例する、(ii)トートロジーは情報量がゼロである、という二つのテーゼからなり、(i-ii)によりトートロジーが豊かな主観性を表すという事実を説明しようとする。このうちテーゼ(i)を取り上げ、それがさまざまな言語学的・哲学的難問を引き起こし、そうした難問を回避するべく(i)を修正していくと、結局、主観性仮説自体が解消されてしまうことを示す。論文 Articles
1 0 0 0 OA メンタル・スペース理論と認知言語学
- 著者
- 酒井 智宏
- 出版者
- 東京大学大学院人文社会系研究科・文学部言語学研究室
- 雑誌
- 東京大学言語学論集 (ISSN:13458663)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.TULIP, pp.277-296, 2014-09-30
この論文の目的は、メンタル・スペース理論が、表面上は認知言語学の理論の一つであるとされながら、実際には認知言語学者によって敬遠され、認知言語学の概説においても取りあげられることが少ない原因を明らかにすることである。メンタル・スペース理論の主たる研究対象は、自然言語そのものではなく、自然言語を手がかりにして作り出される認知的構築物である。この認知的構築物の構成要素であるメンタル・スペースは、定義が不明確で、明確に定義しようとすればするほど明確な定義から遠ざかるというジレンマを抱えている。また、この認知的構築物がもつとされる性質や制約は、実はわれわれの自然言語に関する理解を密輸入したものであり、独立の根拠によって正当化されたものではない。これらの点で、メンタル・スペース理論の枠組みでの研究は、言語現象をよりよく理解されている認知過程によって直観的に分かりやすいやり方で説明するという標準的な認知言語学の研究手法とは大きくかけ離れている。これが、メンタル・スペース理論が認知言語学者によって敬遠される原因にほかならない。
1 0 0 0 IR 非存在言明のパズルと単称命題
- 著者
- 酒井 智宏
- 出版者
- 東京大学大学院人文社会系研究科・文学部言語学研究室
- 雑誌
- 東京大学言語学論集 (ISSN:13458663)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.131-151, 2015-09-30
この論文の目的は、固有名に関する記述主義をサポートする証処とみなされてきた非存在言明のパズルが、実は、記述主義と相反する立場である単称主義をサポートするものであることを示すことである。固有名に関するもっとも素朴でもっとも直観にかなった考え方は、「固有名=個体につけられたラベル」というJ.S.ミルに代表される考え方である。ところが、この考え方のもとでは「ペガサスは存在しない」のような非存在言明がパズルを引き起こすことが知られている。「ペガサス」によって指示される個体についてそれが「存在しない」と述べるのは矛盾でしかないからである。そこで、ラッセルは、自然言語の固有名が実は固有名ではなく偽装された記述であるとする記述主義を唱えた。しかし、クリプキが指摘したように、固有名に関する記述主義には問題が多い。それゆえ、もし可能であれば、ミル説と非存在言明の問題とを両立させることが望ましい。この論文では、非存在言明を文法的注釈とみなす野矢(2002/2006)の考え方と、「切り裂きジャック」のような記述名を「いずれ記述を介さずに対象を指示できるようになることを期待された名前」とみなすRecanati(1993)の考え方を統合し、「PNは存在しない」が「『PNはQだ』は単称命題ではない」(Qは任意の述語)を意味すると考えることで、ミル説と非存在言明の両立が可能であることを示す。「『PNはQだ』は単称命題ではない」という意味記述は単称主義を前提とするため、この意味記述を採用すれば、単称主義のもとで非存在言明のパズルが自動的に解決されることになる。The purpose of this paper is to show that the puzzle of non-existential statements, which has long been considered to support Descriptivism, can in fact be accounted for within Singularism as suggested by J.S. Mill. The Millian view on the semantics of proper names regards proper names as labels for individuals. This view, however, is known to give rise to a puzzle when confronted with a non-existential statement such as "Pegasus does not exist", to the extent that the statement denies the very existence of Pegasus denoted by the subject NP. According to Descriptivism as defended by Russell, this puzzle suggests that alleged proper names in natural language are not proper names in the true sense of the term, but disguised descriptions. Since Descriptivism raises more problems than it solves, however, it is better to find a solution for the puzzle within the Millian framework. By drawing on Noya's (2002/2006) idea that non-existential statements are nothing but grammatical statements on the use of proper names, as well as on Recanati's (I 993) view that de Jure any proper name demands that its referent be thought of non-descriptively, this paper argues that the statement "PN does not exist" means that for any predicate Q, "Q (PN)" fails to express a singular proposition. The fact that this semantic description presupposes Singularism as opposed to Descriptivism suggests that, as against the traditional conception mentioned above, non-existential statements raise no puzzle for the Millian view on proper names.論文 Articles
1 0 0 0 OA 意味排除主義と自然言語の規範性に関する研究
- 著者
- 酒井 智宏
- 出版者
- 日本フランス語フランス文学会
- 雑誌
- フランス語フランス文学研究 (ISSN:04254929)
- 巻号頁・発行日
- no.95, 2009-09-10
1 0 0 0 OA 矛盾文と自然言語における規範性の源泉
- 著者
- 酒井 智宏
- 出版者
- 東京大学大学院人文社会系研究科・文学部言語学研究室
- 雑誌
- 東京大学言語学論集 (ISSN:13458663)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.255-276, 2012-09-30
論文 Articles