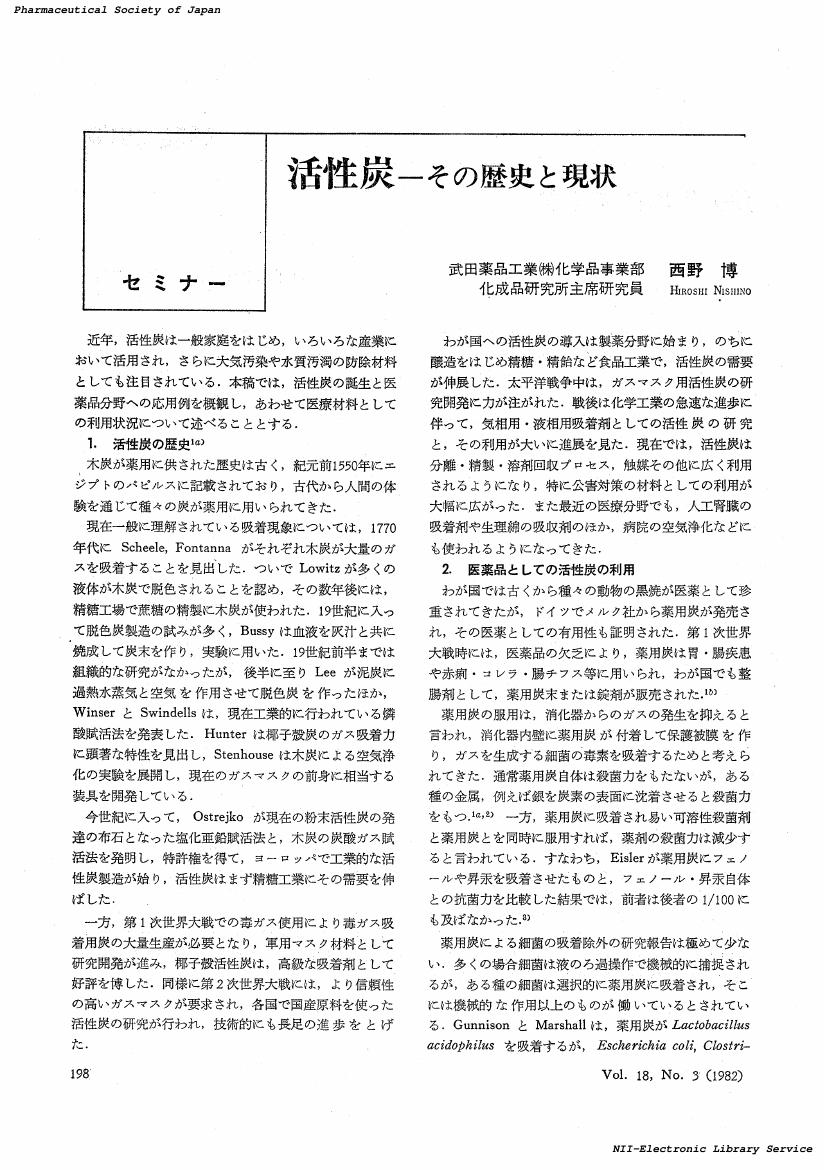4 0 0 0 OA 第10回 御岳百草丸
- 著者
- 浦沢 昌徳
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.12, pp.1192-1193, 2013-12-01 (Released:2016-09-26)
4 0 0 0 OA 野田春彦 : 東京大学理学部教授(人と言葉)
- 著者
- M・A
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.5, pp.360, 1968-05-15 (Released:2018-08-26)
4 0 0 0 OA 活性炭-その歴史と現状
- 著者
- 西野 博
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.3, pp.198-203, 1982-03-01 (Released:2018-08-26)
4 0 0 0 OA 緑茶によるインフルエンザの予防効果
- 著者
- 鈴木 隆
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.11, pp.1080-1084, 2013-11-01 (Released:2016-09-26)
4 0 0 0 OA アトピー性皮膚炎のバリア機能の解明と創薬
- 著者
- 大塚 篤司 椛島 健治
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.10, pp.973-977, 2014 (Released:2016-09-30)
- 参考文献数
- 22
我が国には約40万人のアトピー性皮膚炎(atopic dermatitis;AD)の患者がいるとされる.ADは慢性的なかゆみを伴う皮膚疾患であり,その背景として湿疹ができやすい体質があると考えられている.その体質として皮膚の乾燥が候補因子であったが,十分な解析はなされていなかった.ところが,2006年にADの有病率とフィラグリン遺伝子の相関関係が指摘されたことで,皮膚のバリア機能と免疫とのクロストークが注目を集めることとなった.
4 0 0 0 OA ワクチンの効果はリンパ球の体内時計の影響を受ける?
- 著者
- 加藤 百合
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.10, pp.1020, 2017 (Released:2017-10-01)
- 参考文献数
- 4
朝にインフルエンザワクチンを接種すると,午後に接種する場合と比較して抗体力価が上がることから,概日リズムにより免疫システムが制御されていることが示唆されている.このメカニズムの解明は,様々な病原体に対する効率的なワクチン療法の確立に重要である.ワクチン接種による免疫獲得には,リンパ球が重要な役割を担う.リンパ球は抗原を探索するために,血液からリンパ節へ移行し(ホーミング),その後,遠心性のリンパ管を流れるリンパ液へと放出され(遊出),全身を循環する.これまでに免疫応答が,活動期と休息期で日内変動することは報告されていたが,リンパ球の概日リズムへの関与は長らく議論があった.本稿では,リンパ球が概日リズムで制御されることによって,リンパ節へのリンパ球の移行,リンパ節からのリンパ球の放出,さらには免疫応答が調節されていることを明らかにした,Druzdらの研究成果を紹介する.なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.1) Long J. E. et al., Vaccine, 34, 2679-2685(2016).2) Scheiermann C. et al., Nat. Rev. Immunol., 13, 190-198(2013).3) Hemmers S. et al., Cell Rep., 11, 1339-1349(2015).4) Druzd D. et al., Immunity, 46, 120-132(2017).
4 0 0 0 レセルピンの立体化学表記の訂正
- 著者
- 小平 京佳 阿部 匠
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.8, pp.757-759, 2020 (Released:2020-08-01)
- 参考文献数
- 8
『日本薬局方』収載レセルピンの立体化学表記の間違いを見つけた. 構造確認の重要性を示す好例であるとともに, 間違いを最小限にする表記法について考える良い機会でもあるのでその経緯と詳細について紹介する.
4 0 0 0 OA 薬剤師っていらなくない?
- 著者
- 富野 浩充
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.6, pp.545-548, 2019 (Released:2019-06-01)
単行本が発行されてから多数の記事で取り上げていただいていますが、「薬剤師っていらなくない?」というコピーがよく使われています。コミックスを開いて2ページ目にあるこのセリフには、かなりの破壊力があるようです。病院薬剤師漫画「アンサングシンデレラ」医療原案担当としての活動内容、ライター活動の経緯などを伝えます。
4 0 0 0 Vaccine hesitancy 予防接種への逡巡
- 著者
- 中山 哲夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.11, pp.1009, 2019 (Released:2019-11-01)
2019年になって麻疹の流行は日本だけでなく世界中で患者報告数が増加してきている。こうした背景にはvaccine hesitancyが深く関係している。科学的な根拠のない流言、批判的主張からワクチン接種を躊躇している人々が増えつつある。こうした主張に科学的なエビデンスはなく、ワクチンに対する不安・誤解を招いている。惑わされることなく科学的なものの見方を培い正しい選択をしてほしいものである。
4 0 0 0 OA 反復社会挫折ストレス
- 著者
- 北岡 志保 古屋敷 智之
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.7, pp.702_2, 2017 (Released:2017-07-01)
げっ歯類を用いたうつ病モデルの1つである.このモデルでは,解析対象のマウスを体格が大きく攻撃性の強いマウスの攻撃に1日10分間,10日間連続で曝露し,その後,マウスの行動変化を調べる.反復社会挫折ストレスは社会性の減弱(社会忌避行動の誘導)や,不安亢進,快感覚の消失といったうつ病でみられる症状を誘導する.反復社会挫折ストレスによる社会忌避行動の誘導は抗うつ薬の反復投与により改善する.つまり,このモデルは予測妥当性を満たすうつ病の動物モデルとして注目されている.
4 0 0 0 生物活性をもった天然有機化合物とのめぐりあい(研究室)
- 著者
- 竹本 常松
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.12, pp.890-892, 1968
4 0 0 0 OA 編集後記
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.9, pp.902, 2016 (Released:2016-09-02)
4 0 0 0 OA 第2回 日本の医療から学んだこと
- 著者
- Hari Prasad DEVKOTA
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.67, 2018 (Released:2018-01-01)
私はネパールのポカラ大学薬学部を卒業後、10年前に来日し、熊本大学で薬学博士の学位を取得し、現在は熊本大学の教員として働いている。来日後から今まで、日本の生活、医療制度、高齢化社会、地域医療について学んだこと、気づいたことをまとめた。また、専門分野である南アジアの伝統医療について日本から学んだことについてもふれた。
4 0 0 0 DILIsym®を用いた薬剤誘発性肝障害の臨床予測
- 著者
- 齊藤 隆太
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.5, pp.420-424, 2018 (Released:2018-05-01)
- 参考文献数
- 17
薬剤誘発性肝障害は創薬における大きな課題の1つだが,ヒトでの肝障害リスク評価は十分と言えないのが現状である.薬剤誘発性肝障害予測ソフトウェアDILIsym®は様々な肝障害評価系のデータや臨床・非臨床PKデータからヒトでの肝障害リスクを評価することができるため,近年注目されている技術である.本稿ではDILIsym®について,コンセプトや開発の歴史,最近のトピック,具体的な解析事例について紹介する.
4 0 0 0 水素医学の現状:基礎医学から臨床医学へ
- 著者
- 太田 成男
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.8, pp.767-771, 2012
- 参考文献数
- 20
4 0 0 0 生物活性化合物と生理活性物質という言葉の使い方について
- 著者
- 日野 亨
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.7, pp.716-717, 1998
4 0 0 0 OA ダメな統計学 悲惨なほど完全なる手引書
- 著者
- 田中 智之
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.12, pp.1207_3-1207_3, 2017 (Released:2017-12-01)
4 0 0 0 自閉症:発症機序とモデル動物への原因遺伝子からのアプローチ
- 著者
- 松本 裕司
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.9, pp.890-890, 2012
4 0 0 0 薬学領域での統計学の本 : 生物系を主に
- 著者
- 佐久間 昭
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.10, 1985
4 0 0 0 OA 私の年賀状 : その1
- 著者
- 金尾 清造
- 出版者
- 公益社団法人日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, 1979-01-01