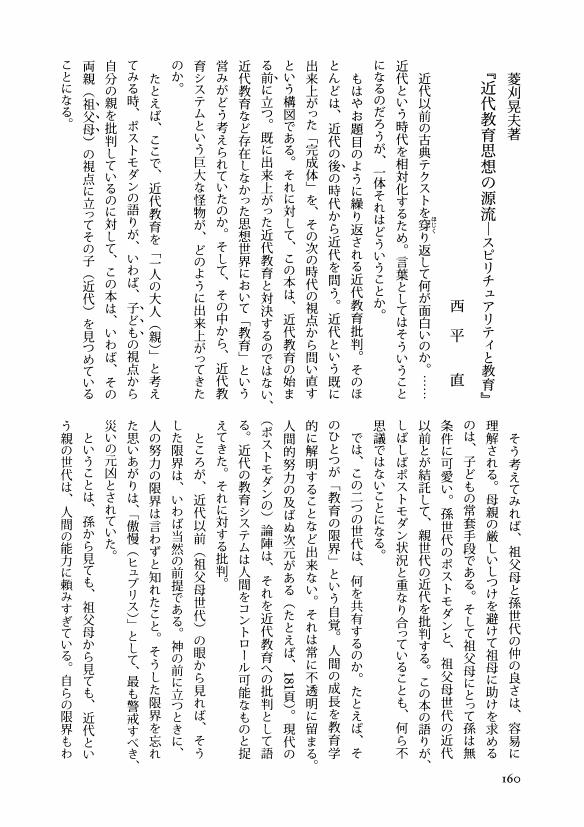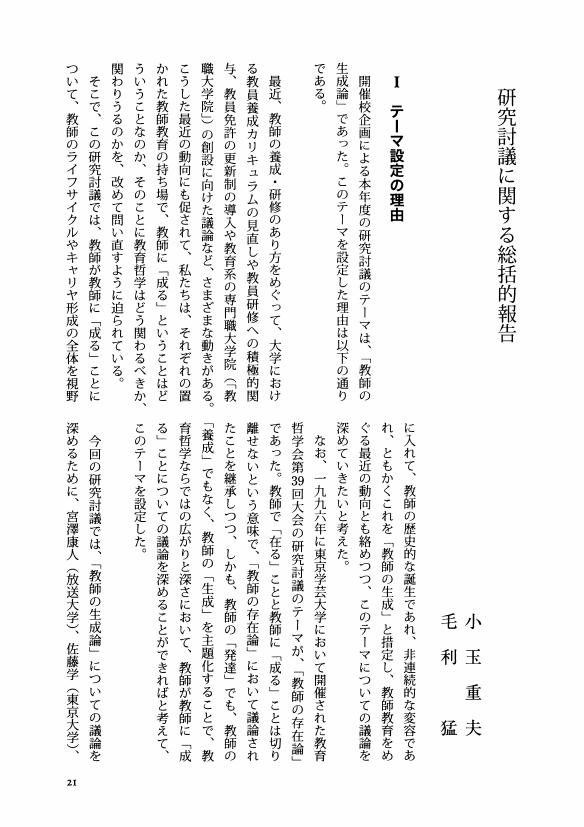1 0 0 0 OA 齋藤直子著『内なる光-デューイとエマソンにおける道徳的完成主義の教育』
- 著者
- 市村 尚久
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.94, pp.98-113, 2006-11-10 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 18
久々にスケールの大きな、しかも読み応えのある力作に出会った。アメリカ教育哲学の新たな在り方を視野に入れて、デューイ自然主義成長論の再解釈を試みた論考をこれから紹介する。齋藤直子により、この書評の主題のように英文で書かれ、アメリカで刊行された近著である。本書の主題および各章の日本語標記は、著者自身によるものであることをはじめに断っておきたい。本書『内なる光-デューイとエマソンにおける道徳的完成主義の教育』は、アメリカ哲学界で、アメリカの哲学叢書としてフォーダム大学出版部から叢書第十六番目の一巻として二〇〇五年に刊行された単著である。著者は本書がこのような専門学術書としてアメリカで上梓されるに至るまで、本書に関連する相応の研究業績を挙げられてきたという研究歴をもっている。そのことは本稿の後段で紹介し、具体的な関連論文名は本稿の末尾に列挙することとして、先ずは本書の形式的な構成から示したい。
- 著者
- 佐藤 隆之
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.94, pp.114-121, 2006-11-10 (Released:2009-09-04)
批判も少なくないなか、それでも廃れることなく、いまなお個性教育をめぐる主張や解釈が連綿と繰り出されている。この現状をみるにつけ、「今日、 “個性” という言葉は麻薬のような働きをもっている」 (iii頁) という本書の冒頭を飾る一文に、共感を覚える読者も少なくないだろう。そのような状況において、「教育における個性尊重は何を意味するか」という問いに答えることは容易ではない。それでは、過去についてはどうか。とくにわが国に直接間接に影響を与えてきたアメリカの進歩主義教育における個性教育の遺産について、私たちはどこまで理解しているのだろうか。過去を清算しきれないままに新たな言説を上積みすることにより、個性教育をめぐる理解や事態をますます混乱させ、生産的な議論を難しくしてはいないか。その遺産から個性教育について示唆をえようとすることそれ自体は目新しい試みではないにせよ、多種多様なその改革の思想、目的、方法、実践、結果などを検討し、それらを総括して進歩主義教育ならではの特徴を解明することは、今なお課題として残されているといってよいだろう。本書の副題に掲げられる「教育における個性尊重は何を意味してきたか」という問いに答えることは、それが個性という「麻薬」に対する解毒剤を手にするうえでの鍵を握ることは重々承知していても、その対象の大きさやとらえ難さゆえに、やはり容易ではないのである。著者の宮本氏はこれまで、「個性尊重の教育」というテーマに、アメリカ進歩主義教育を主たる対象として一貫して取り組んでこられた。その研究成果の集大成として、二〇〇三年一二月、京都大学に提出された学位論文である本書は、その難問に真正面から挑んだ労作である。本研究の直接の課題は、「個性概念」の明確化と、「一斉授業の改革としての個別化・個性化の思想と実践の系譜」の解明にある (四頁) 。ここに示されるとおり、浩潮な本書の考察を貫く視点であり対象となっているのは、教育の個別化・個性化である。詳しくいえばそれは、「学年と学級を定め、一人の教師が多数の生徒を対象に、同一の教材を一斉に教授するという一斉教授の方法」 (=「学級一斉教授」) の画一性や受動性を批判し、個々の個人差や自発性に応えることをめざして開発が進められた方法である (五-六頁) 。そのうち、個別化とは、「ひとりひとりの個人差に応ずるために教育方法の画一性を打破する」方法であり、個性化とは、「子どもひとりひとりの能動性を保障する」方法と定義される (七頁) 。本書の内容やその特徴について解説をくわえる前にまず、課題とされる「個別化・個性化の思想と実践」について簡単にふれておきたい。それは長年の研究の蓄積から導出された著者ならではの着想に支えられており、本書のねらいや意義を体現していると考えられるからである。第一に、この簡にして要を得た独自の視点に考察全体が貫かれていることにより、多彩であるがゆえに錯綜している進歩主義教育における個性教育の理論や展開が、包括的に論じられている。第二に、個別化・個性化の「思想と実践」を考察の対象とするとあるとおり、教授理論の基底にある「思想」にまで踏み込む精緻な検討が展開されている。それにより、個性教育のルーツをひもとき、整理しながら、その原理や特質が照射されている。第三に、その「思想」とならんで重点がおかれている「実践」とは、授業実践ではなく、教育に関わる行政、政策、制度、理論などを包括している (v頁) 。本研究はこの広義の実践に注視した「教育実践学」の成果であり、教育現場を強く意識しながら、個性教育の実態について多面的に切り込む論考となっている。そのため、著者は安易に過去を現代に結びつけることはしないが、現代の教育実践にきわめて示唆的な内容となっている。最後に、その思想と実践の分析にあたっては、著作・論文以外に、統計、報告書、時間割、授業案などを含む膨大な史料が収集されている。それに基づいた実証的考察は、説得力に富んでいる。 (その一端をなす貴重な写真や雑誌は二〇頁にわたって巻末に掲載され、本書の論考を補完するとともに興趣を添えている。本文と併せてご覧いただきたい。) 以上の諸点に特徴が認められる課題について、次のような構成で考察が展開されている。紙幅の関係から節以下は省略して示す。
1 0 0 0 OA 川村覚昭著『島地黙雷の教育思想研究-明治維新と異文化理解-』
- 著者
- 皇 紀夫
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.94, pp.122-127, 2006-11-10 (Released:2010-05-07)
本書はすでに「教育学研究第72巻4号」の〈図書紹介〉において、さらに「日本仏教教育学研究第14号」「関西教育学会研究紀要第6号」の〈書評〉で取り上げられており、本誌で改めて書評することは屋上屋を架すの感なきにしもあらずであるが、編集委員会から1年前に依頼を受けていた関係上、先行の書評などを参照して評者なりの論評をしてみたい。本書の書評としては「関西教育学会研究紀要」誌での松井春満氏のものが学術的な評価として簡潔にして要を得ていると思う。評者は明治期の教育や仏教教育の分野を専門とする研究者ではないため、以下の論述では専門的な知識の不備による誤解が含まれているかも知れないが、興味深い研究テーマに引き込まれた好奇心からの勇み足としてご寛恕いただきたい。本書の構成と方法論的立場に関しては先の〈図書紹介〉に詳しいからこれを省略して、評者の関心 (臨床教育学) に従ってその内容や研究手法を独自に紹介し評価と批判を加えることにしたい。
1 0 0 0 OA 田中智志著『人格形成概念の誕生-近代アメリカの教育概念史-』
- 著者
- 松浦 良充
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.94, pp.128-136, 2006-11-10 (Released:2009-09-04)
教育哲学と教育思想史研究との関係をどのように考えるか。この問題を、私たちの学会はくりかえし問うてきた。現在でもさまざまな立場や議論が存在するだろう。これまで教育哲学の名の下に展開してきた研究の少なからぬ部分が、教育思想、特に欧米のそれらの紹介や分析であったことは周知の事実である。そしてそのような実態に対して、しばしば強い懸念が示されてきてもいる。他方教育哲学は、現在の日本の教育問題に対して考察を挑もうとするとき、その枠組みをなす概念装置を必要とする。そうした概念装置をより精緻で有効なものに練りあげるために、既存の教育思想を資源として活用することは論難されるべきことではない。しかも「教育」という概念や認識の枠組みが、近代社会において生成した歴史的な構成物であることを考慮に入れれば、欧米の教育思想が参照されることには一定の正当性があると言えよう。もっとも、教育哲学の名の下に展開している教育思想の研究が、必ずしも教育思想史研究になっているわけではない。それらの多くは、その教育思想が課題として直面したはずの社会的状況や歴史的文脈とは無関係に、ただ抽象的な概念のみが抽出されて論じられることが多いからである。かといつて社会的・歴史的視点がないのが教育哲学、あるのが教育思想史ということにはならない。実は、現代日本の教育問題自体が歴史的文脈のなかで構成されているのである。したがって教育哲学の考察も必然的に歴史的な視野をふまえて展開されるべきである。そうした視野や文脈を無視するからこそ、教育哲学が教育の現実的問題に有効なはたらきをなしえていない、との批判を浴びることにもなるのであろう。一方、教育思想史研究も、それが単なる過去や異国へのディレッタント的な関心以上のものをめざすのならば、現代の教育問題とそれを構成している歴史的文脈と無関係なところに、その研究課題を設定するわけにはゆかない。その意味で、教育哲学と教育思想史研究は、それぞれが対象とする課題の歴史的文脈を照合しつつ、共有できる概念装置を練りあげるために協働することができるはずである。そしてその接点を構成するのが、教育にかかわる概念史研究である。
1 0 0 0 OA ヤスパースの哲学と教育学の間で 交わりの教育学のナラトロジー
- 著者
- 広川 義哲
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.94, pp.21-38, 2006-11-10 (Released:2010-05-07)
- 参考文献数
- 48
Recently, attention has been drawn to historical-pedagogic anthropology proposed by Ch. Wulf. It raised the problem that conventional pedagogic anthropology is ineffective as it simply discusses the human being in general. While the universal requirement has lost its ground, historical-pedagogic anthropology emphasizes that the theme discussed is historical and that the person discussing the theme has a historical perspective. Based on that point, this paper takes Karl Jaspers' communication theory as a theory constructed through his historical life, and pedagogy, which has been assimilating it into its own territory, as an archive constructed in historical swell. It then focuses on displacement that takes place when Jaspers' communication theory is assimilated into pedagogy.At this point, an idea of autobiographical pact (Ph. Lejeune) is helpful. This is a pact which an author establishes as a condition for determining an autobiographical form. When we apply this idea to Jaspers' Existential Elucidation, we can find some autobiographical pacts in that text. We can, therefore, regard Existential Elucidation as an autobiographical text. And then, if we acknowledge an inseparability of his life and his thought, we can find autobiographical space in this text and his Philosophical Autobiography. The first person narrative induces a polarity of persons (É. Banveniste). Namely, Jaspers' narrative in his philosophy opens resonant space for pedagogy. There is a symmetrical relationship between autobiographical space and resonant space.Moreover, on this boundary pedagogy hasbeen assimilating Jaspers' narrative of communication into its category of educational aims. If that is the case, description about the “I” has been remodeled into anorm through pedagogical filter. That is “cooperative construction of description and normatization” operates on this displacement.
- 著者
- 丸橋 静香
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.94, pp.39-56, 2006-11-10 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 39
Auf der Grundlage der Einsicht, dass ein nicht-individualistisches Konzept der Verantwortung für spezifisch gegenwärtige Problematik wie das Umweltsproblem notwendig ist, versucht dieser Aufsatz, eine neue Bedeutung des “verantwortlichen Seins” zu bestimmen und pädagogische Aufgaben festzustellen, die zu losen sind, damit jenes “verantwortliche Sein” verwirklicht werden kann.Zuerst wird erklärt, wie man in der Pägagogik ein “verantwortliches Sein” als Erziehungsziel bisher diskutiert hat. Immer ging es dabei um individuelle Zurechnung. Individuelle Zurechnung taugt aber nicht mehr fiir spezifisch gegenwärtige Problematik.Um das traditionelle, individualistische Konzept der Verantwortung zu überwinden, wird zweitens K.-O. Apels Konzept der “Mitverantwortung” in Hinblick auf seine Validität in der gegenwärtigen Situation untersucht. Demnach wird ein “verantwortliches Sein” zeitgemäß bestimmbar, und zwar als ein Sein, das so eingestellt ist, an dem Diskurs zur Losung von Problemen bereitwillig teilzunehmen, wenn sie für ihn auch nicht direkt von Belang sein dürften.Hervorbringung solcher Einstellung hängt davon ab, ob man zu einer universalistischen Perspektive gelangt hat. Anhand der Diskursanthropologie von M. Niquet und H. Burckhart wird drittens dargestellt, wie die universalistische Perspektive durch Erfahrung der Teilnahme an Diskurs moglich wird.Daraus folgt schließlich : für eine Verwirklichung des “erantwortlichen Seins” ist es konstitutiv, dass intersubjektive Diskussion einen wesentlichen Teil des Bildungsprozesses ausmacht.
1 0 0 0 OA 教育哲学を考える
- 著者
- 鳶野 克己
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.94, pp.73-74, 2006-11-10 (Released:2009-09-04)
- 著者
- 山口 恒夫
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.94, pp.75-79, 2006-11-10 (Released:2010-05-07)
- 参考文献数
- 6
今日の大学における教員養成教育の課題のひとつは、学校での「体験」と大学での「省察 (reflection) 」をいかに有機的に結びつけるかという点にある。日本教育大学協会の答申「教員養成『モデル・コア・カリキュラム』の検討」 (二〇〇四年) をも契機として、「〈体験〉-〈省察〉的な科目群」や「臨床経験科目」が多くの教員養成系大学・学部の教員養成プログラムに導入されている。そこでは、教員の職務の体験や子どもたちとの触れ合いを目的として、教育現場での体験的学修の機会が養成段階の初期から提供されている、しかし、子どもとの触れ合いを積み重ね、教員の職務にいわば身体知によって接近しても、それが単なる児童生徒の操作技法の獲得に終わっては、教師の職務を単なる専門技術者のレベルに貶めることになりかねない。重要なのは、「臨床の場」で求められる判断力や子どもたちとの相互作用を省察する態度と方策を身につけることである。臨床の場とは、状況に捲き込まれつつ、当事者同士がコミュニケーションを進展させながら「関係」を構築する場である。こうした臨床の場に立つケアの専門家-教師や看護師等-には、状況にコミットしつつ、自己自身の応答や作用過程に対して不断にモニタリング=リフレクションする能力が求められる。「省察=リフレクション」は、ドナルド・ショーンによる「反省的実践家 (reflective practitioner) 」の概念の提唱を契機として、教員養成ばかりでなく、医学教育・医師養成や看護教育においても重要なキーワードとなっているが、リフレクションの意義やその理論的基礎づけは必ずしも十分ではない。筆者らの研究グループが取り組んでいるプロセスレコードによる「臨床経験」のリフレクションの試みは、教育実践の現場に立ち会う教員や実習生と子どもとの関係の生成過程をつぶさに浮かび上がらせる方法の探究であるとともに、子どもとの多様な相互作用場面における教師の判断・応答の適切性とは何か、また、その適切さの根拠はどこに求められるべきかを明らかにする試みでもある。
1 0 0 0 OA フロイトと精神分析を教育哲学において問うこと
- 著者
- 下司 晶
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.94, pp.80-84, 2006-11-10 (Released:2010-05-07)
- 参考文献数
- 16
教育哲学においてあるいは教育哲学として、フロイトと精神分析を問うことには、いかなる意味があるのか-一九九八年に初めての研究発表を本学会にて行って以降 (下司一九九九) 、このような問いかけをしばしば受け、その都度答えに窮するとともに、言語化できない違和感が蓄積されてもきた。
1 0 0 0 OA 川村覚昭著『教育の根源的論理の探究-教育学研究序説-』
- 著者
- 大西 正倫
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.93, pp.158-159, 2006-05-10 (Released:2009-09-04)
1 0 0 0 OA 菱刈晃夫著『近代教育思想の源流-スピリチュアリティと教育』
- 著者
- 西平 直
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.93, pp.160-163, 2006-05-10 (Released:2009-09-04)
1 0 0 0 OA カール・ノイマン著小笠原道雄・坂越正樹監訳『大学教育の改革と教育学』
- 著者
- 山元 有一
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.93, pp.166-168, 2006-05-10 (Released:2009-09-04)
1 0 0 0 OA スタンリー・カベル著齋藤直子訳『センス・オブ・ウォールデン』
- 著者
- 田中 智志
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.93, pp.169-171, 2006-05-10 (Released:2009-09-04)
1 0 0 0 OA クリストフ・ヴルフ編藤川信夫 監訳『歴史的人間学事典 第二巻』
- 著者
- 高橋 勝
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.93, pp.171-173, 2006-05-10 (Released:2009-09-04)
- 著者
- 奥野 佐矢子
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.93, pp.85-101, 2006-05-10 (Released:2010-05-07)
- 参考文献数
- 38
It is a specific conceptualization of the twentieth century, the century of the linguistic turn, that language is in general 'performative'. Building from Austinian notion of performativity and Althusseruan notion of interpellation, this essay explores the production/construction of the subjects based upon the main work of Judith Butler.Butler begins with her contention that as linguistic beings, our existence is unavoidably dependent on language. For her, the subject is constructed through the process of subjection; it can be explained as the simultaneous process of becoming the subject and being compelled to participate in reproducing dominant discourse. Butler's understanding that the status of the subject is thus constituted and her insistence that the compelled reiteration of conventions is the essence of performativity help us clarify how the subject is unwittingly complicit in sustaining hegemonic social structures.To deconstruct this discursive and social formation involving the subject, it is necessary to focus on the very process of the construction of the subject. As Butler explains the subject is subjected to a norm while being the agent of its use. Accordingly if the formation of the subject is the repeated inculcation of the norm, it will be possible to repeat that norm in unexpected ways. The norms of performative identity resemble the sign, and they are vulnerable to the recitation of the same and semantic excesses. The subject performatively and linguistically constituted is not ultimately defined by the interpellative call; neither is the subject fully determined or radically free from the deployed discourse. Steering a careful middle course between voluntarism and determinism, Butler distances herself from the strategic deployment of the category of the “essential” identity in political practices. What she offers instead is rejection and resignification in her alternative political mode.Crucially, the deconstruction of the subject is by no means equivalent to its destruction as Butler argues. In seeking out the instabilities of language and of the constitutive terms of identity we are guided to a new sense of ethics, with the limit and inevitable opacity of the subject that always fails to define itself.
1 0 0 0 OA テクスト解釈の憂欝な歓び
- 著者
- 舟山 俊明
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.93, pp.137-138, 2006-05-10 (Released:2009-09-04)
1 0 0 0 OA 実践研究の隘路と可能性 広島大学附属幼稚園教諭との共同研究の経験を振り返る
- 著者
- 鳥光 美緒子
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.93, pp.139-144, 2006-05-10 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 OA 美的・倫理的人間形成論の現在性をめぐって
- 著者
- 白銀 夏樹 村田 美穂 久保田 健一郎 奥野 佐矢子 小野 文生
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.93, pp.145-150, 2006-05-10 (Released:2010-01-22)
- 参考文献数
- 9
現代の人間形成論においては、「美」「倫理」という言葉によって、人間形成をめぐる現代的状況を解明しようとする議論や人間形成論の可能性を提起しようとする議論が少なからず見受けられる。だが「美」と「倫理」の概念の接点をさぐりながら人間形成論の現代的射程を探る共同研究の試みは、いまだ豊かに展開されているとはいいがたい。教育哲学会第四八回大会 (香川大学) において「美」と「倫理」の概念に関心を寄せる若手研究者が集まり、「美的・倫理的人間形成論の現在性をめぐって」と題したラウンドテーブルを開催した。ドイツ語圏の美的人間形成論 (白銀・久保田) 、英語圏の道徳や倫理を扱う人間形成論 (奥野・村田) 、ドイツ教育思想史における「美」「倫理」概念 (小野) といった各々の関心から、現代の「美」「倫理」概念の人間形成論的射程を議論した。以下はラウンドテーブル当日の提案者四名 (村田、久保田、奥野、白銀) と指定討論者 (小野) による報告である。本論の最終的な文責は企画者 (白銀) が負うが、それぞれの項目は担当者が執筆したものである。
1 0 0 0 OA 生成し/生成される教師を「語る」 「論述行為」の意味への問いに誘われて
- 著者
- 山崎 洋子
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.93, pp.14-20, 2006-05-10 (Released:2010-05-07)
- 参考文献数
- 10
1 0 0 0 OA 研究討議に関する総括的報告
- 著者
- 小玉 重夫 毛利 猛
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.93, pp.21-27, 2006-05-10 (Released:2009-09-04)