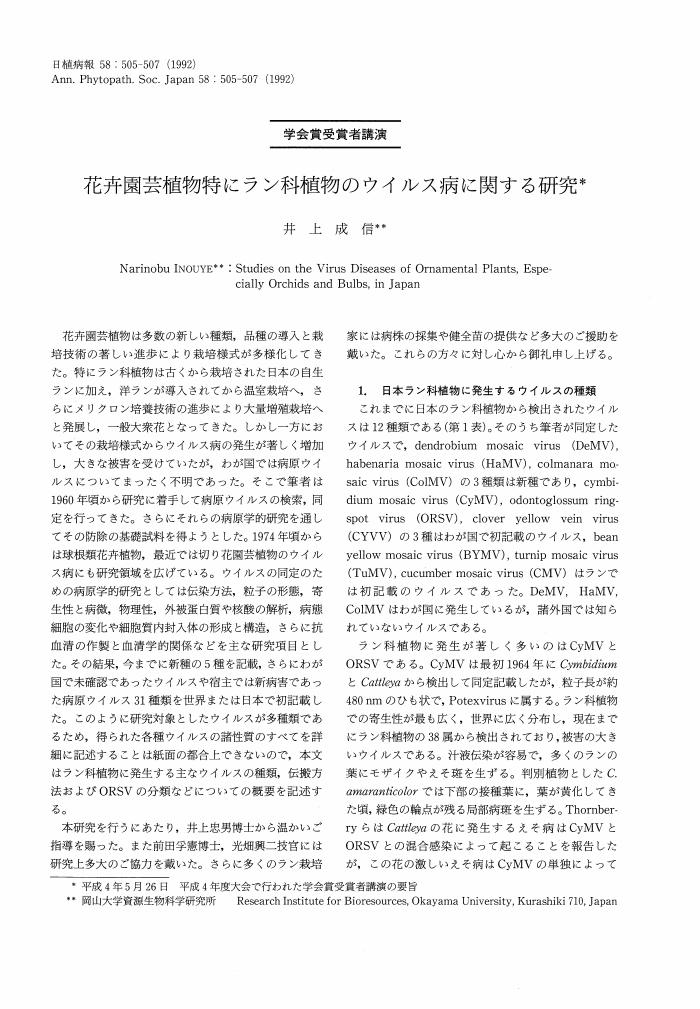2 0 0 0 OA アジサイ葉化病(新称)の発生とphytoplasmaの検出
- 著者
- 兼平 勉 堀越 紀夫 山北 祐子 篠原 正行
- 出版者
- 日本植物病理学会
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.5, pp.537-540, 1996-10-25 (Released:2009-02-19)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 6 10
In 1994 and 1995, hydrangea phyllody occurred in Tochigi, Shizuoka and Oita Prefectures, Japan. The affected plants (Hydrangea macrophylla and H. serrata) showed phyllody and proliferation of flower organs, as well as stunting and dieback. Electron microscopy revealed the presence of phytoplasmas in the phloem sieve elements of affected sepals and leaves. The phytoplasmas were transmitted to healthy Catharanthus roseus by graft inoculation. Using primers for 16S rDNA by polymerase chain reaction (PCR), DNA fragments of 1.3 and 0.75kbp were amplified in DNA samples extracted from affected hydrangeas but not in those extracted from healthy plants. This is the first report on the occurrence of hydrangea phyllody in Japan.
2 0 0 0 OA 近年大発生したさび病とさび病防除に対する基礎生物学的研究の重要性
- 著者
- 山岡 裕一
- 出版者
- 日本植物病理学会
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.100th_Anniversary, pp.S40-S48, 2014 (Released:2014-12-27)
- 参考文献数
- 132
2 0 0 0 OA 稻熱病抵抗性に關する研究
- 著者
- 吉井 甫
- 出版者
- 日本植物病理学会
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.81-88, 1941 (Released:2009-04-03)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 4
1) 各種稻品種の有する葉片の強靱度・珪酸竝びに窒素含量を比較し,その結果を各品種の稻熱病抵抗性との間に何等かの相關的關係を見出さんとした。2) 本實驗に於て供用した稻の品種はカマイラズ・旭・晩神力・銀坊主・龜治・愛國・眞珠1號・戰捷の8品種であつた。3) これらの品種を春日井液の窒素を3倍にせるものによつて水耕し,その穗孕期直前の葉片を材料として稻熱病發病程度・強靱度(貫穿抵抗)・珪酸竝びに窒素含量を求めたのである。4) 葉片の強靱度・珪酸及び窒素の測定方法は前報文(12, 14)の通りである。發病程度を調査するに當つては,先づPiricularia oryzaeを噴霧接種し,その抵抗性の強弱を發病比數によつて求めると同時に,野外に於てポット栽培をなせる同じ品種の稻に自然發生せる稻熱病につき,その發病程度を目測によつて求めた。5) 實驗の結果によれば,稻熱病に對する稻の品種的抵抗性の強弱は,各品種の稻葉片の示す夫々の強靱度・珪酸含量・窒素含量或は後兩者の含有量に於けるSiO2/Nの比の何れとも相關的の關係がないのである。即ち品種間抵抗性はかかる物理的或は化學的の計量の外にありと云はざるを得ない。
1 0 0 0 OA イネ萎縮ウイルスゲノムの構造解析
- 著者
- 鈴木 信弘
- 出版者
- The Phytopathological Society of Japan
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.176, 1995-06-25 (Released:2009-02-19)
1 0 0 0 OA クログワイの橙色斑点から分離されたNimbya scirpicola
- 著者
- 原田 幸雄 今泉 誠子 田中 博 根岸 秀明 藤森 嶺 山田 昌雄 本蔵 良三 三浦 喜夫
- 出版者
- The Phytopathological Society of Japan
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.5, pp.766-768, 1992-12-25 (Released:2009-02-19)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 3 2
1989年,宮城県名取市の休耕田において,茎が橙色の斑点を示すクログワイを発見した。橙色の病斑部から病原菌が分離され,胞子の形態,培地上のコロニーの形状から,Nimbya scirpicola (Fuckel) Simmonsと同定された。本菌は分離宿主のクログワイとタマガヤツリに対してのみ病原性を示し,イネを含むいくつかの主要栽培植物に対しては病原性を示さなかった。なお,クログワイから本菌が病原菌として分離されたのは日本で最初である。
1 0 0 0 OA ホップべと病に関する研究
- 著者
- 森 義忠
- 出版者
- The Phytopathological Society of Japan
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.92-97, 1968 (Released:2010-03-08)
- 参考文献数
- 9
前報(1962, 1966, 1967)で筆者はホッブべと病の一次発生源として根株中の越年菌糸の重要性と,このような潜在菌糸の主原因は秋感染によつておこることを強調した。もし,秋感染が潜在菌糸の主な根源,つまり春発生するふしづまり芽条の主因であるとすれば,秋の殺菌剤散布はふしづまり芽条発生を防ぐことになる。このことは古里ホップ試験場での諸実験の結果からある程度確認されている。本試験はこの結果にもとついて,大面積にわたる圃場試験として計画され,ふしづまり芽条防除のため殺菌剤の秋散布の効果試験がA, BとCの3地区で行なわれた.Aは長野県の平坦部,一方BとCは山間部が選定された。圃場試験でも当場の実験と同じ結果が再現され,球果収穫後の殺菌剤の秋散布が一次感染の除去に重要であることを示唆し,それがまた一次の“ふしづまり”芽条の減少に効果的であることを示した。
1 0 0 0 OA ニホンナシ黒星病菌分生子接種葉の濡れ時間および温度と発病程度
- 著者
- 梅本 清作
- 出版者
- The Phytopathological Society of Japan
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.212-218, 1991-04-25 (Released:2009-02-19)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 5 6
ニホンナシ黒星病菌分生子をナシ葉へ接種した後の葉の濡れ時間および温度と発病程度との関係について検討した。9時間濡れ状態に保持した場合,15°Cでわずかに発病し,12時間以上では5∼25°Cで発病し,20°Cで最も多発したが15°Cもそれに近い発病であった。一方,30°Cでは36時間濡れ状態に保持した場合および5∼25°Cで6時間以内の濡れ保持時間では発病しなかった。これらの結果は,Millsがリンゴ黒星病で得た結果と酷似し,素寒天培地上における温度別分生子および子のう胞子の発芽状況および20°Cで濡れ状態に保持した場合のナシ葉上における分生子の発芽・侵入行動ともよく一致した。また,分生子と子のう胞子のナシ葉に対する病原性はほぼ同一であることが確認されたので,以上の結果は子のう胞子による感染場面にも適用できると考えられた。
- 著者
- 井手 洋一 古田 明子
- 出版者
- 日本植物病理学会
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.1, pp.1-8, 2023-02-25 (Released:2023-03-08)
- 参考文献数
- 38
タマネギべと病の薬剤防除の精度向上を目的として,ブームスプレーヤの噴霧高さが薬液付着や防除効果に及ぼす影響について検討した.葉先の30 cm上方から散布した場合の薬液付着は,葉身中央部,葉身抽出部ともに良好であったが,葉先とほぼ同じ高さから散布した場合は,葉身中央部付近の薬液付着が劣った.また,べと病に対する防除効果も葉先とほぼ同じ高さから散布した場合は劣った.今後は,本試験で得られた噴霧高さと薬液付着,べと病に対する防除効果の関係性をもとに,適切な薬剤散布技術に関する指導を行う必要がある.
1 0 0 0 OA Phytophthora citrophthoraによるショウガ疫病(新称)
- 著者
- 山崎 睦子 松岡 弘明 矢野 和孝 森田 泰彰 植松 清次 竹内 繁治 有江 力
- 出版者
- 日本植物病理学会
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.4, pp.299-303, 2011 (Released:2011-12-09)
- 参考文献数
- 22
In 1997, Phytophthora rot caused serious losses to ginger (Zingiber officinale Rosc.) production in Kochi Prefecture, Japan. In the field in early summer and autumn, water-soaked rot on basal pseudostems and brown rot on rhizomes were first observed, then plants developed stem blight. The disease also developed on rhizomes stored at 15°C in the dark. A Phytophthora sp. was consistently isolated from the symptomatic lesions and caused the same symptoms after inoculation with the isolates. The identical Phytophthora sp. was then reisolated. White stellate colonies grew on PDA at a minimum temperature of 10°C, optimum of 23°C and maximum of 30°C. Sporangia were ovoid, ellipsoid, globose and distorted (variable) with one or two apices, noncaducous, 30–90 × 20–50 (average 50.0–56.1 × 25.0–32.6) μm, with a length to breadth ratio of 1.5–1.7:1. Nucleotide sequence of the r-DNA ITS regions agreed well with those of Phytophthora citrophthora (R. E. Smith and E. H. Smith) Leonian previously reported. Based on these results, the isolate was identified as P. citrophthora. This report is the first of a disease of ginger caused by P. citrophthora, and we propose the name “Phytophthora rot” for the disease.
1 0 0 0 OA 本会初代会長白井光太郎先生の生誕第百年を迎えて
- 著者
- 末松 直次
- 出版者
- The Phytopathological Society of Japan
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.3, pp.99-101, 1962-05-25 (Released:2009-02-19)
1 0 0 0 OA 黄麻の新病害炭疽病
- 著者
- 鑄方 末彦 吉田 政治
- 出版者
- The Phytopathological Society of Japan
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2-3, pp.141-149, 1940 (Released:2009-04-03)
- 被引用文献数
- 9 9
(1) The present paper deals with the study carried out by the writers on a new fungus which causes an anthracnose disease of jute.(2) The jute anthracnose affects the stems, leaves and pods of this crop and its presence in Kumamoto and Shizuoka Prefecture was first observed in 1938. In the next year it has been found in Aichi Prefecture.(3) The causal organism has been isolated and its pathogenicity has been proved by inoculation experiments. The incubation period is about three days.(4) As the fungus seems to be new to science, the name Colletotrichum Corchorum is proposed and a brief technical description is given, as follows:Colletotrichum Corchorum IKATA et TANAKA nov. sp.Lesions on stems, leaves and pods, brown to black, not sunken, definite in outline. Acervuli black, superficial, scattered; stroma patelliform, 100-350μ in diameter by 25-50μ high; setae several to abundant, originating from margin of stroma, yellowish brown to black and becoming lighter toward the apex, 2 to 5 septate, 36-117 μ long by 3.6-5.0 μ wide. Conidiophores simple, hyaline, arising from stroma, 15-35 μ long by 3-4 μ wide; conidia abundant, non-septate, hyaline, curved, bluntly tapered, oblong-fusoid to falcate-fusoid, 12-25×3.6-6.0μ, with 16-22×4μ as the most common size.HAB: Parasitic on stems, pods and leaves of Corchorus capsularis L.(5) The optimum temperature for growth of the fungus is 30°C.(6) The disease is seed-borne, the fungus mycelium exists in the seed and spores are adhering on the external part of seeds.
1 0 0 0 OA 花卉園芸植物特にラン科植物のウイルス病に関する研究
- 著者
- 井上 成信
- 出版者
- The Phytopathological Society of Japan
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.4, pp.505-507, 1992-10-25 (Released:2009-02-19)
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 植物病害の薬剤防除
- 著者
- 廣岡 卓 石井 英夫
- 出版者
- 日本植物病理學會
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.100, pp.S172-S178, 2014
- 被引用文献数
- 1
病害防除において,総合的病害虫管理(IPM)の基幹になるのは薬剤防除である。薬剤防除の歴史は,1800年代に使用が開始された石灰硫黄合剤やボルドー液を端緒に,病原菌の多くの生化学的作用点を阻害し保護的作用が主体の殺菌剤,いわゆる多作用点阻害剤で始まる。1960年代になり,病原菌の特異的な部位を阻害することによって病害防除効果を発揮する特異作用点阻害剤が導入された。特異作用点阻害剤は,浸透移行性があり予防および治療効果を併せ持つことが多いことから防除適期が広く,半世紀の間に殺菌剤の主流となった(Knight et al.,1997; Morton and Staub,2008)。殺菌剤は,企業の研究開発プロセスを経て最終化され,各国の農薬登録を取得した後に初めて農業生産者に使用される。ここでは,半世紀にわたる薬剤防除の動向を述べるとともに,(i) 殺菌剤市場,(ii) 作用機構による殺菌剤の分類,(iii) 薬剤防除の実例として,日本におけるイネいもち病および薬剤防除を取巻く諸問題,欧州におけるムギ病害,ブラジルにおけるダイズ病害,(iv)日本における殺菌剤耐性問題とその対策,について考察した。
- 著者
- 成田 武四 平塚 保之
- 出版者
- The Phytopathological Society of Japan
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.3, pp.147-153, 1959
- 被引用文献数
- 10
1) 1956年夏, 北海道各地に発生したトウモロコシの斑点性病害は従来未報告の不完全菌の寄生によることを認め, 正式にトウモロコシ褐斑病と命名した。<br>2) 本病は1956年以降発生が認められ, その分布は11支庁管内におよんでいるが, 日高, 胆振, 石狩, 渡島など北海道の西南部に発生が多く, 7, 8月寡照多湿のときに蔓延が著しい。<br>3) 本病はトウモロコシの葉片, 葉鞘, 苞葉, ときに茎などに径1∼3mm, ほぼ円形の病斑をつくるが, 病斑はしばしば癒合して大形となり, また径1mm以内の微細斑点として密集する。周縁褐色または紫褐色, 中央灰白色で, 周囲に淡黄色の暈が存在する。<br>4) 本病病原菌はトウモロコシの各変種, フリントコーン, デントコーン, スイートコーン, ワッキシーコーン, ポップコーンなどをおかすが, トウモロコシ以外のイネ科植物16種, マメ科植物2種には寄生しなかつた。<br>5) 本病病原菌の形態, 性質は <i>Kabatiella</i> 属の特徴と合致し, 本菌と既知の <i>Kabatiella</i> 属の菌種とを比較した結果, 本菌を新種と認め, <i>Kabatiella zeae</i> Narita et Y. Hiratsuka としてその標徴を記載した。
1 0 0 0 OA 植物病害の薬剤防除
- 著者
- 児玉 基一朗 赤木 靖典 髙尾 和実 難波 栄二 山本 幹博 秋光 和也 柘植 尚志
- 出版者
- 日本植物病理學會
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.4, pp.207-216, 2014
地球上に存在する糸状菌の大多数は,分解者として腐生的生活を送っている。その一方で,特定の糸状菌が生物学的に大きなコストをかけて植物寄生能力を進化させてきた要因は,宿主植物というニッチを占有することの利点にある。病原糸状菌の感染様式は,栄養関係の樹立に生細胞との相互作用を必要とする活物寄生菌(biotroph)から,感染成立過程において植物細胞を激しく加害し死に至らしめる殺生菌(necrotroph)まで多岐にわたる。その他,共生菌,あるいは感染過程の少なくとも一部において生細胞との相互作用が重要であるとされる中間型の寄生菌(hemibiotroph)なども存在する。このように多種多様な寄生様式のいずれも,相互作用における進化のほぼ最終的な形態として具象化されているのか,それとも単に理想的な最終型に収斂する過程の途上に現れた一つにすぎないのか,議論の分かれるところである。
コロジオン膜被覆スライドガラス上に<i>Fusarium oxysporum</i> f. <i>raphani</i>の厚膜胞子懸濁液を滴下してその発芽率を調べた。厚膜胞子はpH4.0∼7.0の範囲では90%前後の高い発芽率を示した。厚膜胞子は,塩類溶液中の密度が2×10<sup>4</sup>個/ml以下のときは90%以上の発芽率を示したが,9×10<sup>5</sup>個/ml以上になると発芽率は1%以下に低下した。厚膜胞子の密度が高いときに生じる発芽率の低下は塩類溶液にグルコースを添加すると回復し,その添加効果は0.1mM以上であらわれた。<br>気相の酸素濃度が5%以下になると,塩類溶液中における厚膜胞子の発芽は減少しはじめた。この酸素の影響は培地にグルコースを添加すると緩和された。しかし気相を窒素で完全に置換すると,厚膜胞子の発芽率は培地中のグルコースの有無にかかわらず著しく低下した。<br><i>Fusarium oxysporum</i> f. <i>raphani</i>の菌糸懸濁液を入れたペトリ皿の気相で厚膜胞子の発芽試験を行うとき,発芽培地として塩類溶液を用いると,発芽は著しく阻害された。一方,この発芽阻害はグルコースを添加した塩類溶液を用いると認められず,飢餓培養した菌糸を用いると増大し,菌糸懸濁液にグルコースを添加すると消失した。<br>以上の結果をもとに<i>Fusarium oxysporum</i> f. <i>raphani</i>の菌糸が産生する揮発性物質,およびそれらの産生におよぼす炭素源の濃度について論じた。
- 著者
- 土崎 常男 與良 清 明日山 秀文
- 出版者
- 日本植物病理学会
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.237-242, 1970
- 被引用文献数
- 5
1. ササゲおよびアズキにおいて,種子伝染性ウイルスと非種子伝染性ウイルスを用い,ウイルスの種子伝染と配偶子感染との関係を調べた。<br>2. 花粉伝染と胚のう伝染は種子伝染の起こるアズキ・モザイク・ウイルス(AzMV)とアズキ,ササゲ・モザイク・ウイルス(CAMV)とササゲの組合せでだけ起こり,種子伝染の起こらないキュウリ・モザイク・ウイルス-アズキ,CAMV-アズキ,サブクロ-バ・モットル・ウイルス-ササゲの組合せでは起こらなかった。<br>3. ササゲを親植物とした場合,種子伝染の起こるvirus-hostの組合せの場合だけ,検定植物への汁液接種により花粉からウイルスが検出された。しかし葯,子房からは,種子伝染しないvirus-hostの組合せでもウイルスが検出されることが,ササゲ,アズキのいずれを親植物としたときにも認められた。<br>4. 各種ウイルスに感染したアズキ,ササゲの雌しべ,雄しべ,花弁,葉につき,ウイルス濃度を比較した。一般に雌しべ,雄しべのウイルス濃度が花弁,葉より低い傾向がみられたが,種子伝染の有無とはとくに関係はなかった。次にCAMVに感染したササゲ,アズキの葯,子房のウイルス濃度を比較した。葯ではササゲの方がアズキよりもウイルス濃度が高かったが,子房ではその逆で,種子伝染の有無と葯,子房のウイルス濃度の間にとくに関係は認められなかった。<br>5. CAMV-ササゲ,AzMV-アズキの組合せで,開花期にウイルスを接種し,開花日別に分けて種子を集め,種子伝染の有無を調べた。その結果,ともに接種日から約20日以後に開花し,結実した種子だけに種子伝染が起こった。一方,CAMV-ササゲの組合せで接種後一定間隔の期日ごとに花粉,葯,子房,花弁からのウイルスの検出を試みた。子房,花弁では接種4日後から,葯では接種10日後から,花粉では接種17日後からウイルスが検出され,種子伝染にはウイルスの配偶子感染が必要であることが示された。
1 0 0 0 ブル-ムレス台木接ぎ木キュウリにおける褐斑病抵抗性の低下
- 著者
- 挟間 渉 森田 鈴美 加藤 徳弘
- 出版者
- 日本植物病理學會
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.3, pp.p243-248, 1993-06
- 被引用文献数
- 2
キュウリの代表的なブルームレス台木として使用されている'スーパー雲竜'と, 従来から使用されブルームの発生が多い台木の'新土佐1号'を供試して, 褐斑病の発病推移を比較検討した。この結果, 褐斑病の発生は, ブルームレス台木への接ぎ木により著しく増加する傾向が認められた。この傾向は特にビニールハウス栽培において顕著であった。台木の違いによる葉中無機成分含有率を比較したところ, 必須元素の含有率に差異は認められなかったが, ブルームレス台木接ぎ木区のキュウリ葉ではケイ酸含有量がきわめて少なかった。さらに, ケイ酸無施用で栽培したキュウリは, ブルームレス台木栽培の場合と同様, 褐斑病に対する侵入阻止および病斑拡大阻止作用が低下する傾向が認められた。これらの結果から, ブルームレス台木への接ぎ木キュウリにおけるケイ酸の吸収阻害と褐斑病に対する病害抵抗性の低下との関連が示唆された。
- 著者
- 宮本 雄一
- 出版者
- 日本植物病理学会
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.4, pp.207-212, 1959
- 被引用文献数
- 1
1) 低温下 (0∼2°C) で乾燥し, 無酸素下 (5∼10°C) で貯蔵した, 病葉中のコムギ縞萎縮病ウイルス (WYMV) およびオオムギ縞萎縮病ウイルス (BYMV) はともに, 2年後においてもかなり強い感染力を示した。<br>2) 前報より引続き行つた実験の結果, 病土から分離濃縮された粘土部分 (<2μ) 粒子の病原性の強いことが, 播種試験および摩擦接種試験により, 再確認された。これらの粘土部分の粒子中には線虫類を全く認めず, また特記すべき頻度であらわれる糸状菌または細菌類を認めなかつた。さらにこの粘土フラクション中には, 根毛と判別できる植物の組織を認めなかつた。<br>3) 罹病植物汁液を粘土鉱物およびその他の土壌に吸着させ, 比較的高温下 (10∼15°C) で貯蔵した結果, WYMVおよびBYMVはともに, 約8カ月後の次のシーズンまでわずかながらその病原性を維持した。<br>4) 以上の諸事実とこれまでの実験結果から, ムギ萎縮病ウイルスの土壌伝播機作を説明するためには, 必ずしも特定の微生物的媒介者あるいは罹病植物の残根の存在を必要とせず, 蛋白質を吸着し保護すると考えられる粘土部分の土壌粒子 (無機および有機のコロイドを含む) がこれらのウイルスを吸着して伝播者の役割を果しているものと考える。