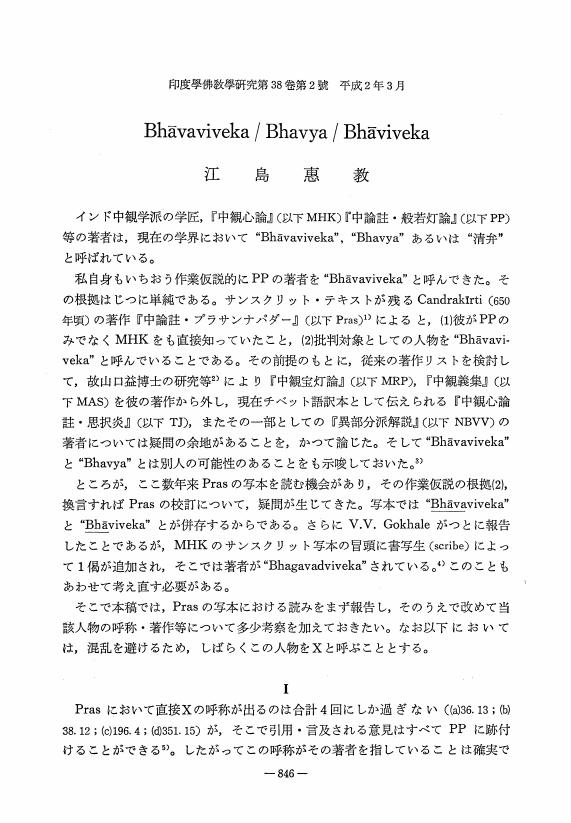- 著者
- 堀田 和義
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.2, pp.933-929, 2018-03
2 0 0 0 OA 『六度集経』の成立について : 康僧会の動機と目的
- 著者
- 伊藤 千賀子
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:18840051)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.996-991, 2013-03-20
- 著者
- 小川 太龍
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.40-45, 2017-12
- 著者
- 師 茂樹
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.1-9, 2017-12
2 0 0 0 OA Bhvaviveka/Bhavya/Bhaviveka
- 著者
- 江島 惠教
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.846-838, 1990-03-20 (Released:2010-03-09)
2 0 0 0 OA VasundharaとVasudhara
- 著者
- Sudan SHAKYA
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.2, pp.995-990, 2011-03-20 (Released:2017-09-01)
2 0 0 0 学処解説の違いから見た有部系律蔵の系統分類
- 著者
- 佐々木 閑
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.809-802, 2017-03
2 0 0 0 学処解説の違いから見た有部系律蔵の系統分類
- 著者
- 佐々木 閑
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.2, pp.809-802, 2017
<p>It seems to be strange that two different Vinayas, the <i>Shisong lü </i>十誦律, Ten Recitation Vihana, and the Mūlasarvāstivāda Vinaya, are extant but belong to the same sect, the Sarvāstivādins. The issue of how we should place them in the historical development of the Sarvāstivādins is particularly meaningful with respect to the investigation of the history of Buddhism, but no clear result has so far been found because of a lack of information; we have only some vague traditions.</p><p>In this article, the author presents information which clearly shows that the <i>Shisong lü</i> and the Mūlasarvāstivāda Vinaya were related with the Kāśmīra-vaibhāṣikas and Sautrāntikas respectively.</p><p>A passage in the Vinaya is quoted in a dispute between the Sautrāntikas and Kāśmīra-vaibhāṣikas described in the <i>Karmanirdeśa </i>of the <i>Abhidharmakośabhāṣya</i>. The corresponding passage can be found in both the <i>Shisong lü</i> and the Mūlasarvāstivāda Vinaya and, as a result of a detailed investigation, it turned out that the corresponding passage in the <i>Shisong lü</i> was modified for the purpose of reinforcement of the Kāśmīra-vaibhāṣikas' claim in the dispute appearing in the <i>Abhidharmakośabhāṣya</i>,<i> </i>and the corresponding passage in the Mūlasarvāstivāda Vinaya (Chinese version) was modified to reinforece the claim of the Sautrāntikas.</p><p>From this fact, we can establish a close relationship between the <i>Shisong lü</i> and Kāśmīra-vaibhāṣikas, and the Mūlasarvāstivāda Vinaya and the Sautrāntikas.</p>
2 0 0 0 珍海著『菩提心集』における女性救済の問題
- 著者
- ミークス ローリ
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.20-23, 2007
2 0 0 0 OA 『識身足論』の論破形式 : 『カターヴァットゥ』との比較を通して
- 著者
- 清水 元広
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.306-304, 2003-12-20
2 0 0 0 ディグナーガによるavita批判およびprasangaについて
- 著者
- WATANABE Toshikazu
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.1229-1235, 2013-03
本稿では『プラマーナサムッチャヤ』第3章でディグナーガが行う,サーンキヤ学派のavita説批判を検討し,(1)ディグナーガの理解するavitaの構造は,サーンキヤ学派の提示する本来のそれを大幅に改変したものであり,prasangaを証因の三条件説に組み込むことに成功している(2)ディグナーガによるavita解釈が,ダルマキールティが用いるprasangaviparyaya,そしてバーヴィヴェーカがブッダパーリタを批判する際に用いるviparyayaと同じ構造である という二点を明らかにした.(1)ディグナーガの理解するavitaは,vitaと同じ主題(A)について,vitaでの遍充関係(B→C)の対偶(¬C→¬B)を用いて望ましくない帰結を導くものである.vita:A(B→C) avita:A(¬C→¬B)) ∧¬¬B∴ ¬¬C 従って,avitaはvitaに変換され,同じ内容を表すものと理解される.このことは,prasangaも証因の三条件説の枠内に収まるということを意味し,さらには正規論証(sadhana)へ変換されうる可能性を示唆するものである.(2)ダルマキールティおよび彼の注釈者達によるprasangaとprasangaviparyayaの関係は,前者がディグナーガのvitaに,後者がavitaに対応する.また,バーヴィヴェーカの提示するviparyayaへの変換も,バーヴィヴェーカは否定(¬)をparyudasaで理解しているのに対してディグナーガのそれはprasajyapratisedhaであるという点は異なるが,ディグナーガがavitaをvitaへ変換した手順と構造的に同じである.
2 0 0 0 OA 初期仏典における(a-)parigraha-について
- 著者
- 稲葉 維摩
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.324-321, 2011-12-20
2 0 0 0 OA 三階教と『冥報記』・『日本霊異記』
- 著者
- 洪 在成
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.947-945, 2003-03-20
2 0 0 0 OA 天台智〓の地論四宗義批判について
- 著者
- 山口 弘江
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.703-706, 2008-03-20
天台智〓は当時の仏教界の中心的存在であった地論師の説に批判を加え独自の教学を形成した。一方、その教学形成において地論師の思想が影響していることも諸先学の研究に指摘されるところのものである。本稿ではその一つである四宗義批判について取り上げる。特に智〓の最晩年に成立した文献である『維摩経玄疏』の記述に着目し、智〓が強調する地論師四宗の問題点が奈辺にあるかを考察する。その上で智〓がこのような批判を展開する背景についても検討を加えたい。
2 0 0 0 OA 杏雨書屋所蔵三階教写本『普親観盲頓除十悪法』の基礎的研究
- 著者
- 西本 照真
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:18840051)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.1, pp.1-10, 2014-12-20
2 0 0 0 OA 「蓮華喩讃品」に表された『金光明経』説示者の誓願
- 著者
- 鈴木 隆泰
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.1143-1150, 2013-03-25
筆者はこれまで,『金光明経(Suvarna[-pra-]bhasottamasutrendraraja)』の制作意図に関して以下の<仮説>を提示してきた.・大乗仏教出家者の生き残り策としての経典:『金光明経』に見られる,従来の仏典では余り一般的ではなかった諸特徴は,仏教に比べてヒンドゥーの勢力がますます強くなるグプタ期以降のインドの社会状況の中で,余所ですでに説かれている様々な教説を集め,仏教の価値や有用性や完備性をアピールすることで,インド宗教界に生き残ってブッダに由来する法を伝えながら自らの修行を続けていこうとした,大乗仏教出家者の生き残り策のあらわれである.・一貫した編集意図,方針:『金光明経』の制作意図の一つが上記の「試み」にあるとするならば,多段階に渡る発展を通して『金光明経』制作者の意図は一貫していた.・蒐集の理由,意味:『金光明経』は様々な教義や儀礼の雑多な寄せ集めなどではなく,『金光明経』では様々な教義や儀礼に関する記述・情報を蒐集すること自体に意味があった.本稿では第4章「蓮華喩讃品(Kamalakara-parivarta)」に焦点を当て,<仮説>の検証を続けた.その結果,「仏教がかつての勢いを失いつつある中,仏教の存続に危機感を抱いた一部の出家者たちは,在家者から経済的支援を得てインド宗教界に踏みとどまり,仏教の伝承と実践という義務を果たすため,『金光明経』を制作した.『金光明経』の功徳や価値や有用性や完備性をアピールするため,適宜『金光明経』を増広発展させていったが,「蓮華喩讃品」においては他の多くの諸品とは異なり,世間的利益を説かず出世間的利益のみが求められている.これは,「蓮華喩讃品」に表れる祈願・誓願が,聞く側(在家者)ではなく説く側(出家者)のもののみであることに基づいていると考えられる.この「出家者の祈願・誓願は全て出世間的利益を求めるもの」ということに,『金光明経』が全篇に渡ってどれほど世間的利益を説こうとも,『金光明経』制作者の出家者としての「本義」「面目」があったものと判断される.同時に,『金光明経』が世間的利益を強調したのは,そこに魅力を感じる在家者を惹きつけ彼らから財政支援を受けることを目的としたからであって,出家者自身が出世間的利益を放棄したのではないことも確認される.」という結論を得たことで,所期の目的を達成した.『金光明経』から見る限りにおいても,インド仏教は第一義的には出家者のための宗教であったといえる.
2 0 0 0 OA 日本で発見されたオリヤー語の『マハーバーラタ』について
- 著者
- DASH Shobha Rani
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.872-869, 2006-03-20
2 0 0 0 OA 大乗の諸経論における<仏が悟った時,一切衆生も同時に悟る>との記述の認識論的理解
- 著者
- 島村 大心
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.491-487, 2006-12-20
2 0 0 0 OA 『開目抄』にみる日蓮の法華経観
- 著者
- 関戸 堯海
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:18840051)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.1300-1307, 2014-03-25
文永九年(1272)二月,寒風が吹きつける佐渡の塚原三味堂で,日蓮は『開目抄』を書き上げた.「日蓮のかたみ」として門下に法門を伝えるための論述である.日蓮は『開目抄』において,諸経にすぐれる『法華経』が末法の衆生を救う教えであることを力説する.まず,あらゆる精神文化と仏教を比較して,その頂点に『法華経』があることを論述する.一切衆生が尊敬すべきは主徳・師徳・親徳であり,学ぶべき精神文化は儒教・仏教以外の宗教思想・仏教であるとして,それぞれの思想的特徴を精査して,仏教が最もすぐれるとし,なかでも『法華経』が釈尊の真実の教えであることを「五重相対」の仏教観によって証明する.続いて,『法華経』のすぐれた思想的特色として,一念三千および二乗作仏・久遠実成を挙げて詳細に論じている.そして,『法華経』迹門の中心をなす方便品は一念三千・二乗作仏を説いて,爾前諸経の二つの失点のうち一つをまぬがれることができたが,いまだ迹門を開いて本門の趣旨を顕らかにしていないので,真実の一念三千は明らかにされず,二乗作仏も根底が明らかにされていないと述べ,本門を中心とした法華経観を提示する.また,末世の『法華経』布教者に数多くの迫害が待ち受けていることを『法華経』みずからが予言している(未来記).その経文を列挙して,数々の迫害の体験は予言の実践(色読)にほかならないとして,日蓮は末世の弘経を付嘱された上行菩薩の応現としての自覚に立ち,不惜身命の弘経活動を行なった.ことに龍口法難(佐渡流罪)を体験した日蓮は法華経の行者であることを確信した.そして,『開目抄』には「我れ日本の柱とならむ,我れ日本の眼目とならむ,我れ日本の大船とならむ」の三大誓願によって,人々を幸福な世界へと導くという大目的が表明されている.
2 0 0 0 OA 宮沢賢治の作品に現れた法華思想
- 著者
- 趙 明烈
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.952-948, 2003-03-20