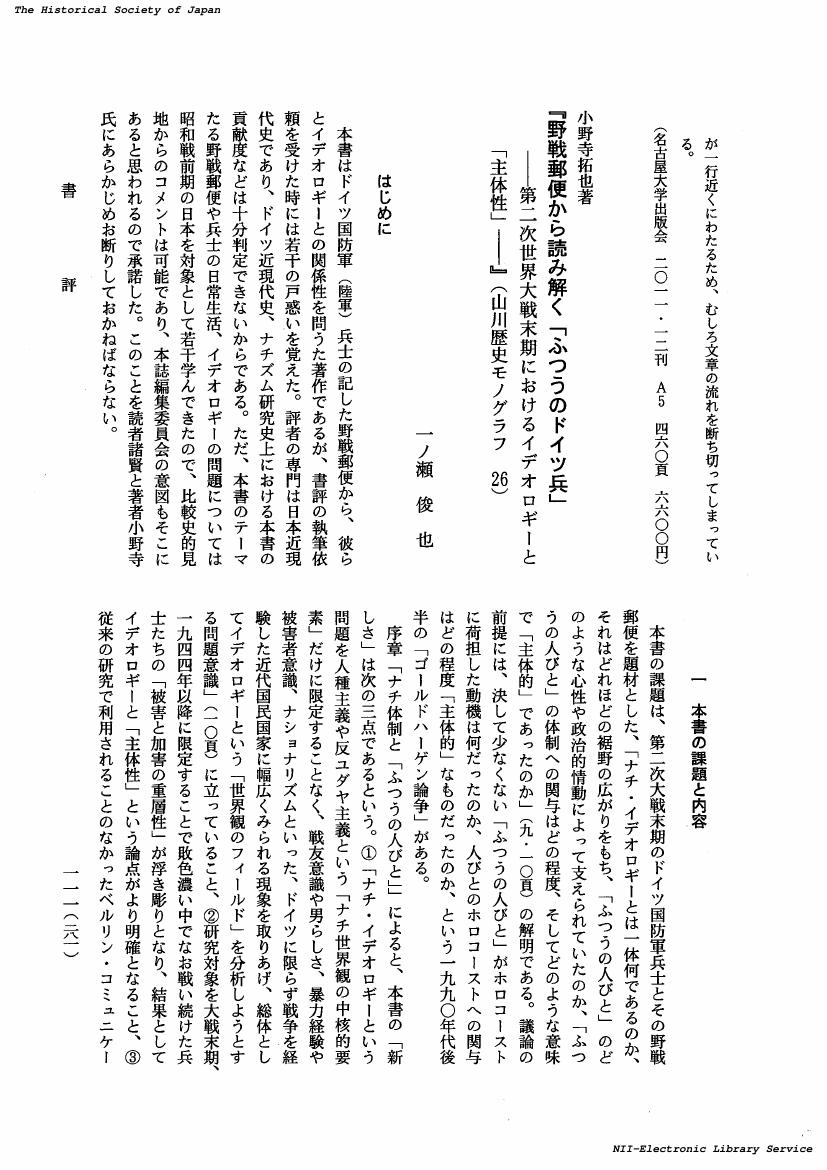40 0 0 0 OA 佐倉連隊の日常生活 : 昭和九年のある上等兵日記から
- 著者
- 一ノ瀬 俊也
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.131, pp.51-84, 2006-03-25
戦場における佐倉歩兵第五七連隊の行動は、いくつかの連隊史や回想録で比較的よく知られている。しかし、兵士たちの平時の日常生活、意識については不明な点も多いように思われる。本稿は一九三四(昭和九)年に連隊のある上等兵がほぼ毎日書いていた日記帳の内容を分析して、連隊の兵士が毎日どのような訓練・生活を送っていたのかを再構成することを目的とする。日記の筆者は(おそらく)三三年一月現役入営し、翌三四年七月一九日除隊している。日記帳にはこのうち三四年一月一日から除隊後の同年八月一八日までの記述がある。具体的に千葉での演習・勤務、富士山麓での演習、対抗競技と連隊への帰属意識、日常の衣食住、私的制裁、連隊と地域社会との関わり、といった諸テーマを設定して、兵士たちの〈日常〉の再構成に努めるとともに、彼らが自己の所属する軍隊をどうみていたのか、それは帝国軍隊の支持基盤たりえたのか、といった問題にも展望を示したい。なお、参考資料として、本日記の全文を連隊生活とは直接関係のない除隊後のものを除き、翻刻した。
32 0 0 0 現代の戦争研究と総力戦研究とを架橋する学際的戦争社会学研究領域の構築
2018年度は、5年間の研究計画の二年目であった。まず、4月14、15日に東京大学で行われた戦争社会学研究会第9回大会の場を利用して、野上は、東京大学文学部社会学教授・佐藤健二氏を招いて特別講演「「戦争と/の社会学」のために」を企画した。これもまた、学際的研究領域としての「戦争社会学」の内実を検討するものであり、活発な質疑を経て、戦争社会学の可能性を検討することができた。また西村は、テーマセッション「宗教からみる戦争」を企画した。宗教と戦争と社会の結びつきについて、多面的な議論が行われた。6月には、同研究会の研究誌『戦争社会学研究』の第二号が刊行された。特集となる「戦争映画の社会学」は、昨年度企画したシンポジウム「『野火』の戦争社会学」の活字化である。企画者の山本ほか、野上・福間が寄稿した。また、第二特集として「旧戦地に残されたもの」があり、西村が企画趣旨文を寄せている。8月12日には、京都女子大学で小林啓治『総力戦の正体』の書評会を開催した。歴史学の立場からの「戦争と社会」研究であるが分野をまたいだ議論を可能にする幅広い問題提起を行う書物であった。書評担当者の一人を野上が担ったが、「戦争と社会」研究における「総力戦」概念の重要性に照らした検討を行った。この2018年度より、筑波大学を所属機関とする非常勤研究員として木村豊氏を雇用し、研究会の事務手続きを手伝ってもらうことになった。こうした研究会の企画のほか、研究打ち合わせを12月に行い、プレ調査の実施計画を進め、科研メンバーだけのクローズドな研究会を行った。また、筑波大学大学院「歴史社会学」演習と合同で、深谷直弘『原爆を継承する実践』の書評会を筑波大学で行った。若手研究者による戦争社会学的研究の成果である。
- 著者
- 一ノ瀬 俊也
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, no.8, pp.1370-1385, 2003
The intent of the present article is to analyze "histories" compiled by each regiment in the Japanese army from the Russo through the Sino-Japanese wars, concluding that such works were nothing the Sino-Japanese wars, concluding that such works were nothing but attempts to praise "the heroic past" and provide a means to instill such a consciousness in both the troops and society in general.The historical remembrances of the Russo-Japanese conflict were more and more emphasized with the outbreak of the First World War and the anti-war and anti-militarization movement that accompanied it.The descriptions of those who had died in past conflict were intended to stir the emotions of the troops and provide a route by which to legitimized "dying forons's country".Even on the local level during that time, "memorials to veterans" of both wars were compiled with the similar intention of establishing a forum upon which to instill a common sentiment about the viewpoints and logic of the military within local society.After the outbreak of the Manchurian Incident, "regimental histories" took on two distinct forms.The first consisted of memoirs concerning the victorious history of the Russo-and Sino-Japanese Wars, which in addition to insisting upon Japan's legitimate claim to Manchuria, tried to prove that even the Japanese people, who had not really experienced a genuine war since the Russo-Japanese conflict and had become used to peace, could indeed win another full-scale war, thus playing a role in attempts to instill"definite behavior patterns" and encourage the country's fighting spirit.The second contained contemporary regiment-by-regiment accounts of the Manchurina Incident told from the personal views of individual combatants with the intention of verifying the regiment's consciousness concerning the Incident, encouraging further sacrifices for the cause, and appsaling to society at large.The veteran memorial literature published on the local level at that time were compiled with a similar intent in mind, attempting like during World War I to instill military ideals and persuasive logic into society at large.
5 0 0 0 IR 佐倉連隊の日常生活--昭和9年のある上等兵日記から (共同研究 佐倉連隊と地域民衆)
- 著者
- 一ノ瀬 俊也
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.131, pp.51-84, 2006-03
戦場における佐倉歩兵第五七連隊の行動は、いくつかの連隊史や回想録で比較的よく知られている。しかし、兵士たちの平時の日常生活、意識については不明な点も多いように思われる。本稿は一九三四(昭和九)年に連隊のある上等兵がほぼ毎日書いていた日記帳の内容を分析して、連隊の兵士が毎日どのような訓練・生活を送っていたのかを再構成することを目的とする。日記の筆者は(おそらく)三三年一月現役入営し、翌三四年七月一九日除隊している。日記帳にはこのうち三四年一月一日から除隊後の同年八月一八日までの記述がある。具体的に千葉での演習・勤務、富士山麓での演習、対抗競技と連隊への帰属意識、日常の衣食住、私的制裁、連隊と地域社会との関わり、といった諸テーマを設定して、兵士たちの〈日常〉の再構成に努めるとともに、彼らが自己の所属する軍隊をどうみていたのか、それは帝国軍隊の支持基盤たりえたのか、といった問題にも展望を示したい。なお、参考資料として、本日記の全文を連隊生活とは直接関係のない除隊後のものを除き、翻刻した。The activities of the 57th Sakura Infantry Regiment on the battlefield are relatively well known from a number of regimental histories and memoirs. However, little is known about the daily life and thoughts of soldiers during peacetime. The aim of this paper is to reconstruct the daily training and life of soldiers in the regiment from the study of a diary written virtually everyday by a private first class in the regiment in 1934. The diarist most likely took up his position in January 1933 and then left the regiment on July 19, 1934. The diary contains entries from January 1 through August 18, 1934, by which time he had been discharged from the regiment.This paper attempts to reconstruct the daily lives of soldiers and covers the topics of exercises and duties in Chiba, exercises at the foot of Mt. Fuji, competitive sports and loyalty to the regiment, everyday clothing, food and shelter, un-offirial forms of punishment, and the relationship between the regiment and the local community. It also takes a look at how the soldiers regarded the regiment they were attached to and whether this constituted support for the Imperial Army. It may be noted that this diary, with the exception of the part following the writer's discharge from the regiment which is not directly related to the daily activities of the regiment, has been republished in full to provide background information.
4 0 0 0 IR 佐倉連隊の日常生活--昭和9年のある上等兵日記から (共同研究 佐倉連隊と地域民衆)
- 著者
- 一ノ瀬 俊也
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.131, pp.51-84, 2006-03
戦場における佐倉歩兵第五七連隊の行動は、いくつかの連隊史や回想録で比較的よく知られている。しかし、兵士たちの平時の日常生活、意識については不明な点も多いように思われる。本稿は一九三四(昭和九)年に連隊のある上等兵がほぼ毎日書いていた日記帳の内容を分析して、連隊の兵士が毎日どのような訓練・生活を送っていたのかを再構成することを目的とする。日記の筆者は(おそらく)三三年一月現役入営し、翌三四年七月一九日除隊している。日記帳にはこのうち三四年一月一日から除隊後の同年八月一八日までの記述がある。具体的に千葉での演習・勤務、富士山麓での演習、対抗競技と連隊への帰属意識、日常の衣食住、私的制裁、連隊と地域社会との関わり、といった諸テーマを設定して、兵士たちの〈日常〉の再構成に努めるとともに、彼らが自己の所属する軍隊をどうみていたのか、それは帝国軍隊の支持基盤たりえたのか、といった問題にも展望を示したい。なお、参考資料として、本日記の全文を連隊生活とは直接関係のない除隊後のものを除き、翻刻した。The activities of the 57th Sakura Infantry Regiment on the battlefield are relatively well known from a number of regimental histories and memoirs. However, little is known about the daily life and thoughts of soldiers during peacetime. The aim of this paper is to reconstruct the daily training and life of soldiers in the regiment from the study of a diary written virtually everyday by a private first class in the regiment in 1934. The diarist most likely took up his position in January 1933 and then left the regiment on July 19, 1934. The diary contains entries from January 1 through August 18, 1934, by which time he had been discharged from the regiment.This paper attempts to reconstruct the daily lives of soldiers and covers the topics of exercises and duties in Chiba, exercises at the foot of Mt. Fuji, competitive sports and loyalty to the regiment, everyday clothing, food and shelter, un-offirial forms of punishment, and the relationship between the regiment and the local community. It also takes a look at how the soldiers regarded the regiment they were attached to and whether this constituted support for the Imperial Army. It may be noted that this diary, with the exception of the part following the writer's discharge from the regiment which is not directly related to the daily activities of the regiment, has been republished in full to provide background information.
- 著者
- 一ノ瀬 俊也
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.123, no.2, pp.281-289, 2014
- 著者
- 一ノ瀬 俊也
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.126, pp.119-131, 2006-01
太平洋戦争中、補給を断たれて多くの餓死・病死者を出したメレヨン島から生還した将校・兵士たちをして体験記の筆をとらしめたのは、死んだ戦友、その遺族に対する「申し訳なさ」の感情であり、そこから死の様子が描かれ、後世に伝えられることになった。あるいは自己の苛酷な体験を「追憶」へ変えたいというひそかな願いもあった。自己の体験をなんとか意義付けたい、しかし戦友の死の悲惨さは被い隠せない、と揺れる心情もみてとれた。このように生還者たちの記した「体験」の性格は多面的であり、容易に単純化・一本化できるような性質のものではない。戦後行われてきた戦死者「慰霊」の背後には、そうした複雑な思いがあった。いくつかのメレヨン体験記を通じて浮かびあがってきたのは、「昭和」が終わり、戦後五〇年以上たってなおやまない、〈戦争責任〉への執拗な問いであった。その矛先は、時に天皇にまで及んだ。たとえそこで外国への、あるいは己れの戦争責任が問われることがなかったとしても、「責任を問うこと」へのこだわりや「死んでいく者の念頭に靖国はなかったろう」という当事者たちの文章は、戦後日本における「先の戦争」観の実相を問ううえでも、さらには戦争体験の風化・美化を進める今後の世代が前の世代の「戦中の特攻精神や飢えの苦しみは戦後教育と飽食に育った世代の理解は不可」という声に抗して「戦争体験」を引き継ぐさい、今一度想起されてよいのではないか。Former officers and soldiers who survived their time on Mereyon Island during the Pacific War, when the disruption of supplies ended in the death through starvation and disease of many in the Japanese army, have put pen to paper to record their experiences. These reminiscences contain sentiments of "apology" to their fallen comrades in arms and their families, and describe the circumstances of their deaths, which can be passed on to future generations. They also represent a hidden desire to transform their own harsh experiences into "reminiscences". They also tremble with emotion as they seek to give some meaning to their own experiences and are not able to hide the tragedy of the deaths of their fellow soldiers. In this way, the characteristics of the recorded "experiences" of these survivors are varied, and cannot be easily simplified or unified. Such complex emotions are to be found behind post-war "memorials" to the war dead.One theme that reveals itself from several records of their experiences on Mereyon Island is the persistent question of responsibility for the war, which is still asked today, 17 years after the end the Showa period and more than half a century after the war. At times, the brunt of this question is directed as high up as to the emperor. Even if foreign countries or the soldiers themselves have not been brought to task over responsibility for the war in their writings, the obsession with "asking who was responsible" and the words of the people of that time that say "Those about to die would not have thought about Yasukuni (Shrine)" question the reality of the view in post-war Japan of "the next war". Their writings should be remembered once again when inheriting "war experiences", as future generations subjected to the toning down and romanticizing of war experiences are faced with voices from the preceding generation claiming that "It is impossible for those generations educated after the war who have only known full stomachs to understand the suicidal spirit and suffering of starvation that were present during the war".
2 0 0 0 国民が兵営の様子を知るために
2 0 0 0 OA 兵士たちの死と“郷土”(死)
- 著者
- 一ノ瀬 俊也
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, pp.99-117, 2001-03-30
満州事変以降の各市町村では,国防同盟会・銃後奉公会などの名称を有する銃後後援団体を設立,歓送迎や慰問などの後援活動,公葬を実施した。それは前線兵士の“労苦”,死の公的な意義づけ,顕彰であった。これを受けた兵士,遺族たちの側も「身命を君国に捧げ」る覚悟を披瀝したり,身内の死者が「護国ノ神トナツテ益々皇基ノ御隆昌ヲ護ラル」だろうなどと繰り返し声明させられたことは,彼らが公定の〈正義〉の論理に同意させられていく過程に他ならなかったのではないかと思われる。政府,軍が“郷土”の慰問・激励を奨励し続けた理由は,そこにあった。ただし,戦中戦後を通じて兵士たちの“郷土”がその“労苦”,犠牲の顕彰に努力し続けたことは,遺族たちにとって身内の死の「意義」の説明をうけることでもあった。それが彼らの一定度の謝意を獲得してもいったことは,注目されて然るべきと考える。
1 0 0 0 OA 餓死の島をなぜ語るか : メレヨン島生還者たちの回想記
- 著者
- 一ノ瀬 俊也
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.126, pp.119-131, 2006-01-31
太平洋戦争中、補給を断たれて多くの餓死・病死者を出したメレヨン島から生還した将校・兵士たちをして体験記の筆をとらしめたのは、死んだ戦友、その遺族に対する「申し訳なさ」の感情であり、そこから死の様子が描かれ、後世に伝えられることになった。あるいは自己の苛酷な体験を「追憶」へ変えたいというひそかな願いもあった。自己の体験をなんとか意義付けたい、しかし戦友の死の悲惨さは被い隠せない、と揺れる心情もみてとれた。このように生還者たちの記した「体験」の性格は多面的であり、容易に単純化・一本化できるような性質のものではない。戦後行われてきた戦死者「慰霊」の背後には、そうした複雑な思いがあった。いくつかのメレヨン体験記を通じて浮かびあがってきたのは、「昭和」が終わり、戦後五〇年以上たってなおやまない、〈戦争責任〉への執拗な問いであった。その矛先は、時に天皇にまで及んだ。たとえそこで外国への、あるいは己れの戦争責任が問われることがなかったとしても、「責任を問うこと」へのこだわりや「死んでいく者の念頭に靖国はなかったろう」という当事者たちの文章は、戦後日本における「先の戦争」観の実相を問ううえでも、さらには戦争体験の風化・美化を進める今後の世代が前の世代の「戦中の特攻精神や飢えの苦しみは戦後教育と飽食に育った世代の理解は不可」という声に抗して「戦争体験」を引き継ぐさい、今一度想起されてよいのではないか。
1 0 0 0 OA 日本陸軍と"先の戦争"についての語り : 各連隊の「連隊史」編纂をめぐって
- 著者
- 一ノ瀬 俊也
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, no.8, pp.1370-1385, 2003-08-20 (Released:2017-12-01)
The intent of the present article is to analyze "histories" compiled by each regiment in the Japanese army from the Russo through the Sino-Japanese wars, concluding that such works were nothing the Sino-Japanese wars, concluding that such works were nothing but attempts to praise "the heroic past" and provide a means to instill such a consciousness in both the troops and society in general.The historical remembrances of the Russo-Japanese conflict were more and more emphasized with the outbreak of the First World War and the anti-war and anti-militarization movement that accompanied it.The descriptions of those who had died in past conflict were intended to stir the emotions of the troops and provide a route by which to legitimized "dying forons's country".Even on the local level during that time, "memorials to veterans" of both wars were compiled with the similar intention of establishing a forum upon which to instill a common sentiment about the viewpoints and logic of the military within local society.After the outbreak of the Manchurian Incident, "regimental histories" took on two distinct forms.The first consisted of memoirs concerning the victorious history of the Russo-and Sino-Japanese Wars, which in addition to insisting upon Japan's legitimate claim to Manchuria, tried to prove that even the Japanese people, who had not really experienced a genuine war since the Russo-Japanese conflict and had become used to peace, could indeed win another full-scale war, thus playing a role in attempts to instill"definite behavior patterns" and encourage the country's fighting spirit.The second contained contemporary regiment-by-regiment accounts of the Manchurina Incident told from the personal views of individual combatants with the intention of verifying the regiment's consciousness concerning the Incident, encouraging further sacrifices for the cause, and appsaling to society at large.The veteran memorial literature published on the local level at that time were compiled with a similar intent in mind, attempting like during World War I to instill military ideals and persuasive logic into society at large.
1 0 0 0 書評と紹介 松田英里著『近代日本の戦傷病者と戦争体験』
- 著者
- 一ノ瀬 俊也
- 出版者
- 吉川弘文館
- 雑誌
- 日本歴史 (ISSN:03869164)
- 巻号頁・発行日
- no.872, pp.155-157, 2021-01
- 著者
- 一ノ瀬 俊也
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.123, no.2, pp.281-289, 2014-02-20 (Released:2017-07-31)
1 0 0 0 地方都市の都市化と工業化に関する政治史的・行財政史的研究
本研究は北九州地域の都市を主たる対象に、近代日本の都市化・工業化における地方都市の位置と機能を明らかにすることを目的とする。本研究の鍵となる史料は、今回初めて利用可能になった安川敬一郎の日記をはじめとする関係史料(北九州自然史歴史博物館蔵、以下「安川文書」と略)である。本研究では第一に、「安川文書」の整理を同博物館と協力して行い、その史料情報をデータベース化して活用できるようにした。「安川文書」の活用は、地方財閥の代表的な存在であった安川財閥の企業活動を詳細に明らかにするのみならず、企業、政党、行政、社会運動等の都市主体の動向と相互関係(対抗・競合・協調)を検証し、それによって近代日本の地方都市史研究に新たな地平を開くことを可能にすると思われる。「安川文書」の主要な内容は、(1)安川敬一郎日記、(2)安川家の経営実態を示す帳簿類をはじめとする経営史料、(3)安川宛の書簡および安川の書簡草稿、(4)安川の膨大な意見書類である。本研究ではこれらの分析によって、安川の経済活動のみならず、それと結びついた政治活動、および政治・経済活動を結び付ける独特の国家観、国際情勢認識を明らかにすることができた。帳簿類の検討からは、安川家と松本家の事業上の関係(組織構造)や安川家の投資行動(資産運用のあり方)の実態が解明された。それによれば、安川家は日清戦争時の石炭ブームで得た利益を、鉱区の拡大と鉄道投資に投下し、事業多角化を実現した。また、安川敬一郎日記、書簡、意見書等を、的野半助関係文書、永江純一関係文書、新聞史料などと付き合わせることによって、これまでほとんど言及されなかった安川の政治活動の詳細が初めて明らかになった。衆議院選挙における安川の活動の舞台は北九州ではなく福岡市であり、そこでは安川は政友会系と玄洋社系双方の支持を調達できる立場にあった。安川は中央政界にも人脈をもち、第二次大隈内閣期に立憲同志会と政友会を牽制する第三勢力の形勢をはかったが、その意図は挙国一致による日中関係の安定化と、そのもとでの中国への資本進出にあった。
- 著者
- 一ノ瀬 俊也
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, pp.593-610, 2003-03
各市町村における従軍者記念誌は、日露戦争終結直後、戦死者が忘却されていくことを嘆いて作られた。だが第一次大戦後、主に在郷軍人会市町村分会によって作られた記念誌は、そのような後ろ向きの意図ではなく、ある積極的な政治的意図、すなわち過去の栄光の記録・記憶化を通じて軍人という自己の存在意義を再確認し、反軍平和思想の盛んだった社会に訴えていくために作られていった。そのような記念誌の中で日清・日露の追憶を語った老兵たちは、戦死者の壮絶な死を語って戦争の「記憶」に具体性を与えて、人々の共感を呼び起こす役回りを演じた。そうした語りのあり方は「郷土の英雄」を求める人々の心情にもかなうものだった。老兵たちが自己の従軍体験を語る際、確かに悲惨な体験も語ったものの、基本的には名誉心充足の機会として戦争を描いていた。そのような従軍者たちの「語り」を彼らの〝郷土〟が一書に編む時、彼らが国家の大きな歴史に占めた位置、役割の説明が熱心に行われた。それは戦死者の死の〝意味〟を明らかにし、ひいては戦争自体の持つ価値を地域ぐるみで再確認、受容することに他ならなかった。以上の過程を通じて、満州事変勃発以前から満州は「血をもって購った」土地であり、したがってその権益は擁護されるべきという論理や「社会主義共産主義」の脅威が市町村という末端レベルで繰り返し確認されていった。満州事変に際して軍、在郷軍人会などが国民の支持を調達する際、日露戦争の「記憶」を強調したことは周知のことだが、本稿が掲げた諸事例は、そのような「記憶」が当時の社会において具体的にいつから、どのようにして共有化されていったのかを示すものである。
- 著者
- 一ノ瀬 俊也
- 出版者
- 校倉書房
- 雑誌
- 歴史評論 (ISSN:03868907)
- 巻号頁・発行日
- no.689, pp.14-25, 2007-09
1 0 0 0 OA 紙の忠魂碑 : 市町村刊行の従軍者記念誌(2. 慰霊)
- 著者
- 一ノ瀬 俊也
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, pp.593-610, 2003-03-31
各市町村における従軍者記念誌は、日露戦争終結直後、戦死者が忘却されていくことを嘆いて作られた。だが第一次大戦後、主に在郷軍人会市町村分会によって作られた記念誌は、そのような後ろ向きの意図ではなく、ある積極的な政治的意図、すなわち過去の栄光の記録・記憶化を通じて軍人という自己の存在意義を再確認し、反軍平和思想の盛んだった社会に訴えていくために作られていった。そのような記念誌の中で日清・日露の追憶を語った老兵たちは、戦死者の壮絶な死を語って戦争の「記憶」に具体性を与えて、人々の共感を呼び起こす役回りを演じた。そうした語りのあり方は「郷土の英雄」を求める人々の心情にもかなうものだった。老兵たちが自己の従軍体験を語る際、確かに悲惨な体験も語ったものの、基本的には名誉心充足の機会として戦争を描いていた。そのような従軍者たちの「語り」を彼らの〝郷土〟が一書に編む時、彼らが国家の大きな歴史に占めた位置、役割の説明が熱心に行われた。それは戦死者の死の〝意味〟を明らかにし、ひいては戦争自体の持つ価値を地域ぐるみで再確認、受容することに他ならなかった。以上の過程を通じて、満州事変勃発以前から満州は「血をもって購った」土地であり、したがってその権益は擁護されるべきという論理や「社会主義共産主義」の脅威が市町村という末端レベルで繰り返し確認されていった。満州事変に際して軍、在郷軍人会などが国民の支持を調達する際、日露戦争の「記憶」を強調したことは周知のことだが、本稿が掲げた諸事例は、そのような「記憶」が当時の社会において具体的にいつから、どのようにして共有化されていったのかを示すものである。