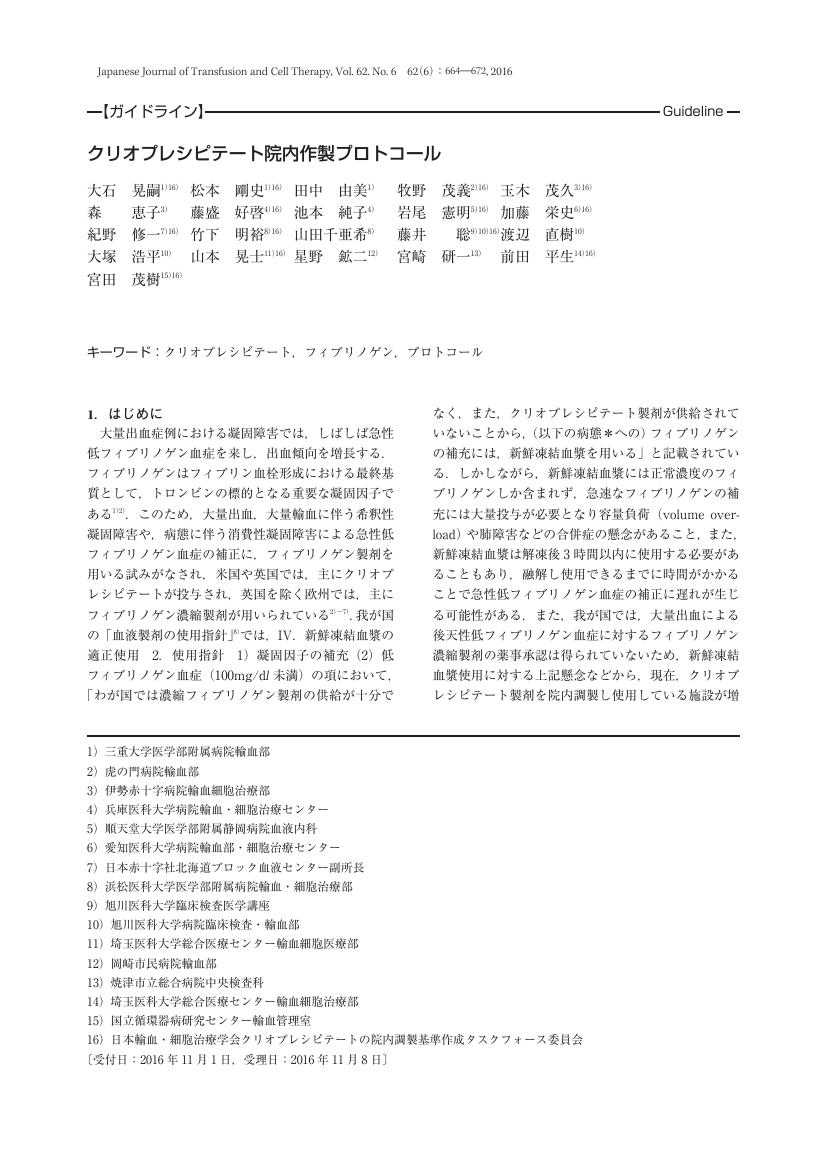2 0 0 0 OA 大量出血に対するフィブリノゲン製剤のエビデンスと今後の展開
- 著者
- 山本 晃士 松永 茂剛 澤野 誠 阿南 昌弘 今井 厚子 大木 浩子 前田 平生
- 出版者
- 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会
- 雑誌
- 日本輸血細胞治療学会誌 (ISSN:18813011)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.625-629, 2017-08-31 (Released:2017-09-22)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 2 2
2 0 0 0 OA PAI-1と生活習慣病
- 著者
- 山本 晃士
- 出版者
- 一般社団法人 日本血栓止血学会
- 雑誌
- 日本血栓止血学会誌 (ISSN:09157441)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.55-63, 2008 (Released:2008-03-25)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 OA 重症外傷患者に対するフィブリノゲン製剤の先制投与は予後の改善に寄与する
- 著者
- 山本 晃士 山口 充 澤野 誠 松田 真輝 阿南 昌弘 井口 浩一 杉山 悟
- 出版者
- 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会
- 雑誌
- 日本輸血細胞治療学会誌 (ISSN:18813011)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.135-139, 2017-04-20 (Released:2017-05-11)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1 1
背景と目的:外傷患者の急性期には凝固障害を認めることが多く,その程度は患者の生命予後を左右する.当院の高度救命救急センターでは,外傷患者の凝固障害,特に高度な低フィブリノゲン血症をすみやかに改善させる目的で,積極的にフィブリノゲン製剤の投与を行ってきた.その治療の実際と,同製剤の投与群と非投与群間で行った輸血量および生命予後の比較検討(症例対照研究)結果を報告する.方法:フィブリノゲン製剤投与の有無および投与基準の違いによって症例を3群に分けた.A群,フィブリノゲン製剤未使用;B群,受診時のフィブリノゲン値と外傷重症度を見た上でフィブリノゲン製剤3gを投与;C群,患者搬送前の情報(外傷重症度,出血状況)から判断し,搬送時ただちにフィブリノゲン製剤3gを投与.外傷重症度スコア≧26の症例における輸血量および生命予後について3群間で比較検討を行った.結果:3群間の輸血量には有意差を認めなかった.受診30日後の総生存率(搬送時の心肺停止症例を除く)はC群で有意に高く(p<0.05),搬送後48時間以内の急性期死亡率はC群で有意に低かった(p=0.005).さらに,きわめて重篤とされる外傷重症度スコア≧41群での死亡率も,C群で有意に低かった(p=0.02).結論:重症外傷症例においては,フィブリノゲン製剤の先制投与が急性期死亡率の低下に貢献し,結果として高い生存退院率をもたらす可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA ドクター・ヘリコプター内への血液搬送装置ATRの設置
- 著者
- 今井 厚子 阿南 昌弘 植松 正将 野呂 光恵 安田 絵理子 大木 浩子 田坂 大象 山本 晃士
- 出版者
- 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会
- 雑誌
- 日本輸血細胞治療学会誌 (ISSN:18813011)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.5, pp.775-776, 2019-10-25 (Released:2019-11-15)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 コラム:PT,APTT検査とpoint-of-careテスト
- 著者
- 山本 晃士
- 出版者
- メディカル・サイエンス・インターナショナル
- 巻号頁・発行日
- pp.1158-1159, 2020-11-01
術中の出血量増加時には凝固障害の程度を評価するため,一般的にプロトロンビン時間(PT),活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)検査が行われる。しかしPT,APTT値は,必ずしも患者の凝固能を反映しているとはいえない。そもそもPT,APTT検査は,凝固障害の原因がどこにあるか(内因系凝固経路か外因系凝固経路か両方か)を知るために有用な質的検査であり,定量的な意味合いで用いられるのは,ワルファリンやヘパリン投与時の効果判定および投与量の調節の際くらいである。端的にいえば,「PT,APTT値30%」がすなわち「凝固因子量30%」ということではなく,いったいどの程度の凝固能が維持されているのか,PT,APTT値から見当をつけることは難しい1,2)。治療に際しても,「新鮮凍結血漿(FFP)をどのくらい投与すればどの程度PT,APTT値がよくなるか」がわからないのである3)。つまりPT,APTT値には,「治療による達成目標値を決められない」という致命的な欠点がある。また,PT,APTT検査は凝固反応(=トロンビン生成反応)の初期相のわずか5%程度の良し悪しを反映する検査であり4),トータルとしての凝固能を表す指標とはなり得ない。そして最も重要なのは,高度な低フィブリノゲン血症(<100mg/dL)に陥ってもPT,APTT値はそれほど延長せず,大量出血をまねく危機的状況を察知できないことである(表1)。したがって,FFP投与のトリガー値をPT,APTT値とするのは不適切であると言える5,6)。 最近,ベッドサイドで全血を用いて迅速に検査できる「point-of-care(POC)テスト」が注目されている7)。中でもさまざまな観点から血液粘弾性を評価できるトロンボエラストメトリーrotation thromboelastometry(ROTEM)およびトロンボエラストグラフィthromboelastography(TEG)の有用性が期待されている。しかし,大量出血の主要因となる凝固障害の本態は「高度な低フィブリノゲン血症」であることがわかってきており8),リアルタイムに評価すべきなのは患者の血中フィブリノゲン値である。そして「高度な低フィブリノゲン血症」の改善のためには,乾燥人フィブリノゲンもしくはクリオプレシピテートなどの濃縮フィブリノゲン製剤の投与が必須である9,10)。こう考えると,術中大量出血時にPOCテストを使っていち早く知るべきはフィブリノゲン濃度であり,そのためには血液凝固分析装置Fib Careなど,フィブリノゲンに特化した検査機器で十分である。なぜなら,フィブリノゲン値から他の凝固因子の低下度もおよそ把握できるからである。仮にPT,APTT値がすぐにわかったとしても,その値に応じた治療(すでにFFPは十分投与しているはず)を選択できるわけではない。つまり,「治療につながらない検査をPOCテストで行う必要はない」ということであり,標的を絞った迅速検査と,その検査結果に応じた実効性のある治療が最も重要なのである(表2)。
- 著者
- 山本 晃士 西脇 公俊 加藤 千秋 花井 慶子 菊地 良介 柴山 修司 梛野 正人 木内 哲也 上田 裕一 高松 純樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会
- 雑誌
- 日本輸血細胞治療学会誌 (ISSN:18813011)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.36-42, 2010 (Released:2010-03-15)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 14 17
<背景・目的>手術関連死亡の最大原因は術中の大量出血であるが,その背景には外科的手技による止血が不可能な希釈性凝固障害という病態が存在する.したがって術中の大量出血を未然に防ぐには止血のための輸血治療が必要であり,その治療指針の確立が急務である.<方法・結果>術中の大量出血・大量輸血症例を後方視的に調査した結果,その60%強を胸部大動脈瘤手術,肝臓移植術,肝臓癌・肝門部癌切除術が占めていた.術中大量出血の背景にある止血不全の主要因は,出血量の増加にともなう凝固因子(特にフィブリノゲン)の喪失,枯渇であると考えられた.そこで上記症例の手術中に起こった低フィブリノゲン血症に対し,クリオプレシピテートおよびフィブリノゲン濃縮製剤の投与を行ったところ,速やかなフィブリノゲン値の上昇と止血の改善,および術中出血量・輸血量の顕著な減少(平均で30~40%減)を認めた.<結論>術中の出血量増加時には,フィブリノゲン値を確認した上で速やかにフィブリノゲン濃縮製剤を投与することが,大量出血・大量輸血を未然に防ぎ,手術患者の予後改善に大きく貢献するとともに,血液製剤の使用削減・有効利用につながると考えられた.
1 0 0 0 OA クリオプレシピテート院内作製プロトコール
1 0 0 0 OA 血栓症リスクファクター・先天性/後天性プロテインS欠乏症発症の分子基盤解明
先天性プロテインS(PS)欠損症・異常症の遺伝子解析において、未解析の新たな症例検体については従来のPCRダイレクトシーケンス法を用いた遺伝子変異の同定を行った結果、新規変異を含めてその原因と思われるPROS1遺伝子変異を同定した。その中でPROS1遺伝子の蛋白翻訳領域には変異は見つからなかったものの、翻訳開始点より168bp上流のプロモーター領域に同定したC→T (c.-168C>T)の点突然変異のルシフェラーゼ・レポーター解析の結果、変異型では転写活性が20%まで低下し、先天性PS欠損症の原因と思われた。先天性PS欠損症症例で従来の各エクソンのPCRダイレクトシーケンス法にてPROS1遺伝子に変異の見つからなかった症例において、PROS1遺伝子の15個の各エクソン部に偽遺伝子と区別するPCRプライマーを設定し、Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA) 法によってPROS1遺伝子欠失の同定解析を行ったところ、PROS1遺伝子の全欠失を示す症例を1例同定した。しかし、他の多くの症例では欠失を同定できず、遺伝子欠失の頻度はまれであると思われた。ヒトPSを産生するHepG2 細胞を用い、エストラディオール(E2)の添加による培養上清中のPS分泌量の変動についてELISA 解析を行ったところ、30%の発現低下を認めた。また、細胞内PS mRNAの変動についてReal Time PCRを用いて定量した結果、同様にE2 の添加によるmRNA発現低下を認めた。現在、PS遺伝子プロモータ領域をクローニングし、ルシフェラーゼ・レポーター解析による、HepG2細胞でのE2 によるPS遺伝子発現の制御動態解析を施行中である。
肥満・糖尿病のモデルとして遺伝的肥満マウス(ob/obマウス)を用い、血栓傾向の分子メカニズムを検討した。肥満マウスでは、対照マウスと比較して血中PAI-1抗原量は数倍に上昇しており、組織におけるPAI-1 mRNAの発現増加も認められた。もっとも顕著だったのは脂肪組織で、血管平滑筋細胞、血管内皮細胞、脂肪細胞等においてPAI-1 mRNAの発現が著明に増強していた。また肥満マウスでは外因系凝固の起始因子であるTFの発現も亢進していた。このTF mRNA発現増加も脂肪細胞自体によることがわかったが、脂肪組織内の血管を構成する細胞(血管外膜細胞)においても発現の増強が認められた。PAI-1に加えてTFの発現増加が、肥満個体における凝固亢進状態を増幅しているであろうと推測された。さらに、脂肪組織におけるPAI-1およびTFの発現を強力に誘導するTGF-βの発現自体も、肥満マウスの脂肪組織では週齢依存的に増加しており、血栓傾向を増悪させるTGF-βのメディエーターとしての役割は非常に重要であろうと考えられた。一方、肥満マウスに心因性ストレスを負荷し、線溶阻害因子PAI-1の発現と組織内微小血栓形成について解析を行った。肥満マウスおよび対照マウスを50ml用チューブ内に閉じ込めて拘束ストレスを負荷すると、肥満マウスではストレス負荷2時間後に早くも著明な血中PAI-1抗原量の上昇と組織におけるPAI-1 mRNAの発現増加を認めた。特に、脂肪組織や心臓、腎臓におけるPAI-1 mRNA発現は対照マウスに比べて顕著に増加していた。この傾向は20時間という長時間ストレスでも同様であった。また、このPAI-1 mRNA発現は腎糸球体の内皮やメサンギウム細胞、心筋内微小血管内皮細胞、脂肪細胞等に一致して認められた。さらにストレス負荷後の肥満マウスでは腎糸球体微小血管内にフィブリン沈着を認めたが、対照マウスでは認めなかった。以上より、肥満およびインスリン抵抗性を有する個体ではストレス負荷によってPAI-1遺伝子発現が著明に亢進し、これが組織内微小血栓形成を促進するひとつの原因と考えられた。これらの研究成果は、肥満・糖尿病患者における血栓症発症の病因・病態を考える上で重要な知見と言える。