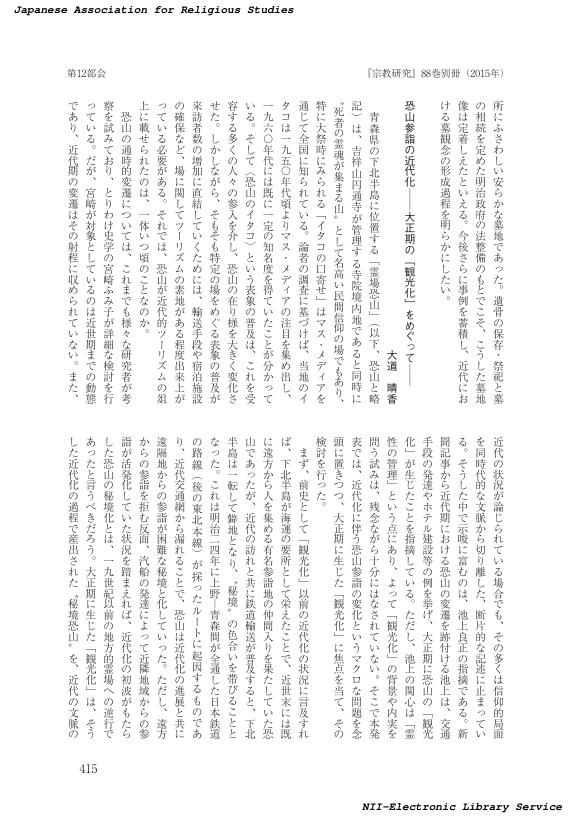13 0 0 0 OA 大教院分離運動と仏教天文学
- 著者
- 岡田 正彦
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.92, no.2, pp.31-53, 2018-09-30 (Released:2018-12-30)
明治政府は、神祇官復興や神仏分離に象徴される神道国教化政策を展開するが、廃仏毀釈による各地の混乱や教化政策の停滞によって方向転換し、明治五年には教部省のもとで仏教や儒教を取り込んだ大教院が設立される。しかし、「神主仏従」の教化政策は、真宗の大教院分離運動を招き、明治八年に大教院は解体されることになる。本稿では、こうした大教院の教説に対する仏教側の不満を色濃く反映する事例の一つとして、明治七年(一八七四)に出版された、花谷安慧『天文三字経』を取りあげ、これまで仏教側の大教院批判の言説としては注目されなかった、須弥山説に基づく国学的宇宙像の批判について考察したい。安慧は、仏教と儒教・神道の宇宙像の一致を主張する一方で、キリスト教/西洋の宇宙像に影響された平田篤胤の国学的宇宙像を厳しく批判する。こうした平田派国学の位置づけは、当時の大教院の教説と仏教思想の軋轢を色濃く反映しているのではなかろうか。
13 0 0 0 OA ジェンダー論的転回が明らかにする日本宗教学の諸問題
- 著者
- 川橋 範子
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.2, pp.31-55, 2019-09-30 (Released:2020-01-07)
本稿ではジェンダー論的転回(gender-critical turns)が明らかにする日本の宗教研究の問題点を概観し、それらを修正するいくつかの方向性を提示していく。この作業にあたり、筆者と個人的な交流があるウルスラ・キング(ブリストル大学名誉教授)とモーニィ・ジョイ(カルガリー大学教授)という二人のフェミニスト宗教学の開拓者・先駆者(trailblazer)の理論的テクストの重要性を、日本で文脈化していく。宗教はグローバルなジェンダー正義を保障するための重要で積極的な要因となりうる。宗教の象徴力と組織力が強大であるがゆえに、宗教はジェンダー平等に敏感なものへと再構築される必要があると主張していく。結論部では、宗教と女性の主体を巡る近年の言説の陥穽とそれが日本の宗教研究に及ぼす個別の影響について考察する。
13 0 0 0 OA 北畠親房における祭政一致説の意義(第九部会,<特集>第七十回学術大会紀要)
- 著者
- 齋藤 公太
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.4, pp.1223-1224, 2012-03-30
- 著者
- 塚田 穂高
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, pp.108-109, 2015
13 0 0 0 OA 明治三〇年代における「修養」概念と将来の宗教の構想
- 著者
- 栗田 英彦
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.3, pp.471-494, 2015-12-30
本論文では、哲学者・井上哲次郎によって構想された将来の宗教-「倫理的宗教」-と、それに対する改革派宗教者らの批判から、「修養」と呼ばれる宗教性を帯びたカテゴリーが生まれてきたことを論じる。明治三〇年代における教育からの宗教の排除と倫理教育への宗教の必要性という矛盾した要求のなかで、井上も宗教者らも新しい宗教のあり方を模索していた。それゆえ、宗教者たちは倫理的宗教論の抽象性を批判しつつ、その諸聖賢などの理想の人格や内観や坐禅といった具体的な実践をそこに結びつけることで、より実践的な倫理的宗教、すなわち「修養」を生み出した。さまざまな論者によって「修養」概念は用いられ、倫理と宗教、宗教と宗教の境界を超えて展開する超宗教的なカテゴリーとして、戦前日本で幅広い影響を与えることになったのである。
12 0 0 0 OA キリストの幕屋と日猶同祖論(第七部会,<特集>第72回学術大会紀要)
- 著者
- 山本 伸一
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.Suppl, pp.312-313, 2014-03-30 (Released:2017-07-14)
12 0 0 0 OA 職場スピリチュアリティとは何か その理論的展開と歴史的意義
- 著者
- 堀江 宗正
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.2, pp.229-254, 2017-09-30 (Released:2017-12-30)
二〇〇〇年代に入ってから主に英語圏の経営学で「職場スピリチュアリティ」をめぐって活発な議論が交わされている。本稿はその理論的展開と歴史的意義を明らかにするサーヴェイ論文である。この概念は経営者や従業員を対象とする調査から構築された多次元的概念であり、同時にコミュニタリアン的な徳倫理学の価値観のセットとしても提示される。その構成要素はコミュニティ感覚、従業員の疎外の改善、従業員の多様性の尊重、企業の不正への不寛容などである。だが批判者は企業中心主義、スピリチュアリティの道具化、従業員のコントロールの強化、カルトとの類似、訴訟の増大の危険を指摘する。一連の議論は経済活動と宗教を両立させようとする歴史的な試行錯誤のパターンを反映している。世俗化や近代化を生き延びつつ経済活動を支えてきたスピリチュアル資本の現代的な育成の形とも見られる。最後に日本で研究するべきいくつかの関連テーマについて展望を示したい。
11 0 0 0 OA 恐山参詣の近代化 : 大正期の「観光化」をめぐって(第十二部会,<特集>第73回学術大会紀要)
- 著者
- 大道 晴香
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.Suppl, pp.415-416, 2015-03-30 (Released:2017-07-14)
11 0 0 0 OA 大谷栄一著『日蓮主義とはなんだったのか──近代日本の思想水脈──』
- 著者
- 粟津 賢太
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.94, no.2, pp.185-191, 2020 (Released:2020-12-30)
- 著者
- 伊藤 雅之
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.4, pp.1255-1256, 2011-03-30
11 0 0 0 ライシテは市民宗教か
- 著者
- 伊達 聖伸
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.3, pp.531-554, 2007-12
フランスの政教関係を定めた「ライシテ」の原理は、いわゆる近代社会の基本的原則たる政教分離を最も徹底させたものだとしばしば見なされている。それを裏づけるように、フランスのライシテは、「アメリカの市民宗教」-教会から切り離されたユダヤ=キリスト教の文化的要素が政治の領域に明白に見て取れる-とは構造を異にすると分析されている。だが、この差異から、フランスでは政治の領域に宗教的次元が存在しないという結論が導けるわけではない。事実、研究者のあいだでは、ライシテ(およびこの原理に即した近代的な価値観)を市民宗教などのタームでとらえることの妥当性が問われている。本稿では、彼らの議論の一部を紹介しながら、市民宗教の五類型を提示し、ライシテがいかなる条件において、どのような意味での「市民宗教」に近づきうるのかを、ライシテの歴史の三つの重要な節目-フランス革命期、第三共和政初期、現代-におけるいくつかの具体例を通して検討する。
11 0 0 0 OA 流行神の誕生と展開 : 長野県飯田市貧乏神神社を事例に(第十部会,<特集>第73回学術大会紀要)
- 著者
- 黄 緑萍
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.Suppl, pp.383-384, 2015-03-30 (Released:2017-07-14)
11 0 0 0 OA 明治三〇年代における「修養」概念と将来の宗教の構想
- 著者
- 栗田 英彦
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.3, pp.471-494, 2015-12-30
本論文では、哲学者・井上哲次郎によって構想された将来の宗教-「倫理的宗教」-と、それに対する改革派宗教者らの批判から、「修養」と呼ばれる宗教性を帯びたカテゴリーが生まれてきたことを論じる。明治三〇年代における教育からの宗教の排除と倫理教育への宗教の必要性という矛盾した要求のなかで、井上も宗教者らも新しい宗教のあり方を模索していた。それゆえ、宗教者たちは倫理的宗教論の抽象性を批判しつつ、その諸聖賢などの理想の人格や内観や坐禅といった具体的な実践をそこに結びつけることで、より実践的な倫理的宗教、すなわち「修養」を生み出した。さまざまな論者によって「修養」概念は用いられ、倫理と宗教、宗教と宗教の境界を超えて展開する超宗教的なカテゴリーとして、戦前日本で幅広い影響を与えることになったのである。
- 著者
- 入澤 崇
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.2, pp.505-511, 2007
- 著者
- 竹下 政孝
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.1, pp.190-195, 2014
- 著者
- 熊田 一雄
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.1, pp.248-254, 2021 (Released:2021-09-30)
10 0 0 0 OA 愛は義務になり得るのか : キェルケゴールのキリスト教倫理
- 著者
- スザ ドミンゴス
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.3, pp.765-787, 2009-12-30
キリスト教の隣人愛の命令は様々な問題を提起する。愛は人間に最も深く根ざした必要性であるが、なぜ命じられるのか。その愛の命令が要求しているように、偏愛せずすべての人を平等に愛することが可能なのか。キリスト教的愛に社会的表現が与えられ得るのか。本稿は、このような問いに伴う倫理的意味に関するキェルケゴールの見解を考察する。彼は、感情と衝動に基づく自然的愛に対して、キリスト教的愛が自然派生的に生じるのではなく、神によって命じられる愛であると特徴付け、義務になることによってのみ、愛はあらゆる変化から守られると主張する。キェルケゴールによれば、キリスト教的愛の究極的目的は、神を人が愛するように隣人に手を差し伸べるということであるが、それはある学者たちが批判するような非社会的および非現実的倫理を伴うのではない。神への愛は隣人への愛を媒介として常に表現されなければならないのであり、かならず現実的な人に向けられている。
10 0 0 0 善知識としての病:古代日本における仏教美術と疫病
- 著者
- 山本 聡美
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.2, pp.121-144, 2021
<p>近代的疾病観においては、病を健全な身体の対極にあるものと捉え、加療を通じて健常なる状態へ近づけることに価値が置かれる傾向にある。一方、古代・中世日本においては、これとは異なる疾病観が存在していた。特に仏教の教義や実践において、病には、人間の存在の根源に関わる現象としての重要な意味が見出されていた。病を生存への脅威として排除するのではなく、これと折り合い、場合によっては、秩序ある社会を構築する梃子として肯定的に捉えていくことさえなされた。</p><p>本稿では、平安時代末期の浄土僧、永観による「病は善知識なり」との成句に着眼する。善知識とは、仏教における発心や成道への導き手を指す。通常、多くの修行を積んだ高徳の僧を言うが、悟りに至るきっかけとなる人物や事物を広く指す言葉でもある。「粉河寺縁起絵巻」に描かれた病に発心の契機としての肯定的な意味を読みとくことからはじめ、そのような疾病観が形成された歴史的経緯を、古代日本における造像の伝統から明らかにする。</p>
10 0 0 0 OA シモーネ・ルッツァット『議論』に現れる近世ヴェネツィアのユダヤ教観念
- 著者
- 李 美奈
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.3, pp.49-73, 2019 (Released:2020-03-30)
近世イタリアでは市民の道徳の発達と共に、キリスト教徒とユダヤ教徒の差別化の論理から非道徳的なユダヤ人ステレオタイプが作られた。本論は『ヘブライ人の状況についての議論』において、一七世紀ヴェネツィアのラビ、シモーネ・ルッツァットがこの偏見にどのように反論し、かつユダヤ教を守ることを試みたかを明らかにした。ルッツァットはユダヤ教を特殊な儀礼と普遍的な道徳性に分け、前者はユダヤ人のみが自由意志で守るが、後者は全人類が積極的に共有すべきとした。これは近代に似た宗教観念と言えるが、他方で個人はまず儀礼を通して繋がり、その外で道徳性によって異教徒と関係を持つと主張し、近代と異なる社会観念も持つ。この見解を当時の社会背景から考察し、ルッツァットがユダヤ教も兄弟団と同様に道徳的教えを持ちヴェネツィアの秩序に貢献するとしつつ、儀礼に関しては外国人組合nationeに認められた慣習法に落とし込み、ヴェネツィア当局の統治方針に合わせて議論していると結論づけた。
- 著者
- 月本 昭男
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.Suppl, pp.51-52, 2014-03-30 (Released:2017-07-14)